事業承継の進め方を解説!成功させるためのポイントも紹介します
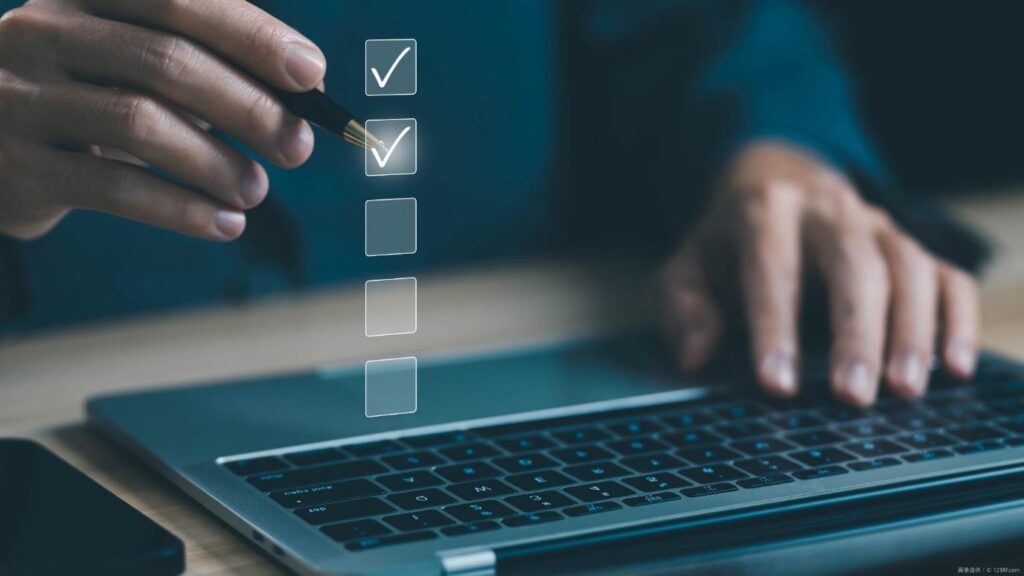
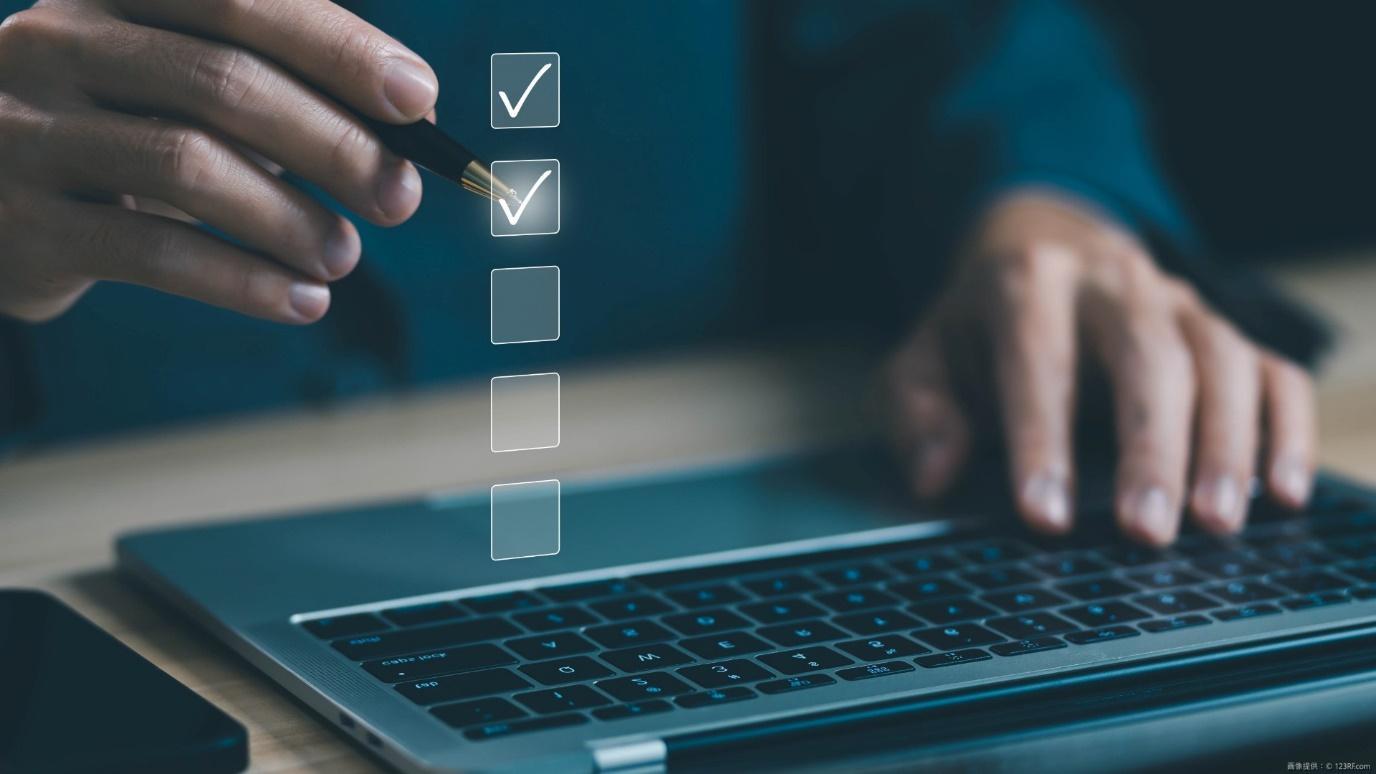
事業承継は、経営者が事業を次世代へと引き継ぐことです。次世代へスムーズな移行を実現するために、このコラムでは承継計画の立て方から、成功に導くポイントまでをわかりやすく解説します。
事業承継とは?
事業承継とは、企業の経営者が変わる際にその企業のビジョンや技術、ノウハウなどを次の経営者へと引き継ぐことを指します。とくに中小企業においては、その企業の存続や発展を維持するために重要視されています。
事業承継の必要性
事業承継は、企業が世代を超えて繁栄を続けるために不可欠なものです。計画的な承継により経営の安定性を確保し、企業文化と価値観を保持しながら、さらなる発展を目指すうえで欠かせません。
中小企業経営者の高齢化
事業承継の必要性が叫ばれる背景には、中小企業経営者の高齢化があります。現状では多くの経営者が退職年齢に達しており、後継者不足により企業の存続が危ぶまれています。
2019年時点において、中小企業の代表者平均年齢は62.1歳といわれています。60歳以上の経営者の約35%以上は、廃業を選択しています。中小企業が国内経済の大きな柱の一つであるため、この問題はより深刻です。経営者の高齢化とそれに伴う事業の閉鎖や売却は、地域経済に悪影響を及ぼす可能性があります。
後継者不足
日本の会社のうち99.7%は中小企業です。後継者不足は、とくに中小企業や家族経営の企業で問題になりがちです。後継者がいないため望まぬ廃業が増えていて、黒字にも関わらず廃業の危機にある企業数は60万社(中小企業庁推計)といわれています。
後継者がいない場合、企業は経営継続の危機に直面し、従業員の雇用や地域経済にも悪影響を及ぼす可能性があります。2020年1月から12月の後継者難による倒産は370件に及び2013年の調査開始以来、年間最多を更新しつづけています(東京商工リサーチ調査)。この課題に対処するためには、事業承継計画の早期立案が必要となります。
事業承継によって引き継ぐ3つの要素
企業の存続に欠かせない事業承継には、引き継ぐべき3つの要素があります。
-
- 人(経営権)の承継
- 資産の承継
- 知的資産の承継
これらについて説明していきましょう。
人(経営権)の承継
事業承継における人(経営権)の承継とは、企業の経営権が現経営者から次世代の経営者へと移行することを指します。この段階では企業の経営哲学、および経営戦略の継続性が重要視されます。
成功する経営権の承継には、適切な後継者の選定と育成、丁寧な準備、そしてスムーズな権限移譲が不可欠です。後継者は、現経営者のビジョンと価値観を継承しつつ、新たな視点と革新を企業にもたらす責任があります。
資産の承継
資産の承継には、不動産、設備、現金、株式など、企業が保有するあらゆる形態の資産が含まれます。資産の適切な評価と合法的な移転手続きは、この過程で極めて重要です。
事業承継計画において資産の承継を適切に進めることで、新たな経営者は企業運営に必要なリソースを確保し、事業のスムーズな継続と成長を促進できます。法人形態の場合は自社株式を承継させることでこれらの承継が包括的にできます。
知的資産の承継
知的資産とは、企業の無形資産である特許や商標、著作権、ノウハウ、顧客リスト、組織力、経営ノウハウなど競争力の根源となっている会社の強みを指します。これらの資産は、企業の競争力の源泉であり、市場での地位を確立する上で不可欠です。
知的資産の適切な評価や保護、そして移譲は事業承継計画において重要な役割を果たします。目に見えない経営資源のため、承継すべき経営資源として見落とされがちです。後継者はこれらの資産を承継し、活用することで、企業のイノベーションと成長を持続させることを期待されるのです。
事業承継に用いられる3つの方法とメリット・デメリット
事業承継には以下のケースがあります。
-
- 親族内に承継するケース
- 親族外に承継するケース(従業員や外部)
- 第三者に承継するケース(M&A)
それぞれについて、メリット・デメリットも含め解説していきましょう。
親族内に承継するケース
親族内に承継するケースは、事業承継のもっとも伝統的な方法の一つであり、とくに家族経営の中小企業でよくみられます。この方法は、従業員や取引先など社内外の関係者からも心情的に受け入れられやすい選択肢で、経営者と後継者がコミュニケーションをとれる機会が多いため、スムーズに承継を進められます。
親族内に承継するメリット
親族内に事業を承継するメリットには、企業文化の継承や経営の安定性があります。家族が経営を継ぐことで創業者の理念や価値観を保持し、長年にわたり築き上げた企業文化を次世代に伝えることが可能になります。
親族内に承継するデメリット
親族内に事業を承継するデメリットには、適性に欠ける後継者の選定や家族間の対立、およびイノベーションの欠如が含まれます。後継者が適性や熱意に欠ける場合、事業の持続的な成長と成功が阻害される可能性があります。
また、家族内での承継はしばしば対立を引き起こし、これが事業運営に悪影響を及ぼすことも。さらに親族内承継では、外部の視点や新鮮なアイデアが導入されにくく、イノベーションの機会が失われがちです。
親族内継承ならではのポイントを押さえよう!メリット・デメリットについても解説
親族外に承継するケース(従業員や外部)
事業を従業員や外部の第三者に引き継ぐ承継は、経営者が親族内に適切な後継者をみつけられない場合や、新たな視点や専門知識を事業に導入したいと考える場合に採用されます。新しい経営戦略やイノベーションを事業にもたらし、成長の新たな機会を開くことが期待されます。
親族外に承継するメリット
外部の後継者や従業員への承継は、新たなアイデアやイノベーションを事業にもたらし、成長の機会を拡大する可能性があります。また、専門的な知識や経験を持つ外部の後継者を選択することで、経営の効率化や専門化を図れます。
親族外に承継するデメリット
事業承継を従業員や外部の第三者に行う場合、外部の後継者が持つ異なるビジョンや経営スタイルが、従来の企業文化や価値観と衝突する可能性があり、これにより軋轢が生じることが考えられます。また、長年築き上げてきた従業員や顧客との信頼関係が損なわれるリスクもあります。
従業員承継の方法と流れ!事前に把握しておくべきリスクや注意点を解説
第三者に承継するケース(M&A)
M&A(合併・買収)は、事業承継の一形態として、企業が後継者をみつけることが困難な場合や、新たな成長機会を探求したいときに選択されます。後継者不在により会社が廃業してしまった場合は、従業員や取引先などの関係者に多大な影響を及ぼしますが、M&Aで譲渡することで事業継続が可能になります。
第三者に承継するメリット
M&Aの場合、新たな市場へのアクセス、そして企業の成長加速が挙げられます。広い範囲から実績や意欲ある第三者を選定できるため、後継者教育も不要で新しい経営陣が革新的なアイデアや技術をもたらし、事業を次のレベルに引き上げる可能性が高まります。
第三者に承継するデメリット
新たな買手が会社運営の意思決定を行うため、売却後の事業方針などが売却前と変わってしまう可能性があります。買手企業にとって魅力ある会社でなければ、買手企業をみつけることが困難となります。
また、M&Aは会社の内情を知らない第三者による承継であることが多いため、事前に十分な調査を行うなど、譲渡契約までに多大な時間を要することが少なくありません。
事業承継の進め方
事業承継は下記のステップで進めます。
|
|
|
|
|
|
|
それぞれ詳しく説明します。
STEP1:経営状況・経営課題を見える化する
経営状況・経営課題を見える化するとは、企業の現在の業績や財務状況、市場でのポジション、内外の課題などを客観的かつ明確に把握し、理解することを指します。これには、財務諸表の分析や業務プロセスの評価、競合分析、SWOT分析(強み、弱み、機会、脅威の分析)など、多岐にわたる手法が用いられます。
この見える化を通じて、経営者は自社の実際の立ち位置を正確に理解し、将来に向けた戦略立案の基礎とすることができます。とくに事業承継を控えた企業にとって、この見える化は非常に重要です。また、経営課題を明らかにすることで、承継中に解決すべき問題を特定し、事業の持続可能性を高めるための改善策を講じることが可能になります。このように経営状況と経営課題を見える化することは、事業承継を成功に導くための重要なステップといえます。
STEP2:事業承継に向けて経営改善を図る
事業承継に向けて経営改善を図るとは、事業を次世代に引き継ぐ過程で、企業の持続可能性と競争力を高めるための一連の施策を実行することを指します。これには、財務状況の健全化や業務プロセスの最適化、収益性の向上、そして組織構造の再編などが含まれます。
具体的には、不要な資産の売却やコスト削減、新たなビジネスモデルへの転換、市場ニーズに合わせた製品・サービスの開発、人材育成といった取り組みが挙げられます。
この過程を通じて、後継者が引き継ぐ企業がより健全で効率的な経営基盤を持てて、新たな経営戦略を実行しやすくなります。経営改善は、事業承継が単なる権限移譲でなく、企業の新たなステージへの移行を意味することを強調し、承継後も企業が成長し続けるための土台を築きます。
STEP3:後継者選びと育成
後継者選びと育成は、事業承継の重要なステップです。適切な後継者を選び、その人材を育成することで、事業の継続性や発展性を高めることが可能となります。後継者の育成には時間を要するため、計画的に取り組む必要があります。
親族内に承継
親族内承継は、日本の中小企業でもっとも選ばれやすく、企業の価値観、伝統、および長期的なビジョンを継続することを目的としています。また、従業員や取引先など社内外の関係者からも心情的に受け入れられやすい選択肢です。
経営者と後継者がコミュニケーションをとりながら、スムーズに承継を進められます。しかし、複数の候補者がいる場合は経営権をめぐる争いが発生するリスクが高まり、社内分断を招くおそれがあります。
従業員などへ承継
従業員などへ承継することは、従業員が会社の運営に深く関わることから、事業の理念や文化の継続性を保ちやすいというメリットがあります。従業員への承継は、従業員所有計画(ESOP)などの形式を取ることが多く、経営参加の意欲を高め、会社への忠誠心を促進します。
また、すでに事業運営に精通しているため、スムーズな移行が期待できる一方で、適切なリーダー選択と育成が成功の鍵となります。
STEP4:事業承継計画策定
事業承継計画を策定することは、企業が将来にわたって安定して発展を続けるために不可欠です。この計画には後継者の選定や経営権の移譲時期、必要な財務計画、および後継者に必要なスキルと教育プログラムが含まれます。
緻密な承継計画を作成することで、目標の明確化やリスクの評価、スムーズな承継を実現します。専門家の意見を取り入れるなどして、戦略的に計画しましょう。
STEP5:事業承継の手法決定や条件交渉
承継の手法には、親族内承継や従業員への承継、第三者への売却(M&A)などがあり、それぞれにメリットとデメリットが存在します。これらの中から事業の特性や経営者の意向、後継者の能力と希望を考慮して最適な方法を選択します。
条件交渉では、承継時期や価格、支払い条件、経営権の移行方法など、承継に際して必要な条件を明確にし、双方の合意を形成します。
STEP6:契約の締結
事業承継における契約の締結は、経営者が次世代の経営者へ事業を引き継ぐ重要なフェーズです。承継の範囲や価格、支払い条件、移譲のスケジュール、責任の範囲など、承継に関する詳細な条項が含まれます。
契約締結により、双方の合意内容が明確化され、法的に拘束力を持つことになります。このプロセスは事業承継が円滑に進行し、将来的な紛争を避けるためにとても大切です。
STEP7:従業員や関係者へ通知
従業員や関係者への通知は、計画の透明性とスムーズな移行を実現するうえで重要です。この段階では、事業承継の意図や後継者の紹介、そして移行のスケジュールについて、従業員や取引先、顧客に正確かつ明確な情報を通知します。これにより関係者の不安を軽減し、後継者への支持を得ることが期待されます。
また、開かれた対話の場を設けることで疑問や懸念を払拭し、組織全体の一体感を保てる可能性が高くなります。
事業承継を成功させるためのポイント
事業承継を成功させるには、以下のことを意識しましょう。
-
- 事業承継で活用できる支援策の確認
- 事業承継で有効な相続対策を実施
- 自社株の買い取りを実施
- 税金対策を行っておく
事業承継で活用できる支援策の確認
事業承継を成功させるためには、利用可能な支援策の確認が欠かせません。政府や地方自治体、民間団体から提供される各種の支援策には、資金調達のサポートや税制優遇措置、専門家によるコンサルティングサービスなどがあります。
これらの支援を活用することで、事業承継を円滑に進めることが可能となり、財務的な負担の軽減や適切な承継計画の策定に役立ちます。支援策を最大限に利用するためには早期に情報収集を始め、条件に合った支援策を見極めることが重要です。
事業承継で有効な相続対策を実施
事業承継における有効な相続対策は、事業の継続性と発展性を確保するために重要です。事業承継税制を活用することで、節税効果や後継者問題の改善が期待できます。これには、生前贈与の活用や相続税の猶予・減免制度の適用、ファミリートラストの設立などが含まれます。
生前贈与の場合
生前贈与は、事業承継で有効な相続対策の一つです。オーナーが生前に事業資産や株式を後継者に移譲することで、相続時の税負担を軽減し、資産の円滑な移行を促進できます。後継者は早い段階で経営に加われて、作成者が自由に撤回できる遺言と比べると後継者の地位が安定するという点に利点があります。
生前贈与には特定の税制優遇措置が適用される場合があり、これを利用することで、より効果的に財産を引き継ぐことが可能になります。ただし生前贈与を行う際には、贈与税の影響を考慮しましょう。
遺言を利用する場合
遺言は経営権の移転や資産の分配、後継者の指名など、事業承継における多くの要素をカバーすることが可能です。遺言を通じて、後継者に事業をスムーズに移譲し、そのほかの財産分配についても具体的な指示を残せるのです。売買等による承継と比べて、資金準備が少なく済むという点に利点があります。遺言作成にあたっては、法的な問題をクリアするために専門家のアドバイスを受けましょう。
自社株の買い取りを実施
自社株の買い取りは、事業承継計画において重要な戦略のひとつで、企業が自己の発行株式を市場や特定の株主から買い戻し、経営権の集中を図ります。とくに事業承継を控える中小企業において、後継者の経営権確保や不要な株主からの影響を排除するために有効です。
また買い取りを通じて、余剰資金の有効活用や株価のサポート、株主価値の向上が期待されます。事業承継の観点からは、自社株買い取りは後継者へのスムーズな移行を実現し、経営の安定化に貢献します。自社株の買い取りに際しては、税理士などの専門家に頼るとスムーズに進むでしょう。
税金対策を行っておく
税金対策は、事業承継を成功させるための重要なポイントです。とくに相続税や贈与税の負担は、事業承継計画に大きな影響を及ぼす可能性があります。適切な税金対策を行うことで、税負担を最小限に抑え、事業資産を守りながらスムーズな承継を実現できます。
対策としては、生前贈与の利用や小規模企業共済や経営者保険の活用、事業用資産の特例や家族信託の設定などが挙げられます。これらの手段は、承継計画の目的や事業の特性に応じて選択し、適用することが重要です。また、税法は変更されることがあるため、常に最新の情報を把握し、専門家と連携することをおすすめします。
まとめ
事業承継は後継者の選定から税務対策、適切な通知方法まで、計画的な準備と戦略的な実行が鍵です。成功の鍵は「人・資産・知的資産」の3つの承継と、適切な税制や補助金の活用にあります。ときには専門家のアドバイスを求めることをおすすめします。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。


