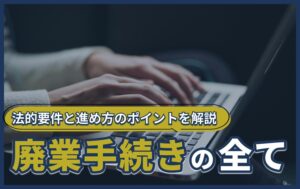親族内継承ならではのポイントを押さえよう!メリット・デメリットについても解説
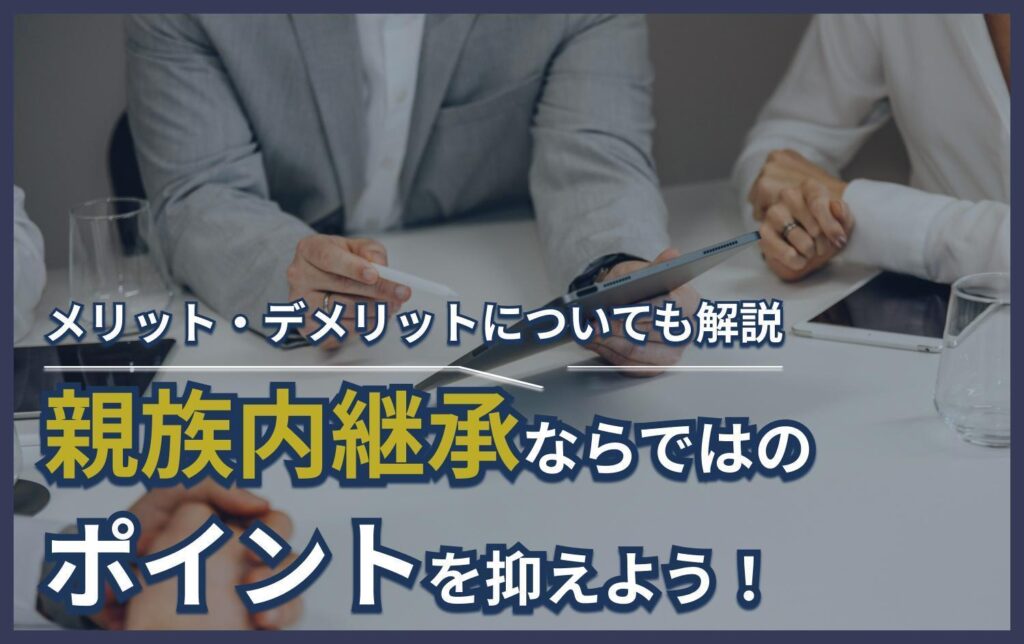
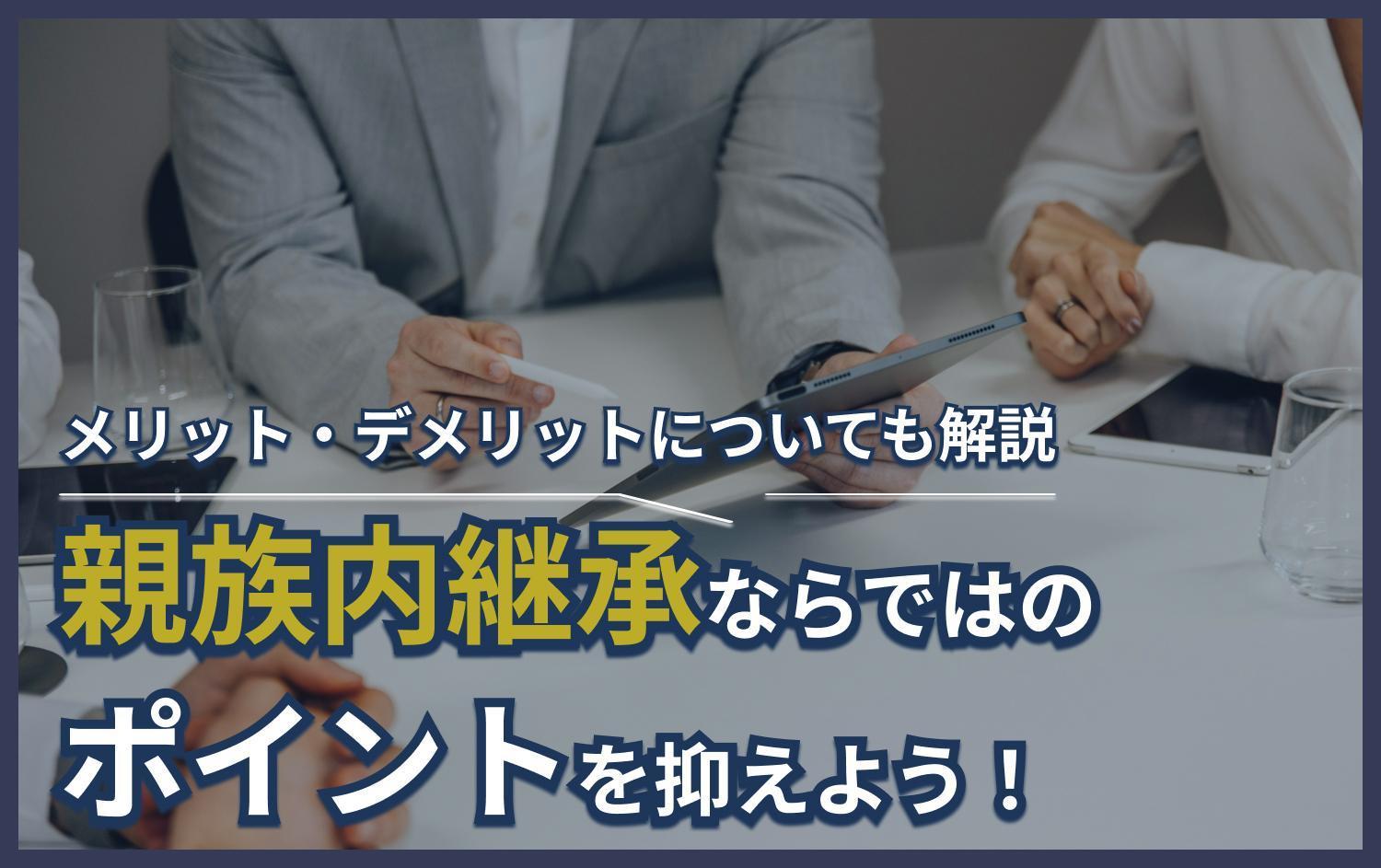
経営者の皆様、事業承継に関してお悩みではありませんか?特に、後継者不在という問題に直面されている方も多いのではないでしょうか。
会社を長年率いてきた経営者にとって、事業の引継ぎは人生におけるターニングポイントです。スムーズな承継ができない場合、これまで築いてきた企業の存続も危ぶまれます。
そんな中、一般的な選択肢とされているのが「親族内継承」です。自分の子供や親族に経営を引き継ぐ方法です。親族なら安心して任せられますし、何より会社への思い入れも深いはずです。
ところが実際には、コミュニケーション不足から親子の意思疎通がうまくいかなかったり、相続を巡って兄弟姉妹の間で対立が生じたりと、思わぬ落とし穴が待ち構えている可能性があります。
ではどうすれば、そうした課題を乗り越え、幸せな親族内継承を実現できるのでしょうか?
本記事では、親族内継承の基本的な考え方から、後継者教育の進め方、さらには法的・税務的な注意点まで実践的なアドバイスを解説します。
目次
親族内継承のメリット
- 経営理念や家訓の継承がスムーズ
- 経営者と後継者の間に強い信頼関係が期待できる
- 権限委譲がスムーズに進む
- 従業員の抵抗感が少ない
親族内継承のデメリット
- 経営者と後継者の意見対立が起こりやすい
- 相続税の負担が重い
- 親族外の役員・従業員の反発を招く恐れがある
- 事業と家庭の問題が混同しやすい
親族内継承のコツ
効果的なコミュニケーション
円滑な親族内承継のカギを握るのは、何と言ってもコミュニケーションです。経営者と後継者が率直に対話を重ね、お互いのビジョンを共有することが何より重要です。
例えば、定期的な面談の場を設け、事業の将来像について腹を割って話し合うのも一案でしょう。また、日頃から後継者の意見に耳を傾け、経営に反映させる柔軟な姿勢も求められます。「上から目線」ではなく、対等なパートナーとして接することが、信頼関係の構築につながります。
加えて、親族外の役員や従業員とのコミュニケーションも欠かせません。後継者の評価を定期的に聞き取り、フィードバックすることで、周囲からの理解と協力を得やすくなるはずです。
後継者教育の方法論
後継者教育は、親族内継承の要と言えます。経営に関する知識やスキルを体系的に習得させる必要がありますが、具体的にはどのような方法が考えられるでしょうか。
まず、OJTを通じて、営業から財務、人事まで幅広い実務経験を積ませるのが基本です。各部門をローテーションしながら、業務の全体像を把握してもらうことが重要です。
Off-JTの活用も検討に値します。外部セミナーへの参加や、経営スクールへの通学など、社外の学びの機会を提供することで、視野の拡大が期待できます。異業種交流などを通じて人脈を広げるのも有効でしょう。
さらに、徐々に権限を委譲していく段階的なアプローチも欠かせません。
例えば、まずは特定のプロジェクトのリーダーを任せ、徐々に責任の範囲を広げていく。経営者としての自覚を促しつつ、周囲の信頼を獲得する絶好の機会となります。もちろん、教育プランは後継者の特性に合わせて柔軟にカスタマイズすることが重要です。
適切な継承タイミングの見極め
後継者教育と表裏一体をなすのが、適切な継承タイミングの見極めです。経営者としての能力が十分に備わるまで待つ一方で、現経営者の引退時期とのバランスも考慮しなければなりません。
50代での交代が望ましいとされています。後継者に一定の経験を積ませつつ、現経営者もアドバイザーとしてサポートできる年代だからです。ただし、あくまで目安であって、個社の事情に合わせて判断すべきでしょう。
継承のタイミングを見誤ると、後継者が力不足で舵取りに失敗したり、逆に現経営者が長居し過ぎて不要な軋轢を生んだりしかねません。外部の目線も交えながら、客観的に見極める必要があります。
事業承継税制の活用メリット
親族内継承に伴う税負担を和らげるには、事業承継税制の活用が有効です。これは、一定の要件を満たす非上場株式等の贈与・相続について、納税猶予・免除の特例を認める制度です。
具体的には、経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定を受けた上で、後継者が先代経営者から非上場株式等を贈与・相続により取得した場合、その株式等の評価額の最大100%に対する贈与税・相続税の納税が猶予されます。
さらに、その後の一定の要件を満たせば、納税が免除されるのです。
本制度の適用を受けるには、事前の計画策定や、一定のガバナンス体制の構築など、様々な要件をクリアする必要があります。
手続きの流れを把握した上で、早期の準備に取り掛かることが重要と言えるでしょう。
もちろん、税制の適用可否は個社の事情によって異なります。最新の情報は、中小企業庁の「事業承継税制特集」をご確認ください。
自社に最適なスキームを設計するには、専門家との連携が欠かせません。顧問税理士等を交えて、入念に検討を進めることをおすすめします。
親の会社を継ぐメリットは多い?親族内承継の方法や注意点を解説
親族内継承における課題とその解決策

考え方の相違によるコンフリクト
親族内継承では、経営者と後継者の考え方の相違から、深刻なコンフリクトが生じることがあります。特に、事業の方向性を巡る対立は、経営の根幹を揺るがしかねない問題です。
例えば、先代経営者が長年築いてきた社風を大切にしたいのに対し、後継者が思い切った改革を志向するケース。あるいは、積極的な設備投資に踏み切りたい後継者に対し、現経営者がリスクを懸念するケース。こうした意見の食い違いを放置すれば、事業の停滞を招くおそれがあります。
大切なのは、建設的な議論を重ねる姿勢です。一方的な主張ではなく、お互いの考えの背景を理解し合う。そして、最良の選択肢を見出すために知恵を出し合う。そんな成熟したコミュニケーションが求められます。
場合によっては、第三者の視点を借りるのも一案です。中立的な立場の専門家に、調整役を務めてもらうことで、感情的な対立を避けられるかもしれません。柔軟な発想で、打開策を模索することが肝要です。
後継者教育の停滞
せっかく後継者の指名を行っても、教育が計画通りに進まないことがあります。多忙を理由に、育成プランがないがしろにされるのは典型的な事例です。
しかし、後継者教育の停滞は、スムーズな事業承継の大きな障壁となります。経営ノウハウの伝授が不十分なまま交代の日を迎えれば、後継者は荷が重すぎて身動きが取れなくなるでしょう。
そうした事態を避けるには、トップの強いリーダーシップが欠かせません。忙しさを言い訳にせず、後継者教育を最優先の課題と位置付ける。そんな覚悟を持って、育成プランの着実な遂行を主導することが求められます。
また、教育の進捗を定期的に確認し、必要に応じて軌道修正を図ることも重要です。外部の専門家に評価を仰ぐなど、客観的なチェック機能を設けるのも有効な一手と言えるでしょう。PDCAサイクルをしっかりと回し、後継者の成長を促すことが重要です。
周囲の巻き込み不足
親族内継承を円滑に進めるには、経営者と後継者だけでなく、周囲の巻き込みも欠かせません。社内の役員・従業員はもちろん、取引先や金融機関など、ステークホルダーの理解と協力が何より重要です。
しかし、トップ同士の話し合いに終始し、社内への説明が疎かになるケースが少なくありません。突然の交代宣言に、現場に動揺が走るのは容易に想像できますよね。
そうした混乱を避けるには、早い段階から周囲への働きかけを始めることが肝心です。
例えば、役員会で継承プランを説明し、率直に意見を求める。従業員向けの説明会を開催し、後継者への期待を伝える。
取引先に挨拶回りを行い、今後のビジョン・方針を共有する。こうした地道なコミュニケーションの積み重ねが、スムーズな承継の準備となるのです。
近年は、社外取締役の登用も進んでいます。
第三者の視点から継承プロセスにフィードバックしてもらうことで、ガバナンス面での信頼性も高まるでしょう。
法的・税務的側面での検討事項

親族内継承では、民法や会社法など、関連する法規定への理解が欠かせません。特に重要なのは、遺留分に関する規定です。
民法上、一定の相続人(配偶者、子、直系尊属)には、遺留分という権利が認められています。遺留分とは、被相続人が遺言などで自由に処分できる財産の限度を定めたもので、一定の相続人に最低限保証される相続分のことを指します。
遺留分の割合は、以下のように定められています。
- 直系尊属のみが相続人である場合:被相続人の財産の三分の一
- 配偶者または子が相続人である場合:被相続人の財産の二分の一
この遺留分を侵害するような遺言や生前贈与は、減殺請求の対象となり、結果的に株式の分散につながりかねません。
こうしたリスクを回避するには、遺留分に配慮した承継プランが不可欠です。
具体的には、遺留分権利者の同意を得た上で、株式の集中を図る工夫が求められます。
加えて、株式の評価方法にも注意が必要です。
相続税法上、非上場株式は原則として類似業種比準方式により評価されますが、例外的に純資産価額方式が適用される場合もあります。
後継者の相続税負担を軽減するには、適切な評価方法の選択が欠かせません。
親族内継承以外の選択肢の検討
M&Aの手法と流れ
親族内継承が難しい場合、M&A(合併・買収)による第三者への引継ぎも選択肢の一つです。自社の経営資源を引き継いでもらうことで、雇用の維持や取引関係の継続を図れるメリットがあります。
M&Aの手法には、株式譲渡と事業譲渡の2つがあります。株式譲渡は、自社株式を譲受企業に売却することで経営権を移転する方式。一方、事業譲渡は特定の事業を切り出して譲渡する方式で、自社は清算・解散することになります。
いずれの手法を選ぶにせよ、まずは譲受候補企業のリストアップから始まります。仲介機関やM&A専門家の助言を得ながら、幅広い選択肢を検討することが重要です。その上で、秘密保持契約を締結し、相手先企業の精査(デュー・デリジェンス)を進めます。
条件面での折り合いがつけば、譲渡価格や契約内容を詰めていきます。従業員の処遇や、ブランドの継続使用など、様々な論点をクリアしなければいけません。法務・財務・税務の専門家を交えて、入念に詰めていくことが求められるでしょう。
M&Aとは?買手・売手の目的やメリット・デメリット、手法、費用まで解説
M&Aの相談はどこにすればいい?相談の内容や相手、選定方法などを紹介
親族内継承のための準備チェックリスト
最後に、親族内継承を進める上での準備事項を、チェックリスト形式で整理しておきましょう。
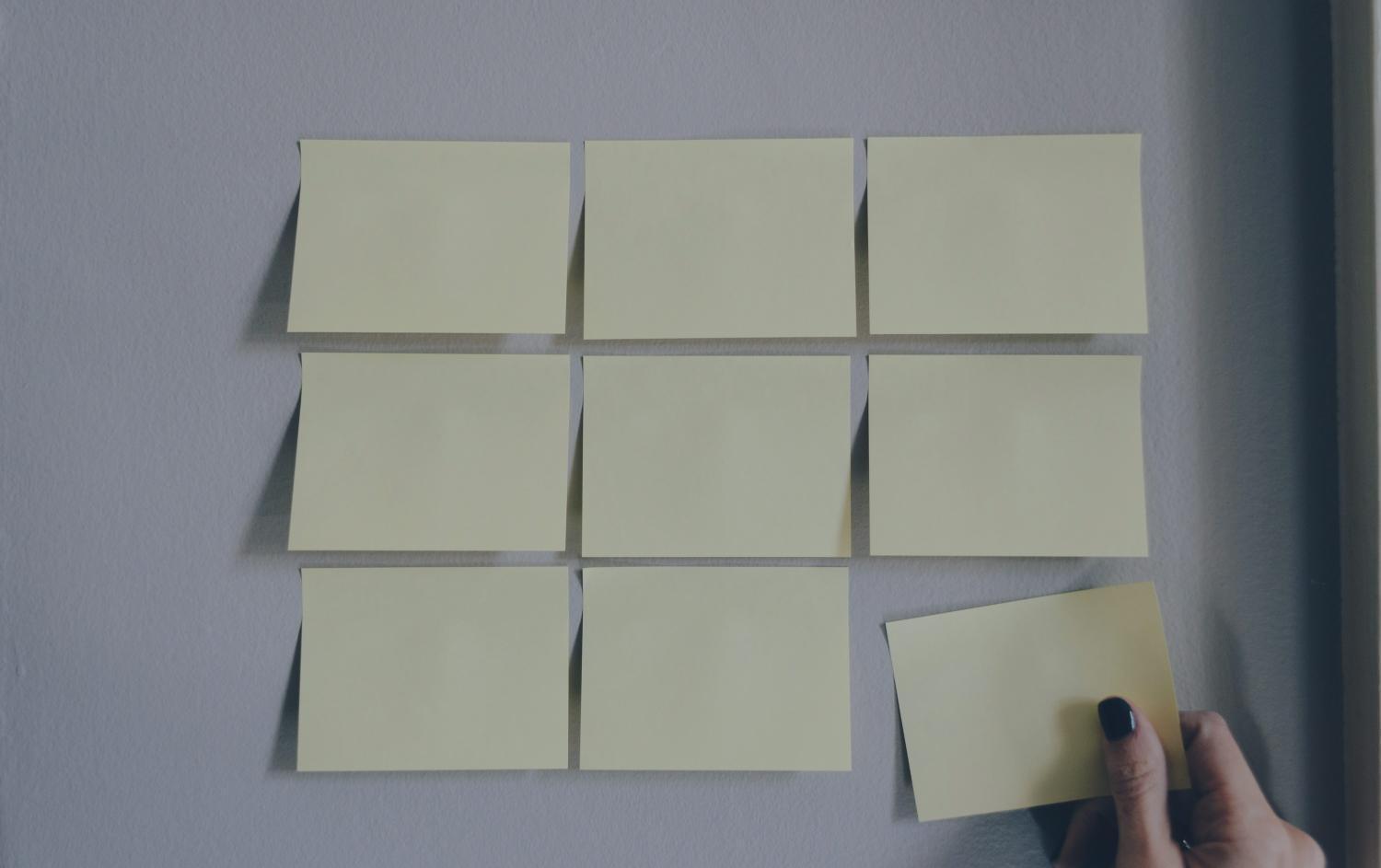
- 事業承継に関する経営者の意思決定
- 親族内継承の意思決定
- 具体的な承継時期の設定
- 経営理念・家訓の明文化
- 後継者の選定と教育プログラムの策定
- 後継者の人選(資質・能力の見極め)
- 後継者の意思確認
- 教育プログラムの策定(OJT・Off-JTの設計)
- 株式・事業用資産の集約方法の検討
- 株式の集約スキームの設計
- 遺留分に配慮した相続対策
- 経営承継円滑化法に基づく認定の取得
- 税務・法務面でのリスク対策
- 顧問税理士・弁護士への相談
- 自社株評価方法の選択
- 必要な税務申告・各種届出の洗い出し
- 従業員・取引先への説明
- 役員会・従業員向け説明会の開催
- 取引先への挨拶回り
- 承継プランの社外への公表(プレスリリース等)
- 財務基盤の強化
- 自社の財務状況の精査
- 必要資金の試算と調達方法の検討
- 金融機関との折衝(借入条件の改善等)
- 家族・親族間の合意形成
- 家族会議の開催
- 親族間の意見調整
- 財産分与・遺言書の作成
継承プロセスには、以上のような論点が含まれます。
このリストを基に、自社の準備状況をチェックしてみてはいかがでしょうか。不足している部分については、早めに着手することが重要です。
事業承継に関する支援制度と相談先
最後に、事業承継の実務で役立つ支援制度と相談先を紹介しておきます。
事業承継・引継ぎ支援センター
各都道府県に設置された公的機関で、事業承継やM&Aに関する無料の相談に乗ってもらえます。専門家による伴走支援のほか、プレマッチング支援、事業承継診断なども行っています。親族内継承の悩みを抱える経営者にとって、頼れるパートナーと言えるでしょう。
中小企業基盤整備機構
中小企業の支援機関に対するサポートのほか、経営者向けのセミナーなどを開催しています。支援機関との連携を通じて、事業承継ニーズの掘り起こしと、課題解決に向けた情報提供を行っています。
金融機関の事業承継支援
メインバンクを中心に、多くの金融機関が事業承継支援に注力しています。M&Aのマッチング支援から、株価算定、財務デューデリジェンスまで、幅広いサービスを提供。難易度の高い親族内継承でも、専門的な知見とネットワークを活かした伴走支援が期待できます。
各士業の専門家
事業承継の個別論点については、税理士・公認会計士・弁護士・司法書士といった専門家の助言が欠かせません。各種専門家から成るチームを組成し、バランスの取れたアドバイスを受けることが理想的です。日頃から顧問先とのリレーションを深め、いざという時に備えておくことが重要でしょう。
事業承継の相談窓口6選!相談相手の選び方や注意点まで徹底解説
最後に
以上、親族内継承の基本的な考え方から実務的な注意点まで、幅広く解説してまいりました。事業承継は一朝一夕に成し遂げられるものではありません。経営者のリーダーシップを起点に、後継者・従業員・親族が一丸となって、理想の承継に向けて歩みを進めることが重要です。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。