債務超過でも事業承継は可能なのか?倒産との違い・対処法を解説
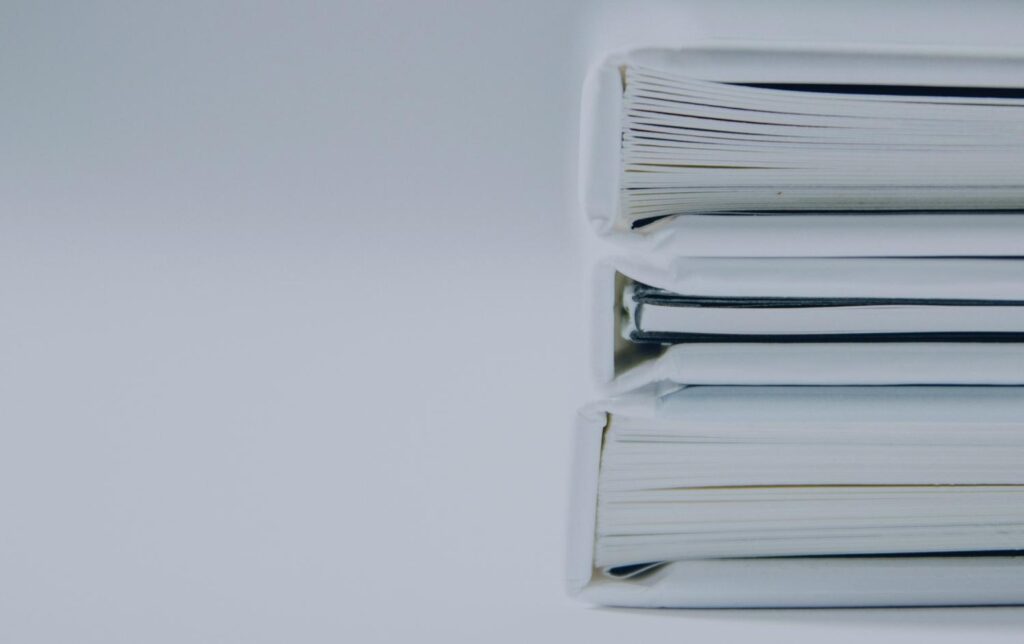
事業承継を検討する際、「債務超過でも事業承継は可能なのか?」という疑問が浮かぶかもしれません。特に起業したばかりのベンチャー企業では資本金の額が小規模であるため、債務超過に陥ることは珍しくありません。そこで、債務超過と倒産との関係や債務超過を避ける方法、や事業承継は可能かなどについて、Seven Rich会計事務所の日野陽一さんにお話を伺いました。
目次
1.債務超過とは何か
債務超過の定義から話を進めます。
結論から述べると、債務超過と赤字・倒産は別概念です。
①債務超過とは
資産や負債をどの程度保有しているのか等の企業の財務状況を表すのが「貸借対照表」です。この貸借対照表を確認すると左側に「資産の部」、右側に「負債の部」が記載されていますが、この資産額よりも負債の金額が大きい状態であればその企業は債務超過に陥ったといえます。
②倒産とは
他方、倒産とは企業が経営を継続できない状態を指すので、債務超過と倒産はまったく別の問題です。つまり企業が債務超過に陥ったとしても、企業活動自体は継続可能です。たとえば資産が100万円で負債が200万円であれば、その企業は債務超過の状態に陥っています。しかし負債の中には銀行融資で長期にわたって返済する負債も含まれています。そのため、200万円のうち190万円を長期で返済する能力を企業が有していれば、負債が200万円でも企業は事業を継続可能です。つまり、企業は負債をすぐに返済する必要はありません。
③赤字との違い
赤字とは、損益計算書において支出が収入を上回っている状態を指すものであり、債務超過とは異なります。
赤字は1事業年度において収益がマイナスになっている状態であり、債務超過は期間にかかわらず会社の資本がマイナスになっていることを指します。
経営状況を改善すべき状態という点では同じですが、赤字だからといって債務超過とは限りません。
当期の収益が赤字の場合でも、資産を多く保有していれば債務超過にはなりません。また、債務超過の状態になっていたとしても、当期の収益は黒字になっていることもあります。
④上場企業の債務超過
日本の場合、上場企業が2期連続債務超過に陥ると、上場廃止が決定されます。ところが海外の場合には、企業が債務超過でも上場やその維持が可能です。海外では上場廃止の要件が日本ほど厳格ではないので、意図的に債務超過にする企業も存在します。現在アメリカの金利は安い状態なので、スターバックスやマクドナルドなどの上場企業は借入金で自社株を購入して株主を減らす等、意図的に債務超過にしています。
⑤債務超過と倒産との相関関係
債務超過と倒産とのあいだに相関関係が成り立ちますが、債務超過だから倒産するという因果関係が成立するとは限りません。
債務超過に陥っていても、経営が可能な中小企業も多く存在します。出資を受けて多額の資金調達している企業は債務超過に陥っていませんが、主に銀行融資で成長しているスタートアップ企業は債務超過に陥っているケースが多く散見されます。つまり企業が5~7年といった長期の借入をしている場合にはすぐにその借入金を返済する必要はないので、債務超過でも経営の継続や企業の成長が可能です。
2.債務超過の原因
では、なぜ企業は債務超過に陥るのでしょうか。
(1)債務超過が起こる原因
債務超過の主な原因は赤字です。貸借対照表の「純資産の部」に含まれる資本金や資本準備金の合計額を企業の累積赤字が超える場合には、企業は債務超過に陥ります。たとえば、資本金100万円で企業を設立した場合、1年で500万円の赤字が発生すれば400万円の債務超過です。
債務超過に陥ると企業に対する銀行からの評価が下がります。融資をする際の基準があり、債務超過かどうかが重視されているポイントです。ただし企業が利益を出している場合でも、債務超過に陥っている事例もあります。たとえば過去に大量赤字を計上して最近に入り黒字へと転じた企業の場合、直近の黒字よりも累積赤字の金額が大きく債務超過に陥ることも理解しておきましょう。もちろん債務超過であっても直近の業績などが評価され、銀行などから融資を受けるケースはあります。ただし、債務超過が解消された状態と比べると、融資金額が下がるケースが多いため、債務超過にならないに越したことはありません。
(2)債務超過により倒産した企業の事例
上場企業の債務超過による倒産の事例は多くありません。2期連続で債務超過に陥れば上場廃止になるので、どの企業も債務超過にならないように努力をしています。また債務超過に陥ったからといって企業が倒産するとは限りません。そのため、事例として表に現れることは少ないでしょう。
企業倒産情報は東京商工リサーチに掲載されています。たとえば、2019年度の倒産企業としてパナソニックの子会社であるMT映像ディスプレイが挙げられます。液晶との競合が激化したため赤字体質になり、2018年3月期に債務超過に陥ったことが確認可能です。
MT映像ディスプレイの場合、有機ELなど、競合する製品によって液晶の売上が減少したという事例です。東京商工リサーチによると、2019年の倒産企業のうち債務超過に陥っていた企業は61.4%だと記載されています。
3.債務超過の企業を事業承継するリスク
債務超過の企業を事業承継するリスクには、次の2つがあります。
-
- 負債が引き継がれる
- 連帯保証人が引き継がれる
事業承継後にトラブルが発生しないように理解しておきましょう。
(1)負債が引き継がれる
事業承継をする際、会社の経営権や資産だけでなく、負債まで引き継がれてしまう点は大きなリスクです。
負債がある場合、返済のスケジュールが決まった状態で後継者に引き継がれてしまい、会社の収益から返済し続けなければなりません。
会社の収益が減り、返済が滞ってしまうと資産の売却を求められる場合もあり、経営が悪化してしまう恐れもあります。
負債があることや返済のスケジュールなどを伝えずに事業承継をすると、後継者が退職してしまう可能性もあります。
資金面でトラブルが発生すると、経営にも大きな影響を与えるので、あらかじめ後継者に伝えたうえで対策を講じましょう。
(2)連帯保証人が引き継がれる
事業承継を行うと、連帯保証人が引き継がれる点もリスクのひとつです。
会社の負債は会社のものであり、経営者や代表に返済義務はないので、倒産した場合でも経営者に支払い義務はありません。
ただし、資金を借りる際に経営者が会社の連帯保証人となっている場合、返済義務があります。
事業承継時には、連帯保証人も引き継がれてしまうため、万が一の際には後継者が返済する必要があります。
事業承継時に経営状況が悪く、廃業や倒産を検討しなければならない場合は、あらかじめ後継者にも説明をしておきましょう。
4.債務超過による倒産を未然に防ぐために
債務超過と倒産とは相関関係のみが成立し因果関係が成立しているとは限りませんが、債務超過が原因で企業が倒産したという可能性は否定していません。これがこの節で述べる話の大前提です。
先述の通り、債務超過は累積赤字によって発生します。そのため、本業で黒字を出していくのがひとつの対策として挙げられます。黒字倒産にも該当しますが、倒産は資金繰りのショートが原因で発生するので、企業が堅実な資金調達を継続することも重要です。中小企業の場合、主に銀行融資で資金調達を行いますが、着金までの期間が2〜3ヶ月、長いと半年にも及びます。そのため銀行融資で資金繰りが間に合わない場合にはファクタリングによって企業は資金化が可能です。このような手段を利用しつつ、資金をショートさせないよう経営を継続することが可能です。
総括すると、キャッシュ・フローをどのような手段で発生させるかに帰着します。本業で黒字を計上しながら、キャッシュ・フローをしっかり確保するという両輪で進めるのが重要です。
5.債務超過に陥った場合の対処法
債務超過時の対処法として事例を4つ挙げています。債務超過を解消する場合には、貸借対照表にある「純資産の部」が赤字だと債務超過に陥るので、その差分を黒字化する必要があります。
(1)増資
増資し資本金を増やすことが、債務超過を解消するひとつの対処法です。もっとも中小企業の場合には、増資は難しいかもしれません。
たとえば自分の会社を起業した際、資本金を少額の100万円に設定したと仮定します。持続的に事業拡大している場合には、エンジェル投資家やベンチャー・キャピタルなど支援者が会社に増資することが可能です。ただし、エンジェル投資家やベンチャー・キャピタルから出資を受けることはハードルが高いです。また自己資金で増資するケースも考えられますが、その場合には株式総会の開催や登記手続きなどが煩雑になっています。自己資金の場合には、増資ではなく代表からの借入金として会社に資金を入れることが一般的でしょう。
(2)DES(デット・エクイティ・スワップ)
上記でも述べましたように、中小企業で社長が自社に資金を補填した場合には、貸借対照表上、借入金(負債)として計上されるのが一般的です。これにより負債が増え続けるので、借入金を資本金で振り替えることが債務超過を解消する対処法として考えられます。これがDES(デット・エクイティ・スワップ)です。つまり負債から資本金に振り替わるので、債務超過の金額の減少解消が可能です。ただしDESも同様に、増資をする手続きが必要となります。
(3)債務免除
債務免除とは、社長が資金を補填した借入金をDESのように資本金へ振り替えるのではなく、借入金の返済を免除することです。債務免除した場合には、会計上返済を免除した借入金の分だけ負債の金額が減少し、利益として計上されます。そのため黒字になる可能性が高まります。黒字が増えれば「純資産の部」で債務超過の原因だった累積赤字の額が減少し、結果として債務超過の解消が可能です。
総括すると借入金の処理として、DESと債務免除という2つの対処法が考えられます。役員の借入金を資本金として計上することも可能ですし、債務免除により借入金利益として計上するのも可能です。
私の経験上、債務免除よりも繰越欠損金に影響を与えないDESを選択するケースが多いです。
(4)含み益のある遊休資産の売却
最後が含み益のある遊休資産の売却です。たとえば、過去に購入し現在は事業で利用していない土地を所有している場合、会社の決算書には1,000万円など購入時の価格が記載されています。その土地が現時点で値上がりし、1億円で売却したとします。その場合には、1億円と1,000万円の差額である9,000万円が会社の利益として計上可能です。この利益により、累積赤字が解消に向かいます。
7.債務超過の企業を事業承継する際の検討事項
債務超過の企業を事業承継する際には、次の3点も検討しましょう。
-
- 分社化
- 事業再生
- 廃業
3つに関して詳しく紹介するので、債務超過の企業を事業承継するか悩んでいる方はこれらの選択肢も理解したうえで判断しましょう。
(1)分社化
分社化は一部の事業を切り離し、新しく会社を作る方法です。
会社全体として債務超過に陥っており、赤字が増えていたとしても、ひとつの事業だけは黒字を出し続けていることもあるでしょう。
このような場合、収益性の高い黒字事業のみを分社化して事業承継をすれば、後継者に引き継ぐ負債を軽減できます。
分社化には、事業譲渡や新規分割、吸収分割などの方法があり、負債は元の会社に返済義務が残ります。
元の会社で破産をはじめとした手続きを行えば、債務超過を回避できるため、事業継承方法に悩んでいる方は分社化を検討してみてはいかがでしょうか。
(2)事業再生
事業再生とは、会社が債務超過などに陥った際に事業を抜本的に改革し、廃業や倒産をせずに収益力を取り戻す手段です。
事業再生を行うためには、次の2つの観点から存続させるべきかを各都道府県の家庭裁判所に判断されます。
-
- 負債がなくなれば再生が可能か
- 再生する価値がある事業か
収益力が取り戻せる可能性がある事業に関しては、事業再生を検討してみてはいかがでしょうか。
また、国が中小企業向けに「事業承継・引継ぎ補助金」を行っており、補助を受けながら事業再生を進められるので、必要な企業はぜひ利用してください。
(3)廃業
債務超過により経営が改善できず、収益力のある事業もない場合は、事業承継ではなく廃業も検討しましょう。
株式会社の場合、株主総会の特別決議によって解散を決議し、解散登記をしてから清算手続きを行います。
複雑な手続きであり、従業員の職を奪う結果となりますが、後継者に負債を背負わせることは避けられます。
会社の債務を完済できない場合には廃業ではなく倒産となり、異なる手続きとなるため、会社をたたもうと考えた際の対応は弁護士や税理士などに相談しましょう。
8.リスクを理解したうえで債務超過の事業承継を行うか判断しよう
債務超過の事業を承継する場合、負債や連帯保証人が後継者に引き継がれてしまう点に注意しましょう。
負債や連帯保証人を引き継がないための対策として、事業承継ではなく、分社化や事業再生、廃業をはじめとした他の選択肢も検討してみてはいかがでしょうか。
事業承継や分社化などを行う場合、専門家に相談して適切なサポートを受けることが重要です。当社が運営する「TSUNAGU」では、希望に沿った会社を提示し、最適なマッチングを実現できるようにサポートします。着手金なしで相談できるので、お気軽にお問い合わせください。
Description
債務超過の事業を承継する場合、どのようなリスクがあるか気になる方もいるでしょう。本記事では、債務超過の概要や原因、事業承継するリスクなどを紹介します。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。


