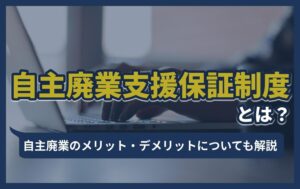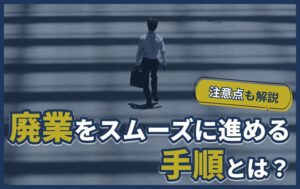第三者継承で失敗しない方法とは?よくある落とし穴とその対策
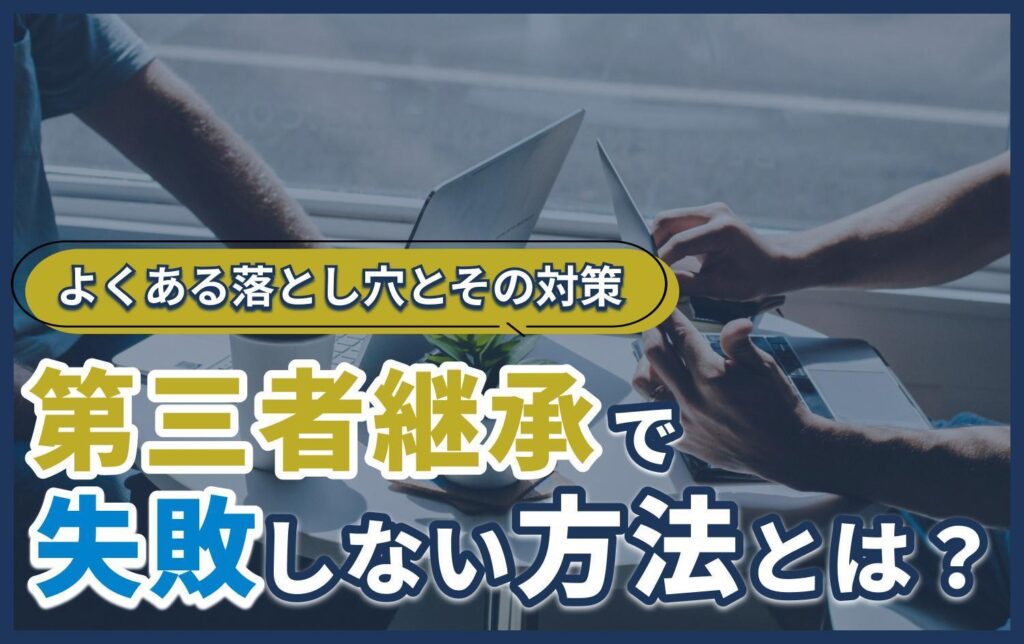
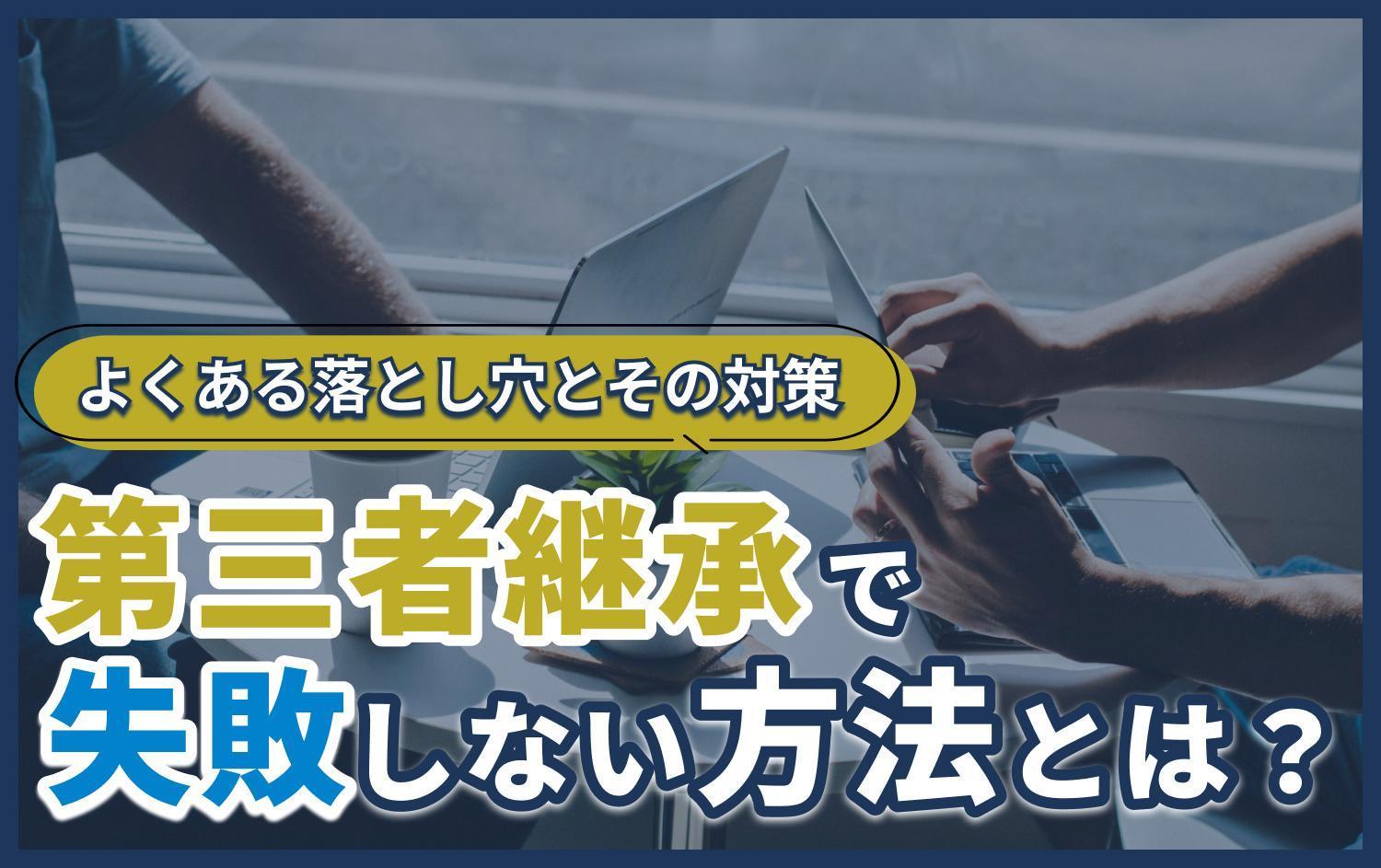
「第三者承継を検討しているが、本当にうまくいくのだろうか」「他社の失敗事例を見ると、不安が募る一方だ」――。
このような悩みを抱える経営者の方は少なくないでしょう。
特に、後継者不在に頭を悩ませる中小企業の経営者にとって、第三者承継は魅力的な選択肢である一方で、リスクも伴う難しい決断と言えます。
しかし、失敗事例から学び、適切な対策を行うことで、第三者承継の成功確率を高めることは可能です。
この記事では、第三者承継の典型的な失敗パターンと、その原因、リスク管理の方法から、承継計画の策定、円滑な承継のためのコミュニケーション戦略まで解説していきます。
第三者承継の失敗パターンと対策
第三者承継を行う際に、経営者が陥りがちな失敗パターンと対策について解説します。
(1)事業の将来性の見極めの甘さ
第三者承継先の選定において、事業の将来性や市場性を適切に見極められず、衰退産業や競争の激しい業界の企業を承継先に選んでしまうケースがあります。
対策としては、コンサルタントなど外部の専門家の知見も借りつつ、客観的なデータに基づいて市場分析を行うことが重要です。加えて、承継先企業の強みや独自性にも着目し、事業の優位性を多角的に評価することが求められます。
(2)財務デューデリジェンスの不十分さ
承継先企業の財務状況を十分に精査せず、簿外債務などの隠れた負債を見落としてしまうケースも少なくありません。
対策としては、財務の専門家を交えて、綿密なデューデリジェンスを実施することが欠かせません。
過去の財務諸表だけでなく、直近の資金繰りや債権債務の状況にも注意を払う必要があります。
(3)企業文化の違いの軽視
企業文化の違いを軽視し、経営理念やワークスタイルの衝突から、従業員の離反を招くケースもあります。
対策としては、事前に両社の企業文化を入念に分析し、すり合わせを図ることが重要です。
トップのメッセージ発信や、両社の従業員交流など、文化の融和に向けた施策を積極的に展開することが求められます。
(4)統合プロセスの混乱
統合に向けたロードマップが不明確で、責任の所在が曖昧なまま統合を進めると、業務プロセスの混乱を招きかねません。対策としては、
統合推進の専任チームを立ち上げ、詳細な統合プランを策定することが重要です。
役割分担を明確にし、両社の従業員に対して統合の進捗を適宜公開するなど、透明性の高いプロジェクト管理が求められます。
(5)株主間の合意形成の難航
株主間の利害対立から、承継条件の合意形成が難航するケースも見られます。対策としては、株主間の対話を粘り強く重ね、互いの立場を理解することが重要です。
第三者の調停を仰ぐことも一案でしょう。株主間契約など、法的な論点にも早期から取り組み、円滑な合意形成を目指すことが求められます。
第三者承継を成功に導くには、これらの失敗パターンを念頭に、入念な準備と適切な対策を講じることが何より重要です。自社の状況を冷静に分析し、専門家の知見も交えつつ、周到な計画を立てることが肝要だと言えるでしょう。
(6)派閥争いに後継者が巻き込まれる
社内に派閥が存在する場合、事業承継を機に派閥争いが激化する場合があります。
そのため、事業承継の前に、社内の派閥争いをできる限り解消しておくことが肝要です。全社で一丸となって事業承継に臨める準備を整えましょう。
(7)既存の従業員からの不満
「自分たちではなく、よそ者が経営者になるのか」といった不満が、社内の紛争を引き起こすことがあります。第三者への事業承継では、従業員の考え方を得ることが難しいケースがあります。 丁寧な説明と対話を重ね、従業員の不安を解消する努力が必要です。
(8)引退後も、創業者が影響力を維持する
事業承継後も、引退した創業者が会社に影響力を保ち続けるケースがあります。後継者の経営の自由度が制限され、自由な決断ができなくなってしまうのです。事業承継の際は、引退する経営者の影響力をコントロールすることが大切です。
後継者が自らの経営方針を実現できるよう、適切な権限委譲を行いましょう。
(9)事業承継後の業績不振
引き継いだ後、後任の未熟さから、業績が悪化するケースがあります。会社の存続が危険な状況に陥ることもあります。
事業承継の際は、後継者の経営能力を見極めることが重要です。必要に応じて、経営幹部による支援体制を整えるなど、リスク対策を行いましょう。
(10)専門家に相談しないまま事業承継を進めてしまう
専門家に相談せず、自社だけで事業承継を進めてしまうケースがあります。法律や税務の知識不足から、トラブルに巻き込まれる恐れがあるのです。
M&Aの相談はどこにすればいい?相談の内容や相手、選定方法などを紹介
業種別にみる第三者承継の注意点

近年、M&Aが活発化している業界では、第三者承継のニーズも高まっています。ここでは、業種別に注意すべき点について解説していきます。
(1)製造業における注意点
製造業では、技術継承の失敗が事業承継の大きなつまずきとなることがあります。特に、高度な専門技術を持つ企業では、後継者への技術伝承が円滑に進まないケースが見られます。承継先企業の技術力を見極めつつ、計画的な技術移転を進めることが重要となります。
(2)小売業における注意点
小売業では、店舗運営ノウハウの継承に失敗するケースが少なくありません。仕入れや在庫管理、接客といった個人商店ならではのノウハウが、スムーズに引き継がれない事例が見受けられます。暗黙知の「形式知化」を進め、マニュアルの整備などを通じて、ノウハウの継承を確実なものとすることが求められます。
アパレル業界のMA動向・スキーム・価格相場・事例・実施メリット
(3)サービス業における注意点
サービス業では、独自の企業文化の継承に苦しむケースが目立ちます。特に、カリスマ経営者の下で独特の文化を築いてきた企業では、その継承が難しい場合があります。企業文化の見える化を図りつつ、承継先企業との文化的な融和を粘り強く進めることが肝要です。
ホテル・旅館業界のM&A動向・スキーム・価格相場・事例・メリット
(4)調剤薬局における注意点
近年、調剤薬局業界でもM&Aが活発化していますが、薬剤師の確保や薬局運営の非効率化から、期待した統合効果を得られないケースも少なくありません。薬剤師の処遇改善などを通じて優秀な人材を確保しつつ、業務フローの最適化にも注力することが重要となります。
調剤薬局におけるM&Aとは?業界動向・価格相場から事例紹介まで
(5)IT業界における注意点
IT企業の第三者承継では、技術者の離反リスクが高いことが特徴です。キーパーソンの処遇を早期に協議し、インセンティブ設計などを通じて優秀な人材の確保に努めることが求められます。加えて、知的財産の棚卸しと適切な権利処理にも留意が必要です。
(6)飲食業界における注意点
飲食業界でも、M&Aを通じた事業承継が増えつつありますが、店舗業態の不一致などから、統合に苦慮するケースが見られます。承継先企業の業態や顧客層を見極めつつ、メニュー開発や営業施策の融合を図ることが重要となります。衛生管理面での摺合せにも注意が必要です。
(7)建築業界における注意点
建築業界では、職人の高齢化が進む中、技術継承の問題が深刻化しています。若手職人の育成に注力しつつ、設計図面や施工ノウハウのデジタル化なども積極的に進めることが求められます。工事の引き継ぎや下請け業者との関係承継、建設機械などの資産評価の問題などに留意しつつ、スムーズな事業承継を目指すことが肝要です。
このように、業界ごとに第三者承継の特徴と留意点は異なります。自社の業種特性を踏まえつつ、他社の失敗事例からも学ぶ姿勢が、承継の成功を左右すると言えるでしょう。
未然にトラブルを防ぐ、関係者とのコミュニケーションのコツ
第三者承継を円滑に進めるには、ステークホルダーとの適切なコミュニケーションが欠かせません。ここでは、ステークホルダーごとのコミュニケーションのコツを確認しましょう。
(1)従業員とのコミュニケーション
第三者承継では、従業員の不安を払拭することが大きな課題となります。社内報やイントラネットを活用し、承継の方針や進捗状況を丁寧に伝えることが求められます。
加えて、経営陣と従業員の対話集会を開催するなど、双方向のコミュニケーションも欠かせません。率直な意見交換を通じて、従業員の理解と協力を得ることが重要です。
(2)取引先とのコミュニケーション
取引先に対しては、承継後もビジネスが継続されることを丁寧に説明する必要があります。代表挨拶状の送付や、個別訪問など、きめ細かな対応が求められます。
特に、重要な取引先には、新旧経営陣が揃って挨拶に伺うことが望ましいでしょう。事業承継を機に、さらなる関係強化を図る姿勢を示すことが肝要です。
(3)株主・金融機関とのコミュニケーション
株主や金融機関に対しては、事業承継の意義や、承継後の事業計画を丁寧に説明することが重要です。株主総会や、個別の説明会を開催し、理解と支援を求めることが求められます。
金融機関に対しては、承継後の資金繰り計画を示し、継続的な支援を要請することも必要です。早めに相談を始め、信頼関係を構築しておくことが肝心だと言えます。
このように、ステークホルダーごとにきめ細かなコミュニケーションを展開することが、円滑な事業承継の鍵を握ります。一方通行ではない、双方向の対話を心がけることが何より大切です。
まとめ
第三者承継は、後継者不在に悩む中小企業にとって魅力的な選択肢ですが、同時にリスクも伴う難しい決断です。しかし、適切なタイミングで適切な対策を行うことで、その成功確率を高めることができます。
まずは、第三者承継の典型的な失敗パターンを知ることが重要です。事業の将来性の見極めの甘さ、財務デューデリジェンスの不十分さ、企業文化の違いの軽視、統合プロセスの混乱、株主間の合意形成の難航を想定し、入念な準備と対策が求められます。
また、業界ごとに第三者承継の特徴と注意点が異なります。自社の業種特性を踏まえ、他社の失敗事例から学ぶ姿勢も大切です。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。