自主廃業支援保証制度とは?自主廃業のメリット・デメリットについても解説
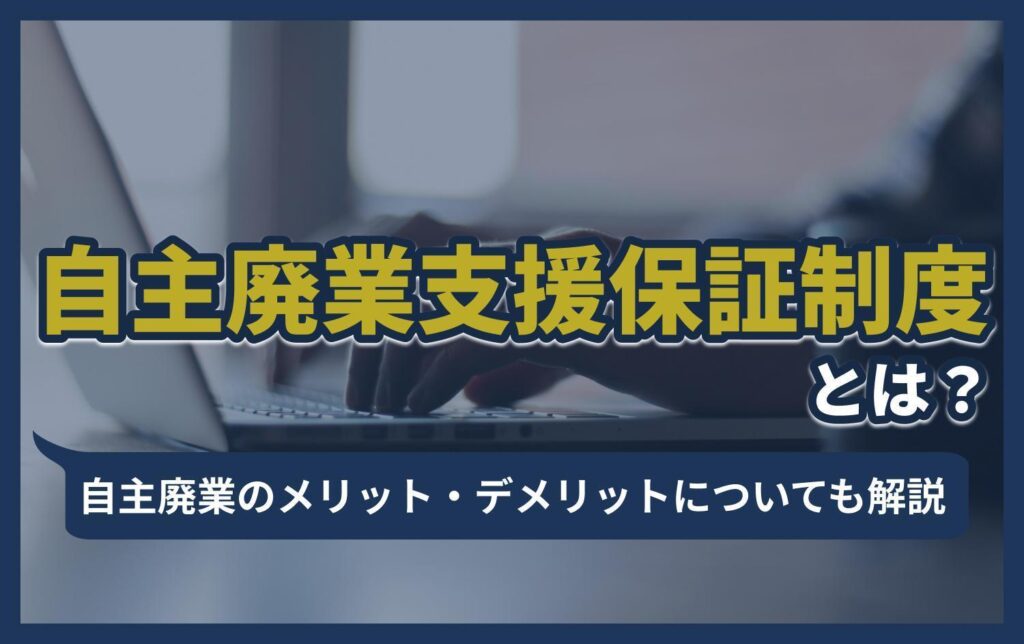
「廃業」という言葉に、どのようなイメージを抱かれるでしょうか。苦渋の選択、あるいは最後の手段といったネガティブな印象を持つ方も少なくないかもしれません。しかし、時代の変化とともに、廃業の意味合いも変わりつつあります。
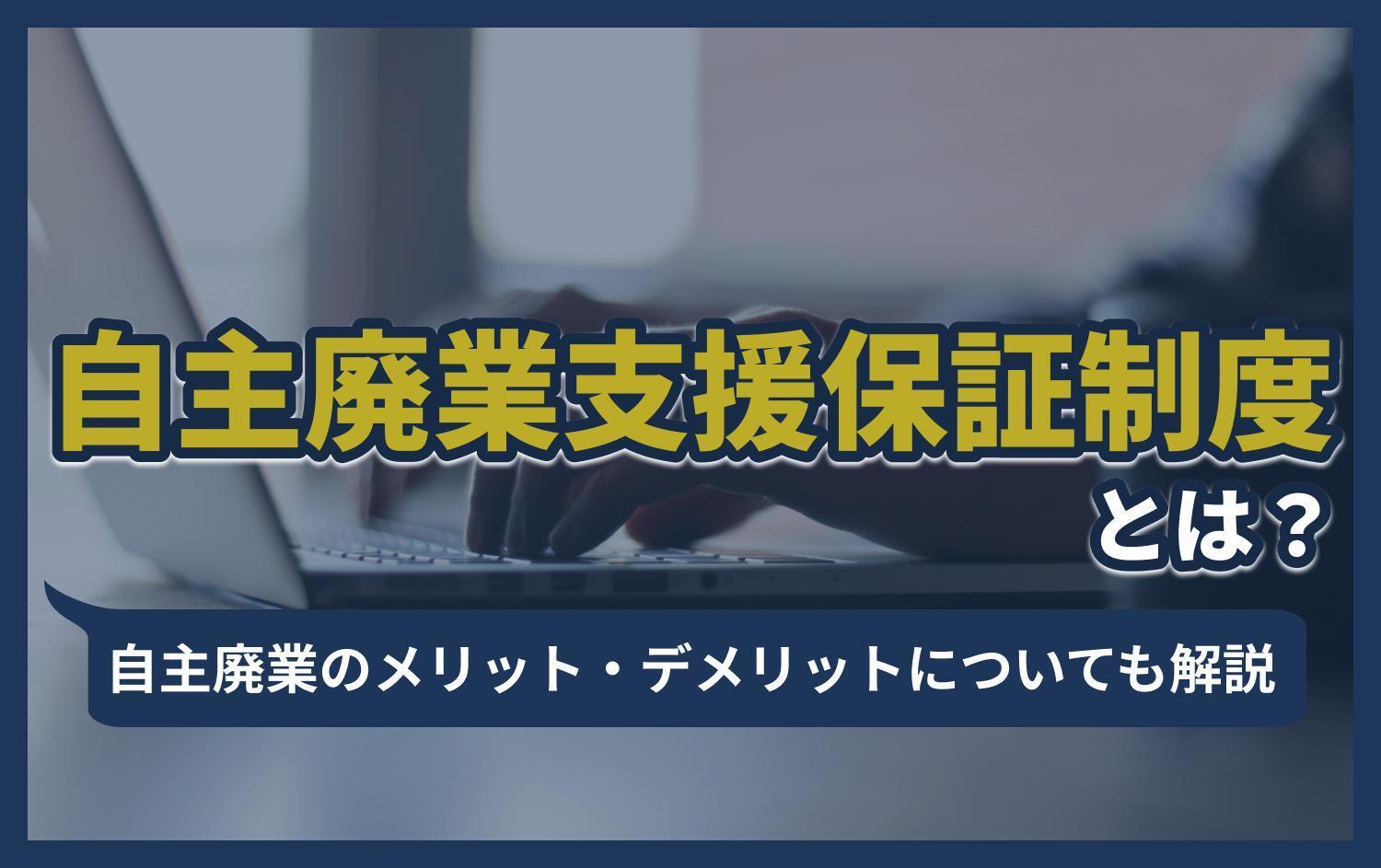
特に後継者問題に悩まれている方。自主廃業という選択肢は、新たな人生の扉を開くチャンスかもしれません。そのきっかけとなるのが、自主廃業支援保証です。
本記事では、この制度の概要や活用方法、そして自主廃業後の人生設計について解説します。廃業を前向きな一歩として捉え直し、未来を切り開くヒントを見つけていきましょう。
目次
自主廃業支援保証の必要性とは?
長年事業を営んできた経営者にとって、廃業は簡単には踏み出せない決断です。事業の将来性への不安、借入金の返済、従業員の雇用、取引先への影響など、様々な課題が立ちはだかります。
事業承継やM&Aは、事業を存続させる有力な選択肢ですが、適切な候補者が見つからない、あるいは条件面で折り合いがつかないなど、思うように進まないケースも多いのが実情です。
こうした状況下で、円滑な廃業を支援する制度の重要性が高まっています。
自主廃業支援保証とは何か?
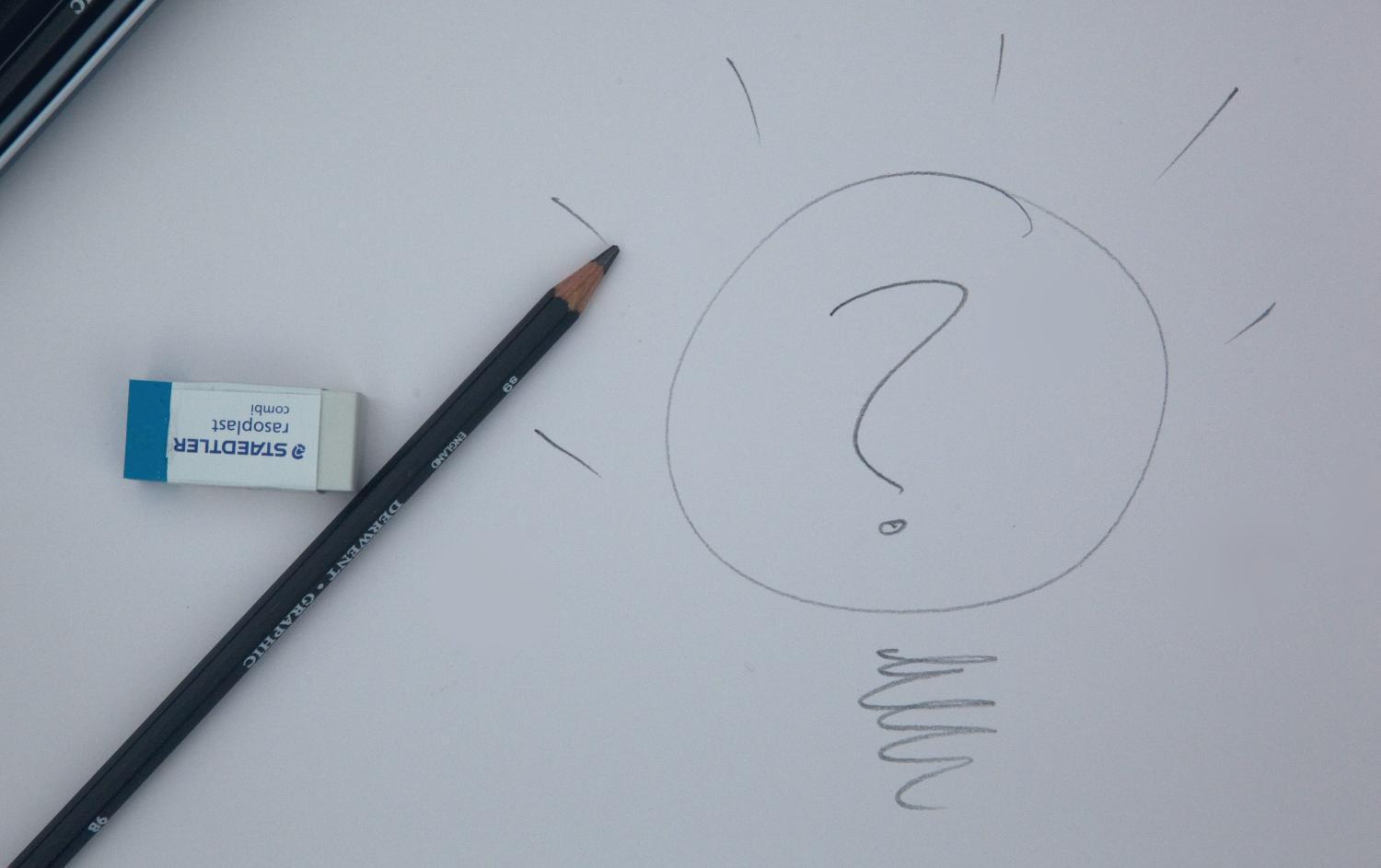
自主廃業支援保証とは、事業譲渡やM&Aによる事業継続が見込めず、自ら廃業を選択する中小企業者を支援する制度です。信用保証協会が、廃業に必要な資金について保証を行います。
この保証の対象となるのは、経営状況や資産内容を踏まえ、今後も事業を継続することが困難と判断される中小企業者です。具体的には、以下のような条件があります。
-
- 事業譲渡や経営者交代等による事業継続が見込めず自ら廃業を選択するもの。
- 債務超過でなく、事業生産により債務の完済が見込めること。
- バンクミーティング等により合意に至った廃業計画書に従って計画の実行及び進捗の報告を行うもの。
加えて、信用保証協会は、申込み企業の事業内容や経営者の資質なども審査します。事業に将来性がないと判断された場合や、経営者の誠実性に欠けると認められた場合は、保証の対象外となる可能性があります。
自主廃業支援保証のメカニズムは、次のようになっています。まず、中小企業者は金融機関に対し、廃業計画を提出します。金融機関は、その計画の妥当性を審査し、信用保証協会に保証を申し込みます。保証が承諾されれば、金融機関から中小企業に対し、廃業資金が融資されます。
こうして、経営者は金融面の不安を軽減しながら、円滑な廃業を進めることができるのです。
自主廃業のメリット
自主廃業のメリットについて、解説していきます。
①自主廃業支援保証を利用することで、借入金の支払い負担減
自主廃業を検討する経営者の皆様にとって、借入金の支払いは大きな負担となります。この制度を利用することで、信用保証協会が借入金の一部を保証してくれます。つまり、経営者の皆様の返済負担を軽減することができるのです。
②事業譲渡やM&Aに比べ、手続きが簡単
事業承継の選択肢として、事業譲渡やM&Aが候補に挙げられますが、これらの手続きには時間と労力がかかります。一方、自主廃業は、事業譲渡やM&Aに比べて、手続きが簡略化されています。会社の清算手続きを進めるだけですので、比較的スピーディに廃業することができるのです。
自主廃業のデメリット
自主廃業にはどのようなデメリットがあるのでしょうか。ここでは、経営者が直面するリスクについて、3つのポイントを挙げてみたいと思います。
①信用が毀損される
自主廃業を選択すると、事業の清算に伴って信用が毀損される可能性があります。取引先や金融機関から「信頼できない」と見なされてしまうかもしれません。
例えば、自主廃業の理由が経営難だった場合、取引先から「債務を返済できない会社だ」と受け止められるリスクがあります。また、事業を清算するということは、継続的な取引関係を絶つことを意味します。長年築いてきた取引先との関係性が失われてしまうのです。
②同じ業界での再起が難しくなるリスク
自主廃業を選択すると、同業界での再起が難しくなるかもしれません。事業の清算は、経営者としての実績に傷がつくことを意味するからです。
同業界の関係者から「あの会社は自主廃業した」と認識されると、ネガティブなイメージが付きまとうことになります。新たに事業を始める際に、取引先や顧客から信頼を得るのが難しくなる可能性があります。
③廃業資金の返済義務は残る
自主廃業を選択しても、廃業資金の返済義務は残ります。事業の清算に伴い、金融機関からの借入金を返済しなければならないのです。廃業資金の返済は、経営者の個人資産にも影響を及ぼすことがあります。
事業用の資産だけでは返済資金が不足する場合、個人の資産を処分せざるを得なくなるかもしれません。
自宅や貯蓄などの個人資産に手をつけることになれば、経営者の生活基盤が揺らぐリスクがあります。
廃業資金の返済計画は、自主廃業を決断する前に綿密に立てておく必要があります。返済義務を履行できなければ、経営者個人の信用にも傷がつくことを忘れてはいけません。
自主廃業支援保証の手続きの流れ

-
- 金融機関に相談し、廃業計画を作成。
- 信用保証協会に保証を申込み。
- 保証承諾後、金融機関から廃業資金の融資。
- 融資を受けて、廃業の準備を進める。
- 事業の清算と債務の弁済。
必要書類は、信用保証協会や金融機関によって異なりますが、一般的には、廃業計画書、直近の決算書、資産の明細などが求められます。手続きの詳細は、最寄りの金融機関や信用保証協会へご相談ください。
廃業計画の作成方法
自主廃業支援保証の申込みに際しては、綿密な廃業計画の作成が求められます。ここでは、その作成方法を段階的に解説しましょう。
廃業までのスケジュールを設定する
まず、廃業の目標時期を決め、そこから逆算して、具体的なスケジュールを立てます。資産の処分、従業員への説明、取引先への連絡など、実行すべきタスクを洗い出し、期限を設定していきます。
資産の評価と処分方法を検討する
事業用資産の評価を行い、売却可能なものとそうでないものを仕分けします。不要資産は、できるだけ早期に処分し、現金化を図ります。売却が難しい資産については、廃棄などの方法を検討します。
従業員や取引先への説明方法を考える
廃業の決定を、従業員や取引先にどのように伝えるか、綿密に考えておく必要があります。説明会の開催や、個別面談の実施など、できる限り誠意を持って対応することが大切です。
廃業すると従業員はどうなる?雇用終了通知から再就職支援まで解説
廃業したら従業員に補償はある?解雇のタイミングや退職金の扱い、雇用を守れるM&Aについても解説
必要な廃業資金を算出する
廃業に際しては、様々な費用が発生します。人件費の清算、在庫の処分、設備の撤去など、必要な資金を詳細に洗い出し、総額を算出しておきましょう。この金額が、自主廃業支援保証の申込み額となります。
以上のステップを踏まえ、廃業計画書を作成します。
計画書には、廃業の目的、スケジュール、資産の処分方法、必要資金の内訳などを明記します。信用保証協会や金融機関との協議を経て、実現可能性の高い計画に仕上げていきます。
廃業にかかる費用・税金はどのくらい?合同会社や個人事業主の廃業も解説
自主廃業を決断するタイミング
「廃業」という選択は、簡単に下せる決断ではありません。しかし、事業の状況によっては、早めの決断が賢明なこともあります。自主廃業を考えるべきタイミングのサインを見逃さないことが大切です。
例えば、以下のような状況は、廃業を検討すべき兆候と言えるでしょう。
-
- 売上の減少が続き、回復の見込みがない。
- 借入金の返済が困難になっている。
- 新規の設備投資が難しく、競争力の低下が避けられない。
- 後継者が見つからない。
業種や規模によっても、廃業のサインは異なります。例えば、小売業であれば、商圏人口の減少や大型店の進出が脅威となり得ます。製造業では、技術の陳腐化や海外移転の圧力が、廃業を検討すべき要因かもしれません。
また、事業承継やM&Aといった選択肢とも比べてみることをおすすめします。
事業に将来性があるなら、承継やM&Aによって事業を存続させることも検討の価値があります。一方、廃業による損失を最小化できるなら、自主廃業はリスクの少ない選択肢と言えるかもしれません。
いずれにしても、早めの情報収集と専門家への相談が、適切な判断の鍵を握ります。特に、以下のようなポイントで専門家の助言を求めることをおすすめします。
-
- 事業の将来性分析と経営判断
- 廃業計画の作成と実行方法
- 自主廃業支援保証の申込み手続き
- 廃業後の資金計画と生活設計
税理士や中小企業診断士、弁護士など、様々な分野の専門家がサポートしてくれます。ためらわずに相談し、最善の道を模索していきましょう。
自主廃業後の人生設計
自主廃業は、事業の終了であると同時に、新しい人生の始まりでもあります。廃業後のキャリアプランを考えることは、廃業の決断を後押しするでしょう。
例えば、長年の経験を活かして、別の企業で活躍することも可能です。あるいは、趣味を仕事にしたり、ボランティア活動に打ち込んだりと、新たな生きがいを見つけるチャンスでもあります。
自主廃業支援保証を利用した場合、返済負担は軽減されるものの、資金的な不安は残るかもしれません。そこで、国や自治体の支援制度を活用し、セーフティネットを確保することも重要です。
最後に
自主廃業を決断するには、勇気が必要です。周囲の反対を押し切り、自分の信念に従って行動するのは容易なことではありません。しかし、その一歩を踏み出す場合、自主廃業支援保証が強力な味方になってくれるはずです。
まずは、自社の状況を正しく把握することから始めましょう。財務データを分析し、事業の将来性を見極めます。その上で、自主廃業のメリットとデメリットを比較検討します。
次に、専門家に相談し、具体的な廃業プランを練っていきます。資産の処分方法や、必要な資金の算出など、一つ一つ確認しながら、実行可能な計画を立てることが大切です。
そして、自主廃業支援保証の申込み手続きに進みます。金融機関や信用保証協会との折衝には、専門家のサポートを受けると良いでしょう。必要書類の準備や、審査への対応など、手続きをスムーズに進められます。
申込みが承諾されたら、いよいよ廃業の実行段階です。計画に沿って、着実に進めていきましょう。従業員や取引先への説明は、誠意を持って行うことが肝要です。
廃業手続きが完了したら、次は新たな人生の始まりです。支援制度を活用しながら、再就職や創業など、新たなチャレンジに挑戦してみてはいかがでしょうか。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。


