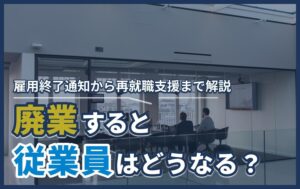債務超過の場合、廃業するしかないのか?支援機関について徹底解説
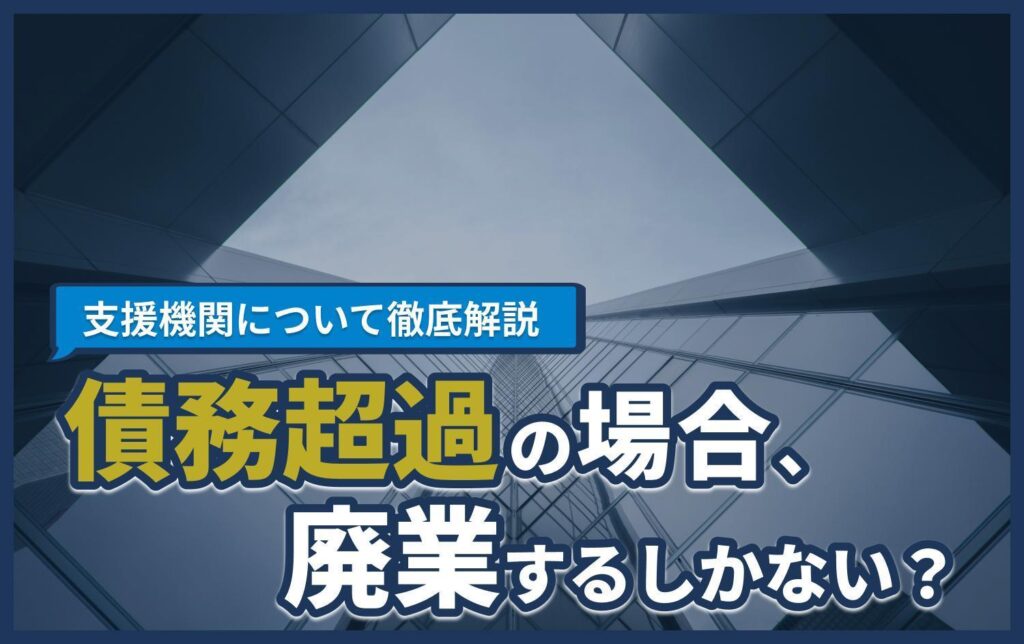
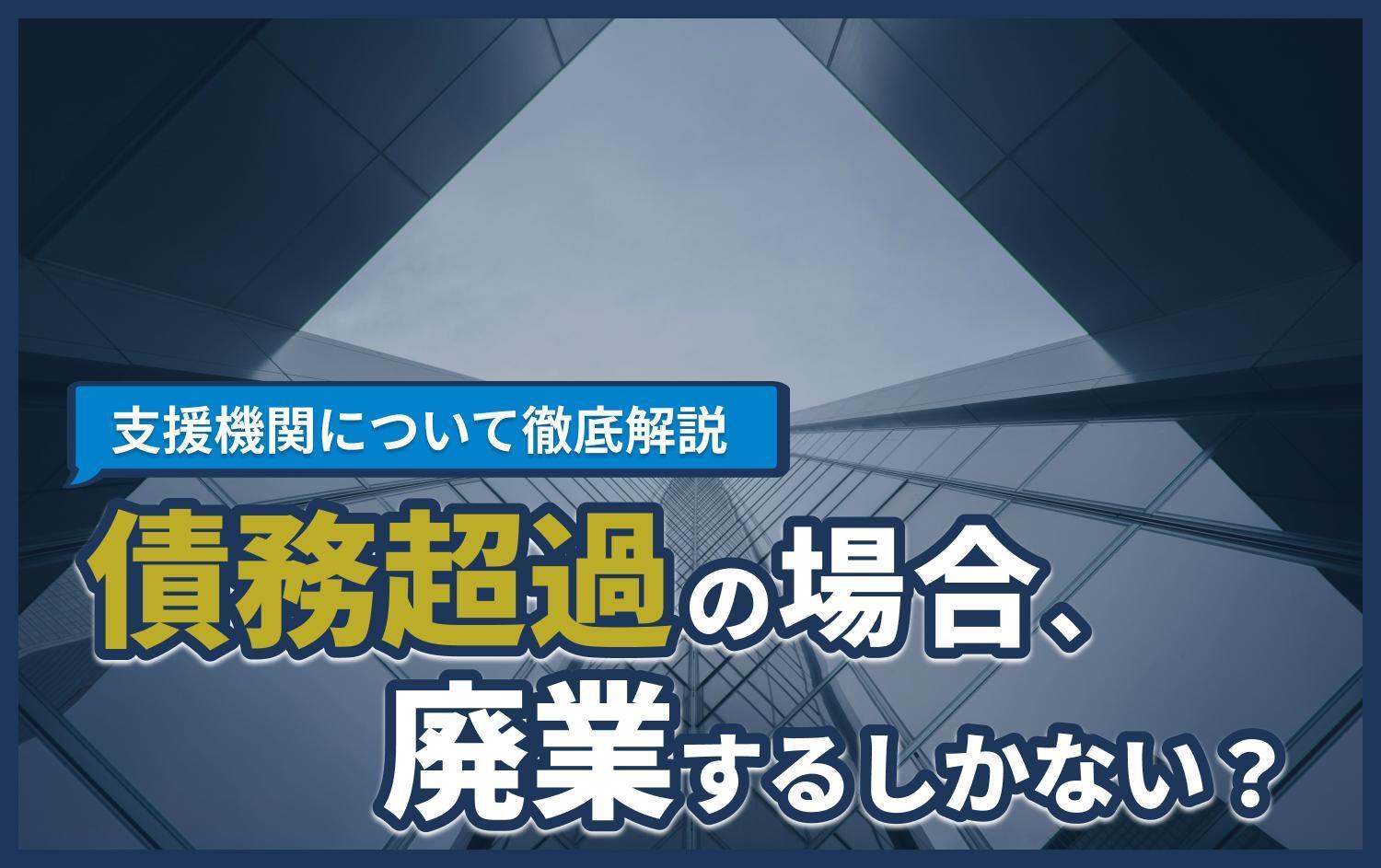
「後継者不在で事業の先行きが見えない…」
「債務超過の状態から抜け出せない…」
このような悩みを抱えている経営者の方は少なくないのではないでしょうか。
事業を続けるか、廃業するか。どちらの選択も勇気のいる決断です。特に、債務超過に陥った状態での廃業は、法的・手続き的な複雑さに加え、経営者の心理的負担も大きいものです。
適切な手順を踏み、専門家の力を借りながら、一つひとつ課題をクリアしていきましょう。
また、状況によっては、債務超過からの脱却を目指す事業再生の選択肢も考えられます。
この記事では、債務超過からの廃業を検討されている経営者の方に向けて、具体的な手順や注意点を詳しくご紹介します。
目次
債務超過に陥る原因と予防策
債務超過とは、会社の負債が資産を上回る状態を指します。
つまり返済不能な借金を抱え、会社の純資産がマイナスに陥ることを意味します。
債務超過の原因は様々ですが、代表的なものとしては以下が挙げられます。
-
- 過剰な設備投資や在庫の積み増し
- 売上の減少や利益率の低下
- 取引先の倒産などによる貸し倒れ
- 代表者の個人的な借入れの会社への付け替え
- 急激な為替変動や自然災害による影響
これらの原因を事前に察知し、手を打つことができれば、債務超過を未然に防ぐことも可能です。
日頃から財務状況をチェックし、資金繰り表を作成するなど、先を見据えた経営管理を心がけましょう。
取引先の与信管理、為替リスクのヘッジ、適切な在庫管理なども欠かせません。
また、経営状況が芳しくない場合は、早めに金融機関や専門家に相談することをおすすめします。
中小企業再生支援協議会など、債務超過に悩む経営者をサポートする公的機関も存在します。
一人で抱え込まず、支援者とともに再建の道を探ることが重要です。
債務超過時の廃業手順
債務超過状態での廃業を考える際、まずは解散の手続きを行います。
解散とは、会社の法人格を消滅させるプロセスです。
株主総会の特別決議を経て、登記と税務署への届出を行う必要があります。
解散後は、清算手続きを進めます。
清算とは、会社の残務を処理し、残った財産を株主に分配するプロセスです。
この段階で、債権者への弁済や配当が行われます。
清算人を選任し、債権者集会を開催するなど、一定の手順を踏む必要があるでしょう。
清算人の主な仕事は以下の通りです。
-
- 会社財産の換価・債権の取立て
- 債権者への弁済・残余財産の株主への分配
- 裁判所への報告・清算事務の引継ぎ
これらの事務を滞りなく進めるために、清算人は弁護士や公認会計士などの専門家と連携することが重要です。
円滑な清算のためには、早めに準備を始め、必要書類を整えておくことをおすすめします。
通常清算と特別清算の違い
債務超過の場合、通常清算よりも特別清算が選択されることがあります。
特別清算は、債権者への配当を公平に行うための手続きであり、倒産手続きの一種とも言えます。
裁判所の監督下で、清算人が公平な債権の弁済を目指します。
特別清算の申立てには、以下の要件を満たす必要があります。
-
- 債務超過又は債務超過の疑いがあること
- 通常清算では債権者への弁済が困難と見込まれること
- 清算人が特別清算開始の申立てを相当と判断すること
要件を満たせば、裁判所に特別清算開始の申立てを行います。
裁判所の審理を経て、特別清算が開始されると、清算人は裁判所の監督下で公平な債権弁済を進めていきます。
特別清算には次のようなメリットがあります。
-
- 裁判所の監督により、公平性・透明性が確保される。
- 債権者からの個別の請求を受けずに済む。
- 清算人の調査権限により、資産の発見や回収がスムーズに進む。
- 倒産処理のスキームに乗ることで、債権放棄など、債権者の協力を得やすい。
一方、特別清算は通常清算よりも手続きが複雑で、時間とコストを要するというデメリットもあります。
債務超過の程度や、債権者の態様など、会社の状況に応じて適切な手続きを選択する必要があるでしょう。
債務超過時の破産手続き

特別清算が困難な場合、または債務超過の程度が極めて深刻である場合には、破産手続きを検討する必要があります。
破産手続きとは、債務者の財産を換価して債権者に配当し、残った債務を免責する制度です。
破産手続きの主な流れは以下の通りです。
-
- 破産申立て(債務者または債権者による)
- 破産手続開始決定(裁判所による)
- 破産管財人による財産管理・債権調査
- 債権者集会の開催
- 配当の実施
破産手続の終結 破産者は、これらの手続きを通じて財産を処分し、負債を整理します。
破産手続きには以下のようなメリットがあります。
-
- 債務の清算により、経営者の責任から解放される。
- 破産管財人による公正な財産管理・債権調査が行われる。
- 免責により、将来の返済義務から解放される。
- 破産者の生活再建のため、自由財産や生活費の支給がある。
他方、破産手続きには、次のようなデメリットも存在します。
-
- 原則として全財産を失い、ゼロからの再出発を余儀なくされる。
- 経営者の個人保証は免責の対象外となることが多い。
- 破産者名簿に登録され、信用情報に傷がつく。再起が難しくなる。
- 一定の職業に就くことが制限されるなど、破産者の権利に制約が生じる。
破産は最終手段として、慎重に検討する必要があるでしょう。
事前に弁護士など専門家に相談し、考え得る選択肢を洗い出すことが賢明です。
債務超過解消のための再生手続き
廃業を検討する一方で、債務超過から脱却し、事業を再生させる道を模索することも大切です。
その有力な選択肢が、民事再生手続きです。
民事再生手続きとは、債務者が再生計画を作成し、裁判所の認可を得て、債務を弁済しながら事業を再建していく制度です。
会社更生法に基づく会社更生手続きと比べ、手続きが簡素で、経営者の管理権限も維持できるため、中小企業の再建に適しているとされます。
民事再生手続きの主な流れは以下の通りです。
-
- 民事再生の申立て
- 再生手続開始決定
- 債権者集会の開催・調査委員の選任
- 再生計画案の提出
- 再生計画案の可決・認可
再生計画の遂行 手続き中は、債権者による個別の権利行使が禁止されるため(再生債権の支払い停止)、落ち着いて再建策を練ることができます。 公正中立な立場の監督委員の関与により、透明性の高い手続きが期待できるのもポイントです。
民事再生手続きの主なメリットは以下の通りです。
-
- 事業を継続しながら、債務の整理が可能。
- 債権者の同意があれば、大幅な債務カットも可能。
- 経営者が主導権を持ち、柔軟な再建策を打ち出せる。
- 会社更生に比べ、早期に手続きを完了できる。
一方、債権者への弁済原資を確保する必要があるため、過大な債務がある場合や、事業に将来性が乏しい場合には、再生は難しいと言わざるを得ません。
事業の実態を見極め、第三者委員会などの意見も聞きながら、再建の可能性を冷静に判断する必要があります。
債務超過でも事業承継は可能なのか?倒産との違い・対処法を解説
事業再生を目指す場合の心構え

民事再生による債務超過脱却を目指す際は、以下の点に注意しましょう。
-
- 再生計画は現実的で達成可能なものにする
- 債権者との対話を重視し、理解と協力を得る努力を怠らない
- リスケジュールだけでなく、事業モデルの見直しも並行して進める
- 従業員との対話を大切にし、再生へのモチベーションを維持する
- 中小企業再生支援協議会など、外部の専門機関の知恵を借りる
民事再生は「人生最後のチャンス」とも呼ばれます。
事業再生への強い意欲と周到な準備、そして何よりステークホルダーの協力が欠かせません。
安易な計画や場当たり的な対応は厳に慎み、長期的視点に立った再建を目指すべきでしょう。
中小企業支援の専門家から学びつつ、再生の青写真を描き上げていくことが重要です。
支援機関を活用する
債務超過や廃業の問題は、経営者一人の力で解決することは容易ではありません。
幸いなことに、債務整理や再生、キャリア支援など、頼れる支援機関が各所に存在します。
代表的なものをいくつか挙げておきましょう。
中小企業活性化協議会
中小企業活性化協議会は、経営難に直面した中小企業の危機整理や事業再生を支援する機関です。 経験豊富な専門家が、金融機関「借金を減らしたい」「事業を立て直したい」という経営者の皆様は、中小企業再生支援協議会に相談してみてください。
事業引継ぎ支援センター(M&A・事業承継)
M&Aや事業承継の支援を行う機関です。M&Aの対象企業の探索や条件交渉、契約書作成などを全面的にサポートしてくれます。 「会社を継続させたい」「従業員の雇用を守りたい」という思いを持つ経営者の方は、事業引継支援センターを活用してみてもいいかもしれません。
債務超過の企業でもM&Aされる理由とは?スキームや注意点についても解説
商工会議所・商工会(経営相談・専門家派遣)
地域の中小企業を支える身近な存在です。経営相談や専門家派遣など、様々な支援メニューを用意しています。「誰かに相談したい」「専門家のアドバイスが欲しい」という経営者の皆様の支援をしてくれます。
地域金融機関(諮問・融資)
アドバイスや融資など、中小企業の資金ニーズに応じてくれる存在です。事業承継段階、資金計画の策定や資金調達が必要に「資金繰りが心配」「事業承継の資金が必要」というケースもあります。
ハローワーク(就職再支援)
従業員の再就職をサポートしてくれるのがハローワークです。職業紹介、職業訓練など、様々な再就職支援メニューがあります。「従業員の雇用を守りたい」「辞めた従業員を支援したい」という場合に役に立ちます。
よろず支援拠点(各種経営相談)
よろず支援拠点は、中小企業の経営相談に幅広く対応する支援機関です。「よろず」という名前の通り、販路開拓や資金繰り、事業承継など、経営のあらゆる悩みに対応した専門家が、経営者の皆様の相談に無料で乗ってくれるのが心強いポイントです。
廃業を選択する際の準備事項とは
債務超過からの再生が叶わず、廃業を選択する場合、次のような準備が必要です。
-
- 事業の整理(在庫処分、設備売却、契約解除など)
- 従業員への説明と雇用関係の整理
- 取引先・顧客への連絡と債権債務の清算
- 関係機関への届出(税務署、年金事務所など)
- 廃業後の生活設計(再就職、起業など)
これらの準備を計画的に進めることで、トラブルを未然に防ぎ、次のステップにスムーズに移行できます。
特に、従業員や取引先への説明は誠意を持って行い、理解を得るために最善を尽くしましょう。清算人など専門家の力も借りつつ、万全の体制で臨むことが大切です。
さらに、廃業後の資金繰りにも注意が必要です。債務整理や事業売却による資金を、当面の生活費に充てることを検討しましょう。
個人保証の清算も早期に進め、債務に縛られない生活を目指すことが賢明です。再就職や起業に向けた資金計画も、早めに立てておくと安心です。
まとめ
債務超過に陥った場合、事業の継続か廃業かの選択を迫られます。廃業を選択する際は、解散手続きや清算手続きを適切に進める必要があります。
一方、事業再生を目指すなら、民事再生手続きなどの選択肢も検討すべきでしょう。いずれにせよ、経営者一人で問題を抱え込まず、中小企業再生支援協議会や事業引継ぎ支援センターなどの専門機関に相談することが重要です。
債務超過からの脱却には、周到な準備と関係者の協力が欠かせません。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。