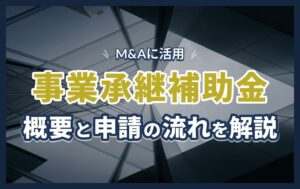【事業を閉じる前に】廃業準備のステップバイステップガイド
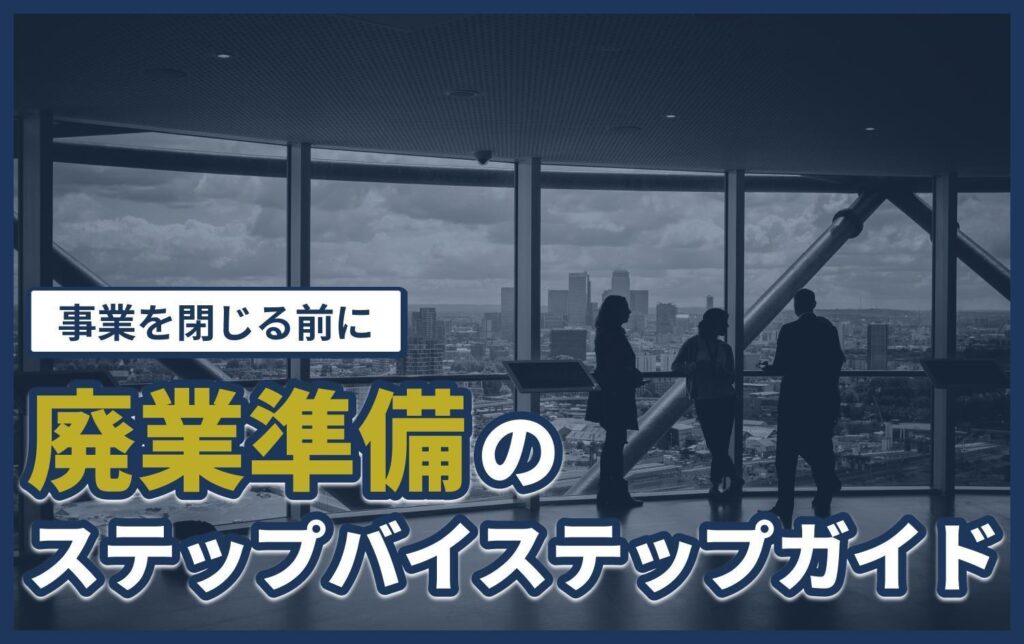
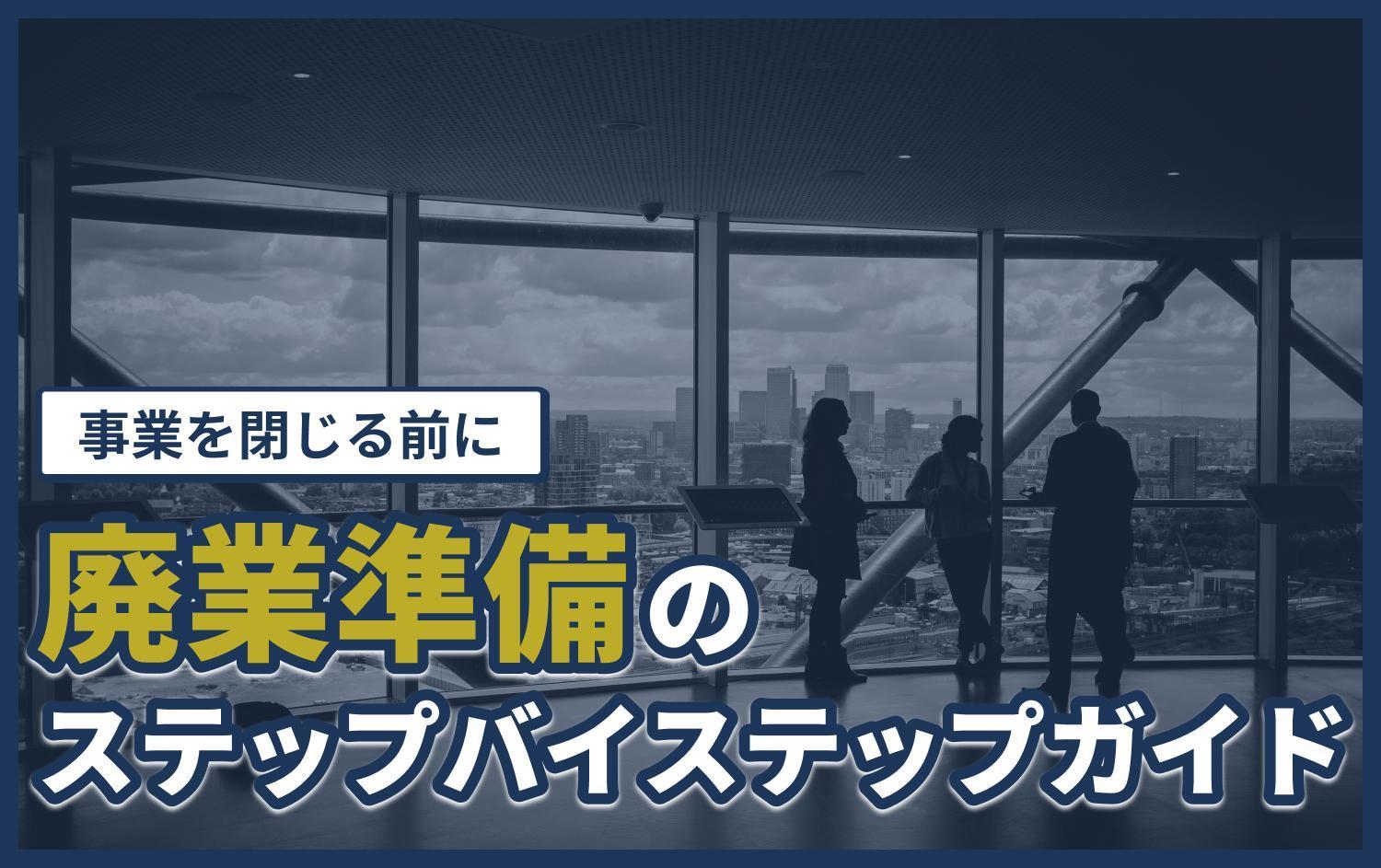
「会社を畳もうかな…」後継者不在に悩む経営者の方。長年続けてきた事業をたたむのは、誰もが簡単には踏み切れない決断ですよね。社員や取引先、そして自分自身の人生を思うと、尻込みしてしまうのも無理はありません。でも、いつまでもその場に留まるのは、会社にとっても、あなたにとっても良くないのかもしれません。
「でも、廃業って何から始めればいいの?」そんな風に不安を感じるあなたに、事業を閉じるまでの道のりを、ステップごとに丁寧に解説していきます。準備を円滑に進めるコツや、よくある落とし穴についても触れていきますので、ぜひ参考にしてください。
目次
廃業を決断する際の心構え
廃業は「失敗」ではありません。事業環境の変化や経営者の年齢、後継者の有無など、さまざまな要因が絡み合って下す決断です。「もう少し頑張れたのでは」と自分を責めるよりも、これまでの努力を称え、新しい人生の始まりと捉えることが大切です。
心構えとして押さえておきたいのは、以下の3点です。
-
- 廃業は単なる終わりではなく、再スタートへの第一歩
- 従業員や取引先など、関係者への配慮を忘れない
- 専門家の力を借りながら、一歩ずつ着実に進める
廃業を意思決定するタイミングで考えるべきこと
(1) 廃業理由の明確化と関係者との合意形成
「なぜ廃業するのか」その理由を明確にし、関係者の理解を得ることが重要です。
経営不振なのか、後継者不在が理由なのか。事業の将来性をどう見るのか。答えは人それぞれですが、自分なりの言葉で説明できるようにしておきましょう。
特に株主や役員、従業員には丁寧な説明が必要です。廃業の理由や今後の見通しを率直に伝え、協力を求める姿勢が大切。一人で抱え込まず、みんなで知恵を出し合える関係性を築いていきましょう。
(2) 事業継続・M&Aの可能性も検討する
「本当に廃業するしかないのだろうか?」と、一度立ち止まって考えてみる価値はあります。
株式や事業を譲渡するM&A(合併・買収)は、廃業の代替策として注目されています。雇用を守りつつ、経営資源を引き継ぐことができるからです。
自社の強みを棚卸しし、M&Aの可能性を探ってみましょう。業界の動向や、自社の技術・ノウハウの優位性など、買い手の関心を引く材料がないか検討を。専門家の知見を借りるのも一案です。もし条件が合えば、廃業よりも良い選択肢になるかもしれません。
廃業スケジュールの策定

(1) 廃業までのタイムラインと優先タスクの洗い出し
廃業の決定から実行まで、半年から1年程度の期間を見込むのが一般的です。この間に行うべきタスクを洗い出し、タイムラインを引いていきましょう。
株主総会の開催、債権債務の整理、資産の処分、従業員の再就職支援…。やることは山積みですが、優先順位をつけて着実に進めていくことが肝心です。
まずは大まかなスケジュールを立て、関係者と共有を。そのうえで、各タスクの担当者とデッドラインを決めていきます。
リソースが足りない部分は外部に委託することも視野に入れて見ましょう。無理のない計画を立てることが大切です。
(2) 必要なコストの算出と手当て
廃業には少なからぬ費用がかかります。登記費用や弁護士報酬、人員整理の費用など、あらかじめ想定される支出は洗い出しておきたいもの。
「思ったより資金が必要そう…」そんな時は、金融機関や公的支援制度の活用も検討を。経営者保証に関するガイドラインを利用した保証債務の整理など、負担を軽減する方策もあります。
利害関係者への説明と調整を行う
(1) 従業員への説明と雇用問題への対応
従業員にとって廃業のインパクトは小さくありません。生活の基盤を揺るがす話だけに、真摯な対応が求められます。
説明会の開催や個別面談など、十分なコミュニケーションを取ることが大切。廃業の理由や今後の見通しを丁寧に説明し、不安を受け止める姿勢を。転職先の斡旋など、できる限りの支援も惜しまないようにしましょう。
早期の退職勧奨制度など、雇用調整の手法も併せて検討を。労働関連法規を踏まえつつ、専門家のアドバイスを仰ぐことをおすすめします。
(2) 取引先・顧客への通知と債権債務の処理
取引先や顧客にも、早めに廃業の旨を伝えることが重要です。代わりの取引先の紹介など、事業の継続に協力する姿勢を示すことで、円滑な移行を促せるはずです。
債権や債務の清算も並行して進めていきましょう。未収金の回収、買掛金の支払いなど、期日までにすべてを処理する必要があります。長期の契約については、解除や譲渡の交渉も必要になります。トラブル防止のためにも、書面でのやりとりを心がけましょう。
(3) 株主・投資家への報告と理解促進
株主・投資家には、廃業の判断プロセスを丁寧に説明することが求められます。臨時株主総会の開催や IR 活動など、適宜コミュニケーションの場を設けるのがよいでしょう。
「なぜ廃業なのか」「今後の資産回収の見通しは」など、ステークホルダーの関心事に誠実に答えていく姿勢が何より大切。透明性の高い情報開示を通じて、理解と協力を得ていきたいものです。
廃業に必要な書類を準備しましょう
(1) 法人の解散手続きに必要な書類の整備
法人を解散するには、一定の手続きと書類が必要です。具体的には以下のようなものがあります。
-
- 定款
- 株主総会議事録(解散決議)
- 債権者への公告に関する書類
- 清算人の登記に必要な書類
これらを滞りなく準備するには、日頃からの書類管理が欠かせません。資料を早めに収集し、不備がないかチェックを。専門家に相談しながら進めるのが確実です。
(2) 税務関連書類の収集と確定申告の準備
廃業に際しては、各種の税務手続きが発生します。申告や届出に必要な書類を整えることが重要です。
例えば、以下のようなものがあります。
-
- 法人税の清算確定申告書
- 消費税の納税申告書(課税事業者の場合)
- 源泉所得税の納期特例の中止届出書
税務署への提出期限を確認し、早めの準備を心がけましょう。廃業に伴う税務処理は複雑なだけに、税理士等の専門家のサポートは欠かせません。書類の作成から申告まで、一括して依頼するのも選択肢の一つです。
資産の処分と債務の弁済の進め方
(1) 事業用資産の売却・譲渡の進め方
設備や在庫など、事業用資産の処分は計画的に。売却先や譲渡先を探すのはもちろん、適正な価格設定も重要なポイントです。
不動産や大型設備など高額な資産は、仲介業者を通じての売却が一般的。希望価格と相場とのバランスを見極め、タイミングを逃さないことが肝心です。
一方、在庫や什器備品は、業者への一括売却や従業員への譲渡も選択肢に。処分コストを抑えつつ、早期の現金化を図ることができます。資産の特性に応じた方法を選びましょう。
(2) 借入金の返済と債務整理の注意点
事業用ローンなど、残る借入金の返済も忘れずに。金融機関との交渉を通じて、返済スケジュールを再設定するのも一案です。
経営者保証による個人保証の取り扱いにも注意が必要。「経営者保証に関するガイドライン」を活用し、保証債務の整理を図ることも可能性として視野に入れましょう。
債務超過に陥っている場合は、弁護士に相談の上、債務整理を検討するのがよいでしょう。私的整理や法的整理など、状況に応じた方法を選択することが大切です。
退職金・残余財産分配について検討する

(1) 適切な役員退職金の設定と支給手続き
役員への退職金は、功績や在任期間に応じて、適切に設定することが求められます。高額すぎると経費として認められない可能性があるだけに、税理士等の助言を仰ぐことをおすすめします。
支給手続きでは、以下のような流れが一般的です。
-
- 株主総会・取締役会での支給決議
- 退職所得の受給に関する申告書の提出
- 源泉徴収と納付の手続き
- 関連書類の整備と保管
慎重かつ丁寧な事務処理を心がけ、トラブルを未然に防ぐことが重要。社会保険労務士など、専門家のサポートを受けながら進めるのもよいでしょう。
(2) 残余財産の分配方法の決定
全ての資産を処分し、債務を弁済した後、残った財産(残余財産)の分配方法を決めます。通常は、株主への分配となるケースが多いものです。
分配の基準は、保有株数に応じて按分するのが一般的。ただし、定款で別段の定めがある場合は、それに従う必要があります。株主間の合意形成を図りつつ、適切な分配を心がけましょう。
分配額が多額になる場合、株主側の税務対策にも配慮が必要です。みなし配当課税を避けるため、一定の留保金を残すことも一案。税理士に相談しつつ、節税効果も意識した分配を検討しましょう。
関係機関への届出
(1) 法務局、税務署、年金事務所等への解散・廃業届の提出
法人の解散・清算結了時には、各種の官公庁への届出が必要です。主なものは以下の通り。
-
- 法務局:解散登記、清算結了登記
- 税務署:法人税の清算確定申告、消費税の納税申告など
- 年金事務所:社会保険の資格喪失届
提出期限を確認し、もれのないよう処理を進めていくことが肝心。司法書士など、手続きに明るい専門家に依頼するのも有効な方法です。
(2) ライセンス・許認可の廃止手続き
業種によっては、事業に必要なライセンスや許認可の廃止手続きも必要です。例えば、以下のようなものがあります。
-
- 飲食店営業許可
- 古物商許可
- 建設業許可
所管官庁に廃止の届出を行い、必要書類を提出します。期限に間に合うよう、早めの手配を心がけたいですね。管轄の自治体などに確認し、もれのない処理を心がけましょう。
清算手続きの完了
(1) 清算人の選任と事務引継ぎ
清算人は、解散後の会社(清算会社)の代表者として、清算事務を行う役割を担います。通常は代表取締役が就任しますが、第三者に委ねるケースもあります。
いずれにせよ、清算人の選任は慎重に。事務引継ぎを丁寧に行い、清算業務に支障を来さないよう万全を期すことが大切です。
清算人の主な職務は以下の通りです。
-
- 現務の結了(債権回収、債務弁済など)
- 残余財産の処分
- 法的手続きの遂行
会社の実情に精通した人材を選ぶことで、円滑な清算事務が期待できるでしょう。
(2) 清算事務の遂行と清算結了登記
清算人は就任後、適宜、債権者集会を開催しながら、清算事務を進めていきます。債権の取立てや、債務の弁済を適切に行うことが何より重要。資産の処分や税務申告なども、期限内に漏れなく行う必要があります。
すべての清算事務が完了したら、最終の株主総会で決算報告を行います。株主の承認を得たら、清算結了登記を申請。これをもって、会社はその役目を終えることとなります。
登記申請の際は、以下のような書類が必要です。
-
- 清算人の印鑑証明書
- 清算結了登記申請書
- 株主総会議事録(清算報告の承認)
不備のない書類を整え、清算の区切りをしっかりとつけましょう。
廃業後の再スタートに向けて
経営者自身の心身のケアとモチベーション維持
廃業はゴールではなく、新たなスタートです。経営者自身が心身ともに健康であることが、何より大切。廃業の過程で溜まったストレスを発散し、自分をリフレッシュさせる時間を作りましょう。
家族との団欒や趣味の時間など、オフの過ごし方を大切に。前を向いて歩み出す活力を、日々の生活から得ていきたいものです。
新しいビジネスにチャレンジする、社会貢献活動に取り組むなど、次のステージへの想いを膨らませるのもよいでしょう。夢や目標を抱くことで、自然とモチベーションも上がっていくはずです。
新たな事業構想の立案と準備
「次は何をしよう」廃業後の選択肢は、経営者それぞれ。新分野での起業や、別の会社での勤務など、多様な可能性が広がります。
大切なのは、自分の強みと、社会のニーズを見極めること。長年の経験を通じて培ったスキルを、どんな形で発揮できるのか。ビジネスの種は、案外身近なところに転がっているものです。
事業プランを固めたら、仲間集めや資金調達など、具体的な準備を進めましょう。ゼロからのスタートに不安を感じたら、公的支援制度の利用も一案。再チャレンジを後押しする補助金などもあります。
情報収集を怠らず、スモールスタートを心がける。その積み重ねが、新たな一歩を踏み出す原動力になるはずです。
専門家の活用と相談先

(1) 税理士、弁護士、司法書士等の専門家の選び方
廃業の手続きには、多岐にわたる専門知識が求められます。税務、法務、登記など、それぞれの分野に明るい専門家との連携が欠かせません。
専門家選びのポイントは以下の通り。
-
- 廃業支援の実績が豊富か
- 中小企業の実情に詳しいか
- 経営者目線でアドバイスできるか
- 報酬体系が明確で納得できるか
信頼できるパートナーを見つけることで、廃業手続きの負担を大幅に軽減できます。セカンドオピニオンを聞くのもよいですね。
(2) 各種廃業支援機関の利用方法
商工会議所や金融機関など、廃業をサポートする団体は少なくありません。セミナーの開催や個別相談など、状況に応じた支援を受けられる可能性があります。
例えば、以下のような支援機関が挙げられます。
-
- 中小企業基盤整備機構の再チャレンジ支援事業
- 事業引継ぎ支援センター
- 各都道府県の中小企業支援センター
まずは一度、問い合わせてみるのがおすすめ。専門的な視点からのアドバイスが得られるだけでなく、同じ悩みを抱える経営者との交流の機会にもなります。ぜひ、有効活用していきましょう。
円滑な廃業実現のために押さえるべきポイント
廃業は、経営者にとって人生の岐路ともいえる大きな決断です。その道のりは決して平坦ではありませんが、適切な準備と支援を得ながら、一歩ずつ前に進んでいくことが大切です。
円滑な廃業の実現に向けては、以下の点に特に注意しましょう。
-
- 廃業の意思決定に際し、M&Aなど代替策の検討も忘れずに
- 従業員や取引先への説明と調整を丁寧に行う
- 会社の資産や負債の棚卸しを行い、財務状況を把握する
- 税務、登記、許認可など、関連諸手続きは計画的に
- 清算人の人選と事務引継ぎを慎重に行う
- 廃業後の人生設計を見据え、再スタートに向けて準備する
そして何より、専門家の知見を最大限に活用すること。税理士や弁護士など、頼れる相談相手を見つけておくことで、リスクを最小限に抑えつつ、スムーズな廃業を実現できるはずです。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。