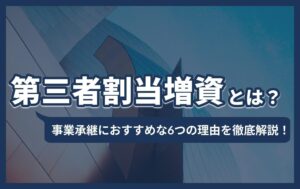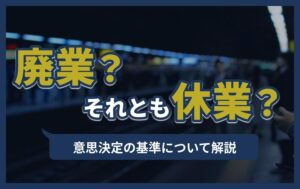廃業時の役員退職金の基礎知識:計算方法と税務処理について解説
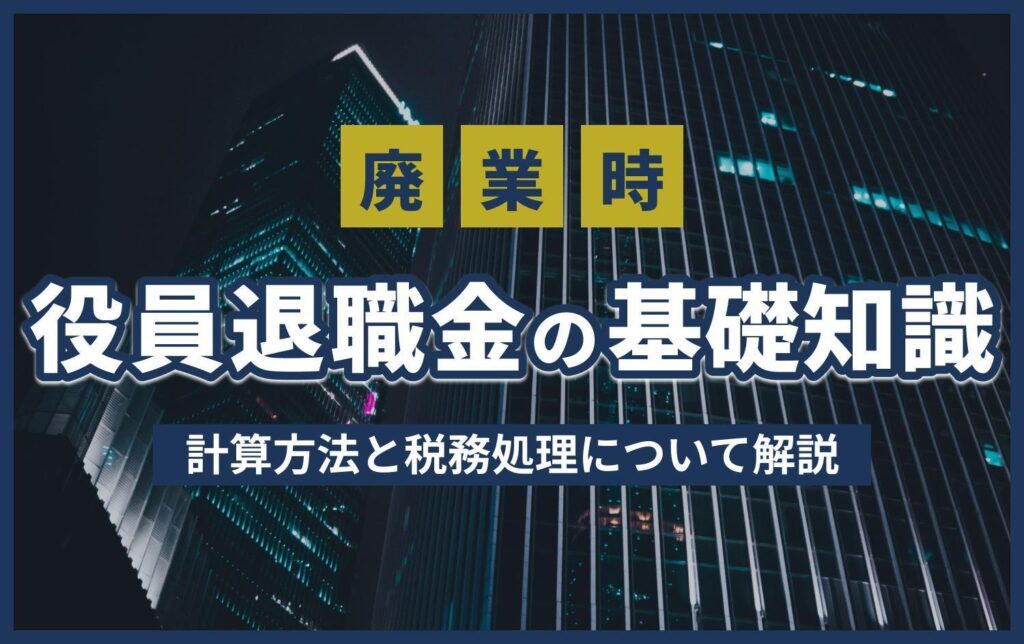
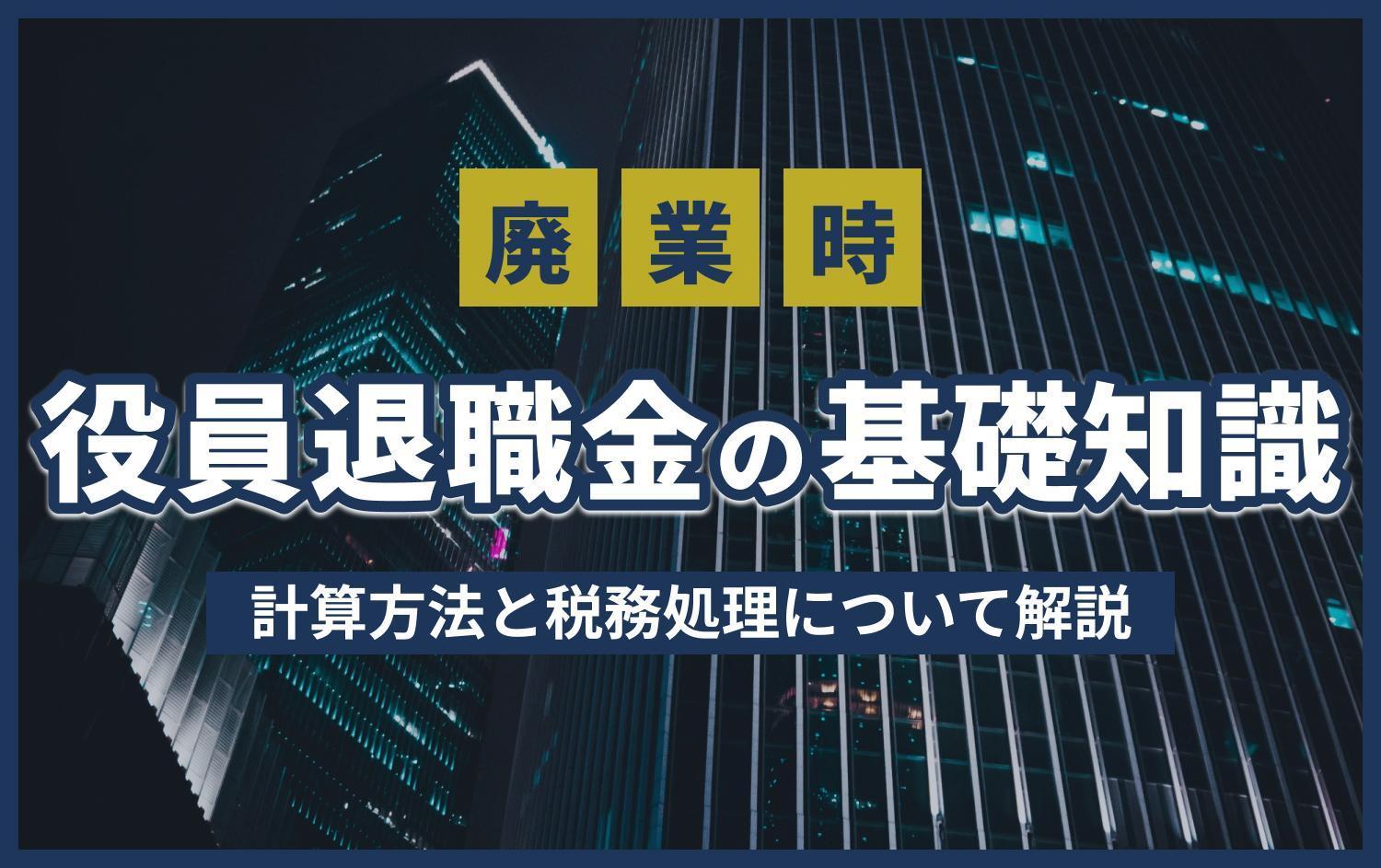
会社の廃業を検討中の経営者の皆様、役員退職金の取り扱いについてお悩みではありませんか?
長年会社経営に尽力してきた役員の功績に報いるため、退職金の支給を考えるのは自然なことです。
しかし、廃業時の退職金は、残余財産の分配とは税務上の扱いが異なります。
適切な金額設定や税務処理を行わないと、思わぬ税負担を招く恐れもあるのです。
本記事では、廃業時の役員退職金に関する基礎知識について解説します。
目次
廃業時に役員退職金を支給するメリット
(1) 残余財産の分配との税務上の違い
廃業時に会社に残った財産(残余財産)を役員たる株主に分配する場合、一定額以上の分配には「みなし配当」として所得税と住民税が課されます。税率は、個人の所得税の最高税率(45%)に住民税(10%)を加えた55%にも上ることがあります。
一方、役員退職金は、みなし配当ではなく退職所得として扱われます。退職所得には、勤続年数に応じた退職所得控除が適用され、控除後の金額の2分の1のみに所得税と住民税が課されます。このように、役員退職金は、功績に対する退職所得として税制上優遇される点が大きな違いなのです。
(2) 役員退職金支給が有利なケース
以下のようなケースでは、残余財産の分配よりも、役員退職金の支給が税務上有利となります。
-
- 株主の出資額以上の金額を分配する場合:みなし配当課税を避けつつ、役員の功績に報いることができます。
- 株主以外の役員(共同経営者など)に金銭を渡したい場合:分配では非株主への支給ができませんが、退職金なら可能です。
- 役員貸付金を税制面で有利に処理したい場合:退職金と相殺することで、税負担を軽減できる可能性があります。
- 株主の相続税対策で財産を分散したい場合:退職金は、相続財産に含まれない「みなし相続財産」として扱われます。
このように、会社や株主の状況に応じて、役員退職金の支給を検討する価値は十分にあるのです。ただし、金額設定には注意が必要です。法外な金額は、税務上の不利益につながりかねません。
役員退職金の支給手順と必要書類

役員退職金を支給する際は、以下の手順を踏む必要があります。
(1) 株主総会・取締役会での決議
退職金の支給は、株主総会や取締役会での決議が必要です。支給額や算定方法を明示したうえで、きちんと決議しましょう。議事録の作成と保管も忘れずに。定款で定められた方法に従って、適切に決議を行うことが肝心です。
(2) 退職所得申告書の提出と保管
退職金を受け取る役員は「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出します。この申告書には、退職金の受給額や勤続年数、退職の理由などを記載します。申告書がないと、会社は退職金の20.42%もの高い税率で源泉徴収しなければならないため、必ず提出を受け、大切に保管しておきましょう。
(3) 源泉徴収票・特別徴収票の作成と提出
会社は、支給した退職金について、所得税と住民税を源泉徴収のうえ、税務署と市区町村に提出します。提出書類は、所得税の「退職所得の源泉徴収票」と、住民税の「退職所得の特別徴収票」の2種類。いずれも、支給日の翌月10日までに提出しなければなりません。
こうした一連の手続きを滞りなく進めるには、必要書類を事前に揃え、スケジュール管理を徹底することが大切です。書類の不備や提出漏れは、税務上のトラブルを招くだけでなく、役員との信頼関係を損なう恐れもあります。慎重かつ丁寧な対応を心がけましょう。
役員退職金の金額設定のポイント
役員退職金の金額設定は慎重に行う必要があります。
(1) 功績倍率の上限と過大支給のリスク
役員退職金は、功績倍率方式で計算するのが一般的です。最終報酬月額に、勤続年数や役位、会社への貢献度などに応じた功績倍率を乗じて算出します。ただし、税法上、功績倍率法は明確に定められておらず、税務上否認されないといえる倍率は特にありません。
一般的に、中小企業の役員退職金の功績倍率が3倍以上になる場合、その退職金額になった具体的な理由が必要とされています。しかし、3倍未満でも否認されているケースもあり、倍率の高低だけでなく、退職金額の妥当性が重要となります。
高額な役員退職金を支給する際は、その金額の妥当性を十分に説明できるようにしておくことが大切です。過大な退職金は、役員賞与とみなされ、損金に算入できなくなるリスクがあることに注意が必要です。退職金額の決定にあたっては、税務リスクについても考慮しておくことが賢明といえるでしょう。
(2) 専門家に相談することの重要性
金額設定の際は、税理士など専門家に相談し、適正な金額を算出することが賢明です。過大支給は、税務上のリスクを招くだけでなく、廃業手続きの中で修正が難しくなるためです。
また、役員退職金規程を作成し、支給額の算定方法を明文化しておくことも有効です。一方的な金額設定ではなく、客観的な基準に基づいて支給していることを示すことができます。規程の作成には、社会保険労務士などの専門家のアドバイスを仰ぐとよいでしょう。
役員退職金から差し引く所得税・住民税の計算方法
役員退職金から差し引く税金の計算方法を見ていきましょう。
(1) 一般退職所得と特定退職所得の違い
退職所得は、勤続年数に応じて「一般退職所得」と「特定退職所得」に分けられます。「一般退職所得」は、勤続5年超の役員等の退職金に適用され、課税対象となる退職所得金額の2分の1が非課税となります。
一方、「特定退職所得」は、勤続5年以下の役員等の退職金に適用され、退職所得控除後の金額全てに課税されます。短期間で多額の退職金を受け取るケースを想定した制度と言えます。
【一般退職所得の計算式】
課税退職所得金額 =(退職手当額-退職所得控除額)× 1/2
【特定退職所得の計算式】
課税退職所得金額 = 退職金 - 退職所得控除額
(2) 退職所得控除額の計算
退職所得控除額は、勤続年数に応じて異なります。
・勤続年数20年以下:40万円×勤続年数(1年未満の端数は1年に切り上げ)ただし、最低額は80万円
・勤続年数20年超:800万円+70万円×(勤続年数-20年)
例えば、勤続15年の役員が3,000万円の退職金を受け取る場合、退職所得控除額は600万円(40万円×15年)となります。
(3) 所得税と住民税の税額計算
課税退職所得金額に税率を乗じて、所得税と住民税を計算します。所得税は、課税退職所得金額に対して5%~45%の累進税率が適用されます。一方、住民税は、所得税とは別に10%の税率が一律にかかります。
このうち、所得税は国に、住民税は役員が住所を有する都道府県と市区町村に納めます。会社が源泉徴収し納付する義務を負うので、期限内の手続きを忘れずに行いましょう。
役員退職金の支給タイミングと注意点
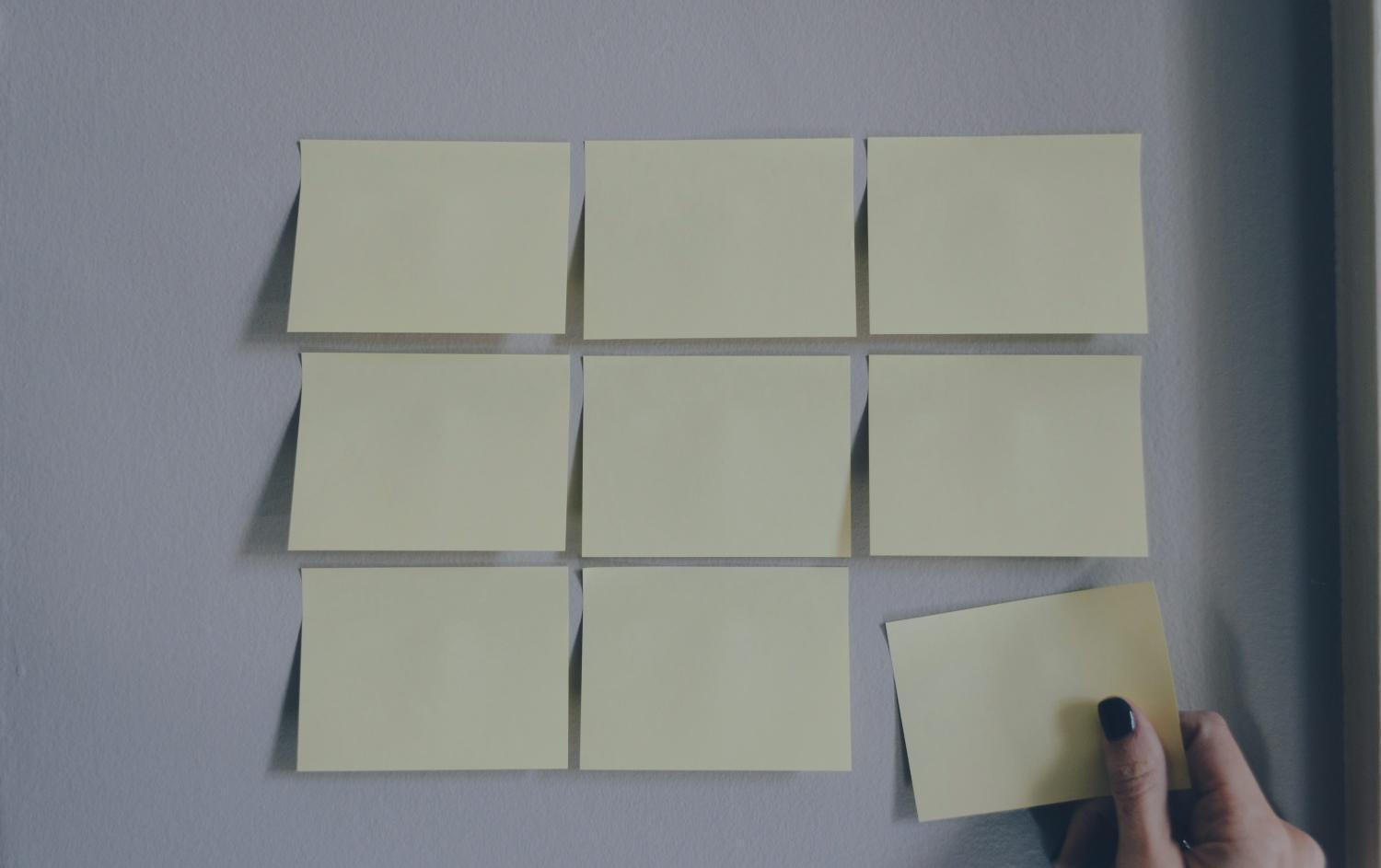
(1) 適切な支給時期の選択
役員退職金の支給時期は、会社の状況に応じて適切に選択します。廃業直前に支給するケースが多いですが、あえて廃業前の早い段階で支給することで節税効果を高められる場合もあります。
例えば、退職金の分割支給です。複数年度にわたって支給することで、1年あたりの所得を抑え、所得税の累進課税による負担を軽減できます。会社の資金繰りが厳しい場合にも有効な方法と言えるでしょう。
ただし、分割支給を行う場合は、支給時期と金額を明確に定めた契約書を交わすなど、トラブル防止に努めることが大切です。
(2) 源泉徴収と納付期限の管理
退職金の支給後は、源泉徴収と納付を期限内に行うことが重要です。源泉徴収した所得税は支給日の翌月10日までに、役員の住所地の所轄税務署に納付します。
住民税についても、同様に支給日の翌月10日までに、役員の住所地の都道府県と市区町村に特別徴収税額を納入します。納付を怠ると、不納付加算税(10%)や延滞税(年14.6%)といったペナルティを課される恐れがあるので注意しましょう。
こうした税務手続きは、煩雑で時間もかかります。余裕を持ったスケジュール管理を心がけ、必要に応じて専門家のサポートを受けることをおすすめします。
廃業時の退職金支給による節税効果と注意点
役員退職金の支給は、廃業時の節税対策としても有効です。会計上は損金として処理されるため、会社の所得を引き下げることで法人税を減らせます。加えて、役員個人の所得税・住民税の負担も、退職所得控除や2分の1課税の適用で軽減できるのです。
ただし、過大な退職金支給は、税務当局に異常値として認定されるリスクがあります。「役員退職給与」は、法人税法上の損金算入要件が厳しく、不相当に高額な部分は、役員賞与として損金不算入となる可能性が高いのです。
支給額の妥当性を客観的に説明できるよう、功績倍率方式など、合理的な算定根拠を明確にしておくことが重要です。前述の退職金規程を整備し、役員退職金の支給基準を明文化するのも一案でしょう。
廃業前にM&Aを検討しませんか?
ここまで、廃業時の役員退職金について詳しく解説してきました。しかし、そもそも廃業は本当に最善の選択なのでしょうか?事業の将来性や市場環境、従業員の雇用などを考えると、もう一度立ち止まって考える価値はあります。
特に注目したいのが、M&A(合併・買収)による事業承継です。会社を存続させつつ、経営資源を引き継ぐことができるため、廃業よりも魅力的な選択肢と言えるでしょう。
M&Aのメリットは、大きく以下の3つが挙げられます。
-
- 事業と雇用の継続:会社の理念や事業、従業員の雇用を守ることができます。
- 役員の退職金確保:M&Aの対価として、役員退職金の原資を確保できる可能性があります。
- 相続税対策:M&Aで株式を譲渡することで、相続財産を分散し、相続税負担を軽減できます。
一方で、M&Aには独自の課題もあります。買い手探しや交渉、デューデリジェンス(調査)など、一連のプロセスには時間と手間がかかります。また、希望する条件で売却できるとは限らず、譲渡価格や契約内容など、条件面でも妥協が必要になることがあります。
とはいえ、事業の存続と役員の退職金確保を同時に実現できるM&Aのメリットは大きいと言えます。自社の事業に魅力があるなら、廃業を決断する前に、M&Aの可能性を探ってみる価値は十分にあるでしょう。
M&Aを成功に導くには、専門家の助言が欠かせません。M&A仲介会社や税理士、弁護士などの専門家に相談し、適切なサポートを受けることをおすすめします。廃業かM&Aか、会社の未来を見据えた決断ができるよう、ぜひ検討してみてください。
専門家に相談するべきケースと選び方
(1) 税理士や社会保険労務士の活用
役員退職金は、会社法、税法、労働法など幅広い知識が求められる分野です。自信がない場合は、税理士や社会保険労務士などの専門家に相談するのが賢明です。
特に、以下のようなケースでは、専門家の助言が欠かせません。
-
- 役員退職金の金額設定や支給方法に迷っている場合
- 退職金規程の作成や改定を検討している場合
- 役員退職金の税務処理や手続きに不安がある場合
- M&Aによる事業承継を検討している場合
専門家の的確なアドバイスにより、税務リスクを回避しつつ、スムーズな退職金支給とM&Aの実現を図ることができるでしょう。
(2) アドバイザー選定の際の着眼点
専門家を選ぶ際は、中小企業の廃業支援やM&Aの実績が豊富で、経営者の立場に立って親身にアドバイスしてくれる方がおすすめです。特に、以下の点に注目して選ぶとよいでしょう。
-
- 中小企業の役員退職金に関する知見の豊富さ
- 廃業支援やM&Aの成功実績の多さ
- 経営者目線でのアドバイスができるコミュニケーション力
- 報酬体系の明確さとコストパフォーマンスの高さ
初回相談が無料の事務所も多いので、まずは気軽に問い合わせてみることから始めてみてはいかがでしょうか。相性の良い専門家に出会えれば、廃業やM&Aの難しい意思決定も、スムーズに進められるはずです。
廃業時の役員退職金支給の際に押さえるべきポイント | まとめ
廃業時の役員退職金の支給は、残余財産の分配よりも税制面で有利なケースが多いです。会社と役員双方の税負担を軽減しつつ、役員の功績に報いることができるからです。
ただし、そのメリットを享受するには、適切な金額設定と税務処理が不可欠。役員退職金の計算方法や支給手順、注意点を正しく理解し、必要に応じて専門家のサポートを得ながら進めることが何より大切です。
加えて、廃業前にM&Aの可能性を探ることも忘れてはいけません。事業と雇用を守りつつ、役員退職金の原資も確保できるM&Aは、廃業の代替策として大いに検討する価値があります。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。