廃業?それとも休業?意思決定の基準について解説
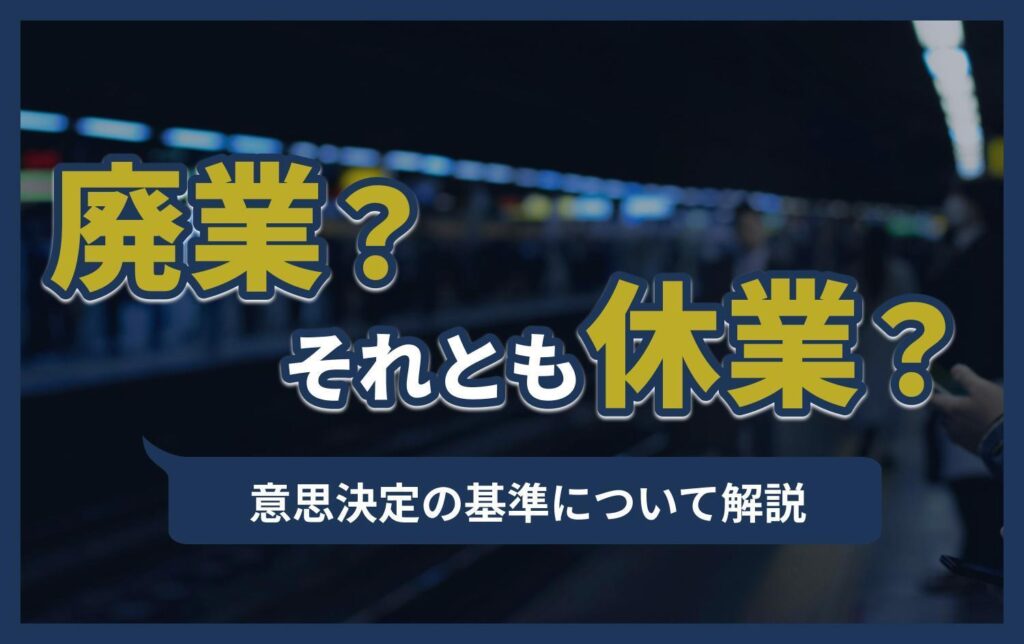
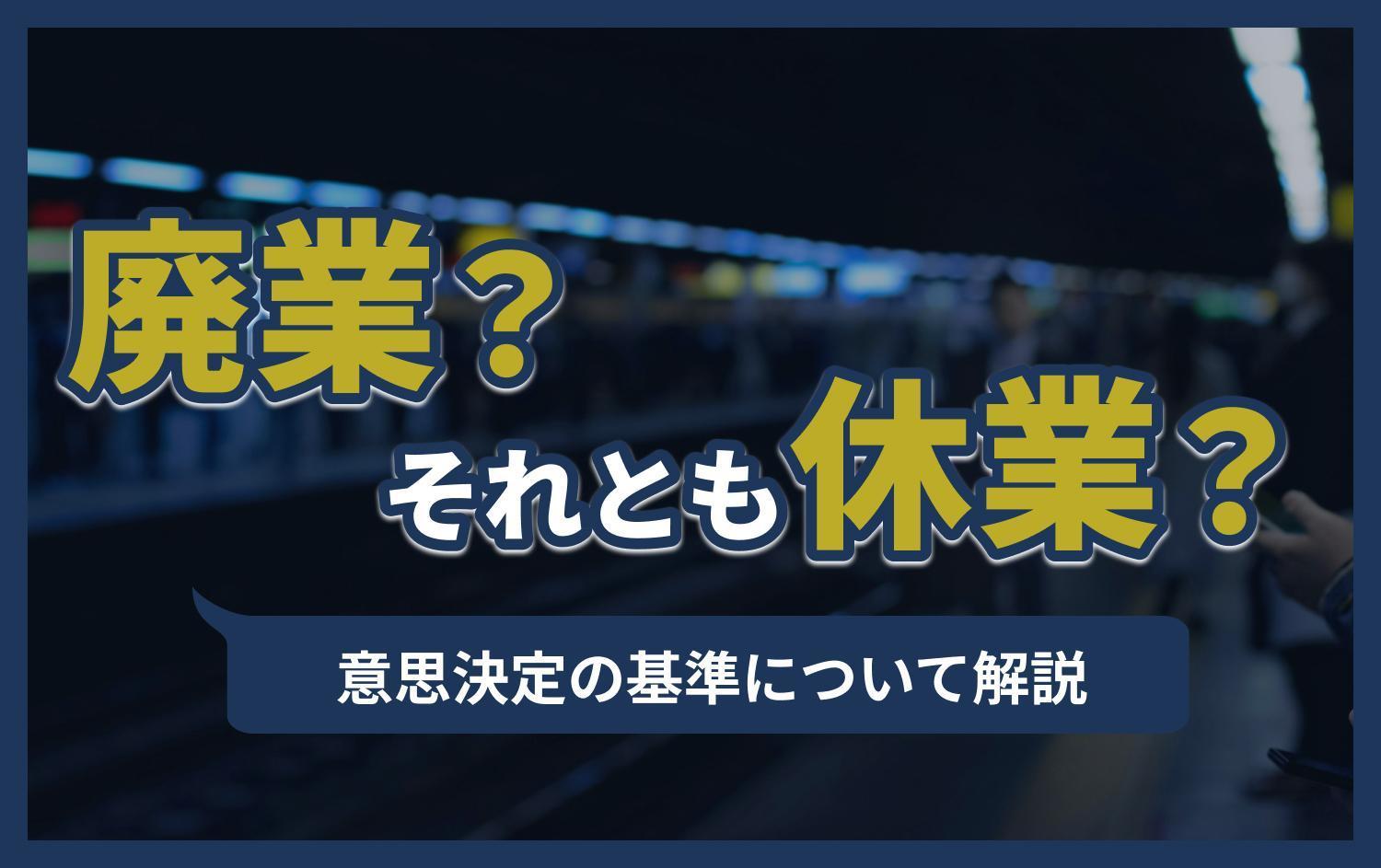
経営者の皆様、事業の継続に悩まれていませんか?後継者不在や業績不振など、廃業や休業を検討せざるを得ない状況に直面したとき、どのように準備を進めればよいのでしょうか。
廃業や休業は決して容易な決断ではありませんが、適切な手順を踏むことで、損失を最小限に抑え、新たな一歩を踏み出すことができます。
本記事では、廃業と休業の違いや、それぞれの意思決定の基準、M&Aの可能性も視野に入れながら、円滑な事業整理に向けたステップバイステップのガイドをお届けします。
廃業と休業の違い
廃業と休業は、事業活動を停止するという点で共通していますが、その目的と手続きには大きな違いがあります。
廃業は、事業を完全に終了し、会社を清算することを目的とします。事業の再開は想定せず、すべての資産を処分し、債務を返済した上で、法人格を消滅させるプロセスです。
一方、休業は、事業活動を一時的に停止し、経営の立て直しを図ることを目的とします。休業中は事業に関連する費用を削減しつつ、事業再開に向けた準備を進めます。法人格は維持されるため、休業からの再起動が可能です。
廃業を選択する際の判断基準
以下のような状況では、廃業を検討することが適切でしょう。
-
- 事業の継続が極めて困難で、経営の立て直しが見込めない場合。
- 事業を継続するよりも、廃業した方が損失を抑えられると判断される場合。
- 後継者が不在で、事業の承継が難しい場合。
- 市場環境の変化や競合他社の台頭により、事業の将来性が乏しいと判断される場合。
廃業を決断する前に、財務状況や事業環境を詳細に分析し、廃業のメリット・デメリットを慎重に見極める必要があります。
休業を選択する際の判断基準
以下のような状況では、休業を検討することが適切でしょう。
-
- 一時的な需要の減少や資金繰りの悪化に直面しているが、事業の将来性はあると判断される場合。
- 事業の抜本的な見直しや組織体制の再構築が必要だが、即座の実行が難しい場合。
- 休業期間を利用して、新たな事業計画の策定や設備投資を行うことで、事業の再建が見込まれる場合。
- 従業員の雇用を維持しつつ、経営の効率化を図る必要がある場合。
休業を選択する際は、休業期間中の資金繰りや、従業員・取引先への対応、事業再開のシナリオなどを綿密に計画することが大切です。
M&Aの検討

廃業を決断する前に、M&Aによる事業継承の可能性を探ることをおすすめします。自社の強みや独自性を生かせる企業との提携や、事業の一部売却などにより、雇用の維持と技術の継承が実現できるかもしれません。M&A仲介会社などの専門家に相談し、最善の選択肢を模索してみましょう。
自社の強みと独自性の整理
他社にはない自社の優位性を明確にし、M&Aの魅力を高めます。技術力、ブランド力、顧客基盤など、自社の強みを棚卸しし、提携先企業にアピールできる材料を準備しましょう。自社の企業文化や経営理念も、重要な差別化要因となり得ます。
M&A仲介会社への相談
M&Aに関する豊富な知見を持つ専門家から、具体的な提案やアドバイスを得ます。自社の事業内容や財務状況、廃業に至る経緯などを詳しく伝え、最適なM&Aの方法を探ります。仲介会社の選定にあたっては、実績や専門性、ネットワークの広さなどを考慮しましょう。
提携先企業の選定
自社の企業文化や事業内容との親和性が高い企業を見極め、相互にメリットの関係を築けるパートナーを探します。提携先企業の選定では、事業シナジーや財務健全性、成長戦略などを多角的に評価することが重要です。自社の強みを活かせる企業、自社の事業を発展させられる企業を見極めましょう。
廃業プロセスの概要
現状の把握と原因の分析から始めましょう
廃業を検討する際、まず自社の財務状況や事業環境を正確に把握することが重要です。売上の推移、債務の状況、市場動向などを詳細に分析し、廃業に至った原因を明らかにしましょう。この過程で、事業の存続可能性や改善の余地がないかを慎重に見極めることが求められます。
財務諸表の精査では、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書などを詳しく分析し、資産状況や収益性の推移を把握します。特に、売上高の変動、売上原価率、営業利益率、借入金の推移などに注目し、財務の健全性を評価しましょう。
市場動向の調査では、自社を取り巻く市場環境や競合他社の動向を調べ、事業の将来性を見通します。市場規模や成長率、競合他社のシェアや戦略などを分析し、自社の立ち位置を明確にします。需要の変化や技術の進歩など、市場の変化に適応できているかも重要なポイントです。
自社の競争力や差別化要因を明らかにし、事業の方向性を見定めましょう。
関係者への説明と調整
廃業の方針が固まったら、従業員、取引先、債権者など、関係者への説明と調整を行います。特に従業員に対しては、誠意を持って状況を伝え、雇用の継続や再就職支援など、可能な限りのサポートを提供することが大切です。取引先や債権者とは、債務の返済スケジュールや残務処理について、早めに協議を始めましょう。
従業員への説明会の開催
廃業の理由や今後の見通しを丁寧に説明し、質疑応答の機会を設けます。説明会では、廃業のスケジュール、法的手続き、従業員への補償内容などを明確に伝えることが重要です。また、従業員の不安や疑問に真摯に耳を傾け、できる限りの配慮を示しましょう。
再就職支援の提供
社内外の求人情報の提供、面接対策、スキルアップ研修など、従業員の再就職をサポートする体制を整えます。社内でのジョブマッチングや、関連企業への紹介など、多様な選択肢を用意することが望ましいでしょう。必要に応じて、再就職支援会社との連携も検討しましょう。
取引先との交渉
債務の返済計画や未履行契約の処理について、誠実に協議を重ねます。取引先の理解と協力を得るためには、廃業に至る経緯や今後の見通しを丁寧に説明することが欠かせません。債務の一括返済が難しい場合は、分割返済やリスケジュールなどの代替案を提示し、合意形成を目指しましょう。
資産の整理と処分
廃業に伴い、不要となる資産の整理と処分を進めます。設備や在庫の売却、不動産の処分など、できるだけ早い段階から着手することが重要です。専門家の助言を得ながら、資産価値を最大限に引き出す方法を検討しましょう。回収した資金は、従業員への補償や債務の返済に充てることができます。
資産の棚卸しと評価
所有する資産を漏れなくリストアップし、適切な時価評価を行います。不動産、設備、在庫、車両、什器備品など、有形資産の現在価値を精査します。無形資産(特許、商標、ソフトウェアなど)の価値評価も忘れずに行いましょう。
売却方法の検討
オークションや不動産仲介など、資産の種類に応じた最適な売却方法を選択します。不動産の場合は、仲介業者の比較検討や、売却条件の交渉が重要になります。設備や在庫は、業界紙やインターネットのオークションサイトを活用するのも一案です。希少性の高い資産は、専門家に相談し、適切な売却ルートを探しましょう。
売却スケジュールの策定
資産処分に要する時間を見積もり、計画的に進めます。売却に適したタイミングを見極め、処分の優先順位を決めることが大切です。必要に応じて、専門家(不動産鑑定士、機械設備評価士など)の意見を参考にしながら、現実的なスケジュールを立てましょう。
法的手続きの完了

廃業に必要な法的手続きを漏れなく行うことが重要です。税務署への届出、登記の抹消、許認可の返上など、各種手続きを遅滞なく進めましょう。行政書士や税理士などの専門家に依頼することで、手続きの負担を軽減できます。
廃業届の提出
税務署に廃業届を提出し、国税・地方税の清算を行います。廃業日までの税金を納付し、必要な書類を整えます。青色申告の場合は、「青色申告承認取消届」の提出も忘れずに。事前に税理士に相談し、必要な手続きを確認しておくことをおすすめします。
登記の抹消
法務局に登記簿の閉鎖を申請し、会社の登記を抹消します。「解散登記」と「清算結了登記」の2段階で行います。必要書類(定款、株主総会議事録、債務弁済証明書など)を準備し、速やかに手続きを進めましょう。
許認可の返上
事業に関連する許認可を所管官庁に返上し、必要な手続きを完了します。業種によって必要な手続きは異なるため、関連する官庁に問い合わせ、確認することが大切です。環境関連の許可、食品衛生関連の許可など、漏れのないよう注意しましょう。
知的財産の保護
長年培ってきた技術やノウハウ、ブランド価値など、自社の知的財産を適切に保護することを忘れてはいけません。特許や商標の権利処理、機密情報の管理体制の構築など、専門家と連携しながら万全の対策を講じましょう。
特許・商標の権利処理
特許庁への権利譲渡や放棄の手続きを行います。特許や商標の権利を譲渡する場合は、譲渡先企業との契約締結が必要です。権利を放棄する場合は、「特許料不納による消滅」の手続きを取ります。弁理士に相談し、適切な方法を選択しましょう。
営業秘密の管理
機密情報の流出防止策を徹底し、秘密保持契約の締結などを進めます。従業員や取引先との間で、守秘義務に関する契約を交わし、情報管理体制を強化します。重要な書類やデータの破棄・消去も確実に行いましょう。
ブランド価値の活用
自社ブランドの譲渡や再活用の可能性を探ります。ブランドに価値がある場合は、M&Aや事業売却の際の重要な資産となります。ブランドの評価額を算定し、譲渡条件を検討しましょう。自社ブランドを継続的に活用してもらえるよう、譲渡先企業との交渉が鍵を握ります。
清算手続き
すべての債務の返済と資産の処分が完了したら、会社の清算手続きに入ります。残余財産の分配、税務申告、役員の退任など、必要な手続きを滞りなく進めましょう。場合によっては、清算人の選任も検討する必要があります。
残余財産の分配
債務の返済後に残った財産を、定款や法令に基づいて分配します。分配方法は、株主総会で決議します。分配先は、株主、従業員、取引先など、関係者の貢献度や法的権利に応じて決定します。公平性と透明性を確保することが大切です。
清算人の選任
必要に応じて、清算人を選任し、清算事務を委ねます。清算人は、残務の処理、債権の取立て、債務の弁済など、清算に関する一切の業務を行います。通常は、代表取締役が清算人を兼任しますが、複雑な清算業務が予想される場合は、外部の専門家に委ねることも検討しましょう。
清算結了の登記
清算が結了したら、法務局に清算結了の登記を行います。清算結了の登記により、会社は法的に消滅します。登記申請には、清算人による「清算報告書」や「残余財産の分配を証する書面」などの提出が必要です。
廃業後の心のケア

事業の幕引きは、経営者にとって大きなストレスを伴います。心身の健康を維持するために、以下のようなセルフケアを心がけましょう。
カウンセリングの活用
専門家との対話を通じて、ストレスや不安を軽減します。経営者向けのカウンセリングサービスを利用し、率直に悩みを打ち明けることが大切です。周囲の理解と支援を得ながら、心の負担を和らげていきましょう。
趣味や運動の充実
新たな興味関心を探求し、リフレッシュの機会を持ちます。事業から離れた時間を作り、趣味や運動に打ち込むことで、心身のバランスを取り戻します。自分らしさを取り戻し、新たな目標に向かうエネルギーを養いましょう。
同じ境遇の経営者仲間との交流
廃業を経験した経営者との情報交換や相互支援を行います。同じ悩みを抱える仲間と語り合うことで、共感と励ましを得ることができます。経営者団体や士業団体が主催する交流会などに参加し、ネットワークを広げましょう。
廃業から学ぶ教訓
廃業は経営者にとって貴重な学びの機会でもあります。失敗から得た教訓を次の挑戦に生かすことで、より強靭な経営者へと成長できるでしょう。
意思決定プロセスの振り返り
廃業に至った意思決定を振り返り、改善点を見出します。情報収集や分析の方法、意思決定の速度やタイミングなど、意思決定プロセス全体を見直します。外部環境の変化に機敏に対応し、適切な判断を下せる力を養いましょう。
リスク管理の重要性
予期せぬ事態への備えの大切さを認識し、リスク管理を徹底します。自社を取り巻くリスクを洗い出し、対応策を準備しておくことが重要です。財務リスク、法的リスク、風評リスクなど、多角的な視点からリスクマネジメントに取り組みましょう。
ネットワークの構築
支援者や同業者とのネットワークを広げ、協力体制を整えます。廃業の過程で得た人脈を大切にし、新たな事業構想の実現に役立てましょう。支援者や同業者との信頼関係が、再起のチャンスを広げてくれるはずです。
まとめ
以上のように、廃業準備には多岐にわたる手順が必要です。しかし、一つひとつの課題に丁寧に向き合い、専門家の力も借りながら着実に進めていけば、問題なく進めることができるはずです。
事業の継続には様々な課題が伴いますが、事業環境の変化を早期に察知することが重要です。定期的な財務分析や市場調査を行い、問題点を早めに特定し、対策を講じることで、事態の深刻化を防ぐことができるでしょう。
また、事業承継やM&Aなど、廃業以外の選択肢も視野に入れておくことをおすすめします。自社の強みを活かせる形で事業を引き継ぐことができれば、雇用の維持や技術の継承にもつながります。日頃から、事業の将来像を描き、様々なシナリオを想定しておくことが大切です。
廃業を決断する際は、従業員や取引先など、関係者への配慮を忘れてはいけません。誠意を持ってコミュニケーションを取り、できる限りの支援を提供することが、経営者の責務と言えるでしょう。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。


