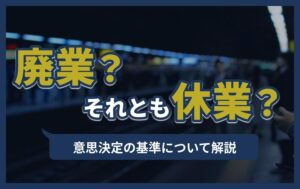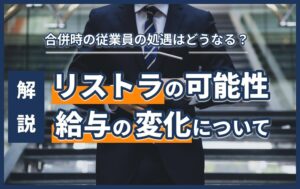債務超過の企業が合併するメリット・デメリットとは?手続きも解説
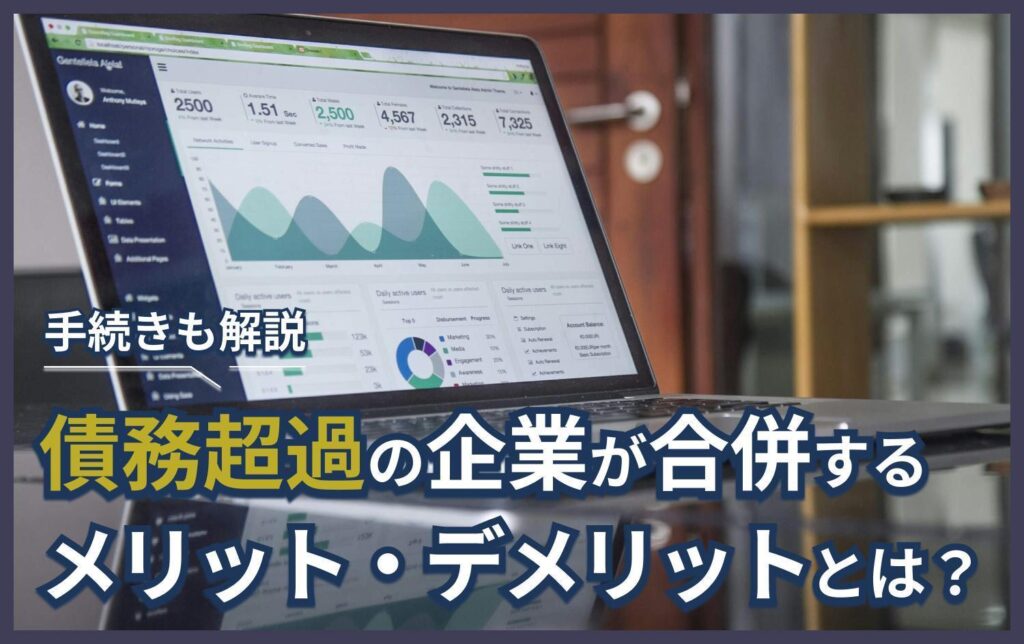

「会社を存続させるために合併を考えているが、債務超過の状態にある。このままでは合併もできないのではないか…」
こうした不安を抱える経営者の方は少なくないでしょう。特に、後継者不在に悩む中小企業の経営者にとって、債務超過は会社の存続を脅かす大きな問題です。
しかし、債務超過状態でも、一定の条件を満たせば合併は可能です。
この記事では、債務超過企業の合併における注意点について、分かりやすく解説します。
債務超過に悩む経営者の皆さまが、合併を選択肢の一つとして前向きに検討するための一助となれば幸いです。
目次
そもそも、債務超過している会社は合併できる?
合併とは、2つ以上の会社が契約によって1つの会社に統合されることを指します。一方、債務超過とは、会社の負債が資産を上回る状態のことです。
具体的には、貸借対照表(バランスシート)において、資産の部の合計金額よりも負債の部の合計金額が大きい状態を言います。
債務超過に陥る主な原因としては、業績不振による累積損失の拡大などが挙げられます。放置すれば倒産リスクが高まるため、早期の対策が必要です。
債務超過企業との合併の可否
債務超過会社が吸収合併により消滅する場合、合併は可能です。
新設合併の場合も、債務超過会社が消滅するのであれば、合併は可能です。
ただし、存続会社の株主にとっては特殊な合併となるため、株主総会の承認が必要となります。さらに、差損が生じる場合は株主総会での説明義務が追加で生じます。
合併を検討する際、債務超過は重要な検討ポイントになります。それは、合併の対価(株式の交換比率など)の算定に影響を与えるからです。
債務超過企業を吸収合併する場合、債務超過額を考慮して合併比率を決める必要があります。また、債務超過企業を存続会社とする合併では、債務超過の解消が合併の前提条件となります。
債務超過企業との合併における、存続会社のメリット
1. 税務上のメリット
債務超過企業との合併における最大のメリットは、税務上の恩恵です。消滅会社が有する繰越欠損金を存続会社が引き継ぐことができるため、将来の法人税負担を大幅に軽減できる可能性があります。
繰越欠損金の活用により、存続会社の税引後利益が増加し、キャッシュフローの改善につながります。ただし、繰越欠損金の引継ぎには一定の要件があるため、事前の確認が必要です。
2. 合併対価の節約
債務超過企業は、負債が資産を上回っている状態にあるため、その企業価値は理論上マイナスとなります。そのため、債務超過企業との合併では、合併対価を安く抑えられる可能性があります。
存続会社は、少ない資金で消滅会社の事業を取得できるため、M&Aコストを節約できます。ただし、債務超過企業の事業価値を適切に評価し、リスクを見極めた上で合併対価を決定する必要があります。
債務超過企業との合併における、存続会社のデメリット
1. 財務状況の悪化リスク
債務超過企業との合併では、消滅会社の負債を存続会社が引き継ぐことになります。そのため、存続会社の財務状況が悪化するリスクがあります。特に、消滅会社の負債が予想以上に大きい場合や、簿外債務が発覚した場合には、存続会社の財務健全性が大きく損なわれる可能性があります。合併前に、デューデリジェンスを徹底し、リスクを適切に評価することが重要です。
2. レピュテーションリスク
債務超過企業との合併は、株主や取引先から批判を受けるリスクがあります。債務超過企業は、財務状況が悪化しているため、合併に踏み切ることで存続会社の経営判断が問われる可能性があります。
消滅会社(債務超過会社)のメリット
1. 債務超過からの解放
債務超過企業にとって、合併は債務超過という状態から解放される絶好の機会です。合併により、消滅会社の負債は存続会社に引き継がれるため、債務超過というレッテルを外すことができます。これにより、取引先や金融機関からの信用力が回復し、事業活動がスムーズに行えるようになります。
2. 事業の存続
債務超過に陥った企業は、自力での再建が困難な場合が多いです。合併により、存続会社の傘下に入ることで、事業を存続させることが可能となります。存続会社の資金力や経営資源を活用することで、事業の再生や成長を図ることができます。事業の存続は、取引先や顧客にとっても好ましい結果をもたらします。
3. 雇用の確保
債務超過企業が単独で事業を継続することが困難な場合、従業員の雇用が脅かされます。合併により、存続会社の一部として事業を継続することで、従業員の雇用を確保することができます。雇用の維持は、従業員の生活の安定につながるだけでなく、事業の継続性や技術の承継にも寄与します。
消滅会社(債務超過会社)のデメリット
1. 合併先の選定の困難性
債務超過に陥った企業は、合併先を見つけることが難しい場合があります。債務超過企業は、財務リスクが高いため、引き受け手が限られます。特に、負債額が大きい場合や、事業の将来性が乏しい場合には、合併先を見つけることが一層困難となります。債務超過企業は、自社の事業価値を適切にアピールし、潜在的な合併先を探索する必要があります。
2. 取引関係への影響
合併により、消滅会社はこれまでの取引先との関係性に影響が出る可能性があります。取引先は、合併後の事業体制や信用力に不安を感じ、取引を見直す可能性があります。特に、存続会社との取引関係がない取引先は、取引の継続に慎重になる可能性があります。合併後の取引関係の維持・強化に向けて、丁寧な説明とコミュニケーションが求められます。
債務超過企業の合併手法
債務超過状態の企業も、一定の条件を満たせば合併は可能です。以下、代表的な合併手法を解説します。
(1) 吸収合併
吸収合併とは、一方の会社(存続会社)が他方の会社(消滅会社)を吸収する形式の合併です。債務超過企業が消滅会社となる場合、存続会社は債務超過額を考慮して合併比率を決定します。この際、存続会社の株主にとって不利にならないよう、慎重な検討が必要です。
吸収合併のメリットは、手続きが比較的シンプルな点です。また、存続会社の商号やブランドを継続できるため、事業の連続性を保ちやすいというメリットもあります。一方、デメリットとしては、存続会社が消滅会社の債務を引き継ぐ点が挙げられます。
(2) 新設合併
新設合併とは、合併する2つの会社がどちらも消滅し、新しい会社を設立する形の合併です。
債務超過企業同士の合併では、この方式が選択されることがあります。新設会社は、債務超過を解消するための増資などを実施することで、健全な財務体質を確保することが可能です。
新設合併のメリットは、新しい会社を設立することで、過去の債務などの負担から解放されやすい点です。また、両社の企業文化を融合させた新しい組織文化を構築しやすいというメリットもあります。デメリットとしては、手続きが複雑で時間がかかる点や、新会社の商号やブランドの構築に労力を要する点などが挙げられます。
合併の種類によって、手続きの複雑さや、債務の引継ぎ方などが異なります。自社の状況に適した合併手法を選択することが重要です。
簡易合併
簡易合併は、合併対価が存続会社の純資産額の5分の1以下であり、かつ差損が生じない場合に可能です。しかし、債務超過企業との合併では差損が生じるため、簡易合併の要件を満たさず、実施することはできません。
債務超過企業との合併比率
債務超過企業の株式価値はゼロまたはマイナスとなるため、合併比率もゼロになる可能性があります。この場合、無対価合併(非適格合併)となりますが、存続会社の税制上の不利を避けるために、1000:1などの比率を設定するのが一般的です。
合併スキームの選択と手続きの流れ
合併スキームの選択は、合併の目的や会社の状況によって異なります。主なスキームとしては、以下の3つが挙げられます。
(1)株式交換による合併
株式交換による合併は、完全親会社が完全子会社の株式を取得し、完全子会社の株主に完全親会社の株式を交付する方式です。完全子会社の株主は、完全親会社の株主となります。
(2)金銭等交付による合併
金銭等交付による合併は、存続会社が消滅会社の株主に金銭や社債などを交付する方式です。消滅会社の株主は、存続会社の株主とはなりません。
(3)三角合併
三角合併は、存続会社の親会社が合併に関与する方式です。存続会社は消滅会社の株式を取得し、消滅会社の株主に存続会社の親会社の株式を交付します。
合併の手続きは、以下のような流れで進められます。
-
- 合併の合意(基本合意書の締結)
- 合併比率の算定と交渉
- 合併契約の締結
- 合併契約書の承認(株主総会での決議)
- 債権者保護手続き
- 合併の効力発生
合併比率の算定方法と交渉のポイント
合併比率とは、合併当事会社の株式がどのような比率で交換されるかを示す指標です。合併比率の算定は、合併交渉における重要なポイントの一つです。

主な算定方法としては、以下のようなものがあります。
(1) DCF(ディスカウンテッド・キャッシュフロー)法
DCF法は、将来のキャッシュフローを現在価値に割り引いて企業価値を算定する方法です。合併当事会社のキャッシュフロー予測をもとに、適切な割引率を用いて現在価値を算出し、合併比率を決定します。
(2) 類似企業比較法
類似企業比較法は、合併当事会社と類似する上場企業の株価や財務データをもとに、合併比率を算定する方法です。PERやPBRなどの指標を用いて、相対的な企業価値を比較します。
(3) EBITDAマルチプル法
EBITDAマルチプル法は、EBITDAに一定の倍率を乗じて企業価値を算定する方法です。合併当事会社のEBITDAを算出し、類似企業のEBITDAマルチプルを参考に、適切なマルチプルを決定します。
合併比率の交渉では、以下のようなポイントに留意が必要です。
-
- 合併当事会社の将来の収益力を適切に反映しているか
- シナジー効果を適切に織り込んでいるか
- 株主にとって公正な比率となっているか
合併後の組織・システム統合の進め方
合併後は、組織やシステムの統合を速やかに進めることが重要です。統合が遅れると、業務の効率化や、シナジー効果の発現が遅れるおそれがあります。
組織統合では、以下のような点に留意が必要です。
-
- 新会社の組織構造をどのように設計するか
- 経営責任者や管理職のポストをどう配分するか
- 従業員の処遇をどうするか
システム統合では、以下のような点がポイントとなります。
-
- 基幹システムをどちらに統一するか
- データ移行をどのように進めるか
- システム統合に伴う業務プロセスの見直し
組織・システム統合には、強力なリーダーシップが欠かせません。トップダウンで進めつつ、現場の声も吸い上げながら、スピード感を持って進めることが求められます。
PMIの重要性と成功のポイント
PMIとは、合併後の統合プロセスを指します。PMIは、合併の成否を左右する重要な要素です。
PMIの主なポイントとしては、以下のようなものが挙げられます。
(1)統合ビジョンの浸透
合併後の新会社が目指すべき姿を明確にし、社内外に発信することが重要です。統合ビジョンは、従業員の一体感の醸成や、ステークホルダーの理解と支持を得るために欠かせません。
(2)シナジー効果の早期実現
合併の目的であるシナジー効果を、いかに早期に実現するかがPMIの重要な課題です。コスト削減や、営業面での連携強化など、具体的な施策を速やかに実行に移すことが求められます。
(3)従業員のモチベーション管理
合併は、従業員にとって大きな不安要素です。PMIでは、従業員とのコミュニケーションを密にし、モチベーションを維持・向上させることが重要です。統合後の処遇や、キャリアパスを明示することで、従業員の不安を払拭することが求められます。
(4)企業文化の融合
合併当事会社の企業文化は、しばしば大きく異なります。PMIでは、両社の文化を尊重しつつ、新しい企業文化を構築していくことが重要です。トップのリーダーシップの下、従業員の相互理解を促進する施策が求められます。
PMIを成功に導くためには、綿密な計画と、強力な実行力が不可欠です。専任のPMIチームを立ち上げ、全社を挙げて取り組む体制を整えることが肝要です。
シナジー効果を実現するためには、合併目的を明確にし、PMIで具体的なアクションを速やかに実行することが重要です。
部門間の連携を密にし、実行状況をモニタリングしながら、PDCAサイクルを回すことが求められます。
合併後のステークホルダー管理の重要性

合併後は、ステークホルダー管理が重要な課題となります。特に、株主、従業員、取引先など、主要なステークホルダーとの関係構築が欠かせません。
株主に対しては、合併の意義や、シナジー効果の実現状況などを丁寧に説明することが求められます。IR活動を通じて、適時適切な情報開示を行うことが重要です。
従業員に対しては、合併後の会社の方向性や、自身の処遇などについて、丁寧なコミュニケーションが欠かせません。経営陣と従業員の対話の機会を設け、不安の払拭に努めることが重要です。
取引先に対しては、合併が与える影響や、今後の取引方針などを明確に伝える必要があります。取引先との信頼関係を維持・強化するために、積極的なコミュニケーションが求められます。
ステークホルダー管理は、合併後の企業価値向上に直結する重要な取り組みです。ステークホルダーとの良好な関係構築なくして、合併の成功はありえません。トップ自らが率先して、ステークホルダーとの対話に努めることが重要です。
まとめ
以上、債務超過企業の合併について詳説してきました。債務超過企業の合併は、法的規制や手続き面での制約が多く、また財務面でのハードルも高いものです。しかし、適切な手法を選択し、必要な手続きを着実に進めることで、合併による再建の道は十分に拓けていくはずです。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。