逆さ合併とは?メリットや手続き方法について解説
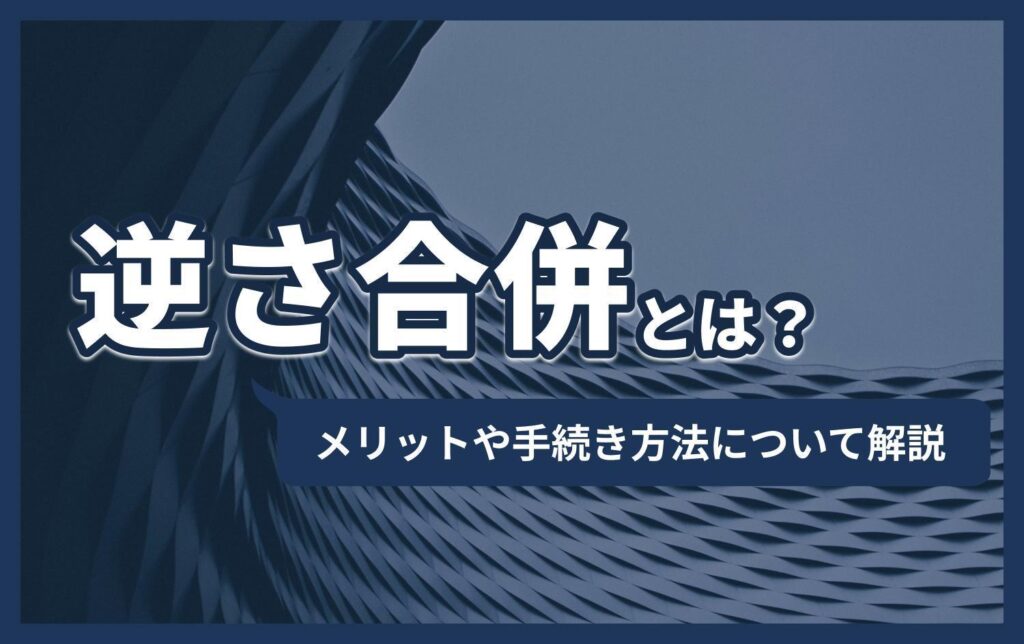
タイトル:逆さ合併とは?メリットや手続き方法について解説
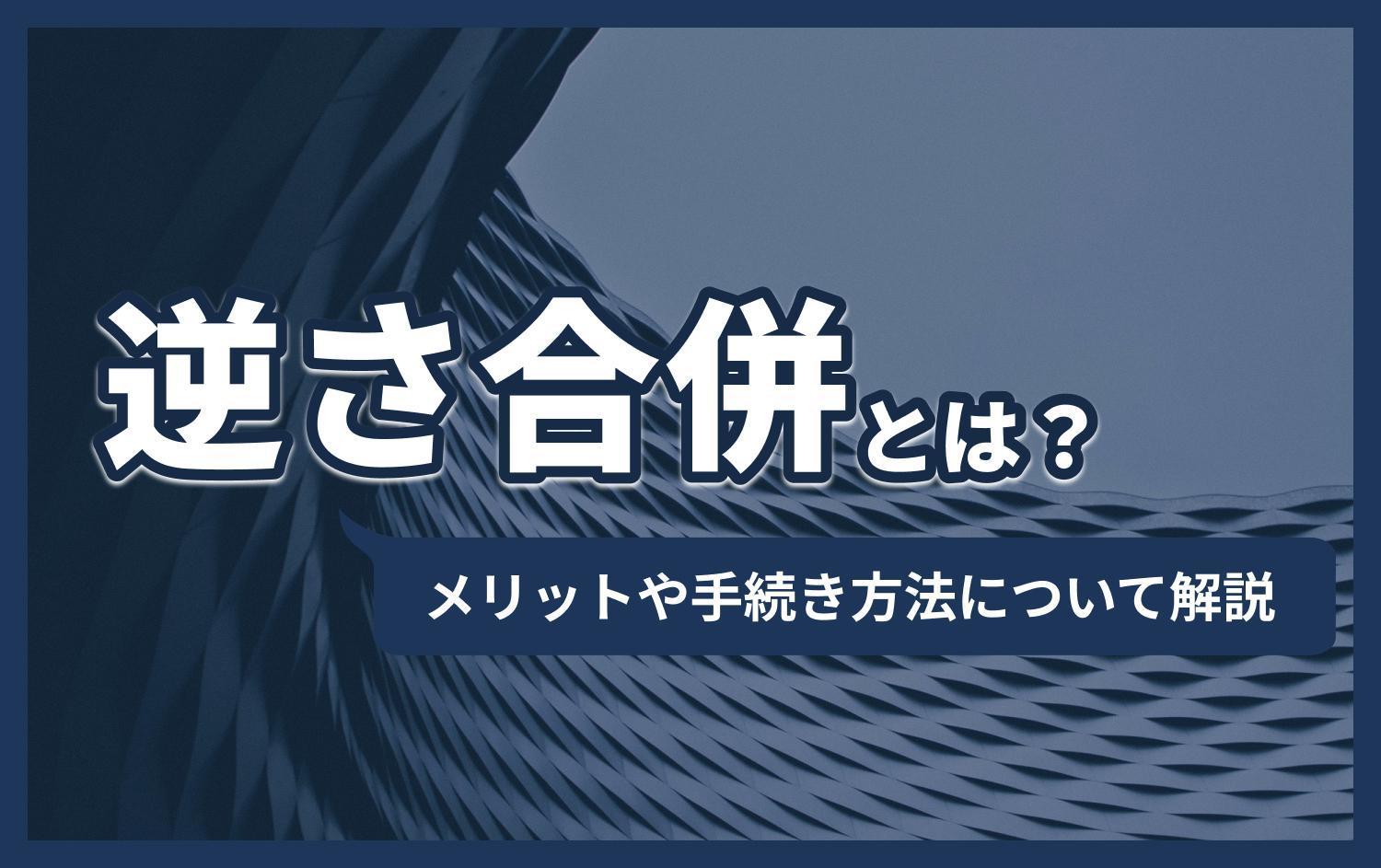
本記事では、逆さ合併について、詳細に解説します。逆さ合併とは、一般的な合併とは逆に、規模の小さい会社が規模の大きい会社を吸収合併する形式の合併です。一見すると奇妙な合併方式ですが、実は企業にとって、様々なメリットがあるのです。
逆さ合併を正しく理解することで、会社の成長に向けた強力な手段となり得ます。新たな事業展開やグループ経営の効率化など、企業の課題解決に、逆さ合併が役立つ場面は少なくありません。
この記事を通じて、逆さ合併について理解を深めていただければ幸いです。
目次
逆さ合併とは何か
逆さ合併とは、規模の小さい会社が、規模の大きい会社を吸収合併する手法を指します。通常、合併では規模の大きい会社が小さい会社を吸収するのが一般的ですが、逆さ合併ではその逆の事象が起こります。
吸収合併と新設合併がある
合併には、吸収合併と新設合併の2種類があります。
吸収合併は、存続会社が消滅会社を吸収する形式で、消滅会社は解散します。一方、新設合併は、複数の会社が合併して新たな会社を設立する形式です。
逆さ合併は、主に吸収合併の形式で行われます。規模の小さい会社が存続会社となり、規模の大きい会社を吸収するのが特徴です。
逆取得との違い
逆さ合併と似た概念に、逆取得があります。逆取得は、買収される会社が、買収する会社を支配下に置く買収手法です。株式交換や株式移転などを通じて、買収される会社の株主が買収する会社の支配権を獲得するのが特徴です。
意味合いは異なりますが、逆さ合併は逆取得に該当する手法の一種です。
逆さ合併はなぜ行われるのか?
逆さ合併の主な目的は、合併差損の回避や、繰越欠損金の引継ぎによる節税効果の獲得にあります。
合併差損とは、合併時に発生する評価損のことで、通常の合併では大きな負担となります。逆さ合併では、規模の小さい会社が存続会社となるため、合併差損が発生しにくくなります。
また、繰越欠損金とは、過去の赤字を将来の黒字と相殺できる税制上の特典です。逆さ合併では、規模の大きい会社の繰越欠損金を、存続会社である規模の小さい会社に引き継ぐことができます。これにより、将来の税負担を軽減できるのです。
逆さ合併を行うことで、これらの財務的なメリットを享受しつつ、事業の存続と成長を図ることができるのです。
逆さ合併で合併差損を回避する仕組み
合併差損は、合併時の資産の時価評価によって発生します。具体的には、被合併会社の資産を時価で評価した際、簿価(帳簿上の価値)との差額が、合併差損として計上されるのです。
例えば、被合併会社の資産の簿価が100億円、時価が80億円だったとします。この場合、20億円の合併差損が発生することになります。通常の合併では、この合併差損は吸収合併存続会社の負担となります。
しかし、逆さ合併では、この合併差損を回避することができます。吸収合併存続会社である小規模会社は、被合併会社である大規模会社の資産を簿価のまま引き継ぐことができるためです。
合併差損の回避は、逆さ合併の大きなメリットの一つです。合併に伴う財務的な負担を最小限に抑えることで、合併後の会社の業績を下支えすることができるのです。
繰越欠損金の引継ぎによる節税効果
逆さ合併を行うことによる大きなメリットが、繰越欠損金の引継ぎです。繰越欠損金とは、ある事業年度の損失を、次の事業年度以降に繰り越して、利益と相殺できる税制上の仕組みです。
適格合併に該当する場合に繰越欠損金の引き継ぎが可能であり、逆さ合併においても、要件を満たすことによって繰越欠損金を引き継ぐことができます。つまり、吸収合併存続会社は、被合併会社の過去の赤字を自社の黒字と相殺し、税負担を軽減できるのです。
例えば、被合併会社に100億円の繰越欠損金があり、吸収合併存続会社が年間20億円の利益を上げているとします。逆さ合併によって繰越欠損金を引き継いでしまえば、向こう5年間は税負担がゼロになる計算です。
このように、繰越欠損金の引継ぎは、合併後の会社の税務面でのメリットとなります。節税効果によって、キャッシュフローの改善や、財務体質の強化が期待できるのです。
逆さ合併の税制適格要件と注意点

逆さ合併で税制適格の適用を受けるには、いくつかの要件を満たす必要があります。ここでは、その詳細と注意点を見ていきましょう。
(1)100%支配関係のあるグループ内再編
完全子会社が親会社を吸収合併する場合、合併後も親会社株主が存続会社の100%株主であり続ける必要があります。この要件を満たせば、合併差損の計上を避けつつ、繰越欠損金の引継ぎが可能となります。
ただし、合併後に第三者に株式を譲渡するなどして、100%支配関係が崩れてしまうと、税制適格が否認されるリスクがあります。グループ内の株式保有関係には十分な注意が必要です。
(2)50%超の支配関係のあるグループ内再編
子会社による親会社の吸収合併でも、50%超の支配関係があれば税制適格の適用が可能です。ただし、合併の前後で、50%超の支配関係が継続していることが条件となります。
組織再編成において、株主等に対して金銭や金銭以外の資産(株式以外の資産)を交付してはならないので、株式以外の資産交付には、細心の注意が必要です。
(3)共同で事業を営むためのグループ外企業との再編
グループ外の企業と逆さ合併を行う場合、合併が「共同で事業を営むための合併」であり、かつ、合併後の存続会社が合併前の事業を引き継ぐことが、税制適格の要件となります。
具体的には、以下の要件を満たす必要があります。
-
- 合併が事業上の必要性に基づくものであること
- 合併当事会社の事業の関連性が認められること
- 合併後の存続会社が合併当事会社の事業を継続すること
- 合併対価の80%以上が存続会社の株式であること
グループ外企業との逆さ合併では、これらの要件を満たすことが税制適格の適用に不可欠です。株主総会の特別決議が必要になる
逆さ合併を行う際は、吸収合併存続会社と吸収合併消滅会社の双方で、株主総会の特別決議が必要となります。特別決議とは、発行済株式数の3分の2以上の賛成を得る決議のことを指します。
通常の合併と比べて、より高いハードルが課されている点は押さえておくべきでしょう。株主の理解と賛同を得るためにも、合併の目的や効果を丁寧に説明し、懸念事項にも真摯に向き合う姿勢が大切です。
合併対価をどう設定するか?
逆さ合併では、合併対価の設定にも注意が必要です。合併対価とは、合併によって消滅会社の株主に交付される、存続会社の株式や金銭などのことを指します。
逆さ合併の場合、吸収合併存続会社が完全子会社の場合、吸収合併消滅会社である親会社の株主が100%存在するため、合併対価の交付先がいないという問題が生じます。この問題を解決するために、いくつかの工夫が求められます。
(1)自己株式の活用
存続会社が保有する自己株式を、合併対価として交付する方法です。存続会社が十分な自己株式を保有していれば、この方法が有効となります。ただし、自己株式の取得・保有には、法的な制限もあるため注意が必要です。
(2)新株の発行
存続会社が新たに株式を発行し、それを合併対価として交付する方法です。この場合、存続会社の資本金が増加することになります。増資手続きには、株主総会の決議など、法的な手続きが必要となります。
(3)金銭対価の交付
株式以外に、金銭を合併対価として交付する方法もあります。ただし、税制適格の要件を満たすためには、金銭対価の割合に上限があることに注意が必要です。金銭対価の資金準備も、事前に計画しておく必要があります。
合併対価の設定は、税務上の要件との兼ね合いを考えつつ、実務上の実現可能性も検討しなければなりません。財務・会計・法務の専門家と連携しながら、最適な方法を選択することが求められます。
業種別に見る逆さ合併の活用ケース

逆さ合併は、財務的なメリットだけでなく、事業戦略の観点からも活用される手法です。ここでは、業種別の活用事例を見ていきましょう。
(1)製造業におけるブランド価値の向上
老舗の高級ブランドを持つ小規模な製造業者が、大手メーカーを逆さ合併するケースがあります。ブランド価値の高い存続会社の下で、グループ全体のブランド戦略を再構築することができます。
(2)小売業における販路拡大
地域密着型の小売業者が、全国展開する大手スーパーを逆さ合併するケースがあります。存続会社の販路を活用することで、事業規模の拡大が可能となります。
(3)サービス業における事業シナジーの創出
専門性の高いサービスを提供する小規模事業者が、総合サービス企業を逆さ合併するケースがあります。双方の強みを生かした新たなサービスの開発や、クロスセルの実現が期待できます。
(4)不動産業におけるポートフォリオの最適化
優良な不動産を保有する小規模事業者が、大手不動産会社を逆さ合併するケースがあります。存続会社の不動産ポートフォリオを組み替えることで、収益性の向上が可能となります。
このように、逆さ合併は、業種や企業の特性に応じて、様々な戦略的目的で活用されています。自社の強みを生かしつつ、合併の相乗効果を引き出すことが、逆さ合併の成功の鍵を握ると言えるでしょう。
逆さ合併を成功させるためのポイント
逆さ合併を成功に導くには、実務面での細やかな準備と対応が欠かせません。ここでは、主な注意点を確認しておきましょう。
(1)デューデリジェンスの重要性
逆さ合併では、吸収合併消滅会社(親会社)の資産や負債を、存続会社が引き継ぐことになります。想定外の損失やリスクを避けるためには、事前のデューデリジェンス(詳細な調査)が不可欠です。財務・税務・法務・ビジネス面での徹底的なチェックを行い、リスクを洗い出しておく必要があります。
(2)契約書の作成と交渉
合併契約書は、逆さ合併の基本的な条件を取り決める重要な書類です。合併の目的や、合併比率、合併対価、従業員の取扱い、表明保証など、細部に至るまで、綿密に規定しなければなりません。契約書の作成には、専門家の助言が欠かせません。また、当事者間の利害調整には、粘り強い交渉が求められます。
(3)組織・人事の統合
逆さ合併では、組織や人事の統合も大きな課題となります。存続会社の経営方針や企業文化を、旧親会社の組織に浸透させる必要があります。コミュニケーションを密にし、従業員の不安を払拭することが何より重要です。統合後の組織体制や、人事施策の立案には、周到な準備が欠かせません。
(4)ステークホルダーとの調整
逆さ合併では、株主や取引先など、ステークホルダーとの調整も重要なポイントとなります。特に親会社の株主に対しては、合併の目的や意義を丁寧に説明し、理解を得る必要があります。取引先にも、合併後の事業継続性をアピールし、安心感を与えることが大切です。
このように、逆さ合併の実務には、多岐にわたる留意点があります。社内の関連部署との連携を密にしつつ、外部の専門家の協力も仰ぎながら、万全の準備を進めることが求められます。
まとめ
ここまで、逆さ合併の仕組みやメリット、活用法、実務上の注意点などを詳しく見てきました。
逆さ合併は、合併差損の回避や繰越欠損金の引継ぎによる節税など、財務面での大きなメリットがあります。加えて、ブランド価値の向上や販路拡大、事業シナジーの創出など、戦略的な目的でも活用される手法です。
一方で、逆さ合併の実現には、税制適格要件の充足や、合併対価の設定など、クリアすべき課題も少なくありません。専門的な知識と、実務面での細やかな対応が求められる局面が多いのも事実です。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。


