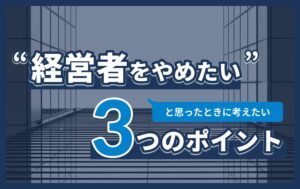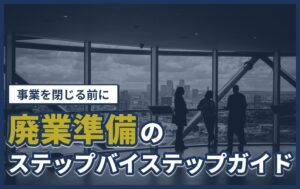【M&Aに活用】事業承継補助金の概要と申請の流れを解説
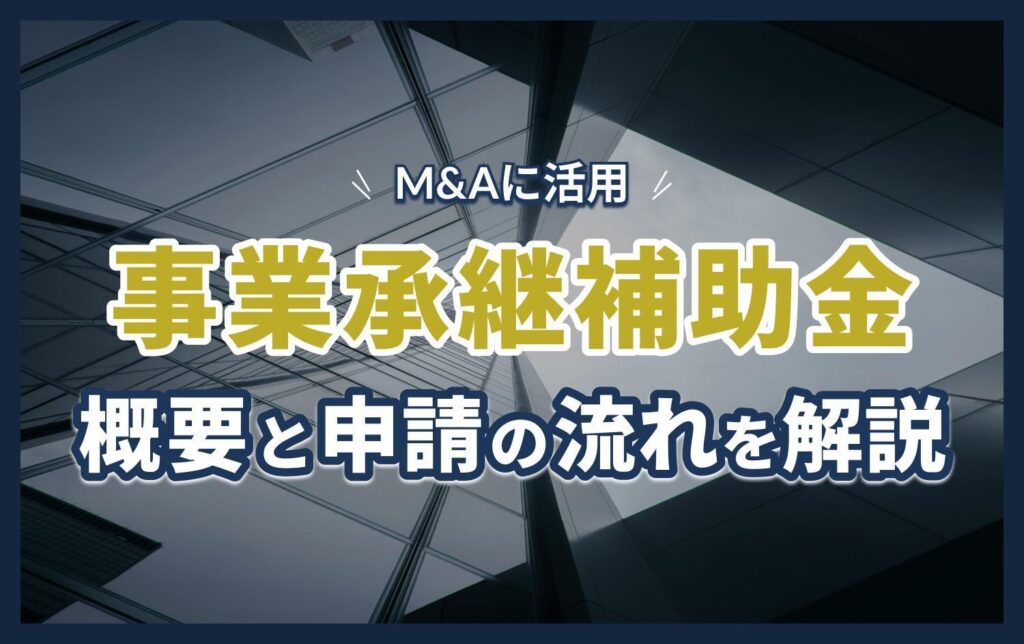
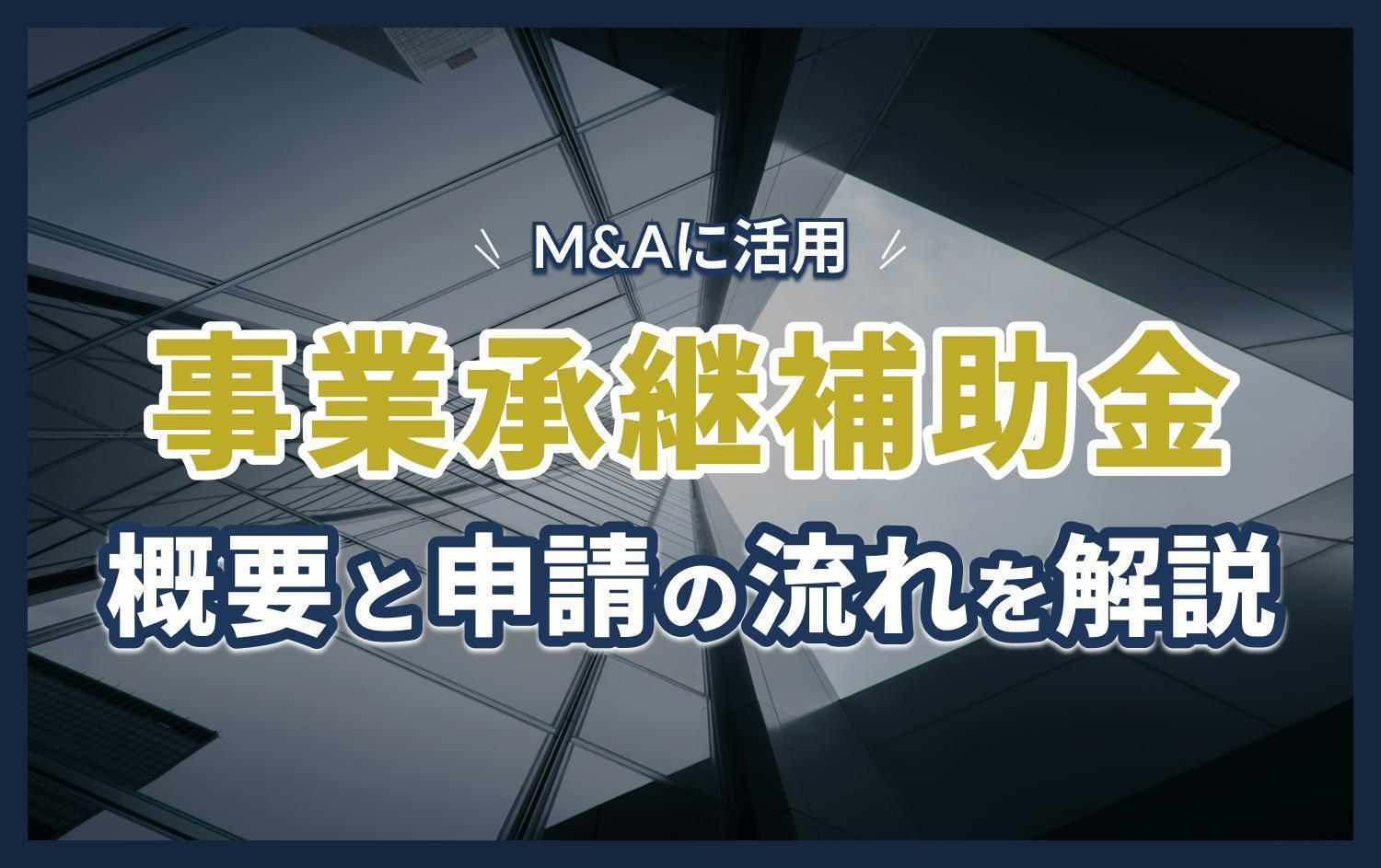
中小企業の経営者にとって、事業承継は避けては通れない重要な課題です。しかし、後継者不在や資金面での負担など、事業承継には様々な障壁があるのが実情です。
そんな中、事業承継の課題解決に向けた強い味方となるのが、事業承継補助金です。本記事では、事業承継補助金の概要や申請のポイントを詳しく解説します。
事業承継に悩む経営者の皆様に、実践的なヒントを提供できれば幸いです。
事業承継補助金とは?
事業承継補助金とは、事業承継やM&Aなどに取り組む中小企業や小規模事業者に向けて、取り組みに要する経費の一部を補助する制度です。この補助金は、以下の3つのカテゴリーに分かれています。
-
- 経営革新事業:事業承継やM&Aを契機に、新事業への進出や設備投資など、経営革新に取り組む費用を補助。
- 専門家活用事業:事業承継やM&Aに関する専門家(税理士、弁護士など)の活用費用を補助。
- 廃業・再チャレンジ事業:事業承継が難しく、廃業を選択した場合の廃業費用を補助。
この補助金は、事業承継の形態に合わせて、適切なカテゴリーを選択できる点が特徴です。自社の状況に合わせた補助金の活用が可能だと言えるでしょう。
補助金の上限金額と補助率
事業承継補助金の上限と補助率は、カテゴリーによって異なります。
経営革新事業では、補助上限は600万円、補助率は2/3となっています。ただし、一定の賃上げを実施する場合、補助上限が800万円に引き上げられます。賃上げ要件を満たすことで、より手厚い支援を受けられるのです。
専門家活用事業では、M&Aに関する専門家等の費用に対して補助が提供されます。補助上限は600万円、補助率は2/3です。M&Aを成功させるためには、専門家の知見が不可欠です。この補助金を活用して、適切な専門家を選ぶことが重要だと言えます。
廃業・再チャレンジ事業の補助上限は150万円、補助率は2/3に設定されています。廃業は、経営者にとって苦渋の決断です。この補助金を活用することで、廃業費用の負担を軽減し、再チャレンジへの一歩を踏み出すことができるでしょう。
支援対象者
事業承継補助金の支援対象者は、事業承継を契機に経営革新に挑戦する中小企業や小規模事業者、M&Aにより経営資源を引き継ぐ企業、または引き継ぐ予定の企業です。
具体的には、以下のような取り組みを行う事業者が対象となります。
-
- 新しい商品やサービスの開発
- 新たな顧客層の開拓
- 未経験の事業活動の開始
- 設備投資による生産性の向上
- 事業再編による経営の効率化
支援対象者の範囲は広く、様々な業種・業態の中小企業が対象となります。自社の事業承継の形態や、経営革新の内容が、支援対象に当てはまるかどうか、確認することが重要です。
事業承継補助金は、幅広い業種・業態の中小企業が活用できる制度です。自社の取り組みが支援対象に当てはまるか、確認してみることをおすすめします。
事業承継・引継ぎ補助金申請の流れ(申請から交付)

では、事業承継・引継ぎ補助金の申請から交付までの具体的な流れを見ていきましょう。
補助対象事業の確認
まず、自社が行おうとしている事業承継やM&Aが、補助対象事業に該当するかを確認します。補助対象事業は、以下の3つの類型に分けられます。
-
- 事業承継型:親族内や従業員への事業承継を行う場合
- M&A型:M&Aにより事業を引き継ぐ場合
- 創業支援型:創業者に事業を引き継ぐ場合
自社の事業承継やM&Aがどのような類型にあるか、しっかりと確認することが大切です。
申請枠の要件確認
次に、申請枠の要件を確認します。事業承継・引継ぎ補助金には、以下の3つの申請枠があります。
-
- 引継補助金(Ⅰ型):後継者が先代経営者の3親等以内の親族である場合
- 事業承継・引継ぎ補助金(Ⅱ型):後継者が先代経営者の3親等以内の親族以外である場合
- 事業引継補助金:M&Aにより事業を引き継ぐ場合
申請枠ごとに要件が異なるため、独自に申請した申請枠を選ぶ必要があります。
認定経営革新等支援機関へ相談
補助金の申請には、認定経営革新等支援機関の確認書が必要となります。認定経営革新等支援機関とは、税理士や公認会計士、中小企業診断士など、事業承継やM&Aに関する専門知識を持つ臓器のことを伺います。
まずは、認定経営革新等支援機関にご相談し、自社の事業承継やM&Aの計画についてアドバイスを受けましょう。その上で、補助金申請に必要な確認書の発行を依頼します。
GビズID プライムアカウント発行
補助金の申請には、GビズIDプライムアカウントが必要となります。GビズIDは、中小企業向けの各種行政サービスをオンラインで利用するためのIDです。プライムアカウントは、本人確認を行うことで発行します。される、より高いセキュリティレベルのアカウントです。
GビズIDのウェブサイトから、プライムアカウントの発行手続きを行います。発行には、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)が必要となります。
GビズIDから譲渡申請・譲渡決定通知
GビズIDプライムアカウントの発行が完了したら、いよいよ補助金の交付申請です。GビズIDのウェブサイトから、必要事項を入力し、認定経営革新等支援機関の確認書などの必要書類を添付してください。
申請内容に問題がなければ、1〜2か月程度で交付決定通知が発行されます。この通知が発行されたら、やがて補助対象事業を開始することができます。
補助対象事業の実施・実績の報告
譲渡決定通知を受けたら、補助対象事業を実施します。専門家への相談や株式評価、M&Aなど仲介、計画に沿って事業を進めていきます。
事業が完了したら、実績報告書を作成し、GビズIDのウェブサイトから提出します。実績報告書には、事業の内容や成果、経費帳などを記載します。
補助金交付
成果報告書内容に問題がなければ、補助金が交付されます。補助金は、原則として事業完了後に一括で交付されます。順次、事業の実施期間が長期にわたる場合は、年度に補助金が交付されますが渡されることもあります。
審査に通過するためのポイント
審査の通過率を上げるためには、制度の趣旨を深く理解し、求められる要件を満たすことが大切です。また、事業計画の策定や申請書類の作成には、細心の注意を払う必要があります。ここでは、経営革新事業、専門家活用事業、廃業・再チャレンジ事業の三つの類型に分けて、審査通過のポイントを見ていきましょう。

経営革新事業
経営革新事業は、新商品の開発や新市場の開拓など、企業の革新的な取り組みを支援する制度です。審査では、革新性と実現可能性が重要なポイントとなります。
革新性を示すためには、自社の強みを活かした独自性の高い事業計画が求められます。単に他社の成功事例を模倣するのではなく、自社ならではの価値提供を打ち出すことが大切です。
実現可能性を示すためには、具体的な実行計画と数値目標が必要です。目標達成のために、いつ、誰が、何を行うのかを明確に示しましょう。また、事業の収支見通しを現実的に示すことも重要です。机上の空論ではなく、市場調査や試算に基づいた計画であることを伝える必要があります。
専門家活用事業
専門家活用事業は、外部の専門家を活用して経営課題の解決を図る取り組みを支援する制度です。審査では、課題の明確化と専門家の適切性が重要なポイントとなります。
課題の明確化においては、自社の現状を正しく把握し、改善すべき点を具体的に示すことが求められます。漠然とした課題設定では、審査を通過することは難しいでしょう。
例えば、「売上を伸ばしたい」というような抽象的な課題ではなく、「新規顧客の開拓率を20%向上させる」といった具体的な課題設定が必要です。
専門家の適切性においては、課題解決に必要な知見やスキルを持つ人材を選定することが大切です。専門家の経歴や実績を示し、課題との整合性を説明しましょう。また、専門家との協働方法や期待される成果についても、具体的に示す必要があります。
廃業・再チャレンジ事業
廃業・再チャレンジ事業は、事業の廃業を円滑に進め、経営者の再チャレンジを支援する制度です。審査では、廃業計画の妥当性と再チャレンジ計画の実現可能性が重要なポイントとなります。
廃業計画の妥当性においては、廃業の理由や手続きの適切性を示す必要があります。
安易な廃業ではなく、事業継続の可能性を検討した上での決断であることを伝えましょう。また、従業員や取引先への影響にも配慮し、適切な対応方針を示すことが求められます。
再チャレンジ計画の実現可能性においては、経営者自身の適性や経験、準備状況が評価されます。前の事業から学んだ教訓を活かし、新たな事業にどう生かすのかを明確に示すことが大切です。また、再チャレンジに必要な資金計画や体制についても、具体的に説明する必要があります。
公的支援制度の審査では、書類審査と面接審査の二段階を経ることが一般的です。書類審査では、事業計画書や申請書類の完成度が問われます。的確な資料を過不足なく準備し、論理的な構成で説明することが求められるのです。
面接審査では、経営者自身の熱意や資質が評価されます。事業への想いを伝えると同時に、質問にも的確に答える必要があります。想定問答を準備し、リハーサルを重ねることが大切です。また、審査員との対話を通じて、事業計画をブラッシュアップするチャンスと捉えることも重要です。
審査の通過率を上げるためには、制度の趣旨を理解し、求められる要件を満たすことが何よりも大切です。
後継者人材バンクの活用も検討を
ここまで、事業承継補助金の概要や申請方法について見てきました。しかし、そもそも事業承継を進めるためには、適切な後継者が必要不可欠です。
後継者不在に悩む中小企業には、「後継者人材バンク」の活用をおすすめします。後継者人材バンクとは、中小企業の後継者不在の解消を目的とした、後継者候補者と中小企業のマッチングシステムです。
経営者層の年齢が上がり、事業承継に課題を抱える中小企業が増える中、後継者人材バンクの重要性は高まっています。民間企業が運営する人材バンクもありますが、信頼性の点から、商工会議所等が運営する公的な人材バンクの活用が望ましいでしょう。
後継者人材バンクの活用手順は、以下の通りです。
-
- Step 1: 人材バンクに登録
- Step 2: 後継者候補者とのマッチング
- Step 3: 面談、実習等を通じた相互理解
- Step 4: 後継者の決定と育成プランの策定
- Step 5: 計画的な後継者育成の実行
後継者人材バンクを活用することで、幅広い後継者候補者との出会いが期待できます。また、商工会議所等の支援を受けながら、後継者の育成を進めることができるのです。
後継者問題は、多くの中小企業が直面する課題です。後継者人材バンクの活用は、この課題の解決に向けた重要な一手だと言えるでしょう。
事業承継補助金と後継者人材バンク。この二つの制度を上手に活用することが、事業承継の成功の鍵を握ります。補助金を活用して経営革新を進めつつ、後継者人材バンクで適切な後継者を見つける。そうすることで、会社の未来を切り拓いていくことができるはずです。
まとめ
事業承継補助金は、事業承継やM&Aに取り組む中小企業・小規模事業者を支援する制度です。経営革新事業、専門家活用事業、廃業・再チャレンジ事業の3つのカテゴリーに分かれており、補助上限や補助率は事業によって異なります。
申請にはGビズIDプライムアカウントが必要であり、認定経営革新等支援機関へ相談の上、申請を進めていきます。審査では事業計画の革新性や実現可能性、課題の明確化と専門家の適切性、廃業計画の妥当性と再チャレンジ計画の実現可能性などがポイントになります。
事業承継を進める上では、後継者人材バンクの活用も検討すべきでしょう。事業承継補助金と後継者人材バンクを上手く活用することが、事業承継成功の鍵となります。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。