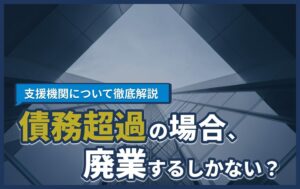廃業すると従業員はどうなる?雇用終了通知から再就職支援まで解説
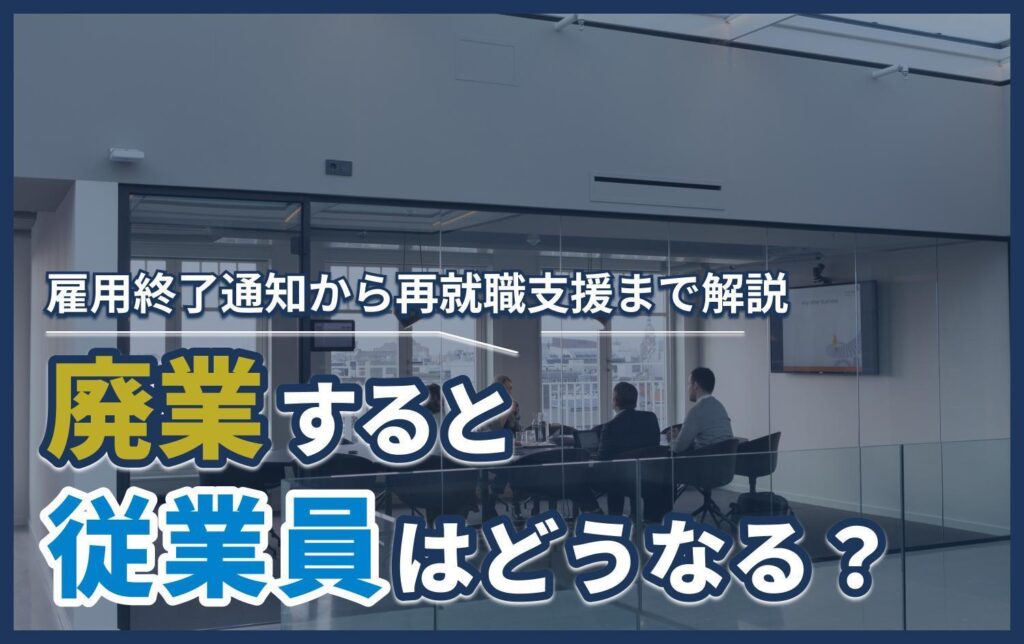
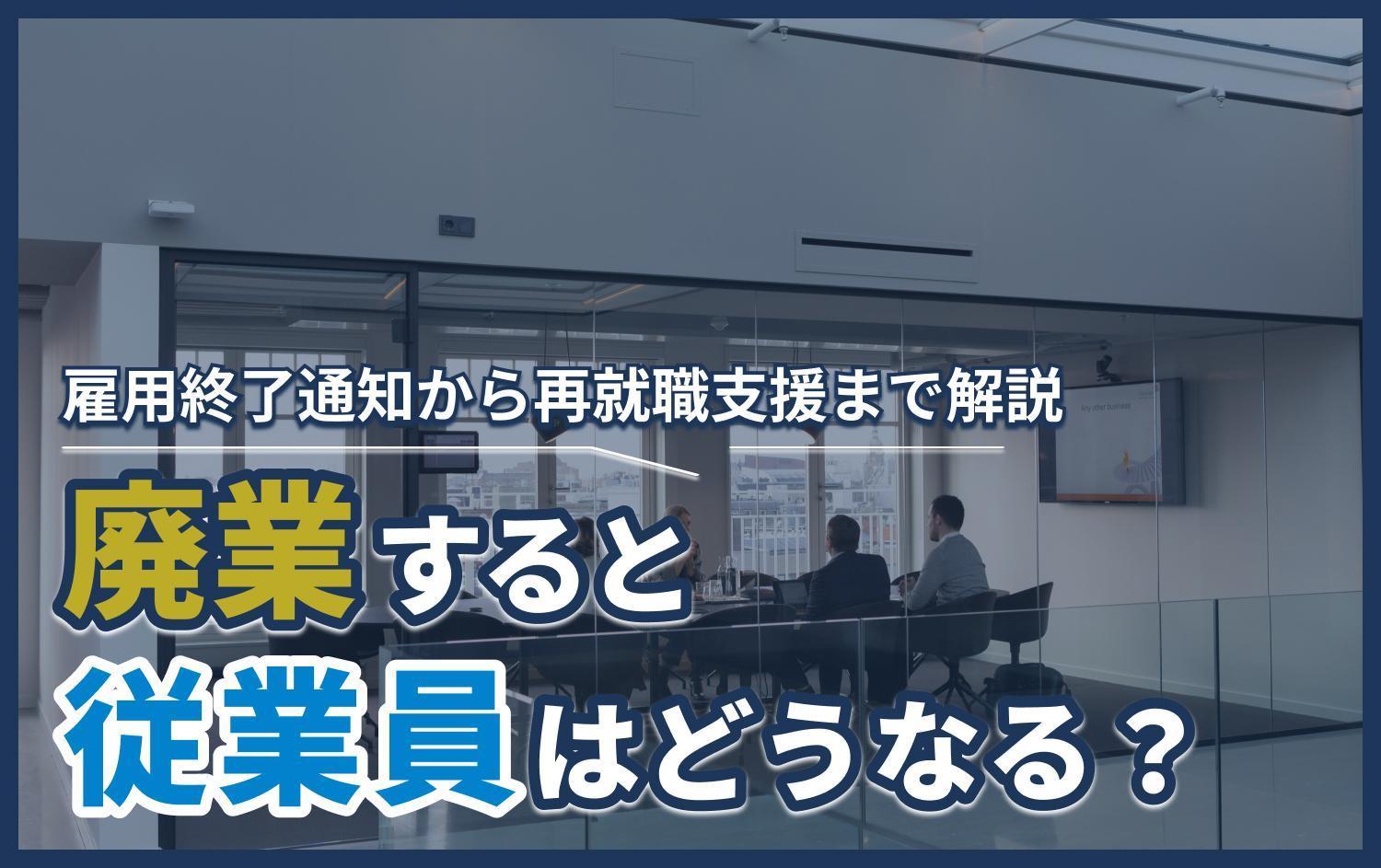
「事業を続けるのが難しくなってきた…。でも、廃業したら従業員はどうなるんだろう?」
こうした不安を抱えながら、廃業を検討されている経営者の方も多いのではないでしょうか。
苦楽を共にしてきた従業員のことを思うと、雇用や生活への影響が気がかりになるのは当然のことです。
廃業は会社の存続が危ぶまれる中での苦渋の決断。従業員のためにも、適切な手続きとサポートが求められます。
この記事では、廃業時に従業員にどのような影響があるのか、経営者として何をすべきかについて、具体的に解説していきます。
目次
廃業が従業員に与える影響は大きい
会社が廃業の道を選ぶと、従業員は雇用契約の終了、つまり「解雇」という事態に直面します。会社の事情による解雇となるため、自己都合の退職よりは手厚い支援が受けられる可能性がありますが、それでも従業員にとってのインパクトは小さくありません。
特に、新たな就職先が見つかるまでの間、収入が途絶えてしまうリスクは看過できません。生活費の工面や、住宅ローンの返済など、目の前に立ちはだかる現実的な問題に直面することになるのです。
キャリアの面でも、ある日突然会社を去らざるを得なくなるのは、大きな転機と言えるでしょう。今後のキャリアプランを見直すことを余儀なくされ、スキルアップや再就職活動に注力しなければなりません。
会社の廃業は、従業員の生活とキャリアに多大な影響を及ぼします。経営者には、その影響を最小限に抑え、従業員の不安に寄り添うことが求められるのです。
給与や賞与がなくなる
廃業による従業員への影響で、まず挙げられるのが、給与や賞与の喪失です。従業員にとって、給与は生活の基盤となる大切な収入源です。廃業によって、その収入源を突然失うことになります。
賞与も、従業員にとって大きな期待を寄せる収入の一つです。多くの企業では、年2回の賞与が支給されています。しかし、廃業によって、その期待が絶たれてしまうのです。
給与や賞与の喪失は、従業員の生活設計に大きな影響を与えます。ローンの返済や子供の教育費など、長期的な資金計画が狂ってしまう可能性があります。従業員の不安を和らげるためにも、廃業の決定から実際の廃業までの期間を十分に取り、新たな就職先を見つける時間的余裕を与えることが大切です。
従業員に給料が払えないとき、経営者が取るべきアクションとは?
失業保険をすぐに受給できる
廃業によって職を失った従業員は、失業保険を受給できます。雇用保険に加入していれば、原則として離職の翌日から失業保険を受給できるのです。
ただし、失業保険の受給には、一定の条件があります。離職理由が自己都合ではなく、会社都合であることが必要です。廃業は、会社都合の離職に該当するため、従業員は失業保険を受給できるのです。
失業保険の受給期間は、年齢や加入期間によって異なります。会社都合退職の場合、受給期間は最低90日から最大330日間となります。失業保険は、再就職までの重要な生活の支えとなるでしょう。
国民健康保険・国民年金への切り替え
廃業によって職を失うと、健康保険と年金の加入先も変更になります。会社の健康保険組合や厚生年金基金に加入していた従業員は、国民健康保険と国民年金に切り替える必要があるのです。
国民健康保険は、職場の健康保険を脱退した日から加入することになります。国民健康保険の保険料は、前年の所得に基づいて計算されます。前年の所得が高かった場合、保険料の負担が大きくなる可能性があります。
国民年金も、職場の厚生年金基金を脱退した日から加入することになります。国民年金の保険料は、定額制であり、所得に関係なく一定額を支払う必要があります。
健康保険と年金の切り替えは、手続きが煩雑なことでも知られています。従業員の負担を軽減するためにも、会社側がサポートすることが望ましいでしょう。社会保険労務士などの専門家に相談することをおすすめします。
従業員の家族が受ける影響
廃業による影響は、従業員本人だけでなく、その家族にも及びます。特に、扶養家族がいる場合、影響は大きくなります。
扶養家族とは、従業員の収入によって生計を維持している家族を指します。配偶者や子供、両親などが該当します。廃業によって従業員の収入が絶たれると、扶養家族の生活も脅かされることになります。
また、従業員の家族は、健康保険の被扶養者としての資格も失います。被扶養者は、従業員の健康保険に付随して保険の恩恵を受けていますが、廃業によってその資格を失うのです。
扶養家族も、国民健康保険に加入する必要があります。
廃業が従業員の家族に与える影響を考慮し、できる限りのサポートを行うことが、経営者の責務と言えるでしょう。
整理解雇の四つの基準

廃業に伴う従業員の解雇は、整理解雇に該当します。整理解雇とは、経営上の必要性から行われる解雇のことを指します。整理解雇が法的に認められるためには、以下の四つの基準を満たす必要があります。
- 基準
- 人員削減の必要性:経営上の必要性から、人員削減を行わなければならない状況にあること。
- 解雇回避の努力の履行:人員削減を回避するための努力を尽くしたこと。配置転換や出向、一時帰休など。
- 人員選定の合理性:解雇する従業員の人選に客観的な合理性があること。年齢や勤続年数などの基準に基づくこと。
- 解雇手続の妥当性:解雇の手続が適正に行われたこと。説明会の開催や、解雇予告通知書の交付など。
これらの基準を満たさない解雇は、無効となる可能性があります。整理解雇の四つの基準を遵守することは、トラブルを避けるためにも重要です。
廃業時に必要な従業員への法的手続き
廃業に伴う従業員の解雇は、労働基準法に則って行わなければなりません。まず解雇予告を行い、30日以上前に従業員に通知することが義務付けられています。即時解雇の場合は、30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払う必要があります。
また、廃業までに発生した未払いの賃金や手当についても、きちんと清算しなければなりません。会社の債務整理の際、従業員への未払い賃金は優先的に支払うべき債務とされているのです。
加えて、社会保険の資格喪失手続きや雇用保険の離職票の発行なども忘れずに行わなければなりません。
これらの手続きを滞りなく行うことは、経営者の責務と言えます。従業員の生活を守るためにも、誠意を持って対応することが大切です。
手続きの詳細については、社会保険労務士などの専門家に相談するのも良いでしょう。スムーズに手続きを進めることで、従業員の不安を和らげることができます。
廃業したら従業員に補償はある?解雇のタイミングや退職金の扱い、雇用を守れるM&Aについても解説
廃業時の退職金・有給休暇の取り扱い
廃業に伴い、退職金、有給休暇の取り扱いにも注意が必要です。
退職金
就業規則や労働契約に定めがある場合、その規定に従って支払う必要があります。定めがない場合でも、勤続年数などに応じて、一定の退職金を支払うことが求められます。
有給休暇
廃業日までに従業員は有給休暇を消化することが原則です。未消化の有給休暇がある場合、会社は従業員に対して廃業日までの有給休暇の消化を促すことが重要です。
ただし、やむを得ない事情により有給休暇を消化できない場合、会社は未消化分を金銭で清算することができます。有給休暇の買い上げ制度を設けている会社もありますが、制度がない場合でも、未消化分を清算することが可能です。
給与、退職金、有給休暇の取り扱いについては、就業規則などで明確に定めておくことが重要です。トラブルを避けるためにも、法律に基づいた適切な対応が求められます。
失業保険と再就職サポート
廃業に伴い解雇された従業員は、失業保険を受給することができます。失業保険を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 条件
- 雇用保険に一定期間加入していること。
- 現在、失業状態であること。
- 積極的に求職活動を行っていること。
雇用保険の加入期間の条件については、離職理由によって異なります。
- 条件
- 会社都合の場合は、退職日以前1年間で6ヶ月以上の被保険者期間が必要です。
- 自己都合の場合は、退職日以前2年間で12ヶ月以上の被保険者期間が必要となります。
失業保険の手続きは、ハローワークで行います。離職票の交付を受けた後、ハローワークに出向き、手続きを進めます。失業保険の受給期間は、年齢や被保険者期間によって異なります。
会社側にできる再就職支援としては、以下のようなものが挙げられます。
- 条件
- 再就職先の紹介:取引先や関連会社に、従業員の再就職先を紹介してもらう。
- 推薦状の作成:従業員の能力や実績を評価した推薦状を作成する。
- 教育訓練の提供:再就職に役立つスキルを身につけるための教育訓練を提供する。
従業員が次のステップに進むためのサポート体制を整えることは、会社の責務だと言えます。できる限りの支援を行い、従業員が前向きに新たな一歩を踏み出せるようサポートすることが望ましいですね。
従業員とのコミュニケーションを円滑に行うコツ
廃業の決定は、従業員にとって青天の霹靂かもしれません。突然の知らせに、従業員は動揺し、不安を感じるでしょう。

経営者には、従業員の心情に寄り添いながら、丁寧にコミュニケーションを取ることが求められます。
廃業に至った経緯や理由を丁寧に説明し、理解を求める
廃業の決定に至った背景や理由を、従業員に丁寧に説明することが大切です。経営状況の悪化や、事業環境の変化など、廃業に至った事情を詳しく伝えましょう。
その上で、廃業はやむを得ない選択であったことを説明し、従業員の理解を求めます。
従業員の不安や疑問に真摯に耳を傾け、サポートを約束する
従業員からの質問や不安な声に、真摯に耳を傾けましょう。一人ひとりの状況に合わせて、丁寧に回答することが大切です。
再就職支援や、生活面でのサポートなど、会社としてできる限りの支援を約束しましょう。
面談や相談会を定期的に開催し、従業員とのコミュニケーションを密に取る
廃業までの期間、従業員との面談や相談会を定期的に開催しましょう。個別の事情を把握し、きめ細やかなサポートを心がけます。
また、従業員同士の情報交換の場を設けることも有効です。不安を共有し、励まし合える関係性を築くことで、前向きな姿勢を維持できるでしょう。
従業員との信頼関係を築きながら、廃業までの過程を丁寧に進めていくことが大切です。
経営者には、リーダーシップを発揮し、従業員を鼓舞していくことが求められます。円滑なコミュニケーションを通じて、従業員との絆を深められたら、それは廃業後も続く財産となるはずです。
廃業後の従業員のメンタルサポート
廃業は、従業員にとって大きなストレスとなります。働く場所を失うことへの不安や、経済的な先行きへの懸念など、精神的な負担は小さくありません。
こうしたストレスは、従業員のメンタルヘルスに影響を与える可能性があります。うつ病や不安障害など、心の健康を害するリスクがあるのです。
従業員のメンタルヘルスをサポートすることは、会社の重要な責務です。メンタルヘルス対策としては、以下のようなものが挙げられます。
- 条件
- カウンセリングの提供:専門のカウンセラーによるカウンセリングを提供する。
- 相談窓口の設置:社内に相談窓口を設け、従業員の悩みに耳を傾ける。
事業承継という選択肢も検討:従業員の雇用を守ることができる
ここで、廃業を回避するための選択肢として、事業承継について考えてみましょう。
会社を存続させることで、従業員の雇用を守ることができるというメリットがあります。
事業承継には、親族や社内の後継者に株式や資産を譲渡し、経営を引き継ぐケースが一般的ですが、M&Aという形で外部の企業に譲渡することも可能です。
自社の事業の強みや将来性を見極め、適切な譲渡先を探すことが重要となります。
譲渡先企業との間で、従業員の雇用継続について合意を交わすことも必要でしょう。
良好な関係構築を通じて、従業員の雇用を守りながら、会社の価値を次世代に引き継ぐことができるはずです。
事業承継は、廃業という選択肢に代わる有力な手段と言えます。経営資源を有効活用しつつ、従業員の生活を守ることができるのは大きな利点です。
自社の実情を冷静に分析し、M&Aも視野に入れた事業承継の可能性を探ってみてはいかがでしょうか。
事業承継の進め方を解説!成功させるためのポイントも紹介します
廃業とM&Aではどちらが良い?メリット・デメリットを詳しく解説!
まとめ
会社の廃業は、従業員の雇用に大きな影響を及ぼします。経営者には、整理解雇の四つの基準を満たした上で、解雇予告や未払い賃金の清算など、法的手続きを適切に行うことが求められます。
加えて、再就職支援やメンタルケアなど、従業員に寄り添ったサポートも欠かせません。従業員の不安や悩みに真摯に向き合い、きめ細やかな支援を行うことが重要です。
こうした対応を通じて、従業員の不安に寄り添い、生活とキャリアを守ることが、経営者の重要な責務と言えるでしょう。
一方で、廃業を回避し従業員の雇用を守る手段として、事業承継という選択肢も検討に値します。M&Aも視野に入れつつ、様々な可能性を模索することで、会社の存続と従業員の雇用継続を図ることができるかもしれません。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。