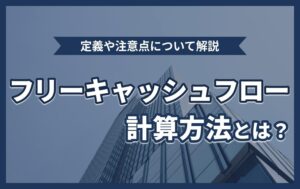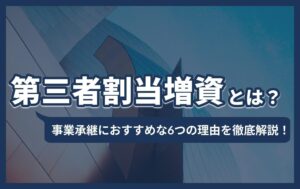従業員に給料が払えないとき、経営者が取るべきアクションとは?
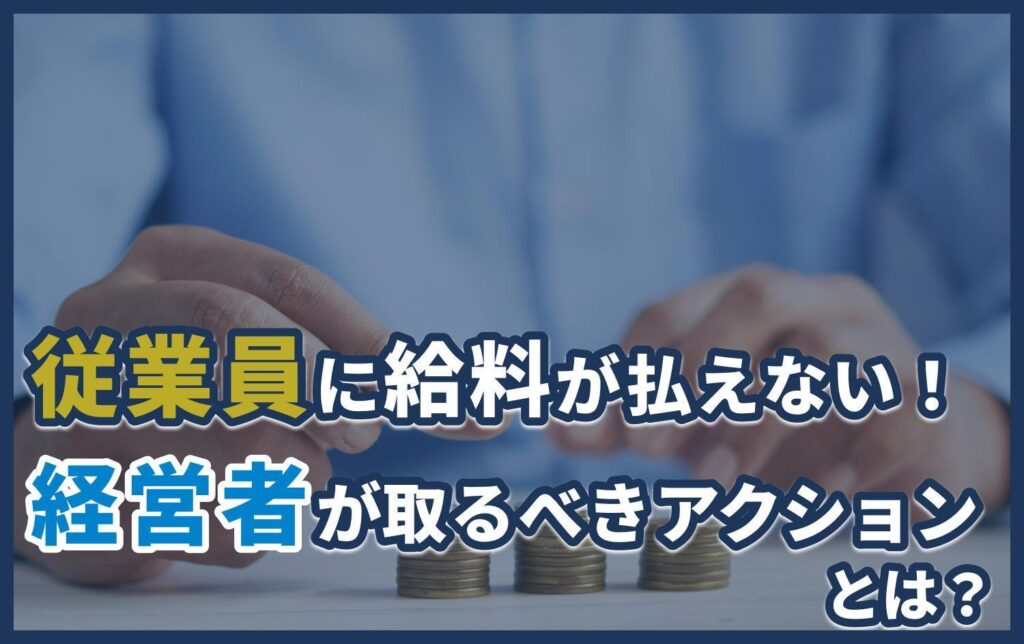
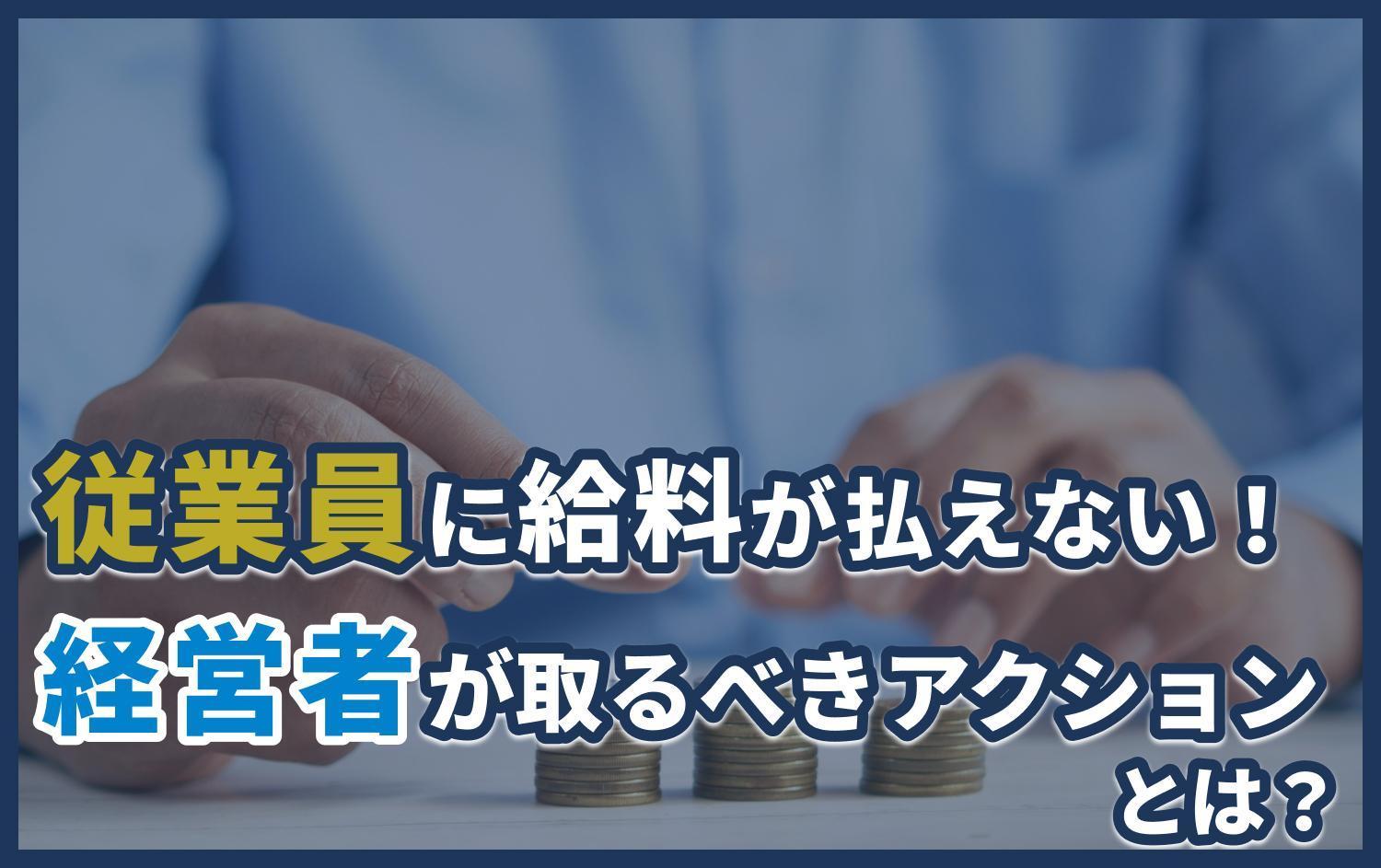
「従業員の給料が支払えない…」――。そんな恐怖と戦っている経営者は、決して少なくありません。
売上の減少や、資金繰りの悪化などから、給与の支払いに窮する状況に陥ることは、どの企業にも起こり得ることです。しかし、そのような状況下でも、経営者には従業員の生活を守る責任があります。
給与の未払いは、従業員の信頼を失うだけでなく、法的なペナルティを招く恐れもあるのです。
では、給与の支払いが難しい状況に直面したら、どのように対処すべきでしょうか。
この記事では、給与未払い時の対応策から、資金調達の選択肢、そして長期的な経営改善に向けたヒントまで、幅広く解説していきます。
給料が支払えないことで生じるリスクと罰則とは?
従業員への給与の支払いは、経営者に課せられた法的な義務です。
労働基準法第24条では、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定められています。この規定に違反し、給与を支払わない場合、以下のようなリスクが生じます。
引用:e-Gov法令検索 「労働基準法 第24条」
労働基準監督署からの是正勧告
労働基準監督署は、労働者からの申告などを受けて、調査を行います。その結果、給与の支払いに問題があると判断された場合、是正勧告が行われます。
刑事罰の可能性
是正勧告に従わない場合、労働基準法違反として、30万円以下の罰金に処されるリスクがあります。
民事上の責任
未払い賃金について、従業員から民事訴訟を提起される可能性があります。その際、未払い賃金に加え、遅延損害金の支払いが命じられるケースもあります。
このように、給与の未払いには重大なリスクが伴います。経営者には、給与支払いの重要性を再認識し、適切な対応を取ることが強く求められます。
従業員へのコミュニケーションは誠心誠意をもって対応しましょう
給与の支払いが遅れる、あるいは一時的に支払えない状況に陥った際、経営者に求められるのは、従業員への誠実な説明です。
給与支払いの遅延や未払いは、従業員の生活に直結する重大な問題です。その状況を曖昧にしたり、説明を避けたりすることは、従業員の不安を増幅させ、信頼関係を損なうことにつながります。
経営者は、以下のようなポイントを意識して、従業員とコミュニケーションを取ることが大切です。
状況の正直な説明
なぜ給与の支払いが難しい状況に陥ったのか、その原因を具体的に説明します。会社の業績悪化や、取引先の倒産などの外部要因がある場合は、それを明確に伝えましょう。
今後の対応策の提示
給与の支払いに向けて、どのような対応策を検討しているのかを説明します。資金繰りの改善策や、金融機関への相談状況なども、できる限り具体的に伝えることが重要です。
謝罪と再発防止の決意表明
従業員に多大な迷惑をかけていることを謝罪し、再発防止に全力で取り組む決意を示します。経営者としての責任を真摯に受け止める姿勢を示すことで、従業員の理解を得やすくなるでしょう。
従業員への誠実なコミュニケーションこそ、難しい状況を乗り越えるための基盤となります。会社の置かれた状況を隠さず、従業員と向き合う姿勢が何より大切だと言えます。
給与未払いを防ぐための対策とは

給与の支払い資金を確保するには、外部からの資金調達が欠かせません。ここでは、主な資金調達の選択肢を見ていきましょう。
事業性融資(ビジネスローン)
金融機関から事業資金を借り入れる方法です。日本政策金融公庫や民間金融機関が、中小企業向けの様々な融資制度を用意しています。ただし、融資審査には一定の時間を要するため、給与支払いの緊急性が高い場合は、他の選択肢も検討する必要があるでしょう。
ファクタリング
売掛金を担保に、資金を調達する方法です。売掛金を買い取ってもらうことで、比較的短期間で資金を得ることができます。ただし、手数料分だけ資金調達コストが高くなるのがデメリットです。
役員報酬の減額
役員報酬を一時的に減額し、その分を給与支払いに回す方法です。経営者自らが身を削ることで、従業員の理解を得やすくなります。ただし、役員報酬の減額だけでは、必要な資金を確保できない場合もあるでしょう。
個人資産の売却・担保提供
経営者個人が保有する不動産や有価証券などを売却したり、担保に提供したりすることで、資金を捻出する方法です。個人資産を事業のために投じることは、経営者としての覚悟が問われる選択だと言えます。
取引先への支払い期限を伸ばす
取引先への支払いの繰り延べについても検討しましょう。仕入先や外注先などに、支払いの猶予を相談するのです。
取引先との信頼関係があれば、一時的な支払いの繰り延べを受け入れてもらえる可能性があります。例えば、通常は月末締めの翌月末払いを、2カ月後の支払いに延ばしてもらうなどです。
売掛金の早期回収
また、売掛金の早期回収です。得意先に、通常よりも早い支払いを相談するのです。
売掛金は、企業の資金を大きく左右する要素の一つです。回収が遅れれば、資金繰りが悪化します。逆に、早期に回収できれば、資金繰りの改善につながるのです。
得意先との信頼関係を活かし、早期の支払いを相談してみましょう。例えば、通常は2カ月後の支払いを、1カ月後に繰り上げてもらうなどです。
従業員から減額同意を取得するには

業績悪化などにより、一時的に給与の減額を検討せざるを得ない状況もあるでしょう。その際、経営者は従業員の同意を得る必要があります。
給与減額の同意を得るには、以下のようなステップを踏むことが求められます。
減額の必要性の説明
なぜ給与の減額が必要なのか、その理由を具体的に説明します。会社の財務状況や、業績回復に向けた計画なども、できる限り詳しく伝えることが重要です。
減額幅と期間の提示
給与をどの程度減額するのか、その幅と期間を明確に示します。この際、減額後の給与が最低賃金を下回らないよう注意が必要です。
従業員との個別面談
従業員一人ひとりと面談を行い、減額について直接説明します。従業員の意見や質問に真摯に耳を傾け、理解を得るように努めましょう。
同意書の取得
減額に同意する従業員からは、同意書にサインをもらいます。同意書には、減額の内容や期間などを明記し、トラブルの防止を図ります。
給与の減額は、従業員にとって大きな不利益となります。従業員の生活への影響を十分に考慮し、慎重に判断することが求められます。
未払い賃金の立替払制度とは
会社が倒産して賃金の支払いができなくなった場合、従業員の生活を守るために、未払い賃金の立替払制度が用意されています。
この制度では、独立行政法人労働者健康安全機構が、会社に代わって従業員に賃金を立替払いします。
立替払制度を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。
従業員は労働者であること
従業員は、労働基準法で定義される労働者であり、労災保険の適用事業所に1年以上雇用されていた必要があります。
倒産が原因で退職し、賃金が未払いであること
会社の倒産が原因で、賃金が支払われないまま退職した場合に適用されます。退職日は、倒産日(法律上の倒産の場合は破産手続き等の申立日、事実上の倒産の場合は労働基準監督署への認定申請日)の6か月前から2年の間であることが必要です。
未払い賃金額が証明されていること
法律上の倒産の場合は破産管財人等の証明、事実上の倒産の場合は労働基準監督署長の確認を受けた未払い賃金額であることが必要です。
この制度を利用すれば、従業員は未払い賃金の一部(上限あり)を国から受け取ることができ、生活の安定が図れます。
ただし、立替払制度はあくまで緊急時の措置です。会社の経営を立て直すには、抜本的な改善策が必要不可欠です。
今すぐ経営改善策を打ちましょう
給与の未払いは、根本的には会社の業績悪化が原因です。
したがって、給与支払いの問題を根本から解決するには、長期的な視点に立った経営改善が不可欠となります。
経営改善の具体策としては、以下のようなものが考えられます。
事業の選択と集中
採算性の低い事業から撤退し、経営資源を有望な事業に集中させます。事業ポートフォリオの見直しを通じて、収益性の向上を図ります。
場合によっては、M&Aは有効な手段となります。自社の経営資源の中に光るものがあれば、買い手が見つかる可能性があります。
M&Aには株式譲渡、事業譲渡、合併など様々なスキームがあり、それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、最適なスキームを選定していく必要があります。
コスト削減
無駄な経費を洗い出し、徹底的なコスト削減を実施します。材料費の見直しや、業務プロセスの効率化などを進めることで、利益率の改善につなげます。
資金繰りの安定化
金融機関との関係強化や、資金調達手段の多様化を図ります。売掛金の早期回収や、在庫圧縮などにより、運転資金の改善を進めることも重要です。
組織体制の見直し
組織体制や業務フローの見直しを通じて、効率的な組織運営を目指します。社員の意欲を引き出す人事施策の導入も、検討に値するでしょう。
まとめ
以上、給与支払い問題に直面した際の対応策について、詳しく見てきました。
給与の未払いは、従業員の生活を直撃する重大な問題です。経営者には、リスクを認識し、適切な対処を取ることが強く求められます。未払いが発生した際は、透明性の高いコミュニケーションを心がけ、従業員の理解と協力を得ることが重要だと言えるでしょう。
資金繰りの改善には、外部からの資金調達が欠かせません。ビジネスローンやファクタリングなど、自社に合った資金調達手段を選択することが重要です。
給与の減額は、従業員の同意を得た上で、慎重に実施する必要があります。未払い賃金の立替払制度は、倒産の危機に際しての重要なセーフティネットとなります。
そして、給与問題の根本的な解決には、長期的な経営改善が不可欠です。事業や組織の見直しを通じて、収益力の向上と財務基盤の強化を図ることが何より大切だと言えます。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。