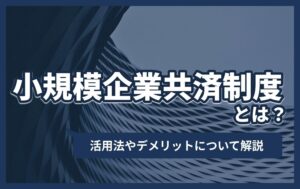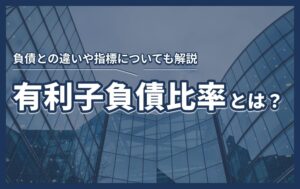破産手続きの一般的な流れとは?その後の影響についても解説
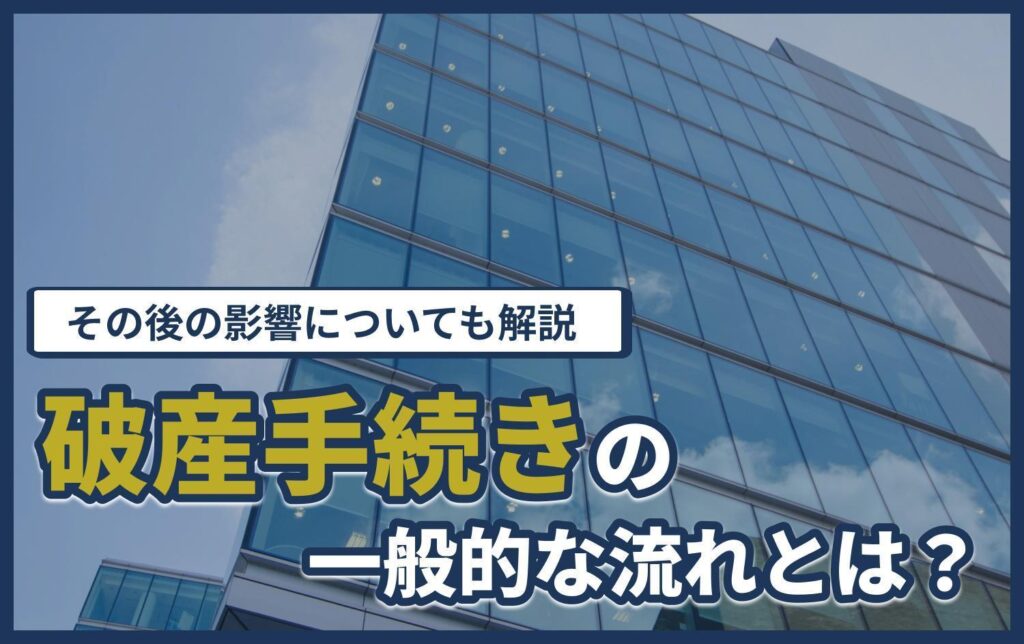
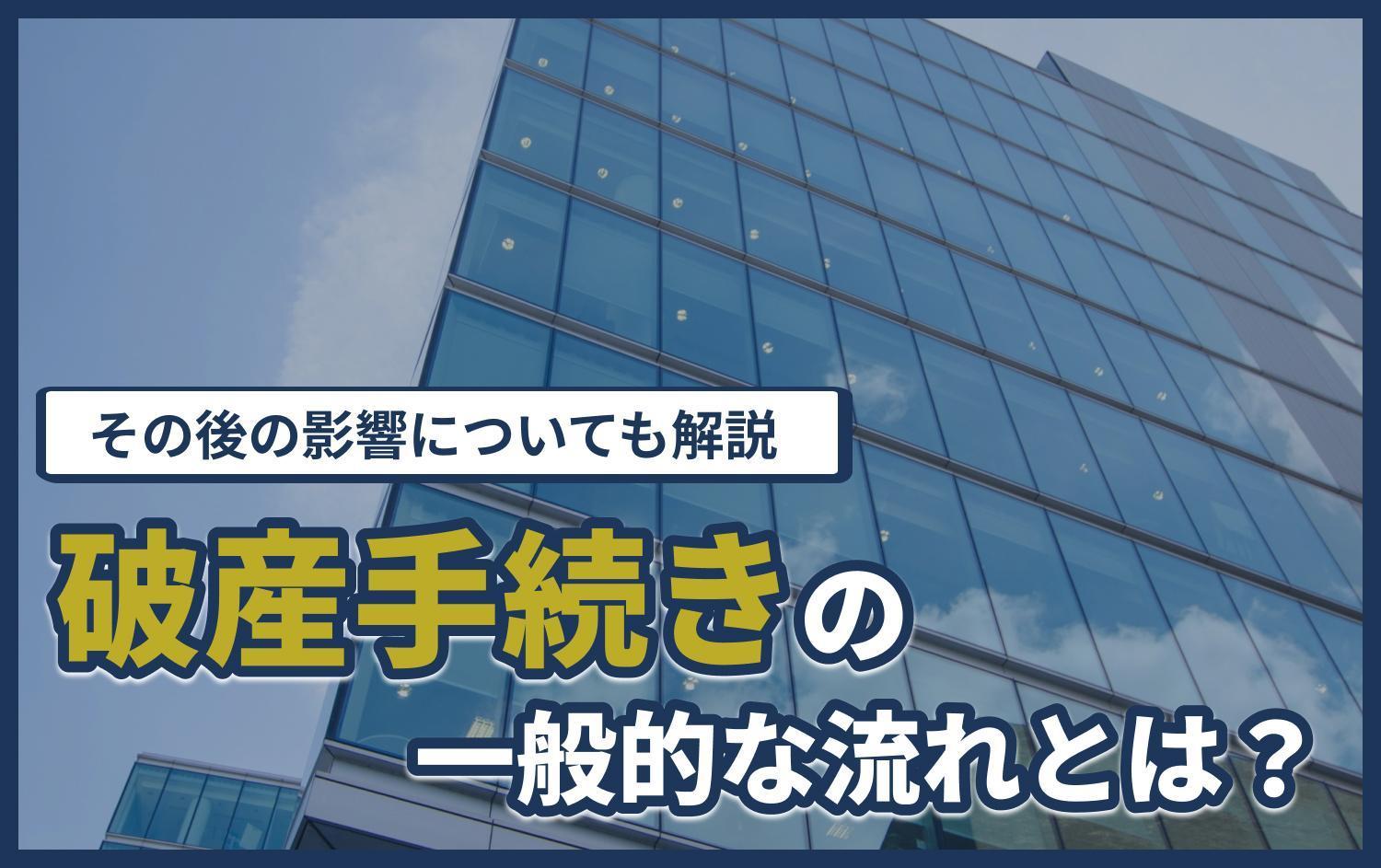
破産は、債務者が債務を返済できなくなった状態を指し、個人や企業が直面し得る深刻な財務上の危機です。
本記事では、破産の要件や手続きの概要、破産者の義務と制限、そして破産と民事再生の違いなどについて詳しく解説します。
目次
破産とは
破産とは、債務者が債務を弁済できなくなった状態を指します。会社の場合、事業の継続が困難になり、借金を返済できなくなった状況が該当します。
債務を弁済できなくなった場合とは、以下のようなケースが考えられます。
-
- 売上の減少や資金繰りの悪化により、借入金の返済が滞る状況に陥った場合
- 事業の失敗により、多額の損失を抱え、債務の弁済が困難になった場合
- 取引先の倒産などにより、売掛金の回収が見込めなくなり、資金繰りが悪化した場合
このような状況に陥ると、債権者から支払いを求められても、応じることができなくなります。債務の弁済が困難な状態が続けば、最終的には破産手続きを申請せざるを得なくなるのです。
法人破産の要件 – 支払不能と債務超過
破産手続きを申請するには、どのような要件を満たす必要があるのでしょうか。ここでは、破産の要件である「支払不能」と「債務超過」について説明します。
支払不能
支払不能とは、債務者が支払期日にある債務を弁済できない状態を指します。
例えば、取引先からの入金が滞り、手元の現金が不足しているため、金融機関からの借入金の返済ができないケースなどが該当します。このような状態が続けば、支払不能に陥ったと判断されます。
支払不能は、一時的な資金繰りの悪化では認められません。恒常的に債務の弁済ができない状態で認められます。
債務超過
債務超過とは、債務者の総資産よりも総負債が上回っている状態を指します。債務超過は、バランスシートを見れば判断することができます。総資産と総負債を比較し、総負債の方が上回っていれば、債務超過の状態にあると言えます。
支払不能と債務超過、この2つの要件のいずれかを満たした場合、破産手続きを申請することができます。
破産手続きの概要
債務を返済できなくなった個人や企業が、裁判所の手続きを通じて債務を整理し、再スタートを切るための制度が破産手続きです。
破産の申立てを受けた裁判所は、破産原因の有無を調査し、破産手続開始の決定を下します。
破産手続開始が決定すると、破産管財人が選任されます。債務者の財産を管理・換価し、債権者への配当を行います。この際、債務者の財産は全て破産財団に組み入れられ、破産管財人による管理下に置かれます。
破産手続きを申立てるには、以下の書類を裁判所に提出する必要があります。
-
- 破産申立書:破産申立ての理由や債務の状況などを詳細に記載します。
- 債権者一覧表:債権者の名称、住所、債権額などを網羅的に記載します。
- 財産目録:債務者が所有する全ての財産を漏れなく記載します。
- 収支明細書:破産申し立て前の一定期間の収支状況を詳細に記載します。
- 破産手続予納金:裁判所への予納金を納付します。
なお、破産申立書には、破産手続開始の原因となる事実を具体的に記載する必要があります。代表的な破産手続の開始理由は、「支払不能」と「債務超過」です。
破産手続の開始が決定した後は、債権者集会の開催、債権の調査・確定、配当などのプロセスを経て、最終的に免責が決定されれば、残存債務は免責され、債務者は再スタートを切ることができます。ただし、非免責債権については、免責の対象外となります。
破産手続きの費用と期間

破産手続きには、以下のような費用がかかります。
-
- 予納金:20万円程度(管財事案の場合)、2万円程度(同時廃止事案の場合)
- 弁護士費用:30万円~50万円程度
- 官報公告費用:10万円程度
- 破産管財人の報酬:破産財団の価額に応じて算定
特に、管財事案と同時廃止事案では、予納金に大きな差があります。管財事案は、破産財団からの配当が見込まれる場合に選択されますが、予納金が高額になります。
一方、同時廃止事案は、破産財団からの配当が見込めない場合に選択され、予納金は低額ですが、免責までのハードルが高くなります。
破産手続きの期間は、個人の場合は6ヶ月〜1年程度、法人の場合は1年〜2年程度が一般的です。ただし、さらに長期化する可能性もあります。
破産と民事再生の違い – どちらが適切か?

経営難に陥った法人が選択し得る手続きとして、破産と民事再生があります。両者の主な違いは以下の通りです。
-
- 目的:破産は債務の清算が目的。民事再生は事業の再建が目的。
- 債務の取扱い:破産では原則として全ての債務が免責。民事再生では再建に必要な債務は残る。
- 事業の継続:破産では事業を継続できない。民事再生では事業を継続しながら再建を図る。
- 株主の地位:破産では株主の地位は消滅。民事再生では維持される。
法人にとって、事業の継続を望むなら民事再生、債務を完済して清算するなら破産が適しているといえます。ただし、民事再生を選択するなら、再建の見込みがあることが前提です。将来の事業見通しを冷静に判断することが重要です。
経営者個人に対する責任追及のリスクも考慮する必要があります。民事再生では経営者責任が追及される場合もあるのに対し、破産ではそのリスクは低くなります。
民事再生とは?破産との違いや手続きの流れ、メリット・デメリットなどを解説
破産手続き中の債務者の義務と制限
破産手続き中、債務者には以下のような義務と制限が課されます。
債務者の義務
-
- 破産管財人への協力義務:財産の状況や債権者に関する情報を誠実に開示する義務があります。
- 財産の不当な処分の禁止:破産財団に属する財産を不当に処分してはいけません。
- 裁判所の呼出しに応じる義務:裁判所から呼び出しがあった場合は、必ず応じる必要があります。
債務者の制限
-
- 職業選択の制限:破産者は、一定の職業(公務員、弁護士など)に就くことが制限されます。
- 財産の管理処分権の制限:破産手続き開始決定後は、破産財団に属する財産の管理処分権が破産管財人に専属します。
- 信用取引の制限:破産者は、クレジットカードの使用や、ローンの利用などが制限されます。
これらの義務と制限は、破産手続きの適正な進行と債権者の保護を目的としています。債務者は、これらを十分に理解し、誠実に対応することが求められます。
破産申立て後の生活はどう変わる?
破産手続きを経て免責を受けると、原則として残存債務は消滅します。しかし、破産者には以下のような制約が課されます。
-
- 一定期間の公職就任制限
- パスポート取得の制限(破産手続開始決定から5年間)
- 資格制限(弁護士、公認会計士など一部の資格に制限あり)
- 信用情報への登録(5年〜10年程度)
特に、信用情報への登録は、その後の金融活動に大きな影響を及ぼします。
新たな借入やクレジットカードの作成などが制限されるため、再スタートを切る上での障壁となります。
破産手続きに伴うこれらのデメリットを最小限に抑えるには、破産に至る前の早い段階で対策を講じることが重要です。
事業や財務の状況を定期的にモニタリングし、リスクを早期に察知することが求められます。
そして、事態が深刻化する前に、専門家に相談し、適切な選択を行うことが重要です。
まとめ
破産は、債務の返済が困難になった個人や企業が、裁判所の手続きを通じて債務を整理し、再スタートを切るための制度です。破産手続きには、支払不能や債務超過といった要件があり、申立てには各種書類の提出が必要です。
手続き中は、破産管財人による財産の管理・換価が行われ、債務者には財産の開示や不当処分の禁止などの義務が課されます。一方、破産者には職業選択の制限や信用取引の制限などのデメリットもあります。破産と民事再生の違いを理解し、状況に応じて適切な選択を行うことが重要です。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。