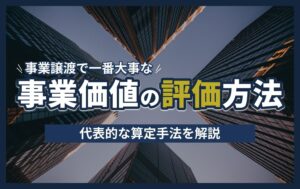清算とは?手続きの全体像と注意点について解説
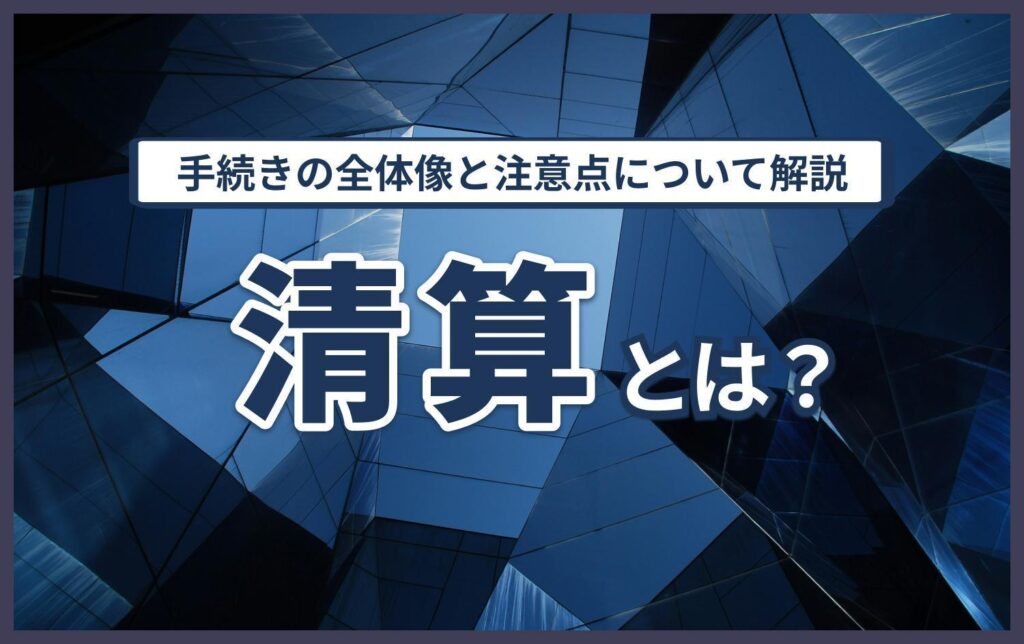
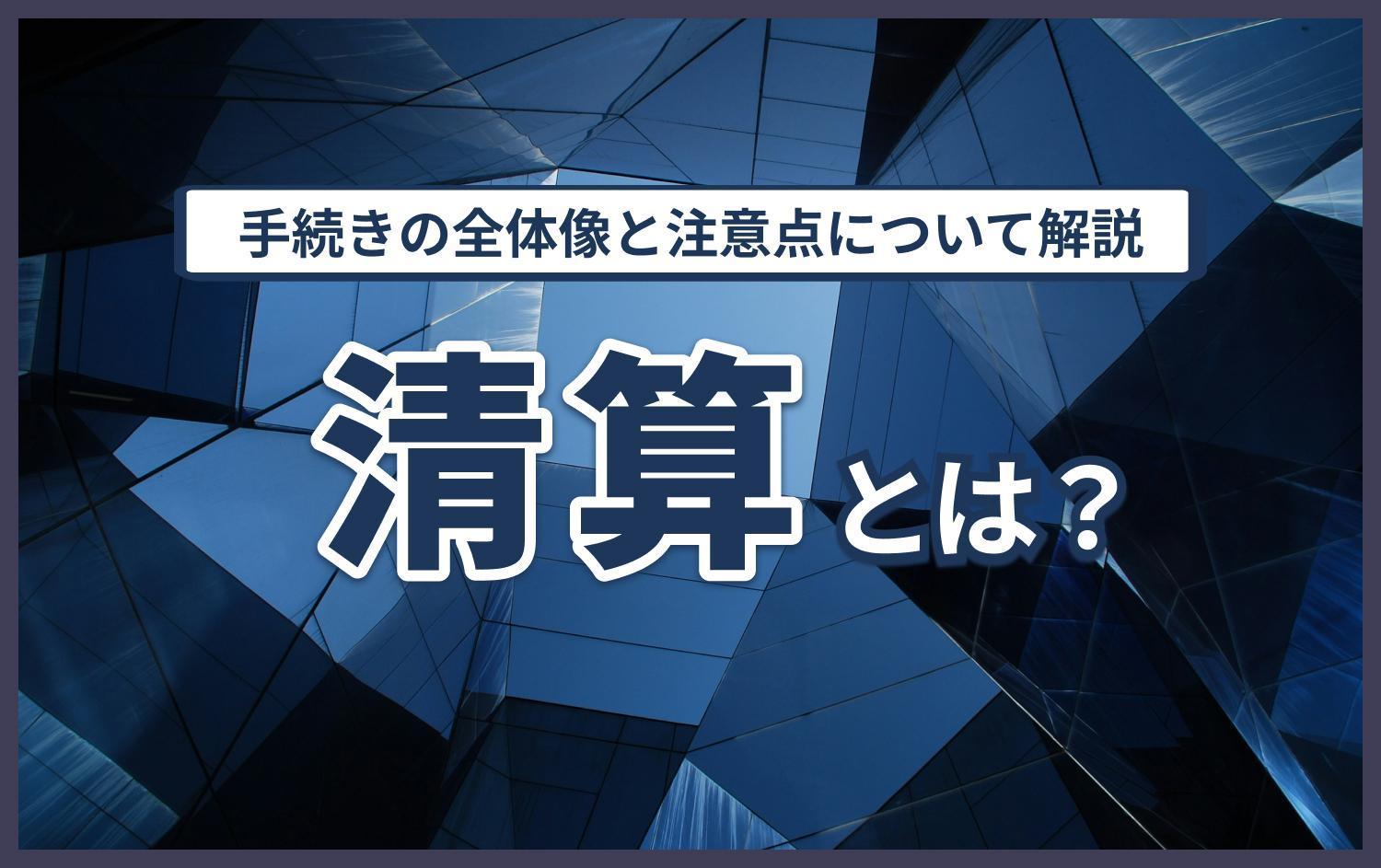
後継者不在に悩む中小企業の経営者の皆様、事業を円滑に終了させる方法についてお悩みではありませんか?長年築いてきた会社を整理し、新たな人生の一歩を踏み出すには、清算のプロセスを正しく理解することが欠かせません。
本記事では、会社清算の基本的な仕組みから具体的な手続き、注意すべきポイントまでを分かりやすく解説します。清算を前向きに捉え、新たなスタートに向けて一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。
目次
清算には、任意清算と法定清算がある
会社の清算には、任意清算と法定清算の2種類があります。任意清算は、会社の意思で自発的に行われる清算で、手続きの多くを会社側の裁量で進められるのが特徴です。一方、法定清算は、会社法上の事由により義務的に行われる清算です。
法定清算はさらに、「通常清算」と「特別清算」に分けられます。通常清算は、会社法に定められた一般的な清算手続きで、清算人が裁判所の監督の下で清算事務を行います。通常清算は、会社の存続期間の満了、定款で定めた解散事由の発生、株主総会の決議、破産手続開始の決定などを原因として行われます。
他方、特別清算は、通常清算よりも公的色彩が強い清算手続きです。特別清算は、会社の財産が債務の弁済に不足する場合に、裁判所の開始決定により行われます。裁判所が選任した清算人が、裁判所の監督の下で公平かつ慎重に清算事務を行うのが特徴です。特別清算では、債権者の権利保護のため、より厳格な手続きが求められます。
任意清算は、事業を計画的に終了させ、円滑に法人を解散させたい場合に適しています。債務を上回る資産がある場合や、関係者の同意を得られる場合は、任意清算を選択するのが一般的です。他方、法定清算は、会社法上の事由により義務的に行われる清算で、通常清算と特別清算に分かれます。このうち特別清算は、債務超過の場合に行われる、より厳格な清算手続きといえます。
法定清算(通常清算)の手続き
法定清算の中でも、一般的な通常清算の手続きについて説明します。
清算開始の原因発生
清算事由(会社の存続期間の満了、定款で定めた解散事由の発生、株主総会の決議、破産手続開始の決定など)が発生します。
清算人の選任
清算が開始されると、清算人が選任されます。清算人は、清算手続きを行う者で、会社の代表機関となります。通常は、取締役が清算人を兼任します。これは、取締役が会社の業務に精通しており、清算手続きを円滑に進められると考えられるからです。ただし、定款で清算人について別段の定めがある場合や、株主総会の決議で他の者を清算人に選任した場合は、取締役以外の者が清算人になることもあります。
清算開始の登記
清算人が選任されると、清算人は清算開始の登記を行います。登記事項には、清算人の氏名及び住所、清算開始の年月日などが含まれます。この登記により、会社が清算手続き中であることが公示されます。清算開始の登記は、清算人の就任後、遅滞なく行わなければなりません。登記申請書には、清算人の就任を証する書面や、清算事由の発生を証する書面などを添付する必要があります。
債権者に対する公告及び催告
清算開始の登記後、清算人は債権者に対する公告と催告を行います。公告は、官報に掲載する方法で行います。公告には、債権者に対して一定の期間内に債権を申し出るべき旨を記載します。この期間は、2か月以上でなければなりません。また、清算人は知れている債権者に対して、個別に催告を行います。催告書には、債権の申出期間を記載し、期間内に申出がない場合は、債権が切捨てられる旨を記載します。
債務の弁済等
債権の申出期間が経過すると、清算人は債務の弁済等の処理を行います。まず、清算人は申し出のあった債権の存否や金額を調査します。債権が確定した後、清算人は債権者に対して弁済を行います。会社の財産で債務の全額を弁済できない場合は、債務の一部を弁済し、残りの債務については債権者の同意を得て、債務の引受けや供託等の処理を行います。
残余財産の分配
債務の弁済が終了し、会社に残余財産がある場合は、清算人はその残余財産を株主に分配します。分配は、株主の持分に応じて行います。残余財産の分配は、債務の弁済後、遅滞なく行わなければなりません。分配の方法は、金銭の交付によるのが一般的ですが、現物の分配も可能です。
清算結了の登記
残余財産の分配が終了し、清算事務が完了したときは、清算人は清算結了の登記を行います。登記申請書には、残余財産の分配が完了したことを証する書面などを添付する必要があります。清算結了の登記により、会社は消滅します。
通常清算でかかる費用内訳と相場
通常清算を行う際には、様々な費用が発生します。以下に、主な費用の内訳と相場を説明します。
清算人の報酬
清算人の報酬は、清算業務の複雑さや清算人の職責に応じて決定されます。報酬額は会社の規模や清算手続きの難易度によって異なりますが、一般的には数十万円から数百万円の範囲が相場です。
登記費用
清算開始時と清算結了時の登記に関する費用が発生します。
登記費用は、登録免許税(資本金の0.7%または6万円のどちらか高い方)と謄本取得費用(数千円)が主な内訳です。資本金が1,000万円の会社の場合、登記費用は約7万円程度が相場です。
官報公告費用
債権者に対する公告を官報に掲載する費用が発生します。官報公告費用は、文字数に応じて計算されます。1回の公告で約5万円から10万円程度が相場です。
債権者への通知費用
債権者に対して、個別に催告書を送付する費用が発生します。通知費用は、郵送料と事務手数料が主な内訳です。
弁護士・公認会計士等の専門家報酬
清算手続きには法律的・会計的な専門知識が必要とされるため、弁護士や公認会計士等の専門家に依頼することが一般的です。専門家報酬は、業務内容や事案の難易度によって異なります。弁護士報酬は着手金と成功報酬を合わせて数十万円から数百万円、公認会計士報酬は数十万円から数百万円程度が相場です。
その他の諸経費
清算事務を進める上で必要な諸経費(通信費、交通費、事務用品費など)が発生します。
これらの諸経費は、会社の規模や清算手続きの複雑さによって異なりますが、数万円から数十万円程度が相場です。
以上が、通常清算でかかる主な費用の内訳と相場です。総費用は、会社の規模や清算手続きの難易度によって大きく異なりますが、小規模な会社の場合で数百万円程度が相場になります。
任意清算の手続きの全体像
任意清算のプロセスは、一見複雑そうに見えますが、段階的に進めていくことで、スムーズに完了することができます。以下に、主な手続きの流れを説明します。
1.営業活動の終了
まず、会社の事業活動を停止し、営業活動を終了します。在庫品の処分や設備の売却など、資産の整理を進めていきます。在庫品は、販売先を探すか、廃棄処分を検討します。
販売する場合は、価格設定に注意し、できるだけ高値で売却できるよう交渉しましょう。設備売却の際は、買取業者の選定や価格交渉が重要です。
複数の業者から見積もりを取り、条件を比較検討することをおすすめします。
2.取引先への報告
取引先に対して、会社の清算を行うことを報告します。債権者には、債務の弁済についての通知を行います。報告の際は、書面で行うことが望ましいでしょう。
取引先の担当者に直接連絡を取り、清算の理由と今後の見通しについて丁寧に説明します。
債権者への通知は、債権額や弁済方法を明記した書面を送付します。あわせて、債権者集会の開催予定についても伝えておくと良いでしょう。
3.株主総会での解散決議
株主総会を開催し、会社解散の決議を行います。あわせて、清算人を選任し、清算手続きを委任します。株主総会の招集通知は、法定の期限までに発送します。決議に必要な定足数や議決権数を確認し、円滑に総会が進行できるよう準備しましょう。解散決議の議事録は、正確に作成し、適切に保管することが求められます。
4.法務局での解散登記
清算人は、解散の登記を法務局に申請します。これにより、会社は清算手続きに入ったことが公示されます。解散登記の申請には、解散決議議事録や清算人の就任承諾書など、必要書類を揃える必要があります。登記申請から完了までには、通常2週間ほどかかります。登記にかかる費用は、収入印紙代や登録免許税などがあります。
5.税務申告
清算事務所を設置し、債権債務の整理、財産目録・貸借対照表の作成、清算所得の申告など、必要な税務手続きを進めます。清算事務所は、通常、会社の本店所在地に置きます。事務所の運営は、清算人が行うことになります。財産目録や貸借対照表は、会社の資産・負債の状況を正確に反映するよう作成します。清算所得は、清算中の収支を基に計算し、法人税の申告を行います。
6.債権者集会の開催
官報に公告し、債権者集会を開催します。債権者からの債権申告を受け付け、弁済すべき債務を確定させます。官報公告は、債権者集会の開催日の1か月以上前に行います。
公告には、集会の日時、場所、債権申告の方法などを記載します。債権申告は、集会当日に会場で受け付けるほか、事前に書面で受け付けることもできます。申告のあった債権は、内容を精査し、弁済額を確定させていきます。
7.残余財産の分配
債務の弁済が完了した後、残余財産を株主に分配します。分配が完了したら、清算結了の登記を行い、会社は消滅します。残余財産の分配額は、株主の出資比率に応じて計算します。分配の実施に当たっては、株主総会の決議が必要です。分配完了後は、清算結了の登記を法務局に申請します。登記が完了した時点で、会社は法的に消滅します。
任意清算手続きにかかる費用

清算手続きには、様々な費用がかかります。主なものは以下の通りです。
登録免許税
清算に関する登記(解散登記、清算結了登記など)を行う際に、登録免許税が課されます。税額は、資本金の額や登記の種類によって異なります。例えば、解散登記の場合、資本金額が1,000万円以下の会社であれば、3万円の税額となります。
官報公告費用
債権者集会の開催に先立ち、官報に公告を掲載する必要があります。公告には、一定の費用がかかります。費用は、公告の文字数や掲載回数によって異なりますが、通常は数万円程度です。
その他の諸費用
清算事務所の運営費用、書類の作成・発送費用、債権者への支払いにかかる振込手数料など、様々な経費が発生します。これらの費用は、会社の規模や債権者の数などによって異なりますが、総額で数十万円から数百万円程度になることもあります。
専門家への依頼費用
清算手続きは複雑で、専門的な知識が必要とされるため、弁護士や公認会計士などの専門家に依頼することが一般的です。専門家への報酬は、事案の難易度や業務量によって異なりますが、数十万円から数百万円程度が相場といえるでしょう。
清算にかかる費用は、会社の状況によって大きく異なります。事前に想定される費用を見積もり、十分な資金を確保しておくことが重要です。
清算業務を円滑に進めるためのヒント
清算業務を円滑に進めるには、入念な準備と、関係者との緊密な連携が欠かせません。まずは、全体のスケジュールを立て、優先順位を決めましょう。各タスクに期限を設定し、定期的に進捗状況を確認します。必要な書類や資料は早めに収集し、整理しておくことが重要です。
また、弁護士や税理士など、専門家のアドバイスを適宜取り入れることも有効です。専門家の選定に当たっては、清算業務の経験が豊富で、中小企業の実情に詳しい人材を探すと良いでしょう。顧問先などにも相談してみてください。
清算における会計と税務における注意点
清算中の会計処理では、通常の決算とは異なる点がいくつかあります。例えば、資産の評価替えや、清算所得の計算などです。資産の評価替えは、売却予定価額や処分見込額を基に行います。債権の取立不能見込額は、損失として計上します。清算所得は、清算中の収支を基に算出します。この際、清算所得に対する法人税の申告と納付が必要です。
また、清算に伴う消費税の申告や、地方税の清算なども忘れずに行いましょう。税務署による清算関係の調査に備え、帳簿書類や証憑類は整理し、適切に保管しておくことが大切です。必要に応じて、税理士など専門家の助言を求めることをおすすめします。
清算中には、様々な税務・財務上の課題に直面します。例えば、法人住民税の取り扱いや、未払いの借金・税金の処理などが挙げられます。
法人住民税は、清算決算時に精算する必要があります。
税率や計算方法は自治体によって異なるため、所管の税務署に確認しましょう。未払いの借金がある場合は、債権者との交渉を通じて、弁済方法を決めていきます。
返済のための原資が不足する場合は、債務免除や減額を申し入れることも検討しましょう。未払いの税金については、税務署と相談の上、分割納付などの対応を探ります。
これらの課題に対応するには、税務署や都道府県税事務所、市区町村の窓口に相談するのが有効です。経験豊富な担当者から、前向きなアドバイスを得ることができるでしょう。
必要に応じて、税理士など専門家のサポートを受けることも検討してみてください。顧問の税理士や、中小企業診断士などに相談するのも良いかもしれません。
清算手続きで直面するリスクとその回避
清算手続きにおいては、いくつかのリスクが潜んでいます。例えば、資産の隠匿や、貸借対照表の不正記載などが発覚した場合、法的責任を問われるおそれがあります。
違法な資産の隠匿は、詐欺罪や背任罪に問われる可能性があります。また、財務諸表の改ざんは、虚偽記載として処罰の対象となります。
これらのリスクを回避するためには、透明性の高い手続きを心がけることが大切です。株主や債権者への適切な情報開示、公正な債務弁済などを通じて、清算プロセスの信頼性を高めていきましょう。
清算人には、誠実かつ公正な職務遂行が求められます。利害関係者との癒着には十分注意しましょう。すべてのステークホルダーに対して、平等かつ公平な対応を心がけることが重要です。
内部統制の仕組みを整備し、不正の芽を摘むことも有効です。会計処理や資金の流れを可視化し、けん制機能を働かせましょう。必要に応じて外部の専門家による監査を受けるのも一案です。リスク管理の徹底は、清算人の重要な責務の一つといえるでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。清算は、決して容易なプロセスではありませんが、正しい手順を踏まえ、適切な支援を受けることで、円滑に進めていくことができます。
清算手続きには、株主総会の開催、法務局への登記、税務申告、債権者への通知など、様々な段階があります。それぞれの手続きに必要な書類を整え、期限を守ることが大切です。
また、清算にはある程度の費用がかかるため、資金面の準備も欠かせません。登録免許税、官報公告費用、専門家への報酬など、主な費用項目を把握し、必要額を確保しておきましょう。
清算人には、公正かつ誠実な業務遂行が求められます。株主や債権者への適切な情報開示、債務の弁済、リスク管理などを通じて、透明性の高い清算プロセスを心がけることが重要です。
専門的な判断が必要な場面では、弁護士や公認会計士など外部の専門家の助言を仰ぐことをおすすめします。
本記事が、円滑な清算の一助となれば幸いです。清算を新たなスタートのチャンスと捉え、前を向いて一歩を踏み出していただければと思います。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。