廃業にかかる税金とは?費用の目安についても解説
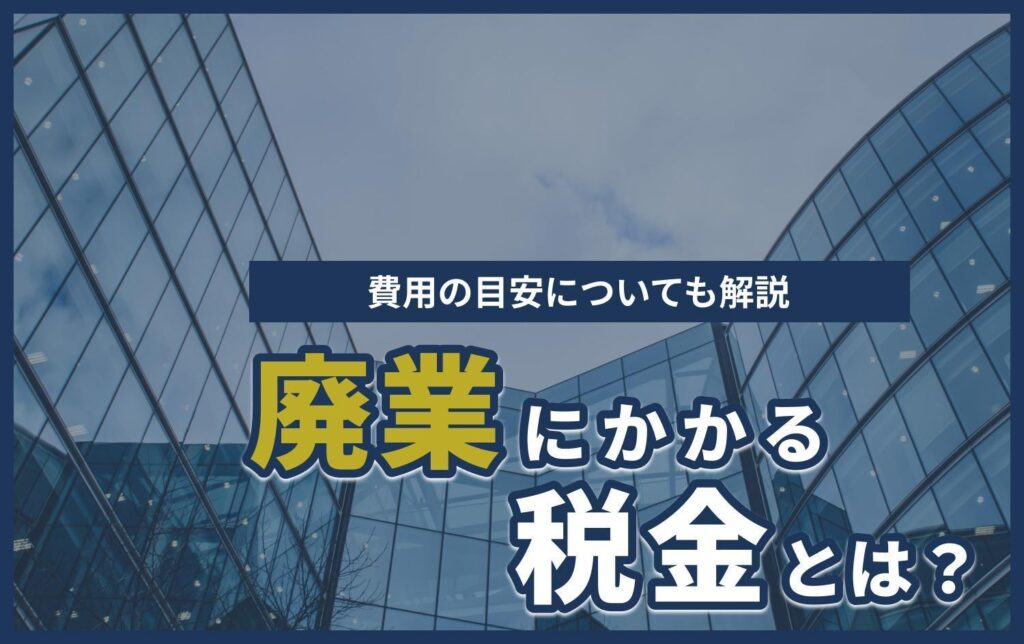
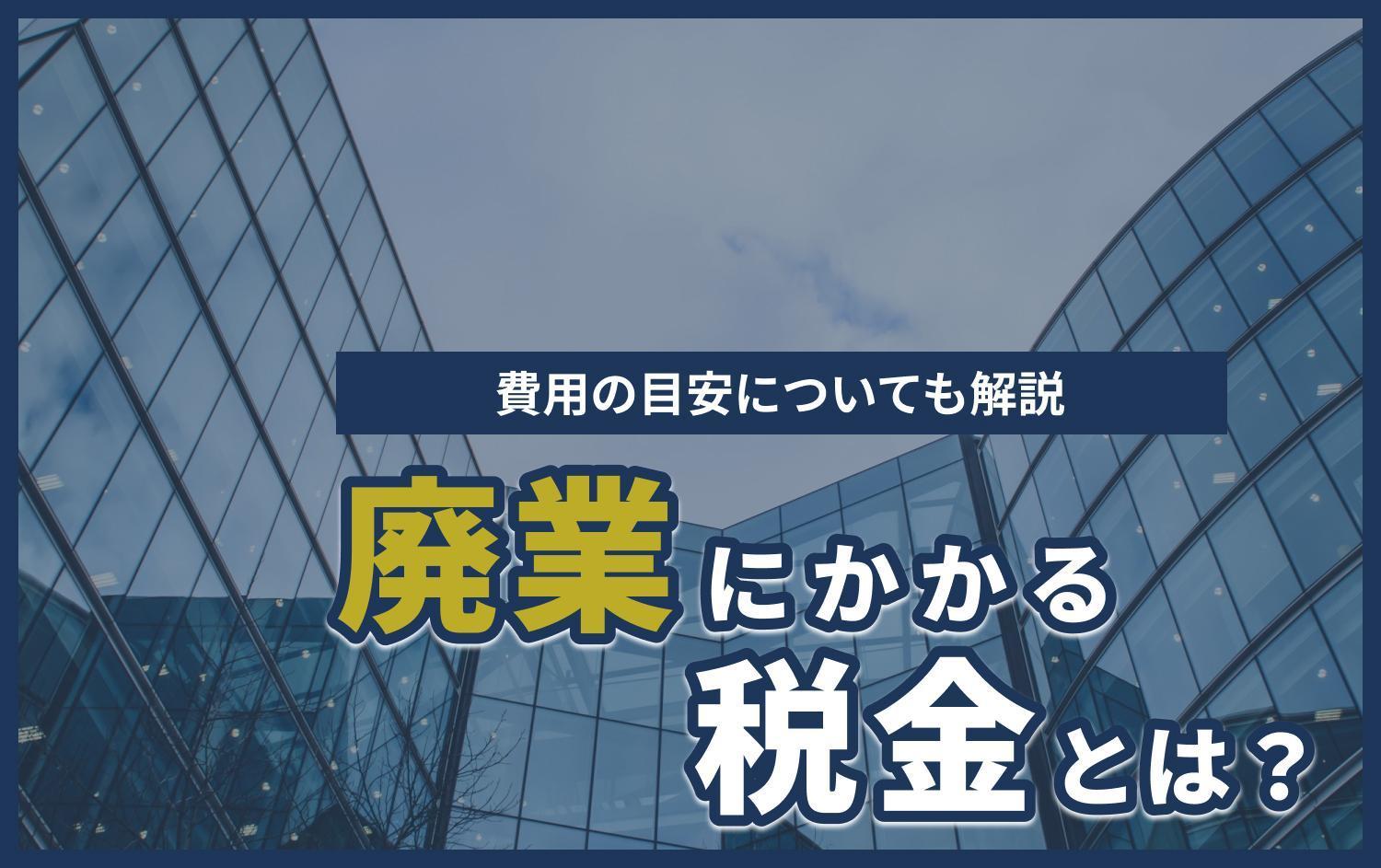
本記事では、会社の廃業にかかる税金と費用について、経営者の皆様の疑問にお答えしていきます。廃業時に必要な税務手続きや、発生する費用の内訳、税理士に相談するメリットなど、押さえておくべきポイントを具体的に解説します。また、状況によっては事業承継という選択肢も視野に入れながら、税制面からのアドバイスもお届けします。
この記事を読むことで、廃業時の税務リスクを最小限に抑えつつ、適正な手続きを円滑に進められるようになるでしょう。
目次
廃業時の税務手続き – 解散事業年度と清算事業年度
会社が廃業する際には、通常の事業年度とは異なる税務手続きが必要になります。大きく分けると、「解散事業年度」と「清算事業年度」の2つの期間に分かれます。
解散事業年度
事業年度の開始日から解散日までの期間を指します。この期間の所得に対して、法人税や消費税などの確定申告を行う必要があります。申告期限は原則として解散日から2ヶ月以内ですので、注意が必要です。
清算事業年度
解散日の翌日から1年ごとに区切られる期間で、清算に係る所得が対象になります。清算事業年度が発生する度に確定申告が必要となり、各事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内が申告期限です。
最後の清算事業年度で残余財産が確定した場合は、残余財産確定日の翌日から1ヶ月以内に確定申告を行います。この申告を「清算確定申告」と呼びます。
ここで覚えておきたいのは、廃業に伴う税務申告は通常の事業年度とは区分して行うという点です。期限も通常の確定申告とは異なりますので、漏れのないようスケジュール管理が大切になります。
廃業にかかる費用の内訳
廃業にはどのくらいの費用がかかるのでしょうか。主な内訳は以下の通りです。
-
- 登記費用:解散登記に3万円、清算人登記に9千円、清算結了登記に2千円の印紙代が必要です。
- 官報公告費用:官報に解散公告を掲載する費用で、1行あたり3,589円(税込)かかります。概ね3〜4万円程度の費用を見込んでおくとよいでしょう。
- 専門家報酬:税理士や司法書士、弁護士などに業務を依頼する場合は、その報酬も発生します。金額は依頼内容によって変わりますが、一連の手続きで50〜100万円程度が目安です。
- その他諸費用:事務手数料、証明書発行手数料、株主総会開催費用など、数万円程度の雑費も見込んでおく必要があります。
このように、廃業には少なくとも40〜50万円程度の費用がかかるのが実情です。予め資金計画を立てておくことが大切ですね。場合によっては、廃業支援制度や金融機関からの融資など、外部の資金調達も検討に値するでしょう。
法的な手続き・登記に関する費用
廃業には、法的な手続きや登記が必要です。具体的には、以下のような手続きが必要となります。
-
- 定款変更(解散事由の追加)
- 臨時株主総会の開催(解散決議)
- 官報への解散公告
- 清算人の選任
- 清算手続き(債権者への通知、債務の弁済など)
- 清算結了の登記
これらの手続きには、司法書士や行政書士への報酬、登記費用、官報掲載料などが必要です。企業の規模にもよりますが、数十万円から数百万円程度の費用がかかるケースが多いようです。
廃業時の法人税
廃業に伴い、法人税の清算が必要になります。具体的には、以下のような税金が発生します。
-
- 清算所得に対する法人税
- 残余財産の分配に対する源泉所得税
清算所得とは、解散から清算結了までの期間に生じた所得のことを指します。資産の売却益や受取利息などが清算所得に含まれます。この清算所得に対して、通常の法人税率での課税が行われます。
また、残余財産を株主に分配する際には、源泉所得税が課税されます。この税金は、清算法人が源泉徴収し、納付する必要があります。
廃業時の消費税
廃業に伴い、消費税の精算も必要となります。具体的には、以下のような手続きが必要です。
-
- 課税期間の短縮届出
- 最終の消費税申告書の提出
廃業日の前日までを課税期間とする短縮届出を提出し、最終の消費税申告を行います。この際、売上げに係る消費税と仕入れに係る消費税の差額を精算することになります。
また、消費税の免税事業者であっても、廃業時には消費税の申告が必要となる場合があります。資産の売却等により、課税事業者となり、申告が必要になるためです。
廃業手続きで税理士に相談するメリット

廃業時の税務は複雑で、専門的な知識が求められます。そこで頼りになるのが、税理士です。廃業手続きを税理士に依頼するメリットは大きく3つあります。
1つ目は、適正な申告と納税が行えること。廃業時の税務は特殊なケースが多く、経験豊富な税理士でないと適切な処理が難しい場面があります。思わぬ税務リスクを避けるためにも、プロの力を借りるのは賢明な選択と言えるでしょう。
2つ目は、事務負担の大幅な軽減が図れること。廃業手続きには膨大な事務作業が伴います。申告書の作成はもちろん、帳簿の整理や各種届出など、税務に関する煩雑な業務を税理士に任せられるのは、経営者の大きな味方になります。
3つ目は、税理士がワンストップで対応してくれること。会社の清算には、税務の他にも法務や会計の知識が欠かせません。税理士法人の中には、司法書士や公認会計士と連携して、トータルでサポートしてくれる事務所もあります。関連業務をまとめて依頼できるのは、経営者の心強い見方になるはずです。
廃業を検討する際は、まず税理士に相談してみるのがおすすめです。初回相談は無料の事務所も多いので、まずは気軽に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
清算人の税務上の責任と注意点
清算人は、廃業手続きの中心的な役割を担う存在です。清算人には、債権の取立てや債務の弁済、残余財産の分配など、会社の財産に関する一切の業務が託されます。同時に、税務上の責任も課せられます。
清算人は、解散事業年度と各清算事業年度の法人税の納税義務を負います。仮に法人税の申告・納税が適正に行われなかった場合、清算人がその責任を問われる可能性があります。
また、清算中に生じた所得について、その帰属時期の判定を適切に行う必要もあります。債権の取立てや資産の譲渡等によって生じた所得は、原則として清算事業年度に帰属しますが、例外もあるので注意が必要です。
加えて、株主への残余財産の分配額は、みなし配当として取り扱われることもあります。個人株主であれば、配当所得として総合課税の対象になる点にも、清算人は注意しておく必要があるでしょう。
このように、清算人は単に財産を整理するだけでなく、税務面の責任も負っていることを認識しておきたいポイントです。自身で処理するのが不安な場合は、税理士など専門家に業務を委ねることも一案と言えます。
廃業か事業承継か – 税制面からの比較検討

社長の高齢化や後継者不在を理由に廃業を検討するケースは少なくありません。しかし、税制面から見ると、廃業よりも事業承継の方が有利なケースもあります。具体的にどのような違いがあるのでしょうか。
まず、廃業の場合、事業用資産を譲渡する際の譲渡益には、原則として法人税が課税されます。含み益のある資産を多く保有している会社では、多額の税負担が生じるケースも考えられます。
これに対し、事業承継では事業用資産を承継先に引き継ぐため、譲渡益課税は発生しません。加えて、事業用資産の贈与や相続に関しては、一定の要件を満たせば税制優遇を受けられる可能性もあります。例えば、非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度などです。
もちろん、事業承継にもデメリットはあります。適切な承継先を見つけるのは容易ではありませんし、株式の評価や契約面での調整にも手間がかかります。それでも、会社の理念や取引関係を次世代に引き継いでいける点は、大きな魅力と言えるでしょう。
廃業か事業承継かは、経営者の事情によって異なります。しかし、税制面のメリット・デメリットを比較検討した上で、判断することが大切です。特に、事業に将来性があるにもかかわらず、安易に廃業を選択するのは、避けたいところです。税理士など専門家の意見を参考にしつつ、会社の未来にとって最善の選択をしていただきたいと思います。
事業用資産の譲渡・評価損益の税務処理
廃業では、事業用資産を譲渡したり、評価損を計上したりすることで、譲渡益や評価損益が発生します。これらは、法人税の課税所得の計算上、重要な要素になります。
譲渡益とは、資産の売却価額が帳簿価額を上回る場合に生じる利益のことです。土地や建物、機械設備など事業用資産の含み益が大きい会社では、多額の譲渡益が発生し、予想外の税負担を招くケースもあります。譲渡益は原則として、その事業年度の所得に算入されます。
一方、評価損は資産の時価が帳簿価額を下回る場合に発生します。土地の含み損などが典型例です。評価損は、一定の要件を満たせば、損金算入が可能です。ただし、資産の評価は適正に行う必要があります。一方的な評価損計上は、税務上のリスクにつながる可能性もあるので注意が必要です。
会社の規模や保有資産の状況によって、譲渡益や評価損益の影響度は大きく変わります。中小企業の経営者にとっては、とりわけ注意すべきポイントと言えるでしょう。適切な税務処理を行うためにも、税理士など専門家のアドバイスを仰ぐことをおすすめします。
個人事業主の廃業と税金 – 消費税の届出、青色申告の取りやめなど
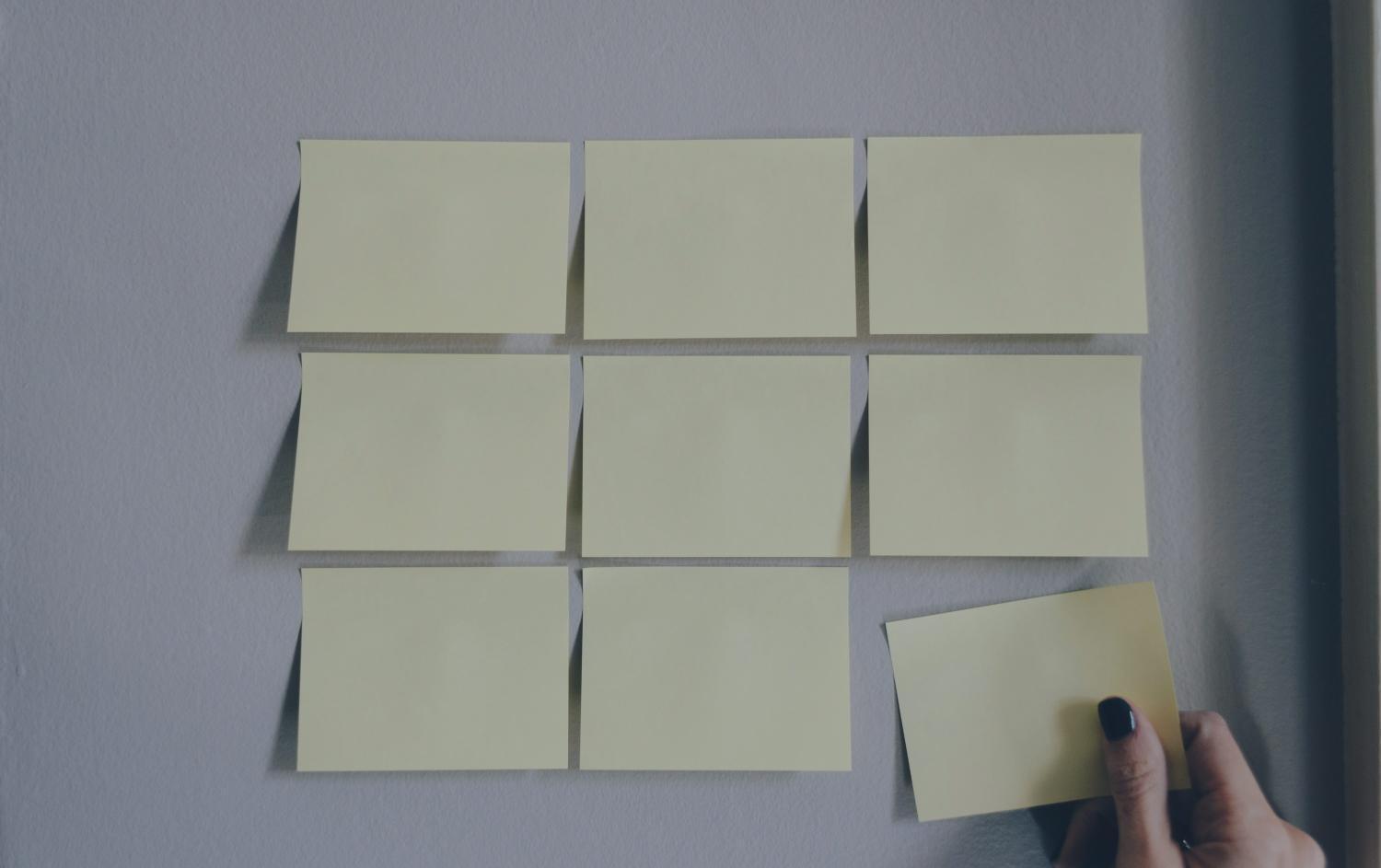
個人事業主が廃業する際にも、いくつかの税務手続きが必要となります。特に注意したいのが、消費税の納税義務です。
消費税の課税事業者であれば、廃業に伴い「事業廃止届出書」を税務署に提出しなければなりません。この届出は、原則として廃業日から30日以内に行う必要があります。
また、所得税の青色申告を行っていた場合は、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」の提出も忘れずに。こちらの提出期限は、廃業した年の翌年3月15日までです。
個人事業主の廃業では法人と異なり、清算手続きは不要です。その分、税務面での手続きはシンプルになります。とはいえ、提出書類の種類や期限を把握しておくことは大切です。漏れのない手続きを行うためにも、チェックリストを作成するなど、体制を整えておくとよいでしょう。
個人事業主の廃業は、法人ほど複雑ではありませんが、後々のトラブルを避けるためにも、きちんとした税務手続きが欠かせません。少しでも不安があれば、税理士など専門家に相談することをおすすめします。
適正な税務処理を行うための廃業手続きのポイント
廃業時の税務処理を適正に行うためには、いくつか押さえておくべきポイントがあります。
まず重要なのが、帳簿書類の整理と保存です。法人税の申告に必要な帳簿書類は、廃業後も一定期間保存しなければなりません。7年間の保存が義務付けられている書類もあるので注意が必要です。適切に整理・保存することで、将来の税務調査にも対応しやすくなります。
次に、債権債務の確認と処理も欠かせません。売掛金や貸付金などの債権は、可能な限り回収に努めましょう。回収不能となったものは、適正に償却する必要があります。一方、買掛金や借入金などの債務は、きちんと弁済することが大切です。残債務を放置したままでは、トラブルのもとにもなりかねません。
さらに、廃業に伴う各種届出も漏れなく行いたいものです。税務署への届出はもちろん、債権者への通知、登記の抹消など、関係各所への手続きは意外と多岐にわたります。リストアップして計画的に進めるとよいでしょう。
これらの手続きを適切に行うためには、正確な情報と書類が不可欠です。日頃から記帳を習慣づけ、証憑書類もきちんと整理・保管しておくことが何より大切だと言えます。
廃業支援制度と税制優遇措置の活用
廃業時の負担を軽減する上で、頼りになるのが各種の支援制度です。国や自治体では、廃業を支援するさまざまな取り組みを行っています。代表的なものが、「中小企業等経営強化法」に基づく支援措置です。
この法律では、事業再編や事業承継を行う中小企業に対し、税制や金融面での優遇措置が用意されています。例えば、事業用資産の買換えや償却資産の引継ぎに係る課税の特例などです。要件を満たせば、譲渡益課税の繰り延べや特別償却などの恩恵を受けられる可能性があります。
加えて、経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務の整理も、大きな後押しになります。ガイドラインの利用で、経営者保証の免除などが実現すれば、経営者の再チャレンジを後押しする効果が期待できるでしょう。
こうした支援制度は、利用できるかどうかで税負担に大きな違いが生じることも。各種支援制度の要件や申請手続きを確認し、うまく活用していくことが重要です。専門家の助言を得ながら、会社の実情に合った方法を探ってみてはいかがでしょうか。
まとめ
本記事では、廃業時の税金と費用について、さまざまな角度から解説してきました。ポイントをまとめると、以下の通りです。
-
- 廃業時の税務は、解散事業年度と清算事業年度の2段階に分かれる。確定申告のスケジュールは通常の事業年度とは異なるので注意。
- 廃業費用の主な内訳は、登記費用、官報公告費用、専門家報酬など。総額40〜50万円程度が目安。
- 廃業手続きは税理士に依頼するのがおすすめ。適正申告や事務負担の軽減、ワンストップ対応などのメリットがあります。
- 清算人は税務上の責任も負う。債権の取立てや資産の譲渡など、帰属時期の判定などに注意が必要。
- 事業用資産の譲渡益や評価損益は、法人税の課税所得の計算上、重要な要素です。適正な処理が求められる。
- 個人事業主の廃業では、消費税の事業廃止届出書や青色申告の取りやめ届出書の提出を忘れずに。
- 中小企業等経営強化法やガイドラインなど、廃業時の負担を軽減する支援制度の活用も検討に値する。
「廃業」は避けては通れない経営課題ですが、税務リスクに備えつつ、適正な手続きを進めることが何より大切です。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。


