赤字続きの対処法:コスト削減からファイナンス戦略まで解説

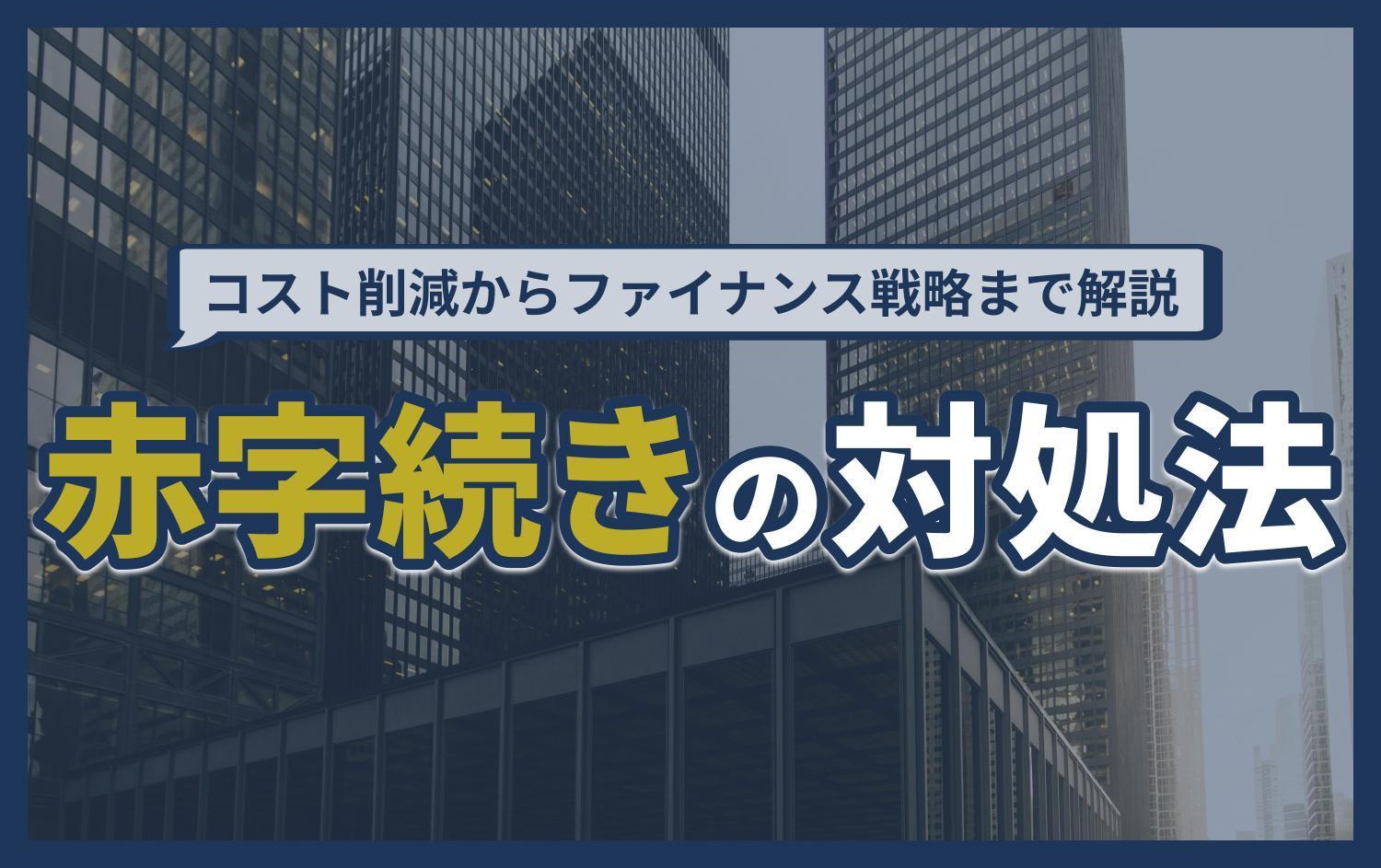
赤字続きで不安を感じていらっしゃいませんか。先行投資を回収できる見込みがある状態の一過性の赤字であれば、さほど問題はないです。
しかし、連続で赤字決算となっている場合は、何かアクションを打たなければいけません。
赤字が続くと、当然ですが手元資金が減少し、資金繰りが困難になります。銀行から融資を受けられなくなったり、返済に追われたりと、経営の自由度がどんどん失われていきます。
それに加えて、従業員のモチベーションが低下し、優秀な社員が離職していくという負のスパイラルに陥りがちです。
しかし、赤字イコール倒産というわけではありません。会社の状況を冷静に分析し、打開策を講じることができれば、V字回復の可能性は十分にあります。
本記事では、赤字続きの企業がどのように事業を回復させるか、その手法について解説していきます。
目次
赤字が続く原因と問題点の特定
赤字脱却への第一歩は、赤字の原因を突き止めることです。売上不振、固定費の高止まり、在庫の滞留など、考えられる要因は様々です。
売上不振の背景には、商品やサービスが市場のニーズに合っていない、価格設定が適切でないといった問題が潜んでいるかもしれません。
固定費の高止まりは、事務所の賃料が割高になっていたり、人件費が売上に見合っていなかったりすることが原因として考えられます。
在庫の滞留も、キャッシュフローを圧迫する要因の一つです。在庫管理が適切に行われていない、不良在庫を抱えているといった点が問題として浮かび上がってくるでしょう。
こうした問題点を洗い出すには、財務諸表や業務プロセスを詳細に分析する必要があります。具体的には、損益計算書を見れば、売上高と費用の推移を把握できます。
売上高が伸び悩んでいる一方で、費用が増加傾向にあれば、コスト管理に問題があることが分かります。
また、貸借対照表からは、在庫の状況や借入金の推移を読み取ることができます。在庫が増加傾向にあれば、在庫管理の甘さが問題だと言えます。借入金が増加し続けているようであれば、収益力の低下が懸念されます。
赤字の原因を多角的に分析し、問題点を特定していくことが重要なのです。原因が明確になれば、打つべき手も自ずと見えてくるはずです。
まずは、事業計画の見直しましょう

赤字脱却のためには、現状の事業計画を見直し、必要に応じて修正を加えていく必要があります。市場環境や競合他社の動向を踏まえながら、自社の強みを生かせる事業領域に経営資源を集中させることが重要です。
例えば、現在の主力事業の市場が縮小傾向にあるのであれば、新たな成長分野への進出を検討すべきでしょう。自社の技術力や営業ネットワークを活用できる分野はないか、探ってみる価値があります。
また、不採算事業からの撤退も選択肢の一つです。事業への愛着があるからと言って、将来性の乏しい事業に資源を投入し続けるのは得策とは言えません。
ただし、事業計画の見直しには慎重さも求められます。安易な方向転換は、かえって混乱を招く恐れがあります。自社の強み・弱みを冷静に分析し、長期的な視点に立って判断することが大切です。
あらゆる角度からコスト削減を検討しましょう
コスト削減は、利益を生み出すための重要な経営施策です。無駄な支出を削り、効率的な運営体制を構築することが、企業の競争力を高めることにつながります。しかし、闇雲にコストを削減しては、かえって業績を悪化させかねません。戦略的な視点を持ち、自社の状況に合った施策を選択することが肝要なのです。
ここでは、人件費、アウトソーシング、オフィス、ツール・通信費、広告宣伝費の5つの領域について、具体的なコスト削減策を見ていきましょう。自社の課題に当てはめながら、検討してみてください。
①採用計画と採用手法を変える
人件費は、中小企業にとって大きな負担となっています。コスト削減の切り札の一つが、採用計画と採用手法の見直しです。
まず、採用計画については、中長期的な視点を持つことが大切です。事業計画と照らし合わせ、本当に必要な人材を見極める必要があります。安易な増員は避け、業務の効率化や自動化も視野に入れながら、最適な人員体制を設計しましょう。
採用手法も工夫の余地があります。従来の媒体広告に加え、SNSやリファラル採用など、多様な手法を活用することで、採用コストを抑えることができるでしょう。また、即戦力となる中途採用だけでなく、新卒採用にも目を向けることで、長期的な人材育成を図ることができます。
人件費の削減は、従業員のモチベーションにも影響します。一方的な削減ではなく、従業員との対話を重ね、理解を得ながら進めることが大切です。
②アウトソーシングを検討する
自社で全ての業務を抱え込むのは、非効率かもしれません。アウトソーシングを活用することで、コスト削減と業務の効率化を図ることができます。
例えば、経理や人事などの間接部門は、アウトソーシングの候補として考えられます。専門性の高い業務を外部に委託することで、人件費を抑えつつ、質の高いサービスを受けられるでしょう。
製造業であれば、一部の工程を外注することも選択肢の一つです。自社の強みを活かせる部分に経営資源を集中し、他社の力を借りることで、効率的な生産体制を構築できるかもしれません。
アウトソーシングを検討する際は、コストメリットだけでなく、サービスの質や情報セキュリティにも注意を払う必要があります。信頼できるパートナーを選ぶことが、アウトソーシング成功のカギを握ります。
③オフィスの縮小
オフィスの維持費用は、意外と見過ごされがちなコスト項目です。オフィス面積の見直しや、拠点の集約化により、大幅なコスト削減が可能となります。
テレワークの浸透により、オフィスに常駐する必要性は低下しています。業務の性質に合わせて、在宅勤務やサテライトオフィスの活用を検討してみてはいかがでしょうか。オフィス面積を減らすことで、賃料や光熱費の削減につなげられます。
拠点の集約化も効果的です。複数の事業所を統合することで、管理コストを削減できるでしょう。ただし、従業員の通勤負担にも配慮が必要です。拠点の立地や、通勤手当の見直しなど、従業員の理解を得ながら進めることが大切です。
オフィスの縮小は、働き方改革の一環としても捉えられます。柔軟な働き方を推進することで、従業員のワークライフバランスを改善し、生産性の向上にもつなげられるでしょう。
④ツール・通信費の見直し
業務で使用するツールや通信サービスは、知らず知らずのうちにコストを押し上げているかもしれません。定期的な見直しが、コスト削減の鍵となります。
例えば、社内で使用しているソフトウェアライセンスは、本当に必要な数だけ購入されているでしょうか。
利用状況を調査し、不要なライセンスを削減することで、コストを抑えられるはずです。クラウドサービスの活用も検討に値します。初期投資を抑えつつ、最新のツールを利用できるメリットがあります。
通信費についても、料金プランの比較や、契約内容の見直しが有効です。複数の通信事業者のプランを比べ、自社に最適なものを選ぶことが大切です。また、固定電話からIP電話への切り替えや、スマートフォンの法人契約への移行なども、コスト削減につながるでしょう。
ツールや通信サービスの選定は、コストだけでなく、利便性や セキュリティ面も考慮する必要があります。業務に支障をきたさないよう、慎重に検討することが求められます。
⑤広告宣伝費の見直し
広告宣伝費は、売上拡大のための重要な投資です。しかし、その効果を検証せずに、漫然と予算を投じていては、コストの無駄につながりかねません。
コスト削減のためには、広告宣伝の ROI(投資対効果)を厳しく評価する必要があります。販促施策ごとに、獲得顧客数や売上高を追跡し、効果の高い施策に予算を集中させることが大切です。
また、デジタルマーケティングの活用も検討に値します。SNSやWebサイトを通じたプロモーションは、従来の広告媒体と比べ、低コストで高い効果を期待できます。ターゲットの絞り込みや、リアルタイムの効果測定が可能なのも大きな利点と言えるでしょう。
一方で、広告宣伝費の削減には注意も必要です。短期的なコスト削減を優先するあまり、ブランド力の低下を招いては本末転倒です。長期的なブランド戦略を見据えながら、バランスの取れた施策を講じることが重要です。
以上、中小企業が取り組むべきコスト削減策を5つの視点から紹介しました。人件費、アウトソーシング、オフィス、ツール・通信費、広告宣伝費。まずはこれらの領域に的を絞り、自社の状況に合った施策を講じることが、コスト削減の近道となるでしょう。
資金調達について検討しましょう

赤字企業にとって、資金調達は死活問題と言っても過言ではありません。運転資金が枯渇すれば、事業の継続そのものが危ぶまれることになります。
資金調達の代表的な手段としては、金融機関からの借入れ、社債の発行、増資などが挙げられます。どの手段を選ぶかは、自社の状況に応じて慎重に判断する必要があります。
金融機関からの借入れは、比較的手軽に資金を調達できるメリットがあります。ただし、赤字企業の場合、融資審査のハードルは高くなります。事業計画の実現可能性を丁寧に説明し、金融機関を納得させることが重要になります。
社債の発行は、投資家から直接資金を調達する方法です。金利負担は借入れよりも重くなりますが、返済期限を長く設定できるメリットがあります。ただし、赤字企業が社債を発行するのは容易ではありません。投資家の信頼を得るには、確かな事業計画と説得力が求められます。
増資は、株主から資金を調達する方法です。金利負担がない点がメリットですが、株式の希薄化が進むデメリットもあります。赤字企業が増資に踏み切るには、将来の成長性を株主に説得する必要があるでしょう。
M&Aも検討しましょう
また、M&A(合併・買収)も選択肢の一つです。自社単独での再建が難しい場合、他社との協業やグループ化によってシナジー効果を生み出し、業績回復を目指すのです。
例えば、競合他社と合併することで、スケールメリットを活かしたコスト削減が期待できます。販売網を共有することで、売上増加も見込めるでしょう。設備や人材の統合により、重複投資を避けることもできます。
ただし、M&Aは高度な専門知識が必要とされる分野です。デューデリジェンス(対象企業の調査)をしっかりと行い、リスクを見極めることが欠かせません。専門家の助言を仰ぎながら、慎重に判断を進めていく必要があります。
赤字続きを解消する組織改革の進め方
赤字脱却のためには、組織全体の意識改革も重要な要素となります。トップの強いリーダーシップのもと、全社一丸となって目標に向かって進んでいく体制を整えなければなりません。
そのためには、経営層と現場の社員との距離を縮め、風通しの良い組織を作ることが大切です。経営者自らが率先して、現場に足を運び、社員の声に耳を傾ける。現場の社員も、経営層に積極的に提案を上げていく。そうした双方向のコミュニケーションが、組織の一体感を生み出すのです。
加えて、社員のモチベーションを高めていくことも忘れてはなりません。赤字が続き、先行きが見えない状況では、社員のやる気が失われがちです。だからこそ、経営者は赤字脱却に向けたビジョンを示し、社員に希望を与えることが重要なのです。
例えば、全社集会で赤字脱却計画を説明し、社員の理解と協力を求める。あるいは、社員との面談を通じて、一人ひとりの想いに寄り添う。こうした経営者の姿勢が、社員のモチベーションを高め、組織の結束力を強めていくのです。
販路拡大と新規事業の検討
業績回復のためには、売上のアップも欠かせません。そのためには、新たな販路の開拓や、新規事業の立ち上げも視野に入れるべきでしょう。
新たな販路を開拓するには、まず自社の強みを改めて見つめ直すことが大切です。自社の商品・サービスは、どのような顧客ニーズに応えているのか。どのような付加価値を提供できるのか。こうした点を整理した上で、ターゲットとなる顧客層を明確にしていくのです。
例えば、既存の顧客との関係をさらに深めていくことで、リピート率を高めていくことができるでしょう。顧客のニーズを丁寧にヒアリングし、課題解決に向けた新たな商品・サービスを提案する。こうした営業活動の積み重ねが、売上アップにつながっていくのです。
一方、新規事業の立ち上げも検討に値します。既存事業の延長線上だけでなく、全く新しい分野に挑戦することで、新たな収益の柱を作り出すことができるかもしれません。
例えば、自社の強みである技術力を活かし、新たな市場を開拓するのも一つの手です。顧客ニーズを探りながら、商品・サービスのラインナップを拡充していく。こうした取り組みが、新たな顧客層の獲得につながっていくでしょう。
ただし、新規事業への参入は、慎重に検討する必要があります。事業の将来性や採算性を十分に見極めなければなりません。自社の強みを活かせる分野を見定め、リスクとリターンのバランスを考えながら、一歩一歩進めていくことが重要です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。赤字脱却への道のりは決して平坦ではありません。しかし、諦めてしまってはいけません。冷静に現状を分析し、打つべき手を着実に実行していく。そうした地道な努力を積み重ねることが、必ずや道を切り拓いていくはずです。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。


