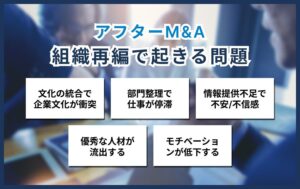M&Aで変わる従業員の未来:経営者が知るべき雇用の知識を徹底解説!
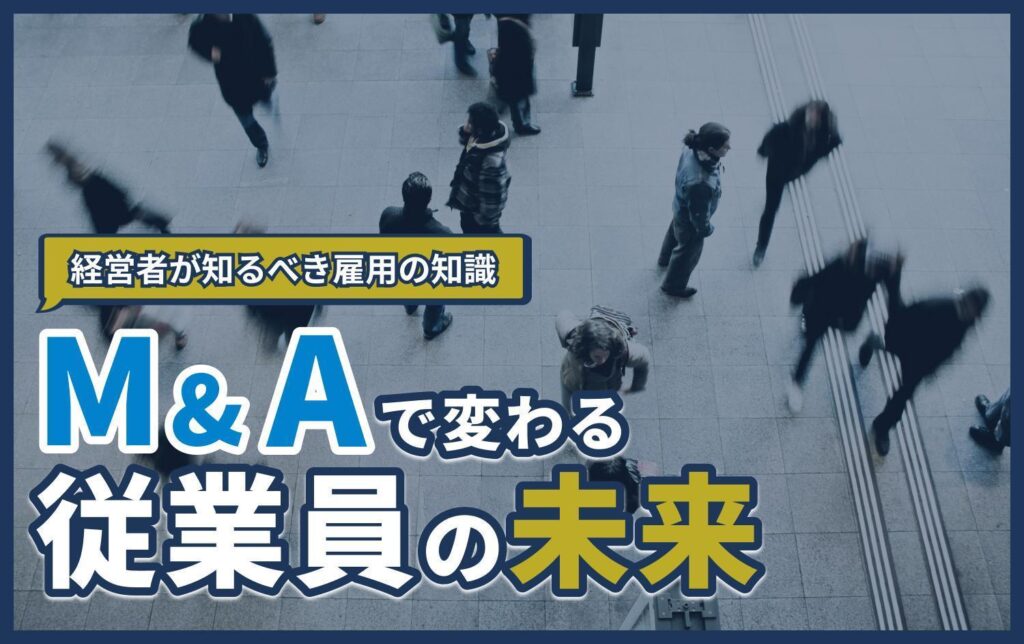
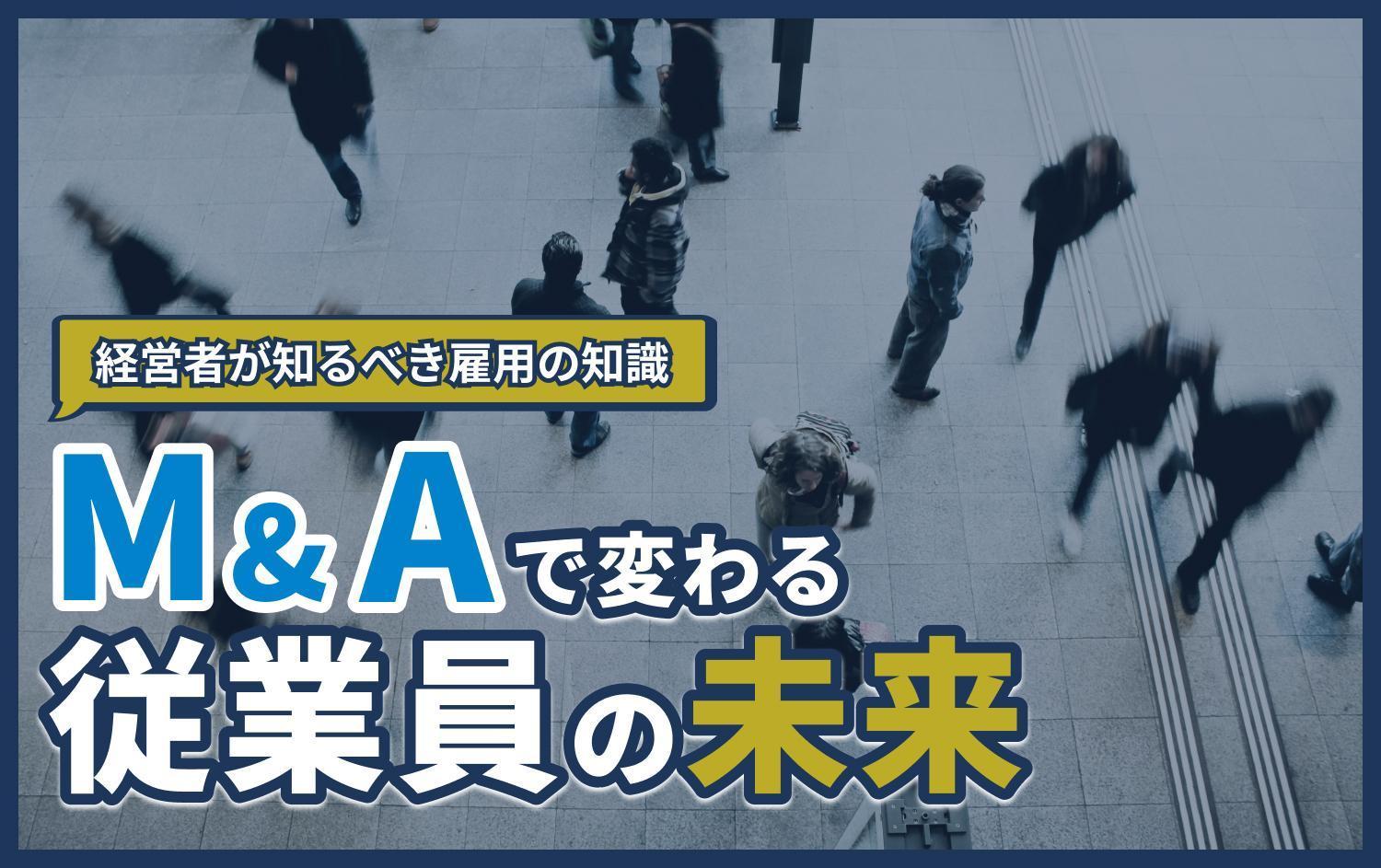
M&Aをご検討の際は、実現した際に従業員に対してどんな影響があるのかを慎重に見ていく必要があります。
M&Aは事業の発展につながる可能性を持っている一方で、従業員にとっては雇用や待遇の変化への不安につながるのも事実です。
特に、事業譲渡の場合は、会社の法人格が変わるため、様々な点で注意が必要です。
本記事では、M&Aを成功に導くためのポイントを、従業員の視点に立って詳しくお伝えします。
目次
M&Aされた時、従業員が気になるポイント
M&Aが決まると、真っ先に従業員の頭をよぎるのが、「リストラの不安」と「給与・待遇の変化」です。
「自分の雇用は守られるのだろうか」「リストラの対象にならないだろうか」という雇用の不安は、誰もが感じるものです。
M&Aの目的が、規模の拡大や業務の効率化にある場合、人員削減の可能性は否定できません。
特に、買い手企業との業務の重複が大きい部門では、リストラが発生するリスクは高まります。子会社化された場合も、親会社の人員削減方針の影響を受ける恐れがあります。
また、「今の給与水準は維持されるのだろうか」「福利厚生はどうなるのだろうか」といった待遇面の変化も、従業員の大きな関心事です。買い手企業の報酬体系に合わせるために、給与や福利厚生が変更されるケースは少なくありません。
年功序列型の賃金体系から、成果主義の賃金体系に変わることもあるでしょう。年収が下がる可能性も否定できません。
加えて、「自分のキャリアはどうなるのだろうか」という将来への不安も拭えません。
今までのキャリアが評価されず、キャリアアップの道が閉ざされるのではないか、と不安を抱く従業員も多いのです。
特に、専門性の高い仕事に従事している従業員は、買い手企業での自分の立ち位置を心配するかもしれません。昇進・昇格の機会が減ることへの不安もあるでしょう。
このように、M&Aは従業員にとって、雇用、給与、キャリア、福利厚生など、働く上でのあらゆる側面に影響を及ぼします。
M&A手法による従業員の雇用契約の違い
M&Aの手法には、大きく分けて「株式譲渡」と「事業譲渡」の2つがありますが、従業員の雇用契約に与える影響は異なります。
株式譲渡の場合
株式譲渡の場合、会社の法人格に変更はないため、従業員の雇用契約は自動的に継承されます。つまり、従業員にとっては、目に見える変化は少ないと言えるでしょう。雇用条件は、原則として譲渡前と同じです。ただし、新しい株主のもとで、経営方針や人事戦略が変わる可能性はあります。
事業譲渡の場合
一方、事業譲渡の場合は、会社の法人格が変わるため、買い手企業との間で新たな雇用契約を結ぶ必要があります。つまり、従業員は、事業譲渡に伴う雇用契約の承継に同意した上で、買い手企業に雇用されることになるのです。この際、雇用条件の変更について、十分な説明と合意のプロセスが求められます。
事業譲渡における従業員の同意は、個別に得る方法と、労働組合との集団的合意により得る方法があります。個別同意の場合、一人ひとりの従業員に対し、丁寧な説明と同意の取り付けが必要です。
他方、労働組合との集団的合意の場合は、組合との誠実な協議を経て、従業員全体の同意を得ることになります。
いずれの方法を採るにせよ、従業員の雇用の安定を最優先に考えることが大切です。雇用契約の承継に不安を感じる従業員に対しては、丁寧にフォローし、理解を得る努力が求められます。特に、事業譲渡の場合は、従業員の納得と同意なくしては、円滑な承継は望めません。
株式譲渡と事業譲渡、それぞれの手法の特徴を理解し、従業員への影響を見極めることが重要です。
特に事業譲渡の場合は、雇用契約の承継に伴う様々な変更点について、従業員に丁寧に説明し、不安を払拭する努力が欠かせません。
M&Aにおける従業員の給与や退職金の扱い
事業譲渡の場合、従業員の給与や退職金の扱いが大きな問題となります。
給与はどうなる?
給与については、買い手企業の報酬体系に合わせるのが一般的です。
もし、買い手企業の給与水準が売り手企業より低ければ、従業員の収入が減ることになります。
年功序列型の賃金体系から、成果主義や職能資格制度に基づく賃金体系に変更されることも考えられます。その場合、評価基準が変わることで、これまでの経験が適切に評価されるかどうか、従業員は不安を感じるでしょう。
管理職手当の減額や、役職定年制の導入など、処遇の変更に伴う不利益も懸念されます。
退職金はどうなる?
退職金の計算方法も、売り手企業と買い手企業の間で決めます。
多くの場合、M&Aの時点で、売り手企業の退職金規程に基づいて計算し、その金額を買い手企業が引き継ぐ形になります。
つまり、従業員は事業譲渡後も、将来の退職時に、譲渡時点までの分の退職金を受け取ることができるのです。
ただし、勤続年数の通算方法や、退職金の支払時期などについては、売り手企業と買い手企業の間で取り決める必要があります。
退職金は従業員にとって、生活の安定に直結する重要な権利です。その取り扱いについては、従業員の納得と同意を得ることが大切です。
企業年金の取り扱いも重要なポイントです。確定給付企業年金や確定拠出年金など、制度の種類によって、引継ぎの方法が異なります。
年金資産の移管や、加入者の同意取得など、必要な手続きを適切に進めなければなりません。企業年金の変更は、従業員の老後の生活設計に大きな影響を及ぼします。
従業員に対して行うべき手続き

M&Aに際しては、適切な情報開示と従業員との対話が何より重要です。特に、事業譲渡の場合は、以下のような手続きが必要となります。
まず、売り手企業は、事業譲渡に伴う雇用契約の承継について、従業員の同意を得なければなりません。個別に同意を得るか、労働組合との協議で包括的に同意を得るかは、状況に応じて判断します。
同意取得の際は、事業譲渡の目的や、譲渡後の雇用条件、給与・退職金の取り扱いなどについて、分かりやすく説明する必要があります。
次に、買い手企業は、譲り受ける従業員と新たな雇用契約を結びます。この際、雇用条件の変更については、十分な説明と同意が必要です。給与体系や勤務地、福利厚生など、変更される可能性のある項目は、丁寧に説明し、従業員の不安を取り除くことが大切です。また、従業員の既得権益についても、可能な限り維持するよう配慮すべきでしょう。
加えて、従業員代表との協議も重要です。事業譲渡に伴う労働条件の変更については、従業員代表との誠実な協議が求められます。協議事項には、雇用の承継、給与・退職金の取り扱い、労働条件の変更内容などが含まれます。従業員代表の意見を真摯に受け止め、合意形成に努めることが大切です。
事業譲渡の場合、従業員との個別面談も欠かせません。承継に伴う処遇の変更点を隠さず伝え、従業員の納得を得ることが大切です。一人ひとりの従業員の不安や疑問に耳を傾け、丁寧に説明することが求められます。個別面談では、雇用の継続性や、キャリアパスの見通しなどについて、具体的に伝えることが重要です。
曖昧な情報は不安を招くだけです。リストラの可能性も含めて、正直に伝えることが重要です。M&Aの目的や将来のビジョンを丁寧に説明し、従業員の理解と協力を求めていくことが求められます。
従業員に対するM&Aの開示・説明タイミング
①従業員にM&Aを開示する最適なタイミングとは
M&Aを従業員に開示するタイミングは、慎重に見極める必要があります。早すぎる開示は、従業員の不安を招き、業務に支障をきたす恐れがあります。一方で、遅すぎる開示は、従業員からの信頼を損ねる可能性があるのです。
開示のタイミングを判断する上で重要なのは、M&Aの進捗状況と従業員に対する影響の大きさです。
例えば、最終契約締結前後のタイミングが適切だと考えられます。この段階では、M&Aの実現可能性が高まっており、従業員への影響も具体的に見えてくるからです。
ただし、M&Aの内容によっては、より早期の開示が求められるケースもあります。事業の一部売却など、従業員への影響が大きい場合は、基本合意書の締結前から、従業員との対話を始める必要があるでしょう。
②従業員への説明により、不安や疑問を解消することが重要である理由
M&Aの開示に際して、従業員への丁寧な説明は欠かせません。単にM&A取引に関する事実を伝えるだけでは、従業員の不安や疑問は解消されません。M&Aの目的や背景、従業員への影響などを詳しく説明し、理解を得ることが重要なのです。
従業員の不安を放置すれば、モチベーションの低下や優秀な人材の流出につながりかねません。特に、中小企業では、従業員一人ひとりの存在が大きく、人材の流出は深刻な問題となります。
丁寧な説明により、従業員の不安を取り除き、前向きな協力を得ることが、M&Aの成功につながるのです。例えば、M&Aにより事業が強化され、従業員の雇用が安定することを伝えれば、従業員も安心して働き続けることができるでしょう。
従業員への説明に際しては、経営者自らが率先して行うことが大切です。トップの姿勢が、従業員の信頼を得るカギとなるのです。また、従業員の質問や意見にも真摯に耳を傾け、対話を重ねることが求められます。
M&Aに否定的な従業員への対処法
M&Aを進める中で、反対する従業員への対応に頭を悩ませる経営者も少なくありません。ここでは、M&Aに反対する従業員への対処法について考えていきます。
①解雇は極めて難しい
M&Aに反対するからといって、簡単に従業員を解雇することはできません。労働契約法には、解雇には合理的な理由が必要であると定められているからです。
M&Aへの反対は、解雇の合理的な理由には当たりません。むしろ、反対意見を理由に解雇すれば、不当解雇として訴えられるリスクが発生します。
解雇を検討する際は、慎重な判断が求められます。客観的な事実に基づき、解雇の正当性を十分に検討する必要があるのです。一方的な解雇は、従業員との紛争を招き、M&Aの障害となりかねません。
②解雇以外の対処法
解雇以外にも、M&Aに反対する従業員への対処法はあります。まずは、丁寧な説明と対話を重ねることが大切です。反対の理由を聞き、誠実に向き合うことで、従業員の理解を得られる可能性があります。
また、反対する従業員の配置転換や職務変更を検討するのも一つの方法です。M&Aの影響を受けない部署への異動や、新たな職務の割り当てにより、反対の理由を解消できるかもしれません。
早期退職優遇制度の活用も選択肢の一つです。M&Aに反対し、会社を去りたいと考える従業員に対し、好条件で退職してもらう方法です。ただし、制度の設計には注意が必要です。不公平感を招かないよう、対象者の選定や条件設定に配慮することが大切です。
M&A後に会社に起こる問題
M&A後、従業員の反応は様々です。新しい経営体制に順応し、意欲的に働く従業員がいる一方で、不安や不満を抱える従業員も少なくありません。
最も深刻なのは、優秀な人材の流出です。キャリアの先行きに不安を感じたり、買い手企業の経営方針に疑問を抱いたりした従業員が、転職を選ぶケースがあります。特に、企業の中核を担う人材の退職は、事業の存続にも関わる大きな痛手となります。
買い手企業との軋轢も、しばしば問題となります。企業文化の違いから、コミュニケーションがうまくいかず、従業員の不満が募ることがあるのです。買収後の組織体制や権限委譲のあり方をめぐって、意見の対立が起きることもあります。
業務プロセスの変更も、従業員のストレスを高める要因です。長年慣れ親しんだ業務の進め方が、買い手企業の方式に合わせて変更されれば、従業員は戸惑うでしょう。IT システムの統合など、業務インフラの変更も、従業員の負担となります。
M&A後は、組織文化の融合も大きな課題です。価値観やワークスタイルの違いから、部門間の連携がうまくいかなくなることもあります。
コミュニケーションの齟齬が、業務の効率性を下げるリスクもあるのです。
こうした様々な変化が、従業員のモチベーションを下げ、生産性の低下を招く恐れがあります。従業員のエンゲージメントを維持・向上させる施策が求められます。
だからこそ、買い手を見つける時に考えるべきポイント M&Aを成功に導くためには、買い手企業の選定が極めて重要です。単に条件の良し悪しだけでなく、以下のような点に注目すべきでしょう。
従業員を守るために確認すべきこと
①企業文化の親和性
まず、企業文化の親和性です。経営理念や価値観が近い企業同士であれば、組織の融合はスムーズに進むはずです。従業員の心理的抵抗も少なくて済みます。
②トップ同士の相性
トップ同士の相性も見逃せません。経営者同士のトップ面談を通じて、人間的な信頼関係が築けるかどうかを確かめましょう。価値観の共有と、円滑なコミュニケーションが期待できる相手が理想的です。
③統合ビジョンの納得感
次に、買い手企業の成長戦略の妥当性です。買収後も事業を拡大し、従業員に活躍の場を提供してくれる企業が望ましいと言えます。
買い手企業のビジョンが、従業員のキャリア形成につながるかどうか、見極める必要があります。
④詳細な意向表明書を求めましょう
最後に、買い手企業に詳細な意向表明書を求めることも一案です。
価格などの条件だけではなく、従業員の処遇や雇用の維持について、どのような方針を持っているのか、明確にしてもらうのです。
曖昧な約束ではなく、書面で確認することで、従業員の不安も和らぐはずです。
M&A後に必要となる人材マネジメント
M&A後の人材マネジメントは、統合の成否を左右する重要な課題です。買収先の従業員のスキルや経験を適切に評価し、モチベーションを高めていくことが求められます。
キーパーソンの選定と登用は、特に慎重に進めるべきでしょう。買収先の中核人材を見極め、ふさわしいポストを与えることが重要です。
単なる役職の踏襲ではなく、実力本位の人材配置を心がける必要があります。
教育研修の充実も欠かせません。統合後の新しい組織で、従業員が力を発揮するには、スキルアップの機会が必要不可欠です。
まとめ
M&Aは、中小企業の成長戦略として大きな意義を持ちますが、従業員への影響は小さくありません。雇用の不安、給与・待遇の変化、キャリアの行方など、従業員の不安に真摯に向き合い、丁寧なコミュニケーションを重ねることが何より重要です。
法的な手続きを適切に進めることは言うまでもありませんが、従業員の心情に配慮した情報開示と対話のプロセスを大切にしたいものです。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。