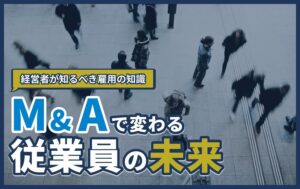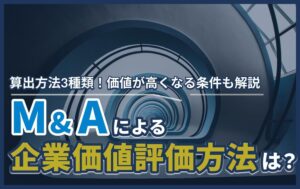M&Aにおける基本合意書(MOU)とは?記載内容、法的拘束力の発生についても


M&Aにおける基本合意書(MOU)は、取引の初期段階で重要な役割を果たします。記載内容や法的拘束力について理解することで、スムーズな取引を進めることが可能となります。本コラムでは、これらの要点を詳しく解説します。
目次
基本合意書とは?
M&Aにおける基本合意書(MOU:MemorandumofUnderstanding)は、取引の初期段階(買い手から意向表明書が提出されて、買い手候補の選定がされて重要な条件などがある程度固まった段階)で作成される重要な文書です。基本合意書は、売り手と買い手が一定時点において取引についての基本的な事項を確認することを明記したもので、取引の進行における大枠の方向性を示します。
基本合意書には、取引の対象となる事業や資産、取引の価格や支払い方法、取引のスケジュール、保証事項、機密保持義務など、取引の基本的な条件が記載されます。これらの内容は具体的な契約書作成の前段階であり、双方の合意に基づいて詳細化されていきます。
また、基本合意書は法的拘束力を持つ場合と持たない場合があり、その違いは文書内の表現や条項によります。法的拘束力がある場合、文書に違反した場合には法的な責任が生じます。
一方、法的拘束力がない場合でも、基本合意書は取引の進行における重要なガイドラインとなります。一部の条項を除いては、法的拘束力を持たないのが一般的です。基本合意書締結後にデューデリジェンスの結果や最終条件交渉時に決裂することにより、最終合意に至らない場合もあるためです。例外的に法的拘束力を持たせる項目として、独占交渉権や秘密保持、裁判所合意管轄などが挙げられます。
このように、基本合意書の作成はM&Aの成功に向けた重要な一歩であり、その管理は適切に行うべきです。また、基本合意書はM&Aのプロセスをスムーズに進め、予期せぬ問題を未然に防ぐための重要な書類となります。
意向表明書や最終契約書との違い
M&Aの交渉過程では基本合意書のほか、意向表明書や最終契約書なども登場します。それぞれの違いはいったいどこにあるのでしょうか。下記にまとめたので、その違いを確認してください。
| 意向表明書 | 基本合意書 | 最終契約書 | |
| 作成する目的・用途 | 買い手の意思表明 | 合意形成を図るため | 最終的な合意を図るため |
| 作成時期 | 交渉開始前 | デューデリジェンスの実施前 | デューデリジェンスの実施後 |
| 法的拘束力 | なし | 一部の条項についてあり | あり |
まず、意向表明書は買い手候補からの意思表明文書は、基本合意書と最終契約書は売り手と買い手候補の合意に基づいた文書です。
また、作成される時期も各文書によって異なります。そのほか法的拘束力の有無もそれぞれ違いがあるため注意が必要です。
基本合意書の作成目的
基本合意書の作成目的は、M&A取引における売り手と買い手間の初期合意を文書化し、両者の意向を明確にすることにあります。基本合意書は、具体的な取引条件やプロセスの枠組みを定義することで、その後の交渉やデューデリジェンス(事前調査)のベースとなります。
基本合意書の主な目的は以下のとおりです。
-
- 取引の意向の明確化
基本合意書により、売り手と買い手は取引に対する共通の理解と意向を文書化し、その後のプロセスに向けた基本的な合意に達します。これには取引対象、目標とするクロージングの時期、概算価格などが含まれます。
-
- プロセスの指針提供
基本合意書は、デューデリジェンスの範囲や最終契約書の主要条項、および必要な承認プロセスなど、取引を進める上でのロードマップとなります。これにより、両当事者はより具体的な計画に基づいて作業を進められます。
-
- 交渉の枠組み設定
基本合意書に記載される条件や期待は、最終契約書への交渉における枠組みとなります。この初期段階での合意は、後続の交渉における指針となり、効率的な合意形成を促進します。
-
- リスク管理
基本合意書には、取引の進行中に発生する可能性のあるリスクを軽減するための条項が含まれることがあります。例えば、独占交渉権の設定や機密保持義務の明確化がこれにあたります。
-
- 関係者への信頼性の向上
基本合意書の締結は、取引が具体的な段階に進んでいることを示し、従業員や株主、および市場に対してポジティブなメッセージを送ります。これにより、関係者の信頼と支持を得やすくなります。
そのほか、スケジュールの明確化や買い手企業のメリットとして独占交渉権の有無などが挙げられます。基本合意書は法的に拘束力がないとされることが多いものの、特定の条項に関しては拘束力を持たせることが可能です。このため、基本合意書作成時には、その内容が将来の紛争の原因とならないように注意しましょう。
基本合意書を締結するタイミング
基本合意書を締結するタイミングは、売り手と買い手間で初期の交渉がある程度進み、双方が取引の基本的な枠組みについて合意に達した時点です。両者の意向が文書化されることで、その後のプロセスに向けた具体的な道筋が設定されます。
正確なタイミングは、取引の複雑さや交渉の進行状況によって異なりますが、双方が取引の基本的な条件について合意できた時点(買い手から意向表明書を入手して重要条件がある程度固まった段階)で検討されるべきでしょう。
基本合意書は原則、法的拘束力が生じる
基本合意書については、一般的には法的拘束力がないとされていますが、実際には一部条項は法的拘束力を持たせています。基本合意書内で特定の条項に拘束力を持たせることが明示されている場合、たとえば機密保持義務や独占交渉権の条項などは、法的に有効とみなされることがあります。
したがって、基本合意書を締結する際は、その内容が将来的な取引にどのような影響を及ぼす可能性があるのか、どの部分が法的に拘束力を持つのかを正確に理解することが重要です。
法定拘束力が認められる条項
基本合意書内で法的拘束力が認められる条項には、機密保持義務や独占交渉期間、違約金、裁判所管轄などがあります。これらの条項は、基本合意書の主体的な取引内容とは別に、両当事者間の一定の行動規範や義務を定めるため、具体的な法的効果を持ちます。
これらの条項が違反された場合、法的措置を取ることが可能になるため、基本合意書作成時にはこれらの条項の表現と範囲に注意が必要です。
法的拘束力が認められない条項
基本合意書内で一般的に法的拘束力が認められない条項には、取引の実行に関する意向の表明や、将来の取引条件に関する条項が含まれます。これらの条項は、取引の意図や期待を示すものであっても、双方に実際の法的義務を生じさせるものではありません。
例えば、将来の取引価格の予測や取引成立の見込み、または特定の取引条件の適用可能性についての記述は最終的な合意に至るまでのあいだ、あくまで目標や期待を示すものに過ぎず、法的な強制力を持たせることは困難です。
また、基本合意書が「合意形成」を目的として作成された文書であるため、その内容が具体的な契約条件として扱われることは稀です。このため、基本合意書に記載されている条項は、両当事者間でさらなる交渉が行われ、最終的な契約書に反映されるまで、原則として拘束力を持たないと考えられます。
基本合意書に記載する内容
基本合意書に記載する内容は以下のものがあります。
-
- 買収金額の概算
- M&Aのスキーム
- スケジュール
- 独占交渉権の付与
- 秘密保持義務の設定
- デューデリジェンスの実施
- 従業員、役員の処遇
- 保証債務の解消等
- 一般条項
それぞれについて、説明していきます。
買収金額の概算
基本合意書に買収金額は、その時点で売り手と買い手が合意している売買価格を記載します。基本的には、純資産価額法やDCF法などで企業価値を算出し、それを基にして売買価格が決められます。
しかし、その後のデューデリジェンス次第では、妥当だと双方が感じるM&Aの価格が変動する可能性があります。あくまでもこの段階での価格は、最終的な取引価格のベースとなります。この金額が最終的な買収価格と異なる可能性があるため、買収金額の概算を記載する際には、その変動性や交渉過程での再評価の余地を明確にすることが不可欠です。
M&Aのスキーム
基本合意書に記載されるM&Aのスキームは、買収が現金交渉によるものか、株式交換によるものか、またはその両方を含むのかといった取引の形態を記載します。さらに、買収対象となる企業の特定の資産や部門のみを対象とするのか、全体の買収なのかという範囲も定義されます。
また、M&Aのスキームでは、取引に関わる重要な中間目標地点や期限、クロージングに至るまでの主要なステップも記載されることが一般的です。この情報により、M&Aプロセスの透明性が高まり、両当事者が取引の流れを明確に理解し、効率的なプロセスの進行が可能となります。
スケジュール
基本合意書に記載されるスケジュールは、M&A取引が進行するうえでの重要なタイムラインを定めます。この部分では、初期の交渉開始から最終的な契約締結、クロージングまでの主要なステップと、それらを完了すべき目標日が明記されることが一般的です。
具体的には、デューデリジェンスの開始と終了日、契約書の最終案の提出期限、取引完了の目標日などがスケジュールに含まれます。このスケジュールは、取引の進行に関わるすべての当事者に明確な期待を設定し、効率的な取引進行を促進するためのガイドラインとなります。
独占交渉権の付与
独占交渉権の付与は、M&A取引において買い手に対して一定期間、売り手が他の潜在的な買い手との交渉を行わないことを保証するものです。この条項により、買い手はデューデリジェンスを含む必要な評価や交渉を、競合する買い手の干渉を受けることなく進められます。
独占交渉権は通常、特定の期間(例えば、数週間から数か月)にわたり設定されます。偏に独占交渉権といっても売り手が買い手候補にアプローチすることを禁止するのか、ほかの企業がアプローチしてきた場合に断る義務まで課すのか、など細かな違いがあります。また、独占交渉権は法的拘束力を持つため、違反した場合は損害賠償責任を負う可能性があります。
秘密保持義務の設定
基本合意書における秘密保持義務の設定は、M&A取引において極めて重要です。この条項は、取引の詳細や交渉中に共有される機密情報が第三者に漏洩することを防ぐためのものです。秘密保持義務は、取引に関わるすべての当事者が、取引の存在や内容、関連する財務情報や戦略に関する情報を含め、共有された情報を厳格に管理し、無断で外部に公開しないことを保証します。
また、この義務は、もし取引が完了しなかった場合にも継続し、特定の期間後に解除されることが一般的です。秘密保持義務は法的拘束力を持つため、違反した場合は損害賠償責任を負う可能性があります。
デューデリジェンスの実施
デューデリジェンスは、M&Aの基本合意書締結後に実施されます。これは、対象会社の実態やリスクを詳細に把握するための調査で、買い手企業が公認会計士、弁護士や税理士などの専門家に委託しておこないます。
デューデリジェンスを行うためには、買い手企業は多くの費用と時間を投じることになります。そのため基本合意書では、売り手企業がデューデリジェンスに協力することが規定されます。そして、デューデリジェンスの結果にもとづいて最終的な取引条件が決定されます。
従業員、役員の処遇
基本合意書では、M&A後の従業員や役員の待遇について記載することが一般的です。これには、給与や退職金、役職などの労働条件が含まれます。買収後の待遇は、買収側企業の人事制度や給与制度にもとづきます。しかし厳密な査定の結果、一部の従業員の待遇が下がる可能性もあります。
また、会社売却方法が事業譲渡の場合は、従業員は買収側企業に新たに入社するのが通常です。その際、それまでの勤続年数はリセットされてしまいます。これを避けるためには、従業員が買収側企業と雇用契約を結ぶ際に、会社売却側の退職金規程(勤続年数)を引継いでくれるように交渉するしかありません。
保証債務の解消等
個人保証・担保提供の解消などに関する記載は、M&A取引の安全性を確保する上で欠かせない要素です。ここでは、売り手が取引完了前に解消すべき負債や保証債務について詳細に定義されます。保証債務の解消には、既存の貸借契約に基づく債務の清算や第三者への保証の終了、または不動産や設備に関連する担保権の解除などが含まれる場合があります。
このプロセスを通じて、買い手は取得する企業が不必要な負債を抱えていないこと、また取引によって想定外の負担が発生しないことを保証されます。
一般条項
基本合意書に含まれる一般条項は、文書の解釈や実行に関わる基本的な規則や条件を設定するために重要です。これには契約の変更や終了の条件や通知方法、適用法、紛争解決の手法などが含まれます。
また、一般条項では、合意書の全体的な有効性に影響を与える可能性のある特定の条項が無効となった場合の取り扱いについても、規定されることがあります。これにより、一部の条項が法的に無効であると判断された場合でも、合意書の残りの部分が有効であることを保証する「分離可能性」の原則が確立されます。
基本合意書の省略は可能なのか?
ではM&Aにおいてこの基本合意書の省略、つまり作成しないことは可能なのでしょうか。結論としては、省略はするべきでありません。省略するべきでない理由とともに説明します。
結論、省略はするべきでない
M&Aにおける基本合意書は、原則として省略すべきではありません。基本合意書は、売り手と買い手がM&Aの基本的な条件について合意するための重要な文書です。その中にはM&Aにおいて重要であり、かつ法的拘束力を持つ条項(例えば、独占交渉権や秘密保持義務)が含まれます。
基本合意書を省略すると、あとから見落としが発覚するなどトラブルの原因になりかねます。また、基本合意書がない場合、買い手はデューデリジェンス(買収監査)を始める前に、売り手との間で独占交渉権や秘密保持義務についての合意がないため、交渉が円滑に進まない可能性があります。
省略するべきでない理由
M&Aにおける基本合意書を省略すべきではない理由は、「独占交渉権」の付与と「秘密保持義務」にあります。これらはM&Aの成功にとって重要な要素であり、基本合意書がないとこれらの要素が確保できません。したがって、M&Aの成功を確実にするためには、基本合意書の締結が必要であり、その省略は適切ではありません。
独占交渉権
基本合意書に独占交渉権を設定することは、M&A取引において非常に重要です。この権利が保証されることで、買い手は限定された期間内でほかの競合する買い手との交渉なしに、売り手との間で取引の詳細について集中して話し合えます。独占交渉権の設定は買い手に安心を与え、必要なデューデリジェンスを行い、取引条件を精査するため欠かせません。
また、売り手側にとっても、交渉プロセスを一定の期間内に集中させることで、取引を迅速かつ効率的に進めることが可能となります。基本合意書を省略すると、このような独占交渉の機会が失われ、結果として取引が不利になる可能性があります。したがって、取引の公正性と効率性を保証するためにも、基本合意書の締結をおろそかにするべきではありません。
秘密保持義務
基本合意書における秘密保持義務は、M&A取引において極めて重要な役割を果たします。この義務は、交渉過程で共有される機密情報が外部に漏れることを防ぎ、取引に関わる双方の企業の利益を保護します。具体的には財務状況、ビジネス戦略や技術的なノウハウなど、競合他社に知られた場合に不利益を被る可能性のある情報が含まれます。
基本合意書を省略することは、このような機密情報の保護を欠くことにつながり、取引の安全性や成功の可能性を損なうリスクを伴います。したがって、取引の透明性と双方の利益を守るためにも、秘密保持義務を含む基本合意書の締結は省略すべきではありません。
まとめ
M&Aにおける基本合意書は、売り手と買い手が基本的な条件について合意する重要な文書です。その一部には、法的拘束力を持つ独占交渉権や秘密保持義務などの重要な要素を含みます。そのため、基本合意書の省略は適切ではありません。基本合意書を確実に作成することが、M&Aの成功につながります。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。