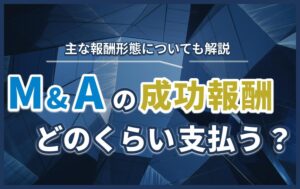M&Aの最終契約書(DA)とは?他の契約書との違いについて解説
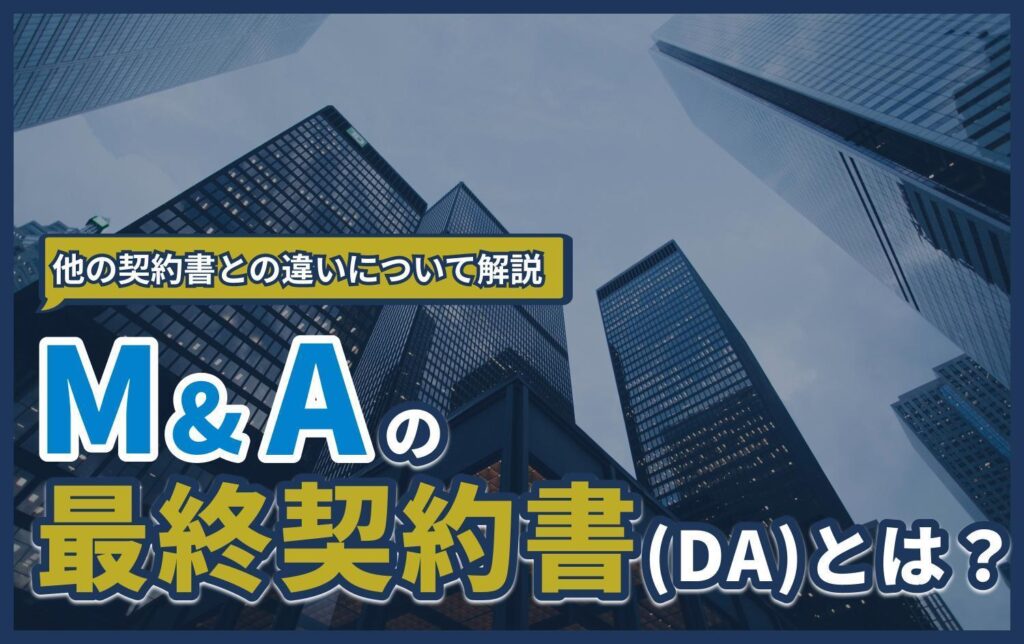
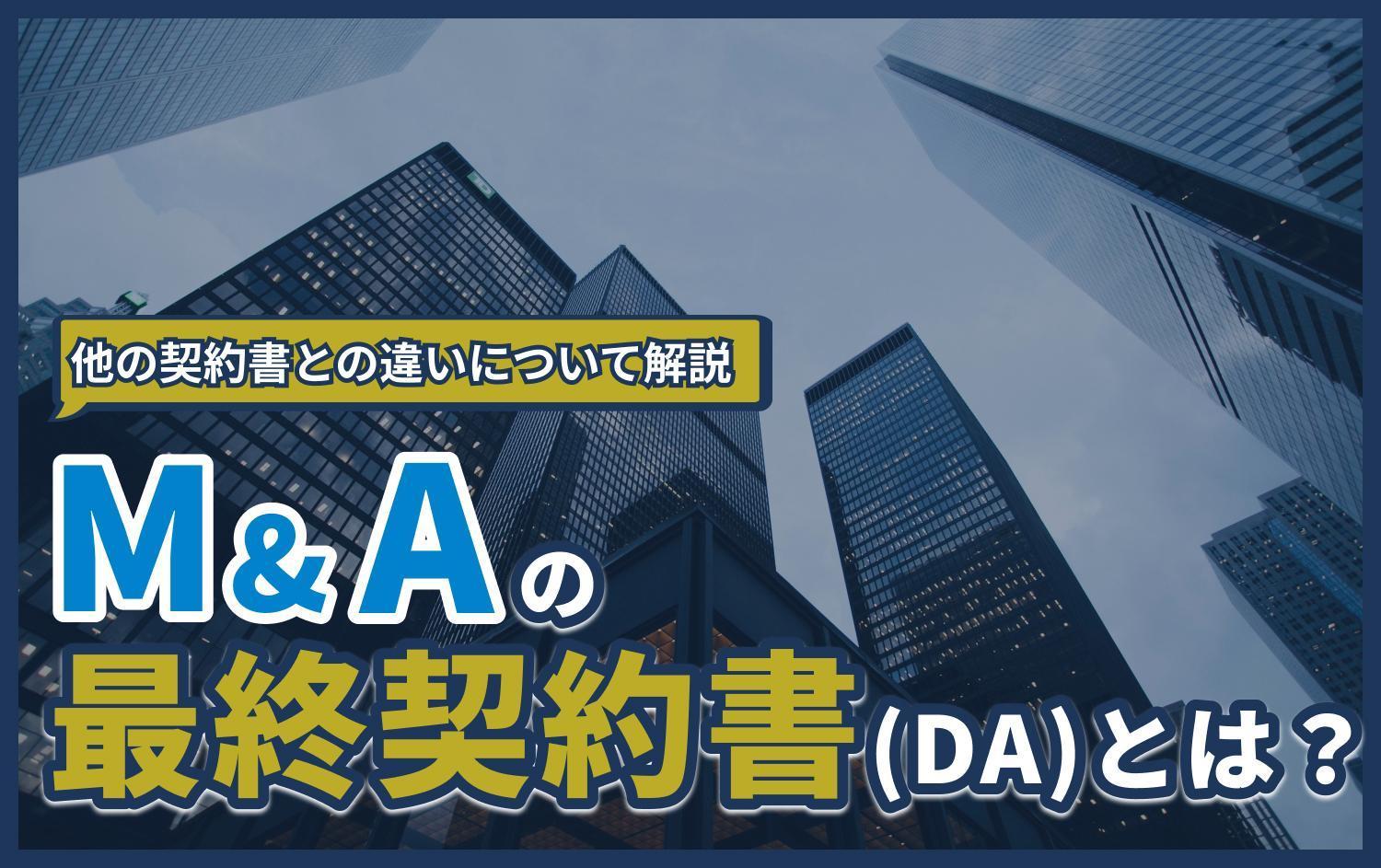
中小企業の経営者の皆様、事業承継や会社売却について悩まれていませんか?特に後継者不在の場合、M&Aによる事業引継ぎが有効な選択肢の一つです。M&Aを通じて、事業の継続、雇用の維持、経営資源の有効活用などのメリットを享受できます。しかし、M&Aプロセスは複雑で、リスクも伴います。
今回は、M&Aの正式成立を意味する最終契約書(DA)に焦点を当て、その概要とDA締結までの流れを詳細に解説します。
M&Aにおける最終契約書(DA)とは
M&A最終契約書(DA: Definitive Agreement)は、買収者と売却者の間で交渉の末に合意された内容を正式に文書化したものです。DAは、M&A取引の諸条件を法的に確定する重要な契約書です。
基本合意書(LOI)や了解覚書(MOU)とは異なり、DAには法的拘束力があります。LOIやMOUは、取引の基本条件を確認するための覚書に過ぎません。法的拘束力はなく、最終的な合意内容ではありません。
一方、DAは正式な契約書であり、M&A取引が成立したことを意味します。
通常、DAは、LOI/MOU締結後のデューデリジェンス(DD)を経て、最終的な交渉を踏まえて作成されます。DDで判明したリスクを反映し、より詳細な内容となります。
DAの締結は、M&Aプロセスの中で最も重要なプロセスの一つです。DAに署名することで、両当事者は取引の実行に法的に成立します。
したがって、DAの内容は慎重に検討する必要があります。
DA(最終契約書)の種類

DAの種類として、株式譲渡契約書、事業譲渡契約書、その他の契約書について解説します。
株式譲渡契約書
株式譲渡契約書を締結することによって、売り手の株式を買い手に譲渡し、経営権を移転します。株式譲渡契約書では、譲渡対象となる株式の種類や数量、譲渡価格、譲渡の時期、譲渡の条件などが詳細に規定されます。
また、株式譲渡契約書には、売り手の表明保証事項や、買い手の表明保証事項が含まれるのが一般的です。売り手の表明保証事項としては、譲渡対象となる株式に瑕疵がないこと、対象会社の財務諸表が適正であること、対象会社に重大な債務や訴訟がないことなどが挙げられます。一方、買い手の表明保証事項としては、買収資金の調達に問題がないこと、買収に必要な社内手続きを完了していることなどが含まれます。
事業譲渡契約書
事業譲渡契約書は、対象会社の事業を丸ごと譲渡する契約書です。事業譲渡の主な特徴は以下の通りです。
事業譲渡契約書では、譲渡対象となる事業の範囲や、譲渡価格、譲渡の時期、譲渡の条件などが詳細に規定されます。譲渡対象となる事業の範囲については、対象会社の全事業を譲渡する場合もあれば、一部の事業のみを譲渡する場合もあります。譲渡価格は、事業の収益力や、資産の価値などを考慮して決定されます。
事業譲渡契約書では、譲渡対象となる資産や負債の範囲についても規定されます。
譲渡対象資産としては、不動産、設備、在庫、知的財産権などが挙げられます。譲渡対象負債としては、事業に関連する債務などが含まれます。これらの資産や負債の範囲については、両当事者の交渉によって決定されます。
また、事業譲渡契約書では、従業員の取り扱いについても規定されるのが一般的です。事業譲渡に伴い、譲渡対象となる事業に従事する従業員は、譲受会社に移籍することになります。移籍する従業員の範囲や、雇用条件の変更の有無などについては、契約書で明確に定められます。
その他契約書
株式譲渡契約書や事業譲渡契約書以外にも、M&Aでは様々な契約書が締結されます。
-
- 合併契約書:合併契約書では、二つ以上の会社が合併して一つの会社になることを決めます。
- 株主間契約書:株主間契約書では、株主の権利義務関係を定めます。 株主の権利や義務、株式の譲渡制限、競業回避義務などが含まれることが多いです。
- 役員契約書:役員の権利義務関係を定めます。報酬や退職金、競業避止義務などが含まれることが一般的です。
DAの法的位置づけと効力
DAは、法的拘束力を持つ正式な契約書です。M&A取引の当事者は、DAに定められた権利を享受し、義務を履行する必要があります。
例えば、DAには通常、クロージングの前提条件が規定されます。株主総会の承認など、一定の条件が満たされない限り、クロージングを実行する義務は生じません。
また、DAには、表明保証条項や補償条項が盛り込まれるのが一般的です。
売却者は、対象会社の財務諸表の正確性、法令遵守の状況などについて、一定の事実を表明し、保証します。これらの表明保証が真実でなかった場合、補償条項に基づき、売却者は買収者に対して損害賠償責任を負うことになります。
加えて、DAには、クロージング後の競業避止義務や守秘義務なども規定されます。売却者が競合会社を設立したり、対象会社の秘密情報を漏洩したりすれば、DAの条項に違反したことになります。
DAの主な構成要素
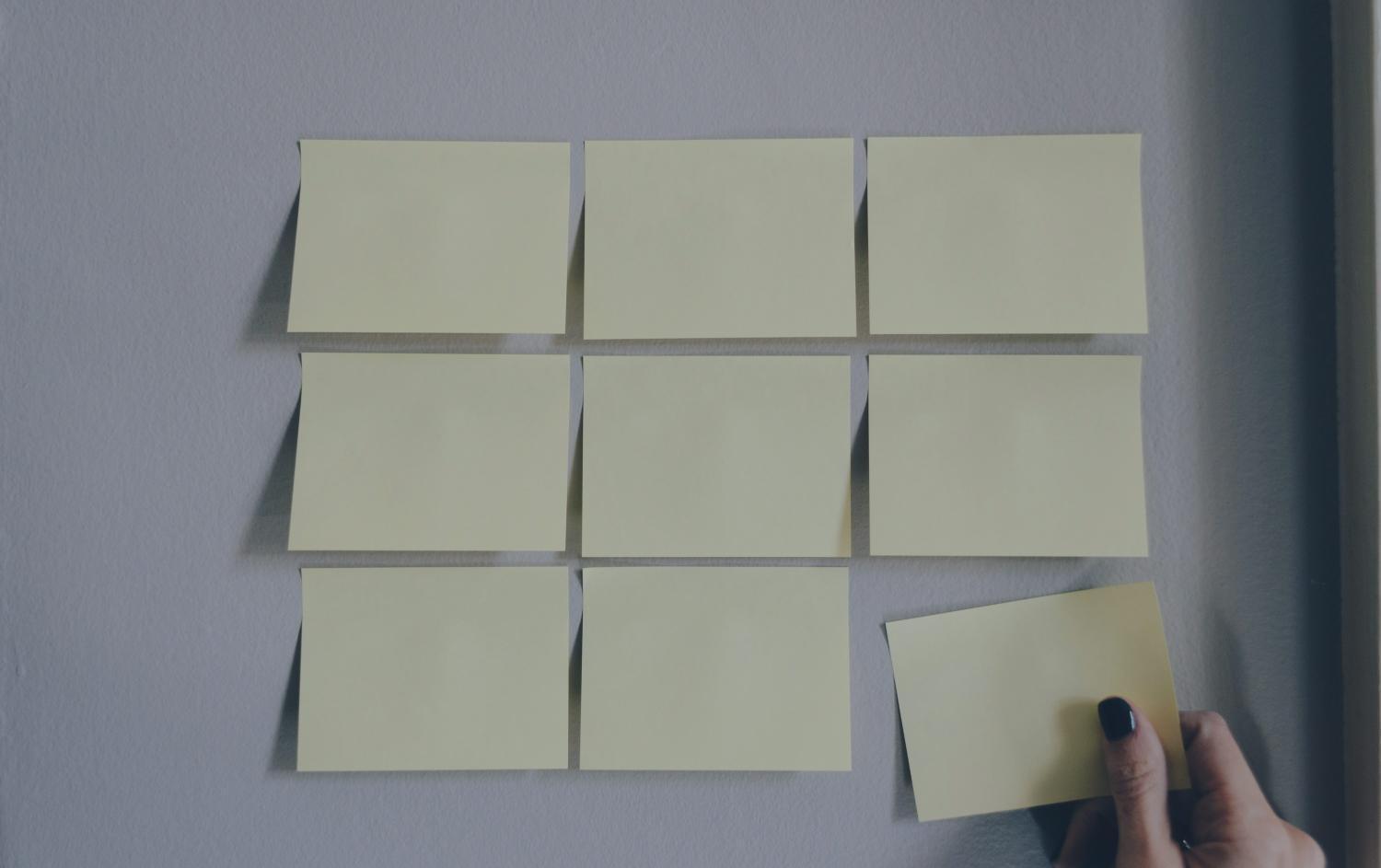
それでは、DAの主な構成要素について、具体的に見ていきましょう。
定義
DAの冒頭部分には、「定義条項」が置かれます。取引対象株式、クロージング日、表明保証の対象範囲などの重要な用語について、明確に定義されます。
例えば、「クロージング日」を「2023年6月30日または両当事者が別途合意する日」と定義することで、クロージングの予定日を特定します。
取引対象の特定
次に、取引の対象となる株式や資産の範囲を特定する条項があります。株式売買であれば、対象株式の種類と数、売買価格などが記載されます。事業譲渡であれば、譲渡対象となる資産・負債の範囲を明記します。
例えば、「売主は、A社の発行済株式100株を、1株あたり50万円、総額5,000万円で買主に売り渡す」といった具合です。
取引金額と価格調整
DAには、取引金額を確定させる条項が置かれます。株式売買の場合、1株あたりの売買価格に株式数を乗じて算出されます。事業譲渡の場合、譲渡対象資産・負債の価額を基に算定されます。
また、クロージング後の価格調整方法についても規定されます。例えば、「クロージング日の運転資本が一定額を下回った場合、買主は売主に対し、不足額を請求することができる」といった条項です。
表明保証
表明保証条項は、DAの中核をなす部分です。売主は、対象会社に関する一定の事実を表明し、保証します。
例えば、「対象会社の財務諸表は、一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して作成されており、対象会社の財政状態および経営成績を適正に表示している」といった表明保証があります。
表明保証の対象は多岐にわたります。資産の権利関係、契約関係、法令遵守、訴訟の有無など、様々な事項が網羅されます。これらの事実が真実でない場合、補償条項に基づく補償義務が生じます。
補償条項
補償条項は、表明保証違反や契約上の義務違反があった場合の救済手段を定めるものです。
例えば、「表明保証違反により買主が損害を被った場合、売主は買主に対し、当該損害を補償する義務を負う」といった規定です。補償の対象範囲、補償の限度額、請求期間などが具体的に定められます。
以上が、DAの主要構成要素の概要です。この他にも、前提条件、コベナンツ、締結後の義務など、様々な条項が盛り込まれることが通常です。
デューデリジェンス(DD)とDAの関係性
デューデリジェンス(DD)とは、買収候補企業が、対象企業の法務、財務、ビジネス、人事・労務など、様々な側面から詳細な調査を行うプロセスです。DDの目的は、リスクの洗い出しと、企業価値の適正な評価にあります。
DDは、通常、外部の専門家(弁護士、会計士、コンサルタントなど)を起用して行われます。専門家の知見を活用することで、対象企業のリスクを的確に把握することができます。
DDの結果は、最終的なDAの内容に直結します。DDで重大なリスクが発見されれば、表明保証条項や補償条項でカバーすることになります。例えば、簿外債務が判明した場合、補償条項で、売却者が債務を補償する旨を規定するのが一般的です。
デュー・デリジェンス終了後の流れ
1. 最終買収契約(DA)の交渉
1.1 DAの初期ドラフトの作成と交渉の開始
DD終了後、いよいよDAの交渉が本格化します。交渉の出発点は、通常、買収候補企業から売却企業に提示されるDAの初期ドラフトです。
DAのドラフト作成は、買収側の弁護士が行うのが一般的です。DDで明らかになったリスクを織り込みつつ、買収側に有利な内容を盛り込むことが基本戦略となります。例えば、表明保証の対象を広く設定したり、補償の上限額を高く設定したりします。
1.2 売却側の修正提案と交渉のポイント
これに対し、売却側の弁護士は、修正提案を行います。表明保証の範囲を限定したり、補償責任を制限したりすることで、売却側のリスクを最小化することが目標となります。
交渉のポイントは、リスク分担のバランスをいかに取るかです。一方的に買収側に有利な内容では、売却側が合意しません。かといって、売却側に過度に譲歩しては、買収の目的が達成できなくなります。
例えば、表明保証違反があった場合の補償責任について、売却側は、補償額の上限を設けるよう主張するでしょう。これに対し、買収側は、上限額をできるだけ高く設定したいと考えます。双方の利害が対立する中で、合理的な落としどころを見出す必要があります。
価格条件も、交渉の重要な論点です。DDの結果を受けて、買収側は価格の引き下げを求めるかもしれません。対象会社の収益力が当初想定を下回る場合などがこれに当たります。他方、売却側は、価格の下方修正には強く抵抗するでしょう。
1.3 交渉の難航と弁護士の役割
このように、DA交渉は、両当事者の利害が複雑に絡み合う場です。買収目的を達成しつつ、売却側の納得も得る必要があります。時間をかけて丁寧に交渉を重ねて合意を目指すことが重要です。
DA交渉が難航することも珍しくありません。交渉が決裂すれば、M&Aは頓挫します。だからこそ、交渉には経験豊富な弁護士の関与が不可欠なのです。法的な論点を押さえつつ、ビジネス面の判断もバランス良く行う必要があります。
2. クロージングまでのタスク
DAが締結されても、すぐにクロージング(取引の実行)に至るわけではありません。DAからクロージングまでには、様々なタスクをこなす必要があります。
2.1 クロージングの前提条件の充足
まず、クロージングの前提条件を充足する必要があります。DAには、クロージングの実行を条件付ける条項が置かれるのが一般的だからです。例えば、株主総会の承認、独占禁止法上のクリアランスの取得などです。
株主総会の承認は、会社法上、一定の場合に必要とされます。株式売買の場合、原則として総会決議は不要ですが、対象会社の事業の全部または重要な一部の譲渡を伴う場合などは、総会決議が必要になります。事業譲渡の場合は、原則として総会決議が必要です。
2.2 事業運営の引継ぎ準備
クロージングに向けては、事業運営の引継ぎ準備も欠かせません。特に、事業譲渡の場合、契約関係の承継手続きが重要なタスクとなります。取引先との契約については、個別の同意を得て契約上の地位を譲受会社に移転する必要があります。従業員との雇用契約についても、譲受会社への移籍手続きが必要です。
2.3 資産の移転手続き
資産の移転手続きも、クロージング前に完了させなければなりません。不動産の所有権移転登記、動産の引渡し、知的財産権の移転手続きなど、様々な実務が発生します。
2.4 スケジュール管理と専門家との連携
このように、DAからクロージングまでには、多岐にわたる法的手続きが必要となります。スケジュール管理を徹底し、専門家と連携しながら、抜け漏れのない対応を進めることが重要です。
おわりに
M&Aは、企業の成長戦略の有力な選択肢の一つです。特に、後継者不在に悩む中小企業にとって、M&Aは事業を継続・発展させるための有効な手段と言えます。
しかし、M&Aのプロセスは複雑で、多くのリスクが伴います。M&Aを成功に導くには、適切なプロセスマネジメントが不可欠です。その中でも、DAの締結は、M&Aの正式な成立を意味する重要なマイルストーンとなります。
M&Aは、企業の将来を左右する重要な意思決定です。本記事がM&A取引への理解を深めるための一助となれば幸いです。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。