事業譲渡の流れを解説!手続きのフローや譲渡に関する注意点も
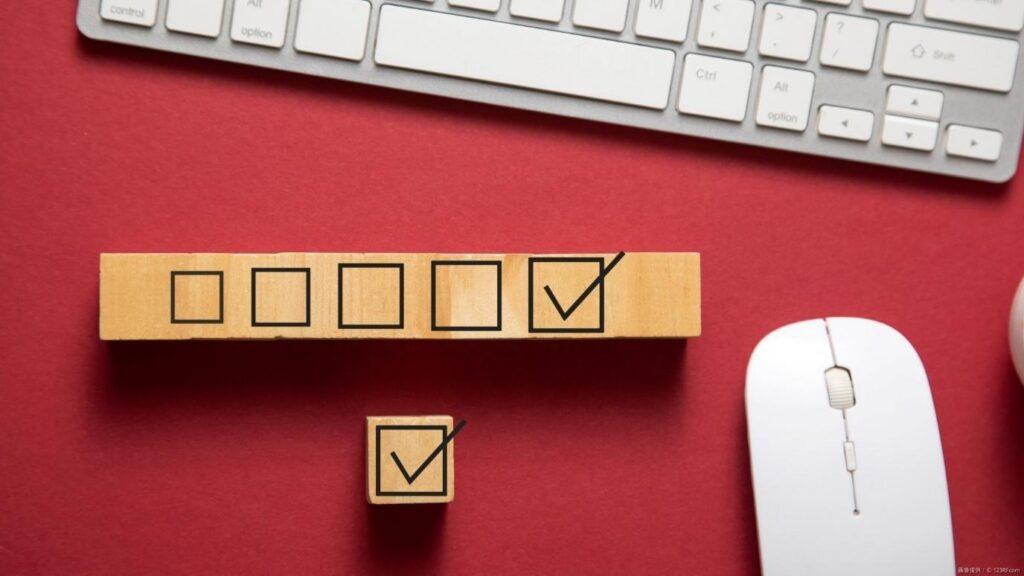

「はじめての事業譲渡でどのような流れで手続きをすれば良いかわからない」、「どのような点に注意するべきか知りたいけど調べるのが大変」だとお困りではありませんか。
事業譲渡は、事業の一部だけを切り取って売却できるメリットがあるM&A手法の一つですが、手続きが複雑で時間がかかる手法ともいわれます。
この記事では、事業譲渡の流れや注意点を徹底解説します。ぜひ最後までご覧いただき、大事な交渉をうまく進められるようしっかりと準備しましょう。
目次
事業譲渡の全体的な流れ
はじめに、全体の流れを把握しましょう。
事業譲渡は、大きく4つのステップに分けられます。
|
|
|
|
事業譲渡は、企業同士の大きな交渉です。各種契約に加え、株主への承認や関係官庁への届出が必要な手続きがあるため、関係法令とともに解説していきます。
事業譲渡の手続きのフロー
ここからは事業譲渡の手続きに関するフローに従って、詳しく解説していきます。手続きの全体像が把握できるため、順番どおりに確認していきましょう。
本記事では、事業を売却する企業を「売り手企業」といい、事業を譲り受ける企業を「買い手企業」として解説していきます。
1.事業売却の検討
事業譲渡の方法は2つあり、検討段階で売却する範囲を決定します。
-
- 全部譲渡
事業のすべてを譲渡すること
-
- 一部譲渡
譲渡する部門を選別すること
売り手企業は、自社の経営状況を分析し、現状把握を行ったうえで譲渡範囲を選定します。
たとえば、一部譲渡では、負債を抱えた事業を切り離して譲渡し、売却益を既存事業の投資に当てられます。
買い手企業は、市場規模の拡大や新規事業の参入を目的に、売り手企業を選定し、必要な事業や人材を見極めて取得できます。
2.事業譲渡の準備
売り手企業は、取引先(買い手企業)を探すための資料作成や、仲介業者を選定します。売り手企業が用意するものは、ノンネームシートと呼ばれる企業名を伏せた資料です。この時点においてはまだ秘密保持契約書の締結がされていない場合も多く、そのためまずは匿名情報に基づき買い手企業の選定を依頼することになります。
ノンネームシートには、事業概要や売却に至る理由・背景、売上高や従業員数、取引先などの情報を記載します。
そのほかの準備として、仲介業者を選定しておくことをおすすめします。買い手企業を探すソーシングや、譲渡の交渉には大きな労力が必要です。そのため、専門のノウハウを持った金融機関やM&Aアドバイザー、仲介業者をこのタイミングで選定しておくとよいでしょう。
3.ソーシング、交渉の開始
ソーシングや事業譲渡の交渉を、売り手企業が単独で行うこともできますが、以下2つのメリットがあるため、仲介業者に依頼することをおすすめします。
-
- 企業リサーチや交渉にかかる労力を分散できること
- 専門知識と実績が豊富な業者を通すと良好な買い手先を見つけやすいこと
そして、ノンネームシートの作成と仲介業者を選定できたら、買い手企業向けに自社情報を開示してソーシング(譲渡先のリサーチ)を開始します。
よい買い手企業を見つけるためにも、ノンネームシートの見直しや、交渉トラブルを避けるため、仲介業者との連携は密に行っておきましょう。
4.秘密保持契約の締結
売り手企業に興味を示した企業がみつかると、事業譲渡の本格的な交渉をはじめる前に、双方で秘密保持契約書を取り交わします。
秘密保持契約書とは、英文で「Non-DisclosureAgreement」と表現され、多くのケースで頭文字をとった「NDA」と言われます。
交渉がはじまると、売り手企業・買い手企業ともに、一般に公開していない取引先や財務状況などの機密情報を明かすため、情報漏洩や交渉トラブルのリスクを回避するためにNDAを締結します。
また、NDA締結後は、買い手企業から譲渡する事業内容について、ある程度合意形成が得られると今後の手続きがスムーズです。
M&AでのNDA(秘密保持契約)とは?|締結目的から作成時の注意点まで完全解説
5.トップ面談
トップ面談とは、売り手企業、買い手企業の経営者同士が面談を行うことです。トップ面談の目的は、経営理念や価値観などの共有を行い、経営者としての人間性や相性を確認し合うことです。
出席者は経営者以外に、経営陣や各部門の責任者に加え、事業譲渡に関わる仲介業者が出席します。また、議決権の過半数を有する株主が同席することもあります。
なお、売り手企業、買い手企業ともに出席人数のバランスが偏っていると相手企業に悪い印象を与える可能性があるため留意しましょう。面談場所は、情報漏洩リスクの観点から売り手企業の本社はできるだけ避けて、買い手企業か仲介業者の事務所で行うのがよいとされています。
M&Aのトップ面談を成功させるポイントとは?質問リストや進め方も解説
6.デューデリジェンスの実施
デューデリジェンスとは、買い手企業が売り手企業の実態の調査をすることを指します。
買い手企業は譲渡後にトラブルが発生するリスクを減らすために、売り手企業の財務状況や、企業価値を見定めるデューディリジェンスを行います。
調査には、弁護士や専門家を派遣します。調査完了後、売り手企業との最終交渉で合意に至れば事業譲渡の手続きに進みます。
7.取締役会、株主総会の開催
企業調査が終わり、事業譲渡の契約手続きをするためには、取締役会と株主総会を開催し承認を得なければなりません。取締役会は、事業譲渡という会社の重要な判断を慎重に行う目的で開催します。株主総会は、取締役会で決議した事業譲渡やそのあとに策定する事業譲渡契約書について、株主からの承認を得ることが開催の目的です。
なお、取締役会を設置していない会社では、取締役の過半数が事業譲渡に賛成する必要があります。
8.事業譲渡契約の締結
取締役会と株主総会で事業譲渡が承認されたら、次は事業譲渡契約を締結します。事業譲渡契約書の記載事項に法律の定めはないため、弁護士や専門家による法的なチェックを受けながら、売り手・買い手、双方の企業で取り決めます。
たとえば、契約書に記載する主な条項は次のとおりです。
-
- 事業譲渡の合意表明
- 譲渡事業の範囲(対象となる資産及び負債の明細)
- 譲渡対価・支払い方法
- 資産価値
- 効力発生日
- 守秘義務
- 従業員の雇用関係
- 競業避止義務
- 契約の解除・損害賠償等
- その他(協議条項・裁判の管轄合意などの一般条項)
9.臨時報告書の提出
有価証券報告書の提出義務がある会社は、事業譲渡の譲受による財務状況が次になる場合、臨時報告書の提出が必要です。
-
- 純資産額が30%以上増減する場合
- 売上高が前年比10%以上の増減が想定される場合
この規定は金融商品取引法24条に定められ、臨時報告書の提出先は内閣総理大臣です。
参照元:e-Gov法令検索「昭和二十三年法律第二十五号金融商品取引法」
10.公正取引委員会への届出
事業譲渡する会社の国内売上高の合計額が200億円を超え、以下の条件に該当する場合は公正取引委員会へ届出が必要です。
-
- 国内売上高が30億円を超える会社から全部譲渡を受ける場合
- 売り手企業から重要な一部分を含む国内売上高の合計が30億円を超える一部譲渡を受ける場合
- 売り手企業の固定資産の全部または一部が国内売上高が30億円を超える譲渡を受ける場合
また買い手企業は、公正取引委員会が事業譲渡の届出を受理してから、30日間は新しい事業譲渡が禁止されます。ただし、公正取引委員会は、買い手企業から事業譲渡禁止期間の短縮申請を書面で申し込まれた場合、独占禁止法上の問題がなければ、禁止期間を短縮することがあります。
参照元:「事業等の譲受けの届出制度」
11.株主への通知・公告と株主総会の特別決議
株主に対する事情譲渡に関わる通知は、事業譲渡をする20日前までが期限です。その理由は、事業譲渡に反対する株主が、株主買取請求を行える期間を設けるためです。また、原則として、譲渡の効力発生の前日までに株主総会の特別決議を行い、株主からの承認を得る必要があります。
株主総会の特別決議には、議決権を行使できる株主の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)の株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成を必要としています。
参照元:e-Gov法令検索「平成十七年法律第八十六号会社法」
12.事業譲渡の準備
事業譲渡契約書が締結されると契約書にもとづいた譲渡手続きが行われます。しかし、事業譲渡では契約締結の他に、次のような手続きが必要なため、契約の締結と並行して準備をしておきましょう。
-
- 登記の手続き
免責の登記・その他登記簿の記載内容に変更が生じる場合
-
- 税務の手続き
譲受した資産や対価に対する税金の会計処理
-
- 労務の移行準備
譲渡契約に従業員を含む場合
13.クロージング
クロージングとは、事業譲渡契約書が締結後に、契約書にもとづき事業譲渡や支払いなどをすべて完了するまでの手続きのことを指します。事業譲渡の場合、契約書の項目を個別に譲渡するため、クロージングの期間は約1か月から1年程度はみておきましょう。
M&Aにおけるクロージングとは?当日までの流れや必要条件、手続きや書類まで徹底解説
14.名義変更、雇用の引継ぎ
事業譲渡契約が締結されたら、売り手企業名義の預金や土地・建物などの資産を買い手企業の名義へ変更します。従業員が譲渡する対象である場合は、雇用の引き継ぎを行います。
なお、従業員の雇用契約内容は買い手企業には承継されません。そのため、引き継ぎ前に従業員から転籍の同意を得るほか、勤続年数や有給休暇残数、退職金規定などについて交渉しておく必要があります。
事業譲渡をおこなう際の注意点
事業譲渡のフローと同様に重要な事業譲渡の注意点をみていきましょう。事業譲渡は売却規模や買い手先により、株主総会決議の要否が分かれます。
また、事業譲渡は他のM&A手法と比較し、手続きに時間がかかるとされています。譲渡後に提供データの誤りが発覚しないよう十分な確認を行うためにも、準備期間は多めに設定しましょう。
参照元:e-Gov法令検索「平成十七年法律第八十六号会社法」
事業譲渡のトラブル事例を解説|事業継承を失敗させない進め方や問題の解決策も紹介
譲渡は株主総会の承認が必要となる
事業譲渡を行う場合、原則として譲渡の効力が発生する前日までに株主総会の特別決議で承認を得る必要があります。
承認が必要な事業譲渡は主に次の3つです。
-
- 事業すべてを他の企業に譲渡する
- 事業の重要な一部分(総資産額の5分の1を超える)を他の企業に譲渡する
- 他の企業から譲受する事業が自社の総資産の5分の1を超える
この規定は会社法で定められており、事業の全部または一部を譲渡する際は、株主総会で議決権を持つ株主へ承認を得なければなりません。
なお、事業の重要な一部分とは、事業の売上高や利益などの「量的基準」と、事業内容や企業イメージなどの「質的基準」の両面から判断されます。たとえば、譲渡される従業員数が事業全体の10%を超える場合は量的基準が重要であると認められます。
ただし、譲渡する事業の価値が、買い手企業の総資産額の5分の1に満たない場合、株主総会の特別議決を必要としないケースがあります。
参照元:e-Gov法令検索「平成十七年法律第八十六号会社法」
株主総会特別決議が不要なケース
次のケースに該当する場合は、株主総会特別決議は不要です。
-
- 譲渡する資産の帳簿価額が売り手企業の総資産額の5分の1を超えない
- 買い手企業が売り手企業の特別支配会社である
1つ目は、簡易手続きとして処理できるケースです。事業譲渡する対価が、事業売買する企業の純資産の5分の1以下の場合は、株主総会の特別決議は不要です。
2つ目は、略式手続きとして処理できます。特別支配会社とは、ある株式会社の総株主の議決権の9割以上を保有している会社です。また、100%子会社など複数社合計で9割以上の議決権を有している場合も含まれます。
議決権を多く有する株主は、その企業に対して大きな影響力を持ちます。株主総会特別決議の要件は、議決権を行使できる株主の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)の株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成を持って可決されます。そのため、買い手企業が90%以上の議決権を持っている場合、株主総会を開催することなく事業譲渡を成立できます。
参照元:e-Gov法令検索「平成十七年法律第八十六号会社法」
事業譲渡における競業避止義務の規定がある
売り手企業が注意したいポイントとして、事業譲渡後に最長30年間、売却した地域において同じ事業を行うことを禁止される「競業避止義務」があります。この規定は会社法第21条に定められ、事業を譲渡した売り手企業は同一の区内や市町村で、原則として20年間、売り手企業が特約をする場合30年の間、同一の事業を行うことが禁止されます。
ただし、インターネットやSNSの普及した昨今では、特定の地域に縛られない事業が可能なため、会社法の規定によらずに取り決めることが多くなりました。たとえば、競業禁止期間を短縮または設けないようにしたり、対象場所を日本国内全域や全世界まで広げたりするなど、当事者間で特約を設けることで柔軟に対応しています。
参照元:e-Gov法令検索「平成十七年法律第八十六号会社法」
事業譲渡の準備期間を多めに設ける
事業譲渡はM&A手法の一つですが、手続きにかかる期間は平均で9か月程度といわれています。早い場合でも約3か月、長いと1年以上の時間を要するため、譲渡完了までの準備期間は多めに設定しましょう。
とくに、交渉フロー前の自社分析や、事業譲渡の検討などの事前準備に時間がかかるケースが多く、譲渡規模が大きい場合や買い手企業の意思決定が遅い場合にはさらに多くの期間が必要です。
事業譲渡ではさまざまな契約や手続きのための期間を確保するほか、買い手企業の事情を考慮した準備期間を設けることが重要です。
契約には正しいデータを提示する
売り手企業は、ノンネームシートや交渉時の提出資料のチェックには細心の注意が必要です。
事業譲渡では、デューディリジェンスにより買い手企業や第三者機関による企業調査が行われますが、調査に問題がなかったとしても、譲渡後に資料の誤りがみつかれば、事後トラブルや損害賠償請求に発展するリスクがあります。
信用できない売り手企業に、買い手企業は興味すら持たなくなるため、提出資料に誤りがないよう入念にチェックしましょう。
まとめ
本記事で、事業譲渡の全体的な流れや注意点がおわかりいただけたでしょうか。大まかにまとめると事業譲渡は、事前準備・交渉・契約の締結・クロージングの4つのステップで手続きが行われます。注意点は、譲渡する金額や規模によって株主総会の特別決議が不要なケースがあることや、売り手企業は原則20年間同一地域で同じ事業ができない競業避止の規定があることです。
事業譲渡は、準備・検討からクロージングまで必要な手続きが多い分、事業の一部分だけを切り離し売買できることで、売り手企業や買い手企業にメリットがある手法です。事業譲渡を選択する際は、手続きの流れや注意点を理解し、十分な期間を設けて交渉を上手に進めましょう。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。


