中小企業の事業譲渡 | 特徴やメリット・デメリットを解説!選ぶポイントも
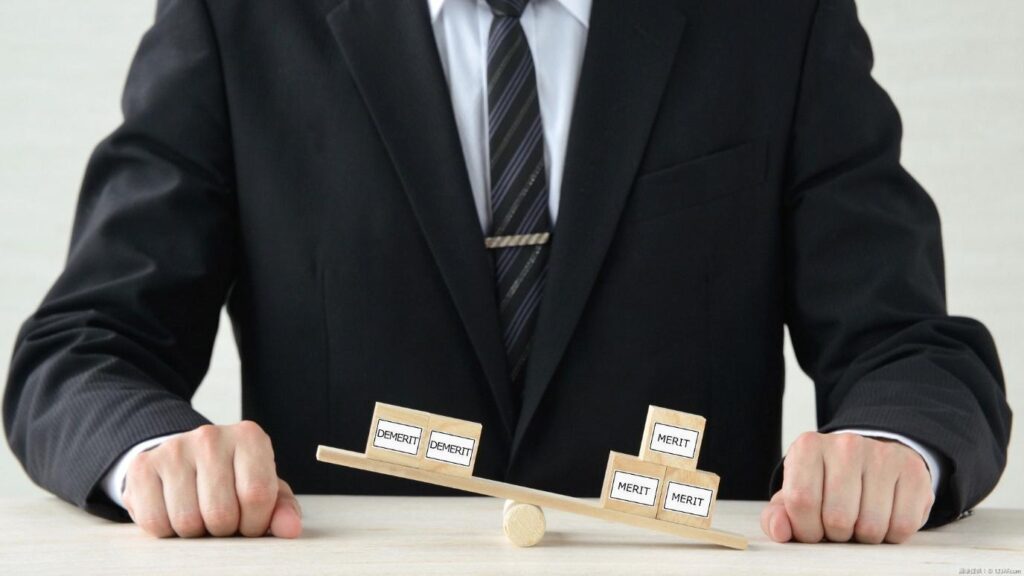

中小企業が直面する事業の拡大や縮小、あるいは方向転換する時の選択肢の一つが「事業譲渡」です。この記事では事業譲渡の特徴をはじめ、事業譲渡のメリット・デメリット、ほかの組織再編手法との違いについて詳しく解説します。
また、中小企業が売り手または買い手として事業譲渡を検討する際のポイントにも触れていきます。
目次
目次
事業譲渡とは
事業譲渡とは、企業がその事業の全部、または一部を他の企業に移転することを指します。特定の事業や店舗だけ引継げるため、法人全体の再生が不可能な場合であっても特定事業を引継ぎ、再生を可能とします。
事業譲渡では、資産や負債、従業員、契約関係など、事業を構成する要素が譲渡対象となり得ます。事業譲渡は、企業が成長戦略の一環として新たな事業機会を追求する場合や、経営資源の再配分、事業の再構築を図る際に行われます。
また、後継者不足による事業継承問題を解決する手段としても事業譲渡が用いられることがあります。事業譲渡を通じて企業は新たな展開を図る一方で、買い手企業は既存の事業基盤を活用して成長を目指せます。
また、財務調査(デューデリジェンス)で簿外負債の存在が見つかった場合など、株式譲渡で法人ごと買収するリスクがある場合にも用いられます。
事業譲渡の特徴
譲渡プロセスは、企業間の契約によって細かく定められ、法的な手続きを伴います。このプロセスには、買い手と売り手の間で詳細な契約交渉が行われ、譲渡される事業の価値評価や資産の詳細なリストアップ、リスクの共有と評価など、多くのステップが含まれます。
また、事業譲渡は速やかに行われることもあれば、株式譲渡に比べて数か月から数年を要することもあります。この過程で、買い手は譲渡される事業の財務状況や法律問題、市場の位置づけなどを徹底的に評価し、リスクを把握します。売り手は、事業の魅力を最大化し、譲渡価格の向上を目指しつつ交渉を進めます。
事業譲渡の注意点
事業譲渡を行う際は、多くの注意点があります。もっとも重要なのは、契約の詳細に関する注意です。譲渡される資産の範囲や従業員の扱い、許認可、顧客情報の移転条件など、細部にわたる交渉が重要になります。
税務上の扱いや法律に関する知識も必要で、とくに譲渡される資産のなかには特許権や商標権などの無形資産も含まれることがあります。これらの評価や取り扱いには、専門的な知識が求められます。
また、従業員の移転に関しては労働法に基づく適切な手続きの遵守が必要であり、これを怠ると法的な問題が生じるリスクがあります。加えて、事業譲渡によって既存の顧客関係やサプライチェーンに影響を及ぼす可能性があります。そのため、これらのステークホルダーとのコミュニケーションも非常に重要です。
中小企業で事業譲渡が行われる理由
中小企業における事業譲渡はさまざまな理由から行われますが、その核心には経営戦略の最適化があります。市場の変化や技術革新に迅速に対応する必要性が高まるなか、中小企業は自社の強みを活かしつつ、リソースの限界内で成長を目指さなければなりません。
事業譲渡は不採算部門の切り離し、コア事業への集中投資、または新たな成長機会へのアクセスという形で、この課題に対応するための戦略的ツールとなり得ます。
経営資源の有効活用も、中小企業が事業譲渡を行う大きな動機の一つです。とくに資金調達が困難な中小企業にとって、事業部門の売却は即時の資金確保につながり、企業の財務健全性を高められます。
さらに、市場環境の変化に伴う事業方針の転換時には、事業譲渡を通じて新たなビジネスモデルへの移行を容易にすることが可能です。
事業譲渡と会社分割・合併・株式譲渡の違い
| 特徴 | 目的 | 効果 | |
| 事業譲渡 | 事業の一部または全部をほかの会社に移転する行為 | 事業の再編、特定事業部門の売却、経営資源の集中 | 事業ポートフォリオの最適化、リソースの再配分 |
| 会社分割 | 会社の事業に関して有する権利義務の全部又は一部を切り離して新しい会社を設立するか、または既存の他の会社に承継する行為 | 事業再編、特化、または分離による経営効率化 | 新会社の創設または強化、経営資源の適正配置 |
| 合併 | 二つ以上の会社が合併して一つの会社になる行為 | 経営資源の統合、競争力の強化、コスト削減 | シナジー効果の追求、経営効率の向上 |
| 株式譲渡 | 会社の株式の所有権がほかの個人または法人に移転する行為 | 経営権の移転、資本関係の変更 | 経営陣の変更、資本構造の最適化 |
事業譲渡や会社分割、合併、株式譲渡は、企業が成長や再編、戦略的再配置のために利用する重要な手段です。しかし、それぞれの特性と目的には明確な違いがあります。
事業譲渡は、企業が自社の事業の一部、または全部を他の企業に譲渡する行為です。事業譲渡では具体的な資産や従業員、顧客リストなどが譲渡されることが一般的であり、企業は特定の事業セグメントから撤退するか、または資金を調達する目的で行われます。
会社分割の違い
会社分割は、企業が事業に関して有する権利義務の全部、または一部を切り離して新たな会社を設立して承継するか、または既存の別の会社に承継することです。会社分割は、特定の事業領域に特化した運営を可能にし、より集中的な管理と資源の配分を目指します。
会社分割の主な目的は、事業部門の潜在能力を最大限に引き出し、企業価値を向上させることにあります。分割により生じる新しい会社は、元の企業とは独立した法人格を持ち、自身の戦略的目標にもとづいて運営されます。
会社分割は、組織内の異なる事業の成長速度や方向性に大きな違いがある場合にとくに有効です。一部門が他の部門よりも迅速に成長している場合や、新しい市場機会を追求するために特定の事業単位に焦点を当てたい場合は、会社分割により各事業単位がそのポテンシャルを最大限に活かす環境を整えられます。また、会社分割はリスク管理の観点から利用されることもあります。
合併の違い
合併は、二つ以上の企業が一つに統合され、新しいまたは既存の法人がその結果として生まれるプロセスです。合併は企業が市場でのポジションを強化し、業務の効率化を図るために利用されます。
企業は、合併により製品ラインを拡張し、顧客基盤を広げられるだけでなく、研究開発やマーケティングなどの分野でのコスト削減と効率化を実現することも可能です。また、競争を減らし、市場における支配力を増すことも合併の目的となりえます。
合併のプロセスは複雑で、通常、法的および財務的な評価、デューデリジェンス、株主の承認、そして規制当局の承認が必要です。合併は文化的・組織的な統合も伴うため、成功するためには従業員間のコミュニケーションと統合後の変革管理が重要となります。
企業文化の違いや、経営方針の相違が合併後の統合プロセスを複雑にする主な要因です。
株式譲渡の違い
株式譲渡は、企業の株式が一方の当事者から別の当事者に移転されるプロセスです。株式譲渡は企業の所有権に直接影響を及ぼし、株式を譲渡される側が企業の経営権を獲得できるため、事業譲渡や会社分割、合併とは根本的に異なります。
株式譲渡は個人投資家やほかの企業が企業の株式を購入することにより、経営権の変更や企業の戦略的方向性の変更を引き起こす可能性があります。
株式譲渡の主な特徴は、企業の運営や事業活動そのものが直接的には変更されない点にあります。つまり、企業の法的な存在やその事業構造は譲渡の前後で変わらず、変更されるのは株式の所有者だけです。このプロセスは比較的シンプルであり、企業買収やパートナーシップの変更、あるいは資本構造の再編など、さまざまな目的で行われます。
中小企業が売り手側で事業譲渡を行うメリット
中小企業が売り手側として事業譲渡を行う場合、多くのメリットがあります。まず、特定の事業部門や資産を譲渡することで必要な資金を得られます。これは、新たな投資機会への資金として再利用できるだけでなく、財務状況の改善にも寄与します。
手放す事業を選択できる
中小企業が事業譲渡を行う際の大きなメリットの一つは、手放す事業を選択できる点にあります。これにより企業は非核心事業や成長が鈍化している部門を譲渡し、経営資源をコア事業や新しい成長機会に集中させることが可能です。
不動産などの所有は継続できる
中小企業が事業譲渡を行う際、不動産などの資産所有権を維持できる点は大きなメリットです。事業の一部を譲渡しても、不動産は売却せずに所有し続けることが可能です。
これにより、譲渡後も賃貸収入を得るなどして資産を有効活用する道が開けます。とくに中小企業にとって、事業構造の見直しや収益源の多角化を図るうえで、不動産の戦略的な保持・活用は貴重な選択肢の一つとなり得ます。
資産を残せる
中小企業が事業譲渡を行うことで、必要な資産を選択的に残すことが可能です。譲渡する事業部分以外の資産は、企業が保有し続けられます。これにより資金やそのほかのリソースを、将来の事業展開や新規事業への投資に活用できます。資産の選択的保持は、企業の柔軟性と将来性を高める戦略的選択となるでしょう。
従業員を可能な限り残せる
事業譲渡を行う際、中小企業は従業員を可能な限り保持できます。とくに、譲渡しない事業部門で働く従業員はそのまま雇用を継続できるため、企業の知識と経験を保持できます。また、譲渡する事業部門の従業員も新しい事業主との協議により、雇用が維持されるケースが多く、従業員の雇用安定に寄与します。
譲渡利益を得られる
事業譲渡は、中小企業にとって重要な収益源となります。譲渡によって得られる一時的な利益は、企業の財務状態の改善、新たな事業投資、または経営者の退職金などに充てられることが多いです。
この利益は、企業の将来の発展に資する資金として、または財務的な余裕を生み出す手段として有効活用できます。
後継者がいない問題を解決できる
中小企業において後継者不足は深刻な問題ですが、事業譲渡はこの問題の解決策の一つとなります。事業を継続させたいが後継者が見つからない場合、事業譲渡によりほかの企業や個人に運営を任せることが可能です。
これにより、企業の価値を維持しつつ、事業の存続を図れます。
大企業よりも事業譲渡の負担が少ない
中小企業にとって、事業譲渡のプロセスは大企業に比べて負担が少ない場合があります。規模が小さいため、譲渡に必要な手続きや協議が比較的簡潔に済み、スムーズに進行することが多いです。
また、柔軟性が高く、個別のニーズに応じたカスタマイズが可能であるため、効率的に事業譲渡を実施できます。
法人格を維持できる
事業譲渡を行っても、中小企業は法人格を維持できます。これは、企業が持続的に事業を進めるうえで、信頼性や法的地位を保持できることを意味します。事業の一部を譲渡したあとも、残った事業部門での事業活動を継続することが可能であり、新たな事業機会に対しても迅速に対応できます。
中小企業が売り手側で事業譲渡を行うデメリット
中小企業が売り手側で事業譲渡を行う際は、デメリットを考慮する必要があります。まず、従業員や取引先との契約を新たに結び直す必要があることで、これには時間と労力がかかります。
また、譲渡した利益に税金がかかるため、収益性の計算に影響します。ここでは、そのほかのデメリットについてもみていきます。
従業員・取引先との契約をやり直さなければならない
事業譲渡を行う場合、中小企業は従業員や取引先とのあいだで新たに契約を結ぶ必要があります。これは、既存の契約が新しい事業主に自動的に移行しないためです。
契約の見直しや更新は、時間とコストを要する作業です。事業のスムーズな移行を妨げる要因となる場合があり、とくに長期にわたる関係性が影響を受けやすいです。
譲渡した利益に税金がかかる
事業譲渡によって得られる利益には、税金が課されます。中小企業は、譲渡利益に対して所得税や法人税の負担を覚悟しなければなりません。
税率は利益の規模や法人の状況によって異なりますが、大きな利益を得た場合は税金が企業の手取り額を大きく減少させる可能性があります。そのため、税務計画と事前の相談が重要な要素となります。
株主総会や債権者保護手続きの実施が必要になる場合がある
中小企業が事業譲渡を行う際は、株主総会の開催や債権者保護手続きの実施が必要となることがあります。株主総会では、事業譲渡の承認を得る必要があり、時間と労力を要します。
株主のなかには譲渡に反対する者もいるため、合意形成には説得力のある説明と戦略的なアプローチが求められます。
許認可などの手続きが煩雑
事業譲渡を行う際に、特定の業種では新たな許認可が必要となることがあります。この手続きは複雑で時間がかかることが多く、企業にとって大きな負担となります。また、必要な資格や許可を取得するためには、追加の要件が課されることもあります。
負債は譲渡されず残るリスクがある
事業譲渡を行っても、中小企業の負債は自動的に新しい事業主に移行しません。譲渡前に存在した負債は、引き続き元の企業の責任となります。このため、負債の管理と返済計画は、事業譲渡のプロセスを検討する際に重要な考慮事項となります
譲渡以降20年は同じ事業はできない
事業譲渡契約によっては、譲渡後一定期間、同じ業種での事業活動が制限されることがあります。この「競業避止義務」により、中小企業は譲渡した事業と同じ分野で20年間新たに事業を開始できなくなる可能性があります。
この制約は、企業の将来の成長機会に影響を及ぼすことがあります。
中小企業が買い手側で事業譲渡を行うメリット
ここでは、中小企業が買い手側で事業譲渡を行う場合のメリットについて紹介します。
獲得したい事業だけを選べる
中小企業が買い手側で事業譲渡を行う大きなメリットの一つは、自社の戦略や目的に合致する事業部門のみを選択的に獲得できる点です。この柔軟性により、企業は必要ない部門に資源を割くことなく、目的に合った成長機会を具体的に手に入れられます。事業部門のみを選択的な獲得できることは、企業の運営効率を高め、経営資源の最適化に貢献します。
人材と技術を獲得できる
事業譲渡を通じて、中小企業は特定の分野の専門人材や先進技術を直接獲得することが可能になります。これにより、新しい事業領域への進出や既存事業の強化を図る際に、人材育成や技術開発にかかる時間とコストを大幅に削減できます。人材と技術の獲得は、競争優位性を高め、事業成長を加速させる重要な要素といえます。
顧客・取引先を継承できる
事業譲渡により、買い手側の中小企業は譲渡される事業の顧客基盤や取引先ネットワークをそのまま引き継げます。これは、新たな市場への進出や顧客基盤の拡大を計画している企業にとって大きなメリットです。
顧客や取引先の継承により、即時に収益を上げる可能性が高まり、ビジネスの安定性を向上させます。
新事業をスタートさせやすい
既に確立された事業を獲得することで、中小企業は新事業を迅速に立ち上げられます。市場調査やブランド構築、顧客獲得にかかる初期投資を大幅に削減できるため、ビジネスの成長速度を加速させることが可能です。
節税につながる
事業譲渡は、適切に計画されれば、税負担の軽減につながる場合があります。営業権が計上される場合は、節税が可能です。買い手企業は、獲得した事業に関する投資を経費として計上することで、税務上の利益を調整して節税効果を期待できます。
また、特定の条件下では譲渡価格の一部を減価償却費として扱うことも可能です。
個別契約のため負債は回避できる
買い手側の中小企業は、事業譲渡を通じて特定の資産や事業を獲得する際、個別契約にもとづき交渉を行います。そのため、譲渡される事業の負債を引き受ける必要がありません。これにより、企業は税金や時間外手当の未払いなど簿外負債を引継ぐ恐れがなく、新たに獲得する事業に関連するリスクを最小限に抑えつつ、資産のみを効果的に獲得できます。
負債の回避は、財務健全性を保ちつつ事業拡大を図るうえで大きなメリットとなります。
中小企業が買い手側で事業譲渡を行うデメリット
中小企業が買い手側で事業譲渡を行う際のデメリットには、新たに獲得した事業の従業員と個別の雇用契約を結ぶ必要がある点があります。また、取引先との契約を再度確立しなければならないこと、さらに必要な許認可の再取得が必要となる場合があることもデメリットとして挙げられます。
これらの手続きは複雑で時間とコストを要し、事業のスムーズな移行を妨げる可能性があります。
従業員と個別契約を結ぶ必要がある
事業譲渡を行う際、買い手側の中小企業は、新たに獲得した事業の従業員と個別に雇用契約を結ぶ必要があります。雇用契約には時間がかかり、法律的な複雑さを伴うことも少なくありません。
従業員ごとの契約条件の見直しや交渉が必要となり、企業の人事部門にとって大きな負担になる可能性があります。さらに、従業員が新しい条件に同意しない場合は、人材の確保が難しくなるリスクもあります。
取引先とも契約を結び直さなければならない
事業譲渡において、買い手側の中小企業は、譲渡された事業の取引先と新たに契約を締結する必要があります。既存の契約関係は自動的に継承されないため、取引先との再交渉が不可欠です。
取引先との再交渉で、取引条件の変更や価格交渉が発生する可能性があります。買い手側の企業にとって新たな契約締結がスムーズに進まない場合は、ビジネスの連続性に影響を及ぼすリスクがあります。
許認可の再手続が複数ある
中小企業が事業譲渡の買い手側となる場合は、譲渡された事業に必要な許認可の取得や更新が求められます。許認可の取得や更新の手続きは、複数の政府機関にまたがることがあり、時間とコストを大きく消費する可能性があります。
とくに、特定の業種においては厳格な規制が適用されるため、再手続きの負担はさらに大きくなります。買い手側の企業にとって、このプロセスの管理と進行は、事業譲渡を成功させるうえでの重要な課題となります。
中小企業の事業譲渡事例
1.コクヨ、富士通コワーコから法人向けサプライ事業を取得
コクヨ株式会社は、2024年8月、富士通株式会社の子会社である富士通コワーコ株式会社から、法人向けサプライ事業を取得することを発表しました。この取引の目的は、コクヨがオフィスサプライ事業における競争力を強化し、さらなる市場拡大を図るためです。
富士通コワーコは、富士通グループの一員として、法人向けに文具やオフィス関連用品を提供しており、長年にわたって確立された信頼と顧客基盤を持っています。
コクヨはこの事業を取得することで、すでに強みを持つオフィス用品事業をさらに強化し、より幅広い法人顧客層へアプローチできるようになります。
引用元:https://maonline.jp/news/20240823a
2.桐のかほり 咲楽による小野写真館の事業譲渡
「桐のかほり 咲楽」は、主に冠婚葬祭関連の商品やサービスを提供している企業で、地域密着型のビジネスに注力しています。この度、同社は「小野写真館」からの事業譲渡を受け、フォトスタジオ事業に新たなビジネスを広げました。
小野写真館は、長年にわたり地域で写真撮影サービスを提供してきた企業で、ウェディングや家族写真、子供の記念撮影など、地元住民に親しまれていました。しかし、次の成長フェーズに進むために、事業の継承を検討しており、結果として桐のかほり 咲楽に事業を譲渡することを決定しました。
この事業譲渡によって、桐のかほり 咲楽はフォトグラフィービジネスにも進出し、顧客に対してより幅広いサービスを提供することができるようになります。特に、冠婚葬祭に関連する写真サービスが強化されることが期待されています。
引用元:https://ono-group.jp/profile/press/20201001/index.html
事業譲渡を選ぶポイント
事業譲渡を選ぶ際の重要なポイントは、譲渡したい事業の範囲を明確にすること、契約や手続きを丁寧に進めること、税金の影響を正確に把握しておくことなどです。
これらの要素は事業譲渡の成功に直接影響し、将来的なリスクや不意の費用を避けるためにも事前の準備と計画が必要です。適切なポイントを押さえることで、スムーズかつ効果的な事業譲渡が可能になります。
譲渡したい範囲
事業譲渡を検討する際、中小企業は譲渡したい事業の範囲を明確に定める必要があります。どの事業部門や資産を譲渡するか、またそれによってどのような効果を期待するかを慎重に分析することが重要です。
譲渡したい範囲の選択は、企業の将来の戦略や財務状況に大きな影響を及ぼすため、目的に応じた適切な範囲の特定が不可欠です。譲渡範囲の決定は事業の価値を最大化し、移行後の運営をスムーズにするための鍵となります。
契約などの手続き
事業譲渡プロセスにおいて、契約書の作成や手続きの遵守は極めて重要です。売り手と買い手双方で合意に至った条件を明記し、法的な義務や責任の範囲を定義することで、将来的な紛争を防げます。
契約には事業譲渡後の運営に関わる細かな条項も含まれます。そのため、専門家との協力のもと、注意深く契約書を作成することが求められます。適切な手続きの遵守は、事業譲渡の成功に不可欠な要素といえます。
税金
事業譲渡には、税金の考慮が欠かせません。譲渡利益にかかる税金の計算、税負担の最小化戦略、譲渡後の税務処理など、多岐にわたる税金関連の問題を理解し、対策を講じる必要があります。
税務アドバイザーと緊密に協力し、事前に税金の影響を詳細に分析することで、想定外の税負担を避け、財務計画を適切に立てられます。税務計画は、事業譲渡のコストとリターンを最適化するために重要です。
まとめ
中小企業が事業譲渡を検討する際は、譲渡したい範囲の明確化、契約や手続きの正確な管理、税金の効率的な対策が重要なポイントになります。これらの要素を適切に管理することで、事業譲渡は企業にとって大きなメリットをもたらす可能性があります。
また、専門家との協力を通じて、リスクを最小限に抑え、企業の将来の成長に資する事業譲渡を実現できます。事業譲渡は戦略的な決断であり、中小企業に新たな機会をもたらす重要なステップとなるでしょう。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。


