【手法別】M&Aの仕組みとは?手順・流れや成功事例も解説
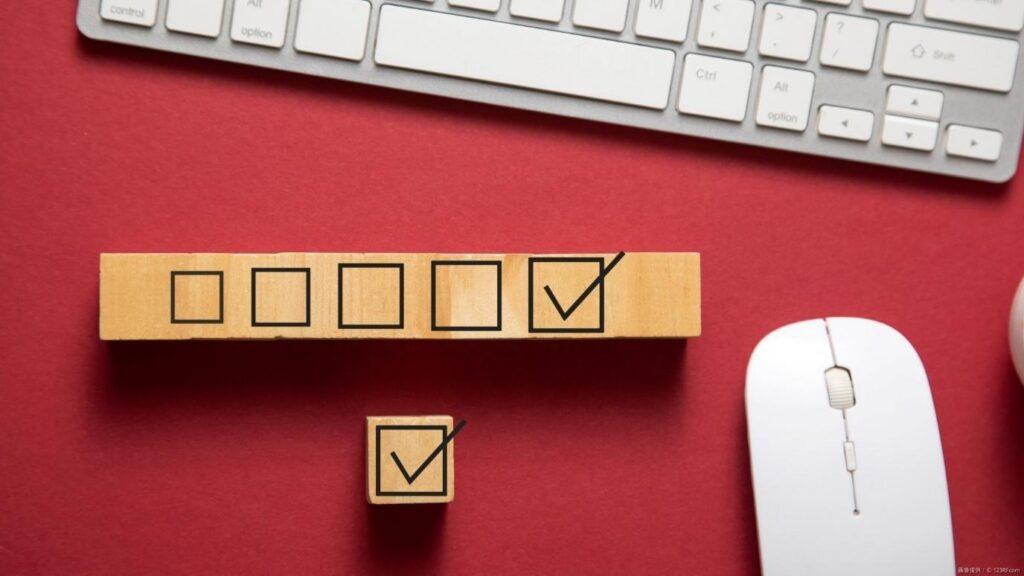
事業を継続する方法としてM&Aという方法を知っているものの、仕組みを詳しく理解できていない方もいるのではないでしょうか。
M&Aの仕組みを理解することは、自社の買収や売却などを円滑に完了するために役立ちます。
本記事では、M&A全体と手法別の仕組みを解説します。M&Aの手順や成功事例も紹介するため、ぜひ併せて参考にしてください。
M&A全体の仕組み
M&Aは「Mergers and Acquisitions(合併と買収)」の略称であり、合併や買収によって企業間の新たな関係を構築する仕組みです。
たとえば、相手先を自社で買収した場合には、自社の傘下に相手先が入り、グループ会社としての関係が生まれます。
合併や買収はM&Aの手法のひとつであり、それぞれ具体的な方法はさらに細分化されます。買収の場合は、株式譲渡や事業譲渡などがあり、仕組みが異なる点に注意が必要です。
また、手法による仕組みの違いだけではなく、相手先の業種や業態でも仕組みが変わってきます。同業種・業態の会社を買収する水平型M&A、同業界の中でもプロセスが異なる会社を買収する垂直型M&Aがあり、相手先との交渉や統合などの仕組みが異なります。
M&Aの仕組みを手法(スキーム)別に解説
M&Aの仕組みは、活用する手法によって変わります。M&Aの主な手法は、以下の6つです。
-
- 株式譲渡
- 第三者割当増資
- 事業譲渡
- 合併
- 会社分割
- 業務提携
上記の手法の仕組みや特徴を解説するため、自社で行いたい手法への理解を深めましょう。
株式譲渡
株式譲渡とは、M&Aの手法における買収のひとつであり、株式の全部または一部の売却によって買収が行われます。
売手の株主が保有する株式を買手に譲渡し、株主が買手に変わる仕組みです。株式の売買契約を締結し対価を支払うというシンプルな仕組みであるため、手続きは比較的簡単に実施できます。
株主が変わるだけであり、売手の企業は事業を継続できますが、経営判断は買い手の持株比率の影響を受ける点に注意しなければいけません。
買手は、売手の資産や事業を自社に組み込むことで、事業の多角化や既存事業の強化などを期待できるのがメリットです。
M&Aにおける株式譲渡のメリット・デメリットや注意点は、以下の記事で解説しているため、詳しく知りたい方はぜひ参考にしてください。
第三者割当増資
第三者割当増資とは、売手が買手から出資を受ける形で経営基盤を強化する手法です。売手が新たに株式を発行し、買手に割り当てることで出資を受ける仕組みとなっています。
売手が新規事業や設備投資に充てる資産を確保したり、業績不信の建てなおしを図ったりする場合に採用されるケースがあります。
買手にとっては、経営権を得たい場合には既存の株主を上回る株式が求められるため、多くの資金が必要になる点に注意しましょう。
事業譲渡
事業譲渡とは、売手が展開する事業の全部、または一部を買手に譲渡する手法です。たとえば、売手の事業Aを買手に譲渡する際は、買手は事業A譲渡に伴う対価を売手に支払います。譲渡する事業の数や関連する資産などを選択できるため、自由度の高い仕組みといえるでしょう。
買手にとっては、売手を買収したいものの、不採算事業を引き継ぎたくない場合に事業譲渡で一部事業をM&Aの対象から除外できます。売手は、主力事業に注力するために一部事業のみ譲渡し、リソースやコストを集中できるのがメリットです。
事業譲渡に伴って事業の名義は買手に移るため、事業にかかわる契約や手続きは再度結びなおすことになります。許認可の申請や従業員の再雇用などは工数がかかるため、スムーズな譲渡には事前準備が重要です。
合併
合併とは、複数の会社をひとつの法人格に統合する手法です。売手は会社を解散し、買手が資産や権利義務を承継し、合併後の法人格で経営を存続します。
買収と似た仕組みと思われがちですが、買収の場合は売手は消滅しません。買手とは別の法人格で存続される一方、合併を選択すると売手の会社は消滅する点が大きな違いです。
合併は、吸収合併と新設合併に分かれています。吸収合併とは、買手の法人格を残し、売手の法人格を消滅させて買手に吸収する方法です。新設合併は、買手と売手の法人格を消滅させ、新しく設立した会社に資産や権利義務を集約します。
吸収合併と新設合併の違いは、以下の通りです。
| 吸収合併 | 新設合併 | |
| 許認可や免許 | 引き継がれる | 改めて申請が必要になる |
| 対価の支払い | 売手は現金や株式などで受けとれる | 新設会社から株式または社債で受けとれる(現金では受けとれない) |
合併については以下の記事で解説しているため、詳しく知りたい方は併せてチェックしてください。
会社(企業)の「合併」についてわかりやすく解説!手続きの流れやメリットは?
会社分割
会社分割は、売手が展開する事業を一部自社から切り離し、買手に承継する手法です。成長している事業を子会社化したり、不採算事業を整理したりする際に選択され、企業再編や経営統合を目的にして行われる傾向があります。
会社分割には、吸収分割と新設分割という2つの仕組みがあります。切り離した事業を買手に承継するのが吸収分割、新たに設立した会社に承継するのが新設分割です。
吸収分割は、買手から株式や現金などを受けとる分社型分割、買手の株式や現金などを売手の株主が受けとる分割型分割に細分化されます。分割方法によって対価を受けとる仕組みが異なるため、最適なパターンを選びましょう。
会社分割のメリット・デメリットや流れは以下の記事で解説しているため、ぜひ参考にしてください。
会社分割とは何か?会社分割の方法やそのメリット・デメリットについて解説
業務提携
業務提携とは、資本の移動を伴わず複数の企業が共同で事業を行う方法です。互いが持っている資産や技術などの経営資源を共有し、弱みを補完しあうことでシナジー効果の創出を目指します。
業務提携は、提携の仕組みの違いによって、以下の4種類に分かれます。
| 業務提携の種類 | 概要 |
| 技術提携 | ・技術や人材を提供しあい共同開発を行う ・特許やライセンスを共有し、共同して新たな特許取得を目指す |
| 生産提携 | ・生産や製造工程の一部を委託する ・委託された生産を行うのではなく、製造にかかわる提案や開発にも携わる |
| 販売提携 | ・販売代理店として商材を販売してもらう |
| 仕入れ・調達提携 | ・材料の仕入れ・調達で共同する ・大量の仕入れによってコストを削減できる |
業務提携のメリット・デメリットや、資本提携や経営統合の違いなどは以下の記事で解説しているため、併せてチェックしてみましょう。
業務提携とはどんなものか?メリットと注意点、M&Aとの相違点も解説
M&Aの手順・流れ【5ステップ】
M&Aの仕組みは手法によって異なりますが、大まかな手順や流れは共通です。M&Aは、一般的に以下の流れで進めます。
-
- 仲介会社や銀行などにM&Aを相談する
- 買手とマッチングし交渉を開始する
- 基本合意契約を締結後、デューデリジェンスを実施する
- 条件の調整後、最終契約を締結する
- 合併や買収などに伴う経営統合を進める
M&Aの手順や進め方などは以下の記事でも解説しているため、詳しく知りたい方はぜひチェックしてください。
M&Aの手順や進め方、売手・買手が得られるメリットまで徹底解説
1.仲介会社や銀行などにM&Aを相談する
M&Aは、専門家の支援を受けて実施するケースが一般的であるため、仲介会社や銀行などに相談しましょう。
専門家との相談では、M&Aを希望する理由や目的を整理したり、自社の現状を把握したりするなど、M&Aが最適な選択かを検討します。
M&Aが必要と判断した場合には、支援を受ける専門家と秘密保持契約や仲介契約を締結します。契約締結後は、専門家が買手を探すための企業概要書を作成するため、求められた資料をすみやかに提出しましょう。
2.買手とマッチングし交渉を開始する
企業概要書をもとに買手を探し、M&Aをしたい買手が見つかった場合には、相手企業との交渉フェーズに移行します。
交渉フェーズでは経営者同士のトップ面談を行うのが一般的で、M&Aの目的や条件などを擦りあわせます。面談の回数に決まりはなく、互いの調整がスムーズにできるようなら、数回でまとまる場合もあるでしょう。
トップ面談後は、M&Aの対価や時期など細かい調整を行い、買収や合併などに伴う具体的な動きを決めていきます。
3.基本合意契約を締結後、デューデリジェンスを実施する
買手との交渉や調整が完了したら、仮契約に相当する基本合意契約を締結します。基本合意締結後は独占交渉期間となるため、他社の介入や交渉は行われません。
独占交渉期間には、デューデリジェンスと呼ばれる買収監査を実施します。買収にあたって財務や法務、労務などの状況への監査であり、細部まで買収することに問題ないかをチェックする重要なステップです。
デューデリジェンスで問題が発覚した場合、M&Aが頓挫するおそれがあるため、実施される前に自社の状況や従業員・取引先との調整などを済ませる必要があります。
4.条件の調整後、最終契約を締結する
無事にデューデリジェンスを終え、条件の調整まで完了してはじめて、最終契約の締結となります。
最終契約で作成される書面は、株式譲渡であれば株式譲渡契約書、事業譲渡であれば事業譲渡契約書となるため、手法にあわせた契約を締結しましょう。
最終契約の締結後は、対価の支払いが行われます。支払いのタイミングは両社の取り決めによるため、別途調整が必要です。
5.合併や買収などに伴う経営統合を進める
合併や買収などのM&Aが完了した後は、売手との経営統合に取り組みます。経営統合は「PMI(Post Merger Integration)」と呼ばれ、制度や業務フロー、各種手続きなどを整えていきます。
経営統合の質やスピードは、新たな組織としてのスタートや従業員のモチベーションなどに大きくかかわる要素です。場当たり的な統合では、社内が混乱したり、M&Aによるシナジー効果を得られなくなったりするおそれがあります。
M&Aが成立してからではなく、事前に経営統合プロセスを策定し、最終契約締結後からスムーズに実行できる準備をしましょう。
M&Aの成功事例3選
最後に、M&Aの事例を3社紹介します。
-
- オリックスによる大京の譲り受け
- セブン&アイ・ホールディングスによるニッセンの買収
- パソナグループによるベネフィット・ワンの子会社化
オリックスによる大京の買収
2013年、オリックス株式会社は日本の大手マンションデベロッパーである「大京」を完全子会社化しました。
オリックスは、不動産事業の多角化を目指しており、大京の買収はその戦略の一環でした。大京は「ライオンズマンション」ブランドで知られており、日本国内で多くのマンションを手掛けてきました。その高いブランド力と豊富な経験を持つ大京を取り込むことで、オリックスは不動産開発事業における競争力を大幅に強化しました。
特に、オリックスは大京の技術力や販売網を活用して、全国規模での不動産事業展開を加速させました。また、マンション開発だけでなく、再開発やリノベーション事業にも注力し、都市部を中心に事業を拡大していきました。
この買収により、オリックスは新築マンション販売のみならず、中古マンションのリノベーション事業や管理業務の拡充にも力を入れ、不動産分野でのプレゼンスを一層強化しました。
引用元:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO36981510W8A021C1EA6000/
セブン&アイ・ホールディングスによるニッセンの買収
2013年、セブン&アイ・ホールディングスは、通信販売事業を手掛ける「ニッセンホールディングス株式会社」を買収しました。ニッセンは、通信販売カタログ事業で知られ、多くの顧客基盤を有していましたが、Eコマースの発展に伴い、オンライン販売への転換を進めていました。
この買収は、セブン&アイがEC(電子商取引)事業を強化し、既存のオフライン事業との融合を進めるために行われました。
セブン&アイは、実店舗を持つ強みを活かしながら、ニッセンの通信販売ノウハウや顧客基盤を統合することで、オンラインとオフラインのシナジーを追求しました。
また、ニッセンの顧客基盤をセブン&アイの多様な流通網に取り込み、Eコマース市場における競争力を高めようとしました。しかし、その後、ニッセンの業績が低迷し、事業再編が必要となりました。最終的に、セブン&アイはニッセン事業の一部を縮小し、グループ全体での収益性改善を進めました。
引用元:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC097J00Z00C24A5000000/
パソナグループによるベネフィット・ワンの子会社化
2020年、パソナグループは福利厚生サービスを提供する「ベネフィット・ワン」を完全子会社化しました。
ベネフィット・ワンは、企業向けに福利厚生プログラムやポイントサービスを提供しており、特に従業員のワークライフバランス向上に貢献するサービスを展開していました。
パソナグループは、この買収によって自社の人材サービスとのシナジーを高め、総合的な人材マネジメントソリューションを強化しました。
このM&Aにより、パソナは企業向けの福利厚生サービスの提供をさらに拡充し、企業の人材戦略を支援する体制を整えました。特に、従業員のエンゲージメントやモチベーションを高めるためのプログラムが注目され、これを通じて、企業の採用や人材定着に貢献することが期待されました。
また、ベネフィット・ワンの強力な顧客基盤を活かし、パソナは人材サービス事業を強化し、より多くの企業に対して包括的なソリューションを提供できるようになりました。
引用元:https://www.dai-ichi-life-hd.com/newsroom/newsrelease/2024/pdf/index_008.pdf
M&Aの仕組みを理解して準備をはじめよう
M&Aの仕組みは手法によって異なるため、自社が採用する手法への理解が必要です。仕組みだけではなく、メリット・デメリットや対価の支払いなどにも違いがあるため、主な手法を正しく理解しましょう。
手法ごとに仕組みは異なりますが、大まかな手順・流れは共通する部分が多いです。M&A全体の仕組みを理解したうえで、順序よく進めていきましょう。
「TSUNAGU」では、事業承継型のM&Aに特化し、第三者への承継をサポートしています。着手金なし・成果報酬という利用しやすい料金体系を採用しながら、豊富な買手リストを活かした支援で、最短3ヶ月でのM&Aを実現できるのが特徴です。ご相談は電話・メールともに無料で受けつけているため、詳しいサービスを知りたい方はぜひお問い合わせください。
【メタディスクリプション】
本記事では、M&A全体と主な手法に分けて仕組みを詳しく解説します。M&Aを進める具体的な手順・流れや成約事例も紹介するため、仕組みと併せて参考にしてください。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。


