株式移転とは?メリット・デメリットから手続き方法まで解説
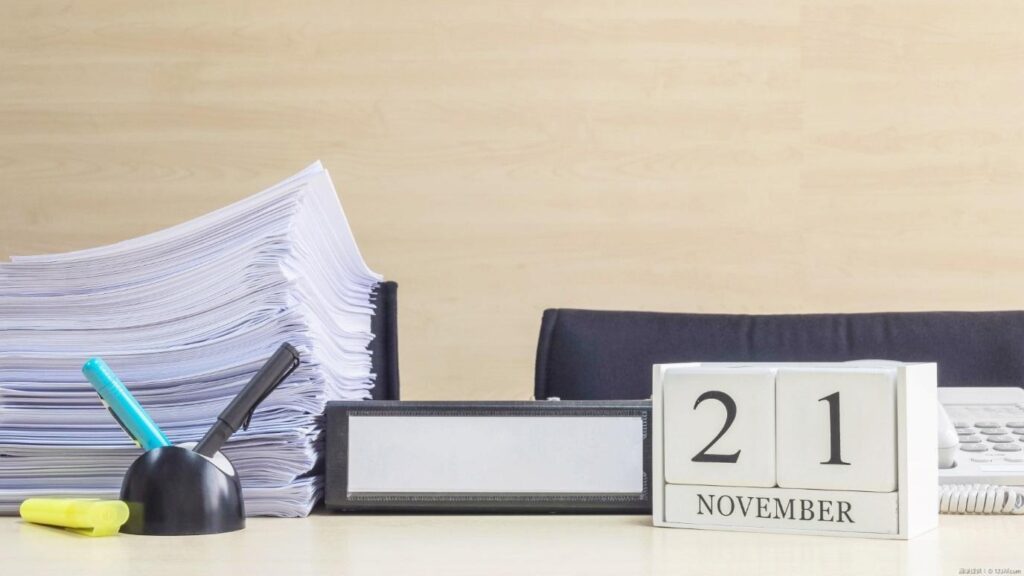
組織再編の手段のひとつに、株式移転があります。
しかし、株式移転についての概要や手続きの方法、有効活用できるケースなど、具体的な内容を知らない人も多いのではないでしょうか。
また、株式移転と似た言葉に「株式交換」というものがありますが、その概要は大きく異なります。
今回は株式移転のメリット・デメリット、株式交換との違いについて解説します。
加えて、株式移転を実施するにあたって踏まえるべき注意点も理解しておきましょう。
株式移転とは?株式交換とは目的が違う
株式移転とは、既存の株式会社を対象に新たに設立する「特定親会社」へ、発行済み株式をすべて取得させる手法のことです。
一方で、株式交換は、既存の企業を対象に親会社と子会社の関係を生み出すことを目的としています。
株式移転と株式交換の目的の違いは「親会社とする会社を、新しく設立するか既存の株式会社にするか」です。
株式移転には一つの株式会社で行う「ホールディングス化」と、複数の株式会社を子会社とする「経営統合」の二つのパターンで実施されます。
株式移転の4つのメリット
組織再編において、株式移転を選択するメリットはどのようなものなのでしょうか。
株式移転のメリットは以下の4つです。
-
- 買取資金が不要
- 経営統合が容易になる
- 少数株主を排除できる
- 適格要件を満たすことで税制優遇も
株式移転で得られる効果を最大限に引き出すために、メリットを理解しておくことは重要です。
自社が求める利益と合致するかを判断してみましょう。
株式移転の主な4つのメリットをそれぞれ解説します。
1.買収資金が不要
株式移転では、親会社となる企業が買収の対価として新株を発行することで成立するため、買収のための資金を準備する必要がありません。
通常の買収においては、子会社となる企業の株式を取得するためには資金が必要であり、企業規模によっては数百億円以上に及ぶこともあります。
買収のための資金がないケースや融資を受けたくない場合に、株式移転は有効な手段の一つです。
2.経営統合が容易になる
買収や合併などの経営統合によって異なる体質をもつ企業同士が一つになることで、従業員同士の摩擦やモチベーション低下につながるリスクがあります。
株式移転の場合は、買収後もそれぞれが別法人として存続できるため、すぐに経営統合する必要がありません。
法人格を保持し、それぞれの企業の体制を崩すことがないため、モチベーションの低下や反発などのトラブル回避にもつながります。
3.少数株主を排除できる
株主移転は新設株式会社が子会社の株式を100%取得して特定親会社とするため、少数株主を強制的に排除して完全子会社化することが可能です。
完全親会社以外の株主のことを少数株主といい、経営方針に対して協力的であれば問題ありません。
しかし、経営統合に反対する少数株主がいると、説得に多くの時間と労力が必要になります。
スムーズに経営統合するにあたり、少数株主を強制的に排除できることは大きなメリットと言えます。
4.適格要件を満たすことで税制優遇も
株式移転には「適格株式移転」と「非適格株式移転」があり「適格株式移転」の適格要件を満たすことで税制の優遇措置が受けられます。
完全支配関係、支配関係、共同事業かどうかによって要件は異なります。
非適格株式移転の場合には子会社に対する課税が発生しますが、適格要件を満たすことで子会社への課税は発生しません。
株式移転の3つのデメリット
株式移転には、手続きやコストの面においていくつかデメリットも存在します。
株式移転のデメリットは以下の3つです。
-
- 移転手続きが複雑
- 反対株主の買取請求権に応じる必要がある
- 上場企業の場合は株価下落のリスクも
組織編成を検討している場合は、株式移転でどのような不利益があるのかを把握しておくことが大切です。
ここでは株式移転の3つのデメリットを紹介します。
1.移転手続きが複雑
株式移転を実施する際には、準備段階から取締役会による決議、各種書類の備置など多くの手続きが必要であり時間がかかります。
公告手続を要する株式移転の場合、1〜2ヶ月程度の期間が必要です。
着手する前に全体的な流れを把握し、計画的にスケジュールを組むことがポイントです。
また、移転手続きにはある程度の専門知識が必要になるため、法律や経営に関する専門家にアドバイスを受けるとよいでしょう。
2.反対株主の買取請求権に応じる必要がある
株式買取請求権とは、株式移転に反対する株主が自社に対して株式を買い取るよう請求できる権利のことです。
株式移転を実行する際には、株主総会の特別決議で承認を得る必要があります。
株式移転に反対する株主が異議申し立てにより買取請求をした際には、公正な価格で応じなければなりません。
そのため、反対する株主が多いと、対応に時間と手間を取られてしまいます。
3.上場企業の場合は株価下落のリスクも
新設する株式会社が上場企業である場合、発行される新株の数によっては、1株あたりの利益が減少することで株価が下落する可能性があります。
また、会社が増えることで管理コストが増えることも株価下落の要因の一つです。
株主にとって株価下落のリスクは株式移転を反対する要因になるので、同意が得られないとスムーズに株式移転を進めることが難しくなります。
事前に株主に対して長期的な収益拡大やシナジー効果などのメリットを周知し、株式移転に対するイメージアップを図ることが重要です。
株式移転の手続きの方法
ここからは株式移転の手続き方法について解説します。
主な手続きの流れは以下の通りです。
-
- 移転計画書の作成
- 移転計画の備置と開示
- 株式総会で移転計画の承認決議
- 債権者保護の手続き
- 公正取引委員会への届出
- 移転の登記、効力発生
- 事後開示書類の備置と開示
デメリットでも紹介した通り、株式移転の手続きは頻雑で時間がかかるものです。
事前に手続きの流れや方法を把握しておくことで、スムーズに進められるでしょう。
1.移転計画書の作成
株式移転を実施する際には、まず移転計画書を作成する必要があります。
株式移転計画書は、株式移転における計画を証明するための重要な書類です。
作成にあたっては、会社法に基づいた適正な計画かどうかを意識しながら作成しましょう。
また、ある程度知識も必要になるため、コンサルタントなどの専門機関からアドバイスを受けるのも有効です。
2.移転計画の備置と開示
株式移転により完全子会社化される企業は、株式移転計画書などの事前開示書類を本店に備置することが、会社法により義務付けられています。
期間は「株主総会の2週間前」など、会社法で定められた日から始まり、株式移転の効力発生から6ヶ月間という規定があります。
3.株式総会で移転計画の承認決議
株主総会の特別決議で、移転計画の承認を得ることも会社法により定められています。
承認決議の段階で株主からの反対があれば、株式買取請求権を行使される場合があります。
買取請求があれば応じなければならないため、株主に対していかに株式移転によるシナジー効果の見込みがあるのかを説明し、納得してもらうことが重要です。
4.債権者保護の手続き
完全子会社から完全親会社へ新株予約権が移された際に、債権者保護の手続きを実施します。
原則として、債権者保護手続きは官報広告と個別通知の両方を行う必要があります。
5.公正取引委員会への届出
大企業同士で株式移転が行われるといった、大規模な業界再編が発生した際には業界全体に影響する可能性があります。
独占禁止法により、共同株式移転において「いずれか1社に係る国内売上高合計額が200億円を超え、かつ、他のいずれか1社に係る国内売上高合計額が50億円を超える場合」に公正取引委員会への届出が必要です。
6.移転の登記、効力発生
株主総会で株式移転の承認を受けた後は、新会社設立における登記申請を行います。
基本的に完全子会社は登記申請が不要ですが、新株予約権を親会社へ移すケースでは完全子会社でも変更登記が必要です。
その場合は、新設会社の登記申請と子会社の変更登記を同時に行う必要があります。
株式移転の場合、完全親会社の資本金や資本準備金は株式資本の範囲内であれば任意で登記申請書へ計上可能です。
新設親会社の登記申請によって株式移転の効力が発生し、効力発生日は基本的に登記申請日となります。
7.事後開示書類の備置と開示
株式移転の効力発生日から完全親会社および完全子会社は事後開示書類を作成し、本店に備置します。
事後開示書類に記載する内容は以下の項目です。
-
- 株式移転の効力発生日
- 反対株主の株式移転の差止請求に関する経過
- 反対株主の新株予約権の買取請求に関する経過
- 完全親会社へ移転した完全子会社の株式数
- その他株式移転に関する重要事項
- 資本金および準備金に関する事項
なお、事後開示書類は株式移転の効力発生日から6ヶ月間備置することが定められています。
株式移転の仕訳と会計処理
まず、株式移転の税務処理に大きく影響するのが「適格要件」です。
法人税により定められた適格要件を満たす「適格株式移転」では税制優遇により課税されませんが、適格要件を満たさない「非適格株式移転」は課税の対象です。
また、株式移転における仕訳や会計処理の流れは、「完全親会社」と「完全子会社」で異なります。
完全親会社の場合
完全親会社の場合には、株式の評価額と資本金は基本的に完全子会社を基準に仕訳を行います。
税務処理は適格要件を満たすかどうかによって異なりますが、完全親会社の場合は基本的に課税されることはありません。
完全子会社の場合
完全子会社の場合、株式は親会社・子会社間で取引されるため、株式移転による資産の変動はないので税務処理は発生しません。
適格要件を満たす適格株式移転の場合は、税制の優遇措置が取られるので課税されません。しかし、非適格株式移転になる場合は一部の資産が時価評価され、課税対象となります。
株式移転の際の注意点
ここからは、株式移転を実施する際に踏まえておくべき注意点について解説します。
主な注意点は以下の3つです。
-
- 設立は株式会社に限定される
- 債権者保護が必要になることもある
- 有価証券報告書の提出が必要なケースがある
株式移転では、基本的な手続き以外に追加で行うべき手続きや対処が必要になるケースもあります。
法律的な問題も関わるため、株式移転を実施する前に理解しておくことが大切です。
設立は株式会社に限定される
株式移転のみならず株式交換や合併などの組織再編行為は「株式会社」であることが条件です。
株式を発行している「特例有限会社」であっても、株式移転による完全子会社化はできません。
特例有限会社が適用されるためには、組織変更によって株式会社へ転換させる必要があります。
債権者保護が必要になることもある
債権者保護手続きとは債権者の利益を保護するための異議申し立ての手続きで、会社法によって定められています。
株式移転の場合には、完全子会社となるべき会社は存続するため、原則として債権者保護手続きは不要です。
しかし、完全親会社が完全子会社の新株予約権付社債を承継したときには、債権者保護手続きが必要になります。
有価証券報告書の提出が必要になるケースがある
金融商品取引法によって、株式移転による組織再編が行われた場合は原則として有価証券報告書を届け出る必要があります。
有価証券報告書は株式を発行する企業が開示する企業情報のことで、事業の業績や財務諸表などを開示しています。
以下の条件を満たす場合に有価証券報告書の提出が必要です。
-
- 完全子会社の株主が50人以上いる
- 株式の発行価額ないし売出価額の総額が1億円以上
- 完全子会社が継続開示会社で、株主に交付される有価証券の開示がされていない
株式移転の特徴を理解してリスクを回避しよう
株式移転は既存の株式会社を完全親会社とする株式交換とは違い、新たに株式会社を新設し親会社とすることを目的としています。
経営統合が容易で少数株主を排除できるメリットがある反面、頻雑な手続きや株価下落といったリスクも存在します。
場合によっては債権者保護や有価証券報告書などの手続きも必要です。
株式移行を検討している際はメリットやデメリットを理解し、注意すべきポイントを押さえておく必要があるでしょう。
本記事で解説した情報を参考に、株式移転による組織再編に伴うリスクヘッジに注力しましょう。
ディスクリプション
株式移転とは何か。株式交換との違いやメリット・デメリットについて解説。手続きの流れから会計処理のポイント、実施における注意点もあわせて紹介します。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。


