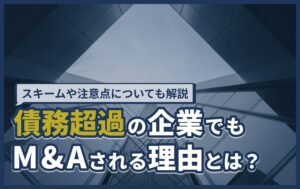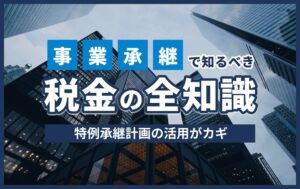事業譲渡時の役員退職金はどうなる?処理方法についても解説
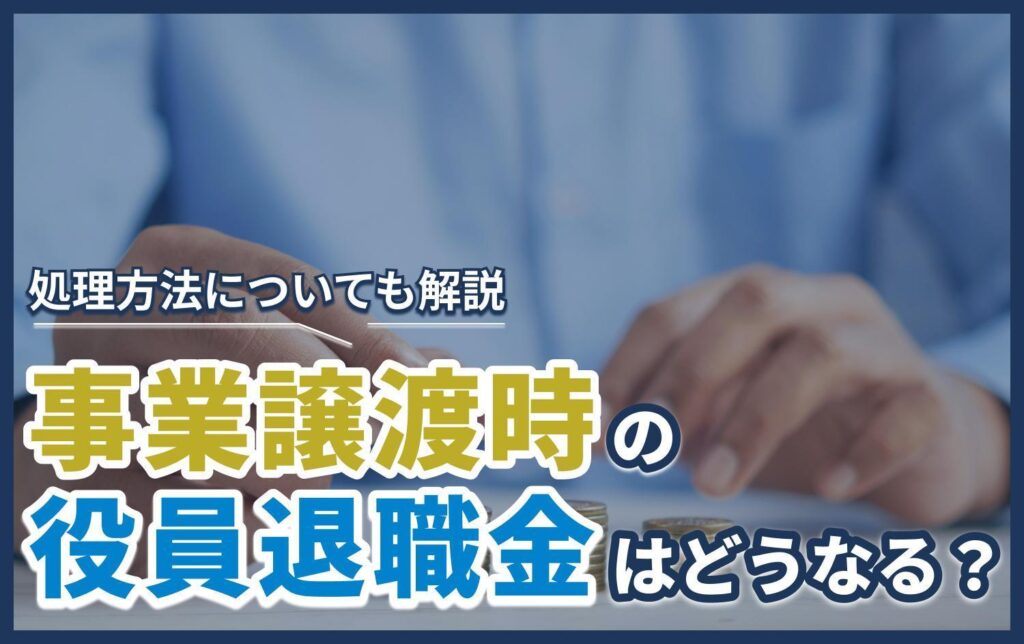
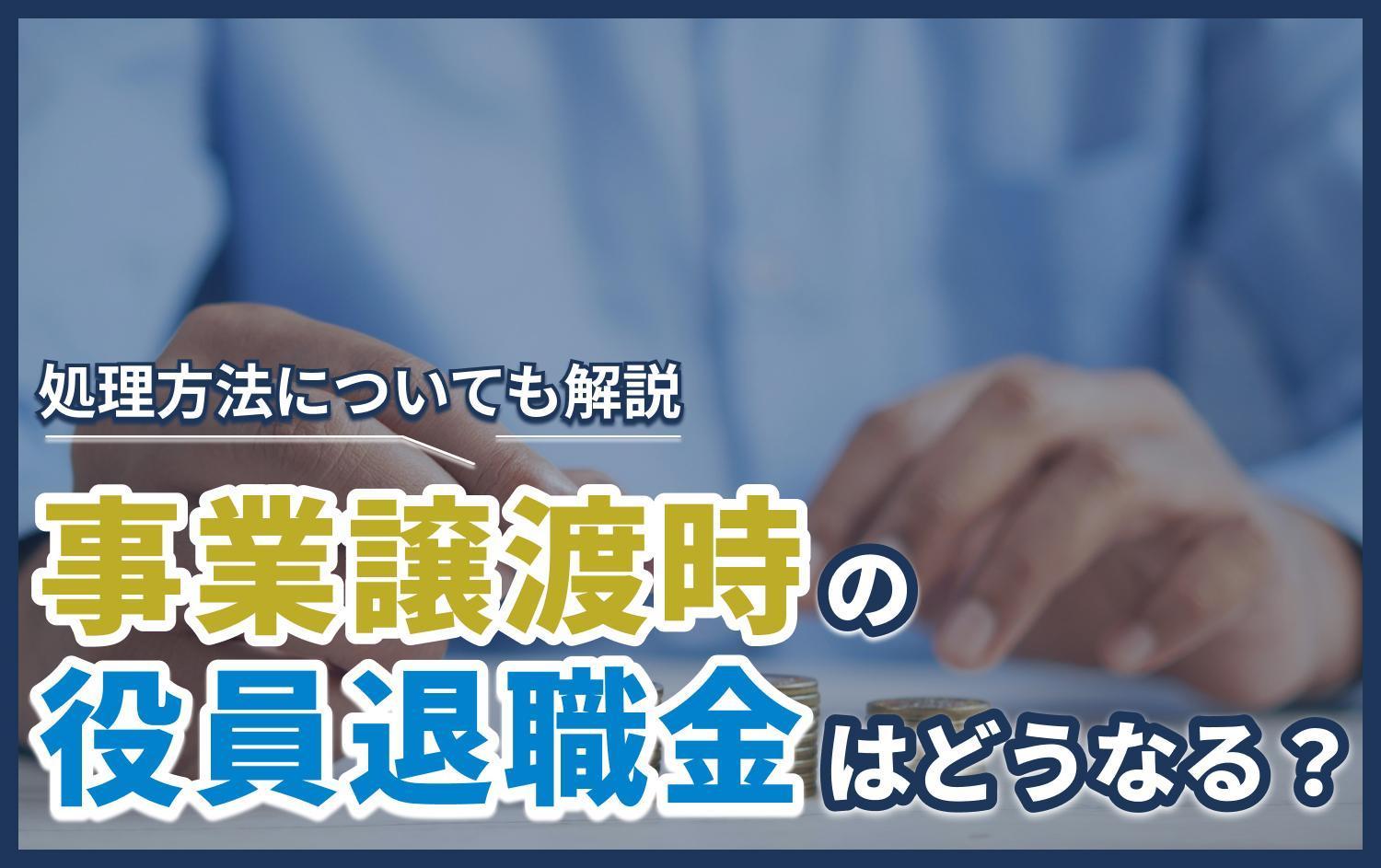
事業譲渡は、企業の将来を左右する重要な意思決定の一つです。事業の売却や譲渡を通じて、企業は新たな成長機会を模索したり、事業ポートフォリオの最適化を図ったりします。しかし、事業譲渡は、法務、財務、人事など、様々な側面でリスクを含んでいます。
特に、事業譲渡に伴う役員の退任と、それに伴う退職金の支給は、慎重な検討と適切な処理が求められる重要なトピックです。
本記事では、事業譲渡に伴う役員退職金の支給方法と、税務処理の注意点について詳しく解説します。役員退職金は、長年企業経営に携わってきた役員の功績に報いるための支給金ですが、その金額や支給方法によっては、税務上の問題が生じる可能性があります。
適正な役員退職金の支給は、円滑な事業譲渡の実現と、税務リスクの回避にとって欠かせない要素なのです。
目次
事業譲渡と役員退任の関係
事業譲渡は、企業の一部または全部の事業を、他の企業に売却または譲渡することを指します。事業譲渡の理由は様々ですが、事業の選択と集中、財務体質の改善、経営資源の再配分などが一般的な目的として挙げられます。
事業譲渡が行われる際、譲渡対象事業を担当する役員は、通常、退任することになります。これは、事業の引継ぎを円滑に行うためであり、また、役員の責任の範囲を明確にするためでもあります。
役員の退任に際しては、その功績に報いるため、退職金の支給が行われるのが一般的です。退職金は、役員の在任期間や、企業への貢献度などに応じて決定されます。
ただし、事業譲渡に伴う役員退職金の支給は、通常の役員退任とは異なる側面があります。事業譲渡の条件として、役員退職金の支給が取り決められる場合があるからです。
このように、事業譲渡と役員退任は密接に関連しており、役員退職金の支給は、事業譲渡の重要な一部分を構成しているのです。
役員退職金の支給方法
事業譲渡に伴い、経営者は通常、役員を退任することになります。この際、役員退職金の支給が行われるのが一般的です。役員退職金は、法的な手続きに則って支給される必要がありますが、支給方法には大きく分けて二つの選択肢があります。
一時金での支給
一時金での支給は、役員の退任日に、退職金の全額を一括して支払う方法です。この方法は、手続きが簡便であり、役員にとっても、まとまった資金を受け取ることができるメリットがあります。
ただし、一時金での支給は、企業の資金繰りに大きな影響を与える可能性があります。特に、大口の役員退職金の場合、一度に多額の資金を用意する必要があるため、事前の資金計画が重要になります。
また、一時金での支給は、税務上のデメリットもあります。退職金の全額が一度に課税対象となるため、役員の税負担が重くなる可能性があるのです。
分割払いでの支給
分割払いでの支給は、役員退職金を数年に分けて支給する方法です。例えば、退職金の総額を3年間で均等に分割して支払うといった具合です。
分割払いを選択する場合、将来の支給額を現在価値に割り引いて計算する必要があります。これは、将来の支給額を現在の価値に換算することで、適正な退職金額を算定するためです。割引計算には、適切な割引率の選択が重要であり、税務上の観点からも慎重な検討が求められます。
分割払いは、一時金での支給と比べて、企業の資金繰りへの影響を分散させることができるメリットがあります。また、役員の税負担も分散されるため、一時金での支給よりも税務上のメリットがあると言えます。
ただし、支給期間が長期化すると、役員の側では、資金の利用可能性が制限されるデメリットがあります。また、企業側でも、長期的な支払債務を負うことになるため、将来的な財務リスクを考慮する必要があります。
支給方法の選択
役員退職金の支給方法は、一時金と分割払いのどちらを選択するかによって、税務上の取り扱いや、企業と役員の双方に与える影響が異なります。
支給方法の選択にあたっては、企業の資金繰りや、役員の税負担、将来的なリスクなどを総合的に勘案する必要があります。また、役員の意向も十分に考慮する必要があるでしょう。
いずれの方法を選択する場合でも、支給額の算定根拠を明確にし、社内規程に基づいて適切に処理することが重要です。支給方法の選択は、事業譲渡の円滑な実行と、税務リスクの回避に大きな影響を与える重要な意思決定なのです。
役員退職金の金額はどう決める?

役員退職金の金額決定は、支給方法の選択と並んで重要な論点です。退職金の金額は、役員の在任期間や退職事由、企業への貢献度などを総合的に勘案して決定されます。
在任期間
在任期間は、役員退職金の金額決定に大きな影響を与える要因です。一般的に、在任期間が長いほど、退職金額は高くなる傾向があります。
これは、長年にわたって企業経営に携わってきた役員の功績に報いるという、役員退職金の基本的な趣旨によるものです。在任期間が長い役員ほど、企業の発展に大きく寄与してきたと考えられるため、より高額な退職金が支給されるのです。
ただし、在任期間と退職金額の関係は、一律に決まっているわけではありません。企業によって、退職金の計算方法は異なります。また、同じ在任期間でも、役員の職位や責任の大きさによって、退職金額に差が生じることがあります。
退職事由
退職事由も、退職金額の決定に影響を与える要因の一つです。一般的に、任期満了や定年退職といった自然な退職事由の場合と、解任や辞任といった特殊な退職事由の場合では、退職金額に差が生じることがあります。
自然な退職事由の場合、通常の算定基準に基づいて退職金額が決定されます。これに対し、解任や辞任の場合は、退職金額が減額されたり、支給されなかったりすることがあります。
ただし、事業譲渡に伴う役員退任の場合、必ずしもこの原則が当てはまるわけではありません。事業譲渡の条件として、役員退職金の支給が取り決められることがあるからです。
この場合、退職金額は、事業譲渡の交渉の中で決定されることになります。譲渡対象事業の価値や、役員の協力の必要性などを考慮して、適切な退職金額が決定されるのです。
企業への貢献度
役員の企業への貢献度も、退職金額の決定に影響を与える要因です。企業の業績向上に大きく寄与した役員や、困難な経営環境の中で会社を立て直した役員などは、より高額な退職金が支給される傾向があります。
ただし、企業への貢献度は、定量的に測定することが難しい要因でもあります。業績の数字だけでは表せない貢献もあるからです。
そのため、企業への貢献度を退職金額に反映させるためには、役員の業績を多面的に評価する必要があります。定性的な評価を含めて、役員の貢献度を総合的に判断することが求められるのです。
社内規程の整備

役員退職金の金額決定にあたっては、社内規程の整備が欠かせません。支給基準や計算方法を明文化し、社外にも開示することで、透明性を高めることができます。
社内規程には、退職金の支給要件や、計算方法、支給時期などを具体的に定めておく必要があります。また、特別な功績があった役員への加算や、特殊な退職事由の場合の減額についても、規定しておくことが望ましいでしょう。
規程の整備は、恣意的な退職金支給を防止し、税務署から役員退職金を否認されるリスクを軽減する効果も期待できます。税務上の観点からも、社内規程の整備は重要な意味を持つのです。
役員退職金の税務処理
役員退職金は、支給する企業側と、受け取る役員側の双方で、税務上の取り扱いが問題になります。
企業側の税務処理
企業が役員退職金を支給する際、原則として、その全額を損金に算入することができます。つまり、役員退職金は、企業の課税所得から控除されるのです。
ただし、役員退職金が不相当に高額な場合、税務署から損金算入を否認されるリスクがあります。例えば、同業他社の役員退職金と比べて著しく高額な場合や、在任期間が短いにもかかわらず多額の退職金を支給する場合などです。
こうした場合、税務署は役員退職金の一部または全部を損金不算入とし、企業の課税所得に加算することがあります。その結果、企業は想定外の税負担を強いられる可能性があるのです。
損金算入が否認されるリスクを回避するためには、役員退職金の金額決定を適切に行うことが重要です。社内規程に基づいて、合理的な金額を算定することが求められます。
また、退職金の支給時期にも注意が必要です。事業年度末日までに支給の決議を行い、かつ、その後一定期間内に実際に支給することが、損金算入の要件となっています。
役員側の税務処理
役員が退職金を受け取る際には、退職所得として所得税が課税されます。退職所得は、他の所得と分離して計算され、退職所得控除の適用を受けることができます。
退職所得控除は、勤続年数に応じて計算されます。具体的には、勤続年数が長いほど、控除額が大きくなる仕組みです。この控除額を退職所得から差し引いた残額に対して、所得税が課税されます。
退職所得に対する税率は、他の所得と比べて低く設定されています。このため、役員にとっては、退職金を受け取る際の税負担が軽減されるメリットがあります。
ただし、退職所得控除の適用を受けるには、一定の要件を満たす必要があります。例えば、役員の勤続年数が短い場合や、退職金の支給が退職後の事前に決まっていた場合などは、退職所得控除の適用が制限されることがあります。
また、分割払いの場合、各年の支給額に対して退職所得控除が適用されます。このため、一時金での支給と比べて、税負担が軽減される効果が期待できます。
役員側の税務処理においては、こうした退職所得控除の適用要件や、分割払いのメリットなどを十分に理解しておく必要があります。税務の専門家に相談し、適切な税務戦略を立てることが重要です。
源泉徴収と年末調整
役員退職金を支給する際、企業は所得税の源泉徴収を行う必要があります。源泉徴収税額は、退職所得の金額と、役員の税額控除の内容などに基づいて計算されます。
企業は、源泉徴収した税額を、所轄の税務署に納付します。これにより、役員の納税義務の一部が履行されたことになります。
役員は、年末調整の手続きを通じて、源泉徴収された税額と、実際の税額との過不足を精算します。年末調整では、役員の他の所得や、控除の内容などを総合的に考慮して、最終的な税額が確定します。
源泉徴収と年末調整の手続きは、企業と役員の双方にとって重要な税務上の義務です。手続きの誤りは、税務署からの指摘や、追徴課税のリスクにつながります。
適正な源泉徴収と年末調整を行うためには、退職金の支給額の算定を適切に行うことが重要です。また、税法の改正にも注意を払う必要があります。税制は毎年のように変更されるため、最新の情報を入手し、適用することが求められます。
事業譲渡と役員退職金の注意点
事業譲渡に伴う役員退職金の支給は、事業譲渡の円滑な実行と、税務リスクの回避という二つの観点から、慎重な検討が求められます。
事業譲渡の円滑な実行
事業譲渡を円滑に進めるためには、役員の協力が不可欠です。特に、譲渡対象事業の責任者である役員の理解と支援は、譲渡の成否を左右する重要な要素です。
役員退職金は、長年の功績に報いるための支給金であると同時に、事業譲渡に対する役員の協力を得るための手段でもあります。適正な退職金を支給することで、役員の士気を高め、円滑な事業譲渡の実現につなげることができるのです。
ただし、事業譲渡の条件として役員退職金を支給する場合、その金額の決定には慎重を期す必要があります。事業譲渡の対価と退職金とを明確に区分し、それぞれの金額の妥当性を説明できるようにしておくことが重要です。
税務リスクの回避
一方で、役員退職金の支給は、税務上のリスクを伴う行為でもあります。不相当に高額な退職金の支給は、税務署から損金算入を否認されるリスクがあります。また、役員側でも、退職所得控除の適用が制限され、想定外の税負担が生じる可能性があります。
こうしたリスクを回避するためには、役員退職金の金額決定と支給方法に十分な注意を払う必要があります。社内規程の整備や、専門家のアドバイスを踏まえた慎重な検討が求められます。
また、事業譲渡の際には、役員退職金以外にも、様々な税務問題が生じます。例えば、譲渡対象資産の譲渡益に対する税務処理や、譲渡に伴う各種税金の申告・納付などです。
事業譲渡と役員退職金の問題は、こうした税務問題と密接に関連しています。事業譲渡全体の税務戦略の中で、役員退職金の位置づけを明確にし、適切な処理を行うことが重要です。
【専門家監修】事業譲渡にかかる税金・税金対策を売り手・買い手ごとに解説
役員退職金の支給と事業譲渡の関係
役員退職金の支給は、事業譲渡の一部として行われることが多いですが、両者の関係には注意が必要です。
事業譲渡の対価と、役員退職金とが混同されると、税務上の問題が生じる可能性があります。事業譲渡の対価は、譲渡資産の価値を反映したものでなければなりません。これに対し、役員退職金は、役員の功績に対する報酬です。
両者を明確に区分し、それぞれの金額の妥当性を説明できるようにしておくことが重要です。事業譲渡の対価と役員退職金とを一体として支給する場合には、特に慎重な検討が求められます。
また、事業譲渡の条件として役員退職金を支給する場合、その金額の決定には客観性が求められます。恣意的な金額決定は、税務署から問題視される可能性があります。
役員退職金の支給と事業譲渡の関係を適切に管理することは、税務リスクの回避にとって重要な意味を持つのです。
事業譲渡の失敗と役員退職金
事業譲渡が失敗に終わった場合、役員退職金の取り扱いが問題になることがあります。特に、事業譲渡の条件として退職金の支給が取り決められていた場合、その扱いが難しくなります。
事業譲渡が失敗した場合、譲渡対象事業の価値は大きく毀損します。このため、当初予定していた退職金額の支給が困難になることがあります。
こうした場合の退職金の取り扱いは、事業譲渡契約の内容によって異なります。事業譲渡の成否にかかわらず退職金を支給する旨の取り決めがある場合は、企業は退職金の支払義務を負うことになります。
一方、事業譲渡の成立を退職金支給の条件としていた場合は、譲渡が失敗した時点で、退職金の支給義務は消滅します。ただし、この場合でも、役員の功績に対する何らかの報酬は必要になるでしょう。
事業譲渡の失敗と役員退職金の問題は、事前の契約内容によって大きく左右されます。事業譲渡の条件と、役員退職金の支給条件とを、明確に分けて規定しておくことが重要です。
また、事業譲渡が失敗した場合の役員退職金の財源についても、事前に検討しておく必要があります。事業譲渡の対価を退職金の原資にする場合、譲渡の失敗は退職金の支給にも直結します。
このリスクを回避するためには、事業譲渡とは別に、役員退職金の財源を確保しておくことが有効です。例えば、退職金積立金の設定や、保険の活用などが考えられます。
事業譲渡の失敗は、企業にとって大きな痛手となります。役員退職金の問題は、こうした事態を想定し、適切にリスク管理しておくことが求められるのです。
最後に
事業譲渡に伴う役員退職金の支給は、円滑な事業譲渡の実現と、税務リスクの回避という二つの課題を同時に解決する必要がある、重要な経営判断です。
適正な退職金の支給は、役員の協力を得て、事業譲渡を円滑に進めるための鍵になります。一方で、不適切な退職金の支給は、税務上のリスクを招く危険性があります。
このジレンマを解決するためには、社内規程の整備や、専門家のアドバイスを踏まえた慎重な検討が不可欠です。役員退職金の金額決定と支給方法を適切に行うことで、事業譲渡の円滑な実行と、税務リスクの回避を両立することができるのです。
また、事業譲渡と役員退職金の関係を適切に管理することも重要です。事業譲渡の対価と、役員退職金とを明確に区分し、それぞれの金額の妥当性を説明できるようにしておく必要があります。
さらに、事業譲渡が失敗した場合の役員退職金の取り扱いについても、事前に検討しておくことが求められます。事業譲渡の条件と、役員退職金の支給条件とを分けて規定し、リスク管理を適切に行うことが重要です。
事業譲渡は、企業の将来を左右する重要な意思決定です。その中で、役員退職金の問題は、各種の課題が交錯する複雑な論点です。しかし、適切な対応を行うことで、この問題を事業譲渡の成功に役立てることができます。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。