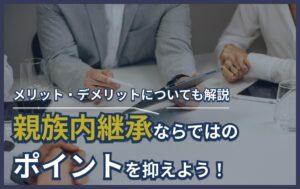【零細企業向け】事業承継のキホン: 準備から後継者選定まで解決
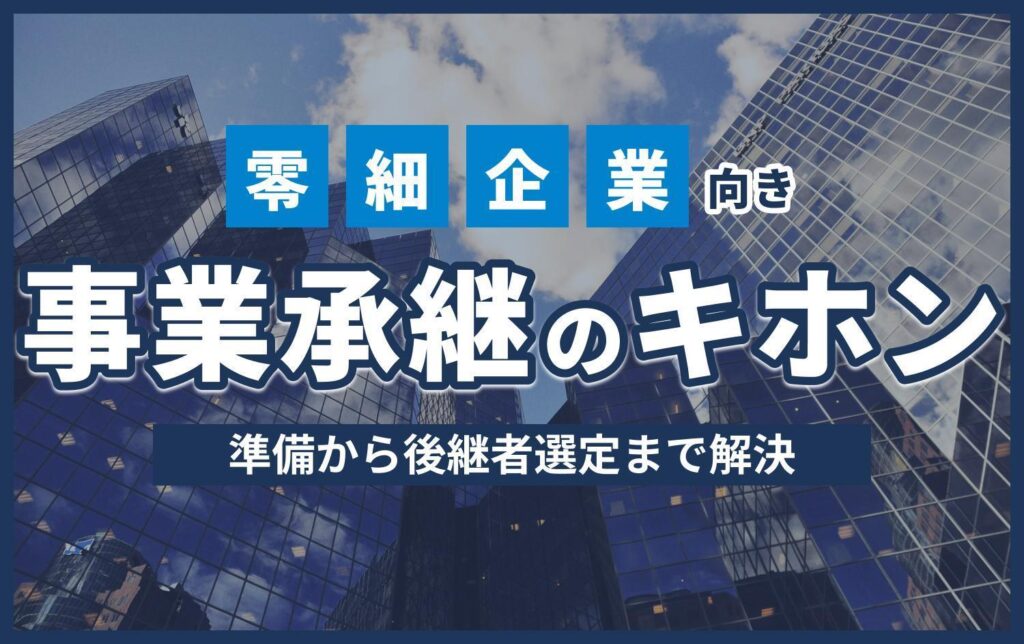

「自分の代で会社を閉じるしかないのか」「長年築いてきた事業を誰かに引き継ぎたい」――。このような悩みを抱える零細企業の経営者は少なくありません。特に、後継者不在に頭を悩ませる経営者にとって、事業承継は喫緊の課題と言えるでしょう。
しかし、事業承継には様々な選択肢があることをご存知でしょうか。この記事では、零細企業の事業承継に関する網羅的な知識を解説していきます。
目次
零細企業における事業承継の重要性
零細企業では、経営者の高齢化が進む一方で、後継者不在の問題が深刻化しています。事業承継ができずに廃業に追い込まれるケースも少なくありません。
円滑な事業承継は、企業の存続のみならず、雇用の維持や地域経済の活性化にも大きな影響を与えます。しかし、事業承継には様々な課題があるのも事実です。
例えば、後継者の育成には長い時間がかかります。経営ノウハウの伝授はもちろん、取引先との信頼関係の構築なども欠かせません。また、相続税や贈与税など、税務面の対策も重要なポイントとなります。
このように、事業承継は一朝一夕では成し遂げられない、息の長い取り組みです。早期の計画立案と、着実な準備が何より大切だと言えるでしょう。
国や地方自治体でも、零細企業の事業承継を支援するための施策を講じています。例えば、中小企業庁では「事業承継ガイドライン」を策定し、事業承継の手順やポイントを分かりやすく解説しています。各都道府県の商工会議所でも、事業承継の相談窓口を設けるなど、きめ細かな支援を行っています。
零細企業の経営者には、こうした支援制度を上手に活用しながら、計画的に事業承継を進めていくことが求められます。
M&Aの相談はどこにすればいい?相談の内容や相手、選定方法などを紹介
親族内承継、従業員承継、M&Aを通じた第三者承継の進め方

事業承継の方法には、大きく分けて親族内承継、従業員承継、M&Aを通じた第三者承継の3つがあります。ここでは、それぞれの特徴と進め方を詳しく見ていきましょう。
(1)親族内承継の進め方
親族内承継は、経営者の子供や親族に事業を引き継ぐ方法です。メリットとしては、経営理念や家訓を継承しやすく、また株式の譲渡に関する税制上の優遇措置を受けやすい点が挙げられます。
親族内承継を成功させるには、後継者の計画的な育成が欠かせません。具体的には、以下のような取り組みが求められます。
- 後継者候補を早期に選定し、経営者の右腕として育成する
- 現経営者の仕事を徐々に後継者に移管していく
- 後継者に社外の経験を積ませ、視野を広げさせる
- 家族会議を定期的に開催し、経営の方向性を共有する
事業用資産の承継については、贈与税の納税猶予制度などを活用することで、税負担を軽減することも可能です。
親族内継承ならではのポイントを押さえよう!メリット・デメリットについても解説
(2)従業員承継の進め方
従業員承継は、社内の役員や従業員に事業を引き継ぐ方法です。親族に適した後継者がいない場合に選ばれることが多いものです。従業員承継のメリットとしては、事業に精通した人材を後継者にできる点が挙げられます。
従業員承継を進めるには、以下のようなステップが必要です。
- 後継者候補の選定(業績、リーダーシップ、将来性などを評価)
- 後継者候補の育成(経営スキルの養成、マネジメント経験の付与など)
- 役員就任や株式移転のスケジュール設定
- 従業員への承継方針の説明と理解の促進
従業員承継では、株式の移転に際して、従業員持株会の活用や、分割払いの方法を検討することも有効です。
従業員承継の方法と流れ!事前に把握しておくべきリスクや注意点を解説
(3)M&Aを通じた第三者承継の進め方
M&Aを通じた第三者承継は、外部の企業や個人投資家等に事業を売却・譲渡する方法です。
メリットとしては、親族内や社内に適した後継者がいない場合でも、広く外部に候補者を求めることができる点が挙げられます。
また、現経営者は会社売却の対価を得ることができます。さらに、M&Aが企業改革の好機となり、さらなる成長の推進力となることもあります。
M&Aを通じた第三者承継を進めるには、以下のようなステップが必要です。
- M&Aアドバイザーの選定(M&Aの経験や実績、専門性などを評価)
- 譲渡先候補の選定(業種、規模、経営理念の合致などを評価)
- 譲渡価格や条件の交渉
- デューデリジェンス(対象企業の詳細調査)の実施
- 契約書の作成と締結
- 譲渡実行後の統合プロセス(PMI)の推進
M&Aを通じた第三者承継では、譲渡先選びが特に重要です。自社の企業理念や文化との親和性、事業シナジーの可能性などを慎重に見極める必要があります。また、PMIを円滑に進め、両社の強みを融合させることが、承継後の成功の鍵を握ります。
親族内承継、従業員承継、M&Aを通じた第三者承継は、それぞれ特徴が異なります。自社の状況や、経営者の想いに合った最適な方法を選択することが何より重要です。
いずれの方法を選ぶにせよ、早期の計画的な準備と、専門家の知見の活用が欠かせません。円滑な事業承継の実現に向けて、しっかりとした計画を立て、着実に歩みを進めていくことが求められます。
M&Aとは?買手・売手の目的やメリット・デメリット、手法、費用まで解説
事業承継税制の要件と手続き
事業承継税制は、経営者の相続税や贈与税の納税を猶予・免除することで、スムーズな事業承継を後押しする制度です。ここでは、事業承継税制の要件と手続きについて、法人版と個人版に分けて詳しく解説します。
(1)法人版事業承継税制の要件と手続き
法人版事業承継税制には、「一般措置」と「特例措置」の2つがあります。特例措置については事前の計画策定等や適用期限が設けられていますが、納税猶予の対象株式数制限の撤廃や納税猶予割合の引上げなどがされています。
特例措置の主な要件は以下の通りです。
- 特例承継計画の提出(令和6年3月31日まで)
- 先代経営者が60歳以上、後継者が18歳以上であること
- 後継者は一定の議決権数を保有すること
- 会社は中小企業者であること
- 株式の贈与・相続から5年間、事業継続・雇用確保すること
手続きとしては、認定経営革新等支援機関の所見を付した特例承継計画を都道府県知事に提出し確認を受けた上で、贈与・相続時に税務署に申告する流れとなります。一般措置の手続きは特例措置と同様ですが、特例承継計画の提出は不要です。
(2)個人版事業承継税制の要件と手続き
個人版事業承継税制は、青色申告を行っていた事業者の事業用資産を、令和10年12月31日までの贈与・相続等により後継者が取得した場合に適用されます。納税猶予の対象となる特定事業用資産は以下の通りです。
- 宅地等(400㎡まで)、建物(床面積800㎡まで)
- 事業用の減価償却資産(機械装置、車両、特許権等)
主な要件は、後継者が18歳以上で、円滑化法の認定を受けており、贈与・相続から事業を継続することなどです。また、個人版でも特例承継計画の提出(令和6年3月31日まで)が必要となります。
手続きとしては、特例承継計画を都道府県知事に提出・確認後、贈与・相続時に開業届出書の提出と青色申告承認申請を行い、税務署に申告する流れです。
事業承継税制の活用には複雑な要件と手続きが必要とされるため、早期の準備と専門家のサポートを得ながら進めることが重要です。円滑な事業承継の実現に向け、これらの制度をうまく活用していきましょう。
零細企業の企業価値はどう決まる?
(1)「時価純資産+営業利益の数年分」で算出
零細企業のM&Aにおける売買価格の相場は、一般的に「時価純資産+営業利益の数年分」と言われています。
時価純資産とは、資産の時価から負債を差し引いた金額のことです。
営業利益は、売上高から売上原価と販売費及び一般管理費を差し引きます。
例えば、ある零細企業の時価純資産が5,000万円、営業利益が1,000万円の場合、売買価格の相場は以下のように計算されます。
- 時価純資産:5,000万円
- 営業利益の2年分:1,000万円 × 2年 = 2,000万円
- 営業利益の5年分:1,000万円 × 5年 = 5,000万円
したがって、この企業の売買価格の相場は、7,000万円〜1億円の範囲になると考えられます。
ただし、この相場はあくまでも目安であり、業種や企業特性によって大きく異なる場合もあります。
例えば、将来性や成長性が高い企業の場合、営業利益の5年分以上の価格になることもあります。逆に、業績不振の企業の場合は、時価純資産のみで売買されることもあります。
(2)取引価格は企業価値評価をもとに、交渉を経て決まる
M&Aの売買価格は、最終的には買い手と売り手の交渉によって決まります。
買い手は、自社の事業戦略や経営資源とのシナジー効果、相性を考慮します。売り手は、自社の強みや将来性をアピールし、少しでも高い価格で売却したいと考えます。
交渉を有利に進めるためには、自社の企業価値を正確に認識することが重要です。企業価値を算出する手法には、いくつかの種類があります。
M&Aにおける企業価値の計算方法とは?企業価値を向上させるポイントも解説
会社をなるべく高く売る方法とは?注意点や価格の算出方法などを解説
事業承継の失敗パターンに学ぶ
円滑な事業承継を実現するには、他社の失敗事例から学ぶことも重要です。ここでは、よくある事業承継の失敗パターンを取り上げ、その原因と教訓を分析してみましょう。
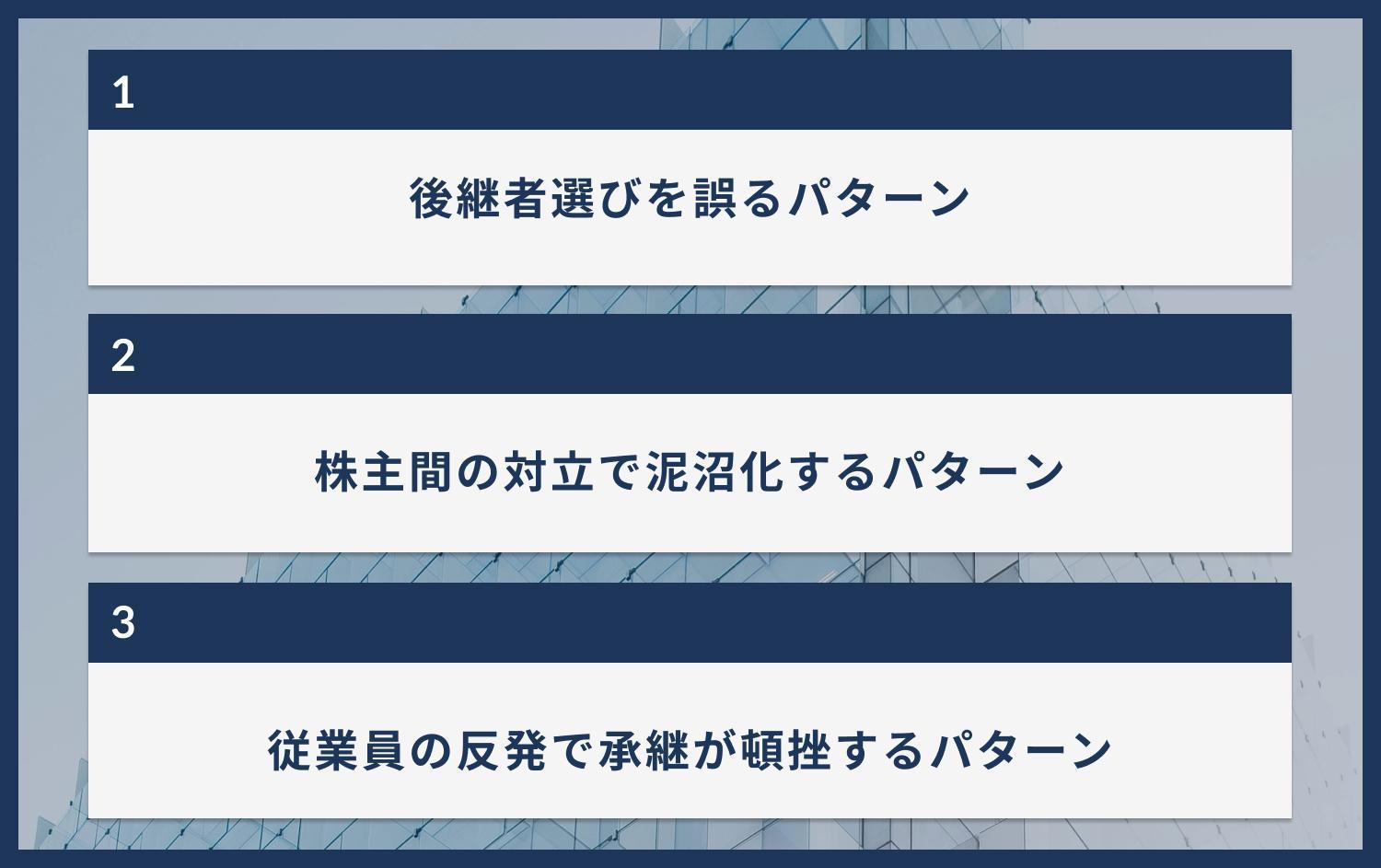
(1)後継者選びを誤るパターン
事業承継の失敗は、後継者選びの段階で既に始まっていることがあります。例えば、経営能力が不足しているにもかかわらず、単に年長であるというだけの理由で長男を後継者に指名するようなケースです。
こうしたミスを避けるには、後継者の資質を冷静に見極める必要があります。客観的な評価基準を設け、時間をかけて後継者候補を見極めることが肝要です。
(2)株主間の対立で泥沼化するパターン
事業承継では、株主間の対立が泥沼化し、承継がストップしてしまうケースがあります。特に、親族内で株式が分散している場合、遺産分割を巡る対立に発展しやすいものです。
対策としては、株主間の利害調整を早期に行うことが重要です。株主間契約を結び、株式の譲渡ルールを明確化しておくことも有効でしょう。
(3)従業員の反発で承継が頓挫するパターン
事業承継では、従業員の反発が原因で、承継が頓挫するケースも見られます。特に、創業家の2代目、3代目が経営能力に乏しい場合、従業員から反発を買いやすいものです。
こうしたリスクを避けるには、後継者の経営能力を高めることが何より重要です。後継者教育の一環として、現経営者の下で十分な経験を積ませることが求められます。併せて、従業員とのコミュニケーションを密にし、承継への理解を得ることも欠かせません。
事業承継の失敗事例7選!うまくいかない理由や対策法を徹底解説
事業承継が失敗してしまう理由とは?失敗防止の戦略や成功事例を解説
事業承継を成功させるための4つのポイント

(1)適切なタイミングを逃さない
事業承継において、タイミングは極めて重要な要素です。特に、会社売却を選択する場合、適切なタイミングを逃さないことが肝心です。売却のタイミングを見誤ると、企業価値が下がり、希望する条件で売却できなくなるリスクがあるのです。
例えば、業績が悪化し始めた時点で売却を検討した場合、買い手から低い評価しか得られないかもしれません。逆に、業績が上向きで将来性が見込める段階で売却に動けば、より有利な条件を引き出せる可能性が高まります。
売却のタイミングを見計らうには、自社の業績自身の健康状態など、様々な要因を総合的に考慮する必要があります。定期的に自社の状況を分析し、事業承継の最適なタイミングを見定めることが重要です。
事業承継の進め方を解説!成功させるためのポイントも紹介します
(2)M&Aから逆算して入念な準備を行う
会社売却を成功させるには、事前の準備が欠かせません。売却に向けて、自社の魅力を高め、買い手にアピールできる体制を整えておくことが大切です。
具体的には、財務諸表の透明性を高める、優秀な人材の確保・育成に力を注ぐなど、根本的な企業価値を高める取り組みが求められます。また、経営の見える化を進め、経営者に依存しない組織体制を構築することも重要です。
M&Aとは?買手・売手の目的やメリット・デメリット、手法、費用まで解説
(3)社員のモチベーション低下・流出を防ぐ
会社売却による事業承継を進める際、社員のモチベーション低下や情報の流出は大きなリスクとなります。売却を検討している話が社内に知れ渡ると、将来への不安から、優秀な人材が他社に流出してしまう可能性があるのです。
このリスクを防ぐには、社員との密なコミュニケーションが欠かせません。売却の意図や将来のビジョンを丁寧に説明し、社員の不安をできるだけ取り除くことが重要です。また、売却後も安定した雇用が維持されるような条件を買い手と交渉することも必要でしょう。
(4)情報管理を徹底する
会社売却のプロセスでは、機密情報の管理が非常に重要です。売却の交渉や due diligence (買収監査)の過程で、自社の重要な情報を開示する必要があります。この際、情報漏洩のリスクを最小限に抑える必要があるのです。
情報管理を徹底するには、守秘義務契約の締結や、情報へのアクセス制限など、物理的・技術的な対策が求められます。また、社内の関係者にも、情報管理の重要性を徹底的に周知することが大切です。
まとめ
事業承継は、経営者にとって人生最大の決断の一つと言えるでしょう。早期の計画的な準備と、外部専門家の知見の活用が、円滑な事業承継の大前提となります。
事業承継の選択肢は、親族内承継、従業員承継、第三者承継と、多岐にわたります。各選択肢のメリット・デメリットを見極め、自社に最適な承継方法を選ぶことが重要です。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。