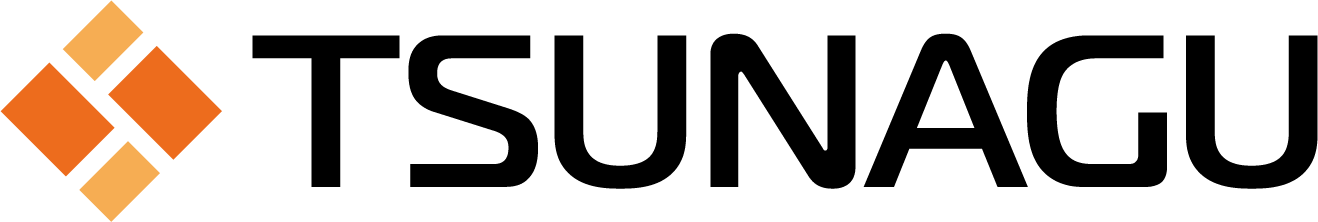美容院を廃業する手続きは? 必要な届け出や経営を引継ぐ方法を解説
はじめに
美容院は、店舗間での競争の激化や、コロナ禍における経営不振などの影響を受け、閉店する店舗が相次いでいます。自身が運営する美容室を廃業する際は、手続きや負担を少しでも軽くしたいと考える人も多いでしょう。
この記事では、美容室やサロンの廃業手続きや廃業に伴うコスト、負担を軽減する方法について詳しく解説します。また、廃業を回避する手段としてM&Aも紹介します。
美容院・サロンの廃業・閉店に関する現状
増加する美容院・サロンの廃業

東京商工リサーチの調査によると、2019年の理容業・美容業の倒産件数は119件であり、1989年以降で過去最多となりました。2000年と比較すると、倒産件数は2倍以上に増加しています。
(参照元:株式会社東京商工リサーチ 2019年「理容業・美容業倒産動向」調査
URL:https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1189682_1527.html)
さらに、2020年の自粛要請により多くの美容室が休業に追い込まれました。コロナ関連支援の効果で倒産件数は抑えられましたが、支援の打ち切りなどにより廃業を選ぶ店舗が増えています。
廃業した美容室のうちコロナ禍に関わるものは、2020年に8.9%、2021年に27.6%、2022年は32.8%と上昇傾向にあります。2023年の1〜4月には54.8%と、半数を超えました。2023年1~4月の4カ月だけで倒産件数は31件に上っており、前年同期と比べ1.4倍に増加しています。
(参照元:株式会社東京商工リサーチ 「コロナ関連」の支援効果薄れ、美容室倒産が1.4倍のペース
URL:https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1197654_1527.html)
美容院・サロンが廃業する主な理由
美容室やサロンが廃業を選ぶ主な理由として、資金繰りがうまくいかないことが挙げられます。美容業界は参入の障壁が低く、美容師が独立して自分の店を持つケースが多くあります。そのため、人気のエリアには美容院が集中し、競争が激しくなります。この競争に勝ち残れず、経営が困難になり廃業する美容院が増えています。また、人件費や電気料金、材料費などの上昇によるコスト増加も経営が厳しくなる要因のひとつです。
美容院の経営を成功させるには、美容師としての技術だけでなく、経営に関する知識も求められます。コスト面では、家賃などの固定費や人件費、水道光熱費、薬剤やスタイリング剤などの仕入れなど、固定費や変動費がかかります。新規顧客を呼び込むためには宣伝戦略にも長けていなければならず、宣伝広告費も必要です。これらを売上金額だけでまかなうことは難しく、開業はできても、多くの美容院が1年後に赤字になると言われています。
美容院・サロンにおける廃業手続きの流れ
美容院を廃業するにはさまざまな手続きが必要です。以下に廃業時に留意すべき事項をまとめました。
1. 関係各所へ告知する
美容院の廃業を決めたら、まず関係者に意向を伝えなければなりません。常連客や従業員、仕入れ先、物件の貸主などに適切なタイミングで廃業を告知します。
伝達の漏れや遅れなどのトラブルを避けるためにも、どこにいつまでに告知すべきか、確認しておきましょう。
賃貸の解約通知を出す
テナントを解約する際は、借りたときの状態に原状回復することが一般的です。そのために必要な期間も含めて、事前にスケジュールを立てましょう。まずは賃貸借契約書で解約通知の提出期限を確かめ、期限日までに解約通知を出します。
また、お店の状態や家賃の支払いが問題なければ、保証金が返還されます。ただし、保証金を返金しないという条件が契約書に記載されている場合もあります。
電気やガス、水道などの解約手続きも必須です。各所に問い合わせ、解約に必要な期日や手続きの内容を調べましょう。これらの手続きは忘れがちなので、早めに済ませておくことをおすすめします。
スタッフに解雇通知を渡す
スタッフにへの解雇通知は、労働基準法により、解雇予定日の30日前までに行うことが定められています。万が一、30日未満で通知した場合は、解雇予告手当を支払わなければなりません。通知が遅れないよう十分に注意してください。
仕入れ先へ通知する
業者からシャンプーやスタイリング剤などを仕入れている場合は、仕入れ先に取引を中止することを知らせなければなりません。契約内容によっては、返品や買取が可能なケースもあるため、事前に確認しておきましょう。
お客様へ通知する
美容院のお客様には、少なくとも1〜2カ月前に廃業を通知しておく必要があります。突然閉店することで迷惑をかけないよう、真摯に対応しましょう。
美容院は、スタッフと顧客の結びつきが強いことが特徴です。事業の再開も視野に入れるのであれば、一人ひとり丁寧に対応することをおすすめします。
2. 各種申請・必要書類を提出する
廃業日の見通しが立ったら、廃業に関する書類の手続きを行います。美容院の廃業手続きは、届出によって期限や窓口が異なります。
廃業届を出す(税務署)
個人事業主が事業をやめる場合は、納税地の税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する必要があります。
作成した届出書を直接持参や郵送で提出することも可能ですが、e-Taxから提出する方法が便利です。パソコンでe-Taxソフトをダウンロードし、届出書を作成して提出します。書類のフォーマットは、国税庁のホームページからダウンロードできます。
提出期限は廃業した日から1カ月以内です。提出できなかった場合も罰則はありませんが、税法上必要な手続きですので、忘れずに手続きを行いましょう。
(国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
URL:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm)
廃業届を出す(保健所)
保健所にも廃業届を提出します。美容院を開店する際は、店舗所在地を管轄する自治体にて美容所登録を行っています。これは美容師法によって定められた手続きのため、廃業する際も忘れずに届け出る必要があります。
手続き方法や提出期限、必要な書類は自治体によって異なるため、自治体のホームページで確認しましょう。
青色申告を取りやめる
青色申告をしている個人事業主は、その取りやめも必要です。提出期限は、青色申告を取りやめる翌年の3月15日です。廃業届と同様にe-Taxで提出できるため、併せて手続きを行うと手間を減らせます。青色申告を取りやめる理由を書く欄には、「廃業のため」と記載します。
(国税庁「A1-10 所得税の青色申告の取りやめ手続」
URL:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200008.htm)
給与の廃止届出書を出す
スタッフに給与を支払っていた場合は、給与支払事務所等の廃止届出書を提出します。スタッフだけでなく、家族が青色事業専従者として働いていた場合も同様です。
廃止届出書は、管轄の税務署に廃業した日から1カ月以内に提出します。e-Taxが利用可能なため、廃業届の提出や青色申告の取りやめと併せて手続きを行うことがおすすめです。
(国税庁「A2-7 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」
URL:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm)
課税事業者は事業廃止届を出す
消費税の課税事業者で、ほかに課税売上になる取引がない場合、「事業廃止届出書」も提出します。廃業届などと同じく、e-Taxでの作成・提出が可能です。
(参照元:国税庁「D1-14 事業廃止届出手続」
URL:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_06.htm
3. 賃貸物件の原状回復を図る
美容院として借りていた物件は、解約日までに借りたときの状態に戻すことが一般的です。その際には家具や設備の処分にコストがかかるほか、床や壁など何もないスケルトンの状態で借りた場合には、原状回復のために解体工事も必要となります。
そのため、廃業にはある程度の資金が必要であることに留意する必要があります。また、工事の範囲は契約状況により異なるため、賃貸契約書をよく確認しておきましょう。
原状回復の費用を節約したい場合は、居抜きで譲る方法もあります。居抜きとは、店の状態をそのまま第三者に譲ることです。詳しくは以降の章で説明します。
美容院の廃業に必要なコスト
美容院を廃業する際は、主に法的手続きと物件の解体に費用がかかります。
個人事業主の場合は、状況によっては法的手続きが0円で済むケースもあります。法人の場合は登記や官報広告、証明書の取得にあたって8〜10万円の費用がかかります。これらを税理士などの専門家に依頼する場合は、報酬としてさらに数十万円の費用がかかると考えておきましょう。
最もコストがかかるのは、テナントの解体です。立地や原状回復の範囲にもよりますが、1坪あたり7000~1万5000円ほどが相場です。早期に複数の解体業者へ見積もりを依頼して比較するとともに、十分な資金を準備しておきましょう。
また、解体の際にシャンプー台やパーマ機器、椅子などの設備や家具が残ったままだと、不用品の処分代金を請求されてしまいます。設備の中には中古品として売れるものもあるため、あらかじめ買取業者に依頼しましょう。売れなかった不用品については、不用品回収業者に処分を依頼します。
美容院の廃業に伴う負担を減らす方法
このように、美容院の廃業にはコストがかかります。できるだけ廃業コストを抑えるには、居抜き物件として売却することも一案です。また、廃業以外の選択肢としては、M&Aを行うという手段もあります。
居抜き物件として売却する
美容院の設備を残した状態で、居抜き物件として売却する場合、在庫処理や原状回復にかかる費用負担を抑えつつ、売却による収益を得ることができるというメリットがあります。
居抜き物件の売却時には、次の借り主との間で美容院の内装や器具、備品などの造作物に対する「造作譲渡契約」を結びます。この契約を結ぶ際には、造作物の法定耐用年数を反映します。例えば、理容・美容機器は5年、そのほか冷暖房機器が6年、金属製のキャビネットは15年です。各設備は、使用年数を差し引いた分の価値になります。例えば、新品で買ったシャンプー台を3年使用していた場合、5分の2程度の価格と計算できます。
(国税庁「確定申告書等作成コーナーよくある質問 耐用年数(器具・備品)(その1)」
URL:https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/genkashokyakuhi/taiyonensukigu1.html)
ほかに、シェアサロンとして再開業するという選択肢もあります。近年では、自分の店を持たないフリーランス美容師も増えており、シェアサロンのニーズは高まっています。この場合は、事業転換の手続きが必要になります。
M&Aで売却する
美容院の内装を残した状態で物件を売却する居抜き販売に対して、M&Aは店の従業員や経営権、営業権など店舗運営に関する権利を第三者に譲る方法です。
赤字でも買い手が見つかれば売却できる可能性もあり、収益性という面では居抜き販売よりも評価は高くなります。ただし、M&Aには財務や法務など専門的な知識が必要なため、居抜き販売よりも実行が難しくなります。
M&Aを実行する場合は、専門業者にマッチングや調査を依頼するのが一般的です。採用されるM&Aの手法は、主に事業譲渡と株式譲渡の2種類があります。以下ではそれぞれについて詳しく解説します。
M&Aの方法1:事業譲渡
事業譲渡とは、会社の事業のすべて、もしくは一部を第三者に渡す方法です。譲渡する範囲を契約書で規定するため、会社自体の経営権は譲渡せず、他事業を継続することもできます。個人経営の美容室であっても事業譲渡は実行できるため、小規模な美容院で多く採用されています。
売り手側としては、高額で売却できる可能性があることがメリットです。特に、人材力やブランド力が優れた美容院であれば、高値での取引が期待できます。
売り手は一時的に経営のリスクや負債から解放されるほか、新たな事業に再投資できる可能性があります。会社自体を手放すわけではないので、採算が取れていない事業を譲り、注力したい事業に資金を集中して美容院を再建したケースもあります。
M&Aの方法2:株式譲渡
株式譲渡とは、株式を譲渡して経営権を第三者に渡す手法です。株式譲渡を行うと、運営する美容院は買い手企業の子会社となります。そのため、株式譲渡をした後は経営統合が必要です。
売り手側のメリットとしては、事業譲渡より手続きが簡易なことが挙げられます。事業譲渡は株主総会の開催が必須ですが、株式譲渡は株式譲渡契約を締結して株式名簿の書き換えを行うことで、手続きが完了します。ただし、株式譲渡制限会社の場合は、取締役会または株主総会で譲渡承認を受けなくてはなりません。
M&A前後の変化は株主変更のみとなります。継続して美容院の運営が可能なため、これまでに培ってきた社風や文化を保った状態で事業を続けられます。
まとめ
美容院は競争が激しく、多くの美容院が廃業しています。特に2019年の廃業件数は過去最多となり、その後も資金繰りの難しさなどの理由で、廃業率は増加傾向にあります。美容院の廃業には各種申請や物件の解体など、多くの手間とコストが必要になります。
廃業以外の手段として、事業譲渡や株式譲渡などのM&Aに注目が集まっています。従業員やお客様に迷惑をかけないためにも、美容院を廃業する前に、M&Aを検討してみてはいかがでしょうか。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。