事業承継に必要な契約書 | 事業承継の3つの方法に合わせて解説!
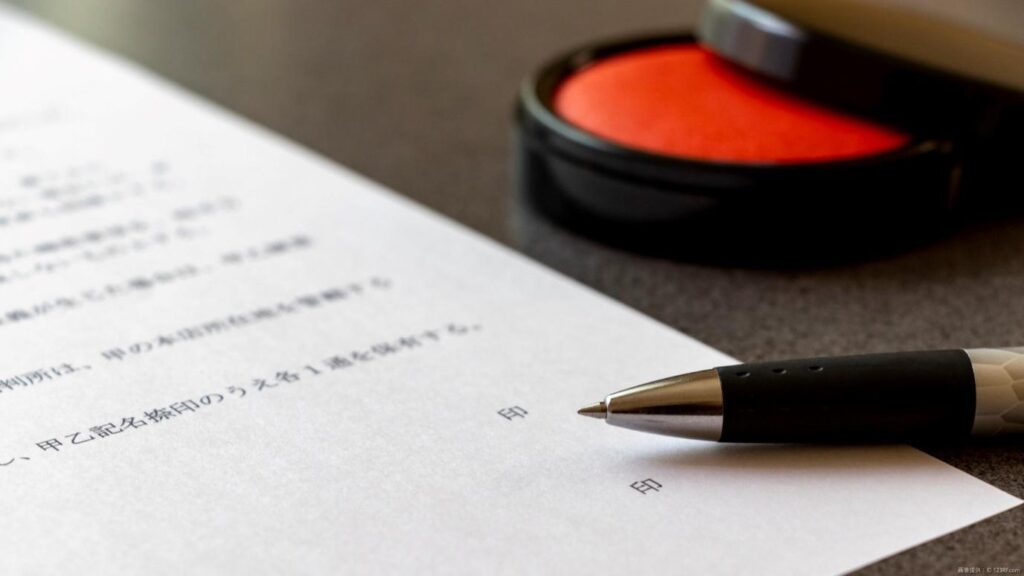
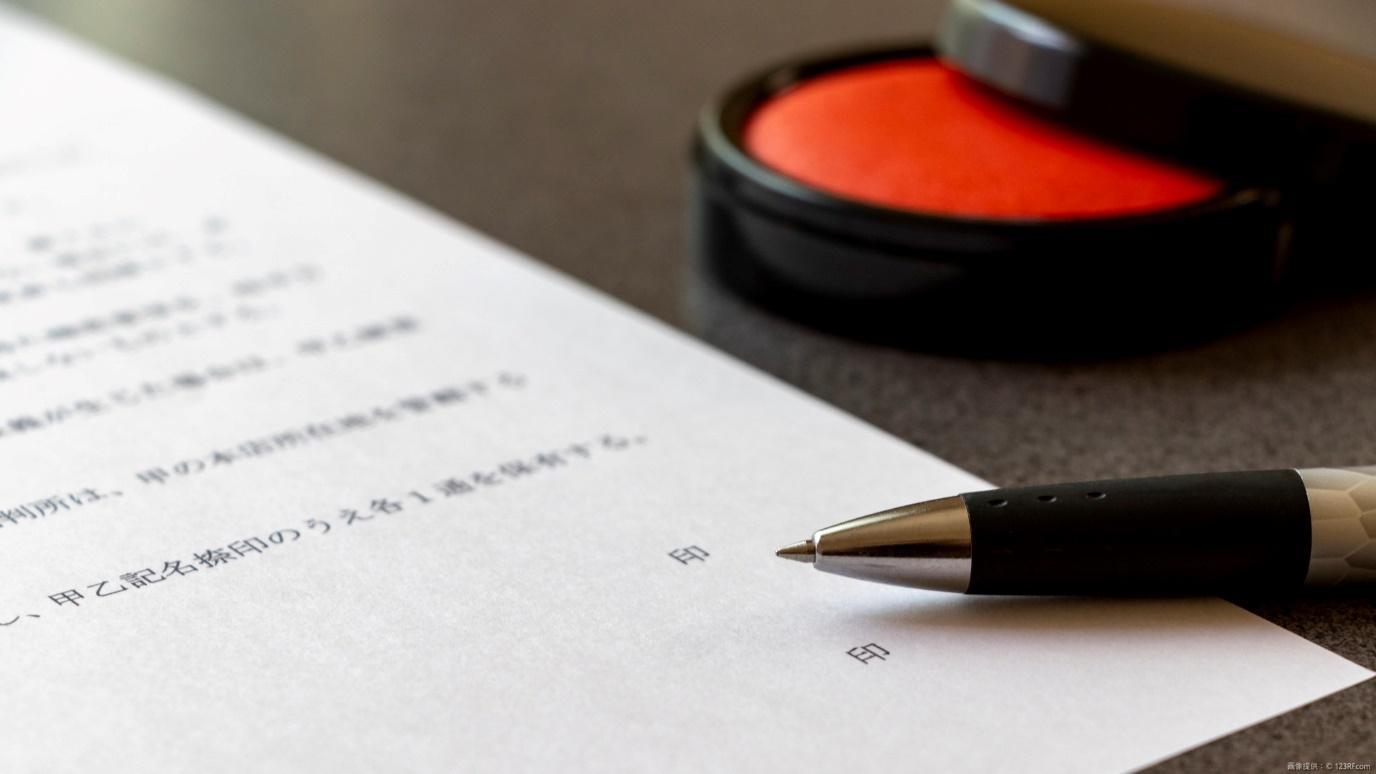
事業承継は、企業の未来を左右します。本記事では、親族内承継や従業員への承継、M&Aという3つの主要な事業承継方法と、それぞれに必要な契約書、ポイントなどについて詳しく解説します。
目次
事業承継とは?
事業承継とは、現在の経営者が自身の会社や事業を次世代の後継者へと引き継ぐ行為を指します。これは単に事業そのものだけでなく、会社の場合は株式やそのほかの財産、役職など、事業に関するノウハウなど、すべての要素を後継者に引き継ぐことを含みます。法的な意味では、株式を引き継ぐことと、法人代表者としての地位を引き継ぐことの2つが重要となります。
事業承継は中小企業の活力の維持、発展に不可欠です。また、昨今では経営者の高齢化に伴い、その重要性は増しています。事業承継を考えているなら、必要な書類や手続きなどをしっかり理解し、着実に準備を進めることが大切です。
【専門家監修】事業承継とは?中小企業の現状と具体的なプロセスを解説
事業承継には3つの方法がある
事業承継には、次の3つの方法があります。
-
- 親族への承継
- 従業員や第三者への承継
- M&Aでの承継
親族への承継
事業承継の際、親族への承継は一般的な方法の一つであり、経営理念や企業文化の継承が比較的スムーズに行われることが特徴です。事業承継には、株式譲渡契約や事業譲渡契約など、事前に準備すべき契約書があります。
具体的には、生存中の経営者が後継者に株式を生前贈与する場合や売買による承継、経営者の死亡後に遺言や遺産分割協議を通じて承継が行われるケースがあります。各契約書の作成には、法的な知識が必要となるため、専門家に頼るのもひとつの手段です。
親の会社を継ぐメリットは多い?親族内承継の方法や注意点を解説
従業員や第三者への承継
事業承継は、企業の存続と発展にとって重要な課題です。親族内での承継が困難な場合、従業員や第三者への承継がひとつの選択肢となります。従業員承継は、企業文化の継承や後継者選びの幅が広がるメリットがあります。
一方、第三者承継は新たな視点や技術をもたらし、事業の更なる発展を促す可能性があります。いずれにせよ、どちらの方法も適切な準備と計画が必要なため、後述する必要な書類などもよく確認してください。
従業員承継の方法と流れ!事前に把握しておくべきリスクや注意点を解説
M&Aでの承継
親族や社員への事業承継が困難な場合は、M&A(株式や事業の譲渡)を活用することで、第三者に自社を譲渡し、企業を存続させることが可能となります。昨今、M&Aは事業承継の問題を解決できる経営手法として注目されています。
事業の継続性を確保しつつ、新しい市場や技術へのアクセスが可能になる場合があります。しかし、M&Aによる事業承継を成功させるためには、しっかりとした計画が必要なため準備を怠らないようにしましょう。
事業承継に必要な契約書一覧
事業承継に必要な書類を、ケース別にまとめました。
親族への承継に必要な契約書(個人事業主の場合)
-
- 遺言書
- 遺産分割協議書
- 生前贈与契約書
- 使用貸借契約書
親族への承継に必要な契約書(法人の場合)
-
- 事業譲渡契約書
- 株式譲渡契約書
従業員や第三者への承継に必要な契約書
-
- 株式譲渡承認請求書
- 株式名義書換請求書
M&Aでの承継に必要な契約書
-
- 秘密保持契約書
- 基本合意書
- 株式売買(譲渡)契約書
M&Aで使用する契約書を解説!記載すべき内容やポイントを紹介
資本提携における契約書について解説!書き方や交わすタイミングも
親族への承継に必要な契約書(個人事業主の場合)
契約書には、承継する権利義務を具体的に記載することが求められます。とくに負債については、事業承継後にどちらが負担するかで争いとなる可能性があるため、特定が不十分であると問題となります。
また事業承継には、売買、贈与、相続のいずれかの方法があります。これらの方法により、必要な契約書や手続きが異なります。
以下では、遺言書や遺産分割協議書、生前贈与契約書、使用貸借契約書、それぞれについてポイントも含め解説します。
遺言書
遺言書は、個人事業主が親族への承継を明確にするために極めて重要な書類です。事業の将来を決定し、遺産分割の争いを避けるために、遺言書には事業の承継者を明確に指名し、その承継条件を具体的に記載することが肝要です。遺言書により、事業主の意思が正確に反映され、スムーズな承継が可能になります。
遺言書の種類
遺言書は、事業主の死後の事業承継を円滑に進めるための重要な文書であり、故人の遺志を相続人へ伝えられます。遺言書の形式としては、以下のものがあります。
-
- 自筆証書遺言
遺言者が自筆することで成立する遺言書です。全文(ただし相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合はその目録は自署によらないことが認められている)、日付、氏名を自分で書き、署名・押印する必要があります。
-
- 公正証書遺言
証人2人以上の立ち会いのもとで、遺言者が公証人へ遺言の内容を伝え、公証人が筆記・作成する遺言書です。
-
- 秘密証書遺言
公証人への依頼が必要になる遺言書ですが、公証人は遺言書の存在を証明するのみとなり、遺言書の作成は遺言者が行います。
適切な遺言書の形式を選び、遺言書を作成することで、事業承継をスムーズに行えます。
記載する内容
遺言書は、事業主の死後の事業承継を円滑に進めるための重要な文書であり、故人の遺志を相続人へ伝えられます。
主な記載内容は以下のとおりです。
-
- 日付
遺言書を作成した日。曖昧な日付は無効となります。
-
- 署名
遺言者の署名です。
-
- 押印
遺言者の印鑑です。印鑑登録証明書と同じ実印が望ましいです。
-
- 相続財産
不動産や有価証券、預貯金、生命保険、そのほかの財産(車、ゴルフ会員権等)など。
-
- 相続分の指定
だれに相続させるのか明記しましょう。
また、事業の未来に関する経営者の願いや指針等も記載することで、スムーズな承継と事業の持続的な成長をサポートすることが可能になります。
遺言書のポイント
遺言書作成の際のポイントは、明確さと法的に認められる体裁になっているかどうかです。具体的には、承継者の明確な指名や事業資産の詳細な記載、及び事業運営に関する指示が必要です。
また、無効扱いされないためにも、自筆証書遺言の場合は全文を自書し、日付と署名を忘れずに書いてください。公正証書遺言では公証人と証人が必要です。これらの点を押さえることで、事業承継の意向が正確に伝えられます。
遺産分割協議書
遺産分割協議書は、被相続人の死後、相続人が相続する財産の分配に関する合意を文書化したものです。遺言書が作成されていない場合や、遺言書が作成されていても一部の財産しか記載されていない場合に必要となります。
個人事業主の事業承継においては、事業資産の明確な分配や承継者の指定が必要です。この協議書は、相続人全員の合意が必要です。相続人が1人でも欠けた状態で行われた遺産分割協議は、原則として無効となります。
記載する内容
遺産分割協議書には、以下の内容を記載します。
-
- 被相続人の氏名と住所、死亡年月日
遺産を残した人の名前と住所、その人が亡くなった日。
-
- 被相続人の最後の住所地
遺産を残した人の最後の住所。
-
- 相続財産の分配内容
遺産をどのように分割するか。不動産、預金、株式などの具体的な資産の指定、各相続人に帰属する遺産の割合、そしてそれらの分配方法も含みます。
-
- 相続人全員の住所・氏名・押印(実印)
遺産を受け取る人々の情報。
遺産分割協議書のポイント
遺産分割協議書を作成する際の重要なポイントは、すべての相続人が納得できる内容であることを確保することです。相続人全員の意見を聞き、公平な遺産の分配を目指しましょう。また、遺産の内容と全ての分割方法を記載することが重要です。遺産分割協議が終了したあとに判明した財産があった場合の対処方法も記載しておきましょう。
また、遺産分割協議書の条文が曖昧だと、記載内容を巡って相続人同士の争い事に発展する可能性があります。遺産分割協議書の作成は専門的な知識を必要とするため、弁護士などの専門家にチェックを受けることをおすすめします。
生前贈与契約書
生前贈与契約書は、事業承継において資産を生前に後継者へ移転するための法的文書です。この契約を通じて、経営者は自身の生前に事業や資産を指定した後継者に渡せます。
親族間で事業をスムーズに引き継ぐためには、事業用資産や土地を生前贈与することが一般的です。適切な生前贈与は相続税の負担を軽減する効果もあり、スムーズな事業の継続を実現します。
記載する内容
生前贈与契約書には、以下の内容を記載します。
-
- 贈与者の情報
贈与者の氏名と住所。
-
- 受贈者の情報
受贈者の氏名と住所。
-
- 贈与の日付
贈与契約締結の日付、実際に贈与を実行する日付
-
- 贈与財産の詳細
贈与する財産の内容(現金・預貯金・不動産・株式など)、その金額・数量、贈与の方法。
これらの情報を明記することで、あとからトラブルが発生した場合でも、契約書が証拠となります。生前贈与は口頭でも成立しますが、明確な記録を残すためにも、贈与契約書の作成を強くおすすめします。
生前贈与契約書のポイント
生前贈与契約書を作成する際の重要なポイントは、贈与される資産の詳細を明確にすること、双方の意思が正確に反映されていることを確認すること、そして税法上の影響を事前に検討しておくことです。
具体的には、贈与者と受贈者の氏名と住所、贈与物の具体的な説明、贈与の条件や時期など、すべてが詳細に記される必要があります。また、贈与契約書は法的な効力を持つため、専門家の助けを借りて作成することをおすすめします。
使用貸借契約書
「使用貸借契約書」とは、一方の当事者が他方に対して、無償で何らかの物を貸す契約のことを指します。個人事業主の事業承継において、事業の資産や設備を承継する際に、この契約書が適切に作成されていることでスムーズな進行が可能となります。
記載する内容
使用貸借契約書には以下の内容を記載します。
-
- 貸主と借主の氏名や住所
- 貸借する物件の詳細説明
- 貸借期間
- 使用料(無料か有料か含む)
- 契約終了の条件
- 物件の維持・管理に関する責任
これらの要素を正確に記述することで、双方の権利と義務が明確になりトラブルを防げます。
使用貸借契約書のポイント
使用貸借契約書を作成する際のポイントは、明確な条項設定です。具体的には、貸し出される物品の詳細説明や利用期間、利用条件、返却に関する規定を具体的に記載することが重要です。
また、双方の権利と義務を明確にし、予期せぬ事態に備えた条項も設けることで、後のトラブルを防ぎます。
親族への承継に必要な契約書(法人の場合)
ここでは、法人が親族へ事業を承継する際の契約書について説明します。一般的には、事業譲渡契約書や株式譲渡契約書が必要となります。ただし、現在の経営者が生存しているあいだは株式を譲渡したくないとする一方、死亡後は後継者に株式をスムーズに譲渡したいと考えるケースについては、遺言書の作成が必須となります。
また、現経営者が遺言書を作成しなかった場合、または遺言書を作成していても何らかの理由で当該遺言書が無効となった場合、株式は遺産分割の対象となり、遺産分割協議書が求められます。
以下では、事業譲渡契約書や株式譲渡契約書それぞれについてポイントも含め、解説します。
事業譲渡契約書
事業譲渡契約書は、企業がほかの企業や個人に事業を譲渡する際に使用される契約書です。この契約書では、譲渡される事業の範囲や販売価格、支払条件、引き渡しの時期と方法、責任と保証に関する条項など、事業譲渡に関する全ての重要な条件が定められます。
記載する内容
事業譲渡契約書に記載される内容は、以下になります。
-
- 契約の当事者
譲渡者と譲受者を明確に記載します。
-
- 譲渡対象
譲渡される事業の詳細、財産、債務の範囲を具体的に記載します。
-
- 譲渡日
契約が効力を持つ日付を記載します。
-
- 譲渡財産等の対象範囲
譲渡する財産については、知的財産権や仕掛かり(製造途中の物など)、在庫、機械設備から、製造部品、机、ロッカーなど多岐にわたる物品を特定する必要があります。
-
- 譲渡金額とその支払い方法
譲渡金額は、適切なものである必要があります。支払方法も一括なのか、分割なのかなどをしっかり定める必要があります。
事業譲渡契約書のポイント
事業譲渡契約書を作成する際の重要ポイントは、譲渡する事業の正確な範囲の明記、事業譲渡の実行日と費用の負担について、譲渡価格と支払条件の具体性、責任と保証に関する詳細な定義などです。
以上の要点を考慮に入れて、事業譲渡契約書を作成しましょう。
株式譲渡契約書
株式譲渡契約書は、企業の株式を譲渡する際に使用される契約書です。この契約書には、譲渡する株式の数量や株式の譲渡価格、支払条件、譲渡のタイミング、株式の引き渡し方法、両当事者の権利と義務に関する詳細が記載されます。
記載する内容
株式譲渡契約書に記載される内容は、以下になります。
-
- 譲渡対象
譲渡する株式の詳細や財産、債務を具体的に記載します。
-
- 譲渡日
契約が効力を持つ日付を記載します。
-
- 譲渡財産等の対象範囲
譲渡する財産については、知的財産権や仕掛かり(製造途中の物など)、在庫、機械設備から、製造部品、机、ロッカーなど多岐にわたる物品を特定する必要があります。
-
- 譲渡金額とその支払い方法
譲渡金額は適切なものである必要があります。支払方法も一括なのか、分割なのかなどをしっかり定める必要があります。
株式譲渡契約書のポイント
株式譲渡契約書を作成する際の重要なポイントは、譲渡される株式の正確な数とそれに対する価格の明確な記載、支払い条件やスケジュールの詳細、両当事者の権利と義務、そして譲渡後の責任に関する条項を含めることです。
株式譲渡契約書(SPA)とは?作成に関する注意点や記載項目を解説
従業員や第三者への承継に必要な契約書
ここでは事業承継における、従業員や第三者への承継に必要な契約書について説明します。
従業員や第三者への承継に必要な契約書には、事業譲渡契約書や株式譲渡契約書などが含まれます。
また、事業譲渡に伴い従業員の労働条件が変更される場合は、新たな労働条件を明記した契約書が必要となります。これらは、新たな経営者と従業員間の権利と義務を明確にするために重要です。
株式譲渡承認請求書
株式譲渡承認請求書は、株式会社が株式の譲渡を行う際に必要となる文書です。この請求書は、会社や他の株主から譲渡の承認を得るために用います。とくに、会社の定款によって株式の譲渡に制限がある場合、この承認が重要となります。
記載する内容
株式譲渡承認請求書に記載する内容は、以下になります。
-
- 譲渡する株式の種類と数
譲渡する株式の種類と数を明記します。
-
- 譲渡の相手方
譲り受ける者の氏名または名称を記載します。
-
- 譲渡承認の請求
会社が譲渡承認をしない旨の決定をする場合は、当該会社、または指定買取人がその当該株式を買い取ることを請求する旨を記載します。
株式譲渡承認請求書のポイント
株式譲渡承認請求書を作成する際のポイントは、明確な譲渡対象の株式数の記載、譲渡する株式の詳細、譲渡の条件、譲渡承認のための必要情報、そして譲渡受け入れの期限などがあります。これらの要素を正確に記載し、譲渡をスムーズに進めるための法的要件を満たしましょう。
株式名義書換請求書
株式名義書換請求書は、株式の所有者が変更された際に、その新しい所有者の名義に株式を正式に書き換えるために使用される文書です。この請求書には、株式を譲渡した人と譲渡を受けた人の情報、書き換えられる株式の詳細、および譲渡の日付などが含まれます。
記載する内容
株式名義書換請求書に記載する内容は、以下になります。
-
- 譲渡する株式の種類と数
譲渡する株式の種類と数を明記します。
-
- 譲渡の相手方
譲り受ける者の氏名または名称を記載します。
-
- 譲渡人
譲る者の氏名・住所を記載し・押印(届出印または、実印、認印)もします。
-
- 譲渡の日付
譲渡する日を記入します。
株式名義書換請求書のポイント
株式名義書換請求書を作成する際のポイントは、正確性です。具体的には、譲渡される株式の正確な数と種類、譲渡者と受取人の正確な名義情報、譲渡の日付、および必要な署名や認証の明記が必要です。
M&Aでの承継に必要な契約書
ここでは事業承継における、M&Aでの承継に必要な契約書について説明します。M&Aでの承継に必要な契約書には、秘密保持契約(NDA)や基本合意書(LOI)、株式譲渡契約書、などがあります。
これらの契約書は、取引の各段階で要求される文書であり、取引の透明性や双方の合意内容の正確な記録、法的リスクの管理に不可欠です。
M&Aで使用する契約書を解説!記載すべき内容やポイントを紹介
秘密保持契約書
M&Aにおける秘密保持契約書(NDA)とは、M&Aの買主と売主が、M&Aで取り交わされる両者の企業秘密について、互いに第三者に開示、漏えいしないと約束する契約です。M&Aでは売主の立場では、とくに買主に対して多くの秘密情報を提供しなければなりません。
企業秘密の外部への漏洩は、売主と買主双方にとって重大な損失につながることがあります。双方の利益を保護するために、M&A取引においては秘密保持契約が結ばれます。この契約は、情報の提供者に情報漏洩を防ぐ義務を負わせることで、双方の利益を守る役割を果たします。
記載する内容
M&Aにおける秘密保持契約書(NDA)に記載される内容は、以下になります。
-
- 秘密情報の範囲
M&Aの秘密保持契約書では、秘密情報の範囲を定義します。このとき、M&Aの場面という特殊性を踏まえると、秘密情報の範囲は限定的に考えるべきです。
-
- 利用目的の限定
M&Aの秘密保持契約書で、秘密情報の利用目的をM&Aの検討に限定し、目的外利用を厳しく防ぐのが通例です。
-
- 契約違反時の対応
どちらかから秘密保持すべき情報が漏れたときの対応、罰則を明確に定義します。
-
- M&A終了時の秘密情報の扱い
M&Aの秘密保持契約書では、その目的が達成されたあとの秘密情報の扱いを定めます。
以上の要点を考慮に入れて、M&Aにおける秘密保持契約書を作成すると、事業の譲渡が円滑に進行します。
秘密保持契約書のポイント
M&Aにおける秘密保持契約書を作成する際の重要ポイントは、保護される機密情報の明確な定義や情報の使用範囲、保持期間、情報返却または破棄の条件を具体的に規定することです。また、契約違反時の対応や罰則についても明確に定め、双方の合意のもとで契約を締結することが重要です。
M&AでのNDA(秘密保持契約)とは?|締結目的から作成時の注意点まで完全解説
基本合意書
M&Aにおける基本合意書とは、最終契約に向けて売り手と買い手がM&Aの基本的な条件について合意した内容を書面にしたものです。基本合意書は、M&Aの最終契約書に先立つ前座的な立ち位置であり、法的な拘束力はありませんが、その後の最終契約書を締結するための重要な書類といえます。
記載する内容
M&Aにおける基本合意書に記載する内容は、以下の要点をご覧ください。
-
- 契約当事者
M&Aの売主と買主を明記します。
-
- 目的
M&Aの目的を具体的に記述します。
-
- 譲渡スキーム
M&Aの形態(たとえば、株式譲渡や事業譲渡など)を定義します。
-
- 最終契約について
最終契約の締結についての条項を含みます。
-
- 基本日程
M&Aの基本的なスケジュールを設定します。
-
- デューデリジェンス(買収監査)
買主によるデューデリジェンスの開始と売主の協力についての条項を含みます。
-
- 解除権
契約を解除する権利についての条項を含みます。
-
- 有効期間
契約の有効期間を定めます。
-
- 独占交渉権の有無
買主が売主とのM&A交渉を独占できる権利についての条項を含みます。
-
- 譲渡禁止
譲渡禁止についての条項を含みます。
-
- 法的拘束力
契約の法的拘束力についての条項を含みます。
-
- 秘密保持義務
M&Aの情報の秘密保持についての条項を含みます。
-
- 費用
M&Aの費用についての概算額や計算方法、条項を含みます。
-
- 協議事項
M&Aの協議事項についての条項を含みます。
以上の要点を考慮に入れて、M&Aにおける基本合意書を作成しましょう。
基本合意書のポイント
基本合意書を作成する際のポイントは、交渉の初期段階での合意内容を明確に定めることです。とくに、取引の概要や目的、買収の条件、期限、および秘密保持の義務に関する詳細を具体的に記載することが重要です。
M&Aにおける基本合意書(MOU)とは?記載内容、法的拘束力の発生についても
株式売買(譲渡)契約書
M&Aにおける株式売買(譲渡)契約書は、株式の売買に関する具体的な条件を定めた法的文書です。この契約書はM&Aの成約時に作成され、株式の買い手は受領する権利を、株式の売り手は引き渡しの義務を負います。
記載する内容
M&Aにおける株式売買(譲渡)契約書に記載される内容は、以下になります。
-
- 譲渡株式
譲渡対象となる株式の詳細を明記します。
-
- 譲渡対価
譲渡する株式の価格を定めます。
-
- 譲渡日・クロージング日
譲渡を実行する日を定めます。
-
- 譲渡実行前提条件
譲渡を実行するための前提条件を定めます。
-
- 表明および保証
売主・買主自身や対象会社について、一定の事項が真実かつ正確であることの表明保証を定めます。
-
- 遵守事項
取引・契約に関する遵守事項を定めます。
-
- 損害賠償
表明保証への違反、又はその他の契約違反の場合の規定を定めます。
-
- 秘密保持
M&Aの情報の秘密保持についての条項を含みます。
-
- 契約の解除
契約を解除する権利についての条項を含みます。
-
- その他の一般条項
その他の一般的な事項を定めます。
株式売買(譲渡)契約書のポイント
M&Aにおける株式売買(譲渡)契約書を作成する際のポイントは、売買対象の株式の明確な定義や正確な価格設定、支払条件の具体化、表明と保証の詳細な記述、および取引完了後の責任分担に関する条項などを明記することです。
株式譲渡契約書(SPA)とは?作成に関する注意点や記載項目を解説
まとめ
事業承継を成功させるには、親族や従業員、または第三者、M&Aによる承継方法、それぞれに応じた適切な契約書の準備が不可欠です。各方法に合わせた契約書作成のポイントを理解し、事前に準備を進めることがスムーズな事業継承への鍵となります。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。


