事業承継におけるリスクと問題点とは?原因と解決法を徹底解説!
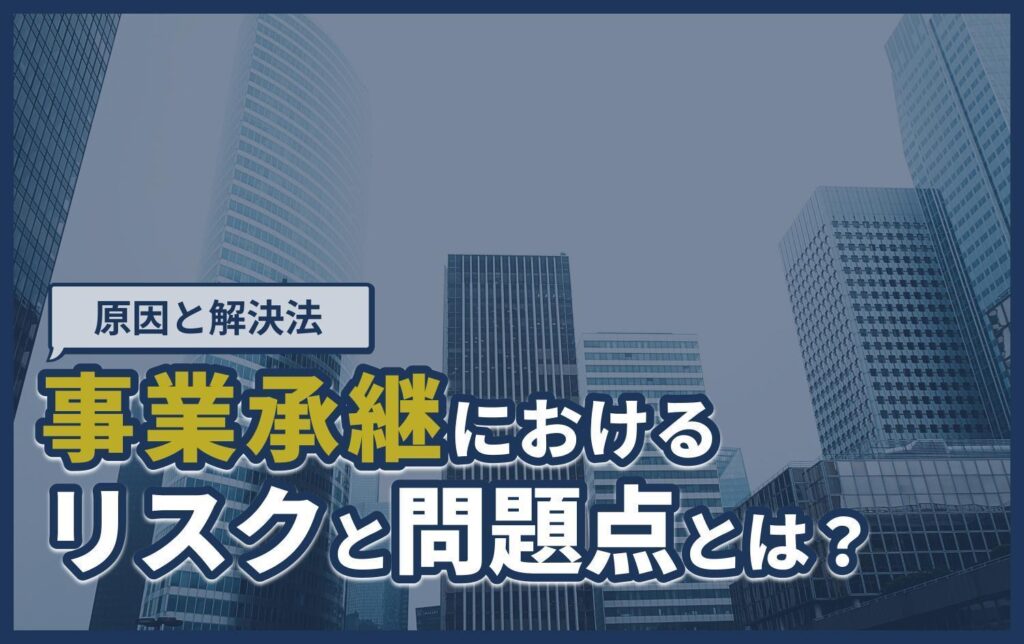
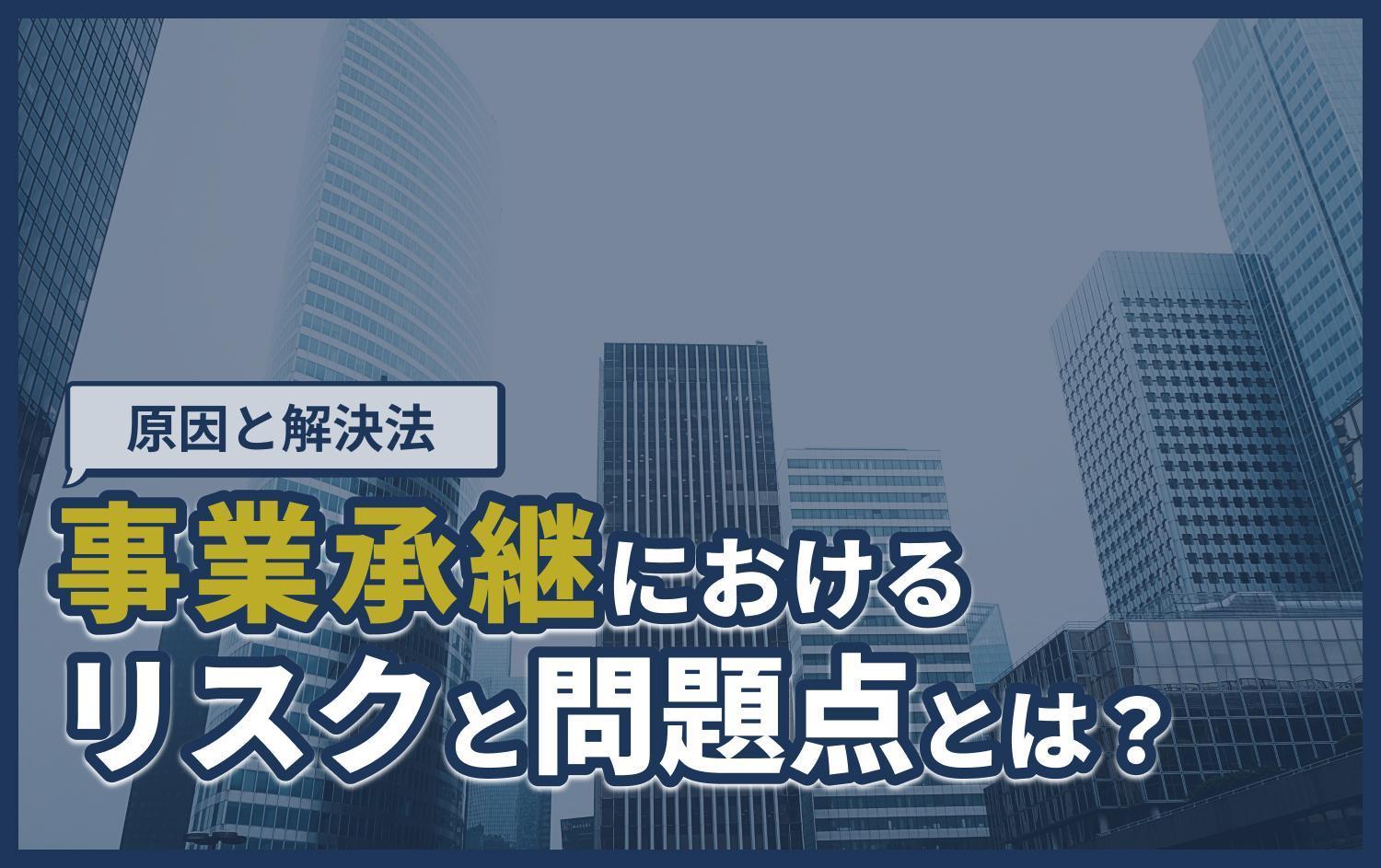
本記事では、事業承継に関わるリスクについて解説します。円滑に事業を継続していくためには、リスクと対策を知っておく必要があります。場合によっては、事業継承後に事業が低迷する可能性がありますので、ぜひ本記事を参考にスムーズに事業継承の手続きを行ってください。
目次
事業承継の種類

まず、事業承継の引継ぎ先について理解しておきましょう。
引き継ぎ先によってリスクの内容が異なります。
- 親族内への事業承継
- 親族外への事業承継
- M&A
上記の3つの選択肢から適任の後継者に事業承継することができます。
ただし、どの方法であっても注意点はあるので、それぞれの事業承継の特徴やリスクについて解説しますので、引き継ぎ先を選ぶ際の参考にしてください。
親族内への事業承継
親族内への事業承継は、経営者の子供や兄弟など、血縁関係のある親族に経営権を引き継ぐ方法です。長年、多くの企業が採用してきた一般的な事業承継の形態と言えます。
しかし、優秀な後継者候補が、自らの能力を活かせる別の道を選ぶことで、承継を拒否するケースもあります。一方で、経営者としての資質や能力が十分でない親族が安易に事業を引き継ぐことで、承継後の経営が傾くリスクも存在します。
親族内継承ならではのポイントを押さえよう!メリット・デメリットについても解説
親族外への事業承継
親族外への事業承継は、社内の従業員や外部の人材に経営権を引き継ぐ方法です。特に社内の人材に承継する場合は「役員・従業員承継」と呼ばれます。
2021年度の調査では、内部昇格による事業承継が31.7%と、親族内承継に次いで多くなっています。しかし、経営者としての知識や能力が不足する従業員が経営権を握ることで、承継後の業績悪化につながるリスクがあります。
従業員承継の方法と流れ!事前に把握しておくべきリスクや注意点を解説
M&A
親族内や親族外に適切な後継者が見つからず、廃業を回避したいという場合に検討されるのが、M&Aによる事業承継です。以前は、身近に後継者がいない場合、廃業を選択せざるを得ませんでしたが、近年は第三者承継によるM&Aで廃業を回避するケースが増えています。
M&Aが選択される理由は、現経営者と譲渡先の双方にメリットがあるからです。現経営者は雇用の確保や譲渡益の獲得が可能となり、譲渡先は参入コストの削減や事業拡大の機会を得られます。
ただし、M&Aにも譲渡先が見つからないリスクや、希望する売却価格で合意できないリスクがあることを認識しておく必要があります。
| 現経営者のメリット | ・雇用の確保ができる ・譲渡による利益を獲得できる |
| 譲渡先のメリット | ・参入までの経費削減になる ・事業発展のチャンスになる |
ただし、以下のようなデメリットもあります。
- 譲渡先が見つからない
- 納得のいく金額で売却できない
M&Aとは?買手・売手の目的やメリット・デメリット、手法、費用まで解説
事業承継の構成要素

事業承継は、会社のすべてを後継者に引き継がなければいけません。
「会社のすべて」を、細かく分類すると以下の3つになります。
- 経営
- 資産
- 知的財産
現経営者は、これらをスムーズに引き継ぐための方法を考えておかなければなりません。以下で、それぞれの構成要素を引き継ぐ際のポイントについて解説しますので、参考にしながら計画を立ててみてください。
経営の承継
経営の承継とは、文字通り「経営権」を後継者に引き継ぐことを意味します。具体的には、発行済み株式の3分の2以上を保有することで、会社の経営権を完全に掌握したと言えます。
現経営者から後継者への株式譲渡が行われた時点で、経営権は移転します。ただし、従業員承継やM&Aの場合は、株式の譲渡ではなく売却となります。この場合、株式売却によって得た利益に対して税金が課されることになります。
親族内承継の場合も、贈与税や相続税の問題が生じます。株式の譲渡に際して、適切な税務対策を講じる必要があるでしょう。
資産の承継
資産の承継は、会社の持つ資産を引き継ぎます。
ここで指す「資産」には、以下のようなものがあります。
| 財産権 | ・物権 ・債権 ・知的財産権 |
| 株式 | – |
| 事業用資産 | ・工場、機械 ・事務所、店舗 |
| 資金 | – |
| 許認可 | – |
資産額によって贈与税や相続税が課されるので、経営の承継と同様に税金との兼ね合いも考えながら進めていかなければなりません。
知的財産の承継
知的財産は、
- 経営理念
- 特許
- ノウハウ
- 顧客情報
- 人脈
などの無形資産を指します。
経営の強みとなる軸を、後継者へ引き継ぎます。そのためには、現経営者が事業承継を検討する段階で漏れなく明確にしておく必要があります。
さらに、後継者への正しい引き継ぎが必要となるので、早い段階から進めていきましょう。
事業承継でよく起きる問題点
事業承継のリスクを知る前に、よく起きる問題点について知っておきましょう。
以下の問題によって、事業承継が進まないケースがあります。
- 後継者の不在
- 後継者が成長しない
- 経営者自身で進めてしまう
それぞれの問題を解決しなければ、事業承継自体が円滑に進みません。これらの問題が発生する原因について解説するので、対策を検討しておきましょう。
後継者の不在
後継者の不在は、多くの中小企業が頭を抱える問題です。帝国データバンクの「全国企業『後継者不在率』動向調査(2023年)」によると、後継者不在企業は53.9%です。
主な要因は、以下の2つです。
- 身内に後継者がいない
- 子どもはいるが後継者として適任ではない
上記のような場合は、従業員承継やM&Aなどの選択肢を検討する必要があります。
出典:全国企業『後継者不在率』動向調査(2023年)」帝国データバンク調査
後継者が成長しない
事業承継を円滑に進めるには、後継者の育成が極めて重要です。単に目に見える業務やスキルだけでなく、経営理念やノウハウといった目に見えない部分まで継承する必要があるため、後継者の育成には長い時間を要します。
現経営者は、事業承継までの時間を逆算し、計画的に後継者の育成を進めなければなりません。早い段階から後継者候補を選定し、戦略的に育成プログラムを実施することが肝要です。
社内での実務経験の蓄積だけでなく、外部の経営塾やセミナーの活用、他社での研修など、多角的な育成方法を検討すべきでしょう。後継者の成長なくして、円滑な事業承継は望めません。
経営者自身で進めてしまう
事業承継の問題を経営者だけで解決しようとすることも、大きなトラブルの要因となります。事業承継は、経営者個人の問題ではなく、会社全体に関わる重要な課題だからです。
中小企業の多くがオーナー経営者によるワンマン経営の状態にあるため、経営者が事業承継の準備を怠ったり、周囲に相談せずに独断で進めてしまったりするケースが少なくありません。
その結果、事業承継の取り組みが遅れ、最悪の場合は後継者が育たないまま時期を逸してしまい、誰にも事業を引き継いでもらえない状態に陥ってしまうのです。
事業承継は、経営者だけでなく、従業員や取引先、顧客など、ステークホルダー全体に関わる問題です。オープンな議論を通じて、関係者の理解と協力を得ながら進めることが重要です。
必要に応じて、外部の専門家や支援機関の助言を仰ぐことも有効でしょう。事業承継の進捗状況を社内で共有し、透明性を確保することも大切です。
事業承継で発生し得るリスク

事業承継は、リスクを理解した上で進めていきましょう。リスクを理解して対策を講じておかなければ、今後の事業に打撃を与えかねないからです。
以下で、リスク要因について解説しますので、確認しておきましょう。
事業承継におけるリスクと問題点とは?原因と解決法を徹底解説!
取引先や従業員の賛同を得られない
事業承継を進める上で、取引先や従業員の賛同を得られないことが、現経営者の勇退を阻む要因となるケースがあります。法的には、「賛同を得られなければ事業承継を行えない」と定められているわけではありませんが、賛同なしに事業承継を強行すれば、取引先や従業員との関係に亀裂が生じかねません。
最悪の場合、取引先の離反による売上減少や、従業員の大量離職といった事態を招く可能性もあります。事業承継の成否は、ステークホルダーの理解と協力が鍵を握ると言えるでしょう。丁寧な説明と対話を通じて、関係者の賛同を得ることが肝要です。
相続トラブルが生じる
事業承継後に頻発するトラブルの一つが、相続をめぐる問題です。親族内で複数の後継者候補がいる場合や、社内や外部から後継者を選任する場合、親族間の対立が生じるリスクがあります。
現経営者は、こうした相続トラブルを未然に防ぐための準備を怠ってはなりません。特に「遺留分」と「相続税」の問題には注意が必要です。
親族内事業承継と遺留分の関係
親族内事業承継を相続で行う際、経営者が遺言で後継者を指名していれば、スムーズに承継が進みます。しかし、複数の相続人がいる場合、指名された後継者以外の相続人から、遺留分(相続人に最低限保証された遺産取得分)の主張を受ける可能性があります。
遺留分の請求が認められれば、会社の資金が流出し、経営に影響を及ぼしかねません。
社内事業承継・M&Aと相続税の関係
社内事業承継やM&Aでは、売却益で得た資産の増加によって、相続税が増える可能性があります。
相続税対策のためには、以下の準備を進めておきましょう。
- 相続する資産をどのように分けるのか?
- 遺産の分割方法をどのように分けるのか?
- 納税資金の準備をどう用意するのか?
さらに、優遇制度の活用も検討しておくべきです。
負債の引継ぎ
後継者が認識しておくべき事業承継のリスクの一つが、「負債の引継ぎ」です。事業承継では、資産だけでなく、負債も引き継ぐことになります。
もし多額の負債を抱えたまま事業を引き継いでしまえば、後継者は返済に追われ、経営に専念できなくなってしまいます。経営者の個人保証が後継者に引き継がれるケースもあるため、注意が必要です。
| ※個人保証とは? 会社が金融機関から借り入れを行う際に、経営者が個人的に連帯保証を背負うこと。 |
事業承継の種類別リスク
リスクに対処するために、引き継ぎ先による主なリスクを把握しておきましょう。
種類別の代表的なリスクは、以下のようになります。
- 親族内事業承継…税のリスク
- 親族外(従業員)承継…資金のリスク
- M&A…利益のリスク
もし現段階で後継者を選任しているのであれば、それぞれのリスクに備えた対応を検討してください。
親族内事業承継のリスク
親族内事業承継における最大のリスクは、相続税・贈与税の負担です。自社株の評価額が予想以上に高額となった場合、株式を承継する際の相続税・贈与税が高額になるリスクがあります。
このリスクへの対策として、株式の移転方法を工夫することが有効です。例えば、持株会社を設立し、株式を間接的に保有する方法などが考えられます。これにより、株価の計算方法が変わり、相続税評価額を引き下げることが可能となります。
親族内継承ならではのポイントを押さえよう!メリット・デメリットについても解説
親族外事業承継のリスク
親族外、特に従業員への事業承継では、従業員の資金不足がリスクとなります。従業員承継では、承継者となる従業員が自ら株式を買い取る必要がありますが、十分な資金を蓄えているとは限りません。
経営者が後継者を指名しても、資金面の問題から承継が頓挫するリスクがあるのです。従業員承継を選択する場合、早い段階から従業員の株式買取資金の確保について、具体的な準備を進めておくことが重要です。
金融機関からの借り入れや、従業員持株会の活用など、資金調達の方法を多角的に検討しておくことが求められます。
従業員承継の方法と流れ!事前に把握しておくべきリスクや注意点を解説
M&Aによる事業承継のリスク
M&Aによる事業承継では、現経営者が納得できる売却価格で合意できないリスクがあります。事業の資産価値が低かったり、将来の成長性が乏しかったりする場合、買い手企業から高い評価を得ることは難しいでしょう。
加えて、経営者自身が企業価値評価に関する知識が不足していると、適正な売却価格を判断できず、本来得られたはずの売却益を逃してしまう可能性もあります。
これらのリスクに対応するには、事業承継の全プロセスを通じて、専門家の支援を仰ぐことが不可欠です。M&Aに精通した税理士や公認会計士、M&A仲介会社などの専門家と連携し、適切な企業価値評価と売却価格の交渉を進めることが重要です。
M&Aとは?買手・売手の目的やメリット・デメリット、手法、費用まで解説
事業承継リスクへの対応策
事業承継のリスクへの対応策として、以下の内容を検討しておきましょう。
- 早い段階で事業継承を進める
- 後継者を育成しておく
- 経営の問題点を洗い直す
- 国の制度を理解しておく
- 相続対策も進めておく
- 専門家に相談する
それぞれの対策でリスク回避が見込める理由について、以下で解説します。
早い段階で事業継承を進める
事業承継は、早い段階から準備に取り掛かることが何よりも重要です。引き継ぎを検討する10年前を目途に、具体的な準備を開始しましょう。
事業承継には、後継者教育も含めて5年から10年の時間を要します。2~3年前になって慌てて準備を始めても、スムーズな引き継ぎは望めません。リスク回避の観点からも、早期からの取り組みが欠かせません。
後継者を育成しておく
後継者教育では、現経営者が培ってきた経験やノウハウを余すところなく伝授する意識が重要です。表面的な数字だけでなく、経営理念やノウハウまでしっかりと継承することが、事業承継後の安定経営につながります。
日々の業務の合間を縫って、理念の共有や人脈の引き継ぎなどを進めておくことが重要です。万全の体制で引き継ぎができなければ、承継後の経営が傾くリスクが高まります。
経営の問題点を洗い直す
事業承継を行う前に、現在の経営の問題点を明確に把握し、可能な限り解決しておくことが重要です。問題点を曖昧にしたまま引き継いでしまうと、後継者に大きな負担を強いることになります。
実際、事業承継後に経営問題が表面化し、苦労する後継者は少なくありません。現経営者は、経営状態や問題点を徹底的に洗い出し、引き継ぎ前に解決しておくことが求められます。
国の制度を理解しておく
事業承継に伴う相続税・贈与税対策では、国の支援制度を有効活用することが重要です。代表的な制度として、相続税・贈与税の納税猶予や免除を受けられる「事業承継税制」などがあります。
これらの制度を活用することで、税負担を大幅に軽減できる可能性があります。現経営者と後継者の双方にとって、税務リスクの回避は大きな課題です。制度の理解を深め、有効に活用することが重要です。
相続対策も進めておく
親族内承継の場合、事業承継と並行して相続対策も進めておく必要があります。中小企業では親族への承継が多いため、相続対策は欠かせません。
相続対策では、遺言の作成、手続き対策、相続人間のトラブル防止、相続税対策など、多岐にわたる準備が求められます。時間もかかるため、事業承継の検討と同時に、相続対策にも着手することが効率的です。
専門家に相談する
事業承継では、経営者だけでは解決が難しい専門的な課題が数多く発生します。企業価値評価、相続・贈与税の算出、M&Aにおける売却先の選定など、高度な知識が求められる業務が少なくありません。
経営者のみで対応しようとすると、「正確な計算ができない」「本業に支障をきたす」などのリスクが生じます。円滑な事業承継のためには、税理士や公認会計士、M&A専門家などの専門家に相談し、適切な支援を受けることが不可欠です。
事業承継の相談窓口6選!相談相手の選び方や注意点まで徹底解説
事業承継のメリットは?
ここまでで「事業承継のリスクが不安」と感じてしまう方もいるかと思います。
確かに解説したように事業承継にはリスクがありますが、一方で以下のようなメリットがあります。
- 会社を残せる
- 売却益を獲得できる
- 従業員の雇用を確保できる
以下でそれぞれのメリットについて解説しますので、事業承継をするか否かを判断する際の参考にしてください。
会社を残せる
事業承継の最大のメリットは、築き上げてきた会社を次世代に引き継ぐことができる点です。後継者不在のまま廃業に至れば、長年培ってきた技術・伝統・価値は全て失われてしまいます。特にオーナー経営者にとって、思い入れのある会社が消滅するのは断腸の思いでしょう。
事業承継を実現することで、オーナー経営者の理念や社会的価値を持つ会社を存続させることができます。
売却益を獲得できる
親族外承継やM&Aの場合、株式や事業の売却益を得ることができます。一方、廃業の場合は残った資産を株主に分配するだけでなく、負債が資産を上回るケースもあり得ます。加えて、設備や在庫の処分にもコストがかかります。
廃業では手元に残る金額が限られるのに対し、事業承継では適正な対価を得られる可能性が高いのです。
従業員の雇用を確保できる
事業承継は、従業員の雇用を守る上でも重要な意義を持ちます。廃業となれば、従業員は新たな職を探さなければなりませんが、事業承継が実現すれば、同じ職場で働き続けることができます。
ただし、経営者が代わることで経営方針や労働環境が変化し、従業員の不満を招くリスクもあります。会社の状況と従業員の満足度を考慮しつつ、最適な後継者を選ぶことが必要です。
事業承継の進め方を解説!成功させるためのポイントも紹介します
専門家に相談し、リスクを避けた事業承継を | まとめ
事業承継のリスクを避けるためには、専門家へ相談しながら進めていきましょう。ほとんどのリスクは、経営者自身が進めてしまうことで起こります。早い段階から専門家に相談して進めていけば、リスク対策を行いながら事業承継を進めていくことができます。
事業承継の相談窓口6選!相談相手の選び方や注意点まで徹底解説
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。


