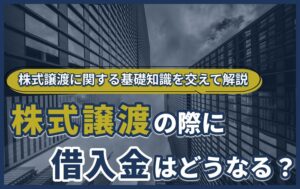会社相続でよくあるトラブルと解決策について解説
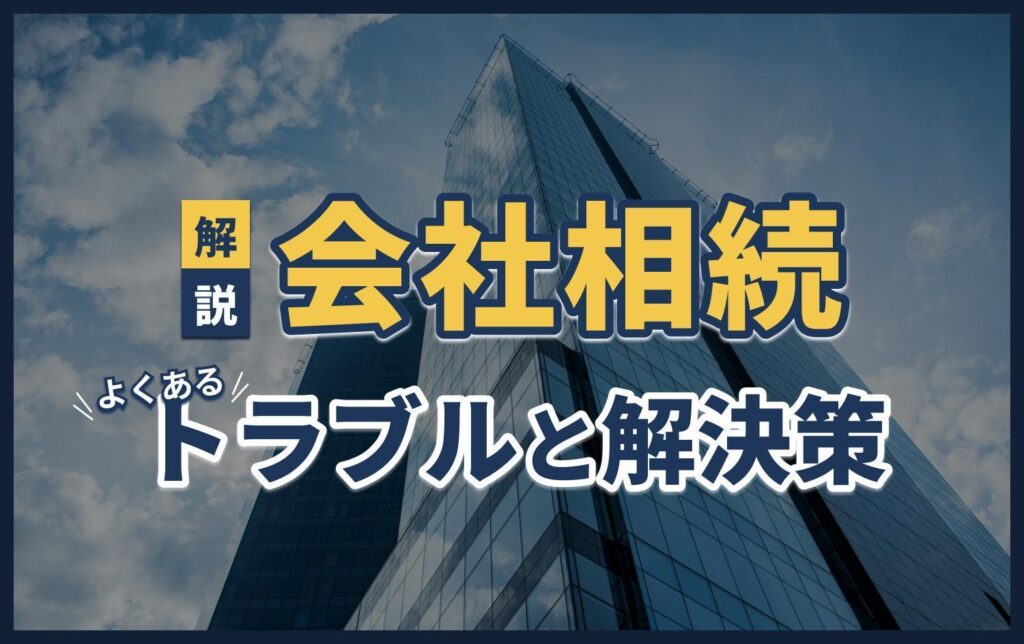
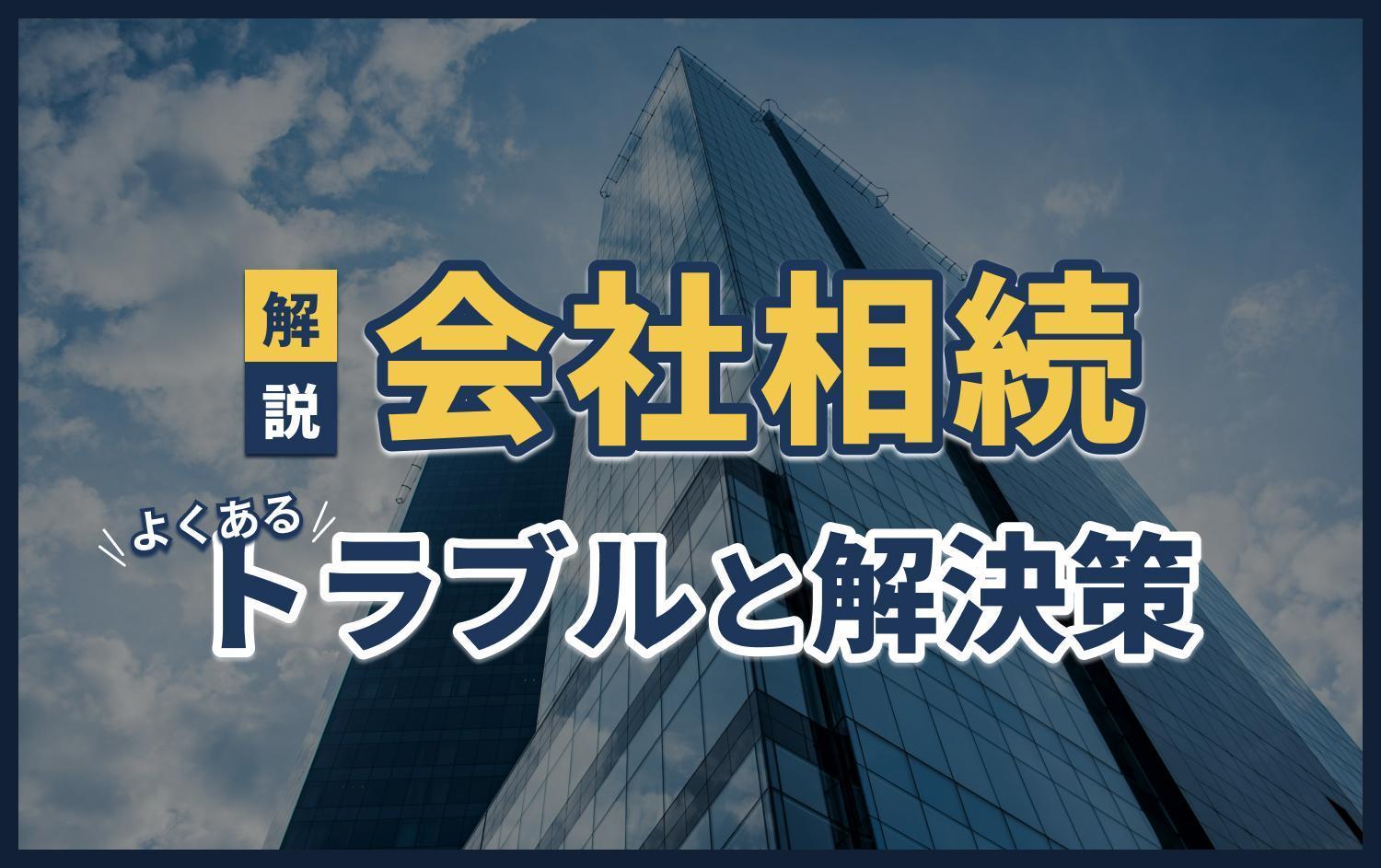
「会社の相続、どうしたらいいの?」
「トラブルが不安で、なかなか一歩が踏み出せない…」
このような悩みを抱える経営者の方は、きっと少なくないのではないでしょうか。会社を次の世代へバトンタッチするプロセスには、様々な課題が伴います。とりわけ、思いがけないトラブルに直面し、立ち往生してしまう経営者も多いものです。
この記事では、会社相続の際によく起こるトラブルを取り上げ、その解決策をご提案します。
会社を相続するステップ
まずは前提として、相続の手順から確認していきましょう。
1.自社株を相続する
会社が法人の場合、オーナー経営者の相続財産には自社株式が含まれることになります。相続発生後、遺言書の有無に応じて、自社株式の承継手続きを進めることになります。
遺言書がある場合は、遺言執行者のもと、遺言の内容に沿って株式が承継されます。遺留分に関する調整は避けて通れません。民法の規定を踏まえつつ、円滑な遺産分割を目指すことが肝要です。
一方、遺言書がない場合は、法定相続分に従って株式が承継されることになります。株式の分散を避けるためにも、生前から株主間契約を締結するなど、事前の備えが重要となります。
いずれにせよ、自社株式の相続は、会社の経営権に直結する重大事項。株主間の対立を避け、スムーズな承継を実現するには、綿密な事前準備と、専門家の的確な助言が欠かせません。
2.株式の名義変更
自社株式の相続が完了したら、次は株式の名義変更手続きです。相続人が取得した株式について、株主名簿の記載を書き換える必要があります。
具体的には、相続人から会社に対し、名義書換請求を行います。請求書には、相続人の氏名・住所、被相続人の氏名、相続株式数などを記載します。印鑑証明書や相続関係説明図など、必要書類を添付して提出します。
会社は、請求書を受理した後、取締役会で承認し、株主名簿の記載を変更します。変更後の株主名簿には、相続人の氏名が新たに記載されることになります。
名義変更の手続きは、あくまでも形式的なものです。しかし、株主としての権利義務は、名義書換の時点で相続人に移転されます。議決権の行使など、株主権の適切な管理は欠かせません。
3.代表者の就任
名義変更の完了後、相続人が会社の経営権を掌握するためには、代表取締役に就任する必要があります。通常、株主総会で選任されることになりますが、定款で別途定めがある場合は、取締役会の決議でも可能です。
代表取締役の選任は、会社の意思決定機関の交代を意味します。事業の方向性や経営戦略の転換など、大きな舵取りが求められる局面と言えるでしょう。
従業員をはじめとするステークホルダーへの説明責任も重要です。「社長が代わっても、会社の本質は変わらない」。そんなメッセージを、行動を通じて示していく必要があります。
リーダーシップの発揮と同時に、旧経営陣との連携も大切。引継ぎ資料の作成や、顧客の紹介など、協力を惜しまないことが円滑な交代の秘訣です。
4.変更手続き
代表者の交代に伴い、各種の変更手続きが必要となります。商業登記の変更をはじめ、銀行印の変更、税務署への届出など、実務的な対応が求められます。
商業登記の変更は、代表者の就任後2週間以内に行う必要があります。登記申請書に、就任承諾書や印鑑証明書などを添付し、管轄の法務局に提出します。登録免許税の納付も忘れないようにしましょう。
銀行印の変更は、金融機関との取引を継続するために不可欠です。まずは、旧代表者の協力を得て、銀行印の引継ぎを行います。その上で、金融機関に対し、代表者変更の届出と、新しい銀行印の登録を申請します。必要書類を整えて、速やかに手続きを進めましょう。
税務署への届出も、代表者変更後の重要な実務です。「異動届出書」に必要事項を記入し、印鑑証明書などを添えて提出します。青色申告の承認を受けている場合は、「青色申告承認申請書」の提出も必要です。税理士など専門家の助言を仰ぎつつ、期限内の手続きを心がけたいものです。
①後継者が決まらない

「誰に会社を任せればいいのか…」。事業を引き継ぐ適任者が身内に見当たらない場合、悩みは尽きませんよね。でも大丈夫です。今は”親族外承継”の選択肢も広がっています。
親族内の候補者を見つけるためには、後継者教育が欠かせません。会社の将来像を語り合える信頼関係を築きつつ、経営ノウハウを計画的に伝授していきます。時には、外部セミナーなどで刺激を与えるのも効果的でしょう。
また、候補者の意欲を引き出すには、会社の魅力アップも重要です。事業の将来性を高める取り組みを通じて、「この会社を引き継ぎたい」と思ってもらえる環境を整えていきましょう。
また、M&Aによる事業承継が注目を集めています。後継者探しに悩む経営者にとって、有力な選択肢の一つと言えるでしょう。
M&Aのメリット
M&Aのメリットとしては、まず、幅広い後継者候補を確保できる点が挙げられます。社内外から適任者を探すことで、事業への理解と意欲を兼ね備えた人材に出会えるチャンスが広がります。
また、M&Aを通じて、自社にない経営資源を獲得できるのも魅力です。販路拡大や技術革新など、事業の発展につながる相乗効果が期待できます。
M&Aのデメリット
一方で、M&Aにはリスクも伴います。社内の反発や取引先の動揺など、関係者の不安に配慮しつつ進める必要があります。何より、譲渡金額や条件面で折り合いをつけるのは容易ではありません。
M&Aを円滑に進めるには、専門家による適切なアドバイスが不可欠です。
M&A仲介会社や法律や税務の専門家など、頼れる存在を見つけ、第三者の知恵も借りながら、将来を見据えた選択をしていきましょう。
②株式を複数の相続人で相続することになった
「兄弟姉妹で株式を分けたら、会社の意思決定が大変そう…」。株主が増えることで経営に支障をきたすのは困りものです。でも、大丈夫です。対策はあります。
生前贈与で株式を集約したり、種類株式を活用して議決権を調整したりできます。さらに、遺留分に関する民法特例で、株式の分散を防ぐこともできます。弁護士など専門家とよく相談し、備えあれば憂いなしです。スムーズな株式承継を実現しましょう。
種類株式の中でも、議決権制限株式の活用が有効でしょう。一定の株主には議決権を付与せず、経営への影響力を制限するというアイデアです。株主間の合意を得て定款変更を行うことで、スムーズな導入が可能になります。専門家のアドバイスを受けつつ、自社に最適な仕組みを設計していきましょう。
また、遺言の活用も大切です。生前に遺言書を作成し、株式の分配方法を明確にしておけば、相続発生後のトラブルを未然に防げます。「自筆証書遺言」であれば、証人2名以上の立会いのもと、全文を手書きで作成すれば有効です。
ただし、遺言執行の段階で、遺留分への配慮は欠かせません。民法で定められた、法定相続人の最低限の取り分について、しっかりと話し合いを重ねることが重要です。
③得意先からの反応が悪い
「代表が代わると、取引先から信用されず…」。確かに後継者の交代に不安を覚える取引先は少なくありません。不安を払拭するためには、後継者を早めに選定し、時間をかけて育成しましょう。「この人なら安心」と、信頼してもらえる関係づくりが大切です。トップ同士の引き合わせを、計画的に進めていきましょう。
後継者教育では、取引先との関係構築も重要なテーマです。営業同行の機会を増やし、商談の場での振る舞いを学ばせます。挨拶状の書き方から電話応対まで、ビジネスマナーの基本を身につける訓練も欠かせません。
加えて、日頃から後継者への権限委譲を進めておくことも大切です。取引先との交渉の場に、徐々に参加させる機会を作りましょう。トラブル対応など、実際の仕事を通じて信頼を得る努力が、承継後の取引継続にも直結するはずです。
④社内からの理解が得られない

「急に若い後継者が就任したら、社員の反発が心配…」。確かに、従業員の協力なくして円滑な承継はありえません。でも、大丈夫です。コミュニケーションの積み重ねでクリアできます。
円滑な事業承継には、従業員の納得感が何より重要です。後継者に対する「あの人についていこう」という意識を、いかに醸成できるかが勝負どころとなります。
後継者教育のプロセスでは、トップの右腕としての役割を徐々に担わせていくことが大切です。
まずは重要な会議の司会進行や、経営計画の策定など、責任あるミッションを任せてみましょう。上司や同僚の協力を仰ぎつつ、リーダーシップを発揮する機会を増やしていけば、自ずと信頼も高まっていくはずです。
「この人なら、安心して会社を任せられる」というような空気感が社内に醸成されれば、スムーズな事業承継は目前です。従業員の理解を得るために、地道な対話と行動の積み重ねを惜しまないことが重要と言えるでしょう。
⑤後継者が相続税や贈与税を払えない
経営者から見れば、「いくら後継者が優秀でも、税金が払えなければ承継は実現できない」というような不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
自社株の評価方法を工夫することで、相続税・贈与税の負担を減らせる可能性があります。
例えば、類似業種比準方式や純資産価額方式など、複数の評価方式を組み合わせるアプローチがあります。株価を適正に算定することで、納税額の圧縮につなげられるのです。
さらに、自社株の一部を役員・従業員持株会に譲渡する方法も有効です。分散した株式を計画的に買い戻すことで、議決権の集中と相続税対策を同時に実現できます。
税理士など専門家とも相談しつつ、自社に最適な対策を講じていくことが肝心です。
事業承継と税務対策は切っても切れない関係にあります。事業承継税制を活用しつつ、中長期的な視点から承継資金の手当てを考えることが大切です。
⑥事業承継後に業績不振に陥る
「せっかく引き継いだのに、業績が低迷したら…」というのは、誰しもが抱く不安ですよね。でも、心配ご無用です。備えるに越したことはありません。
事業承継前から、後継者と二人三脚で会社の体質強化に取り組むことが大切です。「磨き上げ」と言われるステップです。「磨き上げ」のポイントは、自社の強みを見極めることです。技術力や営業基盤、顧客ネットワークなど、他社には真似できない独自の価値に目を向けます。その優位性をいかに引き出し、磨き上げていくかが勝負どころです。
加えて、事業承継を機に、社内外の人材を登用し、組織体制を一新するのも一案です。社外取締役の招聘や、幹部人事の入れ替えなど、経営の透明性を高める工夫がうまくいくケースは少なくありません。
⑦相続人が遺留分を主張する
「株式の多くを後継者に集中したら、相続人から文句が…」というように、遺産分配への不満から、承継がごたごたするのは避けたいものです。でも、大丈夫です。知恵を絞れば解決の道は拓けます。
遺留分に関する民法特例の活用がお勧めです。経済産業大臣の確認を経て、株式を遺留分算定の対象から除外する合意が可能です。この際、弁護士など専門家のアドバイスが必要となります。
まとめ
事業承継は、中小企業の経営者にとって避けては通れない重要な課題です。後継者選びから株式の譲渡、税務対策まで、乗り越えるべきハードルは決して少なくありません。
特に、思いがけないトラブルに直面し、身動きが取れなくなるケースは少なくありません。後継者不在、株式分散、従業員の反発、業績低迷、遺留分問題など、承継の障壁は多岐にわたります。
どんな難局にも、必ず打開策はあるはずです。M&Aや親族外承継の検討、自社株評価の工夫、従業員とのコミュニケーション、経営改善の取り組み、民法特例の活用など、様々な角度から知恵を絞りましょう。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。