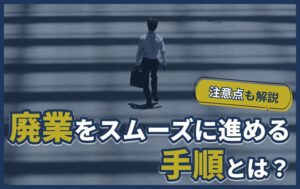株式譲渡で会社を売却したら役員の退職金は出るのか?節税方法も解説


「会社売却を株式譲渡で行った場合に退職金は出るのか」、「役員退職金スキームとは何か」、「役員退職金スキームを活用する売手側・買手側のメリットは何か」など、疑問に感じているのではないでしょうか。
本記事では、株式譲渡を検討している法人に向けて、株式譲渡と役員退職金の基本から会社売却を株式譲渡で行った場合に退職金は出るのか、役員退職金スキームの概要・メリット・注意点について解説します。
目次
株式譲渡と役員退職金の基本
株式譲渡による会社売却時の節税方法として、役員退職金の活用があります。役員退職金は損金として計上できるため、会社の売手側と買手側の双方に税金面でのメリットがあります。
株式譲渡、および役員退職金について解説します。
株式譲渡とは
株式譲渡とは、会社の経営権を持つオーナーが、経営権の譲渡を目的として所有する株式を売却することです。株式譲渡を行うことで、売手側は譲渡の対価として金銭を受け取り、買手側は会社の経営権を所得します。会社のオーナーではない株式保有者が株式を売る場合は、株式売買もしくは株式売却と表現されます。
事業譲渡や第三者割当増資、株式交換、合併、分割といったM&Aの手法のひとつであり、中小企業のM&Aで利用されることが多い手法です。ほかの手続きと比べて簡単に行えて、買手側は会社が保有する資産や契約をそのまま引き継げます。
株式譲渡とは?事業譲渡との違いや4つのメリット、税金などを解説
役員退職金とは
役員退職金とは、取締役や監査役などの役員が任期満了や辞任などで退職した際に支払われる金銭です。役員退職慰労金と呼ばれる場合もあります。
一般の従業員へ支給される「退職金」とは、支給条件や計算方法が異なります。そのため、退職する役員へ慰労金を支払う場合は、「退職金」ではなく「役員退職金」と表現されるケースが多いです。
役員退職金(役員退職慰労金)については法律上の定義がなく、退職所得として取り扱われます。役員退職金を支給するためには、株主総会の決議で承認を得るか、定款に定めておくことが必要です。
また、一般社員の退職金と同様に、企業が役員に対して役員退職金(役員退職慰労金)を支払う義務はありません。役員に対して役員退職金(役員退職慰労金)を支払うかどうかは、企業の判断に任されています。
会社売却を株式譲渡で行った場合に退職金は出るのか?
会社が従業員や役員へ退職金を支給できるのは、一定の要件を満たしている場合だけです。
給与や残業代とは異なり、要件を満たしていない場合は、会社が退職金を支給することはできません。
また、会社には雇用する従業員や役員へ給与や残業代を支払う義務がありますが、会社が従業員や役員へ退職金を支給する義務はありません。退職金は法的に定義されておらず、支給する金額に関する定めがないため、相場より高い金額を支給できます。
ただし、極端に高い金額の退職金を支給していた場合は、税務調査を受けた際に損金計上が認められない場合があります。
一方、会社が従業員や役員へ退職金を支給できるかどうかは、会社が売却されたか、株式譲渡による会社売却なのかとは関係ありません。つまり、会社売却を株式譲渡で行ったかどうかに関わらず、要件を満たしていれば支給でき、要件を満たしていなければ支給できないということです。
会社売却を株式譲渡で行った場合においても、代表取締役が自身へ役員退職金を勝手に支給することはできません。
従業員退職金
従業員退職金とは、従業員が退職する際に、給与や残業代などとは別に支給する金銭です。
給与や残業代などについては、会社側に支給する法的な義務があります。しかし、退職金については会社に支給する法的な義務はありません。支給するかどうかの判断は、会社に任されています。
会社が従業員へ退職金を支給できる要件
-
- 従業員が退職していること
- 就業規則に退職金制度に関する記載があること
会社は、従業員へ支給した退職金の全額を損金として計上できます。退職金は退職所得に該当するため、退職金を受け取った従業員は分離課税制度で所得税を算出します。
会社のオーナーが株式譲渡で会社を売却した場合は、会社の経営者が変わるだけであり会社自体はそのまま存続します。そのため、従業員と会社の間で締結されている雇用契約、退職金制度についてはそのまま維持されます。
会社のオーナーが株式譲渡で会社を売却したからといって、従業員が退職することにはなりません。従業員が会社都合もしくは自己都合で退職する場合は、会社の退職金制度にもとづいて退職金が支給されます。
役員の退職金
会社が役員へ退職金を支給できる要件は以下のとおりです。
-
- 役員が退職(退任)している
- 役員退職金について定款に定めている
- 株主総会の決議で承認を得ている
就業規則に退職金制度に関する記載があれば、一般社員へ退職金を支給できます。しかし、就業規則に退職金制度に関する記載があるだけでは、役員へ役員退職金を支給できません。
また、会社には役員へ給与や残業代を支給する法的な義務がありますが、一般社員の退職金と同様に、役員退職金については会社に支給する法的な義務はありません。役員へ役員退職金を支給するかどうかの判断は、会社に任されています。
会社が役員へ退職金を支給するためには上記要件を満たしている必要があり、退職していない役員へ役員退職金を支給したり、株主総会の決議を経ることなく勝手に支給したりすることはできません。
ただし、会社分割に伴う分掌変更により事実上役員を退職したケースや、会社清算に伴う清算人に選定されたケースについては、役員が退職していない場合でも、役員退職金(役員退職慰労金)を支払うことは可能です。
会社分割で役員に退職金はどうなる?計算方法や損金算入の可否などを解説!
株式譲渡の場合は役員退職金スキームを活用しよう
会社のオーナーが株式譲渡により会社を売却する場合、役員退職金スキームを利用することで、自身が支払う納税額を抑えられます。
売手側は手取り額が多くなり、買手側にとっても会社の経営権を通常よりも低い金額で得られます。売手側と買手側の双方にメリットがあるため、中小企業のM&Aでは役員退職金スキームが利用されるケースが多いです。
ただし、役員退職金を恣意的に活用し、税務法上妥当とはいえないような高額な役員退職金を役員へ支給した場合は、税務調査で役員退職金の損金計上が否認される恐れがあります。
また、高額な役員退職金を支給することで会社の資金が減少し、資金繰りが悪化する恐れもあります。
役員退職金の金額については、功労倍率というものがあります。退職金の金額計算において一定の計算式を用いたときに、功労倍率2倍から3倍程度までは退職金として高額ではない範囲とされる考え方です。
ただし、この考え方にあてはまれば安全というわけではなく、この考え方にあてはめるために役員在任期間のうち最後の月だけ給与を上げるなどした場合は、税法上妥当といえないような高額な役員退職金と判断される可能性もあります。
役員退職金スキームは税制上効果的な手法ですが、恣意的に運用すると節税効果が得られなくなるケースもあるため、公認会計士や税理士など専門家に相談したうえで実施しましょう。
役員退職金スキームとは
株式譲渡による会社売却における役員退職金スキームとは、売手側が会社を売却する前に会社オーナーへ役員退職金を支払うことで、株式を保有する会社オーナーへ支払う金額を抑える手法です。
買手側は、役員退職金スキームを利用しない場合より、会社オーナーへ支払う金額が少なくなります。
売手側は、株式を保有する会社オーナーの納税額が少なくなります。
-
- 譲渡する株式の価値:10億円
- 株式取得価額:3億円
- 役員退職金:1億円
役員退職金スキームを利用しなかった場合、買手側は売手側である株式を保有する会社オーナーへ10億円を支払い、会社オーナーは買手側から10億円を受けとります。会社オーナーの株式譲渡における売却益は7億円となり、7億円に対して所得税を納付します。
役員退職金スキームを利用した場合は、買手側は売手側である株式を保有する会社オーナーへ9億円を支払い、会社オーナーは買手側から9億円を受けとります。会社オーナーの株式譲渡における売却益は6億円となり、6億円に対して所得税を納付します。
また、役員退職金の1億円に対しても所得税を納付します。
退職金の退職所得課税の仕組み
従業員や役員が退職時に受けとる退職金は退職所得とみなされ、分離課税制度が適用されます。分離課税制度とは、給与所得や事業所得などの所得とは合計せずに、切り離して所得税を計算する制度です。
分離課税制度の対象となる所得は以下のとおりです。
-
- 配当所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 利子所得
退職金に対する所得税の計算式は以下のとおりです。
所得税額 = 課税退職所得金額 × 所得税率
課税退職所得金額の計算式
| 一般退職所得 | (退職手当額-退職所得控除額)×2分の1 |
| 特定退職所得(勤続5年以下の役員等) | 退職金−退職所得控除額 |
退職所得控除額
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
| 20年以下 | 40万円×勤続年数 ※合計が80万円に満たない場合は80万円 |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 × (勤続年数 – 20年) |
参考資料:退職金と税「国税庁」
所得税率
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
参考資料:No.2260 所得税の税率「国税庁」
株式売却益の譲渡所得課税の仕組
個人が株式を譲渡した場合は、売却益に対して所得税が課税されます。株式譲渡による売却益にかかる所得税の計算では、分離課税制度が採用されています。分離課税制度とは、給与所得や事業所得などの所得とは合計せずに、切り離して所得税を計算する制度です。
分離課税制度の対象となる所得は以下のとおりです。
-
- 配当所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 利子所得
個人が株式を譲渡することで得た所得は譲渡所得となるため、分離課税制度が適用されます。たとえば、事業所得で1,000万円の損失が出ていて、株式譲渡で1,000万円の利益が出ていた場合、損失と利益が相殺されて課税所得がゼロになるわけではありません。
上記の場合では事業所得に対して所得税が発生しませんが、株式譲渡による譲渡所得1,000万円に対して課税されます。
役員退職金スキームのメリットと注意点
役員退職金スキームに関する以下の点を解説します。
-
- 役員退職金スキームを活用する売手側のメリット
- 役員退職金スキームでの買手側のメリット
- 役員退職金スキームでの売手側の注意点
- 役員退職金スキームでの買手側の注意点
役員退職金スキームを活用する売手側のメリット
役員退職金スキームを活用する売手側のメリットは、役員退職金スキームを利用しない場合より、納税額が少なくなることです。役員退職金の所得税計算では、分離課税制度が適用され、退職所得控除も受けられます。そのため、譲渡する株式の全額をそのまま受けとるよりも、納税額を抑えられます。
役員退職金スキームでの買手側のメリット
役員退職金スキームでの買手側のメリットは、役員退職金スキームを利用しない場合よりも、会社オーナーへ支払った役員退職金の金額分だけ低い金額で経営権を取得できることです。また、株式の取得価額は損金算入できませんが、会社オーナーへ支払った役員退職金は損金算入できるため、節税効果を得られます。
役員退職金スキームでの売手側の注意点
役員退職金スキームでの売手側の注意点は、譲渡所得と退職所得に対する税率の違いです。
株式を譲渡した場合の税率は、売却額に関わらず一律で20.315%です。一方、退職所得の税率では累進課税が採用されるため、最大で45%となります。
株式売却額と比べて役員退職金が非常に高い金額の場合は、かえって納税額が高くなってしまう恐れがあります。
役員退職金スキームでの買手側の注意点
役員退職金スキームでの買手側の注意点は、以下の2点です。
-
- 役員退職金の損金計上が認められない可能性がある
- 資金繰りが悪化する恐れがある
役員退職金を恣意的に活用し、税務法上妥当とはいえないような高額な役員退職金を役員へ支給した場合は、税務調査で役員退職金の損金計上が否認される恐れがあります。また、高額な役員退職金を支給すると会社の資金が減少するため、資金繰りが悪化する恐れもあります。
まとめ
今回は、株式譲渡と役員退職金の基本から会社売却を株式譲渡で行った場合に退職金は出るのか、役員退職金スキームの概要・メリット・注意点について解説しました。
株式譲渡による会社売却では、役員退職金スキームを活用することで、資金を抑えて会社の経営権を取得することが可能です。ただし、役員退職金が適正額の範囲を超えていた場合、損金計上が認められない場合があります。
株式譲渡額と役員退職金のバランスを意識して役員退職金スキームを活用しましょう。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。