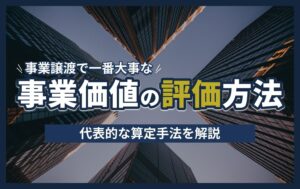会社更生法とは?再建手続きについて解説
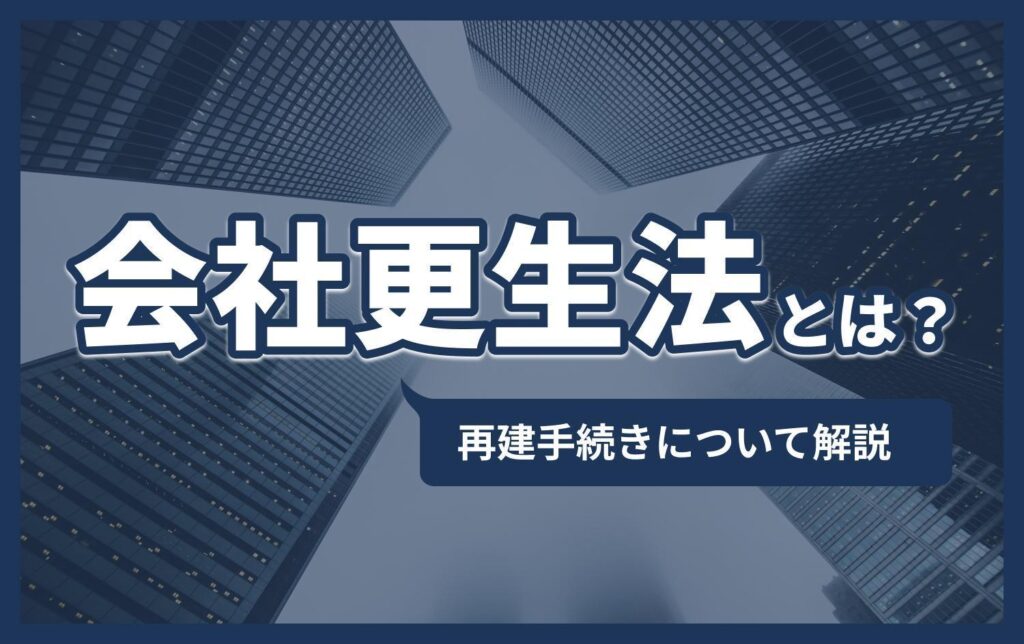
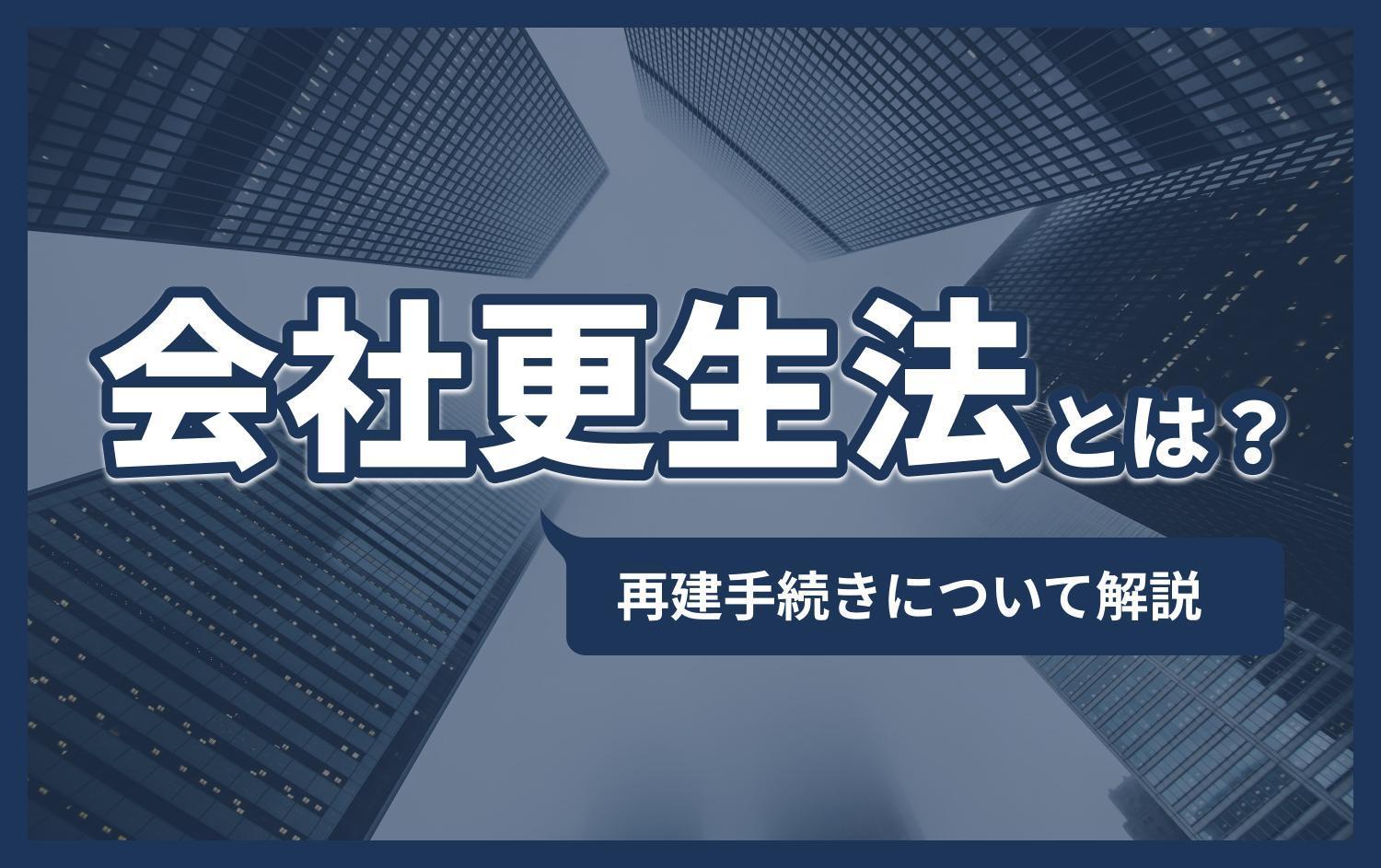
事業の継続が危ぶまれる状況に直面した時の選択肢として、会社更生法という法的手続きをご存知でしょうか。
会社更生法は、事業継続の見込みはあるものの、債務超過に陥っている企業が利用できる法的整理手続きの一つです。
民事再生法と並んで、経営困難な企業の再建を支援する重要な法律と言えます。
本記事では、会社更生法の基本的から、具体的な手続きの流れ、さらには活用事例まで、詳しく解説していきます。
会社更生法とは
会社更生法とは、支払い不能・債務超過になった企業が、裁判所の監督の下で再建を行うための法的手続きのことです。
会社更生法は、主に大企業を対象とした再建型倒産手続きです。裁判所の監督の下、会社更生計画を立て、関係者の同意を得ながら債務の弁済を行います。
会社更生手続きでは、会社の事業を継続しながら再建を進めることができます。これにより、ステークホルダーの利益を保護しつつ、企業価値の毀損を最小限に抑えることが可能となります。
会社更生法は、経営危機に陥った企業に対し、再生の機会を与える重要な法的枠組みと言えるでしょう。
会社更生のメリット
会社更生法適用には、以下のようなメリットがあります。
(1)会社の事業を継続できる
会社更生手続きでは、会社の事業を継続しながら再建を進めることができます。事業の継続により、従業員の雇用を維持し、取引先との関係を維持しながら、企業価値の維持・向上を図れます。
事業承継の観点からも、事業の継続は重要な意味を持ちます。事業の継続は、ステークホルダーからの信頼を維持する上でも不可欠です。
会社更生法は、事業の継続を前提とした再建を可能とする点で、大きなメリットがあると言えます。
(2)会社の再建を進められる
会社更生手続きでは、裁判所の監督の下、強力に会社の再建を進めることができます。
法的根拠があるため、関係者の協力を得やすいというメリットもあります。
裁判所が全体を監督することで、再建計画の確実な遂行が期待できます。債権者の利害調整も裁判所の下で公平に行われます。
会社更生法は、法的な後ろ盾を得ながら、スピーディかつ確実に再建を進める枠組みを提供しているのです。
会社更生のデメリット
会社更生法の適用には、以下のようなデメリットもあります。
(1)コストがかかる
会社更生手続きには、高額の費用がかかります。弁護士費用や管財人報酬など、専門家に支払う報酬が高額になる傾向があります。
また、手続きに時間がかかるため、その間の運転資金の確保も必要です。中小企業にとっては、コスト負担が重荷になる可能性があります。
会社更生法の適用を検討する際は、費用対効果を慎重に見極める必要があるでしょう。場合によっては、他の手続きの選択肢も視野に入れる必要があります。
(2)経営陣は退陣しなければならない
会社更生手続きでは、原則として、経営陣は退陣しなければなりません。
会社更生管財人が任命され、会社の経営権は管財人に移ります。創業者や現経営陣にとっては、経営権を手放すことへの抵抗感があるかもしれません。
特に、オーナー企業の場合、経営者の交代は大きな影響を及ぼします。
事業承継との関係でも、慎重な検討が必要となります。
会社更生法の適用が、かえって企業価値を毀損するリスクについても、十分に理解しておく必要があります。
(3)株式会社のみ可能
会社更生法適用を受けられるのは、株式会社のみです。合同会社などは、会社更生法適用対象外となります。
中小企業の中には、株式会社以外の形態を採用している会社も多いため、注意が必要です。会社の法人形態によっては、会社更生法の適用を断念せざるを得ない場合もあります。
事前に自社の法人形態を確認し、適用可能性を見極めておくことが重要です。
会社更生法は、大企業向けの再建型倒産手続きですが、中小企業の経営者にとっても、知っておくべき選択肢の一つです。
会社更生法と民事再生法の違い

会社更生法と民事再生法は、ともに企業の再建を目的とした法的整理手続きですが、いくつかの重要な違いがあります。
申立て要件に関する違い
まず申立て要件ですが、会社更生手続きは原則として債務者である株式会社のみが申立てを行えるのに対し、民事再生手続きは債権者も申立てが可能です。
また、会社更生手続きでは弁済不能が申立て要件とされていますが、民事再生手続きでは支払不能を申立て要件としています。
つまり、会社更生手続きの方が、より深刻な経営状態を想定しているのです。
債権者の権利の違い
債権者の権利に関しても違いがあります。会社更生手続きでは、更生計画案の決議に際し、
債権者を複数の組に分け、組ごとの決議が必要とされます。
一方、民事再生手続きでは、原則として債権者全員の同意を得る必要があります。会社更生手続きの方が、債権者の権利制限の度合いが大きいと言えます。
会社更生手続きの流れ
会社更生手続きは、以下のような流れで進められます。
(1)会社更生手続開始の申立て
申立ては、原則として債務者である株式会社が行います。裁判所は、申立書や添付書類を審査し、保全処分の要否を判断します。
この段階で、裁判所は、手続開始の適否を慎重に判断します。申立ての内容が不十分な場合は、訂正が求められることもあります。
(2)裁判所による保全処分の決定
裁判所は、必要に応じて会社財産の保全処分を決定します。
具体的には、会社財産に関する処分の禁止や、業務・財産の管理者の選任等が行われます。保全処分により、会社財産の散逸を防ぎ、手続の円滑な進行を図ります。
(3)会社更生手続開始の決定
裁判所は、申立てから原則として1ヶ月以内に、会社更生手続開始の決定を行います。同時に、管財人が選任されます。
手続開始決定により、会社は更生手続に入ることになります。管財人は、手続の中心的な役割を担うことになります。
(4)管財人による財産調査・評定
管財人は、債務者の財産状況を調査し、評定を行います。
また、債権者集会を招集し、債権の届出や調査を実施します。
この段階で、会社の財産状況や債権者の状況が明らかになります。調査結果は、更生計画案の作成に活用されます。
(5)更生計画案の作成・提出
管財人は、調査の結果を踏まえ、更生計画案を作成します。
計画案には、債権の弁済方法や減資・増資、事業の譲渡等の内容が盛り込まれます。
計画案は、債権者の権利の調整と、会社の再建策を具体化したものと言えます。
(6)更生計画案の決議・認可
更生計画案は、債権者集会での決議を経て、裁判所に提出されます。
各組の債権者の過半数の同意と、議決権の2/3以上の賛成を得られれば可決となります。
その後、裁判所による認可を得て、更生計画が確定します。
(7)更生計画の遂行・完了
更生計画の遂行は、債務者である株式会社が主体となって行います。計画の遂行状況は管財人が監督し、裁判所に報告書を提出します。計画が完遂されれば、裁判所は更生手続き終結の決定を行います。
以上のように、会社更生手続きは裁判所の関与の下で進められる公的な手続きです。
債権者の権利調整と事業の再建を図る過程では、管財人を中心に様々な調整が行われることになります。手続きの流れを理解した上で、専門家の助言を仰ぎながら、適切に対応していくことが重要です。
会社更生手続き中の経営と資金調達
会社更生手続中は、事業の継続に必要な資金の確保が重要な課題となります。手続開始後に調達する資金を「DIPファイナンス」と呼び、会社更生法でもその重要性が認識されています。
会社更生法は、更生手続開始後の資金借入れについて、「更生担保権」という優先的な担保権を設定できる旨を定めています。
これにより、金融機関等からの資金調達を容易にし、事業の継続を後押しする狙いがあります。
また、会社更生手続中の経営については、債権者委員会の意見を聴取しつつ、管財人が主導的に進めていくことになります。
株主総会の決議事項の多くは、管財人の権限に委ねられます。
債権者の利益を保護しながら、事業の再生を図っていく過程では、管財人の経営手腕が問われることになるでしょう。
会社更生手続中の経営では、事業計画の策定・実行や、ステークホルダーとの対話等、通常の経営以上に高度な舵取りが求められます。
外部の専門家の知見を活用しながら、再建に向けた道筋をつけていくことが肝要と言えるでしょう。
事業承継との関係
会社更生手続きは、事業承継にも大きな影響を及ぼし得ます。
特に、オーナー企業において、会社更生手続開始決定があった場合、オーナー経営者の経営権は大幅に制約されることになります。事業承継の前提となるオーナーの意向が反映されにくくなるおそれがあるのです。
加えて、会社更生手続により減資が行われれば、オーナー株主の持分は大幅に毀損されます。
創業家一族への事業の引継ぎを想定していたオーナー経営者にとって、会社更生手続の開始は、当初の事業承継プランを根底から覆しかねない事態と言えます。
他方、会社更生手続によって、新たなスポンサーを得て事業の再生と承継を図るという選択肢もあり得ます。
事業の存続可能性や各ステークホルダーの利害を見極めた上で、会社更生手続の活用を検討する必要があるでしょう。
いずれにせよ、事業承継と会社更生手続の関係性については、早期の段階から十分に検討・シミュレーションしておくことが大切です。
事業承継の計画策定に際しては、会社更生手続への対応方針も視野に入れておくべきでしょう。
まとめ
会社更生法は、事業の継続が困難な状況に陥った企業に対し、再建の機会を与える重要な法的手続きです。
裁判所の監督の下、債権者の権利調整を図りつつ、事業の再生を目指すことができます。
会社更生法の適用には、事業の継続や強力な再建推進力といったメリットがある一方で、高額な費用負担や経営陣の退陣といったデメリットもあります。
会社更生手続きは、申立てから計画の遂行・完了まで、複雑かつ時間を要するプロセスです。
手続き中は、管財人を中心に、債権者との調整や更生計画の作成等、様々な局面での対応が求められます。特に、事業の継続に必要な資金の確保や、ステークホルダーとの信頼関係の維持は、重要な課題となります。
また、会社更生手続きは、事業承継にも大きな影響を及ぼし得ます。オーナー経営者の経営権の制約や、株主持分の毀損等、当初の事業承継プランに変更を迫られる可能性があります。
会社更生法の適用は、企業の命運を左右する重大な決定です。メリット・デメリットを十分に理解し、自社の状況に合った判断を下すことが求められます。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。