吸収合併されたときの従業員の処遇は?告知なくリストラされる?
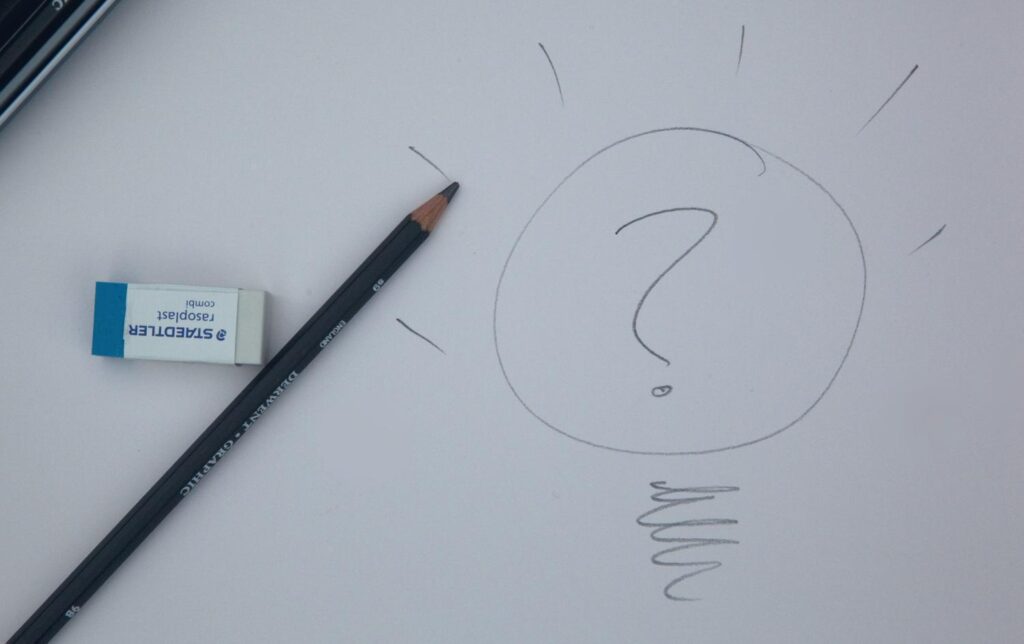
吸収合併を行う場合、合併後の従業員の処遇がどうなるのか気になる方も多いでしょう。
この記事では、吸収合併後の雇用契約や労働条件といった待遇面についてまとめました。
合併後、告知なくリストラが行われるのかについても解説しています。吸収合併が行われた後の従業員の処遇が気になる方は参考にしてみてください。
吸収合併とは?
吸収合併とは、2つ以上の会社を1つにまとめる合併方法の1つです。複数ある会社のうち、1社のみの法人格が存続し、その1社を除いた会社の法人格がなくなります。例えばA社がB社を吸収する場合、A社のみが法人格を継続し、B社は消滅することになるのです。
吸収合併が行われた場合、消滅会社が有していた資産や負債、権利義務は存続会社が全て引き継ぎます。前の例でいえば、B社が有している資産や負債・権利義務をA社がすべて引き継ぐ形になります。
吸収合併は複数の会社の資産や権利義務などを統合し、より効率的な経営を実現することを目的に実施されます。
また、消滅会社のリソースを存続会社が獲得することで、市場販路やシェアの拡大、新規分野への進出なども期待できます。
吸収合併の概要と種類
会社の合併には「吸収合併」と「新設合併」の2つの手法が存在します。
吸収合併は、複数の会社のうち、1社の法人格のみを残して経営を継続していく合併方法です。合併によって消滅する会社の資産や権利義務は、合併後存続する会社が全て引き継ぎます。
一方の新設合併は、2つの会社を消滅させたうえで、新たな会社を設立させる合併手法です。合併に関わる全ての会社が一度消滅し、新しく設立した新会社が消滅した会社の資産や権利義務を承継します。
吸収合併と新設合併の大きな違いは、「株主の対価の受け取り方」にあります。
吸収合併の場合、消滅会社の株主は、合併契約に従い、現金・株式・社債・新株予約権等の中から対価を受け取ることになります。一方の新設合併の場合は、株主が対価として受け取れるのは株式・社債・新株予約権のいずれかです。要するに、吸収合併と新設合併の違いは「現金を対価としてM&Aを実行できるかどうか」だといえるでしょう。
| メリット | デメリット | 違い | |
| 吸収合併 | ・複数の会社の資産や権利義務などを統一することで、効率的な経営が実現可能 ・シナジー効果 ・市場シェア、販路の拡大 ・消滅会社の権利義務を包括的に承継できるため手続きがラク |
・消滅会社と顧客が重複する可能性がある ・複数の会社が1つになるため、経営統合に時間がかかる |
・消滅会社の株主は現金・株式・社債・新株予約権の中から対価を受け取る ・一部業種を除き、新規の許認可や免許申請は不要 |
| 新設合併 | ・組織改編による生産性の向上 ・コスト削減 ・シナジー効果 ・事業規模の拡大 |
・必要となる許認可の新規取得が必要となるなど、手続きが煩雑 ・吸収合併よりもコストがかかる ・現金を対価としてM&Aを実行できない |
・消滅会社の株主は株式・社債・新株予約権の中から対価を選択できる ・許認可や免許の新規取得が必要 |
なお、新設合併では新しい会社を設立させることから、新たに許認可を取得したり、免許を申請したりする必要があります。1からすべての手続きをやり直す必要があるため、新設合併は吸収合併に比べ非常に手間がかかります。そのため、現状として実際の合併のほとんどが「吸収合併」となっています。
存続会社と消滅会社について
吸収合併に関わる会社は「存続会社」と「消滅会社」の 2種類に区分されます。
存続会社とは吸収合併後に法人格が残る方の会社のことで、M&Aにおける買い手企業が該当します。存続会社は消滅会社の権利義務を全て引き継いだうえで、事業を継続していきます。
一方の消滅会社は残った会社に吸収される方の会社のことで、M&Aにおける売り手企業がこれに当てはまります。合併後、消滅会社の法人格はなくなり、資産や負債、権利義務などを全て存続会社に譲り渡すことになります。
吸収合併されたときの従業員はどうなる?
吸収合併が行われる場合の従業員の処遇はどうなるのか、疑問を持つ方も多いでしょう。
ここでは吸収合併された場合の従業員の処遇について、以下の項目ごとに解説します。
- 雇用契約
- 吸収合併後のリストラ
- 給与などの労働条件
- 勤務形態や役職
- 福利厚生
- 雇用保険や社会保険
- 有給休暇
- 退職金
雇用契約
雇用契約は存続会社に引き継がれます。吸収合併では消滅会社の権利義務が全て存続会社に引き継がれるため、雇用契約に変更はありません。
民法上、雇用契約を引き継ぐ際には労働者に個別に承諾を得なければならないと規定されていますが、吸収合併の場合は労働者の個別の承諾を得ることなく雇用を継続できます。
ただし、雇用契約の内容については、吸収合併後に存続会社の雇用条件にすり合わせていく形が一般的です。存続会社内で雇用条件に格差があると、従業員のモチベーションの低下など、悪影響を及ぼしかねないためです。
吸収合併後に雇用契約を変更するケースがある旨を吸収合併実行前に説明し、従業員に周知しておくと、合併成立後も円満に雇用契約を見直せるでしょう。
吸収合併後のリストラ
吸収合併に伴い、雇用契約は自動的に存続会社に承継されます。そのため、吸収合併を理由とした解雇は実施されません。
ただし、希望退職などの手法によって吸収合併後にリストラが行われることはあり得るでしょう。
例えば、管理部門などの部署が重複するために、希望退職を募る形式でリストラが実施される可能性があります。合併が行われると部署によってはどうしても人員が過剰となってしまうためです。人員削減のために従業員の希望退職を募集することは珍しくありません。
そのほか、合併後の経営方針の変更などで配置転換を言い渡され、退職を選択する人もいるでしょう。
一方で、吸収合併を今後のキャリアを見直す良い機会として捉える人もいます。吸収合併後の統合プロセスに関われる機会はそう多くありません。そのような経験を積んだ人材はM&Aを検討している他企業にとって貴重な存在となります。経営統合の経験を転職の際の大きなアピールポイントとして活かし、キャリアアップを図る人も少なくありません。
給与などの労働条件
原則、給与などの労働条件に変更はありません。消滅会社で適用されていた雇用契約や就業規則、労働協約などは存続会社に包括して引き継がれます。
ただし、吸収合併後に労働条件が変更となる可能性は大いにあります。合併後は存続会社の労働条件に変更していくのが一般的です。
それでは、給与はどうなるのでしょうか。給与条件もそのまま存続されるため、2つの給与テーブルが存在することになってしまいます。このような場合、2つの給与テーブルを結合し、差額を「調整給」として支給していく方法を取る企業が多いでしょう。
ほかにも、「緩和期間」を設けて給与を調整していく方法もあります。1〜2年間程度の緩和期間を設け、段階的に給与額を変更していくのです。
給与は従業員のモチベーションに大きく影響します。合併後すぐに給与額を変更するのではなく、調整給や緩和期間といった措置を取り、徐々に金額を変更していく方法が一般的です。
勤務形態や役職
雇用契約の変更は基本的にありませんが、勤務形態変更や配置転換はあり得ます。例えば、営業部から企画部、製造部から人事職などへの配置転換が行われる可能性があるでしょう。
勤務形態の変更や配置転換は雇用契約の範囲内であれば法的には問題ないため、従業員に個別で合意を取る必要はありません。
それでは、役職についてはどうなるのでしょうか。残念ながら、管理職などの職位が保証されているわけではありません。そのままの職位で勤務し続けられるケースもあれば、吸収合併後に等級が下がる可能性もあります。
吸収合併を行うと、同じ部門が複数存在する場合が発生し、人員過剰になりがちです。同じ役職が複数人いる必要はないため、役職などの待遇面が変更となる場合があるのです。一般的には、消滅会社の役職者が降格となる場合が多いといえます。
福利厚生
福利厚生とは、従業員に支給される給与や賞与以外の報酬のことです。福利厚生は「法定福利厚生」と「法定外福利厚生」の2つに分けられます。
「法定福利厚生」は社会保険など、法律によって加入義務があるもの。住宅手当や通勤手当など、企業独自の制度は「法定外福利厚生」に該当します。
福利厚生は基本的には存続会社に包括承継されます。そのため、消滅会社で支給されていた福利厚生は合併後も利用可能です。
しかし、合併後には内容が変更になる可能性もあります。福利厚生を変更する場合、従業員に対し事前に書面で説明し、合意を得る必要があります。
雇用保険や社会保険
雇用保険や社会保険は継続されます。吸収合併後は消滅会社での資格を喪失し、存続会社において新たに資格を取得します。
合併後、雇用保険や社会保険を継続するために必要となる主な手続きは、以下の通りです。
| 雇用保険関係手続き | 社会保険関係手続き | |
| 存続会社 | ・同一事業主認定手続き | ・社会保険資格取得届 ・被扶養者異動届 |
| 消滅会社 | ・雇用保険適用事業所廃止届 ・雇用保険事業主事業所廃止届 ・同一事業主認定手続き |
・社会保険資格喪失届 ・適用事業所全喪届 |
手続きが遅れてしまうと、必要な給付を受けられないなど、従業員に不利益が生じる可能性があります。スムーズな手続きが行えるよう、計画的な準備が不可欠です。
有給休暇
消滅会社と従業員の間で結ばれた労働条件が引き継がれるため、有給休暇の取り扱いについても変更はありません。
ただし、吸収合併後は存続会社内での有給休暇の取り扱いと違いが生じることから、一定期間が過ぎたあとは、存続会社の規定に沿うケースが多いでしょう。
勤続年数が有給休暇の日数に関係する場合は、合併前の勤続年数が引き継がれます。
労働契約法第9条では、「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。」と規定されています。
従業員が不利益を被る労働条件の変更を行う場合、原則として、従業員の個別の同意が必要となる点には注意が必要です。
出典:労働契約法
退職金
退職金の取り扱いについても、原則変更はありません。退職金の計算方法は勤続年数がベースとなっており、合併前の勤続年数がそのまま引き継がれるため、合併前に想定されていた退職金が支給されます。
特に合併直後の退職であれば、合併前の会社の退職金制度が適用されるため、満額支給されるケースが大半です。
ただし、合併から一定期間が過ぎたあとは、存続会社の退職金制度に統一される可能性が高くなります。存続会社が定める退職金が合併前の会社の金額より低い場合、退職金が減額になってしまうケースもあるでしょう。
このように、原則として退職金は合併前の金額が支給されますが、場合によっては時間の経過とともに退職金が減額される可能性がある点には注意が必要です。
吸収合併後の従業員のモチベーションに対する影響は?
吸収合併を伝えられた従業員は今後の展望に不安を覚え、モチベーションが下がる可能性が大いにあります。
吸収合併が経営者にとって最良の選択肢であっても、従業員にとっては不安の要因となるものです。
「解雇されるのではないか」「給与が減るのではないか」などの不安を抱き、転職を検討する従業員もいるかもしれません。
大量の離職者を出さないためには、吸収合併後の待遇について十分な説明を行う必要があるでしょう。
特に合併後にリストラや解雇が行われないことや、雇用条件はそのまま引き継がれることを重点的に説明し、従業員の不安を取り除くよう働きかけましょう。
吸収合併による従業員への告知は必要?
吸収合併の際、会社法上、債権者への催告や株主への通知義務はありますが、従業員への告知は不要です。
吸収合併を理由にリストラが実施されたり、雇用条件の変更が行われたりするなど、従業員にとって不利益な変更は生じないため、法的に告知は義務付けられていないのです。
しかし、告知義務はなくとも、今後の事業継続のために従業員に説明を行うのが望ましいでしょう。
吸収合併では組織改編が行われるのが一般的です。配置転換や勤務形態の変更がある可能性が高いため、従業員に不安を与えないようにすることが重要です。
法的には吸収合併を行うことを従業員に告知する義務はありませんが、従業員のストレスを軽減するためにも、吸収合併について告知はしておくべきです。
吸収合併時の従業員の労務手続きについて
吸収合併では、消滅会社の雇用条件等を存続会社が引き継ぐことになります。そのため、存続会社内で同時に複数の雇用条件が存在する状態になってしまいます。
そのまま複数の雇用条件がある状態を継続してくことは可能です。しかし、企業内で格差が発生してしまうため、不公平に感じる従業員が増える要因となり得ます。人事管理の手間も増え、混乱が生じるといったデメリットも出てくるでしょう。
そこで吸収合併時には、消滅会社と存続会社の人事制度や雇用条件などの統合作業が必要になります。
多くの場合、消滅会社の人事制度や雇用条件を存続会社の条件に合わせていく作業が行われますが、全く新しい雇用条件・人事制度を作成する企業もあります。
合併後の統合作業では、不利益変更にならないように注意が必要です。不利益変更とは、給与の減額、手当や福利厚生の廃止など、従業員にとって不利益な変更を実施することです。原則、会社の都合による労働条件の不利益変更は認められません。
不利益変更を行う場合は、原則、従業員の個別の同意が必要になります。企業が一方的な不利益変更を行えば、従業員の反発を招くだけでなく、法的なリスクを負うことになるため注意しましょう。
まとめ
吸収合併は、消滅する会社をもう一方の会社に吸収させるM&A手法です。手続き上で合併したら終わりではなく、合併後に2つの会社が1つに融合していく過程では、時間をかけた調整が必要になるでしょう。
吸収合併を行う当事者は手続きだけにとらわれるのではなく、従業員一人ひとりのことを十分に考慮し、慎重に進めるよう心がけることが大切です。
吸収合併では基本的に雇用条件などが引き継がれるため、合併前と合併後の待遇に差は生じません。しかし、合併後の処遇に不安を感じる従業員は多く、ケアを怠ると優秀な人材が流出してしまう要因ともなり得ます。
トラブルなく吸収合併を進めるには、M&A仲介や専門家に依頼するのが得策です。経験・知識が豊富なアドバイザーによるサポートがあれば、合併後の従業員の待遇も含め、安心してM&Aを進められるでしょう。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。


