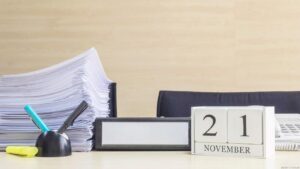M&A仲介手数料はどれくらいかかる?費用の内訳相場や会計処理を解説


M&Aを検討する際に必ず直面するのが、M&A仲介手数料です。M&A仲介業者はスムーズなM&A取引を実現するために、重要な役割を果たします。M&A仲介手数料は高額になる場合があり、M&Aを躊躇させる要因の一つとなっています。
そこで本記事では、M&A仲介手数料の内訳相場や、会計処理について詳しく解説します。
目次
目次
M&A仲介手数料とは?
M&A仲介手数料とは、買い手や売り手がM&A仲介会社などの専門家に支払う手数料のことです。M&A仲介手数料は、専門家により変動します。また、手数料には複数の種類があること、支払う金額・時期が会社により異なるため一概に決められていません。
代表的な手数料を内容も含めて一覧にしています。
| 手数料名 | 内容 |
| 相談料 | 契約締結前の相談料 |
| 着手金 | 契約が締結した際の手数料 |
| 業務実行にかかる手数料 | 出張費、契約書、書類作成などで発生する費用 |
| 中間金 | 買い手や売り手が締結した際に発生する手数料 |
| リテイナーフィー(月額報酬) | 毎月の月額定額手数料 |
| デューデリジェンス | 実態を事前に把握するための企業調査費用 |
| 成功報酬 | M&Aの成約時に発生する手数料 |
次に各手数料について詳しく解説をします。
相談料
M&Aの相談料は、正式な依頼をする前の相談料です。M&A仲介会社やアドバイザーにより異なりますが、無料~1万円程度が相場です。なかには数万円程度かかる場合もあるため、事前によく確認してから相談しましょう。
着手金
業務の本格的な依頼をするための手数料で、50万~200万円程度が相場です。案件の規模により幅があり、M&Aが成約しなかったとしても返金されないケースが大半のため注意をしましょう。
業務実行にかかる手数料
業務を実行する際にかかる手数料として出張費や契約書、書類作成などがあります。仲介会社によっては業務実行にかかる手数料を着手金や成功報酬などは含めているところもあるため、事前に確認をしておきましょう。
中間報酬
M&A仲介会社は、買い手と売り手の双方を結びつけ、M&Aの成立に向けてさまざまな業務を行います。M&Aの中間手数料は買い手や売り手が締結した際に発生する手数料で、M&A仲介会社に支払う報酬です。
リテイナーフィー(月額報酬)
M&Aリテイナーフィーは、M&Aアドバイザリー会社やM&A仲介会社に支払う月額報酬(定額顧問料)です。M&Aの成功報酬とは別に、一定期間の調査や相手先訪問などの業務に対して月額固定金額が設定されます。
M&Aは複雑な手続きを伴うため、専門知識や経験がない場合はM&Aアドバイザリー会社やM&A仲介会社に依頼することをおすすめします。
デューデリジェンス費用
M&Aデューデリジェンス費用は、M&Aの規模や複雑性、調査項目、専門家の人件費などにより異なりますが、一般的には200万円前後です。
成功報酬
成功報酬は、レーマン方式で算出されます。レーマン方式では、金額帯ごとに手数料率を設定して算出します。一概にいえませんが、成功報酬はM&Aアドバイザーのモチベーションを高めるためにも重要な役割を果たします。
M&Aにかかるそのほかの費用
前段でM&Aにかかる手数料について解説をしましたが、ここからはそのほかに必要になる費用について詳しく解説をします。
| 費用 | 内容 |
| 譲渡対価 | 買収側が売却側に支払う対価のこと |
| 弁護士への報酬 | 件の規模や複雑性、弁護士の経験や実績などによりかかる費用が異なります。 |
| 譲渡対価デューデリジェンス」にかかる費用 | デューデリジェンス」にかかる費用は譲受企業側が負担します。 |
| 税理士・会計士への報酬 | 税理士や会計士にM&Aに関する税務手続きや調査を依頼した場合に発生する費用です。 |
| M&Aに関わる社員の人件費 | M&Aに関わる社員が多い場合には費用が大きくなります。 |
| 契約書や計画書の印紙代 | M&Aの手続きを進めるためには、契約書の締結や計画書の作成が必要になります。 |
| 登記にかかる費用 | M&A登記にかかる費用は、登記内容により異なります。 |
| 税金 | M&Aにかかる税金は、M&Aの形態や規模、譲渡する資産の種類などにより変化します。 |
譲渡対価
M&A譲渡対価とは、M&Aにおいて買収側が売却側に支払う対価のことを指します。譲渡対価の算定方法は、DCF法や類似企業比較法、資産価値評価法などの方法を組み合わせて算出します。
弁護士への報酬
M&A弁護士報酬は、案件の規模や複雑性、弁護士の経験や実績などにより費用が異なります。費用面はもちろん、M&A弁護士を選ぶ際は専門性、経験や実績、報酬体系を事前に確認することが重要です。
譲渡対価デューデリジェンスにかかる費用
デューデリジェンスにかかる費用は、譲受企業側が負担します。譲り受けることによるリスクがないか、弁護士や会計士に監査を依頼した際に発生する費用です。
税理士・会計士への報酬
税理士や会計士にM&Aに関する税務手続きや、調査を依頼した場合に発生する費用です。M&A案件の内容により費用は異なるため、M&Aを検討する際は複数の税理士・会計士に相談し、見積もりをとることをおすすめします。
M&Aに関わる社員の人件費
規模が小さい場合は大きな費用はかかりませんが、M&Aに関わる社員が多い場合には必要となる費用として考えておいたほうがよいです。
契約書や計画書の印紙代
M&Aの手続きを進めるためには、契約書の締結や計画書の作成が必要です。必要な契約書は、大きく分けて2つです。1つは、買い手と売り手の企業間で締結される契約書です。2つめは、M&Aのサポートを依頼する仲介会社やアドバイザーと締結する契約書です。M&A契約書や計画書の印紙代は、契約書の内容や金額により異なります。
印紙代がかかる書類
-
- 株式譲渡契約書
- 事業譲渡契約書
- 合併契約書
- その他(資本金増加契約書、定款変更契約書など)
印紙代がかからない書類
-
- M&A計画書
- 秘密保持契約書
- 覚書
複数の契約書を締結する場合は、それぞれの契約書に印紙が必要です。印紙代の計算方法は複雑な場合があるため、税務署に確認することをおすすめします。
登記にかかる費用
M&A登記にかかる費用は、登記内容により異なります。
-
- 登録免許税
登記内容により異なりますが、一般的には数万円〜十数十万円です。
-
- 司法書士報酬
登記申請を司法書士に依頼する場合は、数万円~数十万円かかります。
-
- その他
謄本発行手数料、官報掲載費用などがかかります。
税金
M&Aにかかる税金は、M&Aの形態や規模、譲渡する資産の種類などにより変化します。今回は、代表的な株式譲渡と事業譲渡について解説します。
株式譲渡では原則、売り手にしか税金は発生しません。株式譲渡によるM&Aでは、株主個人の譲渡所得に所得税、住民税、復興特別所得税が課税されます。税率は所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%です。
譲受側(買い手)からの対価は、対象会社に入ります。譲渡側(売り手)の契約当事者は、対象会社となります。事業譲渡で生じた利益に対して法人税(実効税率約34%)などが課税されます。
M&A仲介手数料が必要なタイミング
M&A仲介手数料が必要なタイミングは、M&A仲介会社との契約内容により異なります。一般的には、以下の3つのタイミングで発生します。
-
- 契約締結時
M&A仲介会社と契約を締結した時点で、着手金として手数料が発生します。着手金は、成功報酬の一部として充当される場合と、成功に関係なく支払う必要がある場合があるため、事前に確認が必要です。
-
- 基本合意書締結時
買手と売手がM&Aの基本合意書を締結した時点で、中間報酬が発生します。
-
- M&A成立時
M&Aが成立し、契約が締結された時点で成功報酬が発生します。成功報酬は、M&Aの規模や複雑性、仲介会社の貢献度などにより異なります。
M&A仲介手数料は誰が払う?
M&A仲介手数料は、主に以下の2つのパターンで支払われます。
-
- 両手取引の場合
買い手と売り手の双方から手数料を徴収します。これは、仲介業者が両方の立場に立って公平な取引を促進するためです。手数料は双方から同額ずつ徴収するのが一般的ですが、場合によっては比率が異なることもあります。
-
- 片手取引の場合
買い手、または売り手のどちらか一方のみから手数料を徴収します。これは、仲介業者が特定の依頼者に対してのみサービスを提供する場合です。手数料は依頼者側が全額負担するのが一般的です。
M&A仲介手数料の費用目安
M&A仲介会社に依頼する場合は、手数料がかかります。成功報酬の目安は、売却価格の5%程度が一般的です。また、相談料や着手金、中間金などがかかる場合もあります。
ここでは、成功報酬のレーマン方式(取引対価に一定料率を乗じて算定する方法)について解説します。
レーマン方式の算出方法
M&A仲介会社ごとに、基準額の設定は異なります。以下が手数料率の例です。
-
- 基準額5億円以下の部分:5%
- 基準額5億円超~10億円以下の部分:4%
- 基準額10億円超~50億円以下の部分:3%
- 基準額50億円超~100億円以下の部分:2%
- 基準額100億円超の部分:1%
M&A成立時に発生する手数料で、売却金額の5%程度が相場です。
M&Aの方法ごとの会計・税務処理を紹介
M&Aには、株式譲渡や株式交換、事業譲渡、会社分割、合併などさまざまな方法があります。それぞれの方法により、会計・税務処理が異なります。
株式譲渡
株式譲渡とは、会社が所有する株式を他の会社、または個人に譲渡する取引です。株式譲渡には、譲渡側と被譲渡側それぞれに会計・税務処理が必要となります。
・会計処理
譲渡側:所有権の移転により、譲渡益または譲渡損失を計上します。
被譲渡側:取得価額を資産計上します。
・税務処理
譲渡側:譲渡益に対して、譲渡益税が課税されます。譲渡益税は、所得税または法人税の課税対象となります。
被譲渡側:取得価額は、税務上の帳簿価額となります。取得価額は、将来の譲渡益または譲渡損失の計算に影響します。
株式交換
株式交換とは、会社がその発行済株式の全部を他の会社に取得させる取引です。株式交換には、交換会社と被交換会社それぞれに会計・税務処理が必要となります。
・会計処理
交換会社:交換差益または交換差損を計上します。交換差益または交換差損は、以下の要素によって計算されます。
被交換会社:消滅します。消滅により、以下の処理が行われます。
-
- 資産の帳簿価額が交換価額に調整されます。
- 負債が交換価額に調整されます。
- 株主資本が交換価額に調整されます。
・税務処理
交換会社:交換差益、または交換差損は課税対象となります。交換差益、または交換差損は、所得税または法人税の課税対象となります。
被交換会社:消滅により、以下の税務処理が行われます。
-
- 資産の譲渡益または譲渡損失が課税対象となります。
- 負債の譲渡益または譲渡損失が課税対象となります。
- 株主資本が課税対象となります。
事業譲渡
事業譲渡とは、会社が事業の一部、または全部を他の会社または個人に譲渡する取引です。事業譲渡には、譲渡側と被譲渡側それぞれに会計・税務処理が必要となります。
・会計処理
譲渡側:譲渡資産の帳簿価額と譲渡対価の差額を譲渡益または譲渡損失として計上します。
被譲渡側:取得価額を資産計上します。
・税務処理
譲渡側:譲渡益に対して、譲渡益税が課税されます。
被譲渡側:取得価額は、税務上の帳簿価額となります。
会社分割
会社分割とは、会社が事業に関して有する権利義務の全部、または一部を分割後ほかの会社に承継させる取引です。会社分割には、分割会社と分割承継会社それぞれに会計・税務処理が必要となります。
・会計処理
分割会社:分割差益、または分割差損を計上します。
分割承継会社:分割により取得した資産を帳簿価額で計上します。
・税務処理
分割会社:分割差益、または分割差損は課税対象となります。
分割承継会社:分割により取得した資産の税務上の帳簿価額は、分割会社の帳簿価額を引き継ぎます。
合併
合併とは、2つ以上の会社が1つの会社に統合する取引です。合併には、合併会社と被合併会社それぞれに会計・税務処理が必要です。
・会計処理
合併会社:合併差益、または合併差損を計上します。
被合併会社:消滅します。
・税務処理
合併会社:合併差益、または合併差損は課税対象となります。
被合併会社:繰越欠損金などが引き継がれる場合があります。
M&A費用を下げるためのポイント
M&Aには、さまざまな費用がかかります。これらの費用をいかに抑えるかが、M&Aを成功させるための重要なポイントです。
仲介手数料を抑える
M&A仲介手数料は、M&Aの成功報酬として支払われる費用であり、M&A費用の中で大きな割合を占めます。M&A仲介手数料を下げるために、以下の方法を参考にしてみてください。
-
- 複数の仲介業者から見積もりを取る
- 仲介業者との費用の交渉
- M&Aの規模を小さくする
- 自社でできる部分は自社で行う
完全成功報酬型の仲介会社を選ぶ
成功報酬のみの仲介業者であれば、M&Aが成立しなかった場合は手数料が発生しません。M&A成功報酬のみは、初期費用を抑えられるというメリットがある一方、成立まで時間がかかるといったデメリットも存在します。これらのデメリットを理解したうえで、費用を検討しましょう。
まとめ
M&A仲介手数料は、M&A成功のためには必要ですが、売却価格がさまざまでM&A仲介会社により報酬体系が異なります。話をスムーズに進めるためにも、手数料について把握したうえで相談を進めましょう。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。