事業売却における流れを解説!必要な手順、スケジュール例を紹介
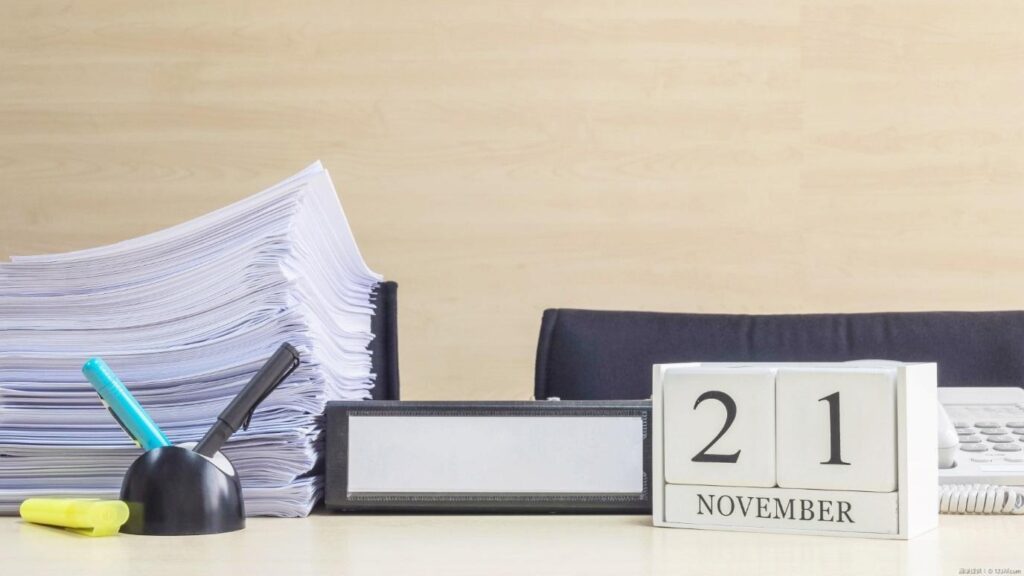
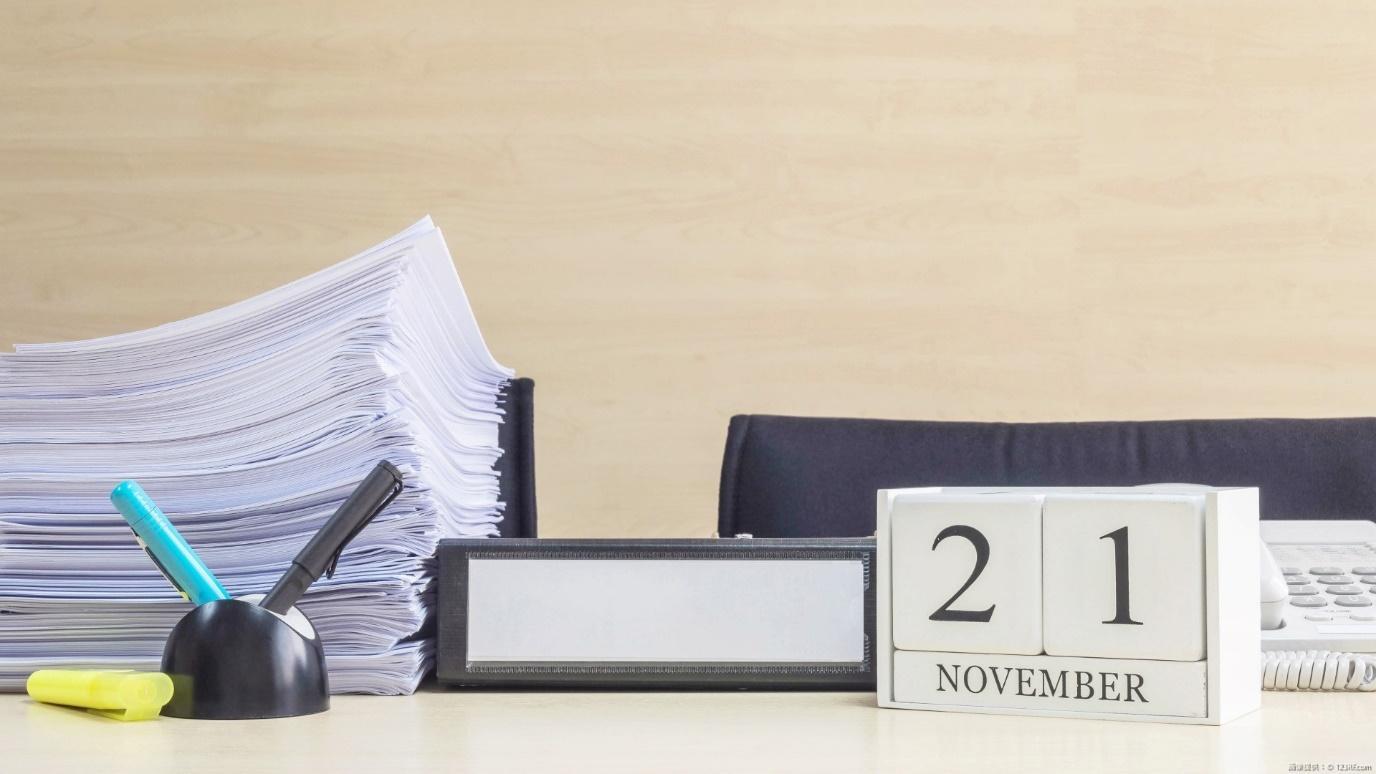
事業売却を検討しようにも、具体的にどのような流れなのかわからない、どのくらいの期間を要するのかといった疑問を持つ方も多いでしょう。本記事では事業売却をおこなう基本の流れや、スケジュールなどを詳しく解説します。事業売却を検討している方はぜひご覧ください。
目次
事業売却をおこなう基本の流れ
事業売却を実際におこなう基本の流れは以下のとおりです。
-
- 社内検討をおこなう
- 売却に向けた準備、計画を立てる
- 専門家へ相談する
- 取引候補の選出、選定をおこなう
- 秘密保持契約を締結する
- トップ面談をおこなう
- 意思表明書の作成、基本合意契約を交わす
- デューデリジェンスを実施する
- 条件交渉をおこなう
- 取締役会、株主総会での決議をする
- 事業譲渡契約書を締結する
- 統合作業をおこなう
- 社内外へ情報開示する
- 法務に関する届出をする
順に解説していきます。
社内検討をおこなう
まず、社内で事業売却についての検討を始めます。経営者だけで事業を売却する計画を練るのではなく、社内のサポートが不可欠です。
社内検討をするうえでは、以下の点を考慮しながら議論を進めます。
-
- 事業を売却することが本当に最良の経営判断か
- ほかに検討すべき選択肢は存在するか
- どの企業へ事業を売却すべきか
- 事業売却の期限はいつか
- 売却対象となる事業の範囲はどの程度か
事業売却は、全員の同意が得られた状態で進めることが重要です。そのために、取締役会や重要な関係者を招集して話し合うなどがよいでしょう。
売却に向けた準備、計画を立てる
次に、事業売却に向けた準備や計画を立てます。買収を考える側は、売り手を見つけるための準備として、直近3期分の決算書などの資料を準備します。一方、売り手は買い手となる企業の条件を選定し、絞り込む作業を行います。
専門家へ相談する
事業売却に向けた大まかな計画が決まったら、専門家へ相談しましょう。
相談先としては以下が挙げられます。
-
- M&A専門サービス
- 事業承継・引継ぎセンター
それぞれについて順に解説します。
M&A専門サービスへ依頼
M&A専門サービスの代表例として、M&A仲介会社があります。M&A仲介会社は、企業や事業の売却を支援する専門の機関です。ここには、M&Aアドバイザーと称される専門家が所属しています。
M&Aアドバイザーは、売却対象を選ぶこと、買い手への接触、取引の交渉といったプロセスに関わり、専門的な助言を提供します。事業売却に関する業界の専門知識はもちろん、法律や税務、会計などの幅広い知識を持っているため、事業売却のプロセスを円滑に進めるためにM&A仲介会社への相談がおすすめです。
事業承継、引継ぎ支援センターなどの機関を使う
事業引継ぎ支援センターは、後継者不在で悩んでいる中小企業や小規模事業者に対し、第三者への事業承継を援助する目的で、2011年度に国によって各都道府県に設立された組織です。
2021年4月からは、これまで第三者への承継支援を専門としていた「事業引継ぎ支援センター」と、親族間での事業承継をサポートしていた「事業承継ネットワーク」の機能が統合され、「事業承継・引継ぎ支援センター」として新たに整備されました。これにより、事業承継および引継ぎに関する一元的な支援を提供しています。
専門家への相談で悩んだ場合、まずは公的な機関として相談しやすい支援センターを頼るのもよいでしょう。そのほか、国による支援機関としては「よろず支援拠点」、「再生支援協議会」、「経営改善支援センター」、「中小企業基盤整備機構」などがあります。
取引候補の選出、選定をおこなう
売却側が最初に取り組むべきは、企業名を伏せた状態で自社の概要をまとめた「ノンネームシート(企業概要書)」の作成です。M&A仲介会社は、ノンネームシートを利用して情報を開示し、適切な買収候補者を探します。
一方、買収側は、M&A仲介会社から提供された複数のノンネームシートをもとに、条件に合った売却側を選び出します。双方がそれぞれの検討を重ね、絞り込んだあと、選ばれた取引先候補とともに次のステップである意向表明書の提出やデューデリジェンスに進みます。
秘密保持契約を締結する
事業売却の取引候補がお互いに決定したあとは、具体的な交渉フェーズに入る前に秘密保持契約(NDA)の締結が求められます。
秘密保持契約は、企業の機密情報を共有する過程でその保護を確保するために不可欠です。また、事業売却を計画している事実自体も一定期間、秘密に保つ必要があり、これを守るためにも秘密保持契約が重要となります。
トップ面談をおこなう
秘密保持契約を結んだあと、事業売却の交渉プロセスのなかで行われる重要なステップがトップ面談です。この面談では、譲渡側と買収側の経営トップが直接会い、対話を行います。
経営の核となるのは経営者の理念や価値観であり、これらは企業経営に大きく影響を与えます。
そのため、トップ面談では双方の経営理念やビジョンを共有し、事業売却を行ううえでの相手の適合性を確認します。この面談を通じて双方の意向が合致すれば、取引が迅速に進展することもあり、非常に重要といえます
意思表明書の作成、基本合意契約を交わす
意向表明書は、買収を望む側が事業売却への参加意志を正式に示す文書です。これは必ずしも交渉プロセスで必要なステップではなく、省略されることもありますが、買収側の誠意を表すために用いられます。
トップ面談や意向表明書の提出などの交渉プロセスを経て、事業売却の基本的な枠組みに関する合意が形成されたら、次は基本合意書の締結に移ります。
この段階では、交渉を通じて合意に達した事業売却の条件を明文化し、双方の理解を確認するための重要なステップです。
しかし、基本合意書には法的な拘束力はなく、この書類の締結が最終的な取引成立を意味するわけではありません。あくまでも、ある一定時点において合意した基本事項を確認した文章で、実際には基本合意書にサインしたあとでも、詳細な検討や追加交渉を経て取引が不成立に終わるケースも存在します。
デューデリジェンスを実施する
デューデリジェンスは、買収側によって行われる譲渡側企業の精密調査です。この過程では、法律家や会計士などの専門家が参画し、譲渡企業についてさまざまな角度から検証を行います。この段階は最終的な取引条件や事業譲渡契約の締結に直接影響を与えるため、譲渡側は積極的、かつ協力的に対応することが望まれます。
デューデリジェンスの内容はさまざまですが、必ずしもすべての調査が実施されるわけではありません。対象となる企業や事業の性質に応じて適切なデューデリジェンスが行われますが、一般的には財務や法務、会計のデューデリジェンスがほとんどの場合で実施されます。
条件交渉をおこなう
デューデリジェンスの結果により、譲渡側企業の実態や将来性などが明らかになり、それが最終的な取引条件の交渉に大きく影響します。
発覚した問題点、たとえば簿外債務や訴訟リスクがある場合、取引条件を不利にする要因となり得ます。基本合意時に設定された条件から価格の再交渉が行われる可能性があり、場合によっては交渉が決裂し取引が成立しないこともあります。
逆に、デューデリジェンスを通じて譲渡側企業の潜在的価値、たとえば優れた技術力やノウハウ、価値ある知的財産などが発見された場合、取引条件を改善する方向に作用する可能性があります。買収側はこうしたポジティブな側面を評価し、取引条件を見直すことで、より公平で双方にとって満足のいく契約につながることが期待されます。
取締役会、株主総会での決議をする
企業に取締役会が存在する場合、事業売却を実施するにあたっては取締役会による決議が必須となります。取締役会では、事業売却に関連する一連の重要事項、たとえば交渉に要する期間や取引の対象となる事業の範囲などが審議・決定されます。
取締役会での決議を経たあと、事業売却のプロセスはトップ面談・基本合意書の締結・デューデリジェンスの実施という一連の手続きを踏みます。これらのプロセスを経て、双方の合意のもとで最終的に事業売却契約が締結され、取引が成立します。
また、基本的に株主総会での特別決議も実施する必要があります。しかし、一定のケースでは、この特別決議を省略できます。
事業譲渡契約書を締結する
事業売却の条件交渉後、内容に合意した場合は事業譲渡契約を締結します。
事業譲渡契約書には次のような内容を記載します。
-
- 定義
- 事業譲渡することを合意した旨(譲渡代金の計算方法・クロージングの実施方法等)
- 事業譲渡の対象となる財産(資産・負債)
- 譲渡の代金と支払日
- 表明保証
- クロージング前の制約事項・クロージングの前提条件・クロージング後の制約事項
- 善管注意義務
- 競業避止義務
- 公表
- クロージング
- 賠償・補償
- 契約の解除
- 役員従業員に関する事項
- その他の一般条項(費用負担・秘密保持義務、協議条項、裁判管轄など)
統合作業をおこなう
統合作業は、売却された事業の従業員を買収企業の体系に統合するプロセスを指します。これには、従業員を買収企業の社内業務システムや人事評価システムに適応させることが含まれ、しっかりと時間をかけて行う必要があります。
統合作業を進める一方で、クロージングの手続きも行わなければなりません。クロージングとは、事業売却に際して生じる一連の最終手続きであり、譲渡対価の支払いや契約書の交換、権利の移転、不動産の名義変更などがこれに該当します。
社内外へ情報開示する
事業売却を実施する際は、契約の効力が生じる20日前までに株主への通告が必要となります。この通告は、事業売却に関する重要情報を株主に提供し、株主が適切な判断を下せるようにするために行われます。
ただし、株主総会で事業売却についての承認が得られた場合は、株主への個別通知を省略し、公告による通知で代えることが可能です。
また、社内の従業員や取引先に対して、周知することも重要です。とくに従業員は事業売却に対して不安や疑問を抱えていることも多く、従業員の士気を維持するうえでも情報開示は適切に行うべきでしょう。
法務に関する届出をする
事業譲渡契約が締結されたあと、当該企業は特定の条件下で必要な法的手続きを遵守し、必要な書類を提出する必要があります。
具体的には、買収側企業のグループ全体の国内売上高が200億円を超える場合、事業の全部や重要な部分、または固定資産を買収する際に一定の条件を満たすと、公正取引委員会への届出が必要となります。これは独占禁止法に基づく規制であり、市場の健全な競争を保持することを目的としています。
また、有価証券報告書の提出義務がある企業には、事業売却により財務に大きな影響がある場合、臨時報告書を提出する義務があります。これは、透明性を保ち、投資家や市場参加者が適切な情報にもとづいて判断できるようにするための措置です。
これらの届出・手続きは、事業売却が関係するすべてのステークホルダーにとって透明かつ公正に行われることを保証し、市場の信頼性を維持するために不可欠となっています。
事業売却をおこなう際の目安のスケジュール
ここまで、事業売却の基本的な流れを解説しました。以下では、事業売却をおこなう際の目安のスケジュールを解説します。
売却までは一般的に3~6か月必要
事業売却は、その複雑性と影響の大きさから、一般的に完了までには少なくとも3か月から6か月を要し、長い場合だと10か月から1年以上かかることもあります。これは、デューデリジェンスや契約書の作成、規制当局への届出、株主とのコミュニケーション、統合の準備など、プロセスが多岐にわたるためです。
事業売却を迅速に進める必要がある場合、早期からの計画立案と専門家への相談が重要です。事前に計画を立て、適切な専門家などのリソースを確保することで、スムーズかつ迅速な事業売却を実現できる可能性が高まります。
スケジュールの例
以下の表は、1月をスタートとした場合の事業売却における効力発生日までのスケジュールをまとめたものです。
| 売却側 | 買収側 | |
| 1月 | M&A仲介会社など専門家と契約 譲渡資産の精査、スケジューリング | |
| 2月 | 買収側企業とのマッチング・条件交渉 | M&A仲介会社への相談 売却側企業との条件交渉 |
| 3月 | 基本合意契約書の確認・締結 社内外への説明など | 基本合意契約書の確認・締結 デューデリジェンス(買収監査) |
| 4月 | 事業譲渡契約書の内容検討・締結 株主への通知・公告 | 事業譲渡契約書の内容検討・締結 許認可の取得準備など 株主への通知・公告 |
| 5月 | 株主総会の開催 引渡の準備 譲渡資産の引渡 | 株主総会の開催 譲渡対価の決済 |
まとめ
本記事では、事業売却における基本的な流れやスケジュールなどを解説しました。事業売却には3〜6か月ほどかかり、効力発生日から逆算したスケジュールを立てることが重要です。
また、プロセスは煩雑で専門性も高いため、スムーズに事業売却を進めたい方は早期から専門家に相談しておきましょう。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。


