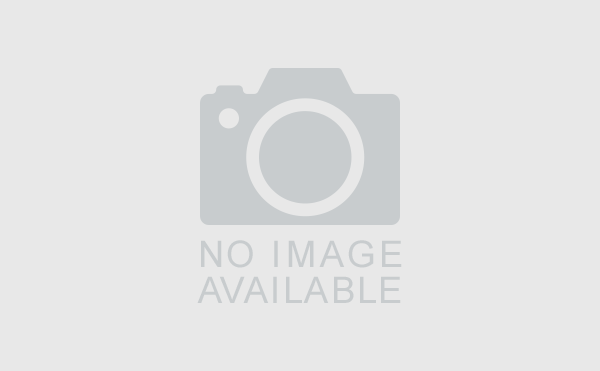M&Aにおける節税効果とは?具体的な方法や注意点を解説

経営者の方の中には「M&Aの売却/買収の際に、税金はどれほどかかるのか」「節税できるのであれば、対策したい」と思われている方もいるでしょう。
この記事では、
- M&Aにおける税金について
- M&Aで発生する税金や対策について
などを網羅的に解説します。
目次
M&Aにおける節税効果とは?
合併を伴うM&Aの場合、買収される企業に税務上の赤字、いわゆる「繰越欠損金」があり、一定の要件を満たした場合には、買手側企業の利益を相殺できるケースがあります。
M&Aの種類によっては、買収後の企業の税負担を軽減することが可能になることもあります。さらに、一定の手続きを行えば、M&Aの効果を高める設備投資に対しては10%(資本金3,000万円超の中小企業などは7%)の税額控除、もしくは全額即時償却ができるという制度も存在します。
M&Aの主な税金対策
M&A実施の際に導入可能な税金対策を3つ紹介します。
- 繰越欠損金の利用
- 役員退職金の活用
- 株式譲渡ではなく第三者割当増資
1.繰越欠損金の利用
法人株主がM&Aにより譲渡損失が生じた場合、欠損金を繰り越すことができます。具体的には、当期発生した赤字の金額を翌期以降の黒字の金額と相殺できるように繰り越すことができます。
2.役員退職金の活用
売却側が対象会社の役員を務めている場合には、退職金を検討することが必要です。退職所得は、下記の算式によって計算され、他の所得と合算することなく分離して課税されます。そのため、株式の譲渡所得税よりも税率が低くなる可能性があります。ただし、恣意性をもって退職金と譲渡対価を決めた場合には、税務当局より指摘される場合があります。
| 退職所得の金額=(収入金額(源泉徴収される前の金額)−退職所得控除額)×1/2 |
3.株式譲渡ではなく第三者割当増資
買収側が50%超の議決権を取得させるような第三者割当増資を実施すると、支配権を買収側に渡すことができます。第三者割当増資を行っても、売却側株主は現金を得ることはできず、対象会社の資金が増資によって増加するのみです。売却側株主に課税が生じず、対象会社にも損益が発生しません。下記の点で株式譲渡と異なるので注意が必要です。
-
- 売り手はイグジットしておらず、M&A後も少数株主として残留する
- 対象会社の資本金が増加するため、財務状況が改善する
- 他の少数株主の議決権が希薄化するため、株主全員に影響する
- 増資後に登記手続が必要となる
- 増資により、法人住民税の均等割が増加してしまう可能性がある
M&Aに発生する主な税金の種類
主な税金と取り扱いについては、以下の通りです。
| 取引の種類 | 売却側が個人株主 | 売却側が法人株主又は法人の一事業 |
| 株式譲渡 | 所得税・復興特別所得税・住民税 | 法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税 |
| 事業譲渡 | 法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税・消費税 |
M&Aには、個人と法人の両方に影響を及ぼすさまざまな税金が存在します。これらの税金は、取引の性質(株式譲渡、事業譲渡など)と譲渡者(個人または法人)によって異なります。以下に、
M&Aのスキーム別に発生する税金について
M&Aのスキームのうち株式譲渡と事業譲渡では発生する税金が異なります。以下では、これらのスキームについて詳しく説明します。
株式譲渡の場合
株式譲渡の場合、個人と法人によってかかる税金が変化します。
個人株主にかかる税金の計算方法
個人株主の場合、譲渡所得の計算は次のようになります。
| 譲渡所得の金額 = 譲渡価格 – 必要経費(取得費+委託手数料等) |
この譲渡所得に対して20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)の税金が課税されます。具体的な例で考えてみましょう。例えば、ある個人株主が取得費が1,000万円、委託手数料が50万円で、譲渡価格が2,000万円の株式を譲渡したとします。この場合、譲渡所得の金額は次のように計算されます。
| 譲渡所得の金額=2,000万円―(1,000万円+50万円)=950万円 |
この譲渡所得に対する税金は次のように計算されます。
| 税金=950万円×20.315%=約193万円 |
この例では、個人株主が譲渡した株式の譲渡所得に対して約193万円の税金が課されます。また、株式の譲渡所得については、他の所得と合算することなく、分離課税により課税されます。
法人株主にかかる税金の計算方法
法人株主の場合、譲渡益の計算は次のようになります。
| 譲渡益の金額 = 譲渡価格 – 必要経費(取得費+委託手数料等) |
譲渡益に対して約30%(法人税等)の税金が課税されます。
具体的な例を考えてみましょう。例えば、ある法人株主が取得費が1,000万円、委託手数料が50万円で、譲渡価格が2,000万円の株式を譲渡したとします。この場合、譲渡益の金額は次のように計算できます。
| 譲渡益の金額=2,000万円―(1,000万円+50万円)=950万円 |
この譲渡益に対する税金は次のように計算されます。
| 税金=950万円×30%=285万円 |
この例では、法人株主が譲渡した株式に対して285万円の税金が課されます。ただし、法人の場合には、他の事業で生じた、収益や経費を合算して所得を計算するため、株式の譲渡に生じた所得のみで課税されるわけではありません。
事業譲渡の場合
事業譲渡の場合、主に下記の3つが課税されます。
- 法人税等
- 消費税
- 不動産が譲渡対価に含まれる場合
法人税等
法人税等の計算は次のようになります。
| 譲渡益の金額 = 譲渡価格 – (譲渡資産の帳簿価額ー譲渡負債の帳簿価額) |
譲渡益に対して約30%の税金が課税されます。
消費税
消費税は、課税資産(有形固定資産や営業権など)に対して現在10%の税率が適用されます。ただし、土地は非課税です。
不動産が譲渡対象に含まれる場合
譲渡対象に不動産が含まれる場合は、買収側に「登録免許税」や「不動産取得税」が発生します。これらの税金は、不動産の価格で異なります。
合併や会社分割などの組織再編時の税金
合併や会社分割などの組織再編型のM&Aの際、税務上一定の要件を満たした組織再編の場合、「税制適格による組織再編」となり。一方、要件を満たさない場合には「税制非適格による組織再編」となります。
税制適格要件を満たすM&Aは税金が発生しない
税制適格要件を満たすM&Aは以下の6つです。
- 適格新設合併
- 適格吸収合併
- 適格吸収分割
- 適格新設分割
- 適格株式交換
- 適格株式移転
下記の適格要件を満たすと、移転に伴う譲渡所得やみなし配当などが発生せず、課税が生じません。
税制適格の要件
税制適格要件は以下の6つに分類されます。
| 対価要件 | 対価が株式のみであること |
| 事業関連要件 | 事業が相互に関連していること |
| 事業規模または特定役員要件 | 売上高の差がおおむね5倍を超えないこと又は合併の場合その前後でそれぞれ常務役員以上に就任 |
| 従業者引継要件 | 従業員80%以上が引き継がれること |
| 移転事業継続要件 | 事業が継続されること |
| 株式継続保有要件 | 株式が継続保有されること |
完全支配関係(持株比率100%)で合併する場合
完全支配関係がある法人間の合併の場合、対価要件及び一の者による継続保有要件を満たせば適格合併です。
支配関係(持株比率50%超100%未満)で合併する場合
支配関係(持株比率50%超100%未満)で合併する場合、対価要件及び一の者による継続保有要件、従業者引継要件、移転事業引継要件の要件を満たせば、税制適格要件を満たします。
企業グループ内でなく合併により共同事業を営む場合
企業グループ内でなく合併により共同事業を営む場合、全てを満たせば税制適格要件を満たします。
M&Aで注意すべき税務上のリスク
M&Aには税務上のリスクが伴います。売却側企業の過去の税務処理が誤っており、買収後の調査で発覚すると大きなリスクを負う可能性があります。リスクを回避するためにも、表明保証やDD(デューデリジェンス)などを行うなど、弁護士、会計士、税理士など専門家との相談は必須です。また、税制適格要件を満たさないと余計な税金が貸される可能性があるため、適格要件を満たすための適切な手続きと対策が必要です。
M&Aの税金に関するQ&A
M&Aは、企業の成長戦略の一部としてますます重要になっています。しかし、M&Aには複雑な税務問題が伴います。以下に、役員退職金と税務否認に関する一般的な質問とその回答を紹介します。
Q:役員退職金で税金対策したいが、退職金はどのくらいが相場か?
役員退職金の相場は個々の状況によりますが、長年の功績に対する報酬として支払われ、その金額は退職者の在職年数や業績などによります。税務上認められる役員報酬を算定する方法としては、功績倍率法が最もよく使用される方法です。
・功績倍率法
役員退職金の適正額 = 最終報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率
功績倍率については、過去の判例で示された「社長3.0、専務2.4、常務2.2、平取締役1.8、監査役1.6」が採用される場合が多いです。
Q:税務否認が心配、安心する方法はないか?
税務否認の心配を軽減するための1つの方法は、早い段階から税理士など専門家と協力して対策を立てることです。税務調査で否認されるケースは、法令要件を満たしていない場合や、損金算入時期の誤りなどがあります。
まとめ
本記事では、M&Aに関連する税務問題、特に役員退職金と税務否認について解説しました。税務上認められる役員退職金は、過去の判例に従った形での功績倍率法で算定されることが多いです。税務否認の心配を軽減するためには、早い段階から税理士など専門家と協力して対策を立てることが重要です。また、税制適格要件を満たすことで、組織再編型のM&Aの際に発生する税金を抑えることができる場合があります。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。