廃業を検討するときの相談先は?具体的な相談の進め方について解説
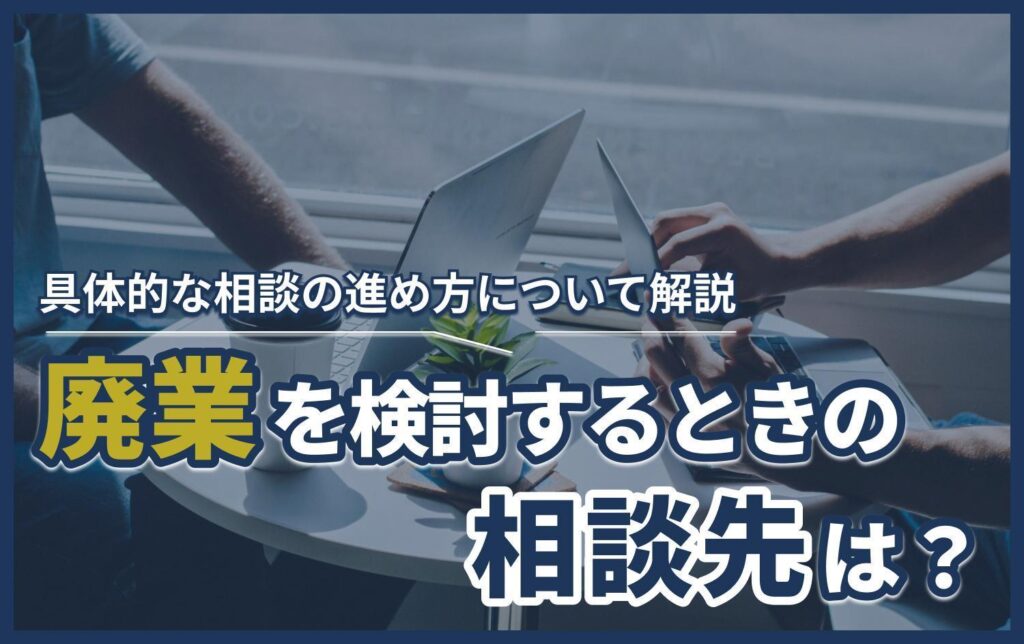
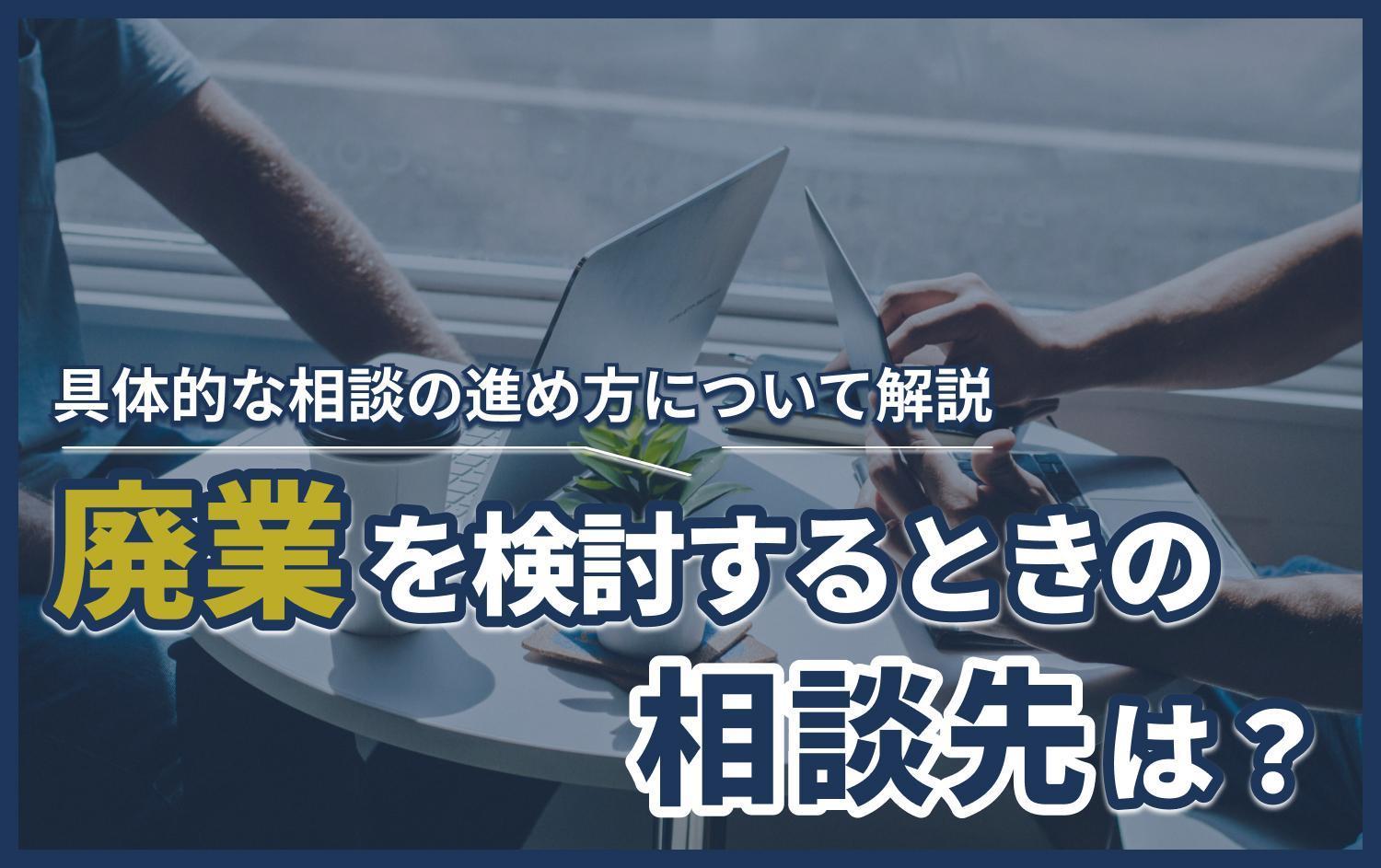
経営環境の変化や後継者不在など、様々な理由から廃業を検討されている中小企業の経営者の方々は、多くの不安や疑問を抱えていることでしょう。
この記事では、廃業を考える際の相談先や、廃業プロセスの進め方について解説します。
専門家への相談・依頼、申し立て前の準備
廃業を決断した後、いよいよ具体的な手続きに入っていきます。ここからは、専門家への相談・依頼と、申し立て前の準備について解説しましょう。
弁護士への相談と依頼
廃業プロセスにおいて、法的な手続きは非常に重要な位置を占めます。解散決議、清算人の選任、債権者への通知など、株式会社の解散・清算には複雑な法的規制が存在するのです。こうした手続きを適切に進めるために、まずは弁護士への相談を検討してみてはいかがでしょうか。
弁護士は、法律の専門家として、廃業に必要な法的手続きを網羅的に把握しています。事案に応じて、最適な解散・清算の方法を提案してくれるでしょう。
例えば、債務超過に陥っている場合、弁護士は任意整理や特別清算など、債務整理の選択肢を示してくれます。法的リスクを最小化しつつ、円滑に廃業を進めるためには、弁護士の知見は欠かせません。
税理士への相談と依頼
廃業に伴う税務処理も、専門家の助言が重要となります。法人の清算所得に対する法人税の申告、消費税の精算、個人事業の廃業届出など、税務署への手続きは多岐にわたります。確定申告や納税で失敗すれば、無用なトラブルに巻き込まれかねません。
そこで頼りになるのが、税理士です。税理士は、税法に精通した専門家として、廃業時の税務リスクを未然に防ぐためのサポートを行ってくれます。事業用資産の譲渡や評価損の計上など、節税につながる提案も期待できるでしょう。円滑な廃業のためには、税理士との連携が欠かせません。
行政書士への相談と依頼
許認可関連の手続きは、行政書士に相談するのが得策です。飲食店営業や風俗営業など、許可を受けている事業者は、廃業時に保健所や警察署への届出が必要となります。こうした手続きを代行してくれるのが、行政書士です。
行政書士は、官公庁に提出する書類の作成や申請手続きのプロフェッショナルです。複雑な許認可の手続きを、正確かつ迅速に進めてくれるでしょう。行政書士に依頼することで、書類不備によるトラブルを避け、スムーズに廃業を進められます。
認定支援機関への相談
経営改善計画の策定を検討している方は、認定支援機関への相談もおすすめです。認定支援機関とは、中小企業の経営改善を支援する専門機関のことを指します。税理士法人や金融機関、商工会議所など、全国に多数存在しています。
認定支援機関では、経営改善計画の策定を無料でサポートしてくれます。財務内容の分析、資金繰りの見直し、事業計画の作成など、再建に向けた様々な支援が受けられるのです。廃業を決断する前に、認定支援機関の門を叩いてみるのも一案かもしれません。
申し立て前の準備
法的整理を申し立てる場合、事前の準備が重要となります。まず、債権者リストを作成し、債務の全体像を把握します。債権者の住所や連絡先、債務額などを正確に記録しておきましょう。
次に、自社の財産状況を明らかにします。現預金や売掛金、不動産など、資産の内容と価値を洗い出すのです。債務超過に陥っているのか、債務の弁済原資が確保できるのか。財産状況を正確に把握することが、適切な債務整理方法の選択につながります。
また、事業の経緯や財務状況を説明する資料も準備しておくと良いでしょう。会社の沿革や直近の決算書、事業計画書など、債権者への説明資料として活用できます。弁護士や税理士と相談しながら、必要な資料を揃えていきましょう。
申し立て前の入念な準備は、円滑な法的整理の実現に直結します。専門家と連携し、適切な資料を整えることが重要です。
以上のように、廃業プロセスにおいては、弁護士や税理士、行政書士など、様々な専門家の助言が重要となります。事案に応じて最適な専門家を選び、緊密に連携を取ることが求められるのです。加えて、申し立て前の入念な準備も欠かせません。こうした地道な取り組みの積み重ねが、円滑な廃業の実現につながるのだと言えるでしょう。
公的支援機関を利用する

経営者は、廃業に関する公的支援機関からのアドバイスも受けられます。
よろず支援拠点
中小企業庁が設置した「よろず支援拠点」では、廃業を含む様々な経営課題の相談に無料で応じています。各都道府県に設置されたよろず支援拠点には、弁護士や税理士、中小企業診断士など、様々な分野の専門家が在籍しています。経営者の抱える悩みに合わせて、最適な専門家が相談に乗ってくれます。廃業の手続きや、その後の再スタートに関するアドバイスも受けられるので、気軽に足を運んでみてください。
商工会議所や商工会
商工会議所や商工会の経営指導員も、地域密着型の支援を提供しています。経営指導員は、日頃から中小企業の経営支援に携わっているため、廃業を検討する経営者の心情を理解してくれます。廃業までの進め方や、必要な手続きについて丁寧に説明してくれるでしょう。また、商工会議所等が開催する事業承継セミナーや個別相談会には、専門家が出席していることもあります。廃業を考えるきっかけとなった課題を解決する糸口が見つかるかもしれません。
これらの機関では、補助金の情報提供や事業再構築のサポートも受けられます。例えば、事業転換や新分野進出を検討している場合、「中小企業等経営強化法」に基づく支援策の活用が可能です。計画策定から融資、税制優遇まで、ワンストップでサポートを受けられます。経営者の新たなチャレンジを、公的機関が力強くバックアップしてくれるでしょう。
金融機関との対話
廃業を視野に入れている経営者にとって、取引金融機関との対話は欠かせません。日頃から経営状況を知る金融機関は、経営者の相談相手として重要な役割を果たします。
金融機関には、中小企業の経営支援を専門とする部署があります。経営改善提案書の作成サポートや、外部専門家の紹介など、様々な支援メニューを用意しています。廃業を考える前に、金融機関と一緒に経営改善の可能性を探ってみるのも一案です。再建の道筋が見いだせれば、廃業を回避できるかもしれません。
一方で、事業継続が困難と判断せざるを得ない場合、金融機関との協議を通じて、債務整理に向けたスケジュールを立てることが重要です。
返済条件の見直しや、不動産等の担保処分による債務圧縮など、金融機関と一体となって解決策を模索しましょう。経営者の誠実な対応は、金融機関の理解と協力を得るためにも欠かせません。
廃業を決める前に検討したい事業承継
「廃業するしかない」そう思い詰めている経営者の方も多いのではないでしょうか。しかし、本当にそれが最善の選択でしょうか。廃業を決断する前に、もう一度事業承継の選択肢について考えてみませんか。
①親族への承継
まず考えられるのは、親族への承継です。子孫や親戚など、身内の中から後継者を見つけ、事業を引き継いでいく方法です。親族承継のメリットは、経営理念や価値観を共有しやすいことでしょう。「この会社をこの先どうしていきたいのか」という想いを、家族の中で語り合うことができます。
ただし、親族承継を円滑に進めるには、後継者教育が欠かせません。単に「跡取り」を指名するだけでは、事業の継続は難しいのです。
後継者候補には、経営者としての資質を磨いてもらう必要があります。計画的に経営の知識やスキルを身につける機会を設けることが大切です。
親族承継は、簡単には実現できません。長い時間をかけて、後継者を育成していく必要があるのです。
②従業員への承継
2つ目の選択肢は、従業員への承継です。社内の有望な人材を後継者として育成し、経営を引き継いでいく方法です。従業員承継のメリットは、事業に精通した人材を後継者に据えられることでしょう。社内の事情に詳しい人物が経営を担うことで、スムーズな事業運営が期待できます。
従業員承継を成功させるには、後継者育成の仕組みづくりが重要です。経営に必要な知識やスキルを身につけられるよう、社内教育のプログラムを整備することが求められます。加えて、後継者候補には経営の実務を経験してもらうことも大切です。徐々に経営の一端を担ってもらい、重責を果たす覚悟を持ってもらうことが必要不可欠です。
「うちには後継者になれる人材がいない」と感じている経営者の方もいらっしゃるかもしれません。しかし、意外なところに”原石”が眠っているかもしれません。
M&Aによる廃業回避

廃業を考える前に、M&Aによる事業承継の可能性を検討してみることをおすすめします。M&Aとは、合併と買収を指す言葉で、企業の経営権の移転を伴う取引を意味します。事業の全部または一部を、他社に売却・譲渡することで、廃業を回避し、事業を存続させることが可能となります。
M&Aのメリットは、以下の点が挙げられます。
雇用の維持
M&Aにより事業が譲渡されれば、従業員の雇用を維持することができます。新しい経営者のもとで、従業員は引き続き働くことが可能となるのです。
取引先との関係継続
事業が譲渡されれば、取引先との関係も引き継がれます。長年築いてきた信頼関係を、新しい経営者のもとで継続していくことができるでしょう。
株主価値の最大
M&Aにより株式を売却すれば、株主は投資に見合うリターンを得ることができます。自社の企業価値を適正に評価し、できるだけ高値で株式を売却することが、株主価値の最大化につながります。
経営資源の有効活用
M&Aにより、自社の持つ技術やノウハウ、ブランド等の経営資源を、他社に引き継ぐことができます。これらの資源を有効に活用してもらうことで、事業の発展を図ることが可能となります。
M&Aを実現するためには、まず自社の企業価値を適正に評価することが重要です。自社の強みや独自性、将来の成長可能性等を客観的に分析し、適正な売却価格を算定する必要があります。この過程では、M&Aに精通した専門家の助言を仰ぐことをおすすめします。
次に、M&Aの相手先を探索します。同業他社や、自社の事業に興味を示す企業に打診してみるのも一案です。M&Aを希望する企業のマッチングを行う仲介会社を活用するのも効果的でしょう。
M&Aの交渉においては、売却価格だけでなく、従業員の処遇や取引関係の継続など、様々な条件について議論することになります。双方にとってメリットのある条件を引き出すためにも、専門家のサポートを受けながら、粘り強く交渉を進めていくことが重要です。
M&Aは、廃業を回避し、事業を存続させるための有力な選択肢と言えます。
経営資源を有効に活用し、従業員の雇用を守りながら、株主価値を高めることができるのです。M&Aを実現するためには、周到な準備と専門家の助言が欠かせません。
廃業を視野に入れている経営者の方々は、ぜひM&Aの可能性についても検討してみてはいかがでしょうか。
円滑な廃業のために
廃業を決断した場合、円滑に手続きを進めるためのポイントがいくつかあります。
まず、廃業の意思決定には慎重さが求められます。周囲の意見に惑わされることなく、自らの判断で決断を下すことが重要です。従業員をはじめとするステークホルダーへの影響を考慮しつつ、腹をくくって決断を行いましょう。
次に、廃業スケジュールを綿密に立てることが欠かせません。法的手続きや税務処理には一定の時間を要するため、余裕を持ったスケジュール設定が必要です。専門家の助言を受けながら、現実的な期間設定を心がけましょう。
また、廃業を決めたら、速やかに従業員への説明を行います。解雇予告や解雇手当の支払いなど、労働基準法に則った手続きを踏まえる必要があります。生活の基盤を失う従業員の不安に寄り添い、再就職支援など、できる限りのサポートを行いましょう。
取引先や顧客への説明も重要です。事業の譲渡先が決まっている場合は、引き継ぎ先を紹介し、取引の継続を求めます。譲渡先がない場合は、早めに廃業の旨を伝え、代替先を探すための時間的猶予を与えましょう。長年の付き合いに感謝の意を示すことを忘れてはいけません。
このように、廃業の際には、ステークホルダーへの配慮が欠かせません。従業員や取引先の立場に立って、誠実に対応することが求められます。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。


