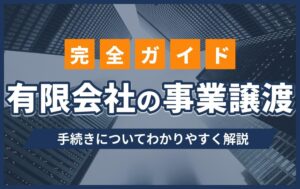会社分割時に社員はどうなる?経営者に必要な労務知識を徹底解説
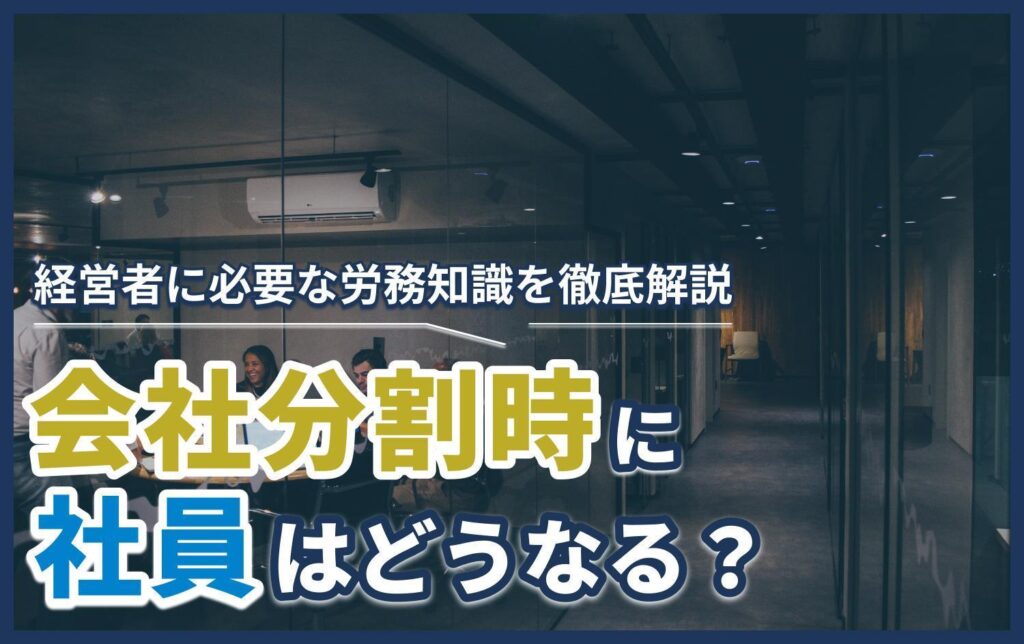
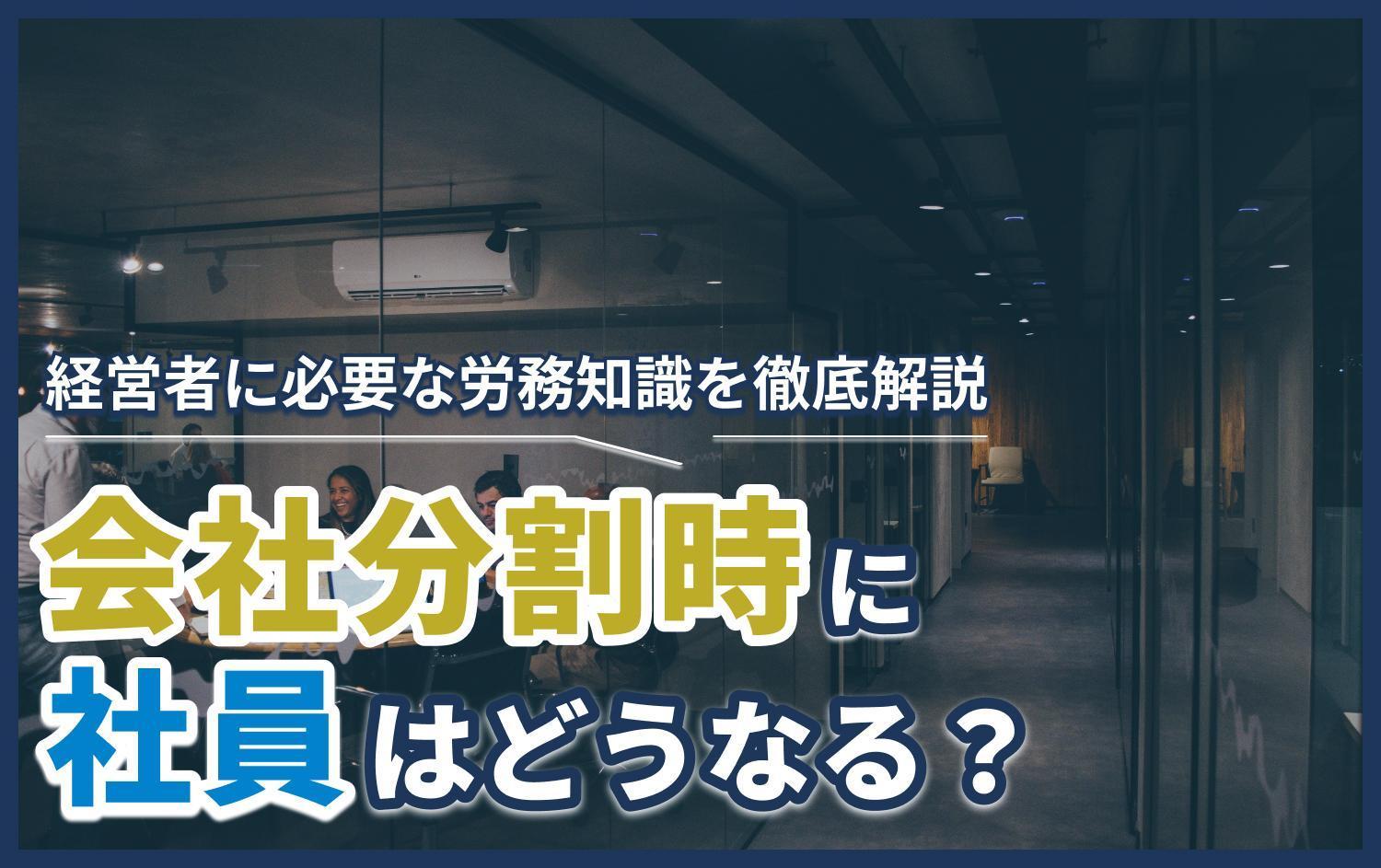
M&Aスキームの中でも、会社分割を活用した事業承継は1つの選択肢となり得ます。
その際、従業員へ与える影響をさまざまな角度から考慮することが不可欠です。
本記事では、会社分割で社員にどんな影響があるのかを網羅的に解説します。
そもそも会社分割とは?
会社分割とは、事業の一部または全部を既存の会社または新たな会社に移転させる手法です。
分社化とも呼ばれ、事業の効率化や専門性の強化、リスク分散などを目的として行われます。
会社分割には、新設分割と吸収分割の2つの方式があります。
新設分割では、分割会社の事業を新たに設立する会社に承継させます。一方、吸収分割では、既存の会社に事業を承継させます。
会社分割のメリットとしては、事業の選択と集中による経営資源の最適化、意思決定の迅速化、株式上場の準備などが挙げられます。
一方、デメリットとしては、分割に伴う費用の発生、従業員の不安や士気の低下、取引先との関係の変化などがあります。
会社分割で労働契約はどうなる?
会社分割の過程では、関連する労働者の労働契約も承継されます。これは、労働契約承継法に基づく措置で、従業員の雇用を保護するための重要な規定です。
労働契約承継法第3条では、「前条第一項第一号に掲げる労働者が分割会社との間で締結している労働契約であって、分割契約等に承継会社等が承継する旨の定めがあるものは、当該分割契約等に係る分割の効力が生じた日に、当該承継会社等に承継されるものとする」と定められています。
労働契約の承継は、従業員にとって重大な関心事です。雇用の継続性や労働条件の維持は、言うまでもなく、従業員の生活や将来設計に直結する問題となります。
労働契約承継法の概要
労働契約承継法は、会社分割における労働者の保護を目的とした法律です。同法の主な内容は以下の通りです。
-
- 会社分割に際し、特定の労働者において労働契約の承継の効果が生じること
- 承継される事業に主として従事する労働者(主従事労働者)の労働契約は、原則として承継されること(承継法3条、4条)
- 主従事労働者でない者の労働契約は、分割契約等に定めがある場合に承継され、労働者が異議を申し出た場合は承継されないこと(承継法5条)
労働契約承継法は、会社分割によって労働者が不利益を被ることのないよう、手厚い保護措置を定めています。
労働契約の承継プロセス
会社分割における労働契約の承継プロセスには、いくつかの重要なステップがあります。

まず、分割会社は、労働者に対して、書面による通知を行う必要があります。通知書には、会社分割の日程や、承継される事業の内容、労働契約の承継先となる会社の名称と住所などを明記します。
通知書に記載すべき事項としては、以下のようなものが挙げられます。
-
- 会社分割の方式(新設分割または吸収分割)
- 分割の時期(効力発生日)
- 承継される事業の内容
- 承継会社等の名称および住所
- 労働契約の承継日
- 労働条件の変更の有無
- 異議申し立ての方法および期限
通知書の作成に当たっては、専門家の助言を得ながら、漏れのないように確認することが重要です。
また、労働協約がある場合は、労働組合に対しても通知を行います。労働組合との事前協議では、会社分割の目的や、労働者への影響などについて、丁寧に説明することが求められます。協議事項としては、労働契約の承継や、労働条件の変更、配置転換の可能性などが挙げられます。
分割会社は、個々の労働者との個別協議も実施します。協議の場では、労働者から質問や不安の声が上がることもあるでしょう。
労働者の理解と協力を得る努力義務(7条措置)
労働契約承継法第7条では、分割会社に対し、厚生労働大臣の定めるところにより、その雇用する労働者の理解と協力を得るよう努めるものとすると規定しています。これを一般に「7条措置」と呼びます。
7条措置の具体的な内容としては、以下のような点が挙げられます。
-
- 会社分割の目的や内容について、労働者に丁寧に説明すること
- 労働契約の承継に関する事項を、労働者に明示すること
- 労働者の不安や疑問に真摯に耳を傾け、誠実に対応すること
- 労働組合がある場合は、労働組合との協議を行うことが望ましいこと
7条措置は、会社分割に際して、労働者の理解と協力を得るための重要なプロセスです。経営者には、労働者とのコミュニケーションを密にし、不安の払拭に努めることが求められます。
従業員からの異議申し立てと対応
会社分割に際して、次のような場合には、労働者は異議の申出を行うことができます。
-
- 会社が主従事労働者を分割会社に残留させる場合(分割契約などに承継する旨の定めが無い場合)
- 会社が非主従事労働者を承継会社などに承継させる場合(分割契約などに承継させる旨の定めがある場合)
異議申出の効果として、労働条件を維持したまま労働契約が承継され、または分割会社に残留することになります。異議申出は、労働者がこれまで主として従事してきた業務から切り離されるといった不利益から、労働者を保護するために定められた制度です。
異議申出の方法は、分割会社が指定した異議申出先に、書面で通知します。異議申出書には、次の事項を記載する必要があります。
-
- 主従事労働者の場合:氏名、労働契約が承継されないことについて反対である旨
- 承継非主従事労働者の場合:氏名、労働契約が承継されることについて反対である旨
異議申出期限は、通知期限日の翌日から起算して、株主総会の承認日の前日(株主総会が不要な場合は、分割の効力発生日の前日)までの間で、分割会社が定めます。
ただし、異議申出期限と通知日の間は、少なくとも2週間(14日)以上の期間を設ける必要があります。これは、労働者が異議申出を行うかどうかを検討するための合理的な期間を確保するためです。
異議申出があった場合、分割会社は労働者との協議を尽くし、合意の形成に努めることが求められます。協議が調わない場合は、最終的に労働委員会のあっせんや調停の手続きを利用することもできます。
従業員保護のための制度と異議申し立て
会社分割における労働契約の承継は、労働契約承継法により、従業員の権利を保護するための制度が整備されています。分割会社は、会社分割が労働条件の悪化を直接の理由として行われることのないよう、配慮する必要があります。
会社分割における労働契約の承継は、労働契約承継法により、従業員の権利を保護するための制度が整備されています。分割会社は、会社分割が労働条件の悪化を直接の理由として行われることのないよう、配慮する必要があります。
労働契約承継法第3条では、「前条第一項第一号に掲げる労働者が分割会社との間で締結している労働契約であって、分割契約等に承継会社等が承継する旨の定めがあるものは、当該分割契約等に係る分割の効力が生じた日に、当該承継会社等に承継されるものとする」と規定されています。つまり、会社分割を理由とした、不当な労働条件の引き下げは認められないのです。
また、同法第4条では、承継会社等に承継されない労働者の異議申立権について規定されており、第5条では、承継会社等に承継される労働者の異議申立権について規定されています。これらの規定により、労働者の意思が尊重され、不当な労働契約の承継が防止されます。
さらに、同法第7条では、「分割会社は、当該分割に当たり、厚生労働大臣の定めるところにより、その雇用する労働者の理解と協力を得るよう努めるものとする」とされており、労働者の理解と協力を得ることが求められています。
通常、通知書の到達から一定期間内に、書面で異議を申し立てる必要があります。
異議申し立てがあった場合、分割会社は、誠意を持って対応し、労働者との合意形成を図ることが求められます。合意に至らない場合は、労働者は、労働委員会に対して、あっせんや調停を申請することもできます。労働委員会は、中立的な立場から、労使双方の主張を聴取し、合意形成を支援します。
会社分割に伴う労働条件の変更と対応策
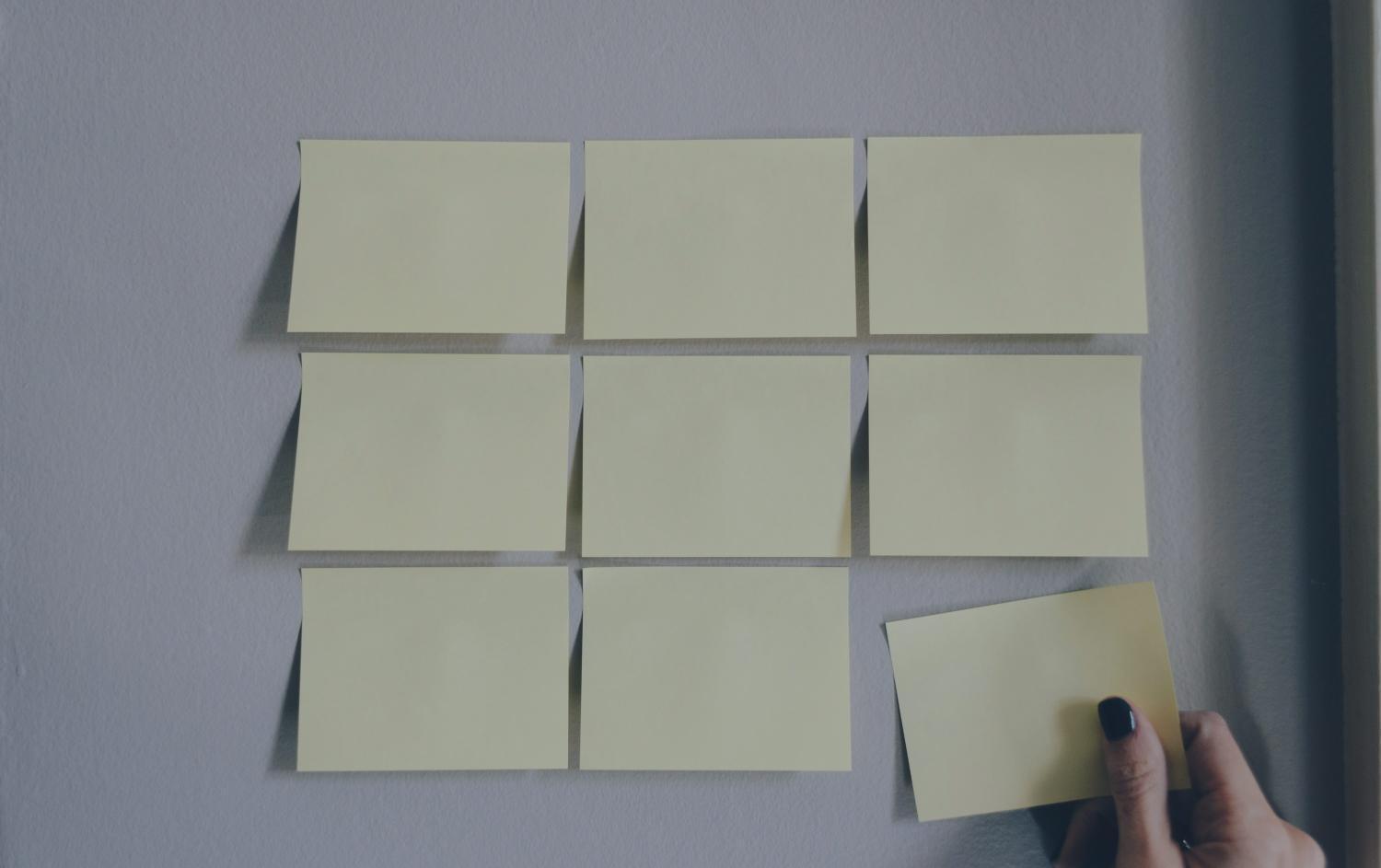
会社分割に際しては、労働条件の変更が生じる可能性があります。労働条件の変更の範囲は、会社分割の内容や、承継会社の状況によって異なりますが、主に以下のような項目が対象となります。
-
- 賃金体系(基本給、諸手当、賞与など)
- 勤務地(通勤手当の変更を含む)
- 勤務時間(始業・終業時刻、休憩時間など)
- 福利厚生(健康保険、年金、住宅手当など)
労働条件の変更については、従業員の個別同意が必要となります。分割会社は、変更内容を明確に提示し、従業員の理解を得るための丁寧な説明が求められます。
労働条件の変更に関する交渉においては、以下のようなポイントが重要です。
-
- 変更の必要性や合理性を丁寧に説明すること
- 従業員の不利益を最小限に抑える努力をすること
- 個々の従業員の事情に耳を傾け、柔軟な対応を心がけること
- 労使双方が歩み寄る姿勢を示し、合意形成を図ること
例えば、勤務地の変更が不可欠な場合には、通勤手当の増額やフレックスタイム制の導入など、従業員の不安を和らげるための施策を提示することが有効でしょう。
また、育児中の従業員に対しては、時差出勤や在宅勤務の選択肢を提供するなど、ワークライフバランスに配慮した対応を行うことが望まれます。
会社分割における従業員の退職金の取り扱い
退職金制度・勤続年数の承継
会社分割において、退職金制度と勤続年数の承継は、従業員にとって大きな関心事です。分割会社から新設会社や承継会社に転籍する従業員は、これまでの勤続年数が引き継がれるのか、退職金はどのように計算されるのか、不安を抱えているでしょう。
退職金制度と勤続年数の承継については、会社分割計画や労働協約などで取り決めておくことが重要です。一般的には、従業員の同意を得た上で、分割会社の退職金制度と勤続年数を承継会社に引き継ぐことになります。
例えば、分割会社で20年勤務した従業員が承継会社に転籍する場合、分割会社での勤続年数が承継され、承継会社での勤務年数と合算されることになります。
退職金の計算も、この合算された勤続年数に基づいて行われるのです。
ただし、退職金制度の内容が分割会社と承継会社で異なる場合は、調整が必要となります。例えば、分割会社の退職金が最終給与の20倍、承継会社の退職金が最終給与の30倍だった場合、どちらの制度を適用するのか、労使間で協議し、合意しておく必要があります。
従業員の不安を解消し、円滑な会社分割を実現するには、退職金制度と勤続年数の承継について、早い段階から従業員に説明し、理解を得ることが大切です。丁寧なコミュニケーションにより、従業員の信頼を得ることが、会社分割の成功につながるのです。
従業員の退職金制度が併存する場合の労務処理
会社分割において、分割会社と承継会社の退職金制度が併存する場合、労務処理にも注意が必要です。
異なる退職金制度を適用する従業員が同じ職場で働くことになるため、不公平感や不満を招く恐れがあるのです。
このような場合、まずは、分割会社と承継会社の退職金制度の違いを明確にすることが重要です。それぞれの制度の適用対象者、計算方法、支給時期などを整理し、従業員に分かりやすく説明する必要があります。
また、将来的には、退職金制度の統一も検討すべきでしょう。異なる制度の併存は、長期的には労務管理の複雑化や従業員の不公平感につながりかねません。
会社分割後の一定期間は併存を認めつつ、将来的な統一に向けた計画を示すことが望ましいと言えます。
退職金制度の統一に際しては、労使間の丁寧な協議が欠かせません。
従業員の理解と協力を得ながら、新たな制度を設計していく必要があります。例えば、経過措置を設けて、現行の制度から徐々に新制度に移行するなど、従業員の不安を和らげる工夫も大切です。
退職金制度が併存する場合の労務処理は、ケースバイケースで判断することが求められます。
会社分割における従業員とのコミュニケーションのコツ
会社分割を成功に導くためには、従業員とのコミュニケーションが非常に重要です。
会社分割の検討段階から実行段階まで、継続的かつ丁寧なコミュニケーションを通じて、従業員の理解と協力を得ることが不可欠です。
会社分割の検討段階では、経営者自らが従業員に対して、会社分割の目的や背景について説明することが求められます。
分割の理由や、期待される効果、従業員への影響などについて、率直に伝えることが重要です。
会社分割の実行段階に入ると、より個別具体的なコミュニケーションが必要となります。分割対象事業に従事する従業員に対しては、個別面談を行い、労働契約の承継や、労働条件の変更について、丁寧に説明することが求められます。
面談の際には、従業員の不安や懸念に真摯に耳を傾け、共感の姿勢を示すことが重要です。従業員の立場に立って、懸念事項について一つ一つ丁寧に説明し、安心感を与えるよう努めます。
また、会社分割後の組織体制やキャリアパスについても、具体的に提示することが求められます。
会社分割における従業員とのコミュニケーションは、一方的な情報伝達ではなく、双方向の対話が重要です。経営者は、従業員の声に耳を傾け、フィードバックを得ることで、より効果的なコミュニケーションを図ることができます。
まとめ
会社分割は、従業員にとって不安を感じる出来事かもしれません。しかし、丁寧なコミュニケーションと適切な対応によって、従業員の理解と協力を得ることができます。
経営者には、従業員の雇用を守りながら、新たな成長の機会を提供していくことが求められます。会社分割を、従業員とともに成長するための変化のきっかけととらえ、前向きに取り組んでいくことが望まれます。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。