廃業時の在庫処分のベストな考え方とは?具体的なステップについて解説
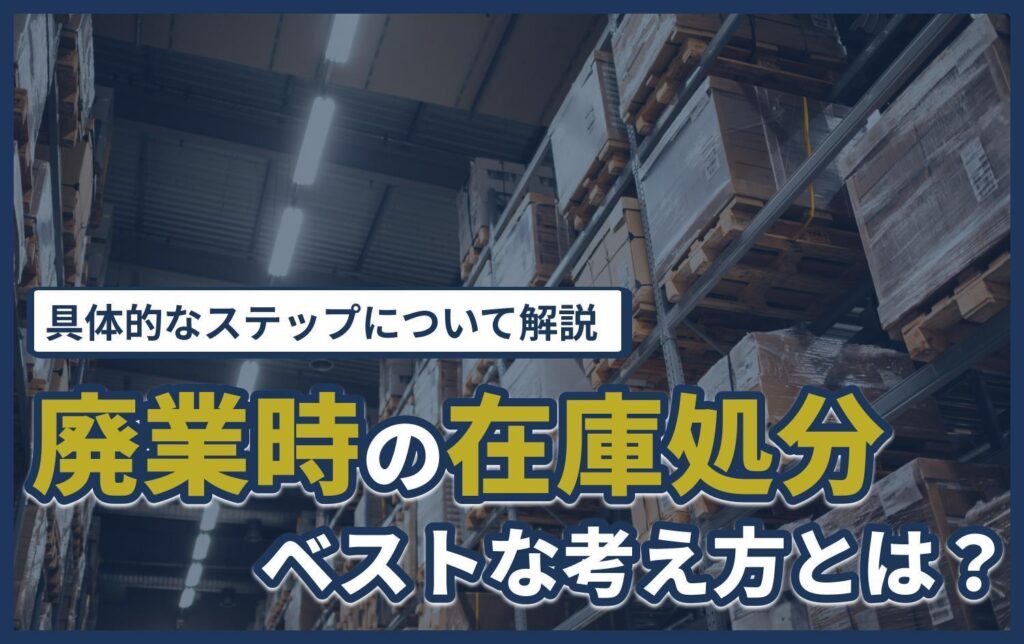
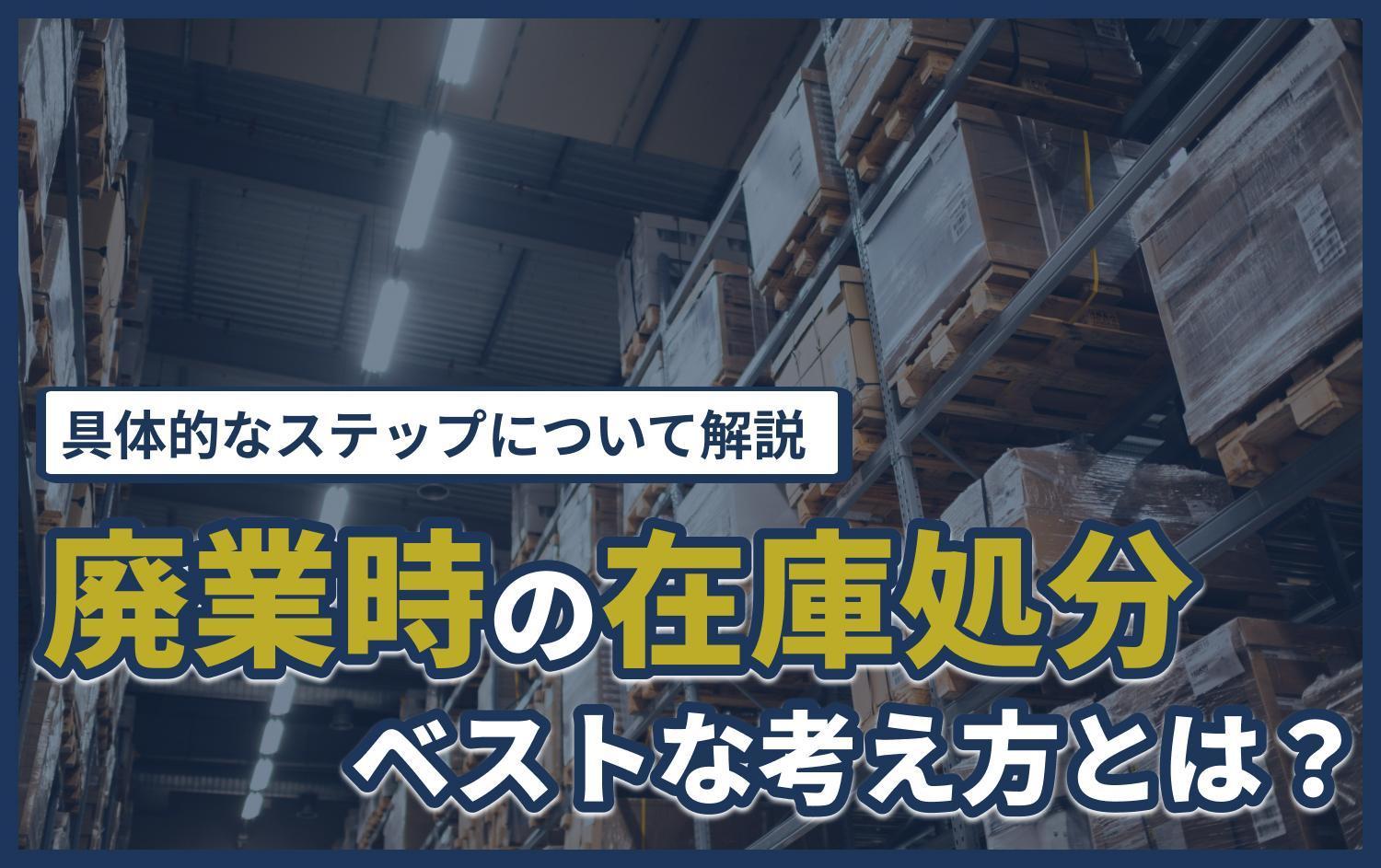
会社の廃業を検討中の経営者の皆様、在庫の処分方法にお悩みではありませんか?
事業をたたむ際、商品や原材料などの在庫をどのように処理するかは、廃業プロセスにおける重要な課題の一つです。
放置すれば余計なコストがかかり、かといって安易に捨ててしまっては貴重な資産を無駄にしかねません。
今回は、廃業時の在庫処分について、基本的な手順と注意点を解説します。スムーズな廃業の実現に向けて、ぜひ参考にしてください。
在庫の把握と評価を行う方法
(1) 棚卸しの具体的な手順と注意点
在庫の把握は、定期的な棚卸しから始まります。品目ごとに数量や状態を正確に記録し、過不足がないかを確認します。 棚卸しの際は、以下の手順を踏むことが大切です。
-
- 在庫の保管場所を網羅的にリストアップする
- 棚卸し実施日時を事前に設定し、関係者に周知する
- 商品の出し入れを停止し、在庫を動かさない状態で数量を確定する
- 複数人で数量を確認し、記録の正確性を担保する
- 棚卸し結果を帳簿と照合し、差異がある場合は原因を究明する
これらの作業を通じて、在庫の実態を正確に把握できます。
特に、在庫の保管場所が複数に及ぶ場合や、商品の種類が多い場合は、もれなく棚卸しを行うことが重要です。倉庫や店舗、事務所など、在庫の保管場所を洗い出し、リスト化しておくことで、効率的な棚卸しが可能となります。
また、棚卸し当日は、通常業務を停止し、在庫の出し入れを制限することが原則です。商品の移動が発生すると、正確な数量の把握が難しくなるためです。事前に棚卸し日程を設定し、関係者に周知徹底しておきましょう。
(2) 在庫管理システムの活用方法
手作業による棚卸しは手間がかかるうえ、人為的なミスも生じやすいものです。
効率的かつ正確な在庫把握のためには、在庫管理システムの導入が有効です。
バーコードやRFタグを用いて商品の出入庫を記録することで、リアルタイムに在庫数を把握できます。また、過去の販売データを分析し、需要予測に基づいた適正在庫量の算出や、発注の自動化なども可能となります。
在庫管理システムは、クラウド型のサービスも数多く提供されており、少ない初期投資で導入できるのも魅力です。
導入にあたっては、自社の業務プロセスや商品の特性を踏まえ、最適なシステムを選定することが重要です。在庫管理の目的や、必要な機能を明確化し、複数のサービスを比較検討することをおすすめします。
また、システムの導入と並行して、運用ルールの整備や、従業員への教育も欠かせません。マニュアルを作成し、システムの使い方や、データ入力の基準を明文化しておくことで、円滑な運用が可能となります。
(3) 在庫評価額の算出方法
在庫の資産価値を適切に評価するには、以下のような計算が必要です。
-
- 商品ごとに、在庫数量と仕入単価(または製造原価)を掛け合わせ、在庫金額を算出する。
- 在庫金額の合計を在庫評価額とする。
- ※ただし、販売可能価格(時価)が仕入単価を下回る場合は、時価で評価替えを行う(「低価法」の適用)。
在庫評価額の算出にあたっては、品目ごとに適切な評価方法を選択することが重要です。例えば、季節商品や流行商品など、陳腐化リスクの高い在庫については、より保守的な評価を行うことが望ましいでしょう。
在庫処分の具体的な方法

(1) 在庫買取サービスの利用
在庫買取サービスは、売れ残った在庫を一括して買い取ってもらえる便利な仕組みです。
ただし、買取業者によってサービス内容や条件は異なるため、以下の点に注意して選定することが大切です。
-
- 買取可能な商品の種類や数量に制限がないか
- 買取価格は適正か(複数の業者から見積もりを取得し、比較検討する)
- 商品の引き取りはスムーズに行えるか
- トラブル発生時の対応体制は整っているか
買取業者の選定にあたっては、インターネットでの情報収集に加え、実際に数社に見積依頼を行うことをおすすめします。
金額面だけでなく、対応の丁寧さや、実績の豊富さなども重要な判断材料となります。
また、買取価格については、業者との交渉の余地もあります。
在庫の状態や数量、これまでの取引実績などを強調し、少しでも高い価格での買取を目指しましょう。
ただし、買取価格の交渉に固執するあまり、スケジュールに遅れが出ては本末転倒です。廃業までのタイムリミットを考慮しつつ、現実的な落とし所を見出すことが重要と言えます。
円滑な在庫処分のために、買取業者とのコミュニケーションを密に取ることが何より大切です。
(2) オークション・フリマアプリの活用
近年は、ネットオークションやフリマアプリの利用者が増加し、個人間売買が活発化しています。
これらのプラットフォームを活用することで、幅広い購買層に在庫商品を届けることができます。
オークション・フリマアプリでの販売を成功させるためには、以下のようなポイントに注目です。
-
- 商品ページの見せ方の工夫(魅力的な商品写真、詳細な説明文など)
- 価格設定の最適化(市場相場を意識しつつ、利益確保も考慮)
- 出品のタイミングと期間の設定(閲覧数が多い時間帯を狙う、十分な出品期間を確保するなど)
- 梱包・発送作業の効率化(資材の準備、スタッフの手配など)
- 特に、商品ページの充実は、販売成功の鍵を握ります。
商品の魅力を最大限に引き出す写真撮影や、詳細かつ丁寧な説明文の作成に力を注ぎましょう。
また、出品価格の設定は、一時的な売上だけでなく、利益率も勘案して決定します。
市場相場を把握しつつ、原価率や手数料なども考慮に入れて、適正価格を追求することが重要です。
出品のタイミングも、閲覧数の多い時間帯を選ぶなど、戦略的に考えていく必要があります。
曜日や時間帯によって、ユーザーの行動傾向は大きく変わります。
販売データの分析を通じて、最適なタイミングを割り出すことが望ましいでしょう。
さらに、梱包・発送作業の効率化も見逃せません。資材の調達や、スタッフの配置など、物流面での準備を万全に整えておくことが求められます。
(3) 廃棄処分
在庫の廃棄は、処分費用が発生するうえ、ロスが避けられない方法です。
ただし、滞留在庫を抱え続けることは、保管コストの増大や、商品劣化のリスクにつながります。
将来的な需要や販売可能性を見極め、思い切って廃棄処分に踏み切ることも必要です。
廃棄処分を行う際は、以下の点に注意が必要です。
-
- 廃棄品のリストを作成し、写真等で記録に残す
- 廃棄にかかる経費(業者への委託費用、残価値等)を算出する
- 産業廃棄物の処理基準に則った適正な処分を行う
- 廃棄品の数量や金額を税務署に申告する
まずは、廃棄対象となる商品を一覧化し、リスト化することから始めます。
商品名や数量などの情報を明記し、処分の正当性を担保するための証拠資料としても活用します。
また、廃棄処分には一定のコストがかかるため、事前に経費を見積もっておくことが重要です。
業者への委託費用や、残価値の算出など、数字を明確にしておくことで、適切な意思決定が可能となります。
産業廃棄物に該当する商品の処理は、法令順守が何より大切です。廃棄物の種類や量に応じて、適正な処理方法を選択しなければなりません。事前に自治体や専門家に相談し、必要な手続きを確認しておくことをおすすめします。
そして、廃棄処分後は、税務署への適切な申告も忘れずに行いましょう。廃棄した商品は、経費として計上することができます。証憑書類を整理し、適正に税務処理を行うことが求められます。ただし、むやみに廃棄処分を繰り返すのは得策とは言えません。
定期的な需要予測や在庫管理の徹底など、そもそもの在庫発生を抑制するための取り組みが何より重要です。過剰在庫のリスクを常に意識し、適正な発注・仕入れ体制の構築を目指すべきでしょう。
在庫処分における税務上の注意点

(1) 事業所得の申告方法と必要書類
在庫処分による収入は、原則として「事業所得」に区分され、確定申告が必要となります。 申告の際には、以下のような書類を準備しておく必要があります。
-
- 在庫処分に関する契約書や請求書、領収書等
- 廃棄した在庫のリストや写真等の証憑類
- 在庫評価額の算出資料
- 処分にかかった経費の領収書等
これらの書類に基づき、収入金額と必要経費を計算し、所得金額を算出します。
個人事業主の場合は、所得税の確定申告書に事業所得として記載します。
法人の場合は、法人税の申告書に益金(収入)と損金(経費)として計上します。
(2) 欠損金の繰戻還付制度の適用条件と手続き
欠損金が生じた場合、前年以前に納めた税金の還付を受けられる制度が「欠損金の繰戻還付制度」です。適用を受けるための主な条件は以下の通りです。
-
- 青色申告書を提出していること
- 前年以前に黒字申告をしており、納税していること
- 欠損金額が、前年以前の所得金額を上回っていること
本制度の適用を受けることで、前年以前に納めた税金の還付を受けられます。還付金は、繰り戻し対象年度の所得税額や法人税額が上限となります。手続きとしては、確定申告書に欠損金の繰戻しによる還付請求書を添付し、提出します。
ただし、本制度の適用には制限事項もあるため、事前に税理士等の専門家に相談し、適用の可否を確認しておくことが重要です。欠損金の繰戻還付制度は、廃業時の資金繰りを助ける有効な手段となり得ます。
制度の概要を正しく理解し、適用要件を満たしているか、慎重に検討することが求められます。
廃業時の在庫処分を円滑に進めるポイント
(1)早期着手のメリットと具体的なスケジュール例
在庫処分は、計画的に進めることが何より大切です。 特に、販売による処分を検討する場合は、一定の期間を要するため、早めに着手することが重要です。
スケジュールの一例を示すと、以下のようになります。
-
- 廃業6ヶ月前:在庫処分方針の決定、在庫データの整理、処分スケジュールの策定
- 廃業5ヶ月前:販売チャネルの選定、価格設定、販促計画の立案
- 廃業4ヶ月前:在庫処分セールの告知、販売の開始
- 廃業2ヶ月前:売れ残り在庫の再評価、買取業者への打診
- 廃業1ヶ月前:在庫処分の完了、必要書類の整理・保管
早期に着手することで、販売機会を十分に確保でき、売上の最大化が期待できます。
一方、時間的な余裕がない場合は、買取サービスの利用や、思い切った値引販売などの方法を選択せざるを得ません。
いずれにせよ、具体的なスケジュールを策定し、それに沿って着実に行動することが重要です。
特に、販売計画や販促施策については、適宜見直しを行い、状況の変化に柔軟に対応することが求められます。
在庫処分は、廃業プロセスにおける重要なマイルストーンです。
スケジュール管理を徹底し、円滑な処理を目指すことが何より大切と言えるでしょう。
(2) 専門家との連携の進め方と相談事例
在庫処分を進めるうえでは、専門家の知見を活用することが有効です。
特に、税務面での適切な処理や、法的な問題への対応は、専門家の助言が欠かせません。
例えば、以下のようなケースでは、専門家に相談することが望ましいでしょう。
-
- 在庫の評価額の算定方法がわからない
- 在庫処分に関するトラブル(買取業者とのトラブル等)が発生した
顧問契約を結んでいる税理士や弁護士がいる場合は、まずは相談してみることをおすすめします。
在庫処分の目的や、抱えている課題を明確に伝えることで、適切なアドバイスを得られるはずです。
また、必要に応じて、在庫処分の経験が豊富な専門家を紹介してもらうのも良いでしょう。
M&Aの進め方と成功のポイント
在庫処分を伴う廃業のタイミングで、M&Aによる事業譲渡を検討されてはいかがでしょうか。会社の経営資源を引き継いでもらえれば、在庫を含む資産の有効活用が可能となります。加えて、従業員の雇用を守ることもできるはずです。
M&Aを成功させるためのポイントは、以下の通りです。
-
- 譲渡対象となる事業や資産の範囲を明確にする
- 自社の企業価値を適切に評価する
- 譲渡先候補企業のリストアップと、秘密保持契約の締結
- 譲渡先企業の選定と条件交渉
- デューデリジェンス(査察)の実施と、リスク要因の洗い出し
- 最終契約の締結と、事業の引継ぎ
M&Aの実行には専門的な知識と経験が必要となるため、専門家のサポートを得ることが不可欠です。
金融機関やM&A仲介会社などに相談し、適切なアドバイスを受けながら進めることが重要となります。
特に、自社の企業価値の適切な評価は、M&A成功の鍵を握ります。在庫をはじめとする資産の価値や、技術力、顧客基盤など、自社の強みを客観的に分析し、適正な譲渡価格を設定することが求められます。その上で、譲渡先候補企業を探索し、条件交渉に臨む必要があります。
秘密保持契約を締結した上で、候補企業に自社の情報を開示し、譲受の意向を確認することから始めましょう。複数の候補先と並行して交渉を進め、最良の条件を引き出すことが重要です。
M&Aは、在庫処分という課題の解決にとどまらず、会社の将来を見据えた戦略的な選択肢と言えます。廃業を決断するのと同じくらい、M&Aについても真剣に検討してみる価値があるのではないでしょうか。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。


