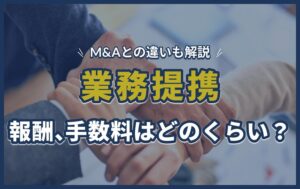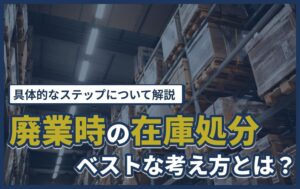ドラッグアロング条項とは?条項の内容や用途について解説


中小企業の経営者の皆様は、企業の将来像を描く中で、株式の所有や移転について悩むことも多いのではないでしょうか。
特に、事業承継やM&Aを視野に入れている場合、株式の取り扱いは重要な検討事項です。
今回は、「ドラッグアロング条項」について解説します。この条項を理解し、うまく活用することでスムーズな株式の譲渡とガバナンス強化を実現できるでしょう。
目次
ドラッグアロングとは
ドラッグアロングとは、株主間契約や定款で定められる条項の一つで、主要株主が自らの株式を売却する際に、他の株主も同じ条件で株式を売却することを義務付ける権利です。
この条項により、全株主が一致した条件での株式売却が可能となります。
例えば、創業オーナーがベンチャーキャピタルから資金調達を受ける際、投資家との間でドラッグアロングを含む株主間契約を結ぶケースがあります。
将来、投資家が株式を売却する場合、創業オーナーも同じ条件で株式を売却しなければならないというルールを予め定めておくのです。
つまり、ドラッグアロング条項は、株式の譲渡に関する制限の一種です。
他の制限とは異なる特徴があります。例えば、「譲渡制限株式」は、株主が株式を譲渡する際に、会社や他の株主の承認を必要とするものです。
これに対し、ドラッグアロングは、特定の株主による株式売却に他の株主が合わせることを義務付けるものであり、譲渡の可否ではなく、譲渡の条件に焦点を当てた条項といえます。
ドラッグアロングのメリットは何か?
そもそも、なぜ譲渡の条件を制限するドラッグアロング条項を株主間で締結する必要があるのでしょうか。
ドラッグアロング条項の主なメリットは、企業の合併・買収(M&A)において、買い手が売り手の全株式を取得しやすくなることです。
経営権の移転を伴うM&Aでは、買い手は通常、対象会社の全株式の取得を目指します。ドラッグアロングがあれば、一部の株主が売却に反対したとしても、全株式の売却を実現できるということです。
また、この条項により、買収後の統合プロセスがスムーズになるというメリットもあります。経営権が分散していると、意思決定に時間がかかったり、株主間の利害対立が生じたりするおそれがあります。
加えて、ドラッグアロングは、株式の流動性を高めるメリットもあります。特に非上場企業の株式は、市場で自由に売買できないため、投資家にとって流動性が低いデメリットがあります。
しかし、ドラッグアロング条項があれば、主要株主の売却に合わせて自身の株式も売却できるため、投資回収の選択肢が広がります。
株式の流動性が高まれば、資金調達がしやすくなるというメリットも期待できるでしょう。
ただし、ドラッグアロングのメリットを享受するためには、条項の内容を適切に設計することが重要です。安易な条項設定は、かえって株主間の対立を生んだり、株式の譲渡を困難にしたりするおそれがあります。
自社の状況を踏まえ、株主間の利害関係を考慮しながら、最適な条項設計を行うことが求められます。
適用される場合とその条件
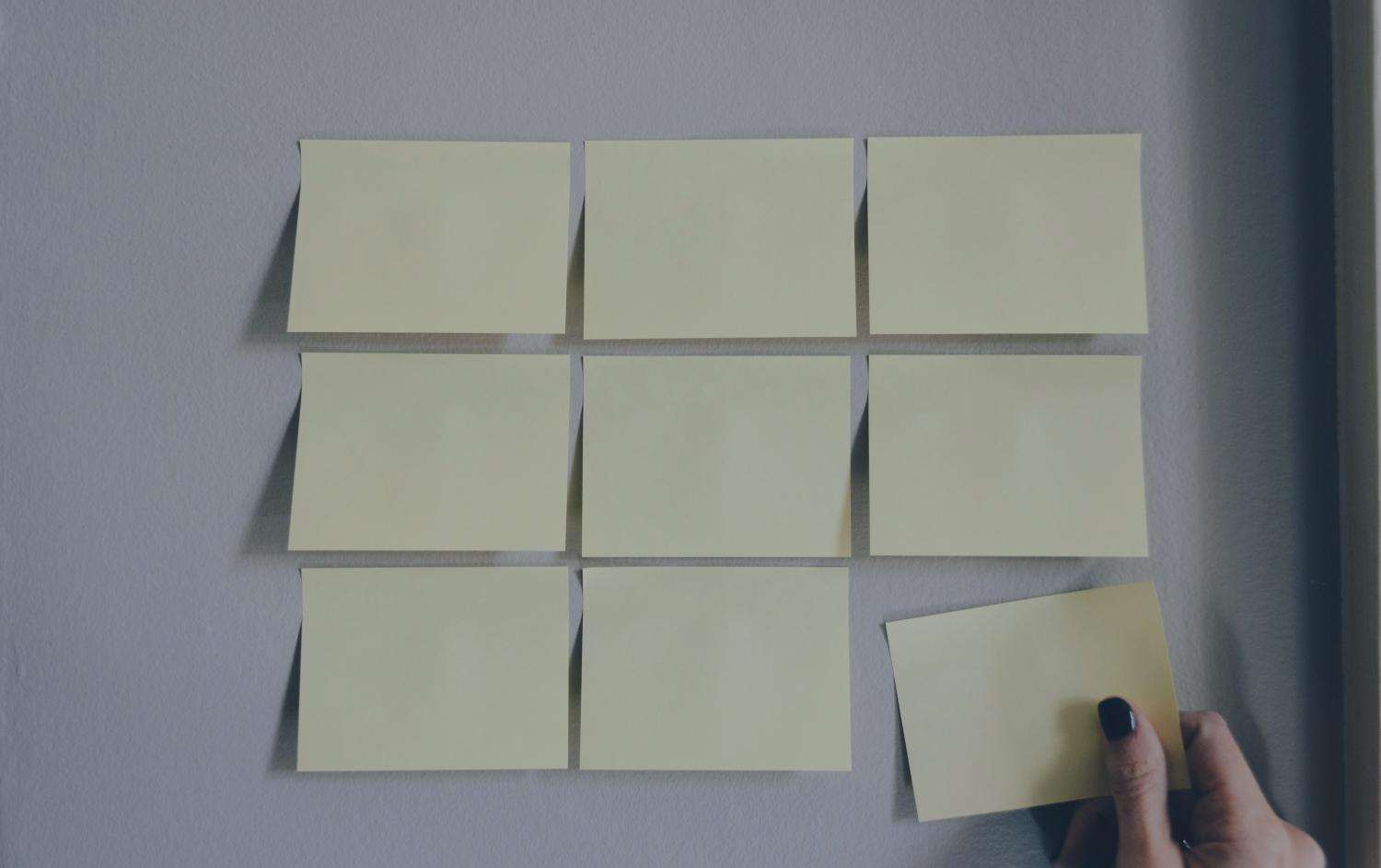
では、ドラッグアロング条項は、どのような場面で用いられるのでしょうか。主に、ベンチャー企業や成長途上の企業が、資金調達やM&Aを行う際に、この条項が投資契約の一部として設定されることが多いです。
ドラッグアロングの適用条件やプロセスは、事前の契約で定めておく必要があります。
例えば、「主要株主が議決権の過半数を保有する買い手に株式を売却する場合、他の株主も同じ条件で応じなければならない」といった内容を盛り込むことが一般的です。
売却価格の決定方法や、株主への通知期間なども、予め取り決めておくとよいでしょう。
適用するタイミングとなる「主要株主による株式売却」の定義も、明確にしておく必要があります。
一般的には、大株主が保有株式の全部または一定割合以上を売却する場合を指すことが多いですが、具体的な基準は都度、契約で定めます。例えば、「議決権の50%以上を保有する株主が、その保有株式のうち、75%以上を売却する場合」などと規定することが考えられます。
また、ドラッグアロングの対象となる株主の範囲も、契約で明記しておくことが重要です。
通常は、主要株主以外の全株主が対象となりますが、例外的に適用除外とする株主を定めることもできます。
例えば、「創業オーナーの親族が保有する株式については、ドラッグアロングの対象外とする」といった規定を設けることも可能です。
ドラッグアロング条項の適用は、株主の権利に大きな影響を及ぼします。そのため、条項の効力が発生する状況を明確に定めておくことも重要です。
通常は、主要株主から他の株主への通知、株主総会での決議、売却実行といった流れになりますが、各ステップの期限や要件を契約で定めておく必要があります。
これにより、手続きの透明性を高め、株主間のトラブルを防ぐことができるでしょう。
ドラッグアロングの注意点
ドラッグアロング条項は、株式の円滑な移転を促す一方で、経営者にとってはデメリットもあります。
例えば、自社の意向とは異なるタイミングや条件で株式を手放さなければならなくなるかもしれません。事業拡大の選択肢が狭まるリスクもあるでしょう。
経営者は、ドラッグアロング条項を契約に含める際、その条項が将来の経営戦略や企業価値にどのような影響を及ぼすかを慎重に検討する必要があります。
特に、少数株主との関係性には注意が必要です。一方的に不利な条件を押し付けられたと感じた株主から、反発を招く恐れもあるからです。
加えて、ドラッグアロング条項の存在が、潜在的な投資家にとってのデメリットになる可能性もあります。
株式売却の条件が制限されることで、投資対象としての魅力が下がり、結果として資金調達が困難になるおそれもあるのです。
このように、ドラッグアロング条項には、一長一短があります。
経営者は、自社の状況を踏まえ、メリットとデメリットを比較しながら、条項が自社に必要かどうかを判断する必要があります。
その際、弁護士や会計士などの専門家に相談し、プロの視点からアドバイスを受けることも有効でしょう。
また、ドラッグアロング条項を設ける場合、株主間の利害調整を丁寧に行うことも重要です。
条項の内容について、全株主に十分な説明を行い、理解を得ておく必要があります。
特に、少数株主に対しては、条項の必要性を丁寧に説明し、不安や懸念を払拭することが求められます。
株主間のコミュニケーションを密に取りながら、合意形成を目指すことが大切です。
ドラッグアロング条項の交渉戦略

ドラッグアロング条項を設定する際は、自社に有利な内容を盛り込めるよう、戦略的に交渉することが大切です。
適用のトリガーとなる株式売却の範囲を限定したり、株価算定方法を自社に有利な形で規定したりするなど、条項の細部にこだわることが重要となります。
例えば、「大株主の株式の51%以上が売却される場合にのみドラッグアロングが適用される」と定めれば、少数株主の利益を保護しつつ、必要な場面で条項を発動させることができるでしょう。
また、株価算定の際は、「直近の取引事例や第三者評価を参考にする」といった客観的な基準を盛り込むことで、恣意的な価格決定を防げます。
交渉では、弁護士や会計士などの専門家の助言を仰ぐことも有効です。ドラッグアロングは法的な側面が強い条項なので、適切な文言を用いた契約書の作成が不可欠だからです。
株主間の利害関係を調整しながら、納得感のある合意を形成していくことが求められます。
また、ドラッグアロング条項の交渉では、株主間の力関係も考慮に入れる必要があります。大株主と少数株主では、交渉力に差があるのが一般的です。
少数株主の立場から条項の修正を求める場合、単独では困難を伴うかもしれません。
そこで、他の少数株主と共同で交渉に臨むことも一案です。複数の株主が共通の利害関係を持って交渉に参加すれば、より大きな影響力を発揮できるでしょう。
さらに、ドラッグアロング条項の交渉では、将来の変化も見据えておく必要があります。
例えば、株主構成や持分割合が変われば、条項の影響も変わってきます。そこで、定期的な条項の見直しを契約に盛り込んでおくことも有効です。状況の変化に応じて、柔軟に条項を修正できるようにしておくのです。
ドラッグアロングの注意点
ドラッグアロング条項は、法的な観点からも慎重な検討が必要です。この条項は、株主の財産権に関わる事項であり、場合によっては、少数株主の利益を不当に害するおそれもあるからです。
特に、ドラッグアロングの対価が不当に低い場合、少数株主からの法的なクレームを招く可能性があります。株主間契約であっても、公序良俗に反するような内容は、無効となる場合があるのです。
また、ドラッグアロングの行使が、株主平等の原則に反するような場合にも、法的なリスクが生じます。例えば、特定の株主を意図的に不利な立場に置くような条項は、問題となる可能性があります。
したがって、ドラッグアロング条項の設計・交渉に当たっては、弁護士などの専門家の助言を得ながら、法的なリスクを最小化することが重要です。条項の内容が適法かつ公正なものとなるよう、十分な注意を払う必要があります。
また、ドラッグアロング条項の実施に当たっても、適切な手続きを踏むことが求められます。
株主総会の決議など、会社法上の要件を満たす必要があるのです。手続き面のミスは、条項の効力を左右する可能性もあるため、細心の注意が必要でしょう。
ドラッグアロングは、経営戦略上の重要なツールとなりうる
ドラッグアロング条項は、法的・実務的な側面だけでなく、経営戦略的な意義も持っています。この条項を活用することで、株式の所有と支配に関する柔軟な設計が可能となるからです。
例えば、ベンチャー企業が成長段階で資金調達を行う際、投資家との間でドラッグアロング条項を設けるケースがあります。
将来の買収や上場の際に、創業オーナーの株式も含めて全株式を売却できるようにしておくのです。これにより、買収価格の最大化や、スムーズな上場が期待できます。
また、オーナー企業が事業承継を行う際にも、ドラッグアロング条項が有効に機能します。後継者への株式集約を円滑に進められるだけでなく、株主間の利害対立を防ぐことにもつながるでしょう。
さらに、ドラッグアロング条項は、株主間の協調関係を維持する役割も果たします。全株主が共通の利害を持って行動するよう、一定の規律とすることができます。
特に、複数の株主が存在する場合、ドラッグアロングを通じて、株主間の結束力を高められます。
加えて、ドラッグアロング条項は、会社のガバナンス強化にもつながるものと言えます。
経営権の分散を防ぎ、意思決定の迅速化を図ることができるからです。株主間の無用な対立を回避し、経営の安定性を高める効果も期待できるでしょう。
このように、ドラッグアロング条項は、単なる株式の譲渡制限ではなく、経営戦略上の重要なツールといえます。
まとめ
中小企業の経営者にとって、ドラッグアロング条項は、株式の円滑な移転を実現し、ガバナンスを強化するための有力な手段となります。一方で、株主間の利害調整には細心の注意が必要です。条項の内容や適用場面を吟味し、専門家の知見も活用しながら、自社に最適なドラッグアロングの在り方を追求していきましょう。この条項を戦略的に活用することが、企業価値の向上につながるはずです。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。