M&Aすると株価はどうなる?メリット・デメリットなどを事例もあわせて紹介
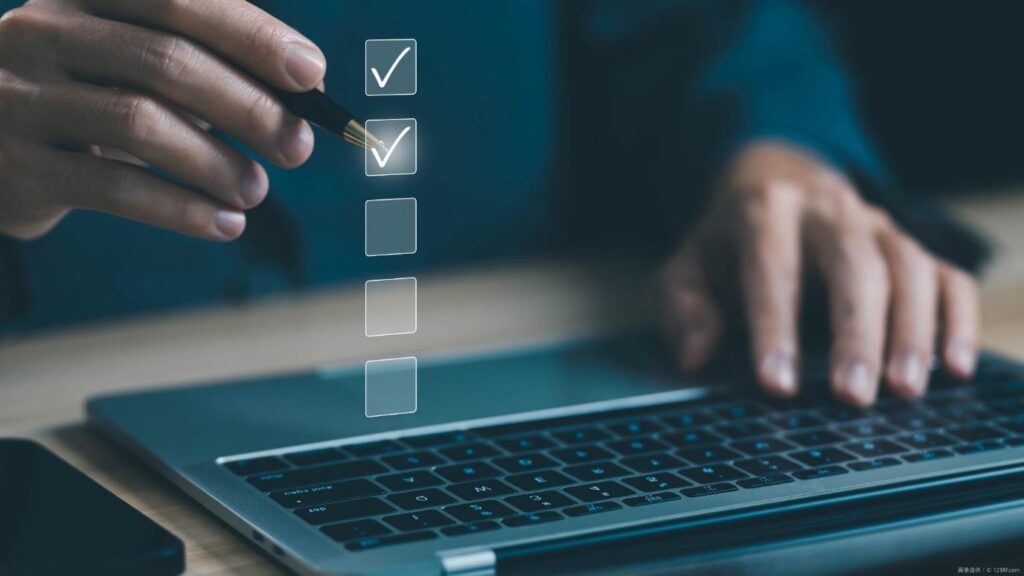
M&Aを検討されている経営層の方々は、「M&Aの実施によって、株価がどうなるか」について詳しく知りたいと考えている方も多いでしょう。
上場企業の場合、M&Aによって買い手企業も売り手企業も、株価が変動するのが一般的です。ここでは、どのような要素によって株価が変動するのか、また、実際にM&Aを実施すると株価はどのように変化するかについて事例を交えて分かりやすく解説します。
この記事を読むことで、自社の株価にM&Aがどのような影響を与えるかが、より具体的に理解できます。その結果、自社にとってM&Aのメリットとデメリットのどちらが大きいかを判断しやすくなります。
M&A(買収)とは
M&A(Mergers and Acquisitionsの略)とは、企業が合併や買収を行うことを指します。より専門的にはM&Aは「会社や経営権の取得」を意味します。M&Aの手法は以下の6つがあります。ただし事業譲渡は、M&Aでなく資産負債の売買取引とみなすこともあるようです。
- 買収:企業がほかの会社や事業などを買うこと
- 合併:複数の会社が一つになること
- 分割:新しい会社や既存の会社に事業を承継させること
- 株式交換:完全子会社となる会社の発行済株式のすべてを取得し、かわりに完全親会社となる会社の株式を交付すること
- 株式移転:既存の株式会社が完全親会社を設立し、保有する株式をその親会社にすべて移転し自らその完全子会社となること
- 事業譲渡:会社が営む事業の全部または一部を他の会社に譲渡する行為のこと
ここまで解説してきたのは狭義のM&Aの意味ですが、広義の意味としては「複数の会社の提携(協力関係)」をM&Aと表現することもあります。このようにM&Aの意味や手法はさまざまな解釈があります。
一口に、M&Aと言っても意味や手法によって「株価がどうなるか」は異なります。例えば、M&Aが買収を意味する場合、株価への影響は大きくなります。一方、提携を意味する場合、株価への影響は限定的であることが一般的です。
M&Aによって株価が変動する要素
次に、上場会社が行うM&Aによって株価が変動する要素を確認しましょう。まず前提として、上場企業の株価は以下の要素で日々変動しています。
- 保有資産
- ブランド価値
- 売上高や利益などの業績
- 投資家の期待値や注目度
- 経済、為替、政治動向 など
これらに加えて、M&Aの発表や実施も株価に影響を及ぼす可能性があります。M&Aによって株価がどうなるかは以下の要素によって変わってきます。
- 売り手企業の株価(買収価格)の妥当性
- 売り手企業の業績や財務状況
- 買い手企業の会社規模
- 買い手企業と売り手企業のシナジー など
例えば、買い手企業の株価で見た場合、買収価格が適正で、売り手企業の財務状況がよい場合、M&Aによって株価が上昇する可能性があります。逆に、買収価格が割高で、投資家から「M&Aが業績にマイナス」と判断されると株価が下落する可能性があります。
買い手側の会社規模
M&Aによって株価がどうなるかについて、影響を与える要素の1つに「買い手側の会社規模」があります。買い手企業がプライム市場の上場企業だったり、資金力のある大手企業だったりする場合は、M&Aによって株価が上昇しやすいといえます。これらの企業に買収されると、株価が上昇しやすい理由として次の3つが挙げられます。
- 潤沢な資金力で成長に必要な投資ができるから
- グループ企業との連携で売上を伸ばしやすいから
- 大企業のグループ企業になることで信用力が増すから
買い手・売り手の事業シナジー
さらに、M&Aによって株価がどうなるかについて、影響を与える要素の一つに「買い手企業と売り手企業の事業シナジー」があります。株価が上昇しやすいのは、両社の事業の相性がよくM&Aによってシナジー(相乗効果)が生まれる場合です。
具体的に、M&Aによってシナジーが生まれるのは次のような場合です。
- お互いの製品やサービスの補完性がある
- 原材料や商品の調達を合理化できる
- 生産能力を拡大できる
- 研究開発を強化できる
- 技術や資源を共有できる
- 販路を拡大できる
- マーケティングや宣伝などの費用を削減できる
- 資金調達力を強化できる など
M&Aが実施されると株価はどうなる?
「M&Aによって株価はどうなるか」というテーマでは、M&Aの発表や実施の後、上場企業の株価は変動するのが一般的です。株価が変動する理由は、投資家がM&Aによって企業の業績が上がると予測すれば株式を購入し、逆に業績が低下すると予測すれば株式を売却するためです。
とくに株価に大きな影響を与える要因は、知名度のある企業や急成長を遂げている企業がM&Aを発表した場合です。期待値の高まりを受けて株価が急騰することがあります。ただし、買い手企業と売り手企業の立場によって、株価への影響は異なります。詳しく見ていきましょう。
買い手側の株価への影響
まずは、M&Aによって「買い手企業の株価がどうなるか」について確認していきましょう。M&Aの発表直後は、投資家の期待値が株価を大きく左右します。投資家の期待値が高いと株価は上昇し、逆に期待値が低いと株価は下落します。
そして、M&Aから一定期間が経過すると、買い手企業の業績が重要な要素となります。例えば、期待されていた成果が得られなかった場合、株価は急落する可能性があります。
株価が上昇するとき
M&Aによって買い手企業の株価が上昇するのは、以下の2つのいずれかの場合です。
- 投資家の期待値が高いとき
- 業績が好調なとき
まず、「期待値が高いとき」とは、M&Aの発表直後に投資家の大半が「買い手企業の業績が今後よくなる」と考えた場合を指します。このような場合、株価は上昇する傾向にあります。投資家は一般的に「株価が安いうちに購入したい」という心理を持っており、業績がよくなると多くの投資家が予想した段階で買いが集まり、株価上昇の流れが強まります。
また、「業績が好調なとき」については、M&A実施後に一定期間が経過し、売り手企業とのシナジーによって業績が向上することで株価が押し上げられる要因となります。
株価が下落するとき
M&Aによって買い手企業の株価が下落するのは、以下の3つのいずれかの場合です。
- 投資家の期待値が低いとき
- 買収額が高すぎるとき
- 買い手企業の業績が悪化したとき
1つ目の「期待値が低いとき」については、M&Aの発表直後に投資家の大半が「買い手企業にとって買収はマイナス材料だ」と考えた場合に株価が下落します。例えば、対象企業が長年赤字の企業である、あるいは、斜陽産業で将来の利益が見込めないなどの場合にマイナス材料と見なされやすいです。
2つ目の「買収額が高すぎるとき」については、買い手企業の規模に見合わない高額な買収価格だった場合に株価が下落しやすいです。高額な買収価格が買い手企業の大きな負担となり、適切な投資が行えない可能性があります。
3つ目の「買い手企業の業績が悪化したとき」については、M&Aのシナジーが得られず、予想していた売上や利益が確保できない状況で株価が下落しやすいです。また、期待値が高いほど、その反動で株価の下落幅が大きくなりやすいです。
売り手側の株価への影響
M&Aによって売り手企業の株価への影響はどうなるのでしょうか。売り手企業の株価は、M&A発表直後、株主から好意的に見られて上昇するケースが多いです。上昇する理由として、以下の理由が挙げられます。
- 買収プレミアムが付くから
では「買収プレミアムが付くから」について、次の項目で詳しく解説します。
買収プレミアムとは?
買収プレミアムとは、M&Aを成立させるために、買収価格に上乗せする金額のことです。買収プレミアムの総額は、売り手企業の時価総額と買収価額の差額です。
例えば、時価総額100億円の企業を買収するために、150億円の買収価額を支出する場合、差額の50億円の部分が買収プレミアムになります。買い手企業が買収プレミアムを負担する理由は、以下の3つが挙げられます。
- M&Aによって大きなシナジーを見込める
- 無形資産(ブランド価値や人材力など)の価値が高い
- 経営陣の変更によって業績好転が期待できる
買収プレミアムを設定することで、売り手企業との交渉を有利に進めやすくなったり、M&A成立までの期間を短縮できたりするなどのメリットがあります。
上場会社が売り手となるM&Aの場合、後述するTOBを行う必要に迫られます。TOBは株価にプレミアムを付けて買い集めることが殆どであるため、株価が高くなります。
M&Aにおける株価の算出方法
M&Aによって「株価はどうなるか」というテーマについて考えるときには、株価の算出方法の基本知識を知ることも役立ちます。M&Aの目的や手法はさまざまですが、ここでは「完全子会社化」を目的とした「株式交換」を行う場合を想定して株価の算出方法(算定方法)を解説します。
完全子会社化を目的としたM&Aでは、売り手企業(子会社になる企業)が買い手企業(親会社になる企業)に株式を100%譲り渡し、その対価として親会社の株式を譲り受けます。その際、親会社の株1株に対して子会社の株●株といった具合に、交換比率を決める必要があります。
株式交換比率と株価の算出方法は、以下のような内容で決められます。
- 市場株価法:株価の終値の平均(1ヵ月〜数カ月内)で決める
- 類似企業比較法:類似した会社の財務指標を参考にする
- 類似取引比較法:類似した会社の実際の取引価格を基準にする
M&Aにより株価が上昇・下落した事例
M&Aによって「株価はどうなるか」というテーマについて考えるときには、M&Aによって企業の株価が実際にどう推移したかを知ることも役立ちます。ここでは、飲食事業に特化してM&Aを行って株価が上昇したA社と、M&Aによる多角化を進めて株価が下落したB社の事例をご紹介します
※M&Aによる多角化を進めて株価が上昇した会社も数多くあります。
M&Aにより株価が上昇した事例
飲食事業を展開するA社は、多岐に渡る飲食ブランド(焼肉、回転寿司、居酒屋、定食など)を買収することで2000年から2023年にかけて売上を2,000億円以上も伸ばしました。その結果、2003年に200円台だった株価は2018年に3,000円を超えるまでに上昇しました。
その後、コロナ禍の影響でA社の株価は1,000円台前半にまで下落しましたが、2023年には2,000円台まで戻しています。A社が成功している理由としては、次の2点が挙げられます。
- 本業である飲食分野に特化してM&Aを進めてきたこと
- ファンが定着している飲食チェーンを中心にM&Aを行っていること
M&Aにより株価が下落した事例
M&Aを繰り返すことで企業を成長させる会社も多いですが、フィットネス事業を本業としていたB社は積極的なM&Aが裏目に出て赤字転落し、株価を急落させました。B社が順調な成長を遂げていたときはM&Aのペースは年間数十社で、グループの規模が大きくなるのに伴って株価は200円台から1,500円台に急騰しました。
その後、一時的に成功したB社はさらにM&Aのペースを年間70〜80社に加速させましたが、業績が悪化して大幅な赤字に転落しました。その結果、株価は1,500円台から100円前後と約15分の1になりました。失敗した理由として、再建の難易度が高い企業を数多く買収したことなどが指摘されています。
M&Aの株価に影響を与えるTOBとは?
M&Aによって「株価はどうなるか」というテーマについて考える際には、TOBについての知識も重要でしょう。TOB(Takeover Bidの略)は、「株式公開買い付け」という意味であり、不特定多数の株主から株式を買い付ける手法です。
通常、上場企業の株式は取引所を通じて取引されます。しかし、TOBの場合は取引所外で直接買い付けが行われます。TOBにおいては、株式の買い付けを行う側を「公開買付者」と呼び、買い付けを受ける側を「対象企業」と呼びます。
公開買付者がTOBを行う条件は金融証券取引法で規定されているため、この要件に該当するときにTOBを行う必要がありますが、TOBを行う動機は、以下のようにさまざまです。
- 企業買収
- 合併
- 子会社化
- 経営権の取得
- 自社株の取得
- 株主の権利の行使
- 上場廃止 など
また、公開買付者は、TOBを実施する前に以下の内容を公表する必要があります。
- TOBの期間
- TOB実施時の株価
- 買付予定株数 など
TOBは2種類
TOBには「友好的買収(TOB)」と「敵対的買収(TOB)」の2種類があります。これらは同じ企業の買収でも、公開買付者と対象企業の関係が大きく異なります。
友好的買収とは、対象企業の経営陣の賛同を得て実施する企業買収です。これに対して、敵対的買収とは、対象企業の経営陣の賛同を得ないで実施する企業買収です。この2つの買収手法の違い、そしてTOBによって株価がどうなるかについて確認していきましょう。
友好的買収
友好的買収(TOB)とは、対象企業の経営陣が公開買付者による株の購入に賛同して実施される買収手法です。一般的に、日本ではTOBというと友好的買収を指します。
友好的買収は、公開買付者と対象企業が良好な関係を築いているため、TOB後も経営者や経営陣がそのまま継続されるケースが多いです。ただし、公開買付者が一部の取締役に自社の人材を送り込む場合もあります。
通常、友好的買収では事前に入念な協議や交渉が行われ、TOB後に迅速な組織統合が行われることを目指します。そのため、M&Aによるシナジーが得やすいといえます。
敵対的買収
敵対的買収(TOB)とは、対象企業の経営陣の賛同を得ずに行われる企業買収のことです。経済産業省が策定した「企業買収における行動指針」内では敵対的買収という言葉ではなく、「同意なき買収」と表現されています。
敵対的買収が実施されると、経営者が交代させられたり、経営陣が一新されたりすることもあります。通常、TOBを行う場合は、公開買付者が設定する株式の保有比率は目的によって異なりますが、敵対的買収を成功させるには、少なくとも発行済み株式総数の50%超を獲得する必要があります。
上記の理由から、敵対的買収を行う公開買付者は、大企業や資金力のある投資ファンドなどに限られます。
TOBが与える株価への影響
一般的には、TOBが発表・実施されると「株価が上昇しやすい」といわれます。
TOBによって株価がどれくらい上昇するかはケースバイケースですが、通常はTOB発表日の終値に対し、TOB買付価格が20〜30%上昇することが多いです。例えば、TOB発表日の終値が1,500円の場合、20%のプレミアムが付くとTOB買付価格は1,800円になります。
また、TOB発表直後の株価は、TOB買付価格に近い価格で取引されることもよくあります。例えば、現在の株価が2,500円でTOB買付価格が3,500円と発表された場合、短期間で株価が3,500円前後に上昇するような流れが生じることがあります。
ただし、TOBが発表された後、株価が必ず上昇するわけではありません。敵対的TOBの場合など、TOBによって株価が下がることもあります。
まとめ
最後に、この記事で解説してきた「M&Aによって株価はどうなるか」について振り返ってみます。
M&Aによって、買い手企業も売り手企業も株価が変動する可能性が高いです。買い手企業の株価は、株主の期待値や一定期間経過後の業績によって変動します。一方、売り手企業の株価は上昇するケースが多いです(ただし、必ず上昇するわけではありません)。
M&Aによって株価が変動する要素には、買収価格の妥当性やシナジーなどがあります。最終的にM&Aの発表や実施によって株価がどうなるかについては、大半の株主が将来の業績をどう考えるかの影響が大きいです。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。


