廃業をスムーズに進める手順とは?注意点についても解説
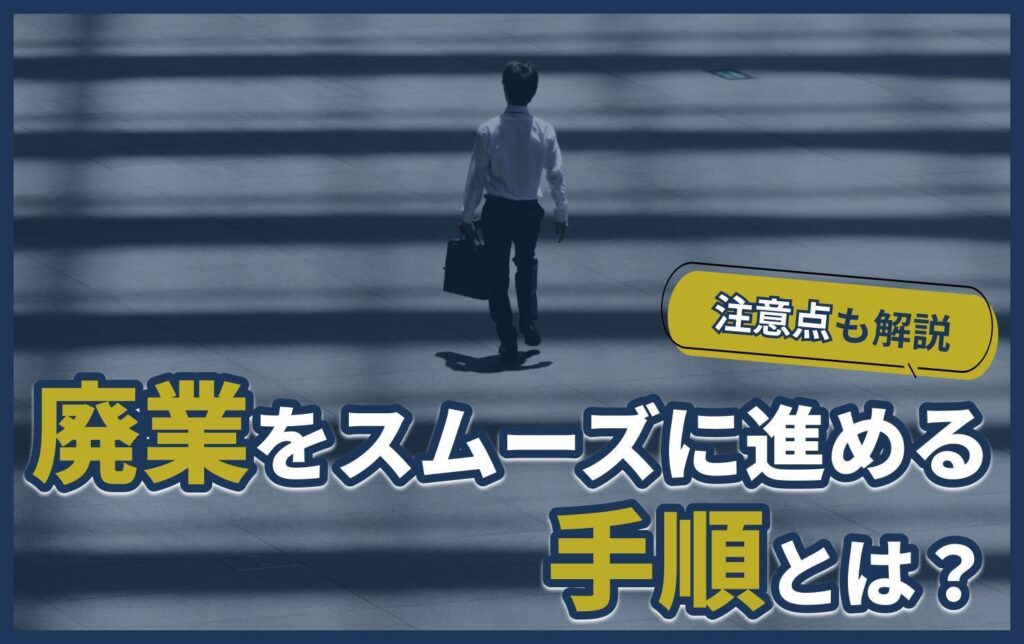
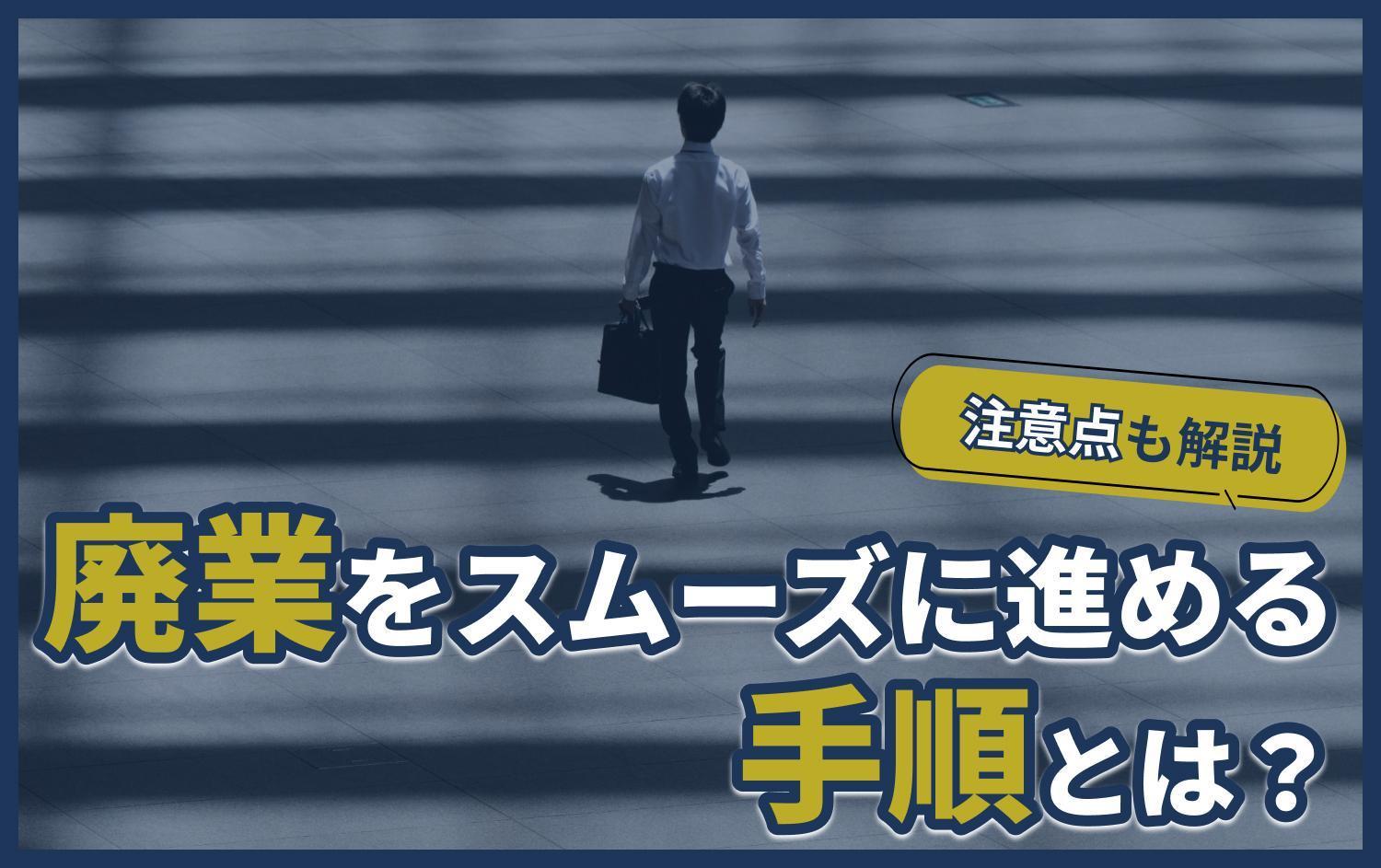
「事業を続けていく自信がない」「後継者が見つからない」そんな悩みを抱え、廃業を検討されている方は多いのではないでしょうか。
会社を畳むという決断は、誰しも簡単にはできないものです。しかし、廃業は決して後ろ向きな選択ではありません。
この記事では、廃業に関する基礎知識から、具体的な手続きの流れ、専門家の活用法まで、幅広くお伝えします。
目次
廃業の基礎知識と重要性の理解
廃業とは、経営状況に関わらず、自らの意思で事業を終了させることを指します。倒産が資金繰りの行き詰まりによる事業の停止であるのに対し、廃業は経営者の判断に基づく自主的な選択であるという点が大きな違いです。
会社を清算し、法人格を消滅させるためには、法律に則った手続きが必要となります。この手続きには通常2〜3か月の期間を要するため、計画的に進めることが重要です。
廃業と倒産の違い
廃業と倒産は、ともに事業を終了させる点では共通していますが、その背景にある事情は大きく異なります。倒産が債務超過や資金繰りの悪化による事業の行き詰まりが原因であるのに対し、廃業は必ずしも財務状況の悪化を伴うものではありません。経営者の高齢化や後継者不在、事業環境の変化への対応の難しさなど、様々な理由から自主的に事業の幕引きを決断するケースが少なくありません。
廃業を検討すべきケース 以下のような状況に直面している場合、廃業を選択肢の一つとして検討してみる価値があるでしょう。
-
- 事業の将来性が乏しく、業績回復の見込みが立たない
- 後継者が見つからず、事業承継が難しい
- 経営者の高齢化や健康上の理由で事業の継続が困難
- 市場環境の変化に対応できず、競争力を失いつつある
- 事業に対するモチベーションが低下し、新たなチャレンジを望んでいる
廃業と倒産の違いとは?メリットやデメリット・M&Aという選択肢も解説
廃業のメリット
廃業には、メリットとデメリットがあります。メリットとしては、事業から撤退することで、これ以上の損失を避けられること、経営者の精神的・肉体的な負担から解放されること、新たなチャレンジに向けて一歩を踏み出せることなどが挙げられます。
廃業のメリット・デメリットとは?経営者が取るべきアクションとは
廃業のデメリット
一方、デメリットとしては、従業員の雇用が失われること、取引先との関係が途絶えること、債権者への弁済が必要になること、個人保証の処理に時間を要することなどがあります。廃業の是非を判断する際には、これらのメリット・デメリットを慎重に見極める必要があるでしょう。
廃業する前に考えておきたい点

廃業を決断する前に、以下の点について十分に検討し、確認しておくことが重要です。
事業の将来性は十分に検討しましたか?
廃業を決める前に、事業の将来性を冷静に見極めましょう。市場動向や競合他社の状況を分析し、自社の強みを活かせる余地がないか、今一度検討してみることが大切です。業績回復の可能性を探るため、事業計画の見直しや、専門家の意見を参考にすることも有効でしょう。
事業承継やM&Aの可能性は探りましたか?
廃業以外の選択肢として、事業承継やM&Aについても検討してみる価値があります。親族内や従業員への承継、第三者への売却など、様々な角度から可能性を模索しましょう。事業の価値を適切に評価し、引き継ぐべき資産やノウハウを洗い出すことが重要です。M&Aの実現には専門家のサポートが欠かせません。
廃業とM&Aではどちらが良い?メリット・デメリットを詳しく解説!
ステークホルダーへの影響を考慮しましたか?
廃業は、株主、従業員、取引先、債権者など、様々なステークホルダーに影響を及ぼします。廃業の意思決定に際しては、関係者への影響を十分に考慮することが重要です。特に従業員の雇用については、丁寧な説明と、再就職支援などのケアが求められます。
債務の処理方法や個人保証の整理は確認しましたか?
廃業に伴う債務の処理方法について、債権者と十分に協議し、具体的な返済計画を立てる必要があります。個人保証を提供している場合、廃業後もその責任を免れることはできません。残債務の処理方法や、時効管理について、専門家のアドバイスを仰ぐことが賢明です。
廃業したら借入金はどうなる?個人事業と法人ごとの手続きを解説
廃業後の生活設計は立てましたか?
廃業後の生活を安定させるためには、綿密な生活設計が欠かせません。年金や退職金、再就職先からの収入など、様々な選択肢を検討しましょう。生活費の見直しや節約の工夫も重要です。再起業を目指す場合は、必要なスキルの習得や、事業計画の準備に十分な時間を確保することが重要です。
廃業手続きの流れと注意点
廃業を行う際には、法律に基づいた一連の手続きを適切に進める必要があります。以下では、廃業手続きの主要なステップと、各段階で注意すべき点について詳しく解説します。
【廃業手続きの全て】法的要件と進め方のポイントを解説廃業手続きのポイント
株主総会での解散決議
廃業を決定するためには、まず株主総会で解散決議を行わなければなりません。総会の招集通知は、開催日の1週間前までに発送する必要があります。株主総会において議決権を行使できる過半数の株主が出席し、その3分の2以上の賛成が必要とされます。可決後は、議事録を作成し、10年間の保存が義務付けられています。
解散・清算人選任登記
解散決議後は、速やかに解散登記と清算人の選任登記を行います。清算人は、債権者への公告や弁済、残余財産の分配など、清算業務全般を担当する重要な役割を担います。通常は取締役から選任されますが、必要に応じて第三者に依頼することも可能です。清算人の氏名・住所は、解散登記の際に登記簿に記載します。
税務署への届出
解散後、1か月以内に税務署へ「法人税の清算確定申告書」を提出します。この際、清算所得に対する法人税を納付します。また、「消費税の期限内申告書」や「源泉所得税の納期の特例の届出書」なども、期限内に提出する必要があります。
官報での債権者への公告と個別通知
解散後、遅滞なく官報で債権者に対して公告を行い、2か月以上の期間を設けて債権の申出を催告します。個別通知が必要な債権者には、別途書面で通知を行います。期間内に申し出のなかった債権は、弁済から除外されるため、債権者への適切な通知が重要です。
財産の換価と債権者への弁済
債権の申出期間終了後、清算人は会社財産を換価し、債権者への弁済を行います。弁済の順位は、①租税公課、②社会保険料、③一般債権の順に行われます。弁済後に残余財産がある場合、株主への分配を行います。
残余財産の分配
残余財産の分配は、定款の定めや株主総会の決議に従って行います。分配方法には、現金分配と現物分配の2種類があります。現物分配の場合、不動産等の資産評価を適切に行い、株主間の公平性を保つことが重要です。
清算結了登記
清算事務が全て終了したら、清算結了の登記を行います。登記申請書には、清算人が作成した清算報告書、残余財産の分配を証する書類等を添付し、管轄の法務局に提出します。登記が完了した時点で、法人としての存在が消滅します。
廃業手続きを進める際は、各ステップで求められる法的要件を満たし、適切な書類を期限内に提出することが重要です。また、債権者への適切な通知や、株主間の公平性の確保など、ステークホルダーへの配慮も必要不可欠です。手続きの複雑さを考慮し、専門家の助言を得ながら進めることをお勧めします。
廃業に必要な費用と資金計画

廃業には、各種手続きや諸費用がかかります。主な内訳は以下の通りです。
-
- 解散登記: 3万円
- 清算人登記: 約9,000円
- 官報公告掲載: 約2万2,500円〜3万2,500円
- 士業専門家への報酬: 約60万〜70万円
- 加えて、不要資産の処分や賃借物件の原状回復にも費用が発生します。
設備処分や原状回復にかかる費用の見積もり方 不要となった設備や在庫の処分費用、オフィスや工場の原状回復費用などを事前に見積もっておきましょう。処分業者や不動産業者に相談し、適正な金額を把握することが大切です。思わぬ出費を避けるためにも、入念な積算が欠かせません。
廃業にかかる費用・税金はどのくらい?合同会社や個人事業主の廃業も解説
資金計画の立て方とポイント
廃業費用の総額を見積もったら、支払いに必要な資金を手当てします。自己資金での捻出を基本としつつ、不足分は金融機関からの借り入れや、公的支援制度の利用を検討します。資金計画は、廃業スケジュールとリンクさせ、時期と金額を具体的に落とし込むことがポイントです。
廃業費用を捻出する方法(自己資金、借入れ、補助金など) 自己資金が十分でない場合は、金融機関から借り入れを行うのが一般的です。経営者保証に関するガイドラインを活用し、保証債務の整理を進めるのも有効です。国や自治体の支援制度、民間の助成金など、活用できる資源がないかリサーチすることも大切です。
廃業手続きにおける専門家の役割
廃業の手続きは複雑で専門的な知識を要するため、士業専門家の助言を仰ぐことをおすすめします。各専門家の主な役割は以下の通りです。
税理士
税務手続きと決算書類の作成 清算に伴う各種税金の申告・納付、確定申告や精算金の計算など、税務面のサポートを行います。適切な税務処理により、ペナルティの回避やコスト削減が期待できます。
司法書士
登記手続きと法的書類の作成 解散登記や清算結了登記など、法律に基づく手続きを担当します。必要書類の作成や法務局への申請を、スムーズに進めてくれます。
弁護士
債権者との交渉と法的トラブルの防止 債権者との和解交渉や、訴訟対応を必要とする場合のサポートを行います。トラブルを未然に防ぎ、円滑な債務整理を進める上で心強い味方となります。
社会保険労務士
従業員の雇用関係の整理と手続き 従業員の解雇手続きや、雇用保険・社会保険の脱退手続きなどを支援します。労働関連法規に則った適切な手続きにより、トラブルのない円滑な雇用関係の清算が可能となります。
廃業を検討するときの相談先は?具体的な相談の進め方について解説
廃業に伴う税務上の注意点
廃業に際しては、税務面の手続きにも十分な注意が必要です。主な注意点は以下の通りです。
法人税の確定申告と精算
清算所得に対する法人税の確定申告を行います。清算所得とは、解散日から清算結了の日までの期間における総収入金額から総損金を差し引いた金額を指します。期限内の申告と納税が求められます。
消費税の納付と還付
廃業に伴い、消費税の納税義務が生じる場合があります。一方で、還付を受けられるケースもあるため、適切な申告が重要です。帳簿や請求書等の管理を徹底し、税務処理に備えましょう。
役員報酬や退職金の取り扱い
清算期間中の役員報酬は、原則として損金算入が認められません。退職金についても、功績倍率法等の合理的な算定基準に基づいて支給する必要があります。税務署との事前協議が求められる場合もあるため注意が必要です。
不動産の譲渡に関する税金
清算に伴い不動産を譲渡する場合、譲渡所得税や印紙税等の課税対象となります。譲渡価格の設定や、必要経費の計上方法など、税務上の取り扱いについて専門家に相談し、適切に進めましょう。
廃業を円滑に進めるためのコツ

廃業を滞りなく進めるには、関係者との連携と、適切な情報管理が重要です。以下の点に注意しましょう。
廃業スケジュールの作成と進捗管理
廃業の手続きは、多岐にわたります。漏れなく確実に進めるため、スケジュールを作成し、タスクを可視化することが大切です。進捗状況を定期的にチェックし、滞りがないか確認しましょう。想定外の事態にも柔軟に対応できるよう、余裕を持ったスケジュール設定を心がけます。
関係者への丁寧な説明と協力の要請
廃業の意思決定から実行まで、関係者への丁寧な説明が欠かせません。株主や従業員、取引先、債権者など、ステークホルダーの理解と協力を得ることが何より重要です。誠実に事情を伝え、廃業後の対応についても明確に示すことが求められます。
書類の整理と保管方法
廃業に際しては、各種書類の整理と適切な保管が必要です。登記簿謄本や定款、株主名簿、債権債務に関する書類など、法律上保存が義務付けられているものもあります。紛失や散逸を防ぐため、体系的にファイリングし、安全な場所に保管しましょう。
トラブル防止のための注意点
廃業手続きの過程では、様々なトラブルが発生する可能性があります。債権者とのトラブル、従業員とのトラブル、株主間のトラブルなど、リスクを事前に把握し、防止策を行うことが重要です。専門家の助言を仰ぎつつ、冷静かつ迅速な対応を心がけましょう。
まとめ
廃業は、経営者にとって貴重な学びの機会でもあります。
廃業を決断するに至った背景を分析し、事業の振り返りを行うことがおすすめです。強みや弱み、成功要因や失敗要因を洗い出し、反省点を整理することが大切です。
経営者としての成長と気づき 廃業のプロセスを通じて、経営者としての資質を問われる場面が数多くあります。困難な状況下での意思決定力や、ステークホルダーとの調整力、ストレス耐性など、様々な能力が試されます。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。


