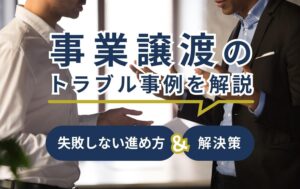会社精算の手続きの流れを解説!解散から精算までの期間はどのくらい?


多くの企業オーナーや経営者は、後継者不在や資金繰りの悪化、休眠会社の整理などの理由で会社の解散や清算を検討する際に「どのような手続きがあるのかわからない」など疑問を持つ方が多いでしょう。
そこで本記事では、会社清算の概要や種類をはじめ、具体的な手続き方法について詳しく解説します。
そもそも会社清算とは?
会社清算とは、会社が解散し清算体として再編されたあと、その資産と債務の清算を行うことを指します。
具体的には、不動産などの資産を売却して現金化することや債権の回収、債務の支払いなどが挙げられます。最終的には、残余資産を株主に均等に分配し、会社の資産と負債をすべて清算します。
会社の清算とは?解散からの流れや必要な手続き、期間、費用なども解説
会社清算の種類
会社清算には以下の種類があります。
-
- 任意精算
- 法定精算
- 通常精算
- 特別精算
任意清算
任意清算とは、定められた存続期間の終了や社員全員の合意に基づいて、自発的に会社を解散させる手続きを指します。
任意清算ができるのは、合名会社や合資会社に限定されています。株式会社が任意清算を行うと、一部の株主が過度な影響力を行使する可能性があるためです。株式会社においては、法定清算のみが許可されています。
法定清算
法定清算は、会社が法に基づいて資産を処理する手続きです。特定の業務を管理するために清算人を指名し、その清算人が債権回収や債務支払い、財産の分配などを担います。
清算人の選出は、清算開始時の取締役(法定清算人)か、会社の定款に基づくか、株主総会で決定されるか裁判所が選任した者がなります。清算人は取締役と同様の責任、すなわち忠誠義務、競業禁止義務、報告義務を負うことになります。
通常清算
法定清算には、通常清算と特別清算という2種類があります。
通常清算は、会社が充分な資産を保有しており、その資産を用いて負債を完済できる状況で適用される清算手法です。通常清算では、特別清算とは異なり、裁判所の監督を必要とせず、清算人が主体となって清算の過程を進められます。
特別清算
特別清算は、債務超過状態にある会社が、自身の負債を全額支払えない場合に選択される清算方法です。破産とは異なり、特別清算は会社が提出する特別清算申し立てに基づいて実施されます。破産が破産管財人によって進められるのに対し、特別清算では会社が指名した清算人がプロセスを主導します。
特別生産のメリットとして、破産というネガティブなイメージを持たず、清算人の主導のもとで手続きが行われるという利点があります。
会社清算と会社解散の違い
会社の「解散」とは、その企業が事業を終了することを意味します。「清算」とは解散した会社が資産を整理し、債権債務を清算する過程を指します。
株式会社が事業を終了する際には、会社を解散したうえで通常清算手続き(資産が負債を上回っている場合)、特別清算手続き(債務が資産を上回っている場合)が行われます。これらの手続きでは会社の資産を現金化し、債権者への支払いを行い、最終的に会社を閉鎖します。
どちらの手続きも、株主総会での解散決議(特別決議)をもとに開始されます。
会社解散から清算するまでの全体の流れ
会社解散から清算までの流れは以下のとおりです。
-
- 会社解散の事由発生
- 会社解散のための精算
- 株式会社の解散登記
- 会社清算人による精算処理
- 清算結了
会社解散の事由発生
以下の会社解散の事由が発生した時点で、会社清算、解散の手続きが開始されます。
-
- 定款で定めた存続期間の満了
- 定款で定めた解散事由の発生
- 株主総会の決議
- 合併により会社が消滅する場合
- 破産手続開始の決定
- 裁判所による解散命令
- 休眠会社のみなし解散の制度
会社解散のための清算
会社解散後、清算手続きに進みます。
株式会社の解散登記
会社が解散する際には、解散の日から2週間以内に解散、及び清算人選出の登記を行う必要があります。また、官報に公告を出して債権者に債権申告を促します。
登記には、定款、株主総会の議事録などの書類提出が必要となり、登記を完了させるためには登録免許税の支払いも求められます。具体的には、解散登記には3万円、清算人登記には9,000円、総額で3万9,000円の登録免許税が必要になります。
会社清算人による清算処理
株式会社が解散登記を完了させたあと、選出された清算人は会社の清算処理を開始します。清算処理には、会社の全資産を現金化して債権の回収を行います。その後、得られた資産で会社の負債を返済する作業が含まれます。
もし会社の資産が不足しており、すべての負債を返済できない場合、会社は特別清算や破産の申し立てを検討することになります。
清算結了
清算処理が完了し、もし残余財産が存在する場合は、その財産を株主に按分して分配します。これにより、会社の資産はすべて処分されます。
残余財産の分配が終わり、決算報告書を作成し株主総会でこれが承認されることで、会社の 清算手続きは完了し、清算結了の登記をすることで法人格は消滅しすべて終了します。
会社解散から清算するまでの具体的な手続き
以下では、会社解散から清算するまでの具体的な手続きを解説します。
具体的な手続きは以下のとおりです。
-
- 株主総会による解散決議
- 解散・清算人選任と登記
- 解散の届け出
- 財産目録と貸借対照表の作成
- 債権者の保護手続き
- 解散確定申告書の提出
- 残余財産の確定・株主等への分配
- 清算確定申告書の提出
- 決算報告書の作成・株主総会での承認
- 清算結了
- 清算結了の届け出
株主総会による解散決議
会社解散の理由として会社法に規定されている7種類がありますが、なかでも株主総会による解散決議がもっとも一般的です。
解散決議を行うには、議決権を行使できる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)の賛成を得る必要がある特別決議が必要です。
解散・清算人選任と登記
会社の解散が決まった際は、解散決定日から2週間以内に「解散の登記」と「清算人の選任登記」を行わなければなりません。
これらの登記に必要な書類は、事例により異なります。
解散の届け出
解散および清算人選任の登記に必要な書類を整えて登記が完了したあと、会社は労働基準監督署や税務署などの関連機関に対して、異動届出書を提出するなどして、会社の解散を届け出る必要があります。
財産目録と貸借対照表の作成
株主総会で会社の解散が決定された際は、清算人が任命され、解散日時点での会社の財産目録および貸借対照表を作成します。
財産目録と貸借対照表の作成は、会社の資産と負債の正確な把握に不可欠であり、清算手続きを適切に進行させるために重要です。
債権者の保護手続き
債権者が異議を唱える可能性があるため、清算人は解散の事実を官報に公告し、かつ、知れたる債権者に個別催告を行います。異議を持つ債権者には、異議申し立てのための期間として通常2か月間が与えられます。
解散確定申告書の提出
会社解散時には、通常の確定申告と同様に解散確定申告書の提出が必要です。解散確定申告に必要な書類は、一般的な確定申告書と同様です。しかし、解散によって事業年度が12か月未満の場合は、通常認められる税額控除が適用されない場合もあります。
また、税制度などは複雑なことが多いことから、税理士や税務署と相談しながら慎重に手続きを進める必要があります。
残余財産の確定・株主等への分配
清算過程ですべての債権の回収と債務の弁済が完了し、結果として財産が残存している場合、その財産は株主に対して分配されます。
財産分配は、株主平等の原則に基づき、各株主の保有株式数に応じた比率で行われます。
清算確定申告書の提出
清算人による残余財産の確定及び分配が終了したあと、税務署に清算確定申告を提出します。清算確定申告では、一般的な確定申告書が使用されます。しかし、清算に伴う申告内容は通常の業務年度とは異なる点があるため、注意が必要です。
また、残余財産の存在下での申告と、債務超過の状況下での申告では扱いが異なるため、申告内容を正確に行う必要があります。複雑な税務処理には税理士のアドバイスを求めたり、直接税務署に相談したりすることで、適切な申告が行えるでしょう。
決算報告書の作成・株主総会での承認
債権および債務の整理と株主への財産分配が済んだあとは、清算事務決算報告書を作成・提出し、清算が完了したことを示します。清算事務決算報告書には、処理された債権、債務、関連費用の合計、残存する剰余財産、株主への分配額等が詳細に記載されます。
また、残余財産とその分配額が最終的に決まったあとは、正式に承認するために株主総会が開催されます。株主総会での承認を受けたことで清算は完了し、その後は清算完了の事実を法的に記録するために、登記所への登記申請や税務署への必要な届出を行います。
清算結了
決算報告書が株主総会で承認されたあと、管轄法務局で清算結了の登記をする必要があります。清算結了の登記は、株主総会での決算報告書承認後2週間以内に実施する必要があります。
清算結了登記に必要な書類は以下のとおりです。
-
- 株式会社清算結了登記申請書
- 株主総会議事録
- 決算報告書
清算結了の届け出
清算結了登記を完了すると会社は法的に消滅しますが、税務関連の手続きも必要です。具体的には、税務署や都道府県税事務所、市区町村役場へ「異動届出書」を提出する必要があります。
異動届出書を提出する際は、閉鎖事項全部証明書、すなわち登記事項証明書の添付が必要になるため注意しましょう。
会社解散から会社清算完了までに要する期間
清算人の登記や債権者への公告など、期日が定められている手続きには厳守が求められます。しかし、その他の手続きは多少前後しても概ね問題ありません。
会社の清算プロセスは、手続きがスムーズに進行した場合でもすべて完了するまでに最低でも約3か月は必要とされます。
まとめ
本記事では、会社清算の種類や清算と解散の違い、手続きの流れなどを解説しました。会社の存続が資金繰りや後継者がいないことなどが原因で厳しくなった場合は、会社解散・清算により廃業しなければならない場合があります。
会社清算は手続きの専門性が高く複雑であり、長い期間を要するため、税理士など専門家のサポートを受けることをおすすめします。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。