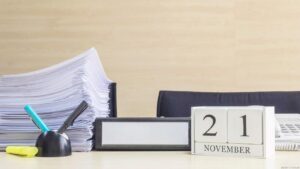株式交換とは?M&Aで大きなメリットに!実施の流れや注意点も解説

株式交換という言葉にあまり馴染みがない人も多いでしょう。
株式交換は親会社と子会社の関係性を生み出し、事業承継やM&Aにおいて事業拡大に有効な手法の一つです。
今回は株式交換についてのメリット・デメリットや手続きの流れ、注意すべきポイントを解説します。
目次
そもそも株式交換とは?株式移転との違い
株式交換とは、子会社へ転じる会社の株主が発行した株式と、親会社へ転じる会社の株式や資産などを、ある一定の割合で交換することです。
株式交換によって、親会社は子会社へ転じる会社の株式すべてを取得して、100%子会社化できます。
株式交換の類義語として「株式移転」という取引方法も存在します。
株式移転は、親会社へ転じる企業が子会社へ転じる企業の株式すべてを取得するという点では株式交換と同様です。
株式交換と株式移転の決定的な違いは「親会社となる企業が既存の会社か新設される会社か」が大きな違いとなります。
すなわち、すでにある企業を親会社とする株式交換に対して、親会社を新規に設立するのが株式移転です。
株式交換の種類は大きく分けて3つ
株式交換には一般的な取引方法の他に以下の3つの形式があります。
-
- 三角株式交換
- 簡易株式交換
- 略式株式交換
簡易株式交換と略式株式交換においては内容も似ていることから混同しやすいです。
形式ごとに条件や利点が異なるため、比較したうえで自社に合う手法を選択しましょう。
ここからは株式交換の形式の違いを一つひとつ解説します。
三角株式交換
三角株式交換はその言葉のとおり、買手・売手企業の2社に加えて第3の企業が加わって実施される株式交換です。
通常の株式交換では、買手企業と売手企業の2社間で取引が実施されます。
三角株式交換の場合、買手企業は自社株式を利用せず、その親会社の株式を対価として譲渡することが可能です。
実際の事例として、海外の企業が日本の企業を買収する「クロスボーダーM&A」の際に活用される手法でもあります。
簡易株式交換
簡易株式交換は、株主総会の特別決議をせずに取引を進めるための手法です。
簡易株式交換が適用されるためには、完全親会社が買収時に支払う対価を純資産額の5分の1以下に抑えることが条件です。
企業の規模が大きくなるほど株主の数も多く、株式交換を実施する際の株主総会の開催や承認を得るための時間や労力、コストは莫大になります。
そこで、簡易株式交換を選択することで消費時間や手間を省略でき、スムーズなM&Aが可能です。
ただし、株式総数の6分の1以上の株主が株式交換に反対した場合や、株式交換によって差損が生じる場合には特別決議による承認が必要です。
略式株式交換
略式株式交換も簡易株式交換と同様に、株主総会を省略できる手段の一つですが、適用条件が簡易株式交換とは異なります。
略式株式交換では、親会社が子会社議決権のうち90%以上を保有している場合に、子会社の株主総会の省略が可能です。
ただし「完全子会社となる企業が公開会社で、譲渡制限株式が交付される場合」と「完全親会社が非公開会社で、譲渡制限株式が交付される場合」においては株主総会の省略はできません。
売手企業からみた株式交換のメリット
株式交換には多くのメリットがありますが、完全子会社となるべき売手側の視点からも利点があります。
ここでは売手企業にとっての株式交換のメリットについて解説します。
経営統合がスムーズに実施できる
株式交換によって売手企業は子会社となりますが、法律上において企業自体の法人格は維持されます。
親会社とは別法人として存続できることから、組織や事業をそのまま承継でき、従業員や関係者への負担を軽減できます。
大きな変化を伴うことなくスムーズな経営統合ができる点においては、大きなメリットと言えるでしょう。
少数株主の反対に対して有効
例として、会社が別の会社にM&Aとして株式を譲渡する際に少数株主が譲渡を拒んでいる場合、なかなかM&Aに移行できません。
株式交換の場合は売手企業が株主総会を開き、特別決議を経ることによって実行できます。
特別議決では以下の2つの条件を満たす必要があります。
-
- 株主総会に出席した株主の議決権が全体の半数以上
- 出席者の3分の2以上が賛成する
条件を満たす場合、少数株主がいくら反対していても株式の買取請求によって強制的に買取ることが可能です。
買手企業からみた株式交換のメリット
株式交換は売手側だけではなく、親会社となる買手企業にとってもメリットが存在します。
M&Aによる組織再編を目指す場合に、主に資金面で有効な手段として多くの企業に活用されている取引方法です。
次に買手企業にとっての株式交換のメリットについて解説します。
買取資金がなくても買収できる
買収を行う際は株式を取得するための莫大な資金が必要であり、売手企業の規模次第では金額が億単位になることもあります。
株式交換における買手企業は、自己株式を買収の対価として支払うことで成立するため、買収のための資金が不要です。
買収の際に自己資金が少ない場合や融資を受けたくない場合に、有効な手段と言えるでしょう。
株式交換のデメリット
株式交換を行う際には、以下のようなデメリットが生じることもあります。
-
- 株価が下落するリスクがある
- 不要な資産や負債も引き継いでしまう
デメリットの多くは、買収の際の状況によって引き起こされるさまざまなリスクです。
株式交換によって組織の再編を図る場合は、起こりうるリスクを事前に把握しておく必要があります。
以下で一つひとつ解説します。
株価が下落するリスクがある
株式交換において、とくに買手企業が上場企業である場合には株価が下落するリスクがあります。
株式交換を行うと、対価として受け取った株式の株価が業績によっては下落する可能性があるためです。
業績向上による相乗効果も期待できますが、リスクとして株価の下落があることは理解しておくべきでしょう。
不要な資産や債務も引き継いでしまう
株式交換によって売手企業を完全子会社化するため、特定の事業だけを承継することはできず、資産すべてを引き継ぐ必要があります。
買手企業にとっては不要な資産だけではなく、債務までも引き継がなければなりません。
事業承継によって大きな効果が得られたとしても、多額の債務を背負ってしまえば経営状態が悪化する可能性があります。
株式交換を実施する前に企業調査を行い、買収後のリスク回避に努めることが必要です。
株式交換すると株主はどうなる?
株式交換の実施は株主の視点からも良い点と悪い点が存在します。
買収によって事業のシナジー効果が現れれば、売手側・買手側の双方の株主にとってメリットとなるでしょう。
株式交換の場合、売手企業も買手企業の一部株式を保有できるため、株主は親会社の議決権を得られます。
親会社の経営に関われる点において、売手側にとって通常のM&Aにはない利点です。
一方で、買手企業にとっては、従来の株主構成が変化することで悪影響を及ぼす可能性があります。
新株発行によって取引を行った場合、一株あたりの株価が下落する、いわゆる「希薄化」が起こります。
また、売手企業の株主が経営に影響力をもつことで、これまで円滑に進んでいた決定事項も難航するかもしれません。
株式交換の手続きと流れ
株式交換の際に必要な手続きの大まかな流れは以下の通りになります。
-
- 株主総会
- 株式交換の契約締結
- 事前開示書類の準備
- 債権者保護の手続き
- 株式交換の効力発生・登記申請
- 事後開示書類の備置
全体的な流れを把握し、円滑に進めていきましょう。
1.株主総会
株式交換を実施するための株式総会にあたり、原則として議決権の過半数以上の出席と3分の2以上の承認を得る必要があります。
ただし、簡易株式交換と略式株式交換の場合は株主総会の省略が可能です。
2.株式交換の契約締結
完全子会社が株式交換をする際、完全親会社との間で契約を締結する必要があります。
3.事前開示書類の準備
親会社および子会社は、株主への情報開示のため事前開示書類を各本店に備置することが定められています。
備置の期間は効力が発生してから6ヶ月間とされています。
4.債権者保護の手続き
原則として株式交換では債権者保護の手続きは不要です。
しかし、新株予約権付社債を承継する場合や自己株式以外を対価として交付する場合などにおいて、手続きが必要になるケースがあります。
5.株式交換の効力の発生・登記申請
株式交換契約書に記載されている日にちから、子会社の株式が親会社へ渡ります。
登記申請は効力の発生から2週間以内に行う必要があります。
6.事後開示書類の備置
株式交換に要する期間は約2ヶ月であるため、事後開示書類株式交換の効力発生から4ヶ月ほどの間、事前・事後開示書類を開示する必要があります。
株式交換の適格要件を満たす基準とは?
株式交換における適格要件とは、税制上の優遇を受けるために満たす必要がある条件のことです。
適格要件は以下の7つの項目で構成されています。
-
- 支配関係継続の要件
- 対価要件
- 従業員の引継要件
- 事業継続の要件
- 事業関連性の要件
- 株式継続保有の要件
- 事業規模もしくは経営参画要件
適格要件を満たすことで「適格株式交換」として認められますが、満たさない場合には「非適格株式交換」として、税制優遇を受けられません。
適格要件は組織の再編成を行ううえで、税金対策として重要な役割があります。
適格株式交換を取り入れようと考えている場合は、税理士のような税務の専門家にアドバイスを受けると良いでしょう。
1.支配関係継続の要件
既存の完全支配関係ないし支配関係が、株式交換後も継続することを要件としています。
それぞれの関係性を継続するためには、株式保有を維持し続けることが必要です。
2.対価要件
株式交換の対価として、自社株式以外の資産を交付しないという要件です。
つまり、金銭での株式交換は認められません。
例外として、親会社が子会社の発行株式のうち3分の2以上を保有していれば、株式以外の資産を譲渡しても要件をクリアできます。
3.従業員の引継要件
株式交換後も子会社の従業員が継続して在籍していることが要件です。
具体的には、株式交換前に在籍していた従業員の80%以上が引き続き在籍している必要があります。従業員の多くが子会社化に反対している場合は、要件を満たせなくなる可能性があるため注意が必要です。
4.事業継続の要件
子会社にあたる企業が、株式交換後も事業を継続していることも要件です。
事業が複数ある場合は、そのうち主要な事業と判断されたものになります。
支配関係・共同事業目的での関係性に対して求められるため、完全支配関係の場合には不要です。
5.事業関連性の要件
事業関連性の要件は、共同事業目的の株式交換に対して適用されます。
子会社となる企業の事業が、親会社が行う事業と相互に関連している必要があります。
事業が複数ある場合は事業継続の要件と同様に、主要な事業と判断されたものが対象です。
業態が異なっている場合でも、同一製品を取り扱うなどの関連性があれば要件は満たされます。
6.株式継続保有の要件
親会社の株主が、株式交換後も継続して子会社の株式を保有していることも求められる要件です。
株式継続保有の要件は、共同事業目的の関係性に対して求められます。
親会社と同グループの企業が半数以上の株式を保有していれば、ほかの株主が20%の株式を売却したとしても要件は満たせるとされています。
7.事業規模もしくは経営参画要件
合併法人と被合併法人の差が、売上金・従業員数・資本金のうちひとつでも5倍を超えないものがあれば要件はクリアです。
経営参画の要件では、子会社の特定役員が1人でも在籍していれば問題ありません。
事業規模もしくは経営参画の要件のうちどちらかを満たすことで本要件が成立します。
株式交換を実施する際の注意点
株式交換による組織編成を図る際には、思わぬトラブルに発展するケースも多いです。
株式交換において注意すべきポイントは以下の3つです。
-
- 社内外の関係者への報告
- 株式交換比率を理解する
- 場合によっては完全子会社も仕訳が必要になる
ここからは注意点について一つひとつ解説します。
社内外の関係者への報告
株式交換を実施する際、取引先や従業員などの関係者への報告は忘れずにしておくべきです。
関係者への報告を怠ることで、トラブルに発展したり不利益が生じたりするおそれがあります。
たとえば、金融機関から融資を受けている場合、株式交換によって融資条項に違反する可能性もあります。
株式交換の実施前に金融機関へ相談しトラブルを回避しましょう。
また、取引先が片方の企業との取引を快く思わないケースでは、契約を打ち切られることも考えられるため注意が必要です。
株式交換比率を公平にする
株式交換比率とは、完全子会社の株主が保有する株式に対して完全親会社の株式を何株受け取れるかの比率です。
完全子会社の株主が株式を譲渡した分の対価が株式交換比率によって決まるため、公平に割り当てる必要があります。
社長の親族だけがほかの株主よりも高い比率で交換されるようなことがあれば、トラブルの原因になるでしょう。
場合によっては完全子会社も仕訳が必要になる
通常、株式交換によって子会社へ転換した企業の資産や債務は変わらないため、仕訳の処理は必要ありません。
しかし、例外として子会社でも仕訳が必要になるケースもあります。
以前から親会社の自己株式を保有している場合は、株式交換により対価が発生するため仕訳が必要です。
また、対価として現金を支払うことで、非適格株式交換に当てはまる場合も仕訳処理を要するケースです。
非適格株式交換に該当すると子会社が保有する資産の一部は時価評価されるため「遅延税金資産および負債」の会計処理が必要となります。
株式交換を有効活用したM&Aでスムーズな組織編成を図りましょう
今回は株式交換についてメリット・デメリットや注意点、手続きの流れについて解説しました。
株式交換はM&Aや事業拡大に前向きな中小企業にとって、資金なしでも完全子会社を取り入れられる有効な手段です。
また、適格株式交換が認められれば税制上の優遇が受けられる点で、大きなメリットと言えるでしょう。
スムーズな経営統合が可能であり少数株主への対策ができるメリットがある反面、株価下落や債務を背負うリスクも存在します。
メリットや注意点を理解したうえで株式交換を有効活用し、スムーズな組織編成を目指しましょう。
ディスクリプション
株式交換とは何か?株式移転とは何が違う?売手企業と買手企業にどんなメリットやデメリットがあるのか徹底解説。実際の手続きの流れや実施における注意点、適格要件についても詳しく紹介します。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。