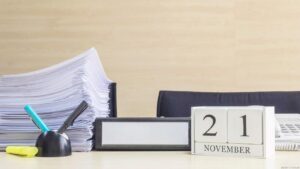会社をたたむ方法は?手続きの流れや費用、解雇のタイミングなどをまとめて紹介

会社をたたもうと考えている方の中には、方法がわからない方もいるのではないでしょうか。
会社をたたむためには、さまざまな手順を行う必要があり、時間や費用が必要となります。
本記事では、会社をたたむ方法や必要な費用・書類などを紹介します。
会社をたたむ以外の選択肢も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
会社をたたむとは
会社をたたむとは、事業を辞めることを意味する言葉です。
どの手法で会社をたたむとしても解散や清算の手続きを経る必要があるため、「明日には会社をたたもう」といったスピード感では行えない点には注意が必要です。
会社をたたむ方法には、破産法あるいは会社法に則って手続きをする「法的清算」と、地域経済活性化支援機構(REVIC)の支援制度や調停スキームによって精算する「私的整理」があります。
複数の方法の中から、経営状況に適した手法を選ぶことが重要です。
会社をたたもうと考える4つの理由
会社をたたもうと考える理由には、以下の4つがあります。
-
- 後継者問題
- 債務超過
- 人材難
- 資金調達の難航
4つの理由について紹介するので、会社をたたむべきか悩んでいる方は参考にしてください。
1.後継者問題
会社をたたむ理由として多いのが、後継者問題です。
経営者の高齢化が進んでいる企業が多いものの、後継者を見つけられず会社の存続が危うくなってしまうことで、会社をたたもうと考えるようです。
どれだけ敏腕な経営者であっても高齢になると現場に出れなくなったり、判断のスピードが遅くなったりして経営に影響が出てしまいます。
会社の未来を考えた際に、後継者へ引き継ごうと考えるものの適任者が見つからずに困っている方も多いです。
帝国データバンクの「全国「後継者不在率」動向調査(2023年)」によると、後継者問題に悩んでいる60歳以上の経営者のうち60%超が将来的な廃業を検討しています。
このように、後継者問題は経営者が会社をたたもうと考える大きな理由となっています。
2.債務超過
債務超過に陥っており立て直しが難しい場合も、会社をたたもうと考える理由になります。
債務超過とは、負債が純資産を上回っている経営状態を指しており、会社の収益を月々の返済に当てなければならず健全な経営が難しくなってしまいます。
一時的な債務超過であれば経営状況が改善できる可能性がありますが、基本的には立て直しが困難です。
債務超過によって経営を続けることが困難となった結果、会社をたたまざるを得ないと判断する経営者もいます。
債務超過について知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
関連記事:事業承継 債務超過
3.人材難
後継者に限らず従業員の採用が難航していることも、会社をたたもうと考える理由です。
従業員の高齢化が進むと業務スピードが落ちたり、新規事業への挑戦が難しくなったりすることが考えられます。
たとえば、若い世代の採用に苦戦して社員が全員50代を超えてしまうと、会社の長期的な存続は難しくなるでしょう。
会社を残したとしても働く人がいないのであれば、自分が引退するタイミングで会社をたたもうと考える経営者もいます。
4.資金調達の難航
銀行からの融資をはじめとした資金調達が難航してしまうことも、会社をたたもうと考える理由のひとつです。
経営者の高齢化や会社の収益減などの理由から、資金調達が難しくなってしまう企業もあります。
資金調達ができなくても経営を続けられる企業は多数ありますが、業種によっては経営が困難な状態に陥ってしまいます。
たとえば、設備投資が必要となる製造業や建設業などでは、資金調達ができないと業務に支障が出てしまうでしょう。
このように、業種によっては資金調達が原因で、会社をたたもうと考えるきっかけになります。
会社をたたむ3つの方法
会社をたたむ方法には以下の3つがあります。
-
- 倒産
- 廃業
- 解散
それぞれ詳しく紹介するので、会社をたたもうと考えている方は自社に適した方法を検討してみてください。
1.倒産
倒産とは、債務超過を解消できず、事業を継続できなくなった状態のことです。
帝国データバンクの「倒産集計」によると、2023年の1年間で8,497件の企業が倒産しており、2022年よりも約2,000件増加しています。
一般的には法的な手続きを経て会社を消滅させる法律上の倒産と、債務超過などによって営業が難しくなっている事実上の倒産に分類可能です。
法律上は、会社を消滅させる破産と事業の存続を前提とした民事再生に分けられ、会社の状況や価値によって対応が異なります。
2.廃業
廃業とは、経営者が自らの意思で事業を辞めることです。
倒産とは異なり、事業は続けられるものの事業継続を選択せず、会社をたたむことが廃業です。
債務超過などがなくとも、後継者問題や経営者のモチベーション低下などの理由から、廃業を選択するケースがあります。
中小企業の経営者の高齢化が進んでおり、帝国データバンクの「全国「後継者不在率」動向調査(2023年)」によると53.9%の中小企業が後継者不在です。
後継者問題に悩んでいる企業が増えていることから、廃業を選択する経営者が増えています。
廃業と倒産の違いや手順などを知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
廃業と倒産の違いとは?廃業を決断する前にM&Aの可能性を探ることが重要
3.解散
解散とは会社を清算し、消滅させるための手続きを進めることです。
会社の経営状況は悪いものの、倒産にいたっていない企業が解散を選択することが多いです。
解散の条件は会社法で以下のように定められています。
-
- 定款で定めた存続期間の満了
- 定款で定めた解散の事由の発生
- 株主総会の決議
- 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合)
- 破産手続き開始の決定
- 裁判所による解散命令
- 休眠会社のみなし解散
これらの条件を満たし、手続きが完了すれば会社の精算は完了です。
会社をたたむ場合に従業員を解雇するタイミング
会社をたたむ場合、従業員は解雇しなければならない点を理解しておきましょう。
会社をたたむと法人がなくなり従業員という概念も消滅するので、必然的に解雇をしなければなりません。
従業員を解雇するためには、労働基準法第20条で定められている解雇予告を行う必要があります。
解雇予告のルールは以下の通りです。
-
- 解雇の30日以上前に、解雇の予告をすること
- 解雇の予告をしない場合は、30日分以上の解雇予告手当(平均賃金)を支払うこと
解雇を通知するタイミングによって、どちらかの対応をしなければならないことを理解しておきましょう。
廃業する際、従業員に補償はあるのか、会社はどのような対応ができるのかなどを知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
廃業したら従業員はどうなる?雇用が守れる選択肢であるM&Aについても解説
会社をたたむ手続きと手順
会社をたたむためには、以下の7つの手続きを行わなければなりません。
-
- 会社をたたむ準備
- 株主総会での決議
- 会社の解散と清算人の登記
- 会社解散の届けと手続き
- 解散の公告
- 解散時の決算書類作成・確定申告
- 決算報告書の作成・株主総会での承認
7つの手続きを手順ごとに紹介していくので、スムーズに会社をたたむために参考にしてください。
1.会社をたたむ準備
会社をたたむ前には、以下のような準備が必要です。
-
- 従業員や取引先、金融機関に対する説明説明
- 買掛金・未払金・借入金・従業員への給料の支払い
- 生命保険・損害保険、各種契約の解約
- 売掛金・未収金・貸付金等の回収
事業を終了したとしても、会社の解散や精算といった法律上の手続きを行う必要があります。
法律上の手続きは完了するまでに多くの時間を要するので、営業日数に余裕がある時期から前もって準備を進めましょう。
2.株主総会での決議
会社をたたむためには、株主総会での解散決議が必要です。
会社の解散とは事業を停止することであり、解散決議を行うためには以下の条件を満たさなければなりません。
-
- 発行済株式の過半数以上の株主が出席
- 3分の2以上の賛成
これらの条件を満たした場合により、解散決議が行われます。
また、株主総会では会社をたたむ手続きを進める清算人の選任をしましょう。
3.会社の解散と清算人の登記
株主総会で決議された会社の解散と清算人の選任は、登記が必要です。
登記は会社の所在地を管轄する法務局にて、株主総会で決議されてから2週間以内に行わなければなりません。
解散と清算人は別々でも登記できますが、「解散及び清算人選任登記」としてまとめて行うのが一般的です。
4.会社解散の届けと手続き
登記を行えば法律上は会社の解散が成立したことになります。
しかし、会社をたたむための手続きは残っており、以下のような対応が必要です。
| 提出先 | 手続き内容 |
| 税務署 | ・異動届出書(法人税) ・事業廃止届出書(消費税) ・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(源泉所得税) ・青色申告の取りやめの届出書 など |
| 法人の住民税・事業税を管轄している行政機関 | 異動届出書 |
| 年金事務所 | ・健康保険・厚生年金保険適用事業書 ・被保険者資格喪失届 など |
| ハローワーク | ・雇用保険適用事業所廃止届 ・雇用保険被保険者資格喪失届 ・雇用保険被保険者離職証明書 など |
| 労働基準監督署 | ・確定保険料申告書 ・労働保険料還付請求書 など |
手続きごとに以下のような期限が定められているため、余裕を持って対応しましょう。
-
- 社会保険:解散登記から5日以内
- 雇用保険:事業廃止日または退職日から10日以内
- 労災保険:事業廃止から50日以内
5.解散の公告
各所への手続きが完了したら、会社の解散を国が発行する官報に掲載して公告しましょう。
債権を持っている人がいる場合、知らないうちに会社が解散してしまい、取り立てができなくなることを防ぐために行わなければなりません。
会社の解散時は、債権の申し出期間として公告から2ヶ月以上経たなければ次の手続きができないため注意しましょう。
6.解散時の決算書類作成・確定申告
解散時には会社の財産を把握し分配や納税を行うために、財産目録と貸借対照表を作成して確定申告を行います。
具体的な手続きと内容は以下の通りです。
| 手続きの種類 | 内容 |
| 会社解散・清算の確定申告 | 解散事業年度及び清算事業年度の各末日の翌日から2ヶ月以内に確定申告を行う |
| 債権回収・債務弁済 | 会社資産を売却て債権回収を行い、債権者へ弁済を行う |
| 残余財産の確定・分配 | 弁済後に資産が残った場合、株主に分配する |
すべての債務を弁済できない場合は、解散手続きから倒産手続きに切り替えなけらばならず、手続きに必要な期間が伸びてしまうため注意しましょう。
7.決算報告書の作成・株主総会での承認
清算人は清算結了決算報告を作成して、株主総会にて承認をもらわなければなりません。
株主総会にて承認をもらったら、以下の3つの手続きを進めます。
| 手続きの種類 | 内容 |
| 清算結了登記 | 承認から2週間以内に管轄の法務局で清算結了登記を行う |
| 残余財産の確定申告 | 残余財産が確定した日の翌日から1ヶ月以内に、残余財産確定事業年度の確定申告を行う |
| 清算結了届 | 清算結了登記後の謄本と清算結了届を管轄の税務署に提出する |
これらの手続きで会社解散が完了し、法人格が消滅します。
会社をたたむために必要な費用
会社をたたむためには、以下のような費用が発生します。
| 費用名 | 金額 |
| 解散登記 | 30,000円 |
| 清算人選任登記 | 9,000円 |
| 清算結了登記 | 2,000円 |
| 官報公告掲載 | 35,000円(10行分) |
これらは全社共通のものであり、会社の状況によっては追加費用が発生します。
たとえば、従業員の給与や退職金、設備処分、事務所の原状復帰費用が発生する企業もあります。
加えて、手続きを弁護士や税理士などに依頼するには、さらに費用が必要となることを理解し資産を残しておきましょう。
会社をたたむために必要な書類
会社をたたむ際には、さまざまな書類が必要です。
株主総会の決議から2週間以内に登記を行う際に必要な書類は以下の通りです。
| 書類名 | 概要 | 理由 |
| 株主総会議事録 | 株主総会での議決の内容を記載したもの | 株主総会が成立する条件を満たしていたかを確認する |
| 定款 | 会社の根本的な規則を定めるもの | 清算人会を設置することについて定款に規定があるか確認するため |
| 清算人の就任承諾書 | 選任された人が清算人に就任する意思があることを確認するもの | 就任の意思を確認するため |
手続きが進み清算結了登記を行う際には、以下のような書類が必要となります。
-
- 株主総会議事録
- 決算報告書
- 株主名簿
本章にて紹介した書類が足りない場合、手続きが滞ってしまい会社をたたむために必要な期間が伸びてしまうので、忘れずに用意しておきましょう。
会社をたたむ以外の3つの選択肢
会社をたたまず、残す方法には以下の3つがあります。
-
- 休眠会社にする
- 事業再生を行う
- M&Aを検討する
会社をたたまない方法がないか探している方は、参考にしながら自社に適した方法を実践してみてはいかがでしょうか。
1.休眠会社にする
一時的な理由で会社の存続が難しくなり会社をたたもうと考えている場合は、休眠会社にする方法があります。
たとえば、一時的に取引が止まっており数ヶ月待てば経営が回復するが、現状は経営が困難であるといった企業は休眠会社にする方法が適しています。
税務署をはじめとした行政機関に届出書を提出するだけで休眠会社にできるので、少しの期間があれば経営が回復する場合には休眠させましょう。
ただし、長期間放置するとみなし解散とされてしまい、結果として会社をたたむことになる点には注意が必要です。
2.事業再生を行う
会社をたたまずに残したいと考えている方は、事業再生という選択肢がおすすめです。
事業再生には以下の2つがあります。
-
- 自主再建:自らの経営努力のみで再建を目指す
- スポンサー支援による再建:第三者から資金等の支援を受けて再建を目指す
中小企業の場合は、大株主が経営者であることが多いため、自主再建を選択して債務免除や弁済のリスケジュールを行います。
自主再建が難しい場合は、スポンサー支援を受ける方法を選択しましょう。
経営状況によっては廃業を避けられるので、事業を残したい方は事業再生を検討してみてはいかがでしょうか。
3.M&Aを検討する
後継者問題や人材難に悩んでいる場合には、M&Aがおすすめです。
M&Aを行えば従業員を解雇する必要がなくなり、職場を提供し続けられます。
M&Aでは、特別な技術やブランド力だけでなく、顧客・取引先とのネットワーク、従業員数なども企業価値となります。
後継者が見つからずに廃業を検討している場合は、M&Aを検討して事業が存続できる道を選んでみましょう。
会社をたたむ以外の選択肢も考慮して存続できる道も探ろう
会社をたたむとは、事業を辞めさまざまな手続きを経て法人格を消滅させることです。
手続きには多くの時間やコストが必要であり、状況によっては途中で倒産手続きへ切り替えなければならない場合もあります。
また、従業員を解雇しなければならないため、会社をたたむ前に他の選択肢も検討してみることをおすすめします。
従業員を守りながら事業を残したい方におすすめの手法はM&Aなので、まずは専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
当社が運営する「TSUNAGU」では、M&Aの戦略や手法の提案、パートナーの選定などを無料で実施しているので、お気軽にご相談ください。
Description
会社をたたもうと考えている方の中には、たたむ方法や手順がわからない方もいるでしょう。本記事では、たたむ際に従業員がどうなるかやたたむ手順、他の選択肢などを紹介します。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。