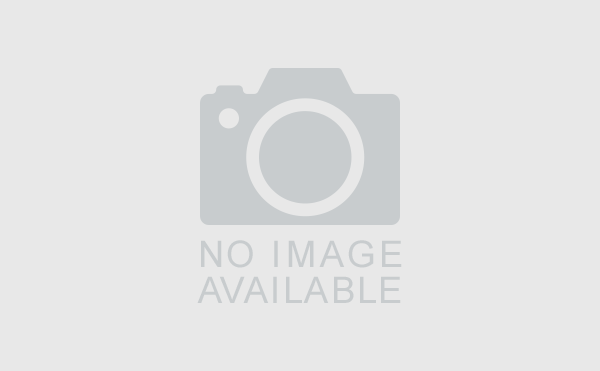M&Aのメリット・デメリット|手法別の強み・弱点や事例も解説

M&Aという方法は理解しているものの、実施を検討するうえでメリット・デメリットを理解したいと考える方もいるのではないでしょうか。
M&Aには、後継者不足の解消や新規事業の展開などのメリットがある一方で、経営統合プロセス構築の労力や従業員離職の可能性といったデメリットもあります。メリット・デメリットは買手と売手でも変わるため、正しい理解が必要です。
本記事では、M&Aによるメリット・デメリットを買手と売手に分けて解説します。手法別のメリットも解説するため、あわせて参考にしてください。
目次
M&Aによる買手・譲受企業側のメリット・デメリット
M&Aには、メリットだけではなく、デメリットもあります。メリット・デメリットは買手と売手で異なるため、自社の立場にあわせた理解が必要です。
まずは、買手・譲受企業のメリット・デメリットを解説します。
| メリット | デメリット |
| ・事業規模やマーケットシェアを拡大できる ・新規事業を展開し多角化を実現できる ・グローバルな事業展開のきっかけになる ・シナジー効果(同業他社の吸収による規模拡大)を期待できる ・時代や環境の変化に対応できる | ・シナジー効果を得るためには時間がかかる ・経営統合や組織再編で混乱を招くケースがある ・従業員が離職するおそれがある ・簿外債務が発生する可能性がある ・のれん(超過収益力)が減損するおそれがある |
メリットから一つひとつ詳しくチェックしていきましょう。
メリット
M&Aにおける買手・譲受企業のメリットは、以下の5つです。
-
- 事業規模やマーケットシェアを拡大できる
- 新規事業を展開し多角化を実現できる
- グローバルな事業展開のきっかけになる
- シナジー効果(同業他社の吸収による規模拡大)を期待できる
- 時代や環境の変化に対応できる
事業の拡大や多角的な展開など、企業の成長につながる可能性を秘めています。
事業規模やマーケットシェアを拡大できる
M&Aによって、売手が持つ顧客や取引先などの資産を自社に加えられるため、事業規模やマーケットシェアの拡大を期待できます。
自社での関連が密接な同業他社をM&Aした場合には、売手が持つ資産を活用しやすく、事業を大きく拡大することも可能です。
これまでよりも多くの顧客に商品を届けられたり、商品の質が向上したりすることで、競合他社との差別化をより強化できるでしょう。
新規事業を展開し多角化を実現できる
自社で新規事業を立ち上げるためには、膨大なコストや時間がかかりますが、M&Aを活用すればスピーディーな事業展開を実現できます。
自社ではじめたいと考えていた事業をすでに実施している企業をM&Aすれば、立ち上げに時間をかけず、すばやく自社の新事業としてスタートできるのがメリットです。
自社の既存事業に売手の事業が加わることで、事業の多角化もかなえられます。異なる市場に参入して売上の最大化を目指せるだけではなく、特定の事業がダメージを受けたときのリスクヘッジにも効果的です。
グローバルな事業展開のきっかけになる
国内企業が海外に進出する事例が徐々に増えてきていますが、グローバル展開は簡単ではありません。現地での拠点や人材の確保、各種手続きなどが必要になり、コストや時間がかかりますが、M&Aを活用すれば海外進出を実現しやすくなります。
国内企業から海外企業へのM&Aを「IN-OUT」と呼び、海外企業の買収によって拠点や人材などの壁をクリアできます。すでに現地でのブランド力や信用を備えているため、スムーズなグローバル展開をかなえられるでしょう。
IN-OUTの事例は、年々件数が増加しています。グローバル展開のきっかけとしてM&Aを活用する事例が増えているため、ぜひ検討してみてください。
M&Aの現状は以下の記事で詳しく解説しているため、詳しく知りたい方はあわせてチェックしてみましょう。
内部リンク:M&A 現状
シナジー効果(同業他社の吸収による規模拡大)を期待できる
シナジー効果とは、複数の強みが相互に作用することで生まれる効果のことで、M&Aでは買手と売手の相乗効果を期待できます。
たとえば、A社がある製品に対する高度な技術を持ち、B社が設備や人材などのリソースが充実しているならば、M&Aによって技術を最大限に発揮できる体制を構築できるでしょう。
互いの弱みを補完するだけではなく、関連する事業の統合によるシナジーも期待できます。生産プロセスや物流などを統合すると、生産から物流までをワンストップで行えるようになり、サービスの質向上やコスト削減などを実現できるでしょう。
時代や環境の変化に対応できる
企業は、時代や環境の変化に柔軟に対応し、ニーズにあったサービスを提供することが重要です。しかし、目まぐるしい変化に自社だけで対応することは難しく、すばやくニーズに応えられないこともあるでしょう。
M&Aは、環境の変化に対応する手法としても効果的です。たとえば、オンラインショッピングの需要が増したときに、すでに通販事業に取り組んでいる企業をM&Aすれば、消費者のニーズに対応した事業を展開できます。
すでに事業ができあがっているため、立ち上げや成長にかかる時間を短縮しやすく、スピーディーに顧客を獲得できるでしょう。
デメリット
M&Aにおける買手・譲受企業のデメリットは、以下の通りです。
-
- シナジー効果を得るためには時間がかかる
- 経営統合や組織再編で混乱を招くケースがある
- 従業員が離職するおそれがある
- 簿外債務が発生する可能性がある
- のれん(超過収益力)が減損するおそれがある
売手の買収や吸収などに伴って、労力やコストが発生する場合があるため、あらかじめ対策が必要です。
シナジー効果を得るためには時間がかかる
M&Aによって売手の資産を受け継ぐことでシナジー効果を期待できますが、実際に効果が現れるまでには時間が必要です。
当初期待していた効果が出なかったり、事業が増えたことでコストが増えたりするなど、思うようにシナジー効果が現れないこともあります。
売手候補の規模や事業などを慎重に見極めたうえで、M&A後に成長させるための準備が必要です。新事業を拡大するためのリソースを確保し、シナジー効果を最大限に得られるように取り組みましょう。
経営統合や組織再編で混乱を招くケースがある
M&Aでは、成立後に売手との統合を図る必要がありますが、経営統合や組織再編のタイミングで混乱が生じるケースがあります。
経営理念の統合や人材配置などがうまくいかなかったり、急な統合で従業員に迷惑がかかったりすると、企業全体の士気が落ちてしまうでしょう。
統合プロセスの混乱を最小限に抑えるためには、計画的な統合が欠かせません。事前に統合に関する計画を綿密に立て、周囲の反応を注視しながら、着実に統合を進めましょう。
従業員が離職するおそれがある
M&Aでは、売手から従業員の雇用を条件として提示される場合が多く、買手の就業規則や労働条件にもとづいて雇用するのが一般的です。
売手の従業員にとっては働く環境や条件が変わるため、求めている条件にとマッチしなかったり、企業風土になじめなかったりしたときに、離職するおそれがあります。
離職が起きない場合でも、慣れない環境での仕事に苦戦し、モチベーションが低下することもあるでしょう。できるだけ労働環境の整備に力を入れたり、統合当初は売手のキーパーソンを継続して配置したりするなど、従業員にも配慮してM&Aを進めるのがポイントです。
簿外債務が発生する可能性がある
簿外債務とは、帳簿に記載されていない債務のことで、未払いの給与や退職給付引当金などが該当します。M&Aの手法によっては、成立後に想定していないコストが発生する可能性がある点に注意が必要です。
また、将来的に企業への影響を与えるおそれがある偶発債務が見つかるケースもあります。たとえば、関係性が悪化している取引先を抱えていた場合、トラブルが発生して訴訟に発展する可能性はゼロではありません。
簿外債務や偶発債務を避けるためには、M&A成立前のデューデリジェンスが重要です。抱えている債務を明らかにしたうえで、最終契約の締結を検討しましょう。
のれん(超過収益力)が減損するおそれがある
のれんとは貸借対照表の勘定項目のひとつであり、超過収益力と呼ばれることもあります。売手の純資産と実際の買収価格の差額であり、減価償却によって経費として計上すれば、節税効果を期待できます。
ただし、想定していたのれんに対して収益が期待よりも出なかった場合には、見込みの数値との差額が損失となり、財務上経営状態が悪化したように見える点に注意が必要です。
当初の計画とは別にお金が出ていくことはなく、財務諸表を見れば理由がわかるものの、のれんが大きくなるほど経営に不安をもたれるリスクがあります。のれんの影響を少なくするため、適正な買収金額を算出し、減損処理をできるだけ抑えることが大切です。
M&Aによる売手・譲渡企業側のメリット・デメリット
M&Aにおいて、売手・譲渡企業側は事業承継や創業者利益などメリットに目が向きがちですが、デメリットにも注意しなくてはいけません。
売手・譲渡企業側のメリット・デメリットは、以下の通りです。
| メリット | デメリット |
| ・買手・譲受企業の信用を活用できる ・後継者問題を解決できる ・従業員の雇用を確保できる ・事業の発展・拡大を期待できる ・創業者利益・キャピタルゲインを得られ | ・買手が見つからない場合がある ・想定した価値がつかないおそれがある ・柔軟な経営や事業展開が難しくなる ・従業員や取引先に影響を与えるケースがある |
デメリットへの対策を実施したうえで、メリットを最大限に得られるようにM&Aを進めましょう。
メリット
M&Aにおける売手・譲渡企業側のメリットは、以下の5つです。
-
- 買手・譲受企業の信用を活用できる
- 後継者問題を解決できる
- 従業員の雇用を確保できる
- 事業の発展・拡大を期待できる
- 創業者利益・キャピタルゲインを得られる
経営課題の解決を期待できるため、課題を感じている場合は前向きにM&Aを検討しましょう。
買手・譲受企業の信用を活用できる
自社よりも知名度やブランド力がある買手にM&Aを実施した場合、売手の信用力が強化されるのがメリットです。
買手のネームバリューがプラスに働けば、取引先が増えたり、商品の認知度が高まったりするなど、さまざまな恩恵を受けられます。
他社には強みがあるものの、ブランド力や信用が不足している場合には、M&Aのシナジーによって大きく成長できる可能性があるでしょう。
後継者問題を解決できる
M&Aは、親族や役員などから後継者を見つけられない場合に、会社を引き継ぐ方法として効果的です。
後継者が見つからないものの「従業員や取引先に迷惑をかけたくない」「技術やノウハウを失いたくない」といった思いから、廃業を決断できない会社もあります。
M&Aでは、買手と条件面でマッチングできれば、第三者への事業承継が可能です。自社の技術やノウハウを受け継ぎながら、従業員や取引先を守れる点で、後継者の不在に悩む企業を救う方法といえるでしょう。
従業員の雇用を確保できる
M&Aでは、売手の従業員を買手が受け入れることを条件に含められるため、苦楽をともにした従業員の雇用を確保できます。
廃業を選択すると、従業員は路頭に迷うおそれがありますが、M&Aで雇用を取りつけられれば、新たな環境で働き続けられるのがメリットです。買手の労働環境や待遇によっては好条件での雇用も期待でき、これまでの頑張りへの恩返しにもなるでしょう。
会社にかかわる人への影響としては、取引先も見逃せません。取引先との関係をM&Aで買手で引き継ぐことができれば、取引先の収益を維持しながら、事業を承継できます。
事業の発展・拡大を期待できる
M&Aによる買収や提携で買手の強みを活用できるようになり、自社の強みとのシナジーによって事業の発展・拡大を期待できます。
買手の資本やインフラを活用したり、ネットワークを活用して販路を拡大したりできれば、より精力的に事業を展開できるでしょう。事業が大きくなり、マーケットシェアを拡大できれば、市場での激しい競争にも立ち向かえるようになります。
また、不採算事業を譲渡し、コア事業に注力することも可能です。自社では成果が出ていないものの、可能性を見出している企業に売却できれば、不採算事業に充てていたコストやリソースを配分できます。コア事業への集中によって、経営の効率化や業績向上を実現できるでしょう。
創業者利益・キャピタルゲインを得られる
M&Aによって会社を売却すると、経営者は譲渡に伴う金銭を現金や株式などの形で得られます。会社の売却で得た資金で新たな事業をはじめたり、セカンドライフの資産を確保したりするなどの利益を得られるのがメリットです。
経営を離れる方法には廃業もありますが、従業員への保証や設備の処分費用など資金が必要になります。M&Aで手元に現金や株式が残れば、廃業に伴うコストに充てられるでしょう。
金銭的なメリットだけではなく、経営者の体力面や精神面にもゆとりが生まれます。年齢を重ねる中で体調不良が起きていたり、責任にプレッシャーを感じていたりする場合に、M&Aで会社を手放すことで、経営者の責務から解放され、負担が軽くなるでしょう。
デメリット
M&Aにおける売手・譲渡企業側のデメリットは、以下の通りです。
-
- 買手が見つからない場合がある
- 想定した価値がつかないおそれがある
- 柔軟な経営や事業展開が難しくなる
- 従業員や取引先に影響を与えるケースがある
メリットに注目しすぎず、デメリットも把握したうえで、課題解決につながるM&Aを目指しましょう。
買手が見つからない場合がある
売手は、自社の買手を探す必要がありますが、最適な相手先が見つからない場合もあります。
自社との関連性が高いが雇用面に不安がある、雇用面は期待できるがシナジーをあまり見込めないなど、条件がマッチせず買手探しが難航するケースもあるでしょう。条件でマッチしても、買収金額の提示が低く、M&Aのメリットを得にくい場合も考えられます。
とくに、簿外債務や偶発債務を抱えている場合にはマッチングが難しくなるため、あらかじめ自社の課題を解決しなければなりません。
M&Aにおいてマイナスになりうる部分を解消したうえで、専門家やプラットフォームなどを活用して、自社にあった買手を見つけましょう。
想定した価値がつかないおそれがある
M&Aにおいて、買収価格を決めるために企業価値を見極めますが、想定よりも価値が低く見積もられるケースがあります。
企業価値の評価は将来性を重視するため、現在利益が高くても将来的に下がると見込まれた場合には、価値が低くなりやすいです。
事前に見積もっていた価値がつかない場合には、事業のブラッシュアップや財務状況の改善などを図り、将来性をアピールできる状態を目指しましょう。
柔軟な経営や事業展開が難しくなる
売手は買手の傘下に入ったり吸収されたりするため、会社を手放さずに経営にかかわりたい場合はM&A前よりも経営に関する権限が小さくなります。経営方針や予算配分などは買手に従う必要があるため、自社が思う経営や事業展開が難しくなる点に注意が必要です。
M&Aは買手と売手が対等な立場で進められますが、実際には売手は立場が弱くなる傾向があります。経営権を大きく残すことは難しいですが、少しでも影響力を維持したい場合は、M&Aの交渉段階で妥協点を探るとよいでしょう。
従業員や取引先に影響を与えるケースがある
売手はM&Aによって従業員の雇用確保や取引先との関係維持を期待できますが、買手の経営判断によっては影響を受けるケースがあります。
従業員は新しい環境や条件のもと働くことになるため、うまくなじめない人材が離職するかもしれません。一定数の離職は予想されますが、できるだけ多くの従業員がなじめる環境や制度の構築が必要です。
取引先との関係は、買手の経営判断の影響を受けやすく、条件の見直しや取引の停止などが起きる場合があります。買手に判断を一任すると、既存の取引先とのトラブルや反発が起きやすくなるため、関係を構築してきた担当者が間に入って調整を行うとよいでしょう。
M&Aにおける手法(スキーム)別のメリット・デメリット
M&Aと一口にいっても、買手と売手が提携する手法はさまざまです。採用する手法によってメリット・デメリットが異なるため、自社の目的にあった方法を選びましょう。
M&Aにおける手法は、株式の移動の有無を基準に、資本提携と業務提携に分けられます。資本提携は株式の移動によって相手先と提携関係を築く方法、業務提携は株式の移動を伴わず業務面のみ提携を行う方法です。
資本提携と業務提携のメリット・デメリットは、以下のとおりです。
| メリット | デメリット | |
| 資本提携 | ・資本金の増加で財政基盤を強化できる ・リスクを抑えて相手先の資本を活用できる | ・買手は売手の経営介入を受けやすくなる ・売手は自社の裁量で経営しにくくなる |
| 業務提携 | ・コストを抑えて経営資源を共有できる ・相手先の強みを経営や事業に生かせる | ・相手先に技術やノウハウが流出するおそれがある ・資本や株式による拘束力がなく、関係性が解消される場合がある |
資本提携は、相手先とどのように提携するかによって、手法が異なります。主な手法のメリット・デメリットは、以下のとおりです。
| メリット | デメリット | |
| 買収 | ・買収によって売上規模やシェアを拡大できる ・相手先の事業を加えて、多角化を実現できる | ・統合作業に手間や時間がかかる ・簿外債務や偶発債務を引き継ぐリスクがある |
| 合併 | ・相手先の事業を継承し、新規分野に参入できる ・相手先の技術やノウハウを活用し、既存事業を強化できる ・対価を株式に設定することで、買手は資金調達の必要がない | ・統合作業に手間や時間がかかる ・簿外債務や偶発債務を引き継ぐリスクがある ・合併比率によっては株価が下落する |
| 合弁会社設立 | ・共同出資によってコストやリスクを分散できる ・参加する企業の強みで相乗効果を期待できる | ・複数の会社がかかわることで意思決定に時間がかかる ・技術やノウハウが流出するおそれがある |
| 資本参加 | ・相手企業との関係性を強化できる ・経営参加で新たなビジネスチャンスを見出せる | ・関係性によっては契約が打ち切りになる場合がある |
M&Aを行う手法によって、相手先との関係性やコストなどに違いがあります。どの手法にもメリット・デメリットが多くあるため、自社の目的と照らし合わせながら、手法を一つひとつ比較・検討することが大切です。
M&Aの成功事例3選
最後に、M&Aの成功事例を3つ紹介します。
-
- ソニーによるインソムニアックゲームズの買収
- リクルートによるグラスドアの譲り受け
- パナソニックによるブルーヨンダーの買収
ソニーによるインソムニアックゲームズの買収
2019年、ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、米国カリフォルニア州を拠点とするゲーム開発スタジオ「インソムニアックゲームズ」を買収しました。このスタジオは「スパイダーマン」や「ラチェット&クランク」シリーズなどの人気タイトルを手掛け、長年ソニーの「プレイステーション」向けに多くのヒット作を開発してきました。
この買収によって、ソニーはゲーム開発力を強化し、特にプレイステーション向けの独占タイトルを増やすことで、競争力を高める狙いがありました。
インソムニアックゲームズは1994年に設立され、プレイステーションの黎明期から協力関係を築いてきました。同社は「スパイロ・ザ・ドラゴン」や「ラチェット&クランク」などの人気シリーズを開発し、その革新的なゲームプレイとキャラクター作りで高い評価を得ていました。これにより、インソムニアックはソニーにとって重要なパートナーとなり、長期的な協力関係が続いていました。
買収後もインソムニアックゲームズは独自のクリエイティブな自由を保ちつつ、ソニーの完全子会社としてプレイステーション向けの独占タイトルを開発し続けています。
2020年には「Marvel’s Spider-Man: Miles Morales」や「ラチェット&クランク: リフトアパート」をPS5向けにリリースし、これらは高い評価を受けました。
この買収は、ソニーが競合他社(Microsoftや任天堂など)に対抗するための戦略の一環であり、プレイステーションプラットフォームの魅力を強化するための重要な手段となりました。
引用元:https://www.nikkan.co.jp/articles/view/528004
リクルートによるグラスドアの譲り受け
2018年、リクルートホールディングスは、米国に拠点を置く求人情報プラットフォーム「グラスドア(Glassdoor)」を12億ドルで買収しました。
グラスドアは、求職者向けに企業のレビュー、給与情報、面接の経験談などを提供しており、企業の内部情報を求職者に公開することで、求職の透明性を高めるというユニークなサービスを展開しています。このプラットフォームは、企業選びにおける情報格差を埋め、求職者がより良い判断を下すための重要な役割を果たしています。
リクルートによるこの買収は、同社がグローバルな求人市場でのプレゼンスをさらに強化するための大きなステップとなりました。リクルートは既に、世界的な求人検索エンジン「Indeed」を保有しており、Indeedは求職者と企業をマッチングするプラットフォームとして圧倒的なシェアを誇っています。
グラスドアの買収により、リクルートは従来の求人情報に加え、企業の評判や労働条件に関する透明性の高い情報も提供できるようになり、求職者がより詳細なデータに基づいて企業を選択できる環境を整えることに成功しました。
この買収は、リクルートの戦略的なグローバル展開の一環であり、特に北米市場での影響力を強化する狙いがありました。グラスドアは米国をはじめとする多くの国で強いブランド力を持っており、世界中で数千万のユーザーが利用しています。
リクルートは、Indeedとのシナジー効果を活かして、求人情報の提供と企業の評判情報の統合を進め、ユーザーにより包括的な就職支援サービスを提供することが可能となりました。
引用元:https://recruit-holdings.com/ja/newsroom/20180509_8170/
パナソニックによるブルーヨンダーの買収
2021年、パナソニックは米国に本社を置くサプライチェーン管理ソフトウェア企業「ブルーヨンダー(Blue Yonder)」を約7100億円(約65億ドル)で完全買収しました。
この取引は、パナソニックの近年の成長戦略において重要なステップとされており、特にサプライチェーンのデジタル化と効率化に向けた取り組みの一環として位置づけられています。
ブルーヨンダーは、AI(人工知能)や機械学習の技術を駆使して、需要予測や在庫管理、物流最適化を支援するソリューションを提供しており、グローバルな製造業や小売業におけるサプライチェーンの効率化を支援してきました。
この買収は、パナソニックがブルーヨンダーの株式の2割を取得した2020年の提携を拡大し、残りの株式を取得して完全子会社化したものでした。
パナソニックは、これによりサプライチェーンのデジタル化を加速し、物流、製造、流通業務の効率向上を図ることを目指しました。特に、ブルーヨンダーの強力なAIベースの予測分析技術を取り入れることで、リアルタイムでの在庫管理や需要予測の精度向上が期待され、サプライチェーン全体の柔軟性と効率性を高めることができます。
パナソニックは、ブルーヨンダーの買収により、サプライチェーン・ロジスティクス分野での市場リーダーとしての地位を確立し、製造業から小売業に至る幅広い業界におけるソリューション提供を強化しています。
引用元:https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/02044/042700003/
M&Aのメリット・デメリットを正しく理解しよう
M&Aにはメリット・デメリットがあり、買手・売手によって異なります。買手にとっては事業拡大や多角化などを期待できる一方で、経営統合の手間や簿外債務のリスクなどに気をつけなければいけません。
売手には、後継者問題の解決や従業員の雇用確保などを実現できますが、買手探しや自社の評価に気を配る必要があります。
M&Aで採用する手法によってもメリット・デメリットは異なるため、自社の目的にあった方法を選びましょう。
「TSUNAGU」では、着手金無料・成果報酬のみで事業承継型M&Aを支援しています。多くの買手リストから最適な買手を提案し、最短3ヶ月で成立できるのが強みです。ご相談は無料ですので、詳しくサービスを知りたい方は気軽にお問い合わせください。
【メタディスクリプション】
本記事では、M&Aのメリット・デメリットを買手・譲受側と売手・譲渡側に分けて詳しく解説します。手法別のメリット・デメリットと事例も紹介するため、あわせて参考にしてください。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。