経営不振とは?主な原因や具体的な対策方法について解説
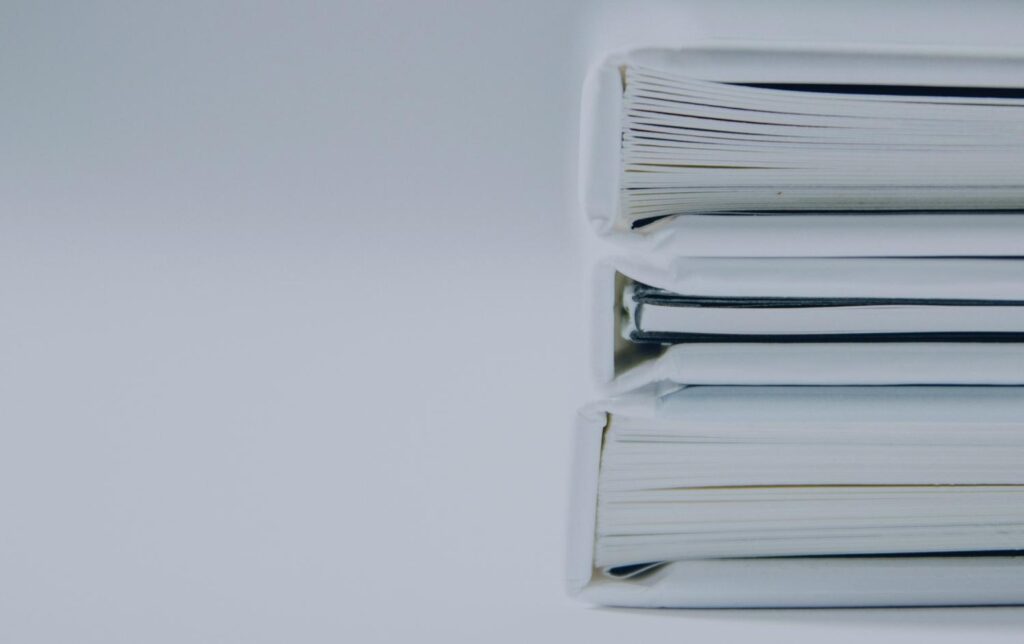
経営不振の原因は多岐にわたります。
- 市場環境の変化
- 内部管理の問題
- 技術革新の遅れ
- 人材の流出
など、企業が直面する複雑な課題です。
経営不振の状態は、ただ単に数字が減っている状態ではありません。従業員や顧客、そして経営者自身の将来に対する不安が蓄積された状態を意味しています。
本記事は、コスト削減から事業の再構築、財務の見直しに至るまで、経営不振から抜け出すための実用的なアドバイスが満載です。
具体的な内容としては、
- 経営不振の主な原因
- 経営不振から抜け出すための対策
- 経営不振によって解雇を検討する場合の注意点
- 経営不振が続くとどうなるのか?
などをわかりやすく解説します。
経営不振とは
経営不振とは、企業が本来の目的である利益を上げられなくなり、事業継続が困難な状態を指します。売上減少やコスト増加、資金繰りの悪化などが主な原因です。
2023年の月別倒産件数と負債総額を以下の表にまとめています。
【月別倒産件数と負債総額】
| 2023年 | 倒産件数 | 前年比 | 負債総額(単位:億円) | 前年比 |
| 1月 | 570 | 26.1 | 565 | ▲15.6 |
| 2月 | 577 | 25.7 | 966 | 36.0 |
| 3月 | 809 | 36.4 | 1,474 | ▲ 13.1 |
| 4月 | 610 | 25.5 | 2,039 | 150.9 |
| 5月 | 706 | 34.7 | 2,787 | 219.0 |
| 6月 | 770 | 41.0 | 1,509 | ▲87.7 |
| 7月 | 758 | 53.4 | 1,621 | 91.7 |
| 8月 | 760 | 54.4 | 1,083 | ▲2.73 |
| 9月 | 720 | 20.2 | 6,919 | 377.6 |
| 10月 | 793 | 33.0 | 3,080 | 254.0 |
| 11月 | 807 | 38.8 | 948 | ▲17.9 |
| 12月 | 810 | 33.6 | 1,032 | 30.3 |
出典:中小企業庁「倒産の状況」、帝国データバンク「飲食店倒産動向調査(2023年)」
企業の倒産数は31年ぶりの高水準に
2023年の倒産件数は8,690件に上り、前年の6,428件から大幅に増加しました。増加率35,18%は、バブル崩壊後で最も高い数字です。
新型コロナウイルス感染症の影響で、消費者が実店舗を訪れる機会が減少したため、売上が大きく落ち込みました。
また、倒産数は全業種で前年度を上回る結果に。「サービス業他」が41.68%増、「小売業」が30.77%増となり、中でも特徴的なのは「飲食店」で、2023年度の倒産件数は768件を記録しました。
不況型倒産は2000年以降で、初めて前年度から3割以上増加しました。また、いわゆるゼロゼロ(コロナ)融資後倒産は、2020年以降で最多を記録しています。
出典:東京商工リサーチ
出典:帝国データバンク
経営不振の主な原因
経営不振は、さまざまな原因が複雑に絡み合って発生します。経営者は常に経営状況を把握し、問題発生時の迅速な対応が不可欠です。
この章では、
- 販売不振
- 外的要因による影響
- 風評被害
- 資金繰りの悪化
- コスト増による利益率の低下
- 取引先の業績悪化
- 過剰な投資
- 人手不足
- 放漫経営
について詳しく解説します。
販売不振
販売不振は、経営不振の主な原因の一つです。販売不振は売上高が減少し、利益が出づらい状態を指します。
販売不振の主な原因は以下のとおりです。
- 競合他社による市場シェアの奪取
- 消費者ニーズの変化
- 大口顧客の喪失
- 取引先の経営不振
帝国データバンクによると、2023年に販売不振で倒産した企業は6,672件です。なかでも、販売不振が中小企業の倒産の理由として78.5%を占め、最も多くなっています。
外的要因による影響
企業の経営不振には、外的要因も深く関わっています。外的要因は、企業の内部管理や努力だけでは対応が難しく、経営戦略の見直しや柔軟な対応が必要です。
主な外的要因としては以下の4点が挙げられます。
1. 新型コロナウイルス感染症の影響
2020年以降、世界的なパンデミックとなった新型コロナウイルス感染症は、経済活動に大きな打撃を与えました。
特に、飲食業・宿泊業・旅行業などのサービス業を中心に、売上減少や顧客離れが深刻化しています。
2. 原材料価格の高騰
2022年以降、エネルギー価格や食料品価格が世界的に高騰し、ウクライナ情勢の悪化や円安の影響などが重なり、企業の収益を圧迫しています。
中小企業を中心にコスト吸収が困難となり、経営破綻に繋がるケースが増加中です。
3. 円安の影響
2022年以降、円安による輸入物価の高騰は、企業の収益を圧迫しています。
エネルギーや原材料を輸入に頼っている企業への打撃は、多大なるものです。
4. ウクライナ情勢の悪化
2022年2月に始まったロシアによるウクライナ侵攻は、世界経済に大きな混乱をもたらしました。エネルギー価格や食料品価格の世界的な上昇が、企業活動を阻害しています。
外的要因への対応には、柔軟な事業戦略の見直しや、リスク管理の強化が必要です。
変化に対応できる組織の構築や、新たな技術や市場への適応も求められるでしょう。
風評被害
風評被害は、
- 従業員の不適切な行動
- 製品の安全性に関する誤解
- 不正確な報道
- 競合他社からの誹謗中傷
など、さまざまな原因によって発生します。
近年ではSNSの普及により、小さな問題が瞬く間に大きな話題となり、企業イメージを大きく損ねるケースも。風評被害は企業にとって無視できない深刻な問題です。
例えば、ある食品企業が、製品の安全性に関する根拠のない噂をSNS上で拡散された結果、売上が大幅に減少した事例があります。
また、従業員が私的なSNSで企業に関する不適切動画を投稿し、それが原因で企業の評判が落ちた事例などもありました。
風評被害による経営不振から回復するためには、まず事実関係を把握し、迅速かつ透明性のある情報提供を心掛ける必要があります。
顧客との積極的なコミュニケーションを通じて信頼回復を目指し、問題が発生した際には、適切な対応体制を整えることが重要です。
資金繰りの悪化
資金繰りの悪化も経営不振の主な原因です。企業の収入と支出のバランスが崩れ、キャッシュフローに余裕がなくなってきた状態を指します。
根本的な原因を解決しない限り、資金繰りの悪化は深刻な問題を引き起こし、収支が黒字であっても倒産するケースは珍しくありません。
企業は、キャッシュフロー管理を強化し、資金繰り問題への迅速な対応が求められます。また、多様な資金調達手段の検討や、将来にわたって持続可能な事業モデルの確立が重要です。
コスト増による利益率の低下
コスト増による利益率の低下は、経営不振に陥る原因です。調達コストの上昇を販売価格に転嫁できない企業は、影響を大きく受けます。
東京商工リサーチによると、調達コストが増加している中、増加分を販売価格に全く転嫁できていない企業は全体の44.2%も存在している状況です。
上昇分を全額転嫁できた企業はわずか5.4%にとどまり、多くの企業がコスト増による利益率の低下に苦しんでいます。
コスト増による利益率の低下は、企業経営を圧迫する重要な問題です。
コスト増による利益率の低下に対処するためには、コスト削減の努力のみならず、価格転嫁の計画を見直し、新たな収益源の確保が求められるでしょう。
取引先の業績悪化
取引先の業績悪化は、企業にとって重大な経営不振のリスクです。
取引先の業績が悪化すると、企業にとって以下のような直接的な影響があります。
- 売掛金の回収遅延または回収不能:取引先の資金繰りが悪化すると支払い遅れや、支払いが行われない可能性があります。
- 受注量の減少:取引先自体の売上が減少すると、発注量が減少します。
取引先の業績悪化は、企業の経営状態に深刻な影響を及ぼす原因です。
取引先の業績悪化に対処するためには、以下の点を押さえておく必要があります。
- 一つの取引先に依存しすぎないこと
- 定期的に取引先の財務状況や業績を把握すること
- リスクが発生する前に適切な対策を講じること
過剰な投資
過剰な投資は、企業財務の健全性を脅かし、経営不振の原因となります。短期の巨額投資で即時の収益を伴わない場合、資金繰りへの影響は避けられません。
過剰な投資が経営不振を引き起こす理由は、以下のとおりです。
- キャッシュフローの圧迫:大規模な投資は、短期的にキャッシュフローを圧迫し、運転資金不足を引き起こす可能性があります。
- 収益性の低下:投資による収益が期待通りに発生しない場合や遅れる場合、資金回収の遅延が財務を圧迫します。
- 市場ニーズの見誤り:市場ニーズやトレンドを見誤り、過剰な設備投資や開発投資をした結果、運転資金不足を招くことがあります。
経営計画を決定する際には、
- 投資規模とタイミング
- 市場の動向
- 財務状況
を考慮し、持続可能な成長を目指しましょう。
人手不足
人手不足は、経営不振に陥る企業が直面する大きな課題です。
マンパワーが必要な業界では、労働力不足が直接的に生産性の低下やサービス品質の悪化を引き起こし、売上の減少につながります。
2023年の帝国データバンクの調査によると、人手不足を理由に事業継続を断念するケースが本格的に増加。人手不足倒産は累計で260件となり、年間ベースで過去最多を更新しました。
特に、建設・物流業界は、人手不足の影響を大きく受けており、人手不足倒産全体の約半数です。
「2024年問題」として知られる時間外労働の上限規制の適用により、人手不足は建設・物流業界において深刻化しています。
企業は人手不足問題に対処するために、
- 働き方改革
- 生産性向上の取り組み
- 外国人労働力の活用
など、さまざまな策を講じる必要があります。
また、業界全体での人材確保や育成に関する取り組みも、長期的な視点で重要となるでしょう。
放漫経営
放漫経営は、企業の利益を減少させ、経営不振に陥る原因です。経営者による適切な管理や監督が欠けている状態が続くと、最終的には倒産に至る可能性があります。
放漫経営の主な特徴は以下のとおりです。
- 予算管理の無計画:財務の無計画や予算管理の甘さが、経費の浪費を招きます。
- 意思決定の不透明性:経営者による一方的な意思決定や情報共有不足が、組織内での混乱やモチベーションの低下を引き起こします。
- 無計画な投資:市場調査やリスク分析を軽視した無計画な投資が、資金の浪費を招き、企業の資金繰りを悪化させます。
経営不振から抜け出すための対策
経営不振から抜け出すためには、
- 根本原因の特定
- 財務状況の改善
- 事業モデルの再構築
- 組織の効率化
が必要です。
経営不振の原因は多岐にわたるため、一律の対策では抜本的な解決が望めません。
- 市場環境の変化
- 内部管理の不備
- 競争の激化
など、企業ごとに状況は異なるためです。
この章では、
- 収益改善ポイントの整理
- 売上高の改善
- 人材育成や外部人材の招致
- 補助金や助成金の活用
- 事業譲渡(M&A)
など、経営不振から抜け出すための対策について詳しく解説します。
収益改善ポイントの整理
収益改善ポイントの整理は、企業が収益性を向上させるための具体的な行動を明確にします。
以下のポイントに注意して、収益改善策を講じましょう。
- 原因の特定:経営不振の原因を明確にし、それに対する具体的な対策を立てる。
- コスト削減:業務委託費用・広告宣伝費・役員報酬・その他固定費などのコストを分析し見直す。
- 売上の向上策:新規顧客獲得や既存顧客のさらなる活用など、売上を増やすための計画を立てる。
- 業務の効率化:業務を見直し、無駄な作業を排除することで、全体の効率を向上させる。
- リスク管理:リスク管理体制を整備し、経営の持続可能性を高める。
重要なのは、一時的な改善に留まらず、持続可能な成長へと繋げる心構えです。
売上高の改善
売上高の改善には、外的要因と内的要因の両面からの分析が重要です。
外的要因には、市場環境の変化や競合の動向、社会情勢の影響などがあります。
内的要因では、商品やサービスの質の問題やマーケティング戦略の不備、顧客ニーズへの対応不足などを分析しましょう。
売上高の改善策としては、以下の点が挙げられます。
- 市場調査
- マーケティング戦略の見直し
- 新規顧客の獲得
- 経費の見直し
- 既存顧客のリピート率向上
- 客単価のアップ
- 商品やサービスの品質向上
- 従業員のモチベーション向上
経営不振から脱却するには、社員全員で売上高の改善に取り組む必要があるでしょう。
人材育成や外部人材の招致
人材育成や外部人材の招致は、新しい視点を取り入れ、企業の革新と成長を促進するための手段として有効です。
会社組織内の人材を育成することで、
- 従業員のスキルアップ
- モチベーション向上
- 組織の競争力強化
が期待できます。
外部人材の招致では専門知識を持つプロ人材を招くことで、新たな視点やアイデアを取り入れられるようになり、結果として組織内の問題解決や新規事業案の具体化をもたらすでしょう。
経営不振からの脱却には、既存の枠組みにとらわれない革新的な方法が必要です。
人材育成による組織内部の能力強化と、外部人材の招致による新しい視点の導入は、経営改善の有効な手段です。
補助金や助成金の活用
補助金や助成金の活用は、経営不振からの脱却において重要です。補助金や助成金の資金サポートを利用することで、財務的な負担を軽減し、経営改善に必要な資金を調達できます。
補助金や助成金は、企業の成長や事業運営における特定の活動を支援するために、
- 国
- 地方公共団体
- 特定の機関(独立行政法人や公益財団法人などの公的な組織)
から提供される返済不要の資金です。
多岐にわたる用途が可能で、一例として
- 新規事業の開発
- 設備投資
- 人材育成
- エネルギー効率改善
などが挙げられます。
特に経営不振に陥っている企業にとっては、外部からの資金援助を活用することで、経営状況を改善し、事業の再構築や市場競争力の強化を図れます。
経営者は、利用可能な補助金や助成金の情報を積極的に収集し、申請条件の理解や書類準備に取り組みましょう。おすすめの情報収集先としては、補助金ポータルがあります。
事業譲渡(M&A)
事業譲渡(M&A)は、経営不振から脱却するための有効な手段です。
企業の成長と持続性を確保するには、不採算事業の切り離しとメイン事業の売却の二つの方法があります。
| 不採算事業の切り離し | 不採算事業は、企業の資金を消費し、利益を圧迫する可能性があります。 事業を切り離すことでより収益性の高い事業に集中し、経営効率の向上を図れるでしょう。 |
| メイン事業の売却 | 企業が繁盛期または衰退期にある場合、メイン事業の売却を検討する価値があります。 売却により大きな資金が得られるため、より競争力のある市場への参入が可能です。 |
事業譲渡(M&A)は経営不振の解決策として、
- 組織再編
- 資本構造の改善
- 新たなビジネスチャンス
など、さまざまな効果が期待できるものです。
事業譲渡を成功させるためには、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 適切なパートナー選定
- 詳細な調査
- 戦略的な交渉
経営不振によって解雇を検討する場合の注意点
経営不振によって解雇を検討する場合、以下の点に注意する必要があります。
・客観的かつ合理性のある解雇理由の設定
解雇が認められるためには、客観的かつ合理性のある解雇理由が必要です。
経営状況の悪化のみでは、解雇理由として認められない可能性があります。
・解雇手続きの適正化
解雇手続きには、解雇予告や解雇手当の支払い、退職金の支払いなど法令で定められた手順があります。
手続きに不備があると、解雇無効となる可能性があるため注意しましょう。
・法令遵守
解雇には、労働契約法や解雇規制法、民法などさまざまな法令が適用されます。
法令に違反すると、損害賠償責任を負う可能性があります。
・従業員への丁寧な説明
解雇は、従業員にとって大きな生活の変化をもたらします。
解雇理由を丁寧に説明し、今後の支援策などを提示しましょう。
経営不振に伴う解雇は、慎重に検討し、法的要件を遵守する必要があります。
経営不振が続くとどうなるのか?
経営不振が続くと、企業に以下のようなさまざまな影響が生じます。
- 資金繰りの悪化
- 信用低下
- 優秀な人材の流出
- 最終的には事業継続の危機
この章では、経営不振が続いた結果引き起こされる以下の点について、詳しく解説します。
- 金融機関からの信用が落ちる
- 優秀人材の退職や取引先との信頼性悪化
- 企業価値が下がる
- 会社が倒産する
金融機関からの信用が落ちる
金融機関からの信用が落ちると、資金調達が困難になり、事業の継続が危ぶまれる可能性があります。返済能力を疑問視されるため、資金繰りの悪化を招く要因となりかねません。
経営不振により売上や利益が減少すると、金融機関は融資のリスクが高まると判断し、既存の融資条件の見直しや新規融資の拒否といった対応を取ります。
信用の低下を防ぐには、経営情報の開示や、金融機関との積極的なコミュニケーションが有効です。
優秀人材の退職や取引先との信頼性悪化
優秀な人材の退職や取引先との信頼性が悪化する原因は、経営不振の長期化です。
経営不振により、給与の支払い遅れや昇給・昇進機会の減少が生じると、従業員のモチベーションが低下し、他の安定した企業へ転職する可能性があります。
また、経営不振が公になると取引先からの信頼を失うこともあるでしょう。新たなビジネスチャンスが減少するだけでなく、既存の取引条件の見直しを迫られる可能性もあります。
経営不振に陥った際は迅速に原因を特定し、従業員のモチベーション維持や取引先との良好な関係維持に努めることが重要です。
企業価値が下がる
経営不振が続くと企業価値が下がり、以下のような影響が出ます。
- 資金調達の困難化
- 株価の下落
- 企業のブランドイメージの損失
- 事業売却時の価格下落
- M&Aの標的になりやすい
経営不振に陥った際は、事業の再構築や財務構造の改善、関係者とのコミュニケーション強化に取り組みましょう。
会社が倒産する
経営不振が長期間にわたって続くと、資金繰りの悪化や信用の低下、最終的には支払い不能に至り、会社が倒産するリスクが高まります。
会社が倒産する主な理由は以下のとおりです。
-
- 資金繰りの悪化:継続的な経営不振により、企業の収益が減少し、資金繰りが悪化します。
- 信用の低下:金融機関や取引先からの信用が低下し、新たな資金調達が困難になります。
- 債務超過:負債が資産を上回り、企業が債務超過の状態に陥ります。
倒産を回避するためには、経営状況を早期に把握し、対策を講じることが重要です。また、金融機関や取引先と積極的なコミュニケーションをとり、信頼回復を図るアクションも求められます。
経営不振の場合はまず専門家に相談しよう
経営不振に直面した際は、問題解決のために早急に、
- 弁護士
- 税理士
- 会計士
- M&Aのコンサルタント
などの専門家に相談することが重要です。
中小企業の経営者は日常的にさまざまな問題に直面しますが、専門家へ相談することによって、問題解決に必要な知見や情報を得られます。
専門家は過去の類似案件に対する経験や専門知識があるため、経営者が見落としている問題点や新たな解決策を提案可能です。
専門家によって、以下のように得意分野は異なります。
- 弁護士:法的な問題や契約の見直し、労働関係の問題に対処できます。
- 税理士や会計士:財務状態の分析や税務の問題に対するアドバイスをし、財務健全性の回復に貢献できます。
- M&Aコンサルタント:企業の買収や合併を通じて、ビジネスを再構築するための戦略的なアドバイスができます。
経営不振を解決するためには、問題の本質を理解し、適切な専門家に相談することが重要です。
企業は専門家に相談することで、経営不振からの脱却に向けた第一歩を踏み出せるでしょう。
まとめ
経営不振は売上高や利益の減少をもたらすため、企業にとって深刻な問題です。一時的な売上減ではなく、持続的な経営悪化になると債務超過や倒産リスクが高まります。
経営不振に陥る主な原因は以下のとおりです。
- 売上高の減少
- 取引先の倒産
- 資金力不足
- 過剰な投資
- 放漫な経営
経営不振から脱却するためには、
- 利益減少への対策
- 売上高向上への取り組み
- 取引先対策
- 経営資金の見直し
- M&Aの検討
など、さまざまな行動が求められます。
具体的には以下の取り組みが有効です。
- コスト削減
- 新規事業への取り組み
- 取引先の多角化
- 資金調達方法の多様化
- 経営統合や事業譲渡
経営不振は、早期に対処することで最悪の事態を避けられます。経営者は、経営不振の兆候を見逃さず、迅速かつ効果的な対策を取るよう心がけましょう。経営不振からの脱却は一朝一夕には達成できないため、継続的な努力と根気が必要です。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。


