事業承継が失敗してしまう理由とは?失敗防止の戦略や成功事例を解説
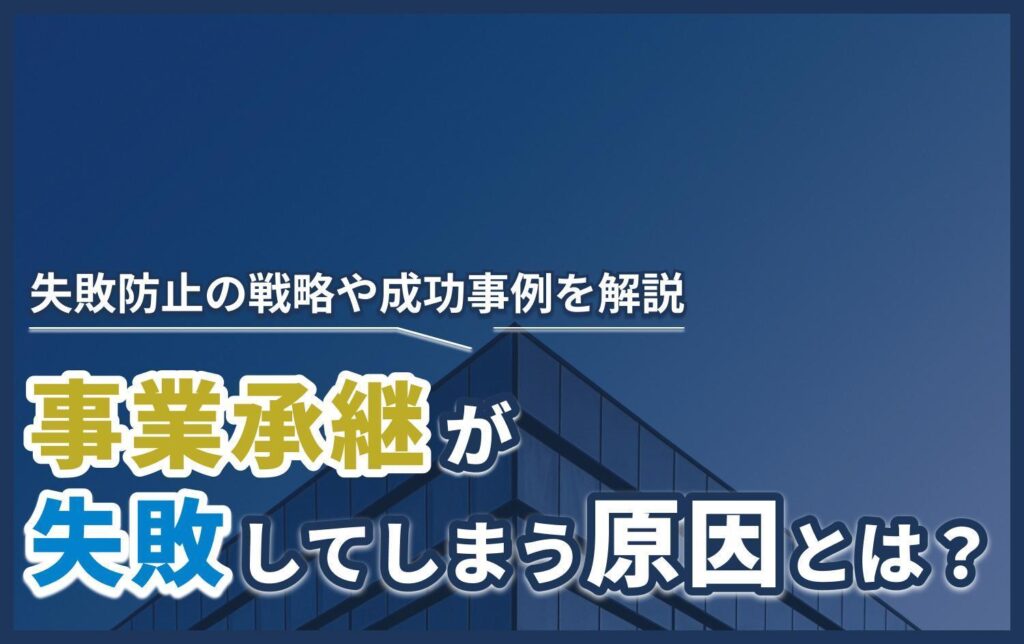
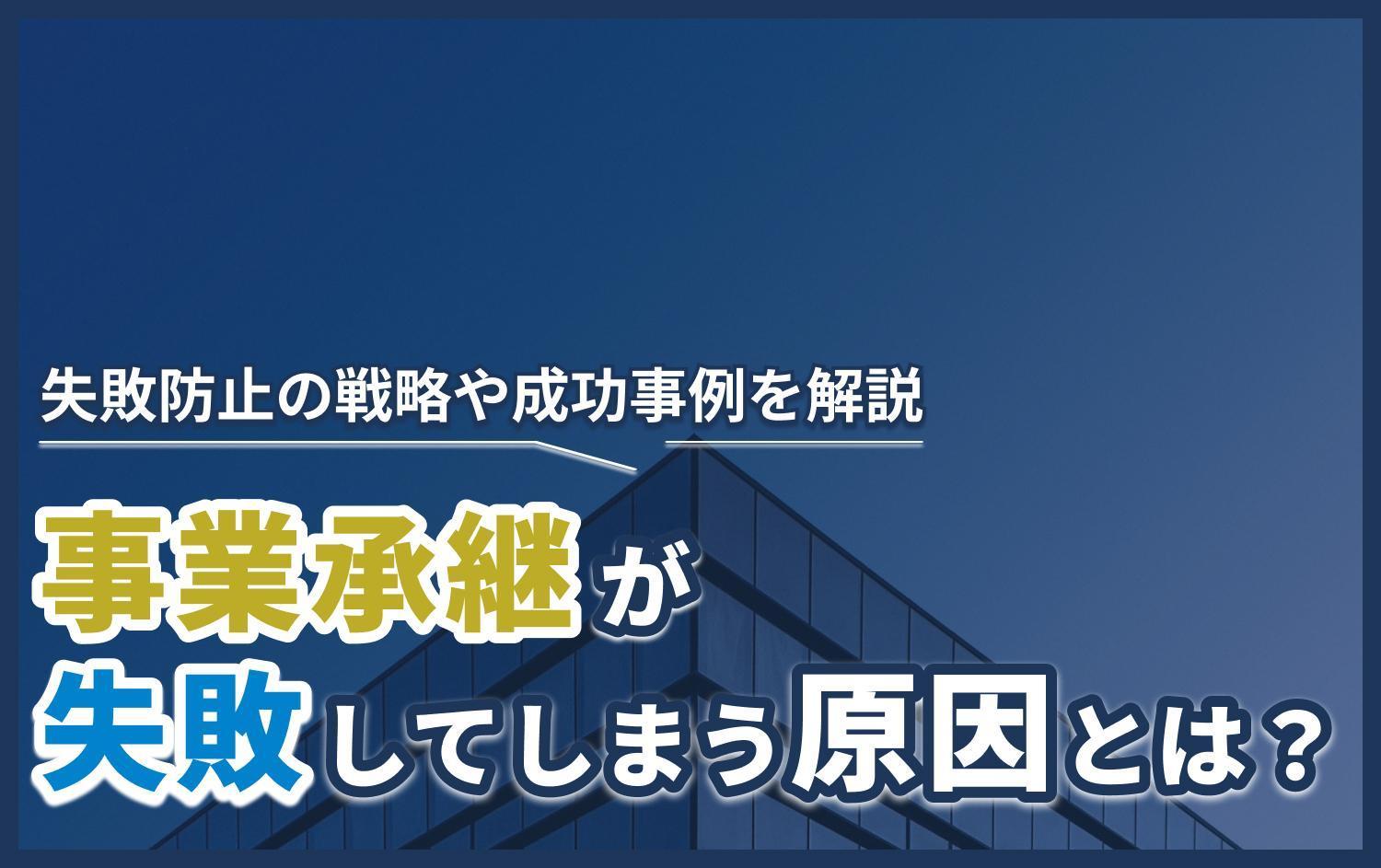
会社を安全に存続させるために、事業承継を早い段階から考えている人も多いでしょう。事業承継は、これまで築き上げてきたビジネスの未来を左右する重要な決定です。中途半端な状態で進めてしまうと、失敗に終わってしまうことも少なくありません。
しかし、よくある失敗パターンから自社の方向性を学ぶことで、事前に対策を打つことができます。本記事を読み事業承継の失敗から成功に導く方法を理解すれば、今後の経営の方向性を定められるでしょう。
この記事では、事業承継の失敗理由を解説しつつ、失敗防止の戦略や成功事例を紹介します。
事業承継における失敗とは
事業承継における失敗とは、具体的にどのような状況のことを指すのかを知っておきたいところです。事業承継に失敗すると、会社は以下のような状況に陥る可能性があります。
-
- 廃業
- 業務成績の低下
- 離職率の増加
- 資金繰りに追われる
ここでは、会社における上記4つの状況について解説します。
廃業
事業承継のプロセスにおいて不具合が生じると、最悪の場合廃業に追い込まれる可能性があります。廃業せざるを得ない主な原因として、次節から解説する「業務成績の低下」「離職率の増加」「資金繰りの困難化」などが挙げられます。
事業承継において、曖昧な戦略が事業の継続に悪影響をおよぼすことは少なくありません。廃業を避けるためには、後継者選びや育成とともに承継後の事業のあり方を検討していく姿勢が重要です。
業務成績の低下
事業承継に失敗し、のちの業務成績が下がり経営に影響をおよぼすケースも少なくありません。業務成績低下の原因の一つに、承継後の経営者が従業員からの信頼を獲得できていないことが挙げられます。企業をよくするためのアイデアを打ち出したとしても、従業員の意思を反映できなければ継続的な業績アップは見込めないでしょう。
事業承継を成功に導くには、後継者の経営者としての資質を早い段階から育てていく計画が必要です。従業員とのコミュニケーションを大事にしながら、次期リーダーとしての存在を確立していく姿勢が求められます。
離職率の増加
事業継承に失敗すると、リーダー交代の前後で離職率が上がる場合があります。事業承継前後での離職率の増加は、従業員が新しい経営体制に対して不安を感じることで生じます。また、リーダーが変わり文化や価値観が変化し、従業員が職場になじめなくなることも要因の一つです。
離職を防ぐためには、事業承継プロセス全体をとおして従業員の不安を払拭する姿勢が必要です。事前の準備と従業員とのオープンなコミュニケーションが、組織の結束力を維持する鍵となります。
資金繰りに追われる
事業承継の失敗により、資金繰りに追われて今後の経営の見通しが立てにくくなるケースもあります。事業承継のスタート段階での財務状況の見落としや、承継後の経営戦略が資金調達と連動していないことが原因です。
資金繰りトラブルを避けるためには、事業承継計画を作る際に財務状態を細かくチェックし、資金調達プランを作成しておくことが求められます。さらに、コストを見直し収益性を高めることで、安定した財務基盤の上で事業を存続できるでしょう。
事業承継の失敗事例5選

事業承継の失敗を避けるために、継承がうまくいかなくなるパターンを知っておきたいところです。ここでは、事業承継が失敗しやすい5つのケースについて解説します。
準備が足りず社内が混乱
事業承継において、準備不足が原因で社内がパニックに陥るケースは少なくありません。ある会社では、経営が安定していたため事業承継について考えることはありませんでした。あるとき、経営者が急病で倒れてしまい、急遽役員を後継者として事業を引き継ぎました。しかし、突然のできごとであるため事業承継における準備を何もしておらず、後継者は経営判断をたびたびミスします。最終的には業績が悪化し、廃業する流れとなってしまいました。
このパターンでは、事業承継の計画や準備をしておく重要性が理解できるでしょう。すぐには事業承継の必要がなくても、不測の事態に備えて準備しておくことが自社を救う鍵となります。
適切な後継者がいない
後継者には、自社の経営理念をよく理解した人物を選任しないと、事業承継は思うように進みません。ある家族経営企業では、後継者として経営者の長男が選ばれました。しかし、長男は業界への理解が浅いだけでなく、従業員からの信頼をなかなか獲得できませんでした。結果的に、従業員は経営者に不満を募らせ、多くの離職者が出る状態に陥ってしまいました。
このパターンで問題となったのは、後継者として経験やスキル、会社への理解が乏しい人を選任してしまった点です。後継者には「長男だから」「親族だから」という理由だけでなく、経営者としての資質が備わった人物を選ぶべきでしょう。
引退した経営者の実質的支配
事業承継が完了しても、引退した経営者が会社に強い影響を及ぼしているというケースも少なくありません。ある企業では、経営者の引退にともない、後継者として親族が選出されました。しかし、引退した経営者は、後継者の意思決定に対してことあるごとに口を挟み続けます。経営方針がぶれるだけでなく、後継者は従業員からの信頼を獲得できず事業は軌道に乗りませんでした。
このパターンの問題点は、引退した経営者が意思決定に関わり続け、社内に混乱を引き起こした点です。経営者には、事業承継を早期から十分に行い、完了したらすみやかに身を引く覚悟も求められます。
後継者へのサポートが不十分
事業承継のあとの業績の落ち込みは、後継者へのサポートが不十分であったことも要因の一つです。ある企業では、企業を長い間成長させてきた経営者が引退となり、事業承継もスムーズに行われました。しかし、実際に新体制がスタートしてからは売上が急激に減少してしまいます。経営を立て直すのも難しく、従業員の離職も相次ぎ厳しい状況が続きました。
事業承継には、事務的な手続きだけでなく後継者の実務サポートも求められます。ある程度期間を決めてアドバイスを行えるよう、事業承継計画を長い目で見て策定することが必要です。
相談なしに事業承継が進む
事業承継について関係者との十分な話し合いがなされないと、思わぬトラブルを生む原因となります。ある経営者は、事業承継にあたり会社売却を決定しましたが、誰にも相談せずに自身の判断のみで手続きを進めました。その結果、役員や従業員から大きな反発が起き、離職が相次いだことにより廃業にまで発展しました。
このパターンからは、周囲とのコミュニケーションを怠ると失敗に陥りやすいことがわかります。事業承継は会社の未来につながる重要なプロセスであるため、関係者全員が一丸となって進める姿勢が必要です。
事業承継の失敗を避けるための5つの戦略
事業承継の失敗を避けるには、どのようなことに気をつけるべきか気になるところです。ここでは、事業承継を意識した時点から知っておきたい戦略を5つ解説します。
事業承継計画を作成し進捗を周囲に随時共有する
事業承継の失敗を避けるには、事業承継計画を作成し、プロジェクトの進捗状況を関係者に随時共有するようにしましょう。事業承継計画書とは、以下の内容を盛り込んだ書類のことです。
-
- 事業承継の時期
- 事業承継における課題
- 課題を達成するための対策
後継者や経営陣とともに事業承継計画を作成することで、企業が置かれている状況やこれから取り組むべき課題を把握できます。また、計画の実行段階では進捗状況を会議などで随時報告することで、周囲からサポートを受けられる可能性もあります。
事業承継計画の作成と共有により、社内の混乱を防ぎ、企業が目指すべき方向性を明確化することが必要です。
早めに引退予告を行う
事業承継の失敗を避けるには、経営者が引退の意向を早めに発表することも対策の一つです。引退の宣言には、社内全体で事業承継が始まることを意識する働きがあるためです。承継するタイミングから逆算し、早くて10年前から、遅くとも5年前から引退予告を行い事業承継をスタートしましょう。
事業承継完了までに十分な時間を確保することで、後継者や従業員の不安を和らげる効果もあります。とくに、今後経営権を握る後継者が自信を持って経営できるよう、準備期間として時間を十分に確保しましょう。
後継者へ多くの経営経験をさせる
事業承継の失敗を避けるには、自身が現役であるうちに後継者へ多くの経営経験をさせることも重要です。後継者が直面するであろう課題の対処には、実務経験と自信が求められます。
後継者にとって、経営者に見守られながらトライ・アンド・エラーを繰り返せる環境は、価値そのものです。これから身を引く経営者にとっても、後継者の準備期間を十分に設けることで引退の心配を最小限にとどめる効果があります。後継者の選定を行ったあとは、なるべく多くの経験を積めるように時間と責任を渡しましょう。
後継者に経営革新計画を作成させる
事業承継の失敗を避けるには、後継者に経営革新計画書を作成させるのも方法の一つです。経営革新計画書とは、中小企業が新しい事業に取り組むことを目的とする中期的な計画書のことです。計画策定を通して自社の課題が明確になるうえ、国や都道府県に計画が認められればさまざまな支援を受けられる可能性があります。
後継者が自社を見つめる機会を与えることで、事業承継後の業績不振や資金繰りの悪化を防ぐ効果も期待できます。経営者としての自信と能力を高めるステップとしても、経営革新計画書の作成は価値のある取り組みといえるでしょう。
参考:東京都産業労働局 経営革新計画
事業承継の専門家からサポートを受ける
事業承継の失敗を避けるには、専門家からのサポートを検討することも重要です。事業承継は、単なる経営権の引き渡しにとどまらず、法律や財務などの専門的な知識が求められます。また、事業承継を考える過程で後継者がなかなか見つからず、承継自体を諦めるというケースも少なくありません。
事業承継に行き詰まりそうな場合や、個別のケースにどう対処したらいいかわからない場合、専門家のサポートが役に立ちます。事業の評価や後継者の選定、税務や法的な手続きのアドバイスなど、事業承継を成功に導くための具体的なアドバイスを受けられます。安全かつ効率的な事業承継を行うためにも、専門家の存在は頭の片隅に置いておきましょう。
事業承継の成功事例とは

事業承継の準備を入念に行っていれば、困難な状況であってもビジネスを安全に引き継ぐことができます。ここでは、事業承継に成功した事例を2つ紹介します。
廃業決定後、後継者の強い意志により再生した事例
北海道札幌市の海鮮居酒屋「てっちゃん」は、人気店であったにもかかわらず新型コロナウイルスの影響で2020年4月に閉店し、廃業を決定しました。しかし、現社長の佐藤ゆかこ氏は居酒屋への強い愛着を持っており、感染症流行下での新たなニーズに応える再出発方法を模索しました。
その結果、北海道よろず支援拠点での相談を経て、事業承継と業態転換を決意し、進めていた廃業手続きの停止に至ります。2020年10月に事業承継を完了し、感染症流行を考慮した新業態である健康志向のぎょうざ専門店として再出発を計画しています。
過去の業績や新しい事業形態の工夫、そして後継者の強い意志があれば再生の可能性があることを示す事例といえるでしょう。
出典:中小企業庁ウェブサイト
経営者の急逝後、M&Aで意欲のある後継者に出会えた事例
石川県加賀市の株式会社新家製作所は、社長急逝後に後継者不在の課題を抱え、石川県事業引継ぎ支援センターに相談しました。のちに同社社長となる航空部品メーカー出身の山下公彦氏は、早期退職後に地元での創業を考えていました。
しかし、後継者不足が課題となっている中小企業の現状を知り、M&Aによる経営者への転換を模索し、新家製作所の事業譲受を決定します。2020年3月の基本合意後、公的支援を活用して株式取得資金を調達し、同年7月に社長に就任しました。
突如開始した事業承継であっても、専門家のサポートにより意欲のある後継者に出会えた事例といえるでしょう。
出典:中小企業庁ウェブサイト
事業承継は計画と準備により成功の確率を高められる|まとめ
事業承継は、これまで築き上げてきたビジネスの未来を左右する重要な決定であり、失敗に終わってしまう企業も少なくありません。しかし、自社の現状を見つめ、早期から準備を行うことで、困難な状況であっても事業承継を成功に導くことができます。
事業承継で起こり得るリスクを知り、十分に準備を行い成功の確率を高めましょう。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。


