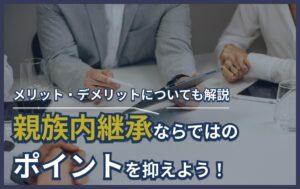【廃業手続きの全て】法的要件と進め方のポイントを解説
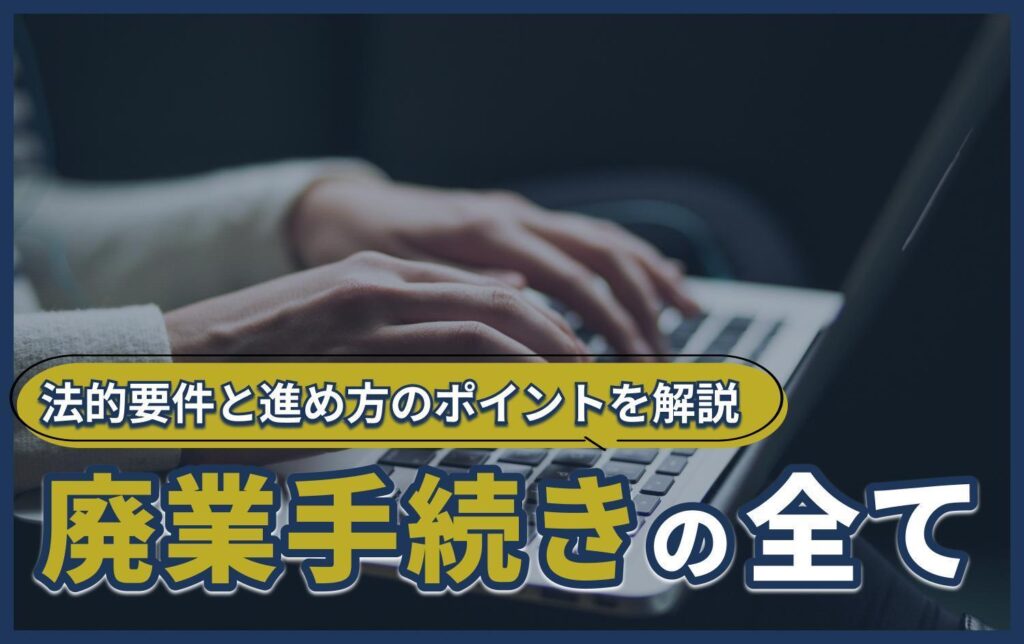
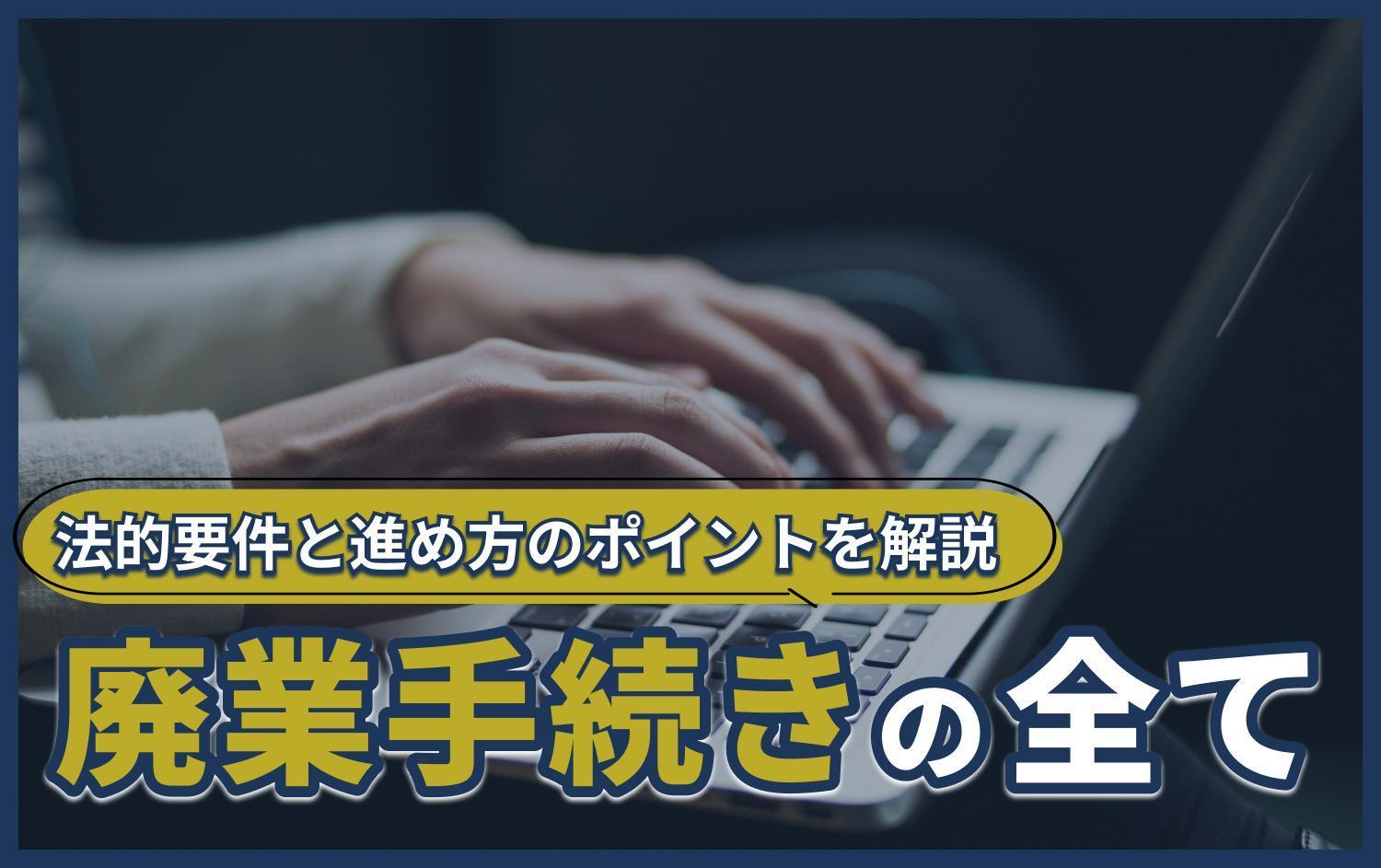
本記事では、廃業手続きの全体像を押さえるべきポイントとともに解説します。法人の解散から清算結了までの流れ、各種届出の要点など、丁寧にお伝えしていきます。
専門的な部分は、税理士など専門家の力も借りながら、一つずつクリアしていきましょう。
廃業手続きのポイント
法人の場合、手続き上は「解散」と「清算」の2段階に分かれます
解散は法人格が存続しながら事業活動を停止することで、清算は財産の整理を経て法人格を消滅させる過程です。
廃業手続きを進める上では、以下の点がポイントとなります。
- ポイント
- 対象法令の確認と遵守:会社法、労働基準法、税法など
- 利害関係者への丁寧な説明:従業員、取引先、債権者など
- 財産状況の的確な把握:債権債務の棚卸し、資産の評価など
- 専門家の活用と役割分担:手続き、財産処分、税務など
一連の手続きには複雑な部分もありますが、焦らず一つずつ確実に進めていくことが重要です。各段階で押さえるべき要件やアクションを整理し、計画的に取り組んでいきましょう。
廃業手続きの全体像
廃業の大まかな流れは以下の通りです。
-
- 取締役会での廃業決定
- 臨時株主総会の開催と解散決議
- 解散登記と清算人の選任
- 官報公告と債権者への個別通知
- 債権の回収と債務の弁済
- 残余財産の処分と分配
- 清算結了登記と法人の消滅
この一連のプロセスには、およそ3ヶ月から1年程度を要します。会社規模や財産状況によっては、さらに時間がかかるケースもあるでしょう。余裕を持ったスケジュール設定を心がけましょう。
上記プロセスと並行して、以下のような手続きを進めていきます。
- 手続き
- 労働関連の手続き(従業員への説明、退職金の支払いなど)
- 税務関連の手続き(法人税の清算申告、消費税の届出など)
- 許認可の廃止手続き(看板の撤去、廃棄物処理など)
これらの手続きには、法令上の期限が定められているものもあります。税理士や社労士など専門家のアドバイスを参考にして、計画的に対応することが大切です。
目次
法人の解散手続き
(1) 株主総会・取締役会での解散決議
廃業を決定したら、まずは取締役会を開催します。そこで解散と清算の方針について決議し、臨時株主総会の招集を決定します。
臨時株主総会では、解散の決議を行います。出席した株主の議決権の過半数かつ発行済株式総数の3分の2以上の賛成で成立します。あわせて、清算人の選任も行います。
(2) 解散登記と清算人の選任
解散を決議した日から2週間以内に、本店所在地の法務局で解散登記を行います。登録免許税として、収入印紙3万円分が必要です。
清算人は、原則として取締役が就任します。別途定款で定めるか、株主総会の決議で選任することも可能です。清算人の登記は解散登記と同時に行い、収入印紙9,000円分が必要となります。
(3) 官報公告の掲載と債権者への個別通知
解散後、遅滞なく官報に解散公告を掲載します。あわせて判明している債権者に対し、債権申出の催告通知を行います。
債権者に対し少なくとも2ヶ月以上の債権申出期間を設ける必要があります。期間内に申し出のなかった債権は、履行の責任を負わなくなるため注意が必要です。
労働関連の手続き
(1) 従業員への説明と合意形成
廃業が決まったら、できるだけ早い段階で従業員に説明を行います。解散の理由や今後の見通しを丁寧に伝え、雇用の終了時期などについて話し合います。
特に、給与や退職金の取り扱いについては、十分な理解を得るよう努めましょう。個別相談の場を設けるなど、従業員の不安に真摯に向き合う姿勢が大切です。
(2) 雇用契約の終了と退職金の支払い
雇用契約の終了にあたっては、予告期間の確保や有給休暇の取り扱いに注意が必要です。就業規則などに基づき、適切に手続きを進めましょう。
退職金の支払いは、従業員の納得を得られるようていねいに。資金繰りを見据えつつ、遅滞なく支給することが求められます。
(3) ハローワークへの届出と雇用保険の手続き
従業員を解雇する場合は、ハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出します。併せて、「雇用保険被保険者離職証明書」を交付しましょう。
雇用保険の手続きでは、会社都合の離職として取り扱われます。再就職先が決まっていない従業員には、失業給付の説明も丁寧に行うことが大切です。
廃業すると従業員はどうなる?雇用終了通知から再就職支援まで解説
税務関連の手続き
(1) 法人税の清算確定申告
解散事業年度と各事業年度の法人税について、清算確定申告を行います。解散事業年度の申告は、解散日から2ヶ月以内に行う必要があります。
清算所得に対する法人税の税率は、解散事業年度と清算中の事業年度で異なります。税理士など専門家の指導を仰ぎつつ、適切に申告を行いましょう。
(2) 消費税の課税事業者の届出
消費税の課税事業者であれば、「消費税課税事業者の届出書」を提出します。原則として、廃業の日から30日以内に税務署に届け出ます。
課税事業者の選択については、税負担や事務負担を考慮して判断します。税理士に相談しながら、適切な選択をしていきましょう。
(3) 源泉所得税の納期特例の中止届出
源泉所得税の納期特例を受けている場合は、「源泉所得税の納期特例の中止届出書」の提出が必要です。
廃業に伴い納期特例を中止する際は、速やかに届出を行います。税務署への提出期限にも注意が必要です。
債権債務の処理と資産の整理
(1) 債権の回収と債務の弁済
解散後、債権の取立てと債務の弁済を進めていきます。売掛金や貸付金などの債権は、早期の回収を心がけましょう。回収困難なものは適切に償却します。
一方、買掛金や未払金などの債務は、債権者への通知後、順次弁済を行います。借入金の返済スケジュールについても、金融機関とよく相談し、無理のない返済計画を立てることが大切です。
(2) 事業用資産の売却・処分
事業で使用していた資産は、原則として換価処分します。動産や不動産の売却を進め、債務の弁済原資を確保します。
売却価格の設定には注意が必要です。簿価との差額は、清算所得の計算に影響します。税理士など専門家の意見を参考にしつつ、適切な価格設定を心がけましょう。
廃業時の在庫処分のベストな考え方とは?具体的なステップについて解説
(3) 事業用不動産の処分と原状回復
事業用不動産を賃借していた場合は、賃貸人との協議が必要です。原状回復義務を負うケースが多いため、あらかじめ費用を見積もっておくことが大切。
オフィスや店舗の明け渡しには、原状回復工事だけでなく、什器備品の撤去なども含まれます。スケジュールに余裕を持って、万全の準備を進めましょう。
各種許認可の廃止手続き
(1) 業種ごとの許認可の確認
飲食店や風俗営業、建設業など、許可を受けて営業している場合は、廃止の届出が必要です。業種ごとに所管官庁が異なるため、確認を怠らないようにしましょう。
例えば、飲食店営業の許可は保健所、建設業の許可は都道府県知事が所管。風俗営業の許可は、公安委員会が所管しています。
(2) 廃止届の提出と必要書類の準備
許認可の廃止には、所定の届出書を提出する必要があります。書式は所管官庁によって異なるため、あらかじめ確認を。
添付書類として、登記簿謄本や廃業届、許可証の原本などが求められるケースも。余裕をもって準備を進め、期限までに提出できるよう注意しましょう。
(3) 看板・標識等の撤去と処分
店舗の看板や、会社名の入った標識類は、廃業後速やかに撤去します。放置された看板が、無用のトラブルを招くこともあるため注意が必要。
撤去した看板等の廃棄には、自治体の定める手続きに則る必要があります。産業廃棄物として適切に処分し、不法投棄などのないよう細心の注意を払いましょう。
清算人の役割と責任

(1) 清算人の選任と職務
清算人は、債権の取立てや債務の弁済など、清算に必要な一切の行為をつかさどる立場です。善管注意義務を負い、清算従事者の範囲内で会社を代表します。
清算人には、取締役が就任することが一般的。定款や株主総会の決議で別途選任することも可能です。いずれにせよ、適任者を選ぶことが肝要です。
(2) 残余財産の処分と分配
清算人は、債権債務の処理を終えた後、残余財産を処分します。換価処分によって得た金銭から、清算費用や債務を控除した額が、最終的な分配原資となります。
分配方法は、定款の定めや株主総会の決議に従います。公平性を保ちつつ、適切に分配を行うことが清算人の責務といえます。
(3) 清算結了時の債務弁済責任
清算人は、清算結了の登記後も一定の責任を負います。清算中の不法行為等により会社に損害を与えた場合などは、任務解怠の責任が問われる可能性があります。
清算事務には細心の注意を払うとともに、分配後に債務が発覚した場合などには、適切に対応することが求められます。
清算結了登記と法人の消滅

(1) 清算事務の完了と清算報告書の作成
全ての清算事務が終了したら、清算人は清算報告書を作成します。財産目録や貸借対照表、事務の顛末を記載し、清算人が署名・押印します。
清算報告書は株主総会に提出し、承認を得る必要があります。可決には、議決権の過半数かつ発行済株式総数の3分の2以上の賛成が必要です。
(2) 清算結了登記の申請と必要書類
清算報告書が承認されたら、2週間以内に清算結了登記を申請します。必要書類は以下の通り。
- 必要書類
- 清算結了登記申請書
- 株主総会議事録(清算報告承認)
- 清算人の印鑑証明書
- 登録免許税納付用台紙
ここで清算人の役割は終了します。後は、管轄の法務局での登記手続きを滞りなく行います。
(3) 法人の消滅と記録の保管
清算結了の登記が完了した時点で、会社は法人格を失います。登記簿上の会社名には「清算結了」と記載され、商業登記簿が閉鎖されます。
会社の帳簿や重要書類は、一定期間保管する義務があります。税法上は7年、会社法上は10年間の保存が求められます。文書管理を徹底し、適切に保管する必要があるでしょう。
廃業後の注意点
(1) 取引先との関係維持と名義貸し防止
廃業が完了しても、取引先との関係維持は大切です。清算結了後も、必要に応じて連絡を取り合える関係性を保つことが望ましいでしょう。
一方で、廃業後の「名義貸し」には注意が必要です。既に消滅した会社名で取引を行うことは、トラブルのもとに。不正使用を防ぐための備えを怠らないようにしましょう。
(2) 個人情報の適切な廃棄
会社には、顧客や従業員の個人情報が多数保管されています。廃業に伴い、これらの情報を適切に廃棄することが求められます。
シュレッダーでの裁断や専門業者への委託など、情報漏洩のリスクを防ぐ方法で処分を。個人情報保護法の規定に則った対応を心がけましょう。
(3) 事業用資産の私的流用の禁止
会社の資産を、経営者が無断で私的に流用することは禁じられています。たとえ廃業が決まった後でも、会社の財産は清算の対象。私物化は厳に慎む必要があります。
資産の処分は、業務日誌などに記録を残しながら、透明性を保って進めることが大切。公私のけじめを明確にし、適切な処理を心がけましょう。
専門家の活用とサポート
(1) 税理士・公認会計士へのアウトソーシング
廃業の手続きには、税務や会計の専門知識が欠かせません。自信がない部分は、税理士や公認会計士などの専門家に委ねるのが賢明です。
財産の評価や税務申告など、専門性の高い領域は思い切ってアウトソーシング。プロの目を通すことで、ミスやトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。
(2) 弁護士への相談と書面作成の依頼
法的な観点からのアドバイスは、弁護士に相談するのがよいでしょう。清算人の義務と責任、債権者対応の注意点など、法律の専門家ならではの視点が頼りになります。
取引先との契約解除や、各種書面の作成などを依頼するのも有効。法的なリスクを回避しつつ、手続きを適切に進められます。
(3) 司法書士への登記手続き等の委託
定款の変更や清算結了の登記など、法務局での手続きは煩雑で時間がかかるもの。書類作成から申請まで、司法書士に一括して依頼するのも一案です。
登記の専門家である司法書士なら、スムーズかつ正確な手続きが期待できます。自身で対応するか、専門家に委ねるか、コストと手間のバランスを見極めましょう。
廃業を検討するときの相談先は?具体的な相談の進め方について解説
円滑な廃業手続きのために | まとめ
廃業の手続きは、法的な要件が複雑に絡み合うプロジェクトとなります。
関係各所への届出や、債権債務の処理、清算人としての責務など、やるべきことは山積み。それだけに、体系的な知識と周到な準備が欠かせません。
この記事を読み、スムーズな手続きを行っていただけたらと思います。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。